「被団協」新聞2025年7月号(558号)
2025年7月号 主な内容
被爆80年 被爆証言の掘り起こしを
日本被団協第70回定期総会
 |
| 田中重光代表委員総会あいさつ |
日本被団協は6月18~19日、東京のTKPガーデンシティお茶の水で第70回定期総会を開きました。28都府県から約100人が参加。基調報告、活動報告、会計報告、運動方針、予算、役員選出、総会決議と特別決議(2面に全文)を承認・決定しました。
ノーベル平和賞受賞と日本被団協の取り組み
基調報告では、被爆80年の今年、これまでの運動を振り返り関係団体と協働で運動を進めることを確認。核兵器が使用されかねない国際情勢の今だからこそのノーベル平和賞受賞だったとし「ふたたび被爆者をつくらない」決意のもと、国内外の市民社会と連携して核兵器も戦争もない人間社会にむけ運動に取り組んでいく、と結びました。
 |
| 箕牧代表委懇親会あいさつ |
 |
| 懇親会の様子 |
初日は2024年度活動報告案と会計報告案の提案、会計監査報告があり、それぞれ質疑、討論を経て採択。また、日本被団協が非営利団体であることの規約への追記事項が提案され、採択されました。
2日目は、今年3月と4~5月に行なわれた核兵器禁止条約締約国会議とNPT再検討会議準備委員会の報告のあと、今年度運動方針案、会計予算案の提案があり、質疑、討論を経て採択。また昼食時間に開かれた役員選考委員会の報告を受け、今年度役員が選出・承認されました(別項)。
2日間を通じて、参加した全国理事およびオブザーバーから、各県の活動報告を含め活発に発言がありました。
被爆80年の取り組み
運動方針では、これまでに被爆者が残してきた体験記を読んで学び語り継ぐとともに、まだ体験を話したり書いたりしていない被爆者の証言を掘り起こすことを提起しました。
また10月11日に東京の有楽町朝日ホールで、多くの市民団体が参加する実行委員会によるイベントの計画も発表されました(別項)。
二大要求に基づいて日本政府や国会に向けた大行動を起こすことも確認しました。
ノーベル平和賞受賞記念懇親会
総会初日の夜、コロナ禍以降開催を見送っていた懇親会を開催。冒頭、20分間の授賞式代表団報告動画を上映しました。参加者から「DVDにして各県に配布を」「秋の集会で上映したい」などの声があがりました。
今年度役員
代表委員=田中熙巳 田中重光 箕牧智之 事務局長=濱住治郎(新) 事務局次長=児玉三智子 和田征子 濵中紀子 代表理事=木村緋紗子 佐伯博行(新) 金本弘 本間恵美子 松浦秀人 中村国利 田中聰司 横山照子 家島昌志 首藤通治 会計監査=三松保則(新) 前田一美(新) 顧問=木戸季市(新)
オンライン国連原爆展・体験記 体験交流会
継承する会・日本被団協
 |
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は一昨年から日本被団協の国連原爆展や各会発行の証言集をオンラインで閲覧できる仕組みをつくっています。これらを継承活動にどう活用していくか-6月19日、日本被団協と共催して体験交流会を開きました。
30人余りの参加者はスクリーンに映し出された画面を初めて観る人がほとんど。国連原爆展を開きたいが、多額の輸送費がかかる、といった悩みも、このサイトを上手に利用すればどこでも開けます。過去に発行された証言集からは、原爆地獄を体験し戦後を生きてきた被爆者たちの苦しみや闘いを知ることも。
交流会では、各県の聞き取り活動や、資料の保管場所の悩みも語られました。各地で大いに役立てていただきたいものです。(栗原淑江)
被爆・戦後80年企画
「核兵器も戦争もない世界を求めて ~記憶を受け継ぎ未来へ~」
10月11日東京・有楽町朝日ホールで開催
被爆・戦後80年企画「核兵器も戦争もない世界を求めて~記憶を受け継ぎ未来へ」を10月11日(土)に、東京・有楽町朝日ホールで開催します。
今年は被爆・戦後80年という節目の年であり、昨年、日本被団協のノーベル平和賞受賞を受け、この機運をさらに高め、核兵器のない世界の実現に向けた具体的な行動を起こそうと、本企画を立ち上げました。
日本被団協の呼びかけにより昨年10月から準備委員会と事務局会議を重ね、4月に30団体・個人が参加した実行委員会が発足。企画の具体化にむけ動き出しています。
被爆の実相を広く伝え、次世代へ継承することを目的として、会場入り口のホワイエとホールの両方を使ったプログラムを検討。ホワイエでは12時から13時まで、被爆者の方々から直接お話を伺い、交流できる場を設けます。また資料等の展示も行ないます。
ホール企画は13時から15時の2時間で、朗読劇上演のほか、核兵器廃絶に向けた活動をする仲間たちによるリレートークも予定しています。朗読劇はプロの劇作家にシナリオを依頼して、日本被団協の運動や被爆の実情をわかりやすい言葉で伝え、参加する若い世代が記憶を継承し、未来へつなげられるような内容を目指しています。リレートークでは各団体がそれぞれの視点からメッセージを発信し、戦争や核について考える時間を共有します。
詳しいご案内は夏以降になりますが、より多くのご参加を心よりお願いします。(実行委員会事務局・日本青年団協議会事務局長 棚田一論)
厚労省、外務省、各政党に要請
 |
日本被団協は定期総会翌日の6月20日、全国の被爆者、被爆二世など約60人が参加し衆議院第一議員会館会議室で中央行動を行ないました。午前は厚生労働省交渉、午後は各政党への要請と外務省交渉でした。
厚労省交渉では、被爆者援護対策の安田正人室長ほかが出席。日本被団協からの要請について、これまで通り積極的回答はありませんでしたが、今年から毎年、全被爆者に体験記を書いてもらうよう、都道府県を通じて知らせていくとの説明がありました。
政党からは公明、立憲、国民、共産、れいわ、社民の各党から党首を含む国会議員が参加。要請書を渡し懇談しました。
外務省交渉には、中村仁威軍縮不拡散・科学部長ほかが出席。核兵器禁止条約は核兵器廃絶への出口である重要な条約だが、核兵器国が参加しているNPTのもとでやっていくと述べました。参加者からの「橋渡しとはどうやって、いつ、どこの国とするのか」との質問には、明確に答えませんでした。
イスラエルとアメリカがイランの核施設を攻撃
日本被団協が抗議声明・談話
イランの核施設をイスラエルとアメリカが相次いで攻撃しました。日本被団協は6月17日に声明「世界はヒロシマ・ナガサキの悲劇を忘れたか」を、24日に田中熙巳代表委員談話「アメリカのイラン空爆に反対する」を発表しました。
声明では、「核施設への攻撃は絶対に許されません」として「ヒロシマ・ナガサキの悲劇をふたたび起こしてはなりません。そのためには、その悲劇を忘れてはなりません。被爆80年のいま思い起こさねばなりません。核施設への攻撃をやめるとともに、一日も早い戦闘終結を強く訴えます」と結んでいます。
談話では、イランへの核攻撃とそれを語るトランプ大統領の演説を「暴挙、暴言」とし、「核抑止論」が破綻を指摘。徹底した平和的外交交渉による解決を求めました。
"超世代トーク"など和やかに
日本キャンペーン発足1周年
一般社団法人核兵器をなくす日本キャンペーンは6月1日、発足1周年記念イベントを東京・渋谷の聖心女子大学で開催し、約150名が参加しました。日本キャンペーンは、核兵器廃絶日本NGO連絡会を母体に昨年4月に発足。2030年までに日本が核兵器禁止条約に参加することを目指し活動しています。
イベントでは、事務局コーディネーターの浅野英男さんが今年度事業計画を説明。新しい取り組みとして、学術アドバイザリーグループの発足と核兵器禁止条約マニフェストを発表しました。マニフェストでは、日本がアジアにおける核軍縮をどのようにリードすべきかなど提言しています。
様々な年代の人たちによる超世代トーク、大学生のエイサー披露など、和やかな雰囲気で幕を閉じました。(竪場勝司)
マクロン大統領に要望書
 |
田中聰司
5月中旬、核保有国のフランスを訪問、被爆体験を語り、核兵器廃絶を訴え各地を回りました。グルノーブル市のエリック・ピオル市長に託したマクロン大統領宛の要望書が届いたようで、期待を胸に詳しい説明を待っているところです。
昨秋、広島県被団協を訪れて交流したピオル市長(写真右)からの招待で前田耕一郎前事務局長と渡仏。11日間にわたり東南部の大学、日本人学校、地域など15カ所で証言し、交流しました。
私の被爆体験とともに広島・長崎の出来事は昔話ではないと訴え、「皆さん、ご存知ですか」と続けました。欧州に核の傘を広げると表明した貴国の大統領は、2年前のG7サミットで広島を訪れ、原爆資料館を見て「平和のために行動することこそが私たちの使命」と記帳されたと。ほとんどの人が知らなかったようです。最後に、5核大国の橋渡し役として、戦争中止と核軍縮の対話の場づくりを大統領に求めようと呼びかけました。
ピオル市長は涙ぐんで握手を求め「私が使者を務めましょう」と。にわか作りの要望書を預けてきたのでした。
6月18日の政府行事で渡されたとのことで、大統領の反応はまだ返って来ません。でも、被爆者の書簡に触れて願いの一端でも伝われば、と望みを抱いています。
もう一つ、南フランスの平和団体が一体となって秋に被爆者を招きたいと、日本被団協の協力を要請されました。いただいた元気と感謝の気持ちを、被爆80年に生かしたいと念じています。
総会決議
~被爆80年にあたって~
被爆80年の今年は、初の原水爆禁止世界大会が開催されて70年の節目でもあります。被爆者が初めて表舞台から思いのたけを訴え、翌年、日本被団協を結成。原爆医療法の制定へとつながりました。それまでの、原爆投下から最も援助が必要だった12年間、原爆被害者が日米両政府によりなんら援護もなく捨て置かれたことに、私たちはあらためて両政府に憤るとともに責任を問いたいと思います。
69年前に私たちは、日本被団協の結成宣言「世界への挨拶」で、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうと誓い合った」と高らかに表明し、運動を続けてきました。ノーベル平和賞発表にあたって、フリードネス委員長は、核兵器の使用は道徳的に容認できなという国際規範の形成にとって、被爆者の証言は唯一無二だと述べて、私たちの運動を評価しました。
現在、被爆者は10万人近くいますが、平均年齢は85歳を超えています。いつか、被爆者がいなくなる時がきます。今こそ、証言の掘り起こしと語り継ぐ運動をすすめ、核兵器の非人道性を国の内外に向けて発信していくことが必要です。体験を次世代に引き継ぐために若いひとたちとともに取り組んでいきます。核保有国とその同盟国の核政策をかえるために、国の内外で証言の機会を作りましょう。
私たちの地獄の体験を子や孫に、世界の人々に味わわせてはならない、「ふたたび被爆者をつくるな」と、国の内外で訴えてきました。核兵器は非人道的な殺りく兵器で、すみやかに廃絶されなければならいこと。「戦争の被害は国民が受忍しなければならい」との国の主張に抗い、原爆被害は戦争を開始し遂行した国によって償われなければならないこと。この二つを訴え、運動してきました。この運動を引き継ぎ、国家補償の「原爆被害者援護法」の成立に向け取り組みます。
2017年に原爆被害者の悲願である核兵器禁止条約が採択、2021年に発効し、これまで締約国会議が3回行われてきました。核抑止政策をとる日本政府は、署名も批准もしないばかりか、オブザーバー参加さえ拒絶しています。核兵器の保有や使用を前提とした核抑止論を変えさせ、核兵器は廃絶しかないという世論をつくらなければなりません。条約には核被害者の支援や環境の回復の条項もあります。核被害者や環境問題に取り組む人たちとも連携しながら、核兵器禁止条約を広げ育て、参加国を増やしていきます。
「戦争の被害は受忍しなければならない」との国の主張は今も生きています。原爆被害者や空襲被害者にいまだ償いが行われていない中で、国の受忍政策をかえさせる世論を大きくしなければなりません。多くの支援者、団体とともに課題に取り組みます。
特別決議
~核兵器も戦争もない人間社会を~
核兵器使用のリスクが今ほど高まった時はありません。
ロシアのウクライナへの侵攻後のプーチン大統領の核兵器使用をほのめかす発言に、私たち被爆者は、あの広島・長崎の悲劇が繰り返される、という恐れと不安を抱きました。プーチン大統領の発言を受け、日本では国の指導者、国会議員の中から「核共有」の必要性に言及する発言も、聞かれました。アメリカの核兵器を日本に配備し、いざという時アメリカの管理下にある核のボタンを押すことになれば、「唯一の戦争被爆国」を自称する日本が加害国になるのです。原爆投下から80年となる今日まで、核兵器が使用されなかった意味はどこにあるのでしょうか。
日本政府は1970年に発効したNPT(核兵器不拡散条約)を核軍縮の基盤としています。191カ国が批准しているこの条約は、核軍縮にほとんど役割を果たさないまま1955年には無期延期となりました。非核兵器国の苛立ち、不満は募りました。その結果、核兵器の人道上の影響に関する国際会議が開催され、数年の経過を経てTPNW(核兵器禁止条約)が採択、2021年に発効しました。
日本被団協の1956年の結成宣言「世界への挨拶」で「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうと誓いあった」この言葉が、やっと日の目を見ることができました。「人類の危機を救う」一見誇大とも思えるこの誓いが、自分たちと同じ経験をさせたくない、核兵器の使用が何をもたらすかを被爆者が、各自の辛い思いや経験を、語ってきたことによって、核兵器の使用を阻止してきました。核の力、暴力によってではなく、言葉によって、語ることによって、核の使用を抑止したとして、ノーベル平和賞を受賞しました。核を持つことで他国を威す核抑止で、人類を救うことはできません。
私たち被爆者は、
言葉によって、語ることによって、若い世代にも伝えていきます。
若い世代の発信力、行動力の支援をえながら、世論の喚起にも努めます。
そして政策を決定する国内外の為政者に働きかけ、核兵器も戦争もない人間社会へ、リーダーシップを発揮することを求めます。
被爆80年に被爆者の80人の証言動画(日・英字幕)を公開
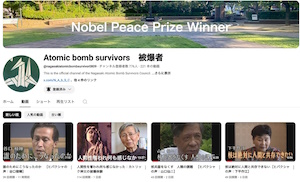 |
長崎被災協
長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)は、被爆80年事業として被爆者インタビュー動画の日本語字幕版と英語字幕版を制作しYouTubeへの公開を始めています。高齢のため被爆者が海外に出かけて体験を語るのが年々難しくなっているため、インターネットを使って動画で被爆者の声を世界に広めるのが目的です。
新たに被爆者にインタビューし、100歳の被爆者のお話も撮影することができました。
 |
その結果、被爆80年に被爆者80人の動画を公開する、との目標を達成できるメドが立ちました。被爆者80人の日本語版動画をすでに公開。現在、英語の字幕を付ける作業を進めています。
長崎被災協のYouTube公式チャンネルは「Atomic bomb survivors被爆者」。左QRコードを読み取ることでも視聴できます。(畠山博幸)
ヒバクシャと出会うカフェ
 |
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会では、「未来につなぐ被爆の記憶プロジェクト」でボランティアが継承の取りみをすすめています。
5月25日、ボランティアの杉野沙歩さんを中心に「ヒバクシャと出会うカフェ=副島圀義さん」を開催し20代~80代の8人が参加しました。副島さんは胎内被爆で当時の記憶はありません。それでも「全部を伝えることはできないけれど、伝える努力をしていきたい」という副島さんの思いを受け止め「心を共有することも記憶の継承につながるという新たな発見がありました。アートを使った心理支援活動などを行っているので、何か活かすことができたらと思います」「育児や仕事で忙しく参加するか迷いましたが参加して良かったです」などの感想が寄せられました。
夏休みに「子ども記者になって被爆体験を伝える新聞をつくろう」という親子向けイベントの準備も進めています。
(島村雅人)
『長野のヒバクシャ80年目の証言』つなぐプロジェクトが完成
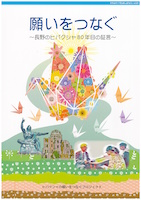 |
長野県内の教員、医療従事者、学生らで結成した「ヒバクシャの願いをつなぐプロジェクト」が、このたび冊子「願いをつなぐ~長野のヒバクシャ80年目の証言」を完成させました。
同プロジェクトは昨年5月から聞き取りを始めました。長野県原爆被害者の会(長友会)が協力して自宅などに出向き聞き取った被爆者8人、被爆2世5人の証言に加えて、長友会のあゆみ、藤森俊希会長の国連での演説、原爆被害者の基本要求、日本被団協のノーベル平和賞授賞理由等も掲載されています。
長野県内の全小中高校、図書館などに配布します。長友会は会員の手記をまとめた証言集「生き続けて~信州の被爆者は訴える」を1971年、76年、81年、96年に第4集まで刊行しています。今回の証言集はこれらを継ぐものになりました。
またプロジェクトメンバーは田中熙巳代表を招いて今年1月19日に長野市で盛大に開催した「ノーベル平和賞を祝う記念講演会・祝賀会」の実行委員にも加わってくれました。(前座明司)
ピアノと声で伝える原爆
 |
兵庫県被爆二世の会
兵庫県被爆二世の会は5月31日、総会を神戸市東灘区文化センターで開きました。二世会員29人と一般の方も含め47人が参加しました。
日本被団協の運動方針で「被爆二世を原爆被害者として明確に位置づけ、医療費や健康診断など被爆者に準じた施策を要求する」旨の報告があり、今後の施策の柱とすべき内容だと感じました。
総会に続いて4回目となる「ピアノと声で伝える原爆」。貞清百合子さんの被爆体験紙芝居『ピカドン』のDVDを初上映。貞清さんも参加され挨拶をいただきました。島本佳直さんが、70歳を過ぎるまで被爆者健康手帳交付の申請をしなかった経緯を含めた父・次雄さんの被爆体験を語り、二世の会朗読グループ「伝える声」は、切明千枝子歌集『ひろしまを想う』から短歌45首を朗読。今後も被爆体験の継承と交流の場として発展すればと願います。(太田光一)
平和への誓い新た
講演会と原爆展
島根・出雲市
日本被団協がノーベル平和賞を受賞し昨年12月の授賞式に参列された、本間恵美子島根県原爆被爆者協議会長の講演会とホール展「原爆と人間展」を、4月19日に島根県出雲市斐川町の荒神谷博物館で開催しました。被爆2世の本間さんが「原爆体験の証言を若い世代に語り継ぐこと、受賞はそのスタートラインに立ったこと」と語られ、戦後80年が経った今、言葉の重みを感じました。
斐川町には、太平洋戦争末期に日本軍がわずか3カ月で建設した「海軍大社基地」があります。滑走路に爆撃機銀河が配備されていたため、島根県にも何度か空襲がありました。県民も平和の尊さは身をもって感じています。
戦後80年は被爆80年でもあります。ノーベル平和賞受賞を機に私たちは原爆の悲惨さ、戦争の恐ろしさを後世へ伝えることの大切さを感じ、平和への誓いを新たにしました。(荒神谷博物館企画監・宍道年弘)
 |
愛媛大学で講演会
国立大学法人愛媛大学は5月23日、「ノーベル平和賞受賞記念講演会~原爆被害者とノーベル平和賞」を開催。日本被団協代表理事で県原爆被害者の会事務局長の松浦秀人さんが、学生、教職員、市民など250人に講演しました。
仁科弘重学長の開会挨拶のあと、胎内被爆者の松浦さんは、母親から聞いた原爆投下直後の広島の様子や、被団協の歩みを紹介。原爆の恐ろしさは「数十年にわたり体をむしばみ続け、子や孫にも時空を超えて被害をもたらすことだ」とし、被爆者が就職や結婚でさまざまな差別を受けてきたことを伝えました。また核抑止力論や核武装論などの暴論を丁寧に批判。学生からの「原爆や戦争を知らない者はどのように学べばよいのか」との質問に「被爆者の声を聴き、原爆資料館で学び、平和のため何かに取り組んで」と答えました。(愛媛大学教授・和田寿博)
被爆80年平和の集い
 |
愛媛
「ノーベル平和賞受賞記念、被爆80年・平和の集い」を6月14日、愛媛県松山市民会館で開催しました。原水禁・原水協・労働組合・生協・民主団体を中心に実行委員会を結成。行政も協力し、県内マスコミもこぞって後援しました。
田中英子さんの被爆証言、松浦秀人日本被団協代表理事のノーベル平和賞受賞報告と、劇団民芸の日色ともえさんが県内被爆者の手記を朗読。また、市村公子さんがうたごえ運動の中から生まれた「死んだ女の子」を歌いました。ロビーに展示した被爆写真を、参加者は食い入るように見つめていました。
(実行委員会)
核兵器使用の危機訴え
 |
広島被爆者7団体は5月22日、日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める署名行動を広島平和記念公園で行ないました。戦後・被爆80年という大きな節目を迎える中で、世界各地で戦争が勃発し、かつてなく核兵器使用の危機が高まっています。「これ以上被爆者を生み出してはいけない」と、道行く人々に署名を呼びかけました。
2026年NPT再検討会議第3回準備委員会は、市民の声を反映することができないまま議長文書の発表にとどまりました。世界は被爆国日本の姿勢に注目しています。日本政府が核兵器禁止条約に一日も早く署名、批准することを求める呼びかけに、修学旅行生や外国人旅行者からも署名が寄せられ、30分で161筆が集まりました。(中谷悦子)
訃報
飯田マリ子さん
6月1日死去。93歳、長崎被爆。
13歳のとき立山町の自宅で被爆しました。
1958年、東京北区の被爆者の会結成に参加し、69年から2014年まで東京都原爆被害者団体協議会の理事、財政部長、副会長、会長を歴任。オランダ・ハーグの国際司法裁判所行動やNPT再検討会議など海外の行動にも参加しました。
1992年~98年と2002年~06年に日本被団協代表理事。
増田善信さん
6月9日死去、101歳。非核の政府を求める会常任世話人、元気象庁気象研究所研究室長、元日本学術会議会員。
広島の「黒い雨」を巡り、証言集の読み込みや丹念な聞き取り調査によって1989年「増田雨域」を発表。2021年の「黒い雨」訴訟広島高裁での全面勝訴に貢献しました。
2020年に始まった厚労省の「黒い雨」に関する検討会に、日本被団協推薦の構成員として参加。科学的知見に裏付けられた発言は、謙虚な人柄も相まって出席者の尊敬を集めました。
相談のまど
介護保険 介護度認定に不服の場合
「要支援」は再申請、「要介護」は区分変更手続きを
【問】「被爆者のしおり」が届いたので電話しました。80歳も中ごろのひとり暮らしです。家賃の安い部屋を借りています。数年前に脳梗塞になって左足に麻痺が残り、身体障害者手帳4級をもらいました。その後、右膝関節も悪くなり、部屋が狭いのでまわりにあるものにつかまって移動しています。病院へも歩行車を利用して何とか行っています。トイレも間に合わないので紙パンツを使っていてお金がかかります。最近はもの忘れもひどくなり、毎日探し物で過ぎてしまいます。
介護保険の手続きをしたら「要支援2」ということで、私は納得できません。デイサービスに行って入浴もさせてもらいたいし、掃除や洗濯も手伝ってほしいと思っています。「要支援2」であきらめなければならないのでしょうか。
* * *
【答】体が不自由なのにひとり暮らしでは大変ですね。「要支援2」という結果に納得できないのであれば再申請をしてください。「要介護」の場合は「区分変更」の手続きをしますが「要支援」の場合は再申請となります。
訪問調査時には74問の調査項目があります。特に問題となるのは認知機能と排泄についてです。もの忘れがひどくなり1日中探し物をしていること、トイレも間に合わないので紙パンツを使っていることは強調してください。
主治医にも、もの忘れがひどくなったことやトイレが間に合わなくなっていること、家の中での移動も大変なことを伝えてください。前回調査の時は何も聞かれなかったとのことですが、今回はしっかり話をしてください。
「要支援」ではなく「要介護1」になったけれども、本人の状態はもっと重いという場合は、介護保険証に書かれている認定期間中でも「区分変更」の手続きが出来ますので申請してください。
介護に関しては、大変な状態が主治医と訪問調査員にはなかなか伝わらないのが実情です。きちんと伝える努力をしてみてください。
空港に平和の壁画
広島とメキシコ、ノーベル平和賞受賞者つないで
クラウドファンディングも開始
広島国際空港に「核のない世界へ 広島メキシコ友好壁画」が誕生します。原爆投下80年を機に平和と核廃絶のメッセージを広島空港より大胆に発信します。
広島県は2014年にメキシコのグアナファト州との友好提携を結んでいます。この取り組みには日本被団協も賛同。メキシコは、世界初の非核兵器地帯条約であるトラテロルコ条約を主導し、近年では国連の核兵器禁止条約の提案国、採択後は締約国会議の議長国を務めるなど、非核外交の先頭に立ってきました。
壁画には、メキシコ人ノーベル平和賞受賞者の故ガルシア・ロブレス元外務大臣と日本被団協の被爆者や折り鶴も描くことを検討。核なき世界に取り組んできた両国の受賞者の繋がりの象徴となります。除幕式は10月15日を予定しています。
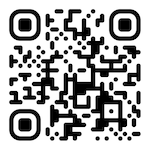 |
プロジェクト実現のため、クラウドファンディングを7月7日に開始します(9月7日まで)。皆様の温かいご支援をお願いいたします。(企画提案者・元ピースボート国際コーディネーター・グティエレス一郎)
寄付のご協力はこちらへお願いします。 https://readyfor.jp/projects/hiroshima-mexico

