「被団協」新聞2024年12月号(551号)
2024年12月号 主な内容
ノーベル平和賞
街頭で、事務所で…各地で横幕かかげ
署名への反応も良く
 |
| 札幌南高校定時制の生徒制作のモザイク画と生徒たち |
 |
 |
| 広島署名行動 | 石川署名行動 |
 |
 |
| 長崎被災協事務所 | 千葉署名行動 |
 |
 |
| 神奈川慰霊碑前 | 埼玉慰霊碑前 |
 |
 |
| 北海道署名行動 | 静岡署名行動 |
 |
 |
| 広島・三原市原爆展 | 広島(佐久間)事務所前 |
ノーベル平和賞が日本被団協に授賞(10月11日発表)されたことを受けて、各地で「祝・ノーベル平和賞」などの横幕が製作され、事務所前に掲げる、街頭行動でアピールする、などが行なわれました。
日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める署名活動では反応も良く、街頭に立った被爆者と支援者も元気をもらっています。
1面の写真に関する記事は2面、3面、4面に掲載しています。
企画展「史料が語る日本被団協の歩み」
戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト
昭和女子大3年 大塚美莉亜
私たち昭和女子大学戦後史史料を後世に伝えるプロジェクトは、11月9日、10日に開催された昭和女子大学秋桜祭において、企画展「史料が語る日本被団協の歩み」を開催しました。プロジェクト発足からの秋桜祭展示も7回目となりました。
現在ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が所蔵する日本被団協関連史料は、1万8000点にのぼります。同会の栗原淑江さんのご協力のもと史料の厳選を行ない、「組織の立ち上がり」「調査活動」「対政府交渉」「国際活動」の4つの観点から、日本被団協のこれまでの取り組みを最もよく表す約50点の史料を展示しました。
2日間を通じて600人近い方にご来場いただき、「生史料を見る貴重な機会となった」「被爆者のリアルな様子を知ることが出来た」などの感想をいただきました。
また、今年はプロジェクト初の試みとして音声ガイドを作成しました。史料の解説や注目ポイントを知っていただくために、原稿から音声の吹き込みまですべてを学生が行ないました。
現在注目が集まっている日本被団協ですが、一時的なものに留まらないよう、被爆者たちの運動の歴史を伝え続けるために、引き続き積極的な活動を続けていきます。
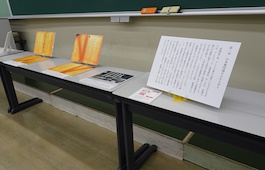 |
 |
| 展示の様子 | |
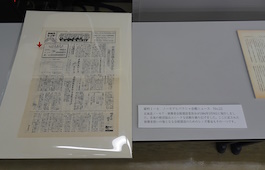 |
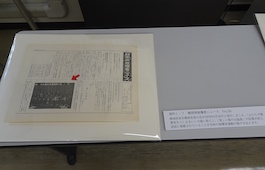 |
| 展示された史料 | |
次世代へつなぐ
 |
熊本被団協
熊本被団協は日本被団協のノーベル賞受賞を受け10月23日、熊本市健康センターで記者会見を開きました。一世・二世合わせて11人が参加し、2時間にわたって平和への熱い思いと核兵器廃絶の重要性を語りました。
記者からの質問は、被爆当時の壮絶な体験を持つ3人の女性被爆者に集中。「生きている限り次世代へ伝えていく」との強い決意が何度も語られました。その言葉には、時間を超えた深い痛みと、未来への希望が込められていました。
熊本被団協は、今回の受賞を新たな出発点として、平和の祈りを次世代へつなぐ決意を強めました。今こそ、私たちは被爆者の祈りを受け継ぎ、核兵器のない世界を次の世代へ引き継ぐ責任を共有する時です。(三村貴久)
「これからが大事」と訴え
北海道
10月29日、札幌平和行動実行委員会と北海道原水協は、ノーベル平和賞受賞の興奮も冷めやらぬ中、国連軍縮週間にちなんだ平和行動を札幌駅前で実施(写真1面)。被爆者協会の金子廣子副会長が自らの被爆体験を語りながら「受賞は正直うれしい、でもこれからが大事、必ずや核兵器のない世界を」と道行く人々に熱く訴えました。
北海道被爆者協会は、12月にはノーモア・ヒバクシャ会館の壁面に道民向けメッセージ「核兵器も戦争もない世界を、ともに」を貼り出すとともに、北海道庁ロビーで「受賞記念 ヒロシマ・ナガサキの証言の会」を開催する予定です。
(北明邦雄)
核兵器なくすまで頑張る
秋田
2024年10月11日は日本被団協を構成する秋田県被団協にとって忘れられない日となりました。朝日新聞秋田版は翌日、相川修会長の喜びの声を伝えています。秋田さきがけ新報では13日、秋田県被団協の60年間の活動・運動を詳細に記事にし「秋田県被団協は小さな組織だが最後まで日本被団協と共にある」という会の方針を載せています。読売新聞は、今回の受賞をチャンスに県被団協発行の『秋田の被爆者』の56人の体験が若い世代に語り継がれることを願っているという被爆者の声を報道しました。
県被団協事務局には、受賞の喜び、おめでとうなどの声が多数届いています。これらの声に励まされ、秋田県被団協は世界から核兵器がなくなるまで頑張る覚悟です。
(佐藤力美)
原爆死没者慰霊碑に報告
埼玉
10月11日は被団協全国都道府県代表者会議から続く最終の中央行動の日でした。この日の朝日新聞夕刊は、今年のノーベル平和賞は対象無しだろうとの記事。外用事の最中、新聞記者から「おめでとうございます」の携帯電話。はじめ何事の「おめでとう」かわかりませんでしたが、事分かり静かな喜び。
16日、昨年から計画の埼玉県立浦和高校広島修学旅行事前学習。1カ月前に田中煕巳名誉会長(しらさぎ会)を講演者と決めていました。ノーベル平和賞発表後最初の講演となり、テレビや新聞の多くの取材で大変な騒ぎとなりました。
17日、木内恭子副会長が肥田舜太郎先生の墓に報告。23日、さいたま市別所沼公園にある「埼玉県原爆死没者慰霊の碑」に役員で報告参拝しました(写真1面)。(髙橋溥)
歌とトークで訴え
千葉
日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める千葉の会は10月30日、JR柏駅北口デッキで署名行動をしました。「祝・日本被団協ノーベル平和賞受賞」の横断幕が駅利用者の目をひきました(写真1面)。
5団体18人が参加し、ギター伴奏で歌声が響く中、リレートークで訴えました。被爆者は被爆被害の実相を語り「ふたたび被爆者をつくってはならない」と署名の協力を求めました。
足早に駅に向かう女性も、快く署名に応じてくれました。学校帰りの中学生3人に日本被団協へのノーベル平和賞の授賞理由を話すと、「学校で被爆者の証言を聞いたことがあります」と言って署名しました。1時間で43筆の署名が寄せられました。(荒木忠直)
原爆被災者慰霊碑に報告
神奈川
神奈川県原爆被災者の会では10月31日、鎌倉市の大船観音寺境内にある原爆被災者慰霊碑の前に集い、先輩方のたゆまぬ努力と活動に感謝し、ノーベル平和賞受賞の報告をしました(写真1面)。
広島、長崎への原爆投下から79年間、一度も核兵器が使われなかったのも、この受賞も、被爆者の「核の恐ろしさを伝え、同じ思い、辛さを世界中の誰にもさせてはならない」との強いスローガンが認められた証だと、皆で喜び合いました。
被爆者の平均年齢が85歳を超えた今、次の世代にバトンを繋ぐことが急務だと日々感じるこの頃です。(西純子)
核兵器なくす運動、いっしょに
石川
核禁条約署名石川県連絡会は10月22日、金沢市の繁華街で日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める街頭署名を行ないました。日本被団協のノーベル平和賞受賞の横幕を掲げての行動となりました(写真1面)。
被爆者の西本多美子さんがスピーチ。被爆国の日本こそが禁止条約に署名・批准すべきだと語り「世界から核兵器をなくす運動を一緒にやっていきましょう」と呼びかけました。30分で22人の署名が集まりました。
(石川県連絡会)
緊急署名行動横断幕かかげ
静岡
静岡では10月22日、日本被団協のノーベル平和賞受賞をお祝いして、静岡市の繁華街ケヤキプラザ前で緊急の署名宣伝行動を行ないました。
お昼の1時間でしたがノーベル平和賞受賞発表直後のこともあって、手づくりの横断幕を掲げての行動(写真1面)に市民の反応も良く、1時間に38人の署名が寄せられました。(磯部忍)
事務所建物前に横断幕掲示
広島(佐久間理事長)
ノーベル賞受賞を、広島の町の人にも知っていただこうと、事務所の建物の前に、横断幕を掲示することにしました。
まず建物のオーナーさんに了解していただくため連絡をすると「とても光栄なこと」と快諾していただきました。出来上がりは縦90センチ、横3メートルの、色も爽やかなブルーの横断幕です。
11月8日、みんなで知恵を出し合い掲示しました(写真1面)。これを見た人からは「すばらしいね」と喜んでいただいてます。(望月みはる)
中央相談所講習会
近畿
 |
11月9日、神戸市内で中央相談所の近畿ブロック講習会を開催、31人が受講しました。
日本被団協近畿ブロックの立川重則代表理事が挨拶で「ノーベル平和賞を受賞しヒダンキョウが国際語となった。長年にわたり被爆者は核兵器を絶対悪と言い続け、禁止・廃絶を世界に発信してきた」と述べました。
午前は日本被団協の濱住治郎事務局次長が「日本被団協の運動とその歩み」を講演。運動をどの様に展開してきたかを、資料・プロジェクターを駆使して語り、「先達のご苦労がよく分かった」「結成以来の日本被団協の運動の歴史、地道な活動がよくわかった」などの感想が寄せられました。
午後は中央相談所の原玲子相談員が講演。病院の差額ベッド代などの費用負担の問題、ジェネリックと先発薬との薬代の問題、介護に関する問題など詳しく説明がありました。(山本裕治)
東海北陸
 |
11月10日、11日に静岡県掛川市の掛川グランドホテルで、東海北陸ブロック講習会が開かれました。51人の被爆者、二世らが参加し、中央相談所の原玲子相談員と生協きたはま診療所の聞間元医師の講演を聞きました。
原さんの講演のテーマは、被爆者の援護と介護問題。被団協結成から68年を経て、「核兵器廃絶」と「国家補償の援護法制定」を求める運動が次世代にどう伝えるか、また憲法25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活」の保証が重要であることも強調されました。
聞間さんは、内部被曝や放射線の人体への影響、核兵器禁止条約と核抑止問題について講演。放射線については、体内の微粒子による被ばくの過小評価を指摘しました。また唯一の戦争被爆国でありながら米国の傘に依存する日本政府の姿勢を批判しました。
11日は二世三世交流会が開かれました。
(深沢税)
中国
 |
中国ブロックの講習会は、2年ごとに中国5県の持ち回りで開催しています。今年は岡山県総社市のサントピア岡山総社で11月12日に55人の参加で開催しました。
最初に、日本被団協のノーベル平和賞受賞が話題になり、参加者全員で喜びを分かち合う講習会となりました。
日本被団協の濱住治郎事務局次長から「被爆80年にむけて」のなかで、日本被団協の運動とその歩みについて、年代ごとの運動の話があり、改めて被爆者運動を再認識し、今後の運動を考えるきっかけになりました。
中央相談所の原玲子相談員からは、「被爆79年の今、被爆者の援護・介護問題」について、被爆者援護施策が高齢者になった被爆者に活用されているか、介護保険制度は上手に利用できているか、被爆者独自の介護手当の積極的活用について話がありました。介護の必要な人、施設に入居する人が多くなった今、被爆者に積極的に寄り添い、制度を広める必要性を痛感しました。(廣信靖之)
 |
東京被爆二世・三世の会
おりづるの子(東京被爆二世・三世の会)は11月3日、東京文京区の平和と労働センターで、秋の学習会を開きました。
被爆の記憶を伝えるために、被爆者の想いを絵に表現することに挑んだ広島市立基町高校卒業生の一ノ間照美さんと竹本茜さんから、「原爆の絵」完成まで被爆者と一心同体の感性で絵を懸命に描き切った貴重な体験談をお聴きしました。「原爆の絵」は2007年から広島平和記念資料館の主催する次世代と描く原爆の絵として続き、二百点を超えています。
その後、被爆者の想いを忠実に絵にしようと葛藤する高校生の姿を舞台化した、劇作家で演出家の福山啓子さんから、青年劇場の公演「あの夏の絵」の逸話や上演の反響などをお聴きしました。
「原爆の絵」と「あの夏の絵」を研究されている大学及び大学院の教授や、映画監督、ジャーナリスト、学生も多く参加し、40余名が集う有為な平和学習になりました。
(澤原義明)
支部の活動「再開」
 |
愛友会瀬戸支部
10月27日、愛知県瀬戸市で愛知県原水爆被災者の会(愛友会)瀬戸支部の「再開総会」が開催されました。瀬戸市の被爆者の会は役員のなり手がなく、長らく休止状態でした。
「再開総会」は被爆者2人、被爆二世3人、支援者10人が集まり、愛友会から大村義則副理事長が参加して開催。被爆2世の太田智恵子さんを会長に選出し、会の再開を決定しました。
瀬戸市では支援者が被爆者とつながり、日常的に支援する活動がありました。今回の総会で、被爆者と被爆二世が会員となり、支援者が会に参加して運営を支援する体制が相談され、再開を決定しました。
愛友会では、被爆者支援ネットワークと協働の体制をつくり、地域の支部ごとに被爆二世三世と支援者で組織を維持し、被爆体験の語り部活動や核兵器廃絶を求める運動を継続しようと取り組んでいます。(大村義則)
 |
被爆二世交流会 兵庫
10月26日、第6回兵庫県被爆二世交流会を神戸市中央区文化センターで開催しました。22人の参加があり、新入会員5人も参加しました。
二世の会制作の紙芝居「長崎で原爆に遭って」と「ピカドン」の原画を展示。貞清百合子さんの証言による「ピカドン」は西岡由香さんの絵で、被爆80周年に公開予定です。貞清さんと西岡さんも参加くださいました。
ノーベル平和賞に日本被団協が選ばれた喜びの声が多くありました。受賞理由の「被爆者の経験とメッセージを伝え続ける新しい世代」には、二世も含まれるとの思いもありました。
交流会では二世健診の内容が話題に。「不十分」の声が多く、また精密検査は「医師が必要と認めるもの」とされ基準が分からないなど、健康への不安に国の対応がなされていません。「不十分」だと言い続ける必要があります。(太田光一)
大学の授業で講演
 |
愛媛
10月31日、愛媛大学の平和学で、愛媛県原爆被害者の会の松浦秀人事務局長が「被爆者の体験を語る」と題する講演を行ないました。胎内被爆の松浦事務局長は、母親の被爆体験を皮切りに、時空を超えて広がる原爆被害の恐ろしさを語りました。毎年の授業ですが、今年はノーベル平和賞受賞のためNHK松山放送局や地元紙などの取材と報道がありました。
授業に参加した学生からは「被爆者のつらさを実感できました」「改めて(核兵器の)怖さを感じた」「選挙に必ず行くというところから、自分にできることを考え続けたい」など感想が寄せられました。(松浦秀人)
 |
神奈川
9月29日、「神奈川県原爆死没者慰霊祭と追悼のつどい」が、鎌倉市の大船観音寺境内慰霊碑前で、被爆者と遺族51人と来賓ほか合わせて94人の参加で行なわれました。死没者を偲び、平和への誓いを新たにしました。
秋とはいえ夏の暑さが続く中、一時の涼しさを感じていただこうと冷やしたおしぼりを全員に配布。参加者から「最高のおもてなし」の声をいただき、スタッフ一同安堵しました。(木本征男)
高校生も参加して
 |
兵庫
兵庫県原爆死没者追悼慰霊祭が10月12日、48人が参列し、厳かに執り行なわれました。
立川重則理事長は、日本被団協のノーベル平和賞受賞を報告し、イスラエルのガザ攻撃にも触れて「核攻撃を止めさせるには核廃絶しかない」と訴えました。兵庫県疾病対策課、反核医師の会、兵庫原水協から追悼の辞をいただき、高校生平和大使の2人が追悼のことばを述べました。
節目となる被爆80年を前にノーベル平和賞を受賞、碑前に良い報告ができました。(山本裕治)
受賞後初の街頭行動
広島
日本被団協へのノーベル平和賞授与発表後初の広島被爆者7団体による街頭署名活動が11月22日、平和記念公園で行なわれ、代表者と支援者ら14人が参加。「ノーベル平和賞受賞」の横断幕も掲げました(写真1面)。
広島県被団協の箕牧智之理事長は「活動の歴史が認められたが政府に批准を訴えていかねばならない」と強調。観光客、若者たちが祝福の言葉とともに署名し、約30分で83筆が集まりました。
これに先立つ10月13日には、箕牧理事長ほかが平和公園慰霊碑に受賞を報告し、事務所前に受賞横断幕を掲げました。
また三原市原爆被害者之会は、10月19日に同市の原爆慰霊碑に受賞を報告。28日には市内で「原爆と人間展」を開催(写真1面)し、受賞ボードを掲示しました。(田中聰司・熊田哲治)
結成3周年集会
 |
岩手県民の会
日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める岩手県民の会は9月29日、盛岡市で結成3周年の集会を開催しました。
同会代表の三田健二郎県被団協会長が「日本がいまだ条約に批准せず核兵器廃絶に背を向けている。運動を大きく盛り上げ政府に迫って行きましょう」と挨拶しました。
ピースボート国際コーデイネーターの渡辺里香さんが記念講演し、続いて、高校生平和大使・青年と渡辺里香さんとのトークセッションが行なわれました。
会では日本政府に批准を求める署名の目標20万筆をめざし、引き続き宣伝、学習、署名運動に取り組みます。(西山剛)
核廃絶ピースウェーブ
 |
宮城
9月22日、4回目となる「核廃絶ピースウェーブinみやぎ」を30人の参加で開催しました。
最初は平和の歌。雨が降っていましたが屋根付きのステージで歌い、うっとうしい気分は吹き飛びました。ミニ集会では木村緋紗子代表があいさつで「唯一の被爆国が核兵器禁止条約に入らないことは本当に悔しい。力を合わせて変えていきましょう」と訴えました。
決意表明では、平和友好祭実行委員会の渡邊副委員長が、来年の被爆80年には広島・長崎に多くの仲間を送りたいと述べました。
最後に全員でもう一度「青い空は」を歌い、ピースコールをして終了しました。
雨が強くパレードと署名活動は中止にしましたが、東日本放送が取材に来て夕方のニュースで流してくれたので、市民へのアピールになりました。(核兵器廃絶ネットワークみやぎ)
相談のまど
地域での被爆者相談
電話やアンケートで状況把握を
【問】私は地域の会で相談員をしていますが、なかなか相談がなく、どうしたらいいのか悩んでいます。会員さんも減ってきているのですが、それにしても、と思ってしまいます。先輩たちの姿を見て、私も役に立ちたいと相談員を引き受けました。皆さんはどうしていますか。
* * *
【答】被爆者の平均年齢が85歳を超えた今、相談したくても自分から行動を起こすことが難しくなってきているのではないかと思います。
会員さんにせめて年1回でも電話をかけて様子を聞いてみる、というのはどうでしょう。そして「何かあったら電話をかけて」と話してみたらいかがでしょうか。
そうはいっても耳が遠くなり電話での会話も困難になってきたと、青森県の会では年1回訪問することにしたそうです。その結果、介護が大変、施設に入所するには「要介護度」の要件に満たないがどうしたらいいか、などの声をつかんでいます。被爆者手帳の助成対象となった「認知症共同生活介護(グループホーム)」についても、地域でつかんできた要望を被団協に寄せた結果実現したものです。
多くの会が、会員にアンケートを行なっていますが、これも継続して取り組むことが大切です。1度では反応がなかったけれど何回目かに悩みが書き込まれ、相談につながったこともあります。
相談員から「実際にどんな相談が来るかわからなくて不安」という声もききます。わからないときは「調べてみます」と返事をしながら、じっくりと話を聞くことだけでも相談をした人にとっては半分解決したようなものです。何かあった時に話を聞いてくれる場があると思い安心します。
会報などで相談日を知らせることも効果があると思います。今は介護問題が主な相談だと思いますが、会報に「介護手当」についての記事を載せるのもいいかもしれません。あなたの思いを、ひとりぼっちで暮らしている被爆者や、介護で疲れている家族に伝えたいものです。
おたよりから
生徒につるバッジを
北海道 野口 隆
北海道被爆者協会賛助会員の北海道札幌南高校定時制地歴公民科教諭の野口と申します。
この度はノーベル平和賞受賞おめでとうございます。北海道被爆者協会様のご協力をいただきながら平和学習をすすめてきたので、自分事のように嬉しい気持ちでいっぱいです。「被団協」新聞を拝読し、シンボルのつるバッジを知りました。私が担任をし今夏朗読劇「あの日あの時ヒロシマで」を道庁ほかで上演したり、「嵐の中の母子像」と「長崎平和祈念像」の巨大モザイク画(1面に写真)を制作した生徒たちに受賞の記念としてプレゼントしたく、つるバッジを発注させていただきます。よろしくお願いいたします。
朗読劇は北海道被爆者協会発刊の「未来への架け橋 被爆者の証言第4集」に掲載されていた道内在住(故人も含)の広島での被爆者3名の手記を脚本化、生徒たちの手で上演しました。今夏は長崎での被爆者3名の手記を基にした朗読劇を計画していて、定時制生徒全員で「焼き場に立つ少年」をモチーフにしたモザイク画も制作します。
投稿 「オッペンハイマー」と「リッチランド」
鳥取 石川行弘
広島、長崎の原爆開発に関連する映画を見た。「オッペンハイマー」については、被団協新聞に田中、箕牧両代表委員が投稿されているので詳しく述べないが、映画の中で「scientific gamble」という言葉があった。初めて聞く言葉であり、どんな場面でどのような意味を込めて話されたのか分からず気になっていたが、原作の和訳(河邉俊彦『原爆の父と呼ばれた男の栄光と悲劇』)に記述を探し出せなかった。
トルーマン大統領は広島への原爆投下の報告を受け、1945年8月6日、ホワイトハウスで出した声明の中に「われわれは、歴史上最大のscientific gamble(科学的賭け)に20億ドルを費やし、そして勝利した」とあった。単純に20億ドルもかけた膨大な開発費用の成功を喜び科学的賭けに勝った? もっと深い意味があると思ったのだが。しかし、gambleとは、もやもやの残る言葉ではある。1946年5月にはオッペンハイマーのことを「原子力を発見したために手が血だらけ、とぬかした泣き虫科学者」と酷評している。映画の中でも印象に残るところ。彼はマッカーシー旋風の赤狩りで徹底的に排除された。この言葉で感じたことは、以降、核兵器は政治家と軍人の手に完全に握られ、支配される状況になったこと。
トルーマンは、その生い立ちから人種差別主義者の性格が強いようだ。原爆の投下に関しては開発に関与した科学者のみならず、マッカーサー、アイゼンハワーなどの前線の司令官、陸軍長官、参謀総長、大統領付き武官などの軍人は懐疑的であるのに対して、国務長官のバーンズは極めて強硬な意見の持ち主で、トルーマンは完全に彼に引きずられたようだ。大統領になって、自分の弱みを見せないためにも、重要課題に対してあまり時間をかけないで即決の判断をして命令し、原爆の放射線の怖さを認識しながらも原爆投下の命令を早々と下している。人種偏見があるために、原爆投下に心の呵責を感じることなく行動できたのだろう。しかも実戦実験が成功したのだから大喜びしたに違いないし、戦後になっても原爆投下の正当性を言い続けてきた。ルーズベルトだったら躊躇したかもしれない命令だが。
永井隆博士は被爆当時、長崎医科大学の放射線科の医師だったが放射線病にかかってしまった。『長崎の鐘』にあるように敵機の撒いたビラを見て、原子爆弾であると認識している。8月9日に被爆した後の治療・救護活動などを通して観察した結果と照らし合わせて合点した。しかし、原爆を評して「科学の勝利、祖国の敗北。物理学者の歓喜、日本人の悲嘆。私は複雑な思いに胸をかき乱されつつ、酸鼻を極むる原子野を徘徊した」とある。この本は、長崎被爆の後の状況を詳細に記録しているので、是非読んで欲しいものだが、人間の尊厳をずたずたに踏みにじる核兵器開発を「科学の勝利、物理学者の歓喜」などと言ってほしくないし、大いなる違和感がある。トルーマンでもあるまいし。
「リッチランド」はドキュメンタリー映画で、2024年7月9日、広島市内の横川シネマで先行上映された。アイリーン・ルスティック監督も交えたトークもあり、川野ゆきよ(アーティスト、米国在住の被爆三世)さんがオン・ラインで参加した。リッチランドはアメリカワシントン州にあり、長崎原爆のプルトニウムを製造する原子炉のあったハンフォード・サイトに働く人々が住んだ町である。映画はこの町中に起こっている日常を捉え、トラウマをかかえて現在をどう生きているかをテーマにしている。原爆製造にかかわって放射線障害にかかっても、経済的な富をもたらしたことや、今は汚染除去の仕事に政府の金が入って豊かな生活ができていることを誇りに思っている人がいる。汚染除去作業で病気になる危惧があると言われても、家族を養える方が大切で、反対するのはシアトルなどの都会人だという。
一方で、リッチランド高校生は校章のキノコ雲にあまり良い印象を持っておらず、全米で悪評の高い校章の10の1つになっているという。核兵器には反対の立場で話していたが、必ず賛成して意見対立する同級生がいるとも言っていた。
映画のポスターに描かれている風船のような芸術品は川野さんの作品「ファットマン」で、長崎原爆開発76周年式典のときに招かれて披露したもの。ファトマンの実物大の大きさで、被爆した祖母の着物をほどいた布を自分の髪の毛で縫い上げたという。
上映の後、会場でトークが行なわれ、その終了後、監督とも話す機会があった。(つづく)

