「オオウソのあらすじ」のこと
はてなブログへのクレーム掲載はHatena Blog2025-01-10、当方がこれを知ったのは2025-09-06、ポル・サンボールに関連する資料をネットで探していた時でした。ポル・サンボールって?なになに?
ええ、KhasyaReportはポル・サンボールに夢中です。
スリランカを代表する作家・マーチン・ウィクラマシンハ氏මාර්ටින් වික්රමසිංහ මහතාがポル・サンボールපොල් සම්බෝල を名作難解と評価の高い小説・ウィラーガヤに登場させています。シンハラ人の生活文化の基にあるのは、金持ちも貧乏人もすべての人が食べるポル・サンボールだ。ここに私たちの原点がある。そう言わんばかり。プリ・コロニアルへの回帰を求め、サロマを纏って海岸を歩く。晩年はヌワラ・エリヤの街のその奥のバンダーラウェワという山村に籠りました。
その暮らしを気取ったわけでもないけど、当KhasyaReportも山の中にあります。縄文回帰の東北の山里。ここを訪ね来るシンハラは「バンダーラウェワみたい」とカシャグラのこの地を評します。どんな意味でそう言ったか、はてさて分からないけど私はとてもうれしい。私は彼らにポル・サンボールとハールマッソーを作ります。草の芽吹きは遅いからゴトゥコラとムクヌワンナが力強く育つのは10月に入ってから。この時期、サンボールもマッルンも深い秋の中で濃緑に染まっているのをバリバリと引き抜きます。
ポスト・コロニアルの激動する転換期を経てなお、ウィクラマシンハ氏の小説にはポル・サンボールが食卓に載っている。シンハラの村の暮らしのシンボルとして小説ウィラーガヤの主人公アラウィンダにウィクラマシンハ氏はポル・サンボールを食べさせています。ああいやだいやだ、こんな食事貧乏くさいと蔑まれるポル・サンボール。でも、それはプリ・コロニアルの時代の清貧で美しい暮らしを象徴する。時代を巻き戻せ。コロニアルの時代、キャピタリズムの嵐に踏みつぶされた村の暮らしが息を吹き返すように。
ポル・サンボール。料理に虚飾はいらない金はかけない。山里に生える草を食え。ウィクラマシンハ氏は粋だねぇ。これをウィクラマシンハ氏と並ぶ文壇二大巨匠のエディリウィーラ・サラッチャンドラ教授මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්රなら小説の中でどう扱うのだろう。はたと疑問が湧いた。小説のページを綴ってみるか。こんな風にして庶民派の食い意地から文豪たちの小説を覗くのはKhasyaReportぐらいかしら。
サラッチャンドラ教授を扱う記事を探してあれこれキーボード叩いてみた。そうしたらポル・サンボールなんか知らないだろうStantsiya_Iriyaさんがお書きになった『南の島のカレーライス』関連の記事が出てきたりして。あれあれ、なんだこれ?あんな昔の本、丁寧にお読みいただいてご指摘あり助言あり、また宣伝あり。ありがたくもあり、また、とちりあって、ああ悲し。『南の島のカレーライス』はカレーで読み解く民俗論なのにカレーに全く触れずサラッチャンドラ教授の短編小説、ああだこうだ、ばっかり。加えて『南の島のカレーライス』は「オオウソのあらすじ」を書いている、と来た。
『南の島のカレーライス』は30年も前の本だけど、今更に出て来たいたずらの悪意っぽい指摘を放っておくのもなんだな。『南の島のカレーライス』のカレーでない部分へのご指摘の件、胡散臭いからちょっと遠巻きに眺めておこうか、『南の島のカレーライス』の執筆者はもう山に籠って自適に没入して久しいけど『南の島のカレーライス』の読者の方々が若しやあれを眼にして、万が一だ、そんなこと決して無いだろうけど戸惑ってもいけないし、誤解曲解したら尚いけないし、『南の島のカレーライス』は市販されている本で「オオウソ」を記載しているなら本を買い求めた読者の経済的損失を招いたことになるし、とご指摘の件、何とかBlogなんてウソ臭無視と決め込まずお節介を焼くことになりました。
ここからお話しするのは誰も知らないようなスリランカ文学の世界ですが、これが、日本人の精神世界や文化と重なることもあり、また、言語としてもいわく有り気なシンハラ語と日本語の関係に小説の主人公が小説のクライマックスで触れていることから、こうして記事を書くのも大切だな、かしゃぐら通信のテーマ・シンハラ語にも関わりそうだし、サラッチャンドラなんて関係ないやと言う方がこの先のお節介を読まれても「読んだ時間、損した」なんてことにはならないはずとばかりに進めさせていただきます。『南の島のカレーライス』のカレーではない部分、取るに足らない部分ですけどその補足です。
「オオウソのあらすじ」指摘へのお応え
『南の島のカレーライス』の作者はサラッチャンドラ教授の小説に関して「オオウソのあらすじ」を並べてるとStantsiya_IriyaさんがHatena Blogでご指摘なさるのは次の三点です。小説の中で、
以上、サラッチャンドラ教授の二編の小説を日本語に訳して一遍にまとめた南雲堂刊「亡き人」(E・サラッチャンドラ著・野口忠司訳 1993)のご本だけを読まれてのご指摘のようです。簡潔にお答えして、
1 デウェンドラさんであり、ダルマさんでもある。
2 一㍉どころか小説の中でおろおろして何度も何度もスリランカ人女性が出てくる。
3 誰であろう、作者のサラッチャンドラ教授自身から。
|
あッ、3は「聞いたん」じゃなくてエディリウィ―ラ・サラッチャンドラ教授の小説で読みました、ということです。エリックじゃなくて。
それではざっとサラッチャンドラ教授のことを中心に据えて文学畑の様子をお話しします。
ノリコさんの恋愛小説三篇 東京を舞台に
エディリウィ―ラ・サラッチャンドラというペラデニヤ大学の教授でスリランカ文学界演劇界の巨匠が、もう亡くなって久しい方なのですが、その昔、日本を舞台にした恋愛小説を三冊記されました。サラッチャンドラ教授はその昔、セイロンを発ちインドからアメリカへ向かう途中、1955年から56年に掛けて一年ほど日本に滞在しました注1。その目的はスリランカに伝統演劇の劇場を作るための調査、下準備で、日本では歌舞伎と能を視察しました。それほど日本には興味がなかったとご本人は自伝で仰るけど、歌舞伎に出会い、古典芸能が現代に通じる力に感銘し、滞在が延べ一年にわたり、日本の東京が舞台の摩訶不思議な恋愛小説を三冊誕生させることになります。
その恋愛小説、まずはマラ・ギヤ・アットゥමළගිය ඇත්තෝ (1959)とマラウンゲー・アウルドゥ・ダーමළවුන්ගේ අවුරුදු දා(1965)というタイトルの短編二冊です。日本へやって来たシンハラ人の男性「デウェンドラさん」と日本人女性「ノリコさん」の純愛がテーマ、東京を舞台に物語が進行します。
また、後にこれら二冊をご本人がまとめて、物語の進行など内容に大胆な手を加えて、しかもシンハラ語を離れて英語版でForm upon the stream(1987)注2というタイトルの本に仕立ててユネスコから出版しました。三冊目のノリコさん純愛物語です。『南の島のカレーライス』の参考文献に掲載したサラッチャンドラ教授の著書はこのご本です。ですからサラッチャンドラ教授のノリコさん純愛物語はForm upon the streamに依っています。Stantsiya_Iriyaサンが『南の島のカレーライス』に対して指摘される「オオウソのあらすじ」というのはエディリウィ―ラ・サラッチャンドラ教授が最後に記した三冊目のノリコさんとその恋人の苦い愛の物語Form upon the streamで語られています。
南雲堂の編集部が「亡き人」の382頁、著者紹介でForm upon the streamは前二編の英語版リライトであると簡単に触れています。注3
リライト?いや、英語圏の読者に向けた完全な修正版です。サラッチャンドラ教授は何を修正したのでしょうか。
ポスト・コロニアルですべてが変わった
デウェンドラさんがダルマさん(本名ダルマセーナ)に変わり、ダルマさんには夫人が居てラーミャramyaという名です。ダルマさん、その夫人のラーミャさんと東京の恋人ノリコさんの間でもだえ苦しみます。これが三作目のノリコ純愛ストーリーです。そして、サラッチャンドラ教授は二作目に取り入れたロマンティシズムを根こそぎ取り去り、この三作目でリアリズムの描写に徹します。注4
一作目はノリコを措いてスリランカへ帰ったデウェンドラさんが友人を集めた自宅パーティでカシューナッツを摘まみウィスキーを手にして東京の思い出に酔うシーンで終わります。二作目は睡眠剤の多量服薬で亡くなった(故意か事故かは分からない)ダルマさんへのノリコの熱い思いが高まり、お盆に里帰りする死者たちと一緒に、その中に混じるデウェンドラさんに寄り添い、私も死者たちの国へ行くと決意するところで終わります。三作目はそれらの幻影をすべて打ち消し、リアリズム小説の技法に回帰し、病院に運ばれたダルマさんが目を閉じるシーンで話が終わります。
二作目のマラウンゲー・アウルドゥ・ダーで読者が感動した名場面が三作目のForm upon the streamでは消えました。おそらく「お盆」を表したであろう、舌を噛みそうなマラウンゲー・アウルドゥ・ダーということばも。
一作目のマラギヤ・アットゥはそのまま訳せば「逝きし人々」、マラギヤで「死んでいった」、アットゥඇත්තෝは「人」の複数名詞なので「逝きし人」(亡き人)ではなく「逝きし人々」(亡き人々)です。日本語では単数複数頓着しないけどシンハラ語ではこれが大切。「逝きし人」ならマラギヤ・アッターමළගිය ඇත්තාとなり、小説主人公のマヘンドラさんのことかと勘違いされてしまうかも。マラウンゲー・アウルドゥ・ダーは「死者たちの周年の記念日」です。これを「命日」としてしまうとそれは特定の故人の亡くなった日のことですからමරණ සංවත්සරයのことです。「死者たちの周年の記念日」はむしろ「お盆」という方が近いと思います。でもスリランカに「お盆」はありません。だから「お盆」というシンハラ語もない。さて、マラウン(死者)も、アウルドゥ(年)も複数名詞ですからここにも注目してください。
ところで、「マラギヤ・アットゥ(亡き人)」はデウェンドラさんの独白で進行しますが、デウェンドラさん、「亡き人」の小説の中で「亡き人」になりません。「亡き人」じゃないんです、一作目の小説の中では。ノリコさんを東京に残してスリランカへひとり帰って、ラトラマナ・アッティディヤඅත්තිඩියに借りた家でカシューナッツの小袋を手にし、酒をまた片手に弄び注5、自宅に集めた友人たちを静かに眺めています。日本での、ノリコさんとの出来事を思い浮かべながら。まるで異次元の世界の夢の出来事だったようにノリコさんとのことが走馬燈のように浮かんでは流れ去ってゆきます。
デウェンドラさんは「亡き人」ではない。じゃ、「亡き人」は誰?あるいは原作のタイトル「マラギヤ・アットゥ」が意味する複数の「亡き人々」は誰のこと?
これら三冊を手に入れるのは難しいけれど
マラ・ギヤ・アットゥとマラウンゲー・アウルドゥ・ダーの二冊を邦訳ではまとめて一部、二部とし、「亡き人」のタイトルで南雲堂が野口忠司訳で出版しました。マラウンゲー・アウルドゥ・ダーから二十二年の時を経て記されたForm upon the streamは英語版でユネスコがシンガポール・アジア支局からE・サラッチャンドラ著で出版しました。これにはシンハラ語訳も和訳もありません。
これら三冊とも今では手に入れることが少々難しい。でも、読む価値は十分にあります。このKhasyaReportがこれからお知らせする三冊の小説の内容に興味を持ったという方は所蔵する図書館を探されて読まれることをお勧めします。マラ・ギヤ・アットゥ、マラウンゲー・アウルッダの二冊は原書のシンハラ語版ならネットでいくらでもPDF版で読めるのですが、これがPDF無料版などにうっかり手を出すとパソコン、タブレットなどにとんでもない悪さをするファイルを潜り込ます悪党がうようよしていますのでお気を付けください。印刷本をスキャンしただけのPDF版はそのままでは自動翻訳に廻せないのでシンハラ語で読まないのなら原作とのズレを覚悟して南雲堂の邦訳を読むことになりますが、Form upon the streamは訳本もなく原書も入手困難な様子で、ここが少々ネックです。
スリランカで三冊目のノリコ純愛小説に出会った
昔、30年以上も前のことですが、東京四谷でスリランカ料理トモカTOMOCAという小さなエスニック料理店を運営していた時、毎年春先にスリランカへ出かけ食材の仕入れと紅茶の購入、定番のシンハラ・スリランカ料理を探して南の島のあちこち、と言っても田舎のあちこちを、スリランカが存在しないコロンボを避けて歩き回っておりました。定番のシンハラ・スリランカ料理というのはポル・サンボールのことで、いかにもスリランカを代表する、いかにもシンプルな田舎料理の端くれ、いや、王道って感じの料理。これを毎年、12年間、訪ね廻っていたのです。
トモカの料理はポル・サンボールがメインと言っていいほど。これが欠かせません。トモカTOMOCAをオープンして間もなくanan(アンアン)が偵察隊をTOMOCAに入れてあの雑誌に掲載して以降、まだアーッパも満足に焼けないというのにほかのグルメ雑誌やらが軒並みやって来てトモカが提供するスリランカ料理の写真を撮っていきました。取材後試食をしながらテーブルの端に置かれたポル・サンボールこそがメイン、取材の方々にはいつもそう説明しておりました。
1月から3月の間の10日前後、店を休業して食材の仕入れとポル・サンボール探索に向かってスリランカへ毎年出かけました。島を巡ってへとへとになった帰国前はコロンボ・フォート、港の入り口正面に建つコロニアルなグランド・オリエンタル・ホテルGOHで休養を取り、朝食はグランド・フロアの狭いビュッフェでアーッパとポル・サンボールを食べ、なんだ、このポル・サンボール辛くないじゃないか、と注文付けて辛くしてもらっていました。コロンボではGOHの朝食だけが田舎料理のポル・サンボールを正確に提供していました。
当時、総合書店としてのレイクハウスはフォートにあってコロニアルなビルの重厚さが売りで、そこを訪ねるのが楽しみでした。そんなあるとき、Form upon the streamが平積みされているのに出会いました。帰りの飛行機の座席で読むか、という軽い気持ちで手に取りました。サラッチャンドラって教授作家の名前は覚えがあるな、とか言うぐらいの、サラッチャンドラ教授には失礼な話ですが、おざなりにしていた本だったのです。私にはシンハラ料理だけが頭に一杯広がっていました。
ストーリー展開は同じだけど
三作目のForm upon the streamはマラ・ギヤ・アットゥ、マラウンゲー・アウルドゥ・ダーを一つにまとめた本なのでストーリー展開は同じです。主人公が東京で日本人女性ノリコさんと出会い恋に落ち、愛の行く先に悩み自殺を図るという話なのですが、なんでだろう、主人公の名前がデウェンドラからダルマセーナ(ダルマさん)に替わっています。ノリコさんはそのままなのになんでデウェンドラさんだけ変えたのって、「それはサラッチャンドラに聞かないと分からない」とサラッチャンドラ教授と同じペラデニヤ大学の文学研究者がサラッチャンドラ研究論文に書き記しているぐらいなので、遠巻きの私たちがわかるはずもない。デウェンドラと言えばインド、ネパールが思い浮かぶから、かな。スリランカにだってたくさんのデウェンドラ性の方々いるけど、ヒンドゥ教と結びついちゃうからかな。英語版にするにはいろいろ配慮するのかな。
その、まさしくいろいろなのです。主人公の名を変えたばかりではありません。サラッチャンドラ教授、Form upon the streamの主人公ダルマさんの職業を画家から大学教授に変えてしまった。ダルマ教授、お金をためては東京へ向かい小説の技を磨いている。デウェンドラさん(同時にダルマさん)の服薬自殺ですが、ここも文豪サラッチャンドラ教授の研究者たちによればいろいろと推測できるそうで、元シンハラ仏教僧だったデウェンドラさん、画家になっても仏教の真義は身から離れない、悟りを得た僧が自殺するなんて前代未聞でしょ、ありえない、というのです。だから、お坊さん上がりの画家という設定は止めた。教授なら自殺してもいいのかなって、一瞬、脳裏をよぎったけど、まあ、いいか。二十二年振りのノリコ純愛ストーリーのリライトだから。
三作目の「リライト」ではダルマさんに奥さんも子供もいます。驚きましたね、Stantsiya_Iriyaさん。こういうこと、起こるんです。「オオウソのあらすじ」って、サラッチャンドラ教授の手の込んだ小説技法を侮辱しないでください。
セイロン(現スリランカ)に妻子を持つのだから日本でノリコさんと結婚するのはホントに難しい。国の奥さんはそれまで料理などせずに使用人に任せてたけど、日本のノリコさんの影に気づいて、料理も自分でやるようになったり、日本女性のかいがいしさを身に着けてダルマ教授を手放すまいと必死です。はて、ダルマ教授、困った。妻と恋人、二股の悩みを抱えて日本とセイロンを行ったり来たりで、ああ眠れない、で、常用する眠剤を失意のうちにか、はたまた故意か、大量服用して「亡き人」になった。これなら納得できるだろうと先の研究論文は主張するのです。注6
こんな具合ですけど、「オオウソのあらすじ」はさて置いて、ウィクラマシンハ氏が嚙みついた「日本のセックス小説はサラッチャンドラに任せておけ」もさて置いて、ここから『南の島のカレーライス』読者の方々への本題です。
サラッチャンドラのシンハラ語は美しい
まずはノリコさんの台詞から。
二作目のマラウンゲー・アウルドゥ・ダーの、ノリコさんが叫ぶように語る、あの美しい極みの台詞、
|
දවස හමාර වුනා ම හෙට දවස。 අදත් හෙටත් දෙකම එකයි.
|
で始まる高名なシーンが三作目のサラッチャンドラ教授自身による英語版では消えています。そのノリコさんの台詞部分はStantsiya_Iriyaさんがご自身のブログに貼ったyoutubeの動画Royal College, Colomboの学生さんたちが演じる舞台化された映像で見て聴くことができます。注7
ノリコさんがこう語ります。
|
" ඔබ එතකොට යනවනෙ? හෙට යනව. එතකොට හෙට ඔබ නෑ. ඔබ ඉන්නෙ අද විතරයි ---"
|
あれ、ノリコさん、シンハラ語できるんだっけ?シンハラ語は日本語のようだから(とノリコさんは言います)、話せちゃう?いや、そこじゃない。物語の中に入ってノリコさんの気持ちを聞きましょう。
行かないで。もう一日傍にいて
それじゃ、あなた、行くのね?明日行くのね。じゃあ、明日、あなたはいない。ここにいるのは今日だけ。
今日が終われば、明日が来る。今日と明日は同じ。今日、私たち二人はここにいる。明日は私だけ。明日も、明後日も、その先いつまでも私だけ。何が違う?今日のように明日も、誰もが起きる、食べる、飲む、仕事に行く、話をする。私もそうする。でも、私だけ。あなたはいない注8」(ほとんど追語訳ですが日本語っぽく改めたところもあります)
|
平易なシンハラ語でノリコさんが語り続けます。ここから先、ちょっと本文交えて続けましょう。情感豊かなサラッチャンドラ教授の小説作法が詰まっています。文末がya/a音、-i音の開音で繰り返されて、それはやわらかなシンハラ語なればこそ。注9
|
彼が何も言わずに私を見つめていたのを覚えています。彼は私の悲しみに気づきました。だけど、「行かない」とは言いませんでした。「また帰って来るよ」と彼は言いました。でも、その言葉は弱弱しかった。彼のその言葉に嘘がなかったか、私、疑りました。彼は行くべきじゃなかった。明日じゃなくて明後日に行くべきだった。もし彼が「明後日行く」と言ってたら、私どれほど慰められたでしょう。明後日なら、まだ一日ある、そうでしょ? 明後日もこんな風に過ぎていく。そしてまた、彼はもう一度「明日行く」と言うだろう。だけど、今日?今日は明日じゃない。彼が行く日じゃないわ、今日は。今日には明日がある。その明日がどうなろうとも。同上意訳部分あり)
|
そして、こう続けます。「変わることのない真実」の部分は原文では නියත ධර්මයක් niyatha darmayakです。
|
彼はじっと座り、私を見つめていました。彼の決断は避けられないものでした。それはまるで、この世の老いや死のように、変わることのない真実のようでした。なぜ?なぜ真実なの?行くと決めたのは彼じゃないの?注10
|
ここで、ダルマさん、冷静な論理を効かせてこう言い放ちます。
|
延期したら、いつまでたっても行けやしない。なぜ延期するんだ?早く行けばこそ、早く戻ってこれるじゃないか。注11
|
ダルマさん、いきり立っていてノリコさんの気持ち、ぶち壊しなのですが、心の優しいノリコさんはこう独白を続けます。
|
耳元でこの言葉をささやくのが聞こえました。戻って来れるからですか、行くのは? 行かなければ、また戻って来るなんてできない。たしかにそうです。でも、私には分からない。行くのはいいんです。行って戻って来るのもいい。この世は行きと戻りの繰り返し。戻らなければ行けはしない。行かなければ戻れない。こう思うと私の心は落ち着きを取り戻しました。注12
|
なんだか、ノリコさんの頭の中の論理って、ものすごくシンハラ的に思考するよう組まれているように感じます。行かなければ戻れない。だから納得した。納得した?どこか仏教問答をオブラートにくるんで腑に落としこむ感じ。「行かなければ戻れない」じゃなくて「行かなければ戻る必要もない」でしょ。ノリコさん、しっかりして。もしや、男のだましのテクニックにまんまと?(いや、利発だけどだらしないダルマさんも苦しいんです)
ノリコさんの言葉(もちろん、小説の中ではシンハラ語)は緩やかな、澄んだ小川の流れのようです。マラギヤ・アットゥとマウルンゲー・アウルドゥ・ダーの二編の小説は柔らかなシンハラ語で語られる、型にとらわれない新しい様式の詩のようです。果てしない言葉の空間に幻想が漂います。
二編目マウルンゲー・アウルドゥ・ダー最終章の冒頭はノリコさんが多摩墓地の先祖代々の墓に親族を集めてデウェンドラさんを埋葬するシーンで始まります。
サラッチャンドラ教授の文章は詩文のように流れます。教授はシタールの奏者。ノリコの言葉が弦楽器のやわらかな振動として伝わります。最終章はとても短い。原文は散文ですが、文章ごとに行を変えて以下に並べてみます。
かれを墓地に連れて行きました
多摩墓地の丘陵へ
私の父たちが眠る中島家の墓のところへ
今日はみんなが一緒に来てくれました
秀次さんと桃子さん、喜美子ちゃんと千恵子と、そして小さなゆきこちゃんも
デウェンドラさんを見送るためにみんなが来てくれました
タクシーに乗るのを見送ってと私、今回はかれに言いませんでした
私はくじけません
かれは行くけど必ず帰ってくるのですから
かれを中島家の墓に埋葬しました
私の家の代々の墓です
この先には父の親族の墓もあります
その先には父の親戚も住んでいます
みんなの処へ行くのです
いつでももみんなと一緒にこちらへ戻ってこられます
今は、早く死者の年(お盆)が来るように祈っています。もし今回彼を引き留められなかったら、彼と一緒に出掛けます。死者の年が来たら、私の願いはすぐに叶うと思います。
あなたが早く帰ってきてくれたら
亡くなった人たちの命日に
私もまた帰ってこられる
亡くなった人たちに付き添われて注13
|
二編目マウルンゲー・アウルドゥ・ダーの最終章はとても短いのです。詩のように散文が流れます。読者はデウェンドラさんに身を寄せて「死者たちの記念日」に「死者の地」へ一緒に”行く/戻る”と心を決めたノリコさんに共感し、勇気づけられるのです。
以上がノリコさん三部作のシンハラ語版1,2編の流れです。
それでは文豪サラッチャンドラ教授ご自身が書き直した英語版の三編目Form upon the streamではどうなっているかって、おっと、ネタバレはここまで。三編目は文学として劇的なんです。あまりに。
次のような読後感を寄せているシンハラの方がおられます。
まったく、デウェンドラさんも勝手な男だ、気が小さくて自分のことしか考えていない。私はそういうデウェンドラさんには共感しないが、なんともサラッチャンドラ教授が記す文体が詩文のように美しく感動的で、だからこの短編小説が手放せない、何度も読み返しています。グッド・リードGood Readsに寄せられた読者の言葉から
「シンハラ語と日本語は同じでしょ」 ノリコさんはそう言った
ここからは一編目の「マラギヤ・アットゥ」ノリコ純愛小説に出てくるシンハラ語と日本語の関係に関して触れます。
シンハラ語は美しい。ならばこれは、日本語の美しさでもあるはずです。ノリコさんは「逝きし人々マラギヤ・アットゥ」で、また、Form upon the streamでも「シンハラ語と日本語は同じだ」と言っています。デウェンドラさん、ダルマさんに涙を流してこんなふうに訴えるんです。
|
デヴェンドラさんが日本語をあんなに上手に話せるのに、どうして私はあの国の言語を話せないのでしょう?二つの言語は対等であるべきなのに。注14
|
これはgoogle 翻訳です1925-09-15の時点。権利意識満載のいかにも英語っぽい和訳なので、
「デウェンドラさんがこれだけ日本語をお上手にお話になるんだから、私にも話せないことはない筈ね? 二つの言葉がきっと似ている筈ね」
と、南雲堂の「亡き人」訳に切り替えて、この訳なら気分がよくなるから、もっと雰囲気をよくして、この「筈ね」はオーナඕන、グーグル翻訳ではwantと訳されてしまいますが、needの意訳なのでもっと強く意味を汲んで、
デウェンドラさんに日本語、これだけ上手にできるのなら、なんで私にあなたの国の言葉が出来ないの?できない理由なんてないわ。二つの言葉、似ているんだもの。KhasayaReport仮訳
|
とneedを「筈」じゃなくて「似てる」と決めつける強調マークとしてsurelyをとらえて注14同上オーナඕනの意味とします。こうするとノリコさんのこの時の戸惑いながらも勝気な様子が強く伝わります。このノリコさんの言葉、サラッチャンドラさんが日本で、いやもしかすると別の処でも脳裏に感じ取っていたのかもしれません。
それなのに「マラウンゲー・アウルドゥ・ダー死者たちの記念日(お盆)」になると打って変わってノリコさんにこう言わせています。
ඔහුගේ බස නම් මට කිසි කලක පුහුණු කර ගන හැකි නොවන්නේ ය.
私は決して彼の言語を習得することはできないでしょう。
ノリコさんが外国語に疎い例証としての次の台詞を合わせて、
එහෙත් මම නැණ මඳයි.එබඳු දේ මට ඉක්මනින් ප්රශුණ කළ නොහැකි ය.
しかし、私は賢くないので、そういうことにすぐに答えることができないんです。
|
そして、「学校で学んだフランス語だってもう忘れている。シンハラ語なんていくら頑張ったって聞いたり話したりできるようになるわけがないわ」と漏らします。もう、すっかり弱気です。どうしたんだろう?どうしましたか、文豪サラッチャンドラ先生。
「マラギヤ・アットゥ」ではシンハラ語と日本語は同じだと言い、「マラウンゲー・アウルッダー」では違うと言いい、Form upon the streamでは二つの言語には"similarity"が"surely"にあると、ー確かに似ているんです―とノリコさんに言わせています。注15
五木の子守歌が”揺れている”
サラッチャンドラ教授は男と女の話に集中してこの短編を書かれましたから、社会的な歴史的な背景というものがないのですが、日本のある歌に関して割と微細な説明を施しています。熊本県民謡の「五木の子守歌」です。和訳本ではこれが物語展開のキーワードにされていますが、シンハラ語原版ではさらりと流されています。そして英語版では奇妙な書き換えが行われています。
「五木の子守歌」をデウェンドラさんは京都の寺で耳にしたとあるのですが、英語版のダルマ教授は靖国神社で聞いています。傷痍軍人が白衣を纏いアコーディオンを抱え、靖国で歌っていたのです。傷痍軍人の辻立ちというせっかく取り入れた小説の時代背景なのですが、でも、これは設定としてアウトです。靖国は傷痍軍人を受け入れない。天皇のために命を投げ出した職業軍人だけをお祀りします。境内で「子守歌」うたって物乞いをされては困る。靖国に傷痍軍人は現れない。
原作にはない箇所、二作目のマラウンゲー・アウルドゥ・ダーのラストに南雲堂の邦訳本は「五木の子守歌」を組み込んでいます。原作そのものへの冒涜です。しかも、危ない。靖国の影がマラギヤ・アットゥの悲しみの愛のテーマを根底から脅かすのではないか。ノリコさん、危ない!ノリコさんとデウェンドラさん、のちに、ダルマさん、の切なく甘いエレジー。なのに、なのに。
この駄文の冒頭に戻ります。シンハラ語タイトルの「死者」は複数名詞なのになぜ日本語タイトルは単数なのか。これは日本語の名詞が単数複数にこだわらないから。そう考えておきます。
では、なぜシンハラ語版のマラ・ギヤ・アットゥමළගිය ඇත්තෝ 、マラウンゲー・アウルドゥ・ダーමළවුන්ගේ අවුරුදු දාは複数名詞なのか。
これはノリコさんの言葉からその意味が見えてきます。
かれを中島家の墓に埋葬しました
私の家の代々の墓です
この先には父の親族の墓もあります
その先には父の親戚も住んでいます
みんなの処へ行くのです
いつでももみんなと一緒にこちらへ戻ってこられます
|
このノリコさんの言葉から推測できるのはマラ・ギヤ・アットゥමළගිය ඇත්තෝは、例えば中島家の「死者たち」なのです。いえ、もう少し広げてみましょう。「死者たち」は私たちの生きる世界を包む死後の世界の人々、それぞれの人のそれぞれの関係する人々なのです。その「死者たち」はマラウンゲー・アウルドゥ・ダーමළවුන්ගේ අවුරුදු දා「死者たちの記念日」に正装してこの世界に戻ってきます。だからこの世界に「生ある人々」も正装してその「死者たち」を迎えます。二編の小説のタイトルに「死」という言葉が寄せられているのは「生」と「死」の出会いのフィードバックが毎年繰り返して行われるからなのです。これは日本に限った風習ではありません。宗教の中にこの風習を含ませる世界はいたるところにあって、「生」と「死」の交換は今も続いています。
ノリコさんはマラウンゲー・アウルドゥ・ダー、「死者たちの記念日」、言い換えて「お盆」にこの世界に戻って来るデウェンドラさんが、また、死の世界に戻るのなら自分もついてゆく、そう決めています。サラッチャンドラ教授のこの愛の物語が美しいのはノリコさんの一途な思い―生と死が交わる年に一度のお盆には私、死の世界へ帰るデウェンドラさんと一緒にまいりますーが美しく輝くからなのです。
『南の島のカレーライス』なのにここでもカレーが出て来ないと、今度はカレーライス派からお叱りを受けそう。なので、小説の中のカレーの部分に1㍉、触れます。
デウェンドラさんも、ダルマさんも、スリランカの料理をカレーと言っています。そして、「カレー」だけ作って、ノリコさんとその一族に提供します。
මම කුකුල් මස් ගෙනවින් කරියක් සෑදුවෙමි.
これ、「カレー」です。シンハラ語でカレーකරියと言ってます。デウェンドラさんも、ダルマさんも都会人だなあ。洒落てるなあ。今どきだなあ。マールだなんて言わないなあ。あれ、ありきたりの魚の煮物だからな。都会人は鶏肉なんだ。もちろんハールマッソーだなんて言うわけもない。煮干し魚なんて貧乏くさい。愛の小説には似合わない。かな、かな?
日本へ来るシンハラ人は「カレー」を自炊するためにトゥナ・パハ(シンハラ語。言ってみればカレー粉か)を持って来るのですが、デウェンドラさんはそんな余裕もなく来日されてスリランカのシンハラ「カレー」を作るのに日本のカレーパウダー(ルゥではないみたい)を使います。だから「カレー」です。ポル・キリもないので牛乳を使います。だから「カレー」です。でも、アッチャールはあったみたい。「カレー」が辛くて食べられないノリコさんにラーブのアッチャールを出して辛味をなだめます。カレーを鍵カッコに入れて『日本の』という意味を込めたのですが、分かっちゃったかしら。「カレー」の扱いはマーチン・ウィクラマシンハ氏と大きく異なります。都会派と田舎派の分岐点でしょうか。
ポル・サンボールを出さなかったんですね。デウェンドラさん、ポル・サンボール作れないのかなあ。馬鹿にしてるのかなあ?貧乏たらしい田舎料理だからかなあ。いや、ポルそのものが日本の食材店にはないか。椰子を削るヒラマネヤも売ってないか。マーチン・ウィクラマシンハさんなら主人公に飛び切り辛いポル・サンボールを食べさせちゃうんだけどなあ。
ポル・サンボールで始まり、ポル・サンボールで閉めたこの雑文。中身はポル・サンボールじゃなかったから、ポル・サンボールのことをここからちょっと…あッ、話が長すぎた。ポル・サンボールはまた、この次に。
| |
注1
The Rockefeller Foundation in the United State of America granted Sarachchandra a scholarship to study world theatre and this provided him with an opportunity to visit Japan. As Sarachchandra states in his autobiographical work ‘PIN ATI SARASAWI VARAMAK DENNE’ his first visit to Japan on this tour was a mere accident. "From India" he wrote "I proceeded to Japan. This visit was not due to any special, attraction or due to curiosity about that country, but because it was easier to stop there on my way to America".
アメリカ合衆国のロックフェラー財団はサラッチャンドラに世界演劇を学ぶための奨学金を授与し、これが彼に日本を訪れる機会を与えました。サラッチャンドラは自伝『පිං ඇති සරසවි වරමක් දෙන්නේ』の中で、この旅における最初の日本訪問は単なる偶然だったと述べています。「インドから私は日本へ向かった。この訪問は、特別な魅力や日本への好奇心からではなく、アメリカへ向かう途中に立ち寄るのが容易だったからだ」と彼は記しています。
Tribute to Prof. Sarachchandra 2008/June/03, P. B. Galahitiyawe Colombo, Sri Lanka Guardian
注2

Foam Upon the Stream - A Japanese Elegy 表紙〈部分〉。エレジーというには主人公の二人は脂がのってシャキシャキしている。南国熱帯、哀歌はなんともエネルギッシュ。
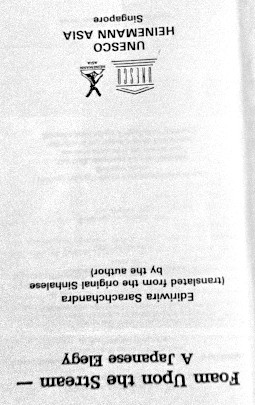
中表紙。Ediriwira Sarachchandra (translated from the original Sinhalese by the author)とある。著者サラッチャンドラ自身がオリジナルのシンハラ語版から翻訳したとある。前二編を基にこの英語版の三編目が生まれた。発行はUNESCO Heinemann Asia Singapore。
Foam Upon the Stream: A Japanese Elegy / UNESCO collection of representative works / Sinhalese series Writing in Asia series /Ediriwira Sarachchandra / UNESCO1987
注3
Form upon the streamのprefaceでサラッチャンドラ教授は三編目のノリコ純愛物語についてこう記している。
This novei is a free translation or, more precisely, a rewritten version of two short novels of mine, Malagiya Atto(1959) and its secuel Marlavunge Avurudu Da(1965), written oriinally in Sinhala.
「この小説は、私の2つの短編小説、もともとシンハラ語で書かれた『Malagiya Atto』(1959年)とその続編『Marlavunge Avurudu Da』(1965年)の自由翻訳、より正確には書き直し版です」
注4
シンハラ現代小説の作法はこうあるべきだと下のように説きながらサラッチャンドラ自身の作品にはこのことが反映されていないという指摘がある。ノリコ純愛物語の二編目マラウンゲー・アウルドゥ・ダ―には特にその指摘される要素が強い。三作目のノリコ純愛物語が二編目の読者に受けが良かった部分を尽く破棄して、ロマンティシズムからリアリズムに「転向」したのはサラッチャンドラ自身が自身のリアリズム主導を主張するシンハラ小説理論に(初めて)忠実に従ったから。ロシア文学の影響のつぎにスリランカを襲ったのはポスト・コロニアルという西欧文化からの洗礼である。
サラッチャンドラが主導するシンハラ小説作法
1. The novel is a form of writing that realistically portrays human life written
in prose.
2. That is the job of novelist to portray characters, characterization,
representation of events and incidents without the direct involvement of
the author nor narrator.
1. 小説とは、散文で表記された人間の生活のリアルな描写である。
2. 小説家の役割は、作者や語り手の直接な関与を避け、登場人物、性格描写、出来事や事件の描写を行うことである。
注5
このアルコールは元のシンハラ語版にමී විතක් とある。සුරාවのこと。アルコール(酒)を意味する。小型のグラスでアラックを連想させるのならそれは表現方法のテクニックだがමී විතක් は小型のグラスではない。මී විතක්が通じないシンハラ人も中には居る。
このමී විතක් の後に続く小説の最後を閉める文章は酒がしみ込んだ脳のように縦横無尽な体で空間に漂う。どのように最終の文を読み取ろうが読者次第。サラッチャンドラ教授の小説作法が極まる。
東京でのノリコとの愛は泡のように消えた。カシューナッツとアラックを手にする今を「受け入れよう」と主人公デウェンドラさんは疲労するこころの中で思う。
いや、小説は「受け入れようか?」のクエスチョンマークで終わっている。ここがサラッチャンドラ教授の極みの手法。こんな風に問い掛けるからみんなデウェンドラは厄介な人だと感じながらも小説に引き込まれてしまう。
この時のデウェンドラさんのつぶやき。
මා නොකා නොබී සිතිවිලි ද මෙහි පැටලී සිටින බව දකින එක් ස්ත්රීයක් මී විතක් ගෙන මට පිරිනමයි.ඈ කජු අහුරක් අතින් ගෙන මගේ අල්ලෙහි තමයි.මම සහජයෙන් මේ අයට අයිති නොවෙම් ද? තම ඇඟෑලිකම ඔවුන් දක්වන්නේ තමන්ට ඇබ්බහි වූ ආවාර විධියකින්ය.ඔවිහු මා පිලිගනිති.මා ද ඔවුන් පිළිගන යුතු ය.මා අවට වූ සත්යය මා වැළඳ ගතහොත්,මීට වධා තිර සැතසුමක් මට වින්දිය නොහැකි ද?
私が何も食べず、何も考えず、思考もここに囚われているのを見て、一人の女性がアルコールを持ってきて、私に差し出した。彼女はカシューナッツを一つかみ握り、私の手のひらに置いた。私は生来、この人たちに属しているのだな?彼らは慣れ親しんだ方法で愛情を示してくれる。彼らは私を受け入れてくれる。彼らは私を受け入れてくれる。私も彼らを受け入れなければならない。私がこの今を受け入れたなら、今見ている走馬燈に流れる幻影よりもっと長く楽しめるのではないか。
注6
Sarachchandra may have realized that an ex-monk with no other attachmentsor obligations did not have a reason to delay a decision to marry Noriko,or commit suicide in the end, and so would have changed to Daruma San witha wife and daughter and a permanent position in a university back in SriLanka. He had to make a difficult decision to leave his wife and child
サラチャンドラは、他に執着や義務のない元僧侶には、紀子との結婚を遅らせたり、最終的に自殺したりする理由がないことに気づいたのかもしれない。そして、妻と娘を持ち、スリランカの大学で恒久的な地位を持つ達磨さんに転向したかもしれない。彼は妻と子を捨てるという難しい決断を迫られた。
English Fiction by Sarachchandradaya dissanayake
"Ediriweera Sarachchandra (1914-1996), a remarkable bilingual became thepreeminent man of letters in Sinhala as well as the leading novelist inEnglish.[i]"
[Sarachchandra] was Sri Lanka's most distinguished man of letters andleading twentieth-century
novelist in English.[ii]" - D. C. R. A. Goonetilleke
注7
ノリコさんを演じる女性のシンハラ語がとてもきれいです。簡単なシンハラ語ですからシンハラ語を学習する初心者にお勧めです。
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQnGDITL0U Malawunge Awurududa Professor Ediriweera Sarachchandra
注8
ඔබ එතකොට යනවනෙ? හෙට යනව. එතකොට හෙට ඔබ නෑ. ඔබ ඉන්නෙ අද විතරයි.
අද දවස හමාර වුනාම හෙට දවස. අදත් හෙටත් දෙකම එකයි. අද අපි දෙන්න ඉන්නව. හෙට මම විතරයි. හෙටත්, අනිද්දටත්, කවදටත් මම විතරයි. මොකක්ද වෙනස? අද වගෙම හෙටත් කවුරුත් නැගිටිනව, කනව බොනව, වැඩට යනව, කතා බහ කරනව. මාත් මේ ඔක්කොම කරනව. ඒත් මම විතරයි. ඔබ නෑ
注9
ඔහු මුවින් නොබැණ මා දෙස බලා සිටිය සැටි මට මතකය. ඔහු මගේ දුක දුටුවේය. එහෙත් " මම යන්නෙ නෑ," යි නොකීවේය. " මම ආයෙමත් එනවනෙ, " යි ඔහු කීවේය. එහෙත් ඒවා දුබල වදන් විය. ඔහුවත් ඒවා විශ්වාස කලාදැයි මට සැක සිතුනි. ඔහුට නොයන්ට තිබුනි. හෙට නොගොස් අනිද්දා යන්ට තිබුනි. " මම අනිද්දා යනව," යි කීවේ නම්, මම කෙතරම් සැනසෙම්ද. අනිද්දා වුවත් තව එක් දවසක් තිබෙනවා නොවේද? ඒ දවසත් මේ වාගේම ගෙවී යනු නියතය. ආයෙමත් " මම හෙට යනව, " යි ඔහුට කියන්ට සිදුවේ. එහෙත් අද? අද ඔහු හෙට නොයයි. ඔහු හෙට යන දවස නොවේ අද. අදට හෙට තිබේ, හෙටට කුමක් වෙතත්.
注10
ඔහු නිසොල්මන්ව හුන්නේය, මා දෙස බලාගෙන. ඔහුගේ තීරණය අනිවාර්යය. එය ලෝකයේ ජරා මරණය සේ වෙනස් නොවෙන නියත ධර්මයක් සේ විය. ඇයි එසේ වන්නේ? යන්ට තීරණය කලේ ඔහු නොවේද?
ここはMartinのViragayaラストと対極をなしています。ウィクラマシンハ氏は「ウィラーガヤ」で変わることのない固定された物差し(これをダルマに置き換えます)などないと言い、サラッチャンドラ教授はダルマ、変わることのない固定された規範、真理、法則はあると言います。なんだか常の二人の言い分が逆転しているような。シンハラ民族の仏教と農村を守るウィクラマシンハ氏。西洋を取り入れ新たなシンハラ文化を作ろうとするサラッチャンドラ教授。二律背反の矛盾。でもお二人は友人、だそうです。ジレンマを止揚する。その思考回路がサラッチャンドラ教授には備えられているようです。
එය ලෝකයේ ජරා මරණය සේ වෙනස් නොවෙන නියත ධර්මයක් සේ විය.
それは、世界の衰退と死のように、変わることのない明確な、固定されたダルマ(規範、真理、法則、性質、教説、事物)のようなものでした。※නියත ධර්මයක්とは「固定された真理法則」のこと。
注11
" තව කල් දැම්මත් කවදා හරි යන්න එපාය. මොකටද කල් දාලා? ඉක්මනින් ගිය තරමට ඉක්මනින් එන්න පුලුවන්."
注12
මගේ කණට මේ වචන කොඳුරනවා ඇසිනි. යලිත් ආ හැකි නිසා ද යන්නේ? නොගියොත් යළිත් ආ නොහැකිය. එය සැබෑවකි. මට එය නොතේරුනි. යාම හොඳයි. ගොස් ඊමද හොඳයි. ලොවැ ඇත්තේ යාම ඊමය. නෑවිත් යන්ට බැරිය. නොගොස් එන්ට බැරිය. මගේ හදවත සැනසුම් ලද්දේය.
注13
දැන් මා පතමින් සිටින්නේ මළවුන්ගේ අවුරුදු දා නො ප්මාව පැමිණේවා කියා ය.මේ වර ඔහු රදවාගත නො හැකි නම් මම ඔහු කැටුව සැරසෙන්නෙමි.මළවුන්ගේ අවුරුදු දා මගේ ආසා නුසුන් කොට එන බව මම දනිමි.
ඉක්මනින්ම නැවත එතොත්
මළවුන්ගේ අවුරුදු දා
මටත් නැවත එන්ට ඇහැකි
මළගිය ඇත්තන් කැටුවම....
注14
この部分、一作目のマラギヤ・アットゥ―では最終章のラストにこうある。
දෙවෙන්ද්ර සන්ට ජපන් බාසාව ඔය තරම් හොඳට පුළුවන් නම් , ඇයි මට ඒ රටේ බාසාව බැරි වෙන්න හේතුව? බාසා දෙක සමාන වෙන්න ඕන. /මරගිය ඇත්තෝ p.123
注15
"Form upon the stream"での著者による英文の記述。
If you could have learned Japanese, why Can't I learn your language? There must be some similarity in the two languages, surely. /"Form upon the stream"p.127
|