ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
その他
| Out Of The Afternoon / Roy Haynes | ||
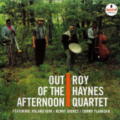 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1962/5/16 1962/5/23 [1] Moon Ray [2] Fly Me To The Moon [3] Raoul [4] Snap Crackle [5] If I Should Lose You [6] Long Wharf [7] Some Other Spring |
Roland Kirk (ts, manzello, strich, nose-fl) Tommy Flanagan (p) Henry Grimes (b) Roy Haynes (ds) |
| 数々のアルバムでクリスピーなドラミングを聴かせているロイ・ヘインズのリーダー・アルバム。ドラマーは、(当たり前だけど)ただの打楽器奏者であって、どんなに力量があっても独自の音楽を作る力がある人というのは少ない。そんなこともあってか、ここでは極めつけの個性派でサイドを固めることによって他にはないオリジナリティを出すスタイルを取っている。なにしろ選んだメンバーが異才の代名詞とも言えるローランド・カークに、どんなジャズでも個性を発揮できるトミー・フラナガン、セシル・テイラーのグループで活躍するヘンリー・グライムズという顔ぶれ。曲じたいは奇をてらったものではなくいかにも60年代的なジャズで、スタンダードを交えたその音楽性はジャズの枠をはみ出してはいないものの、このメンツが演奏すればユニークなものになるのは必然。時に2本の楽器を同時に、時に半分歌いながら吹くカークの個性は強烈で、そこにヘインズのパタパタと小刻みなドラムが加わることで、他に得難い種類のアクが出てくる。そうかと思えば最後の曲ではぐっとムーディに締める粋な演出もある。先にジャズの枠をはみ出していないと書いたのは否定的な意味ではなく、ジャズの中でこれだけの個性を出したところこそが実はこのアルバムの価値であると思える。ボブ・シール(プロデューサー)の企画の勝利。(2008年3月23日) | ||
| Basra / Pete La Roca | ||
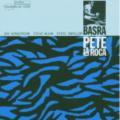 曲:★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1965/5/19 [1] Malaguena [2] Candu [3] Tears Come From Heaven [4] Basra [5] Lazy Afternoon [6] Eiderdown |
Joe Henderson (ts) Steve Kuhn (p) Steve Swallow (b) Pete La Roca (ds) |
| ブルーノートにしては異色の、そしてあまり顔なじみのない組み合わせで、内容もなかなか独特。タイトルの「Basra」がイラク南部の都市名ということからもわかるとおり、中東をイメージしたダークなムードに包まれた演奏が中心で、特に独特の捩れ方をしながらブロウするジョー・ヘンダーソンがイイ。ある意味彼のベスト・プレイのひとつかも。リズム隊はレギュラー・グループなのかと思わせるほどバランス良く、この独特の音世界の基盤をガッシリと構築している。4曲がリーダーの自作であることからもわかるとおり、ドラマーとしての表現ではなく、いち音楽家として見事に独自のジャズを作っているところがあまり評価されていないのは残念。フリーを含めて自由にジャズを表現できた65年という時代がこういう音楽を許していたことも見逃せない事実。決して激しいわけではないんないんだけれど堂々とした余裕の中に漲る緊張感が何とも言えず良い。ダークでシリアスなジャズに抵抗がなければかなりオススメできる好盤。(2011年4月10日) | ||
| Special Edition / Jack DeJohnette | ||
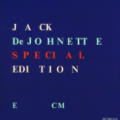 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1979/Mar [1] One For Eric [2] Zoot Suite [3] Central Park West [4] India [5] Journey To The Twin Planet |
David Murray (ts, bcl) Arthur Blythe (as) Peter Warren (b) Jack DeJohnette (ds) |
| 音楽家としての評価を聞くことはまずない、ジャック・デジョネットのリーダー・アルバム。しかし実は、ジャッキー・マクリーンに曲を提供していたことがあったりして、それなりに音楽的主張を持っていたりもするデジョネット。ここでも、コルトレーン作の[3][4]を除き、デジョネットのオリジナルで構成、フリー・ジャズ系の強者を集めて意欲的に作られたアルバムになっている。演奏はフリー系の匂いが濃厚でありつつも、曲はむしろ作り込まれていて、描いている世界、手法がまったく違ってはいるものの、オーネット・コールマン的に、既存のジャズとは違うメロディや曲構造で新しいジャズを創造することにチャレンジしている。その音楽はシリアスでありつつ、少々珍妙な感じのハーモニー(特に[3]は原曲をだいぶ崩していて同じ曲とはわかりにくい)が多く、演奏じたいもブローイングしつつどこか穏やかさが漂うシーンも多い。結果的に素晴らしい成果と言うまでには至っておらず、いろいろなものが噛み合っていない感じがする。また、これが79年の録音ということを考えると、ユニークではあっても決して新しいという感じはしない。一方で79年という時代はアコースティック・ジャズが下火だった時期でもあったことを考えると、よくこんな内容のアルバムを作ったな、とも思う。少なくとも、2000年以降の今のキース・ジャレットとの活動よりはクリエイティヴ。普通のジャズでは面白くない、そしてデジョネットのパワフルなドラムが楽しみたいという人はトライしても良いかも。(2012年1月1日) | ||
| Spectrum / Billy Cobham | ||
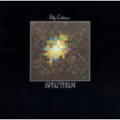 曲:★★★☆ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1973/3/14-16 [1] Quadrant 4 [2] Searching For The Right Door /Spectrum [3] Anxiety/Taurian Matador [4] Stratus [5] To the Women in My Life /Le Lis [6] Snoopy's Search/Red Baron |
[1][3][4][6] Tommy Bolin (g) Jan Hammer (key) Lee Sklar (b) Billy Cobham (ds) [2][5] Joe Farrel (as, ss, fl) Jimmy Owens (tp, flugelhorn) John Tropea (g except [2]) Jan Hammer (key) Ron Carter (b) Billy Cobham (ds) Ray Barretto (per) |
| 「千手観音」の異名を取る手数帝王、ビリー・コブハムのソロ・アルバム。ジャズ/フュージョン系のメンバーをズラリと揃え、そのイメージ通りのジャズ・ロックを展開しており、そこに弾むようなグルーヴ感でコブハムのドラムが躍動するというのがこのアルバムの骨子。曲も全曲コブハムのオリジナル、本人の志向がストレートに表われたサウンドであるためか、ドラムが生き生きしている。大きく分けるとジャズ寄りの[2][5]、フュージョン/ロック寄りの[1][3][4][6]という構成で、特に後者のトミー・ボーリンをフィーチャーしたカルテットはジェフ・ベックの「Wired」や「There And Back」の雛形として知られ、[1]は "Space Boogie" の原型かと思ってしまうほど近似性がある。つまり、ボーリンはこういうスタイルの音楽こそが本質で、それを生かせなかったディープ・パープル(と狂信的リッチー・ブラックモア・ファン)がいかに保守的で視野が狭かったかを、今さらながらに窺い知ることができる。もちろんヤン・ハマーのギターっぽいキーボードとのコンビネーションもバッチリで、ジェフ・ベックのアルバムではソロ奏者としての活躍で知られているヤン・ハマーは、ここではバッキングも含めたキーボード奏者としても優れているところを聴かせている。一方で、管楽器編成の[2][5]が違和感のないジャズ・ロックに仕上がっているのもハマーのキーボードと、コブハムの繰り出すアグレッシヴなリズムに一本筋が通っているからに他ならない。まさに2人のコラボレーションが生んだジャズ・ロックの逸品。(2007年4月21日) | ||
| Mind Transport / Alphonse Mouzon | ||
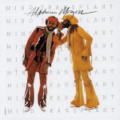 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1974/12/4-6, 9, 10 [1] Mind Transplant [2] Snow Bound [3] Carbon Dioxide [4] Ascorbic Acid [5] Happiness Is Loving You [6] Some Of The Things People Do [7] Golden Rainbows [8] Nitroglycerin |
Tommy Bolin (g [2][3][7][8][9]) Jay Graydon (g [4]) Lee Ritenour (g [4][5][6]) Jerry Peters (elp, org) Henry Davis (b) Alphonse Mouzon (ds, vo, key) |
| ウェザー・リポートの初代ドラマー、またはマッコイ・タイナー・グループ全盛期のドラマーとして活躍したことで知られるアルフォンス・ムザーンのソロ・アルバム。この人、70年代を代表するフュージョン/ロック系のドラマーとして、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、サンタナ、パトリック・モーラツ、果てはロバート・プラントとまで共演経験があるという。そんなキャリアや時代、そして共演者の顔ぶれから、ビリー・コブハムの「Spectrum」と共通性を語られており、実際その通りのサウンドが展開されている。ムザーンの手数が多くパワフルなドラムが全編を支配、そのパワフルな勢いはコブハムの「Spectrum」をも上回っている。ここでもトミー・ボーリンのプレイは鋭く、改めてその才能に唸らされてしまう。他のギタリストもこの強力なドラムに一歩も引かないプレイでハード・ロックにかなり接近したサウンドになっている。いろいろな意味で70年代の良さが濃縮された力作。(2008年9月13日 | ||
| Another Lifetime / Simon Phillips | ||
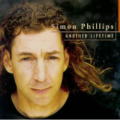 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
Released in 1997/Sep [Recording Date] 1997? [1]-[9] 1997/2/18 [10][11] [1] Jungle Eyes [2] P O V [3] Freudian Slip [4] Eyes Blue For You [5] Kumi Na Mojo [6] Mountain High [7] E S P [8] Euphrates [9] Another Lifetime [10] Cosmos [11] Biplane To Bermuda |
Andy Timmons (g) Ray Russell (g [1]-[9]) Wendell Brools (sax) Jeff Babko (key) Anthony Jackson (b [1]-[9]) Jimmy Earl (b [10][11]) Peter Michael Escovedo (per) |
| まだジャズに興味もなく、フュージョンなんてただの眠い音楽だと思っていた頃の97年にリリースされていた、サイモン・フィリップスのソロ・アルバム。もちろん、ジェフ・ベックの絡みで知ったスーパー・テクニックのドラマーのアルバムという理由で購入したものの、当時、ハード・ロックやプログレッシヴ・ロックばかり聴いていたロック耳の僕にはここで展開されている典型的なフュージョン・サウンドは退屈極まりなく、サイモンのドラムでなければ聴いていられないと思ったくらいだった。だからタイトルに、トニー・ウィリアムスへの敬意が込められたことも当然知らなかった。そこから長い月日が経ち、ジャズへの理解を深めてから改めて聴いてみる。ちなみに、今でも僕はただの耳あたりの良いフュージョン・サウンドは退屈だと思っているんだけれど、このアルバムの演奏のレベルは非常に高く、スリリング。アンソニー・ジャクソンの安定感のあるベース(後に上原ひろみのアルバムで再会)、アンディ・ティモンズのややロック寄りのギター、そこにサイモンがドカドカと叩きまくってくれればそれでも十分爽快なサウンドになってしまう。サイモン、あるいはサイモンとレイ・ラッセルとの共作で占められている楽曲はもうひとヒネリあってもいいかなあと思うけれど、変拍子も巧みに織り交ぜた構成などがしっかりしていて、こちらもレベルが高い。テクニック志向のフュージョンが好きな人なら聴いて損はないでしょう。尚、リリース当時に入手した日本盤に収録されていた2曲のボーナス・トラックは貴重なライヴで演奏も良いけれど、スタジオ盤の完成度には及ばず、アルバムのバランスを崩してしまっている。(2011年7月3日) | ||
| Family First / Mark Guiliana Jazz Quartet | ||
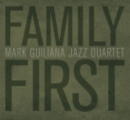 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
Released in 2014 [1] One Month [2] Abed [3] 2014 [4] Long Branch [5] Johnny Was [6] From You [7] The Importance Of Brothers [8] Welcome Home [9] Family FIrst [10] Beautiful Child |
Jason Rigby (ts) Shai Maestro (p) Chris Morrissey (b) Mark Guiliana (ds) |
| ブラッド・メルドーとの共演でその名を知ったものの、電子音楽系が主戦場と聞いて特に関心を持っているわけでもなかったマーク・ジュリアナ。しかし、アコースティック・ジャズのアルバムまで作ったというのでどんなものかとまずは生演奏を2016年1月3日にコットン・クラブで聴いたところなかなかの好感触。というわけでCDも聴いてみた。僕の考えではジャズという音楽は50〜60年代が黄金期でその時期が圧倒的に面白い。その後ももちろんひとつのジャンルとして一定の人気があるとはいえ、決して盛んとは言えない状態で細々と生き延びてきた。黄金期時代のジャズを繰り返していては評価されない現代のミュージシャンはオリジナリティを出そうともがいていはいるものの、これといった音楽を表現できている人は非常に少ない。このマーク・ジュリアナ・ジャズ・カルテットは現代のジャズらしい柔軟さと抑揚を備えつつ、音楽として完成度が高く、表現の幅も広いところが良い。曲はボブ・マーリーの[5](とボーナストラックの[10])を除きすべてマーク・ジュリアナの自作。作曲と独自のサウンド作りに成功してきたトニー・ウィリアムスを敬愛しているというだけのことはあって、音楽がしっかりしているし、自己満足型になりがちな現代のジャズにあって遊びとサービス精神が漂って斜に構えていないところが良い。抑えたコルトレーン的なテナー、スウィング感とは異質の洗練と妖しさが同居するピアノ、安定感抜群のベース、と共演者の実力もかなりのもの。ジュリアナはメルドーとのアルバムとは違ってジャズ・ドラマーに徹し、最低限のシンプルなドラムセットから縦横無尽にビートを繰り出す実力の高さを示している。強いて言えばライヴのときに感じたパワーと勢いをここでは表現しきれていないところが惜しいものの、通して聴いても飽きずに楽しめる2016年のジャズとして貴重な1枚。(2016年1月11日) | ||

