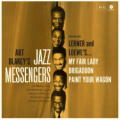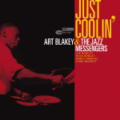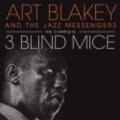ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Art Blakey
| A Night At Birdland | ||
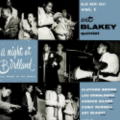 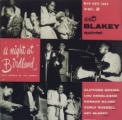 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★☆ ブレイキー入門度:★★★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1954/2/11 Vol.1 [1] Announcement by Pee Wee Marquette [2] Split Kick [3] Once In A While [4] Quicksilver [5] A Night In Tunisia [6] Mayreh [7] Wee-Dot (alt take) [8] Blues (bonus track) Vol.2 [1] Wee-Dot [2] If I Had You [3] Quicksilver [4] Now's The Time [5] Confirmation [6] The Way You Look Tonight (bonus track) [7] Lou's Blues (bonus track) |
Clifford Brown (tp) Lou Donaldson (as) Horace Silver (p) Curly Russel (b) Art Blakey (ds) |
| 名義はアート・ブレイキー・クインテットでジャズ・メッセンジャーズではない。そもそもこのグループはホレス・シルヴァーのグループを母体にブレイキーが加わるという形でできたそうでパーマネントなグループとして活動することを初めから想定していなかったらしい。それでもこのアルバムが今でもハードバップの古典としてジャズ・メッセンジャーズの諸作に引けをとらない、いや場合によってはそれ以上に高い評価を受けている理由は聴いてみれば納得できる。クリフォード・ブラウンのまさに輝かしいと呼ぶに相応しいトランペットとルー・ドナルドソンの明るいアルト・サックスの音色が醸し出す派手なムードはビ・バップ時代のガレスピー+パーカーのコンビに勝るとも劣らない華がある。特にハイノートを流暢に繰り出すブラウンのテクニックの凄いこと。僕はブラウン=ローチ・クインテット不感症なので、このアルバムが唯一ブラウンを満喫できるものだったりする。ホレスの、明快でブギウギをベースにしたピアノもこのムードの中心的存在だしカーリー・ラッセルのシンプルな弾力性は後のジミー・メリットにも通じるものがある。メンツを見るだけだと、あるいは個々の演奏を聴いているだけだと、まだビ・バップの残り香が見え隠れするものの、そこを覆してしまうのがもちろんブレイキーの強力な推進力を持ったドラム。「バンドをプッシュするってぇのはこういうことなんだヨォ」と言わんばかりの煽りっぷりは、それはもうエキサイティング。細かいリズムを駆使してバンド盛り立てるスタイルはそれ以前のケニー・クラークやマックス・ローチと比べると確実に新しく既に永遠の個性を放っている。54年のライヴとしては録音も良いし、このメンツをまとめて聴けるという意味でハードバップに入る最初の1枚としても最適。僕が好きなモーガン=ショーターのジャズ・メッセンジャーズも熱い演奏が売りだけれど、ここにはハードバップが誕生したばかりという時代ならではの熱いムードがある。(2007年4月22日) | ||
| At The Cafe Bohemia | ||
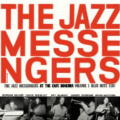 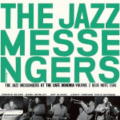 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1955/11/23 Vol.1 [1] Announcement by Art Blakey [2] Soft Winds [3] The Theme [4] Monor's Holiday [5] Alone Together [6] Prince Albert [7] Lady Bird [8] What's New [9] Deciphering The Message Vol.2 [10] Announcement by Art Blakey [11] Sportin' Crowd [12] Like Someone In Love [13] Yesterdays [14] Avila's Tequlia [15] I Waited For You [16] Just One Of Those Things [17] Hank's Symphony [18] Gone With The Wind |
Kenny Dorham (tp) Hank Mobley (ts) Horace Silver (p) Doug Watkins (b) Art Blakey (ds) |
| ジャズ・メッセンジャーズ名義初のアルバムはカフェ・ボヘミアでのライヴ。会場の違いのせいか、バードランドよりも音質が良くない。ケニー・ドーハムにハンク・モブレーという組み合わせは両者共にちょっと控えめでまったり系ということもあって、決してテンションの低い演奏ではないにもかかわらず一聴してパッとしない。ブラウン/ドナルドソンの華やかさ、モーガン/ショーターの激しさと比べてしまうと全体的に少し地味な印象を受けのは仕方ないところ。とはいえ、モブレー、ホレスの持ち味は出ているし、何よりもドーハムの歌心に溢れたトランペットが耳に残る。ブレイキーはいつも通りイイんだけれども、少しだけドラムの音が引っ込み気味でエネルギーがイマイチ伝わってこない。この時期、音楽監督はホレス・シルヴァーだったというのにホレスの曲はひとつもなく、ドーハムとモブレーの曲が目立つこともあって、3者の持ち味がうまくバランス良く配分される結果となっている。ライヴでありながら地味であるため玄人好みか。(2006年6月24日) | ||
| The Jazz Messengers | ||
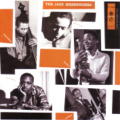 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ ブレイキー入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1956/4/6 1956/5/4 [1] Infra-Rae [2] Nica's Dream [3] It's You Or No One [4] Ecaroh [5] Carol's Interlude [6] The End Of Love Affair [7] Hank's Synphony [8] Wired-O [9] III Wind [10] Late Shaw [11] Deciphering The Message [12] Carol's Interrude (alt take) |
Donald Byrd (tp) Hank Mobley (ts) Horace Silver(p) Doug Watkins (b) Art Blakey (ds) |
| コロンビア在籍時の初期ジャズ・メッセンジャーズのアルバムはあまり話題になることがない。ジャズ・メッセンジャーズという名義でなかったころのバードランド、カフェ・ボヘミアの両ライヴ盤の知名度、ブルーノート時代の充実度に挟まれ、影が薄くなるのは仕方がない部分もある。また、メンバーの入れ替わりもあってサウンド面での軸が曖昧だったということもあるかもしれない。それでもこのアルバムは、モブレー、シルヴァーの両作曲家が在籍していたときとあってオリジナル曲が充実しているし、ドナルド・バード、モブレーのフロントラインがなかなか好調、ホレスのシンプルでわかりやすピアノのサポートに、ブレイキーならではリズムワークまで揃っているとなれば水準はクリアしている。音楽性はやや平凡なハードバップではあるものの56年の録音ということを考えれば妥当な内容に思える。突出した部分こそないものの、バードとモブレーのフロントラインを楽しむのに最適な好アルバム。[8]以降はボーナス・トラック。(2017年7月14日) | ||
| Hard Bop | ||
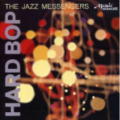 曲:★★★☆ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★ JM入門度:★ 評価:★★☆ |
[Recording Date] 1956/12/12 [1]-[4] 1956/12/13 [5] [1] Cranky Spanky [2] Stella By Starlight [3] My Heart Stood Still [4] Little Melonae [5] Stanley's Stiff Chikens |
Bill Hardman (tp) Jackie McLean (as) Sam Dockery (p) Spanky DeBrest (b) Art Blakey (ds) |
| ホレス・シルヴァー脱退後、メンバーを丸ごと持っていかれた(というかもともとホレスのグループだったんですが)ブレイキーが新しいメンバーで活動、しかしこの時期はジャズ・メッセンジャーズの低迷時期として語られている。アルバムの名義にアート・ブレイキーの名前はなく、ただ「ジャズ・メッセンジャーズ」。「At The Cafe Bohemia」もジャケットにはホレスやブレイキーの名前はなかったのでその流れがまだ続いていたということらしい。肝心の中身は、やはりというか特別な冴えは見られない。ブレイキーのドラムが控えめだからということではなくこのグループならではという音楽の軸を感じられないところが痛い。この当時は、タイトル通りのハード・バップというものがまだ目新しかったのかもしれないけれど、今聴くとそれ以上でもそれ以下でもない、というかむしろまだビ・バップの雰囲気すら若干残っているような気がする。全体に可もなく不可もなくの文字通り典型的ハード・バップで、低迷期というレッテルを貼られたことを否定できる出来栄えではないという事実が残ってしまっている。ミドル・テンポで軽快に演奏される[2]は、スローなマイルス・バージョンを聴きなれた耳にはちょっと新鮮。(2006年7月3日) | ||
| Art Blakey's Jazz Messengers with Thelonious Monk | ||
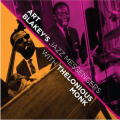 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ JM入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1957/5/14, 15 1957/7/29 [8]-[10] 1958/7/9 [7] [1] Evidence [2] In Walked Bud [3] Blue Monk [4] I Mean You [5] Rhythm-A-Ning [6] Purple Shades [7] Bya-Ya/Epistrophy [8] I Mean You [9] Blue Monk [10] Evidence |
[1]-[6] Bill Hardman (tp) Johnny Griffin (ts) Thelonious Monk (p) Spanky Debrest (b) Art Blakey (ds) [7] Johnny Griffin (ts) Thelonious Monk (p) Ahmed Abdul-Malik (b) Art Blakey (ds) [8]-[10] Bill Hardman (tp) Johnny Griffin (ts) Sam Dockery (p) Spanky Debrest (b) Art Blakey (ds) |
| スタジオ録音としては唯一のブレイキーとモンクの共演企画。他の項目でも書いている通り、僕はモンクの作る音楽が苦手で、その面白さがあまり理解できない。でも、ピアニストとしての唯一無二の個性には敬意を払っている。従って、ジャズ・メッセンジャーズ(以下、JM)にモンクが客演するという形態は理想的である。一方、この時期のJMは決して大きな成功を収めていたわけではなく、現代においてはあまり聴かれていない。理由は優秀な音楽監督がいなかったからで、この時期のJMは演奏こそ悪くないものの、個性という点ではあまり見るべきものがない。そういう時期のJMにモンクが加わるというのは結果的に的を射た企画だったと言える。個人的にビル・ハードマンの微妙なよじれ方をするトランペットに愛着を、ジョニー・グリフィンのパワフルなテナーのブロウに爽快に感じるこの編成、そこに絡むモンクは期待通りのマイペースぶり。ブレイキーのドラムとの共存にはいささかの違和感がなく、何年もやってきたかのようなムードさえ漂う。録音が時代相応にあまり良くないのは仕方のないところで、しかし本格化前のJMが好きでモンクのピアノを楽しみたい方には期待を裏切らない好アルバム。尚、[8]-[10]は通常のJMのメンバーによる演奏で、ライヴという違いがあるとはいえ同じ曲を聴き比べることができる。しかし、単調で面白みに欠け、モンクの存在感がいかに強烈かを知ることになる。(2006年8月5日) | ||
| Moanin' | ||
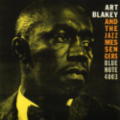 曲:★★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ JM入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1958/10/30 [1] Warm-Up And Dialogue Between Lee And Rudy [2] Moanin' [3] Are You Real? [4] Along Came Betty [5] The Drum Thunder Suite [6] Blues March [7] Come Rain Or Come Shine [8] Moanin' (Alternate Take) |
Lee Morgan (tp) Benny Golson (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| ジャズに興味がない人でも知っている[1]を含む、言わずと知れた超有名盤。ベニー・ゴルソン作曲、編曲、そこにモーガンとの組み合わせという意味では「リー・モーガン Vol.2(Lee Morgan Sextet)」や「Vol.3(Lee Morgan Vol.3)」もよく知られているけれど、編成やメンバーの違いもあってか僕にはまったく違う雰囲気に聴こえる。柔らかなハーモニーが耳に残る中、ゴルソンが作編曲した他のアルバムとの大きな違いはあくまでもブレイキーを引き立てることを主眼に置いたところにある。もちろんモーガンのトランペットはワイルドかつ伸びやかだし、ティモンズのピアノはいかにも黒さ濃厚、ゴルソンのスピーディなフレージングにジミー・メリットの弾むようなベースと各人の個性全開であるところ、それでいてグループとしてのまとまりがあるところが魅力で、もちろんブレイキーの賑やかなドラムもたっぷり満喫できる。他のジャズ・メッセンジャーズのアルバムでこれと似た質感を持ったものがないところもこの盤の価値を一層高いものにしている。曲、編曲、演奏の3拍子が揃った、改めて力説するまでもない素晴らしいアルバムで初心者からベテランまで楽しめる永久名盤。輸入盤では冒頭にモーガンとルディ・ヴァン・ゲルダーの会話、モーガンのウォーミング・アップが入っていて、より気分が盛り上がる。(2006年7月3日) HDtracksより96KHz/24bit音源を入手。2013 Remasterとわざわざ謳っている通り、手持ちのCDとはまるで違う。マスタリング以前にミックスからして違っており、左にトランペット、右にテナーサックスが配置されているところはステレオと書かれていながらモノラルに近い手持ちのCDと大きく異なるところ。この影響で全体に音の分離が良く、スッキリと見通しの良いサウンドに変化している。CDでは音の細部にやや荒れた部分が見受けられるのに対して、このハイレゾ音源では雑味が取れたクリアな音質に生まれ変わっている。(2013年6月22日) |
||
| Drums Around The Corner | ||
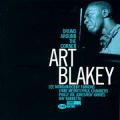 曲:★★★☆ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ ブレイキー入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1958/11/2 [1]-[6] 1959/3/29 [7] [8] [1] Moose The Mooche [2] Blakey's Blues [3] Lee's Tune [4] Let's Take 16 Bars [5] Drums In The Rain [6] Lover [7] I've Got My Love To Keep Me Warm [8] What Is This Thing Called Love |
[1]-[6] Lee Morgan (tp) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Philly Joe Jones (ds, timpani) Art Blakey (ds, timpani) Roy Haynes (ds) Ray Barretto (conga) [7] [8] Paul Chambers (b) Art Blakey (ds) |
| アート・ブレイキー単独名義のアルバム。ジャズ・メッセンジャーズからテナー・サックスを抜いて打楽器奏者を手厚く加えた編成。演奏面ではアルバム・タイトルが示す通りドラム・ソロが多い。ブレイキーにモーガンのワン・ホーンという編成も珍しく、ジャズ・メッセンジャーズのアルバムを多く聴いてきた耳にはなかなか新鮮に響く。あくまでもブレイキーのドラムを中心にロイ・ヘインズやフィリー・ジョー・ジョーンズとのドラム・ソロの応酬がたっぷり入っている。[7][8]はポール・チェンバースのベースとブレイキーのドラムのデュオという珍品。というようにドラム・パフォーマンスをたっぷりをフィーチャーした演奏なだけに、ドラム・ファン、ブレイキー・ファンにはたまらないところで、ああ、またいつものワン・パターンなナイアガラ瀑布かと思いつつも嬉しくなる。しかし、実は僕にとってブレイキーの魅力とはバンドを強烈にプッシュするところ、曲に活力を与えるところにあると考えているので、ドラム・ソロが多いからといってこのアルバムが最高という評価に結びつくわけではない。ゴルソンやショーターといったミュージック・ディレクターに相当する人がいないこともあって、曲やアレンジなどには見るべきものがないのも事実で、そのあたりがブルーノートの正規カタログに載らなかった理由でもあると思うんだけれど、こういう企画モノのアルバムもたまにはいい。(2007年6月22日) | ||
| Olympia Concert | ||
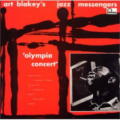 曲:★★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★★ JM入門度:★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1958/11/22 [1]-[3] 1958/12/17 [4]-[7] [1] Just By Myself [2] I Remember Clifford [3] Are You Real [4] Moanin' [5] Justice [6] Blues March [7] Whisper Not |
Lee Morgan (tp) Benny Golson (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| ゴルソン在籍時のジャズ・メッセンジャーズのライヴ盤といえばなんと言っても「サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ(au Club Saint-Germain)」が有名。その影に隠れた存在としてこんなアルバムがあったりする。申し分のないベストな選曲で録音状態もこちらの方がいいのになぜ影に隠れているのか理由はわからないけれど、演奏に熱さが少しだけ足りないように感じるからだろうか。ホールのコンサートとあって臨場感がやや不足していること、ベースとピアノがやや引っ込み気味の音のバランスであることがその印象を強くさせている。演奏面ではティモンズが一番覇気がなく、そこが「サンジェルマン」と一番違うところでモーガンとゴルソンの勢いももうひとつ。熱きファンキー度を売りにするジャズ・メッセンジャーズとしてはお行儀が良すぎるのが少々残念。それでも御大ブレイキーのドラムは熱いし、これだけの名曲を立て続けに演奏されたら悪いはずがない。このラインナップの数少ない音源でもあるだけにファンは押さえておきたいところだし選曲面では初心者にも勧められる内容。(2007年9月1日) | ||
| au Club Saint-Germain/ Complete Concert At Club Saint German |
||
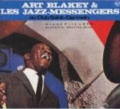  曲:★★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1958/12/21 Disc 1 [1] Politely [2] Whisper Not [3] Now's The Time [4] The First Theme [5] Moanin' With Hazel [6] Evidence (We Named It Justice) Disc 2 [7] Blues March For Europe No.1 [8] Like Someone In Love [9] Along Came Manon [10] Out Of The Past [11] A Night In Tunisia [12] Ending With The Theme |
Lee Morgan (tp) Benny Golson (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) Kenny Clarke (ds) [11] |
| ジャズ・メッセンジャーズ(以下 JM )のアルバムの中で、圧倒的な知名度を誇るのはなんといっても「Moanin'」。そのためにJMといえばあの曲調にあのサウンドのイメージがある。しかし、ベニー・ゴルソン在籍時のスタジオ録音はその「Moanin'」とサントラの「殺られる: Des Femmes Disparaissent」だけで、長いJMの活動期間を考えると、ごく一時期だけに過ぎない。実際、JMの充実期はウェイン・ショーターが在籍していた時代だと考える自分としては「Moanin'」は一時的なユニットによる異色作のように映る。したがってゴルソン在籍時のJMをもっと聴きたいという人にありがたいのがブルーノート以外のレーベルからリリースされたこのライヴ集。欠点は音質がかなりコモリ気味なことで、4年も前の録音である「A Night At Birdland」よりも音が悪いのが残念。ただし、内容そのものは申し分なく、弾けまくるモーガン、速いパッセージでブローするゴルソン、ブロックコードを連打して黒さ全開のティモンズ、JMらしさの基盤と言えるわかりやすい躍動感を演出するメリット、暴れるブレイキー、と美味しいところを満喫できるのが嬉しい。パリジャンはこんなに陽気なのかと驚くほど、観客の異様な盛り上がりがムードを高めているのもこのアルバムの大きな特徴。「Moanin'」に収録されていない[1][2]の演奏も素晴らしく、特に[2]は初演(「Lee Morgan Sextet」収録)よりもクールで味わい深い。アルバムとしての構成力がやや弱いことと録音状態さえ気にならなければ言うことなしの名演集。(2006年7月3日) なんと2012年に、アルバム・ジャケットもタイトルも変えてリイシューされていた。そこまで変えておきながら曲の追加などは一切なし。はて?何が Complete なのか? 聴いてみると、音質向上が目覚ましい。それでもブルーノート盤のライヴほどの高音質ではないけれど、おそらくマスターテープの音を最大限引き出したリイシューと思われ、従来盤からの向上ぶりはよくあるリマスターどころのレベルではない。今までは音が悪くてあまり聴いていなかったんだけれど、感動の底上げと言えるこのクオリティアップなら十分に愛聴盤になり得る。昔はアナログに合わせた高価な3枚組だったものが、CDとして妥当かつ安価な2枚組となったのもうれしい。なるほど、Complete とは「すべてが揃った」ではなく「完成した」という意味だったようだ。(2013年11月15日) |
||
| At The Jazz Corner Of The World | ||
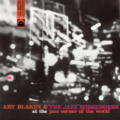 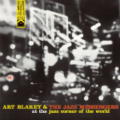 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★★ JM入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1959/4/15 Vol.1 [1] Announcement by Pee Wee Marquette 〜 HipSippy Blues [2] Justice [3] The Theme [4] Announcement by Art Blakey 〜 Close Your Eyes [5] Announcement by Art Blakey 〜 Just Coolin' Vol.2 [5] Announcement by Art Blakey 〜 Chicken An' Dumplin [6] M & M [7] Hi-Fly [8] The Theme [9] Art's Revelation |
Lee Morgan (tp) Hank Mobley (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| ジャズ・メッセンジャーズには数多くのライヴ・アルバムがあるけれど、最も冷遇されていると思われるのがこのアルバム。モーガンのトランペットは伸び伸びとブリリアントに歌い、生涯のベストと言っても決して言いすぎではないほど自在で奔放なプレイ。モブレーも熱気溢れる演奏でそれに対抗。超有名曲は入っていないけれどモブレー作の3曲を筆頭に、適度に捻ってありながらもわかりやすいメロディのテーマを持った曲が自然に耳に入ってくる。また、特に管楽器の音を生々しく捉えた録音が良く(なぜかベースの音は少しモコモコしているけれど)、演奏も当時のジャズ・メッセンジャーズの充実度を捉えた名記録と断言できる。「サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ(au Club Saint-Germain)」の、異様な観客の盛り上がりに後押しされた熱気とは質が異なるものの、内面から湧き出るジャズ・スピリッツの熱さはこちらの方が上。くどいようだけどモーガンが圧倒的に素晴らしい。そんな熱気溢れる演奏はブレイキーのドラムにプッシュされたことによって引き出されていることは言うまでもない。これぞ隠れた名盤。これぞモダン・ジャズ。これぞハード・バップ。テナーがハンク・モブレーだからという理由で聴いていないアナタは損をしている!(2006年5月27日) | ||
| Africaine | ||
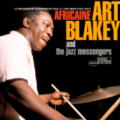 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1959/11/10 [1] Africaine [2] Lester Left Town [3] Splendid [4] Haina [5] The Midget [6] Celine |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Walter Davis Jr. (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) Dizzy Reece (conga [1][4]) |
| 録音から20年後にアルフレッド・ライオンの意志とは関係なくリリースされた本作は、ウェイン・ショーターがジャズ・メッセンジャーズのデビューを飾るアルバムになるはずだったもの。確かに内容としてはもうひとつピリッとしない。実際、録音は苦労したようで[2]は納得できる演奏に仕上がらなかったという。次の「The Big Beat」に収録されたテイクと比べると確かに覇気がなく緩いと多くの人が感じるであろうデキで、なるほどリリースされなかったのもやむ無しと納得できてしまう。しかしながら、なぜだかトランペッターのディジー・リースがコンガで参加している[1][4]にブレイキー一連の打楽器を全面に出したアルバムや "A Night In A Tunisia" "The Back Slider"の雛形が見える(といってもブレイキーの得意技は限られていてバリエーションはこの程度とも言える)し、全体を見ても後のジャズ・メッセンジャーズを予感させるムードは漂っていて、つまらない内容と簡単には切り捨てられない演奏になっている。ベストでないとしてもモーガン、ショーター、ブレイキーの持ち味はに出ていてジャズ・メッセンジャーズが好きな人なら楽しめるはず。後のアルバムはちょっと刺激が強すぎて、という人にはむしろこのくらいがいいのかも。ピアノがウォルター・デイヴィスJr.であることもクセを薄めている要因。[1][2]がショーターの、[3]がウォルター・デイビスJr.の、[4][5][6]はモーガンのオリジナル。(2015年1月4日) | ||
| Paris Jam Session | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★ 評価:★★ |
[Recording Date] 1959/12/18 [1] Dance Of The Infidels [2] Bouncing With Bud [3] The Midget [4] A Night In Tunisia |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) Barney Willen (as [1][2]) Bud Powell (p [1][2]) |
| そもそもは、ジャズ・メッセンジャーズがパリを廻っているときに現地在住のアメリカ人に声をかけてビッグ・バンドで演奏するという企画だったとのこと。既に名声を確立していたアート・ブレイキーのオファーなら皆喜んで受けるだろうという楽観的観測に基づいたその企画、しかし、実際に参加者したのは地元のバルネ・ウィランと、観客のつもりで会場のシャンゼリゼ劇場に来ていたバド・パウエルだけで、そのときの模様を収めたのが[1][2]ということらしい。さて、その出来栄えは、アルバムのタイトル通りのジャム・セッションで演奏に緊張感もなく完成度もイマイチ。むしろ[3][4]の方が聴き応えがある。ショーター参加初期の記録ながら演奏面で特筆すべき点がないのが少々残念。(2006年8月5日) | ||
| The Big Beat | ||
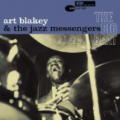 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★☆ JM入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1960/3/6 [1] The Chess Players [2] Sakeena's Vision [3] Politely [4] Dat Dare [5] Lester Left Town [6] It's Only A Paper Moon |
Lee Morgan (tp) Wayne Shoter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| ウェイン・ショーターが加入して最初にリリースされたアルバム。ファンキーで威勢のいい[1]からショーターもモーガンも絶好調。この曲調にティモンズのピアノがまた良く合う。得意の暑苦しいドラム・ソロも[2]で登場。ショーターといえばジャズ・メッセンジャーズに洗練されたムードを持ち込んだというイメージがあったんだけれど、3曲のショーター・オリジナルを早速採用していながら、「サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ(au Club Saint-Germain)」でオープニングを飾っていたビル・ハードマン作[3]に違和感がなく、依然としてファンキー・ジャズの匂いが濃厚であるところが特徴。それでいてショーターの個性もそれなりに出ているところがこのアルバムの聴きどころ。後の作風とはちょっと違うけれどショーターの提示するファンキー・ジャズとして楽しめるし、ショーター自身のソロも充実していて言うことなし。そしてなによりもモーガンのプレイが弾けているところが素晴らしい。ティモンズの人気曲[4]を含め、適度なファンキー・テイストと聴きやすさが魅力。(2006年5月27日) | ||
| A Night In Tunisia | ||
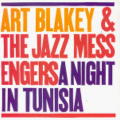 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1960/8/7 1960/8/14 [1] A Night In Tunisia [2] Sincerely Diana [3] Sincerely Diana (alt take) [4] So Tired [5] Yama [6] Kozo's Waltz [7] When Your Lover Has Gone |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| クリフォード・ブラウンが在籍していたころからのお得意レパートリーである[1]を、満を持してスタジオで録音。モーガン、ショーター、ブレイキーの熱演により、数ある演奏の中で決定版とも言える名演となった。しかし、その[1]のインパクトが大きすぎるためか他の曲の存在感がなんとも小粒な印象。僕は「Moanin'」の次にコレを聴いたので「う〜ん、ジャズ・メッセンジャーズはゴルソン在籍時に限るのかな」と思った記憶がある(後にその考えは変わるけど)。演奏面では、ショーターは好調だし、モーガンのハデな吹きっぷりもいつも通り。ただ、本作では[2][4][5]といったモーダルな曲と表題曲のムードがもうひとつ噛み合っておらず、全体のバランスが崩れてしまっている感じがする。とにかく[1]に尽きる。(2006年7月3日) | ||
| Like Someone In Love | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ JM入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1960/8/7 1960/8/14 [1] Like Someone In Love [2] Johny's Blue [3] Noise In The Attic [4] Sleeping Dancer Sleep On [5] Giants [6] Sleeping Dancer Sleep On (alt take) |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| 「A Night In Tunisia」同様、ライヴでの定番曲を冒頭に据えた作品。録音日がまったく同じということもあり、音楽、演奏の傾向に違いはない。それが原因なのか発売されたのは録音から7年後だったとのこと。リラックスしたスタンダード・ナンバーから始まるために力まずスッと入っていけるところが良い。その[1]はライヴでの演奏よりも落ち着いたムードで演奏されていて、ティモンズ得意のブロック・コードによる演奏も抑揚が効いていてイイ味を出している。いかにもモーガン作の[2]は軽快でファンキーな曲に合わせて速いパッセージを炸裂させるモーガンと、今度はシングル・ノートを駆使したティモンズのソロが堪能できる。[3]ではやはり軽快な曲に乗せてショーターが激しいブローを披露。[4] はいかにもショーターらしいムーディなバラード。[5]もオーソドックスでジャズ・メッセンジャーズらしい軽快な曲で、いつものこととはいえ、やはりブリブリ言うショーターとバリバリ吹くモーガンが素晴らしい。これといった目立つ曲があるわけでもなくいわゆるお蔵入り音源だったものだけれども、充実期のジャズ・メッセンジャーズを捉えているだけに水準は軽くクリアしている。(2006年7月5日) | ||
| Meet You At The Jazz Corner Of The World | ||
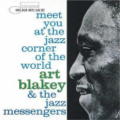 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★★ JM入門度:★★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1960/9/14 Vol.1 [1] Announcement by Pee Wee Marquette [2] The Opener [3] What Know [4] The Theme [5] Announcement by Art Blakey [6] Round About Midnight [7] The Breeze And I Vol.2 [8] Announcement by Pee Wee Marquette [9] High Modes [10] Night Watch [11] The Things I Love [12] The Summit [13] The Theme |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| 「At The Jazz Corner Of The World」に続く、バードランド・ライヴ・シリーズ(?)第3弾。テナーがショーターに代わっているけれど、ほとんど同じと言って良いくらい全体の雰囲気は変わっていない。ショーターのオリジナルは1曲のみ、対照的にこのアルバムのために書き下ろしたモブレーの曲が3曲もあることがその理由でしょう。ショーター・ミュージックを期待すると落胆するかも。では聴きどころがないかというとそんなことはなく、モーガンとショーターの、火傷するほどに熱いプレイはそれだけで聴く価値があると断言できるほどパフォーマンスが素晴らしい。もちろんブレイキーの強力なプッシュもここでは最大級のパワーでもってバンドを牽引しているし、メリットとティモンズも一体化したJMならではのグルーヴが溢れ出ている。[4]が実は聴きどころで、演奏に乗ってまくしたてるアナウンスが盛り上げ、フィーチャリング・ピー・ウィー・マーケットというサブ・タイトルを与えたいくらい。また、[9]の哀愁漂うメロディがたまらないムードでモブレーの作曲家としての力を見せつけている。いずれにしろ、このアルバムも充実期のジャズ・メッセンジャーズのライヴの素晴らしさが満喫できる内容で、「At The Jazz Corner Of The World」に加えて名演を収めたライヴ・アルバムがもうひとつあることを素直に喜びたい。これを聴いて何も感じない人はジャズには縁がないと思ってもいいかもしれない。(2006年6月21日) | ||
| Roots And Herbs | ||
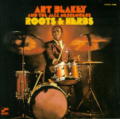 曲:★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1961/2/12 1961/2/18 [8] [9] 1961/5/27 [3] [7] [1] Ping Pong [2] Roots And Herbs [3] The Back Sliders [4] United [5] Look At The Brirdie [6] Master Mind [7] The Back Slider (alt take) [8] Ping Pong (alt take) [9] United (alt take) |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| 全曲ショーターのオリジナルとあってショーター・カラーが強い作品。曲に合わせてかティモンズは得意の叩きつけるような黒々としたピアノをちょっと封印、あの泥臭い演奏がToo Muchという人にはむしろこのくらいでいいかも。とはいえ、あくまでもジャズ・メッセンジャーズのフォーマット範囲内でのことで程よいファンキー・テイストは健在。録音から7年もお蔵入りしていた理由がわからないほど演奏は良い。[1]の終盤を盛り上げる、変幻自在のモーガンのアドリブの素晴らしいこと言ったらそれはもう。強いて言えばオリジナル・アルバムで言う後半の[5][6]の曲がやや弱いかもしれないけれど、モーガンとショーターの好演ぶり、御大ブレイキー自身も熱さともに申し分なく、レベルは高い。数あるジャズ・メッセンジャーズのアルバムの中では知名度が落ちるけれど、充実期を捉えた逸品であることに疑いはなく充分に楽しめる好盤。(2006年6月11日) | ||
| The Witch Doctor | ||
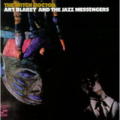 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ JM入門度:★★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1961/3/14 [1] The Witch Doctor [2] Afrique [3] Those Who Sit And Wait [4] A Little Busy [5] Joelle [6] Lost And Found [7] The Witch Doctor (alt take) |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| クールでハード・ボイルドな[1]、ブレイキーらしいリズム・パターンにティモンズとショーターのシンプルなリフを乗せてトランペットがカッコよく絡む[2] 。これらモーガン作の冒頭2曲がこの時期のメッセンジャーズらしさをよく表していて素晴らしい。ショーターの曲は2曲だけとはいえ、ティモンズが以前ほどのアクの強さを見せていないこともあって洗練されたショーターのカラーがうまく融合している感じがある。そしてモーガンは一段とキレ味鋭く、ショーターは硬質かつ引き締まった音でソロを放ち、身震いするほどにカッコいい。一見、特に変わったことをしているわけでもないように見えて他のジャズと明らかに異なるのは、ティモンズ、メリット、ブレイキーのリズム・セクションだけが作り出せるフィーリングがあるからであることを再認識。このアルバムでは、そんなメンツによるグループが円熟期にあることを改めて知らしめてくれる。録音後、7年間も封印されていたとは思えない素晴らしい内容。国内盤が発売されたことがなかったことは、リアルタイムのジャズ・リスナーにとって大きな損失だったと思う。(2006年7月13日) | ||
| The Freedom Rider | ||
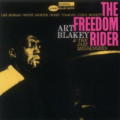 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ JM入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1961/2/12 [7] [8] 1961/2/18 [4] 1961/5/27 [1]-[3] [5] [6] [1] Tell It Like It Is [2] The Freedom [3] El Toro [4] Petty Larcency [5] Blue Lace [6] Uplight [7] Pisces [8] Blue Ching |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| モーガン+ショーターのコンビによる最後の録音。洗練の度合いを強める2管メッセンジャーズの究極の姿が見れるのではないか、という予想とは裏腹にファンキー度の濃厚の[1]で思わずニヤリとさせられる。こういう曲も書けるショーターって本当にスゴイ。[2]はドラム・ソロ。以降、キューバ系ムードのメロディ[3]、オーソドックスなミドル・テンポの[4]と続くところはこの時期のメッセンジャーズの王道路線。とにかくこの頃のショーターの音は硬質でなんともカッコよく意図的にか中音域だけでブリブリと吹きまくる[1]が気持ちイイ。一方で、高音を多用していることが曲のムードにまで影響を与えている[5][7]のような不思議なメロディも聴かせる。これら([4]-[7]まで)すべてがモーガン作で、こんなに多く曲が採用されているのは実は珍しい。演奏面では、ティモンズが以前ほどの泥臭いプレイをしなくなり徐々に存在意義が薄くなりつつあるような気がするけれど、モーガン、ショーターの演奏は高値安定。到る所でブレイキーの掛け声がよく聞こえてきてそれがまた雰囲気を盛り上げる演出にもなっている。(2006年7月18日) | ||
| Art Blakey And The Jazz Messengers | ||
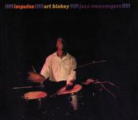 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ JM入門度:★★☆ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1961/5/13 1961/5/14 [1] Alamode [2] Invitation [3] Circus [4] You Don't Know What Love Is [5] I Hear A Rhapsody [6] Gee Baby, Ain't I Good To You |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Bobby Timmons (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| ウェイン・ショーターの提案によってカーティス・フラーを加え3管編成になったジャズ・メッセンジャーズの第一作目。洗練の度合いを強めると同時にこれまでよりさらにショーター・カラーが強く出ている。反面、モーガンの存在感がやや薄いことや、ティモンズが非常に洗練された繊細なタッチを見せて言わば「らしくない」演奏を聞かせることから本作をもって2人が脱退したのも頷ける。当時新興レーベルだったインパルスからのリリースで、有名なスタンダードを中心(偶然なのか同レーベル所属のコルトレーンが演奏した曲を3曲も採用)にした内容は非ブルーノート的で、このアルバムの特徴にもなっている。本作以降、シャープでソリッドなサウンドを特長とするグループへ進化して行く3管ジャズ・メッセンジャーズ、そこへ至るまでの過渡期を楽しむアルバムと言えるでしょう。尚、ドラム・サウンドを含めた録音状態はルディ・ヴァン・ゲルダーの録音ということもあってかブルーノート作品に割りと近いフィーリング。演奏自体は熱さという意味ではやや抑え気味ながら、曲の良さも相まって内容は悪くない。この作品以降、3管メッセンジャーズはリバーサイド、ユナイテッド・アーティスツといったブルーノート以外のレーベルにも並行して作品を残すようになって行く。(2006年7月15日) | ||
| Mosaic | ||
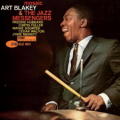 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★☆ JM入門度:★★★★☆ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1961/10/2 [1] Mosaic [2] Down Under [3] Children Of The Night [4] Arabia [5] Crisis |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| 更に洗練度合いを強めた、ハバード、ショーター、フラーによる3管メッセンジャーズの第一作目。サウンド面では当然フロント3人に耳が奪われるけれど、シダー・ウォルトンが持ち込んだモダンなフィーリングも見逃すことはできない。盛大なホーン・アンサンブルから思わず体を揺らしたくなるノリの良い、トリッキーなリズムを持つ[1]はその新加入のウォルトン作。録音前に曲を作ってくるよう宿題を出されていたにもかかわらず、すっかり忘れていたウォルトンがスタジオの近くのカフェで休憩時間にサッと書き上げ、自信なさげに披露したらブレイキーもアルフレッド・ライオンも気に入り「これをタイトル曲にしよう」と決めたという。即興で作られた曲の割には変化と躍動感に富み、ハバードのトランペットが冴える名曲になってしまったのだから世の中わからないものだ。他はハバード2曲、フラー1曲、そして意外なことにショーターは1曲。にもかかわらず、よりショーターの色が出ているのは音楽監督としてショーターが仕切っていたからだと思われる。そのショーターのブローは、ハバードのイキのいいトランペットに互角以上に対抗。フラーもこのグループのカラーに良く合ったプレイですでに鉄壁のフロント陣であることを見せつける。もちろんブレイキーのドラムはバンドの活力の源であることは言うまでもない。落ち着いた曲がなく勢いで押しているので、イキのいいジャズが聴きたいという人に推奨。(2006年7月13日) | ||
| Buhaina's Delight | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★★★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1961/11/28 [1] [3] [4] [5] 1961/12/18 [2] [6] [1] Backstage Sally [2] Contemplation [3] Bu's Delight [4] Reincarnations Blues [5] Shaky Jake [6] Moon River |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| 悪く言うと勢いに任せてできあがった感もある前作「Mosaic」とは異なり、やや落ち着いた感じのカッコよさを聴かせる3管黄金時代の第2弾。[1]は従来のジャズ・メッセンジャーズの持ち味であるミドル・テンポのファンキーな曲で、メッセンジャーズ=ファンキーのイメージを持つ人はこれを聴くだけで気持ちが高揚するはず。自らの回教徒名を冠した[3]にはやはりドラム・ソロをフィーチャー。ゆったりとした曲で知られる有名ミュージカル曲の[6]はハイパー・テンションでパワフルに演奏される。全体としては、フロント陣はもちろん好調だし、シダー・ウォルトンが洗練されたフレーズから黒っぽいフレーズまで柔軟に演奏しているのが印象的。あとはこの作品を最後に脱退するジミー・メリットの弾力性あるベースの存在感も改めて認識できる。次作以降と聴き比べると「Moanin'」以来、ずっとブレイキーとコンビを組んできたメリットがこのグループのノリを作ってきたことが良くわかる。(2006年7月20日) | ||
| Three Blind Mice Vol.1 | ||
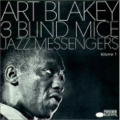 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1962/3/18 [1] Three Blind Mice [2] Blue Moon [3] That Old Feeling [4] Plexis [5] Up Jumped String [6] Up Jumped String (alt take) [7] When Lights Are Low [8] Children Of The Night |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Jymie Merritt (b) Art Blakey (ds) |
| 現在ではブルーノートから発売されている本作は、実はユナイテッド・アーティスツとワン・ショットで契約を結んでリリースされたライヴ盤。ブルーノート(アルフレッド・ライオン)であれば、ライヴ・アルバムを製作する場合であっても何ステージかを録音し、曲順も入れ替えてレコード化される。それはライヴ・アルバムが単にステージの記録という位置づけでなく、ライヴならではの演奏を1枚のレコードという商品として製作していたから。このアルバムは、ハリウッドにあったルネッサンス・クラブであったステージをそのまま収録した通常の普通のライヴ盤。ブルーノートのアルバムと比べると1枚のレコードとしてプロデュースされていないから、昔聴いたときにはあまり印象に残らなかった。しかし、記録だからこそ、[2]ではハバードのみをフィーチャーしたバラード・プレイが聴けたり、[3]ではほとんどシダー・ウォルトンのピアノ・トリオ演奏になっていたり、[7]はフラーのみであったり、というような曲を聴くことができる。そして演奏そのものは恐らくこれが日常のレベルであったと思われ、それが十分素晴らしい。つまり、作り込まなくても、この時期の3管メッセンジャーズが素晴らしいグループであったことを思い知らされる。(2024 年2月5日) |
||
| Caravan | ||
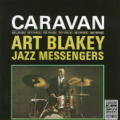 曲:★★★ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★★ JM入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1962/10/23 1962/10/24 [1] Caravan [2] Sweet 'N' Sour [3] In The Wee Small Hours Of The Morning [4] This Is For Albert [5] Slylark [6] Thermo [7] Sweet 'N' Sour (take 4) [8] Thermo (take 2) |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Art Blakey (ds) |
| 僕の所有しているブレイキーCDライブラリーの中では、ベースがレジー・ワークマンに代わってから最初のアルバム。ブレイキーのドラム・ソロをフィーチャーした超有名スタンダード曲[1]で小気味よく始まるところはJMらしさ炸裂。また[3]ではフラーのトロンボーンならではの甘い音色でバラードを聴くことができる。[4]もブレイキーらしいリズムで各曲のソロ・パートも個性を発揮・・・ということで、確かに「らしさ」はある。なのにどうもテンションが低く感じてしまうのはブルーノートとは明らかに録音の感触が違うことが原因のような気がする。ドラムの音が反響音を抑えた録り方でそれはそれでいいのかもしれないけれど迫力不足に感じてしまう。バラードや落ち着いた曲が多いのもテンションが低いと感じることに無縁ではない。こういう落ち着いたジャズ・メッセンジャーズもたまにはいいかもしれないけれどやはりブルーノートでのアグレッシヴな演奏に惹かれる。(2006年5月27日) | ||
| Ugetsu | ||
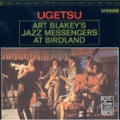 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ JM入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1963/6/16 [1] One By One [2] Ugetsu [3] Time Off [4] Ping-Pong [5] I Didn't Know What Time It Was [6] On The Ginza [7] Eva [8] The High Priest [9] The Theme |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Art Blakey (ds) |
| ユナイテッド・アーティスツ・レーベルからリリースされたバードランドにおけるライヴ。「Three Blind Mice Vol.1」とは異なり、なかなか熱い演奏が聴ける。思い起こせば、これまでもバードランドでのライヴ盤は良い演奏ばかりで、ここにはジャズ・メッセンジャーズを煽る何かがあるんだろうかと思わせる。いかにもジャズ・メッセンジャーズ的盛大かつファンキーな[1]で掴みはOK。アップテンポの[3]で更に盛り上がる。[4]は「Roots And Herbs」にも収録されていた曲で終盤のトランペットの聴きどころをモーガンと比べてみるのも面白い。[5]はショーターのソロのみをフィーチャーした曲、来日でインスパイアされたと思われる[6]は耳当たりが良いけど平凡。[7]は3管アンサンブルを活かしたバラード。[8]は後に「Kyoto」に収録された曲。黄金期の演奏なだけに悪いはずはないんだけれども、あともう一歩燃えきらない感じ。視点を変えると燃えるだけがジャズ・メッセンジャーズではない、ブルーノートは燃える部分にフォーカスしすぎていたと考えることもできるので、こういう音源も聴いてこそこのグループの実態を理解できるということかもしれない。冒頭のピー・ウィー・マーケットのアナウンスは途中からフェード・イン、最後のテーマもすぐにフェードアウトしたりと全体の構成力が甘いところが残念。(2006年7月30日) | ||
| Free For All | ||
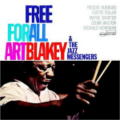 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★☆ JM入門度:★★★★☆ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1964/2/10 [1] Free For All [2] Hammer Head [3] The Core [4] Pensativa |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Art Blakey (ds) |
| 3管になってからのメッセンジャーズは快活でちょっとドライなサウンドが持ち味だけれど、本作はそういうレベルを超越してしまって「激しさ」に昇華された異色作になっている。最初から最後まで、とにかく何かに取り憑かれたかのような勢いとテンションが持続し、圧倒されること間違いなし。[1]はウォルトンの上昇するコード進行に、ショーターが、フラーが、ハバードが、それはそれは激しくブロー。ソロのサポートに入るアンサンブルにまでその力強さが伝染している。もうこれで十分という聴き手に対し、さらにブレイキーがダメ押しのサディスティックなまでのプッシュ。鋭利なソロをかますハバードの背後で叩いているドラムはプッシュを通り越してドラム・ソロとの同時進行かという勢い。[2]はいかにもジャズ・メッセンジャーズらしいミドルテンポでファンキーなノリながら、ここでもそのテンションにはいささかの衰えも見られず[3]で再び興奮がピークを迎える。とにかくショーターが凄い。いや、フラーも。いや、ハバードの饒舌さもかなりキテいる。軽快な[4]でようやく少しだけホッとできるものの、張り詰めた空気が緩むことはない。とにかく「こうしたら知的になるかも」「こう吹けば音楽的に高度なものになるかも」というような雑念がなく。「おっとっと」という前のめりな部分もあるとはいえ、感情の赴くままにヤルというある意味ジャズの原点が、幾分モダンジャズが洗練されてきた64年という時代に蘇るスリルに興奮する。燃えすぎて何も残らず灰になりそうなところを温度調整しているウォルトンの洗練されたピアノとワークマンのモダンなベースも聴き逃せない。激しくありながらフリージャズへは行かず、ジャズであることにこだわっているところがまたジャズ・メッセンジャーズの良さ。ああ、このときのヴァン・ゲルダー・スタジオに僕は居たかった。(2006年5月27日) HDtrackesより96KHz/24bit音源を購入。このサイトで販売されているブルーノートの音源は大きく分けて2種類に分類されるようで、ひとつはミックスからして違うもの、もうひとつはミックスはそのままに音質の向上が図られているものに大別できる。このアルバムの音源は後者で、基本的にミックスは変わっていない。ただし、ピアノの定位がわずかに右に寄っているところがヘッドフォンだとよくわかる(リマスターの証)。このハイレゾ音源を聴くと、CDでは管楽器やシンバルなどの高音成分を含んだ楽器の音が少し荒れていることがよくわかる。音楽の聴こえ方を左右するような違いではないものの、よりまろやかでリアリティのあるこの音質を聴くとCDはさすがにもう聴く気にはなれない。尚、このアルバムは大音量部分、とりわけ迫力のドラム演奏が捉えられているものの、音が歪んでしまっているとことも少なくない。この点はハイレゾ音源でも解消されていないのでマスターテープの時点で既に歪んでしまっていると思われる。(2013年6月23日) |
||
| Kyoto | ||
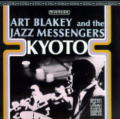 曲:★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★ JM入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1964/2/20 [1] The High Priest [2] Never Never Land [3] Wellington's Blues [4] Nihon Bash [5] Kyoto |
Freddie Hubbard (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Art Blakey (ds) Ellington Blakey (vo [3]) |
| 恐らく来日公演直後に録音されたと思われるアルバム。わずか33分の収録時間なのにこのまとまりのなさは何なんだろう。いかにも3管JMらしい[1]、フラーのオリジナル[2]、「ピーターパン」からのバラード(フラーの甘い音色がいい味を出している)[3]、ブレイキーのいとこがヴォーカルをとるコテコテのブルース[4]、渡辺貞夫作のモーダルな曲(これはなかなかカッコイイ)[4]、最後はハバードのオリジナルという構成。ショーターのオリジナルがない、ドラム・ソロがない、曲はイマイチ、録音があんまりパッとしないなど、なんとも微妙な作り。これもJMの一部には違いなく、だからこそブレイキーはリバーサイドでの録音を選んだのかもしれない。「Free For All」のわずか10日後に録音されたものとはとても思えない作風で、こんなアルバムもあります、という感じが個人的にはするんだけれど、ブルーノートのカッチリしたところが肌に合わない人にはこちらの方が面白いのかも。(2008年5月23日) | ||
| Indestructible | ||
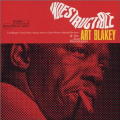 曲:★★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★★ JM入門度:★★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1964/4/24 1964/5/15 [1] The Egyptian [2] Sortie [3] Calling Miss Khadija [4] When Love Is New [5] Mr. Jin |
Lee Morgan (tp) Wayne Shorter (ts) Curtis Fuller (tb) Ceder Walton (p) Reggie Workman (b) Art Blakey (ds) |
| ショーター最後の、そしてジャズ・メッセンジャーズのブルーノート在籍時最後のアルバム。フレディ・ハバードの後任としてリー・モーガンが復帰。3管の厚いアンサンブルは好きなんだけれど、どうしてもハバードが受け付けないという人には福音かも。モーガンが復帰したからといってサウンドが変わったというわけでもなく、いつものファンキー味は健在。強いて言えば、冒頭2曲にフラーの曲を持ってきているところがちょっといつもと雰囲気が違うと思えるところか。その[1]は珍しく作者フラーの熱いソロから始まり、それを引き継ぐショーターのソロが輪をかけて熱い熱い。モーガンも縦横無尽のアドリブを披露。以降も勢いのある演奏の連続。フロント3人の演奏はテンションが高く、ブレイキーの持ち味も出ていてJMの魅力を存分に楽しめる。ウォルトン作の[4]はショーターの曲かと思うようなムードのあるバラード。音楽的にはショーターとフラーのカラーが出ていてモーガンの印象はやや薄い感じ。「Free For All」のような異様なテンションというほどではないけれど、これも素晴らしい熱演集には違いない。(2006年6月11日) | ||
| 'S Make It | ||
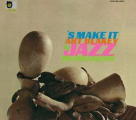 曲:★★★☆ 演奏:★★★ ジャズ入門度:★★ JM入門度:★☆ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1964/11/15 1964/11/16 1964/11/25 [1] Faith [2] 'S Make It [3] Waltz For Ruth [4] One For Gamal [5] Little Hughie [6] Olympia [7] Lament For Stacy |
Lee Morgan (tp) John Gilmore (ts) Curtis Fuller (tb) John Hicks (p) Victor Sproles (b) Art Blakey (ds) |
| ショーター脱退後のジャズ・メッセンジャーズに関する情報は少なく、何を聴いたら良いのか見当もつかないのが実情。そんな中、偶然中古ショップで見つけたこのアルバム。レーベルはライムライトに変わり、メンバーもガラリと入れ替わっていてそこに期待と不安が入り混じる。[1]を除いてメンバー(モーガン3曲、ヒックス2曲、フラー1曲)のオリジナルで、いい加減に作られた印象はないものの、全体にリラックス・ムードが漂う曲と演奏。確かにショーター在籍時とは違うし、ブレイキーのプッシュも控えめ。それでも3管で奏でられるテーマを聴いているとどう聴いてもやはりジャズ・メッセンジャーズ。リー・モーガンのトランペットはのんびりムードの中にも切れ味は健在だしフラーも然り。ところが、後にアンドリュー・ヒルの「Compulsion!!!」でフリーキーなプレイを聴かせるジョン・ギルモアが凡庸で存在感がない。やはりショーターが抜けた穴は大きいと思わずにはいられないけれど、少しのんびりムードのJMはこれはこれで悪くないかも。曲は長くても6分未満という構成も含めてなんともアッサリ風味のアルバム。(2007年5月3日) | ||
| Keystone 3 | ||
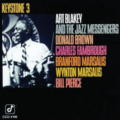 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ JM入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1982/Jan [1] In Walked Bud [2] In A Sentimental Mood [3] Fuller Love [4] Waterfalls [5] A La Mode |
Wynton Marsalis (tp) Branford Marsalis (as) Bill Puerce (ts) Donald Brown (p) Charles Fambrough (b) Art Blakey (ds) |
| 低迷時期に細々とグループを維持してきたブレイキーの人気が復活したのは、稀代の天才トランペッター、ウィントン・マルサリスが加入してからであるというのが一般的に言われていること。ではウィントン在籍時に名盤と呼ばれているものがあるかといえば、これがなく、何を選んだら良いのかわからない。とりあえず容易に入手できるこのアルバムとしてチョイスしたのが本作。決して悪くはないけれど、やはり80年代のジャズは黄金時代の50〜60年代とはムードが違っていてもうひとつ熱気が感じられない。それでも82年にこういうオーセンティックなジャズをやっていたことにはある意味凄いというかブレイキーにはコレしかないというか。注目のウィントンのプレイは素晴らしい。僕なんかが力説するまでなく、このトランペッターのテクニックは間違いなく歴史に残るもの。しかし、このアルバムでは出番は少なくそれも不満要素のひとつ。変わったところでは、ブランフォード・マルサリスがアルト・サックスを吹いているところか。SACDまでリリースされている本作は、しかしとりたてて強調するポイントがないと思う。(2006年8月8日) | ||
| 'Hard Champion | ||
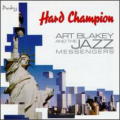 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ JM入門度:★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1985/5/24 [1] [2] [4] 1987/5/3 [3] [1] Scenic Route [2] Come Rain Or Come Shine [3] Theme of 'Hard Champion' [4] Witch Hunt |
[1] [2] [4] Terence Blanchard (tp) Donald Harrison (as) Jean Toussaint (ts) Mulgrew Miller (p) Lonnie Plaxico (b) Art Blakey (ds) [3] J Harper (tp) Kenny Garrett (as) Jevon Jackson (ts) Benny Green (p) Peter Washington (b) Art Blakey (ds) |
| 何故か父の CD コレクションにあった晩年のアルバム。知っている名前がテレンス・ブランチャードとケニー・ギャレットしかない。Projazz というレーベルも知識不足につき、存じ上げない。わずか3分半の[3]を除きニューヨークのスウィート・ベイジルにおけるライヴ(ただし歓声はあまり聞こえない)。演奏はこれがなかなか良く、なによりもブレイキーらしさが健在であるところがうれしくなる。ベースの音に、この当時流行った電気系の響きがあるのでそれが嫌いな人には不向きか。というわけで特に欠点らしいものはないんだけれど、フロント陣のアドリブ奏者としてのパンチがないのが残念。この時代にまだブレイキーが変わらぬジャズをやっていたことに価値があるということか。(2006年7月10日) | ||