ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Bill Bruford
| A Part, And Yet Apart | ||
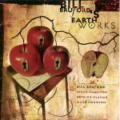 曲:★★★★ 演奏:★★★☆ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1998/Nov [1] No Truce With The Furies [2] A Part, And Yet Apart [3] Some Shiver, While He Cavorts [3] Footloose And Fancy Free [4] Sarah's Still Life [5] The Emperor's New Clothes [6] Curiouser And Curiouser [7] Eyes On The Horizon [8] Dewey-eyed, Then Dancing [9] If Summer Had Its Ghosts (Bonus Track) |
Patrick Clahar (ts, ss) Steve Hamilton (p) Mark Hodgson (b) Bill Bruford (ds) |
| ブラッフォードがついに結成した念願のアコースティック・ジャズ・グループ。名前は同じでも以前のキーボードをフィーチャーしたアースワークスとは別モノと考えた方が良い。ワン・ホーン・カルテットというオーソドックスな編成ながら、そのサウンドはストレート・アヘッドなジャズでもなければフュージョンでもない独自のもの。フォービートは時折顔を出す程度で基本はやはり変拍子。それをあまりわざとらしくやらないで、そこそこ自然に聴かせようとしている点、そしてフリー・ジャズ的なインプロヴィゼーションがない点がキング・クリムゾンとは違うアプローチで、リズムに関してはブラッフォードが敬愛するジョー・モレロ擁するデイヴ・ブルーベック・カルテットの手法と似ている面もある。曲はモダン・ジャズのようなテーマ→ソロ→テーマというスタイルを取っていないので、どこまでが決められたメロディでどこまでがアドリブなのかがわかりにくく、恐らくほとんど作曲されたメロディと思われる。パトリック・クラハーはテクニック、表現力においてはお世辞にも一流までは言えない。引き締まった音色なのはいいとして、熱さや荒さがなく、表情に乏しい。ピアノも特筆するものは感じないものの、ベース共々ブラッフォードのリズムに追随するという点では無難にこなしている。もともとジャズにおけるリズムの基本はベースが作るものでドラムはサポート役だというのが僕の考えだけれど、このグループのリズムの基本は常にドラムにあるところがユニーク。ブルース・フィーリングや黒人臭が皆無であることと合わせて、個性的であることは間違いない。(2007年2月23日) | ||
| The Sound Of Surprise | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 2000/Nov [1] Revel Without A Pause [2] Triplicity [3] The Shadow Of A Doubt [4] Teaching Vera To Dance [5] Half Life [6] Come To Dust [7] Cloud Cuckoo Land [8] Never The Same Way Once [9] The Wooden Man Sings And The Stone Woman Dances a. Prelide b. The Wooden Man Sings c. ...And The Stone Woman Dances [10] The Sound Of Surprise (Bonus Track) |
Patrick Clahar (ts, ss) Steve Hamilton (p) Mark Hodgson (b) Bill Bruford (ds) |
| 前作「A Part, And Yet Apart」と同じメンバーによる第2弾。曲、演奏、音楽性は変わっていない。誤解されがちだけれど、このグループはブラッフォードのドラムを聴くためのものではない。あくまでもブラッフォードが考えるジャズを聴くためのもの。自身が作曲に深く関わり、捻った曲名やタイトルを冠する。演奏者への指示も細かくされていたのではないだろうか。つまりグループを統括し、ブラッフォードがジャズ・ミュージシャンとして自己を表現していることことにプライオリティが置かれている。それでもリズム・チェンジを多用するなど、リズムへのアプローチはブラッフォードならではのものだし、ドラムの基本スタイルは以前と何も変わっていない。ジャズは50年代で終わったという保守的な人はともかく、誰が聴いてもジャズと感じるアコースティック・ジャズでありながら、このような演奏を聴かせるグループは他にない。サックスの演奏に進歩がないところはやや残念だけれどグループとしてのまとまりは良くなっている。(2007年2月23日) | ||
| Footloose And Fancy Free | ||
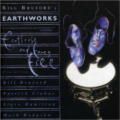 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★☆ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2001/6/23-24 Disc 1 [1] Footloose And Fancy Free [2] If Summer Had Its Ghosts [3] Part, And Yet Apart [4] Triplicity [5] Come To Dust [6] No Truce With The Furies [7] Wooden Man Sings, And the Stone Woman Dances Disc 2 [8] Revel Without A Pause [9] Never The Same Way Once [10] Original Sin [11] Cloud Cuckoo Land [12] Dewey-Eyed, Then Dancing [13] Emperor's New Clothes [14] Bridge of Inhibition [15] The Shadow Of A Doubt |
Patrick Clahar (ts, ss) Steve Hamilton (p) Mark Hodgson (b) Bill Bruford (ds) |
| もう何年も前から思ってた疑問として、このアースワークスは誰が聴いているのだろう、というのがあった。理想的なリスナーはキング・クリムゾンが好きでジャズを聴く耳を持っている人ということになるんだろうけれど、そういう人は絶対的には少なく、ブラッフォードが好きで、少々我慢しながらジャズを聴いている人が多いような気がする(自分もそのうちの一人だった)。アースワークスに関係する周囲の人も恐らく似たようなもので、ジャズに関連している人はほとんどいないのではないだろうか。例えばこのアルバムの英文解説翻訳で、ミュージシャンの名前、例えばポール・モチアン、マックス・ローチ、ゲイリー・バートン、ボビー・ハッチャーソン、ジャッキー・マクリーンなどをすべて原文のままで表記している。一般的に固有名詞がどんなカタカナ表記されているかはその世界に馴染んでいなければわからないわけで、この翻訳に関わった門外漢はそれを調べるのも面倒だったように見える。極めつけは Post-Bop を ポスト「ボップ」と表記されていることで、いかにジャズを知らない人が携わっていかがわかってしまう。そんな不憫なブラッフォードのアコースティック・アースワークスもメンバーを変えずに、つにライヴ・アルバムを発表。2枚組約126分というボリュームは気軽に聴くには躊躇するものの、演奏はスタジオよりもやはり生き生きしていて良い。特にスタジオ盤では力不足を感じたサックスもここでは生気を増している。妙にスネアの音が反響している録音状態がちょっと気になるとはいえ、クラブ演奏ならではの雰囲気もいい。[3]は残念ながら「Bruford Levin Upper Extremities」の方がクールでカッコいい。一方で、エレクトリック・アースワークス時代の[14]の演奏がメチャクチャかっこいい。叩きまくることはなくても、実は中心にあるのはドラムというこのグループを総括する、充実したライヴ盤。(2007年2月23日) | ||
| Random Acts Of Hapiness | ||
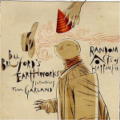 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2003/5/13-14 [1] My Heart Declares A Holiday [2] White Knuckle Wedding [3] Turn And Return [4] Tramontana [5] Bajo Del Sol [6] Seems Like A Lifetime Ago (Part1) [7] Modern Folk [8] With Friends Like These... [9] Speaking With Wooden Tongues [10] One Of A Kind (Part 1) [11] One Of A Kind (Part 2) [12] Blues For Little Joe |
Tim Garland (ts, ss, fl, bcl) Steve Hamilton (p) Mark Hodgson (b) Bill Bruford (ds) |
| 新サックス奏者にティム・ガーランドを迎えて初のアルバムはライヴ盤。このラインナップは2002年4月の来日公演で既に観ていたのでガーランドの実力が前任者を上回ることは知っていたんだけれど、本作でもそれを確認できる。パトリック・クラハーよりも表情豊かでフレーズも多彩。作曲にも深く関わりマルチ・リード奏者であることも相まってグループ全体のサウンドを広げることに成功している。元から黒人臭がしないグループが、さらに白っぽくなったように感じるのもガーランドに負うところが大きく、ブラッフォードの音楽との相性もいいように感じる。ただ、少々アッサリ味というか、もう少しアクというかクセのようなものが欲しいという気もする。それにしてもクリムゾン時代にあれだけ弾けた演奏をしていたブラッフォードが、このような抑揚の効いたジャズを演奏をしてるところが面白い。でも、この2003年という時代にクリムゾンのような音楽がウケるはずもなく、次のステップへ進もうとしているたブラッフォードの方が、ミュージシャンとして前向きな生き方のように思える。尚、このアルバムからDGMの管理を外れ、自ら設立したレーベルからのリリースとなり、配給がより限られたことによって、ついに正式な国内盤は発売されなくなった。何かのインタビューで「ロック・ミュージシャンでジャズを演ってみたいという人は結構いるんだが、食べていけるか不安で足を踏み出せない。でも、やってみれば結構なんとかなるもの。だからどんどんトライした方がいい」と言っていたブラッフォード。つまり、この頃からキング・クリムゾンの後ろ盾がなくてもやっていける自信がついたということなんでしょう。(2007年2月24日) | ||
| Earthworks Underground Orchestra | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 2004/12/10-11 [1] Libreville [2] Up North [3] Pigalle [4] Speaking In Wooden Tongues [5] Footloose And Fancy Free [6] Bajo Del Sol [7] It Needn't End In Tears [8] Wooden Man Sings, And the Stone Woman Dances Bonus Disc [9] Thud [10] Rosa Ballerina |
Tim Garland (ts, ss, fl, bcl) John Owens (tp) Alex "Sasha" Sipiagin (tp) Rock Ciccarone (tb) Robin Eubanks (tb [4][5][9]) Chris Karlic (bs, fl) Steve Wilson (as, ss, fl) Henry Hey (p) Mike Pope (b, elb) Bill Bruford (ds) |
| 演奏家としてよりも音楽家としてジャズ・ミュージシャンを志すとなると、一度は大編成のコンボを率いることに憧れを抱くものらしい。ブラッフォード自身、アースワークスで作曲家としての才能を遺憾なく発揮していたところに、作曲、アレンジの才があるティム・ガーランドと出会いがあり、こういった大編成コンボが実現可能になったものと思われる。ここでの音楽はコンボとしての表現を主眼に置いたものであり、ブラッフォードがドラムを叩きまくっているというシーンはないし、ドラム・ソロもほとんどない。あくまでもバンドのリーダー、グループの一員としてのドラマーといった役割に徹している。それこそがブラッフォードがやりたかったことなんでしょう。バンド全体としての演奏(ソロパートもみんな上手い)とアレンジはなかなかいい。[1]-[3]までは、ガーランドが持ち込んだと思われるアフロ・キューバンなムードのあるアレンジがあり、これまでのブラッフォードの音楽にない一面が見える。他の曲もウェイン・ショーターの「Alegria」のようなアレンジとムードが多い。細かいところではエレクトリック・ベースが多用されているのでアースワークスの曲でもグルーヴ感がちょっと違うところが興味深い。押し出しの強いドラマーとしてのブラッフォードを期待するとつまらないけれど、音楽はなかなか聴きどころがあって面白い。しかし、ロック耳しか持ち合わせていない人にはちょっと辛いかも。ちなみに、このプロジェクトはツアー先の地元ミュージシャンを交えながら活動していたらしく、このアルバムはニューヨーのミュージシャンを起用したライヴとなっているようだ。尚、本作はブラッフォードとガーランドの共同名義作品でアースワークスではないところがちょっとややこしい。(2007年2月23日) | ||
| Bruford Levin Upper Extremities | ||
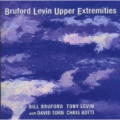 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★ |
Released in 1998 [1] Cerulean Sea Interrude [2] Original Sin [3] Etude Revisited [4] Palace Of Pearls (On a Blade of Grass) - Interrude - [5] Fin De Siecle [6] Drumbass [7] Cracking the Midnight Glass [8] Torn Drumbass [9] Thick With Thin Air [10] Cobalt Canyons - Interrude - [11] Deeper Blue [12] Presidents Day |
Chris Botti (tp) David Torn (g) Tony Levin (b) Bill Bruford (ds) |
| ダブル・トリオ・クリムゾンは、96年のワールド・ツアー終了後に活動が一段落。次の展開は?という時期になっても、実力派売れっ子ミュージシャンが6人も集まった集団なだけにスケジュールの都合から活動を再開できない状況になっていた。そこでメンバーを部分的にセレクトしたユニットとして活動する方法をフリップは採用する。それがProjeKctシリーズになるんだけれど、このBruford Levin Upper Extremitiesは、フリップ抜きの番外編的なユニットとして活動していた。音楽の中心はトニー・レヴィン(ブラッフォード曰く「トニーのユニット」)で、彼のスティック・ワークを中心としたシンプルなリフが曲の基礎になり、そこにブラッフォードが変拍子リズム(エレクトリック・ドラムは使っていない)を絡める。このリズム・セクションに、デヴィッド・トーンのギターとクリス・ボッティのトランペットがサウンドを彩るという構成。トーンのギターは運指やピッキングの正確さという観点の奏法とはまるで考え方が違うスタイルで、そのノイジーかつ不思議なサウンドで音空間を構築し、全体のムード作りに大きく貢献。イケ面トランペッターとしてポップス界でも名前が売れているクリス・ボッティはマイルス・デイヴィスばりのクールかつ甘い奏法を持ち味としていて、ここでは少々シリアスなムードでこのユニットに合ったプレイを聴かせる。レヴィンはスティックだけでなく、ファンク・フィンガーズやエレクトリック・アップライト・ベースなども駆使し縦横無尽の活躍。ブラッフォードの変拍子の入れ方も容赦なく、こういったロック的な演奏をそれ以降しなくなってしまっただけに貴重な記録にもなっている。一般的に話題になることはほとんどないものの、これだけ質の高いジャズ系プログレはなかなかないと思う。(2007年2月25日) | ||
| BLUE Nights | ||
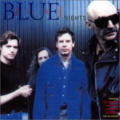 曲:★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★★ |
Released in 1999 Disc 1 [1] Piercing Glances [3] Etude Revisited [3] Palace Of Pearls (On a Blade of Grass) [4] Original Sin [5] Dentures of the Gods [6] Deeper Blue [7] Cobalt Canyons Disc 2 [8] Fin De Siecle [9] Picnic On Vesuvius [10] Cerulean Sea [11] Bent Taqasim /Torn Drumbass [12] Cracking the Midnight Glass [13] Presidents Day [14] 3 Minutes Of Pure Entertainment [15] Outer Blue |
Chris Botti (tp) David Torn (g) Tony Levin (b) Bill Bruford (ds) |
| 番外編かつ一時的プロジェクトだったBruford Levin Upper Extremities。恐らく当初は予定していなかったであろうライヴ・アルバムまでリリースしてしまった。商業的成功なんて初めから念頭に置かず、他にない独自のプログレッシヴ・ジャズ・ロックを作るという純粋な動機で活動する、実力者揃いのグループなだけに内容は非常に充実している。冒頭の[1]からフリー・インプロヴィゼーションで幕を明けるのをはじめ、既発スタジオ盤の曲もより自由に、そしてスリリングに演奏されている。こんなに一般ウケしない音楽を2枚組というさらに一般人を遠ざける形でリリースしてしまうところもまた笑ってしまうけれど、この演奏を聴けばそれも納得というもの。一時的なユニットという気楽さが、ここまで自由にできた理由のように思える。ブラッフォードのドラミングは激しさこそないものの、彼独特の変拍子とリズムチェンジが炸裂しており十分聴き応えがあり、ファンも納得できる。もうひとつ、ケニー・Gのトランペット版と言われるくらい、イージー・リスニングのイメージがあるイケ面トランペッター、クリス・ボッティがノン・ヴィブラートで透明感溢れるクールなトーンを駆使し、シリアスかつアブストラクトな展開に溶け込んでいるところも聴きどころ。とにかく素晴らしい。(2007年2月25日) | ||
