ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Tony Williams
| Life Time | ||
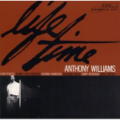 曲:★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1964/8/21 1964/8/24 [1] Two Pieces Of One: Red [2] Two Pieces Of One: Green [3] Tommorow Afternoon [4] Memory [5] Barb's Song To Wizard |
[1]-[3] Sam Rivers(ts) Gary Peacock(b) Richard Davis (b except [3]) Tony Williams (ds) [4] Bobby Hutcherson (vib, marimba) Herbie Hancock (p) Tony Williams (ds, tympani, wood block, maracas, triangle) [5] Herbie Hancock (p) Ron Carter (b) |
| 独自の先鋭的ジャズ観を持つトニー・ウィリアムスの初リーダー・アルバムがブルーノートからというのは、実に自然なことのように思える。前半と後半で曲によってメンバーを使い分けているところは、散漫なのではなくむしろ幅広い表現への熱意の現れ。[1]ではサム・リヴァースのテナーとゲイリー・ピーコックのアルコ弾きベースで不気味なテーマから始まり鋭角なベース・ソロへ。そこから自由なリズムで展開される様はまさにフリー・ジャズで、疾走感やノリといったものは皆無。[2]はほとんどリヴァースとトニーのデュオで、コルトレーン&エルヴィンとはまったく異なる方向性でフリー・ジャズ的に展開する。比較的普通に聴ける[3]はスピーディでスリルがあるけれどフリー・ジャズ的な演奏であるところは変わりない。普通このようなピアノ・レスのワン・ホーンによる演奏はホーン奏者がいかに空間を埋めることができるかが問われることになるけれど、ここではトニーのドラムが空間を支配してしまう。[4]はハッチャーソンがヴァイブ、マリンバを駆使して抽象的な音空間を作り、ハンコックが現代音楽調ピアノで応じ、トニーはドラムだけでなく他の打楽器をも多彩に操るという、パーカッション・パフォーマンス。トニーはどのグループで演奏しても手数が多いけれど、どこかで抑えた知的な部分があって、それは自身のリーダー・アルバムでも変わらない。体を揺らしたくなるようなグルーヴとは対極にあるトニーの正確かつ変幻自在のドラミングとサイド・メンのフリーキーなパフォーマンスで構成された本作が発する冷徹な空気は独特なものがあり、リーダーが演奏に参加しないという異例の[5]を含め、18歳とは思えぬ音世界を作り上げてしまったセンスに感嘆する。(2006年9月15日) | ||
| Spring | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★☆ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1965/8/12 [1] Extra [2] Echo [3] From Before [4] Love Song [5] Tee |
Wayne Shorter (ts) Sam Rivers (ts) Herbie Hancock (p) Gary Peacock (b) Tony Williams (ds) |
| トニーのリーダー・アルバムというと1枚目の「Life Time」が紹介されることの方が圧倒的に多い。確かに18歳が初リーダー・アルバムで独自のフリー・ジャズを作ってしまったことは衝撃的でそれを称賛することはやぶさかではない。しかし、その方向性をさらに成熟させ推し進めた本作の方が内容は上だと思う。メンバーは曲によって出入りがあるものの、ほぼ固定でアルバムを通してまとまりがあるし、フリー・ジャズ的な要素の中にも統制感があって完成度が高い。また、ショーターとリヴァースのツイン・テナー構成が異色で個性的。2人とも似たムードのフリーキーな演奏ながら、左寄りがリヴァース、右寄りがショーターに音が振り分けられているので聴き分けは容易。[3]以降から参加のハンコックは、今回も現代音楽的な演奏で控えめに空間を埋める。[4]はリヴァースのみによるテナーがリラックスした感じで、全体の流れに溶け込んでいながらも静かでシンプルな味わい深い曲。 [5]でようやく5人が揃い踏み。サックス・ソロはショーターのみでベース・ソロの途中でブッツリと終わってしまうのは収録時間の都合だったからなのか。ドラマーとしては最上級の評価を受けていたトニーがわずか19歳にして作曲家、サウンド・クリエイターとしても優れていることを証明しているのが本作。他の誰にも真似できない独自の音楽を作ったことはもっと賞賛されてもいいと思う。[1]でのスピード感溢れるブラシさばき(唐突に終わるエンディングのカッコイイこと!)、5分に及ぶドラム・ソロのみの[2]など、ドラマーとしての力量も十分見せつけている。トニーのドラミングとフリー・ジャズが好きな人なら必聴。(2006年9月15日) | ||
| Emergency ! | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1969/5/26 1969/5/28 [1] Emergency [2] Beyond Games [3] Where [4] Vashkar [5] Via The Spectrum Road [6] Spectrum [7] Sangria For Three [8] Something Special |
John McLaughlin (g) Larry Young (org) Tony Williams (ds, vo) |
| マイルス・グループを脱退した後、トニー自ら率いたグループがこのライフタイム。相手に選んだのは、ジョン・マクラフリンとラリー・ヤング。録音年にしては音が良くない、というかジャズというよりロックにありがちな籠もった録音状態になっていて、それもまた時代の空気という感じがする。したがって人によっては古臭いサウンドと感じるかもしれない。69年といえば、ロックの世界で言うとレッド・ツェッペリン、キング・クリムゾンがデビューしたばかり、ディープ・パープルが「In Rock」を発表した年。ジャズでは、コルトレーンは既に鬼籍に入り、マイルスはロスト・クインテットで活動中で「Bitches Brew」を発表した年。つまりジャズもロックも新しい大きな波が来ていた時期だった。そんな時代のこのライフタイムのサウンド、僕はロックの耳で聴いてしまう。マクラフリンのギターは、既存のジャズ・ギタリストとは明らかに語彙が違うけれど当時のロック・ギターとしてはブルース・フィーリングと派手さが足りない。ラリー・ヤングのオルガンはブルーノート時代のリーダー・アルバムのサウンドとは明らかに異なり、かなりロック的なノイジーな歪みがある。また、ベース・レス編成でベース・サウンドの存在感が薄いことによって更に際立つトニーのドラムは変幻自在、パワフルかつスピード感あふれるスリリングなものでバンド全体をリード。フォー・ビートで展開される曲もあり根底にジャズがあることは間違いないんだけれど、ロック・フィーリングをも消化したこのサウンドは、同時期にマイルスがやっていたロスト・クインテットのサウンドよりも斬新に聴こえる。ドラマーとしても素晴らしいパフォーマンスを披露する中、あくまでも中心にあるのがこの斬新なサウンドというところにトニーの音楽家としてのこだわりを感じる。わかりやすメロディがないところは当時の先進的ジャズと共通の特徴で、その点でロック・ファンにはちょっと馴染みにくいかもしれないけれど、インタープレイのスリリングさはEL&Pやディープ・パープルよりも上と断言。ジャズ・ファンよりはどちらかと言うとロック・ファン、特にプログレ・ファンに聴いてもらいたい傑作。(2006年9月15日) | ||
| Turn It Over | ||
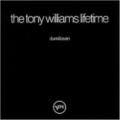 曲:★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1970 [1] To Whom It May Concern - Them [2] To Whom It May Concern - Us [3] This Night This Song [4] Big Nick [5] Right On [6] Once I Loved [7] Vuelta Abajo [8] A Famaous Blues [9] Allah Be Praised [10] One Word (bonus track) |
John McLaughlin (g, vo) Larry Young (org) Jack Bruce (b, vo [10]) Tony Williams (ds, vo) |
| ライフタイムのセカンド・アルバム。サウンドは前作の延長戦上にありながらハードさは更にアップ、というかもう行くところまで行ってしまっている。曲が短めになり、ボーナストラックを除くと約35分という収録時間(前作はアナログ2枚組で約70分)という表面だけを見ると、聴き易さを考えたようにも見えるけれどまったくそうなっていないところが面白い。コンパクトにまとめているというよりは、無理矢理打ち切って濃縮させている感じで、その分演奏が凄まじい。ラリー・ヤングのオルガンはジョン・ロードやキース・エマーソンよりも前衛的かつハード。ロック系キーボード・プレイヤーで人気を誇っていたエマーソンとロードはハードな演奏がウリであったにもかかわらず、クラシックのフレーズを借用していたのはラリー・ヤングとの比較を恐れたからではないかと邪推したくなるほど(実際そんなことはないだろうけど)、ここでのヤングのオルガンはロック的。ジョン・マクラフリンのギターもハード・ロック的で時に歪んだ音でスリルを加速、ジャック・ブルースのベースが加わることでロック・フィーリングをダメ押し。トニーのドラムは若いときから圧倒的テクニックを持ちつつも、勘所で抑える心憎さが魅力だったけれど、ここではそんな流儀を捨て去ってガンガン叩きまくっている。もう誰が聴いてもジャズというよりはハード・ロックなのに、ちょっととぼけたテーマを持つコルトレーン作の[4]をフォー・ビートでやってしまうところなどは「計算」よりも「勢い」や「ノリ」が優先された印象を受ける。しかし、それこそがこのアルバムの持ち味、聴きどころと言えるでしょう。激しさゆえに聴き手を選ぶこのサウンドを、当時はどんなリスナーが聴いていたのか、今どんなリスナーが聴いているのか興味深いところ。尚、CD ケースの左端スペースには (play it loud) と書かれているので指示に従うことをお勧めしたい。(2007年6月2日) | ||
| Believe It | ||
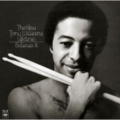 曲:★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★☆ |
[Recording Date] 1975 [1] Snake Oil [2] Fred [3] Proto-Cosmos [4] Red Alert [5] Wildlife [6] Mr. Spock [7] Celebration [8] Letsby |
Allan Holdsworth (g) Alan Pasqua (p, clarinet) Tony Newton (b) Tony Williams (ds) |
| ジャズ界最高峰のドラマーとして君臨するトニーの評価を確たるものにしている要因のひとつは右手にあると思う。何かが宿っているのではないかと思うほどレガート・シンバルを驚異的スピードと正確さで刻み、曲のムードを一変させるほどの力を持っていたその右手。その直線的な推進力は実はジャズのスウィング感には遠く、トニーが嫌いなジャズ・ファンも実は少なくないんじゃないかと思えるし、ウェイン・ショーターが自身のアルバムで起用しなかったのもこの直線的なリズムが理由ではないかと思う。一方でロック色の濃いこのアルバムではその右手の凄みは封印、普通にロック的にハイハットを刻んでロック・ビートを繰り出すトニーを当時のジャズ・ファンは堕落したとみなしたに違いない。しかし、ロック・スタイルであっても、ここで激しく展開されるドラムはトニー以外の何者でもない個性があるのは間違いなく、つまり、トニーにとってジャンルというのはどうでもいいことがわかる。何よりも重要なのは、トニーが優れた音楽家でもあり、その音楽性はジャズの世界に留めておくことができないほどのものであったおかげで、このようなカッコいいジャズ・ロックを僕たちは聴くことができるということ。ここではアラン・ホールズワースの弾きまくりも聴きどころで、脇を固めるメンバーのレベルも申し分なし。ロックの耳で聴くと表面的なサウンドはいわゆるフュージョンでありながら、しっかりと聴けばこんなに熱い演奏はそう簡単にはお目にかかれないことが実感できる。(2007年1月23日) | ||
| Wilderness | ||
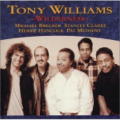 曲:★ 演奏:★ ジャズ入門度:★ 評価:★ |
[Recording Date] 1995/12/6/12 [1] China Town [2] Infant Wilderness [3] Harlem Mist '55 [4] China Road [5] The Night You Were Born [6] Wilderness Voyager [7] Machu Picchu [8] China Moon [9] Wilderness Island [10] Sea Of Wilderness [11] Gambia [12] Cape Wilderness |
Michael Brecker (ts) Pat Metheny (g) Herbie Hancock (p) Stanley Clarke (b) Tony Williams (ds) Lyle Workman (g [7]) David Garibaldi (per [1]) and Orchestra [2] [3] [6] [10] |
| メンツを見ただけで胸躍るアルバムというのがジャズの世界にはときどきあるけれど、このアルバムはその最たるものだろう。もちろん、メンツさえ良ければ素晴らしいものができるとは限らないとわかってはいるものの、あくまでも自身のドラムが中心のサウンドを独自の感性で作り上げてしまうトニーが大半の曲を書き、プロデュースもしているともなれば、悪くてもそれなりに納得できる質の高い音楽が聴けるだろうという期待を抑えることができない。しかし・・・聴いてみてこれほど肩透かしを食らったアルバムは珍しいかも。中途半端な薄味のフュージョンで始まると次は脈絡なく甘いストリングスで彩られた、しかし、さして美しくもないサウンドが出てきてCDを間違えたのではないかと思ってしまう。ところどころでソレとわかる各人のプレイを確認できるものの、目隠しして聴いたらこのメンバーが演奏しているとにわかには気づかないと思えるほど音楽そのものに魅力がない。トータルで見ても統一感がなく、一体何を目指して制作されたのかとの疑問しか浮かばず、期待していた映画を見てあまりにもつまらなかった時のモヤモヤと同じ感覚に襲われてしまう。肝心のトニーのプレイもほとんどいいところなし。どうせなら[4]のようなフュージョン路線で押してくれればまだ聴けたかもしれない。[1]にはパーカッションとして(恐らくタワー・オブ・パワーの)デヴィッド・ガリバルディの名前まで見えるけど何処で何を叩いているのかサッパリわからないという肩すかしもある。いやはや悪い意味でこんなに驚いたアルバムは初めて。聴くにあたって何か予備知識が必要なアルバムなんだろうか?これがトニーの遺作というのは悲しい。(2009年5月30日) | ||
