「被団協」新聞2022年5月号(520号)
2022年5月号 主な内容
平和は武力や核兵器では実現できない
憲法9条の活きる世界を
被爆者と憲法9条
 |
| 国会前に立つ被爆者ら(2018年4月)〈写真=亀井正樹〉 |
 |
|
ノーモア・ヒバクシャ9条の会 リーフレット |
今年3月に101歳で亡くなった被爆者、堀田シズヱさん(元埼玉県原爆被害者の会会長)が、2005年に『自分史つうしん』が行なった憲法9条に関するはがきアンケートに寄せたメッセージです。
2007年3月、日本被団協代表委員3人を含む被爆者と弁護士ほかの呼びかけで「ノーモア・ヒバクシャ9条の会(略称NH9)」が発足。「アピール」で次のように述べています。
「『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすること』を決意した日本国憲法、とりわけ『戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認』を定めた9条は、『ヒロシマ・ナガサキをくり返すな』の願いから生まれました。被爆者にとって、生きる希望となりました。
その9条がいま、変えられようとしています。戦争への反省と多くの人々の命を忘れ去り、日本はふたたび『戦争する国』になろうとしています。『ノーモア・ヒバクシャ』を願う私たちは、心から訴えます。
憲法9条は、絶対に変えてはなりません。憲法9条を守り、活かしてこそ、私たちの『願い』は実現できます」。
日本国憲法施行から75年の今年、ロシアのウクライナへの侵略戦争を受け、今また9条改憲論が高まっています。
「広島・長崎の原爆被爆者は、あの日の“地獄”と、今なおつづく心と体の苦しみの体験から、平和は武力や核兵器では実現できないことを知っています。戦争は殺戮と破壊以外の何ものでもありません」。(NH9アピールから)
「被団協」新聞はNH9と協力して「核兵器のない、9条の活きる世界を」アンケートを実施しました。今号でアンケートに寄せられた声と、沖縄戦被害者、空襲被害者の声をご紹介します
憲法改定は戦争につながる
 |
普天間朝佳(ひめゆり平和祈念資料館館長)
77年前、沖縄はアジア太平洋戦争末期の戦場になり、日米両軍による激しい地上戦が行なわれ、20万人余の尊い命が失われました。砲爆撃を逃げる中で親が子どもを捨てて逃げたり、米軍に追いつめられた住民による「集団自決(強制集団死)」が起き父親が妻子を殺めたり、さらに味方である日本軍によって住民が壕から追い出され、食糧を奪われ、スパイ容疑で殺されるということが起きたのです。
沖縄戦を体験して沖縄の人々が心に刻んだことは、戦争がいかに悲惨なものであるか、戦争では人間が人間でなくなってしまう、そして命どぅ宝(命こそ宝)ということでした。
戦前の日本では主権は天皇にあり、国民はその臣下であるとされました。戦争は天皇と国家のために行なわれる聖戦であり、国民はすべてを投げ打って協力しなければならないとされました。いざという時には自分の命を捧げる覚悟も要求されたのです。
戦後、その反省のもとに生み出されたのが、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を三本柱とする日本国憲法でした。しかし、米軍政下の沖縄には日本国憲法は適用されませんでした。米軍による事件や事故が多発し、沖縄の人々の命や人権が蹂躙され続けました。50年前、沖縄の人々が何より望んだのは日本国憲法がある日本への「復帰」でした。
今、ロシアによるウクライナへの侵攻をめぐり、日本国内では「核共有」や憲法9条見直しの議論が出ています。「侵略されたらどうするのか」という問いかけの前ではたじろぎもしますが、去る大戦で本土決戦の前線となり、これからも前線になる可能性が高い沖縄に住む私たちは、やはり戦争につながる憲法の改定には反対していかなければと強く思います。
座標
憲法が国民の命を守ってきた
今こそ9条を護り活かそう
日々伝えられるロシア軍のウクライナ侵略、虐殺。どうしたら止めさせられるのか苦悩は尽きないが、答えを日本国憲法が教えている。「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにする」、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」と決意して、戦争放棄の9条を定めた。
明治維新から1945年敗戦まで77年の近代日本は戦争に次ぐ戦争の時代だった。戦後の77年は非戦の時代、ただの一人も国の戦争で命を奪われていない。憲法が国民の命を守ってきた、この事実は重い。
広島・長崎への原爆投下は戦争の行きつくところを教えている。原爆から人類を守る確かな道は、武器・核兵器を持たないこと、戦争をしないこと、9条を護り活かすことである。日本国憲法は、第二次世界大戦の直後に、自由と平等のもと人間らしく生きたい日本と世界市民の願いを実現するものとして生まれた。
制定から75年、憲法は苦難の道を歩いてきた。「日本の伝統無視、マッカーサーの押し付け、自主憲法制定」が叫ばれ、条文は変わっていないが実態は変わってきた。
変える役割を果たしたのは保守政権が進めた教育改革だった。自由な教育から命令に服従する教育、戦後教育から戦前教育への復活の企てであった。
4月21日、自民党の安全保障調査会は「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」に変えたうえで、敵のミサイル拠点などを叩く力を保有するよう政府に求める提言案をまとめた。安倍晋三元首相は「(敵基地攻撃を米国だけに委ねたら)『米国の若者だけが危険を冒さなければならないのか』ということに必ず直面する」、「(米軍の戦闘機が)10機行ったら(日本も)1機一緒に行けるぐらいでなければ同盟として機能しない」(2021年12月15日)と語った。攻撃で敵国の人命を奪い、反撃で日本人の命を差し出すというのである。国民を裏切り、非人道極まる言葉ではないか。国民は許さない。
人間の歴史は自由獲得の歩みであった。不断の努力によって日本国憲法を護り活かし、さらに発展させ、平和と命を守ること、それが私たち国民に課せられた責務である。
国際法に通じる憲法
 |
黒岩哲彦(全国空襲被害者連絡協議会運営委員長)
私たちは空襲訴訟で、原爆裁判の「原爆投下は国際慣習法違反」とした東京地裁1963年判決に深く学び、無差別爆撃は国際慣習法違反であるとの旗を掲げています。
国連憲章は戦争を違法化し、国際人道法はジュネーブ諸条約と追加議定書を中心に形式・内容ともに発展し①医療組織の保護、②過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器及び戦闘の方法の禁止、③無差別攻撃の禁止、④原子力発電所への攻撃の禁止を明記しています。
日本国憲法前文の「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」との決意は、国際法の精神と同じ方向です。
ウクライナに侵略し、無差別爆撃や虐殺など戦争犯罪の蛮行を行なっているロシアには、即時・無条件撤退と戦争犯罪の責任の明確化を強く求めます。日本政府には、国連総会で棄権した中国やインドなどに侵略中止の立場に立つよう説得するなど外交的役割を果たすことを求めます。
〈アンケート〉核兵器のない、9条の活きる世界を(2022年3月実施)
全国から寄せられた回答から(被爆地・年齢・居住地)
問1 核兵器禁止条約に日本政府は反対しその理由を、日本はアメリカの「核の傘」に守ってもらっているからだと言い、岸田首相は、核兵器禁止条約は核廃絶の「出口」であり被爆者と思いは同じ、と言っています。こうした政府の姿勢をどう思いますか?
◆「核兵器禁止条約は核廃絶の出口」とは意味不明。「“核の傘”からの出口」ならいいけれど。「被爆者と思いは同じ」と言うのなら、アメリカの「核の傘」から出て、核兵器禁止条約を即刻批准すること。それ以外に戦争被爆国日本の進むべき道はない。
(長崎・90歳・東京)
◆被爆者の思いを本当に聞きましたか?と問い返したい。少なくとも被爆者だった亡父の思いとは異なっています。
(被爆二世・55歳・東京)
◆ロシアに核兵器という後ろ盾が無かったら今回のような事態にはならなかったでしょう。「核兵器」があるから戦争が起るのです。今こそ、「核の傘」の安全妄想をやめ核廃絶へと転換すべきです。核兵器禁止条約発効は核廃絶の出口ではなく入口です。
(広島・81歳・長野)
◆プーチン大統領の核兵器使用をほのめかす発言に恐怖を感じましたが、もっと怖いと思ったのはこの事態に乗じて「核共有」などと言い出す国会議員が日本にいることです。被爆者の思いは、「二度と核は使わない、使わせない」です。核は戦争の抑止力にはならないと思います。今こそ核共有ではなく、核禁止を議論して欲しいです。
(被爆二世・67歳・岐阜)
問2① 1946年8月27日、憲法制定議会で幣原喜重郎国務大臣は「第九条は戦争の放棄を宣言し、わが国が全世界中最も徹底的な平和運動の先頭に立って指導的地位を占むることを示すものであります。…文明と戦争とは両立し得ないものであります。文明が速やかに戦争を全滅しなければ、戦争がまず文明を全滅することでありましょう」と答弁し、原爆出現後の戦争放棄(9条)の意義を述べました。あなたはこのことを知っていましたか? これについてどう思いますか?
◆幣原喜重郎氏の発言は正しいと思います。こういう敗戦直後の大臣の発言を現在の大臣諸氏は発言できるでしょうか。現実に「先頭に立って指導的地位」を占めたとは思えませんが。
(広島・93歳・福島)
◆15年戦争の中で生まれ軍国少女として育ち、原爆で生き残ったことを恥じて死を考えていた頃、憲法が制定された。むつかしいことはわからなかったが、どんな事があっても戦争はしないと聞かされた日のあの喜びは忘れられない。
(広島・90歳・広島)
◆そのとおり。過去のあやまちから新しい方向性として戦争放棄、9条をつくったのであり、「武器も軍隊も持たない」という決断、英断、その大前提に立ってこそ、真の平和の道が開けます。
(長崎・82歳・長崎)
問2② 国民のいのちやくらしを核兵器や軍事力で守れると思いますか。戦争を起こしヒロシマ・ナガサキを体験した日本は、いま、国際社会でどのような役割を果たすべきだと思いますか。
◆核兵器で生命と平和は守れない。安倍元首相の「核共有発言」の無知ぶりに驚き、言葉がない。
(広島・92歳・神奈川)
◆核保有国は、核抑止により相手国をおどかそうとするもので、相手国は更にそれを上廻る兵器を開発しなければならなくなり、核兵器がこの世界に存在する限り 世界の恒久平和はない。
(広島・98歳・島根)
◆戦争はごく少数の政治家によって引き起こされますが、99%の被害者は無辜の国民です。しかし民主主義国家では、戦争を引き起こす政治家を選ぶのは国民であり、政治への関心を高めて、正しく評価できる能力を養う必要性を強く感じます。
(長崎・85歳・福岡)
民主主義の水脈
明治期の憲法草案
濱住治郎
1968年、東京都西多摩郡五日市町(現あきる野市)の深沢家土蔵から「日本帝国憲法」と題した憲法草案が発見されました。起草者は千葉卓三郎(1852―1883)で、五日市地方の自由民権運動の中心であった学芸懇談会のメンバーが起草を支えたといわれています。千葉は戊辰戦争に仙台藩士として出兵し敗残の後、10年間をかけて蘭学、医学、国学、儒学など学びキリスト教の教えも受けました。五日市には勧能学校(小学校)の教員として招かれ自由民権運動の理論的指導者として活躍しました。深沢家は豪農で、東京で出版され政治、法律に関する書籍がそろえられており、深沢権八は自由民権運動の若きリーダーでした。
千葉の憲法草案は203条からなり国民の権利の項目に多くがさかれていました。起草後、1881年に高知を訪れている形跡があり、同じ時期に高知の植木枝盛(1857―1892)の「日本国国憲案」が起草されています。お互いの憲法草案に影響を与えたと考えられています。植木は自由権利に35か条をさき、三権分立を採用、女子にも参政権をあたえ地方自治を最大限に確保しており、現存するもので最も民主主義的な内容を持つものでした。
自由民権運動が盛り上がった1881(明治14)年に「国会開設の詔」がだされ、1889(明治22)年に「大日本帝国憲法」が欽定憲法として公布されましたが、民権派の要求するものとは違うものでした。
植木の草案は鈴木安蔵(1904―1983)によって1936年に発見されました。敗戦後、鈴木は「憲法研究会」に参画し「憲法草案要綱」を起草、GHQ草案を起草する際の参考とされました。
これらの憲法草案に共通する「主権在民」の精神は、日本国憲法に受け継がれています。
参考=ドキュメンタリー映画「太陽と月と」(監督・福原進)、「東京の憲法草案」(町田市立自由民権資料館)、「各種民間憲法改正草案集」(衆議院調査課)、「五日市憲法」(新井勝紘・岩波新書)
復帰50年
沖縄の被爆者の思いを受けとって
 |
|
沖縄で開いた沖縄の被爆者と 日本被団協の交流会(2016年) |
大山広美(沖縄県原爆被爆者協議会事務局)
今年の5月15日で沖縄は日本に復帰して50年目になります。
被爆後広島・長崎から故郷の沖縄に戻った被爆者は、焼け野原になった故郷に愕然としたと語っています。
1964年に沖縄県原子爆弾被害者連盟(69年に沖縄県原爆被爆者協議会と改称)が結成されました。57年制定の「原爆医療法」が沖縄在住被爆者に不適用なのは国民差別と法の下での平等性を欠き違憲であるとして、65年に国に対して違憲訴訟を提訴しました。この訴訟は、72年の日本復帰によって沖縄の被爆者にも法が適用されたため終了しましたが、その後も沖縄独自の問題で運動を続けてきたことが、現在の当協議会の存続に繋がっています。
私が入職した2001年の沖縄在住被爆者は314人、21年3月末には99人となりました。沖縄の被爆者健診は期日指定で地域の県立病院で現在も行なわれています。10年ほど前までは大勢の方が受診していました。その当時の健診待合室は、お互いの被爆地を聞き合い、つらい被爆体験を共有しながら、まるで同窓会のような明るい雰囲気でした。ただ、被爆による差別への恐れ、また沖縄戦に不在であったことのうしろめたさ、自分たちには法律があって援護施策を受けられることで沖縄戦被害者に対しての申し訳なさなどが被爆体験を語りづらくしているのではないかと、その会話の中で痛感しました。
私はこの21年間、被爆者の皆さんから激励や感謝の言葉をいただきながらたくさんのことを学んできました。これから先の活動には不安もつのりますが、できる限り寄り添っていきたいと思っています。
今、この原稿を書いている上空をオスプレイが音をたてて飛んでいきました。
 |
東友会と「おりづるの子」が学習会
東友会と東京被爆二世の会(おりづるの子)が共催で4月3日、「被爆二世の実態と願いは~日本被団協全国被爆二世実態調査から」をテーマに学習会を開催しました。
講師は、この調査の集計・分析を担った八木良広昭和女子大学助教(写真)。東京の682人の回答と全国の3417人の回答を比較した資料をもとに説明しました。「二世であることを意識する=全国78・8%、東京84%」、「二世としての不安・悩み=全国60・3%、東京60・8%」などをあげ、全国と東京の被爆二世の意識がほぼ同じであると述べました。
学習会には被爆者14人、被爆二世17人のほか三世、家族、支援者など合わせて40人が参加。「おりづるの子」の青木克明副会長(日本被団協二世委員)がまとめの挨拶で「全国と東京の被爆二世の意識など比較していただき良く理解できた。被爆者と二世の意見交換会はとても有意義だと思う」と述べました。
(濱住治郎)
核兵器禁止条約への日本の参加求め行動
広島被爆者7団体
 |
広島県被団協(箕牧智之理事長)など広島被爆者7団体は3月22日、広島市の平和記念公園で、日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名活動をしました。ロシアのウクライナ侵略と核兵器による威嚇に抗議し、条約の必要性がますます高まったと訴えました。
条約の運用を協議する第1回締約国会議(6月、ウイーン)を前に、被爆者たち12人が参加。初の被爆地選出の岸田首相に対し、せめて会議へのオブザーバー参加を、首相在任中に条約の批准を、核軍縮―核廃絶のリーダーシップを、と次々に協力を呼びかけました。若者や親子連れが足を止め87筆が集まりました。
7団体は条約発効後の昨年1月から署名活動を始め、11月末までに集めた約53万筆(全国で約65万筆)が日本被団協を通じて外務省へ提出されました。その後の署名は、締約国会議前に岸田首相宛に提出します。
(田中聰司)
シンポジウム「被爆者運動史料とその活用」
継承する会
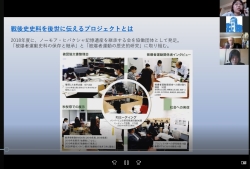 |
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は3月19日、設立10周年企画Ⅱとしてオンラインシンポジウム「被爆者運動史料、その意義と活用」を開催しました。昭和女子大戦後史プロジェクト、日本被団協との共催。
開会にあたって中澤代表理事が「10年間の会の歩みは必ずしも順調ではなかったが、新たに呼応してくれた孫のような若い世代によるプロジェクトの展開を心強く思う」とあいさつ。昭和女子大学の4年間の研究をふまえたシンポジウムは、プロジェクトメンバーによる密度の濃い報告と、50人余の参加者による熱のこもった議論を通じて、被爆者運動史料を残し、学ぶ意義が浮き彫りにされました。
詳細は継承する会ホームページで紹介しています。10周年企画Ⅲは5月21日に開催予定です。
相談のまど
介護度「要支援2」の判定を受けました
訪問介護やデイサービスを利用できますか
【問】介護度が「要支援2」になりました。ヘルパーさんの訪問や、デイサービスを利用できますか。その場合の費用負担はどうなりますか。
* * *
【答】これまで「要支援1」「要支援2」だった介護予防については2017年から3年間かけて介護保険から分離する形で各自治体が責任を持つ「総合事業」になりました。これはボランテイアの力を借りながら地域住民の互助・共助の仕組みを作り、「要支援」や特定高齢者(まだ元気な高齢者)の支援に取り組んでもらうということのようです。地域の元気な高齢者などに自治会単位の交流サロンの場や声掛け・家事援助の協力を得ようということです。
「要支援」の訪問介護と通所介護は「従来型」「訪問型サービスA」「訪問型サービスB(住民主体によるサービス)」「通所型A」などに分けられています。総合事業の単価は自治体ごとに算定をして良いので、介護保険サービスの単価に比べて低く設定している自治体が多く、そのため要支援の利用者を引き受ける事業所が減ったと聞いています。通所介護を引き受けた事業所も、送迎しない、入浴はなし、半日のみなど、利用者や家族にとって負担が大きくなっているようです。また、コロナ感染拡大という中で事業の中止あるいは事業所の閉鎖などの事態も起きています。
費用負担は、被爆者施策では従来型については助成があります。非課税世帯で「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の手続きをして交付されていれば、従来型サービスの場合は使えます。利用者側からすると受けているサービスが「従来型」なのか、その他のサービスなのか判別しにくいと思いますので、必ず確かめてください。
被団協へのお手紙から
胸しめつけられる
東京 澤田一瑩
お世話になっております。私ども被爆者の各種相談には敏速・丁寧にご判断とご指導を頂きましてありがたく感謝しております。
テレビのスイッチを入れると、ロシアの蛮行によるウクライナの悲惨な状況が放映され、広島の被爆時と重なり胸をしめつけられる思いです。少しでも早い終息を祈るばかりです。
日本被団協活動維持募金に微力ながら協力させて頂きます。
核兵器禁止の声を
静岡 磯部典子
ウクライナへ核兵器が使われることがないようにと、祈るばかりです。核兵器被害の実相をロシア、ウクライナに広めて両国からも核兵器禁止の声が広がることを願っています。
今回の戦争を通じて、核武装の危険がより一般化したと思います。それなのに「核共有」などありえない言葉が出現してしまう日本の政治家に、怒りでいっぱいです。
核兵器の被害国が加害国になっていいはずがありません。被爆者だからこそ説得力がある―被爆者をふたたびつくらせない決意をみんなでたかめあっていきましょう。

