「被団協」新聞2018年12月号(479号)
2018年12月号 主な内容
介護保険サービスと被爆者の介護手当を活用しましょう
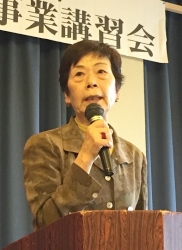 |
| 講習会で話す原玲子相談員 |
被爆者の平均年齢は82歳をこえました。高齢になっても核兵器廃絶と原爆被害への国家補償を求める声はいささかも衰えていません。昨年7月、国連で核兵器禁止条約が採択され、議会への請願や「ヒバクシャ国際署名」に取り組んでいます。一方で、病気や足腰が弱って介護を受けることも増えています。介護保険サービスと被爆者の介護手当の活用についてお話しします。(日本被団協原爆被爆者中央相談所 原玲子)
【介護保険の利用】
被爆者が介護保険サービスを利用するとき、医療と同じように被爆者健康手帳が使えるかどうかが気になるところです。
介護保険のサービスには、在宅で利用するサービスと施設入所があり、それぞれに利用料の自己負担があります。被爆者援護との関係では医療系サービスと福祉系サービスで自己負担の仕方が分かれます。
医療系サービスに関しては、利用料は被爆者健康手帳を提示することで自己負担はありません。
福祉系サービスでは、訪問介護以外は自己負担がありませんが、いくつかの県はまだ立て替え払いになっており、窓口負担をしなくてもいいように交渉中です。また訪問介護も条件を満たせば自己負担なしになります。
医療系サービスと、自己負担なしの福祉系サービスは以下のとおり。
 |
|
デイサービスセンターに展示された利用者の作品 (写真提供=東京さくら福祉会) |
① 訪問看護
② 訪問リハビリ
③ 通所リハビリ
④ 短期入所療養介護(ショートステイ)
⑤ 居宅療養管理指導(訪問診療・訪問薬局・訪問栄養管理指導)
⑥ 介護老人保健施設
⑦ 介護療養型医療施設
⑧ 介護医療院
★福祉系サービス
① 通所介護(デイサービス)
② 小規模多機能型居宅介護
③ 看護小規模多機能型居宅介護
④ 定期巡回・随時訪問看護
⑤ 単期入所生活介護(ショートステイ)
⑥ 訪問介護で、住民税非課税世帯の場合
ただし、食事代や雑費、ショートステイや施設に入所した場合の居住費などは自己負担となります。
【『問答集』の活用を】
介護保険を利用する被爆者の状態や希望によって、ケアマネジャーは在宅でのサービスを組み合わせます。中央相談所が発行した『被爆者相談のための問答集(介護編)』を読んでおくと、ご自分の希望などをはっきり表示できるでしょう。
福祉系サービスの一つであるデイサービスは「保育所みたいで嫌だ」という声を聞くこともありますが、高齢になり社会的な交わりの場が少なくなる人にとっては社会的交流の場になります。朝の送り時に嫌な顔をしていても行けば楽しく過ごせます。
また入浴介助も受けられるので介護負担軽減にもつながります。
【訪問介護】
訪問介護、いわゆるヘルパーによる在宅でのサービスは、住民税が非課税の場合、手続きをすれば自己負担がなくなります。「訪問介護被爆者利用助成認定受給資格者証」の交付を受けることになります。
非課税世帯でなくても訪問介護は必要です。その場合には被爆者援護による介護手当を活用しましょう。介護手当には人に頼んで介護を手伝ってもらう場合と、家族が介護する「家族介護手当」があります。最初に述べましたように被爆者の平均年齢は82歳を超えています。厚生労働省が実施した被爆者の実態調査結果でも「何らかの介助が必要な人」が半数近くいました。これからも核兵器廃絶や国家補償を求める運動を強めていくには介護保険サービスや介護手当を積極的に活用していくことが大事です。
【主治医に伝えて】
介護手当を受けられる「障害」には、中等度と重度の区分があります。診断書は障害の程度を示した「別表2」と「別表3」を参考に、主治医が作成します。別表の「身体の機能障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの」という項目に注目して、主治医に家庭での生活の状態などをしっかり伝え、手当診断書の作成をお願いしてみてください。
【認知症と介護手当】
認知症の場合も介護手当の対象になります。子ども(息子や娘)や、その配偶者などが通ってきて介護している場合も受給できます。家族介護手当は重度を対象としていますが、しっかりと主治医に本人の家庭生活や介助の状況を伝えておくことがやはり大切です。
介護が必要になってくると、誰しも言葉にはださないけれど介助者に対し肩身の狭い思いをしながら生活しています。介護手当を受給してわずかでもお礼をすることで、お互いの気持ちが楽になると思います。
【被爆体験を語り】
会の活動に参加できなくなったからと悲観しないで、ベッドの上からでも、デイサービスの場でも被爆体験を語り、「ヒバクシャ国際署名」を訴える事にも取り組んでみましょう。
被爆者としての役割は、どこにいても果たせるはずです。
ご活用ください
被爆者相談の問答集 No.30<改訂版>、No.31<介護編>
日本被団協原爆被爆者中央相談所が6月に発行した、相談ガイドブック№31『被爆者相談のための問答集―介護編』は好評を得て増刷を重ねています。この「介護編」で扱っていない現行法一般の被爆者施策活用について解説した、相談ガイドブック№30『被爆者相談のための問答集』〈改訂版〉を、9月に発行しました。改訂にあたって、一部古くなった内容などを見直し、「介護編」と重複する部分は省きました。2冊合わせて活用ください。
頒価はどちらも送料別で1部400円、50部以上の場合1部300円です。日本被団協事務局までお申込みください。
<中央相談所講習会>近畿ブロック ― 有意義な2日間
 |
| 講習会・近畿ブロック |
近畿ブロック相談事業講習会が11月9日~10日兵庫県神戸市内で開かれ、2日間で延べ38人が受講しました。
初日は日本被団協の藤森俊希事務局次長が核兵器禁止条約をテーマに、2日目は中央相談所の原玲子相談員が介護保険・介護手当をテーマに、それぞれ講演しました。
藤森さんは、禁止条約の前文と各条文の特徴、条約を生みだした「ふたたび被爆者をつくるな」の運動の歩み、条約発効への展望を詳しく解説。
原さんは『被爆者相談のための問答集~介護編~』にも触れながら、介護保険制度と被爆者介護手当の活用について、実際の事例に即して解説。
講演を聴くだけではなく、その内容に関わる質疑や、各会の経験交換も行ない、有意義な2日間となりました。
(副島圀義)
<中央相談所講習会>東海北陸ブロック ― 7県から多数の参加
 |
| 講習会・東海北陸ブロック |
11月4日~5日、石川県山代温泉で開催されました。ブロック7県から被爆者ら73人、石川の支援者もかけつけて100人近くが参加しました。
石川の西本会長から岩佐幹三顧問に、被団協結成のために手弁当で東奔西走、県友の会立ち上げにも大奮闘してくださったことへのお礼と90歳のお祝いの記念品を贈呈しました。
岩佐顧問は「日本被団協運動の歴史」と題した講演で、自らの被爆体験が運動の原点であると語り、今取り組んでいるヒバクシャ国際署名について「あなたたちはこんなひどい目に遭っていいんですか、人間の命の問題ですよと訴えていかなければならない」と熱く語りました。
日本被団協事務局次長の藤森俊希さんは、核兵器禁止条約採択の背景と意義、これからの運動について話しました。
懇親会では地元フォークグループ「でぇげっさぁ」の皆さんが演奏。去年亡くなった「谷口稜嘩さん」の歌、「平和の子ら」(石川の原爆碑「平和の子らの像」の歌)などの歌で盛り上げてくださいました。
2日目は中央相談所相談員原玲子さんが介護の問題を中心に話し、一人ぼっちにならず何でも話せる人と場所を作りましょうと呼びかけました。木戸季市事務局長の日本被団協運動の話の後、二世交流会の報告、各県活動報告をして終了。
次回は愛知県蒲郡での開催となります。
(西本多美子)
「都民のつどい」で学習・交流 ヒバクシャ国際署名をすすめる東京連絡会

10月30日、ヒバクシャ国際署名をすすめる東京連絡会が主催する「都民のつどい」が東京都生協連会館で開かれました。被爆者や都民70人が参加しました。東京連絡会には東友会や東京原水協、東京都生協連などが参加しています。
開会にあたり、東友会の家島昌志執行理事が、10月までに57万人の署名を集めた東京連絡会の活動にふれて挨拶。オープニングは、映画監督の有原誠治さんが、東京連絡会の2年間の活動を映像で紹介し、10月初旬に国連第一委員会の議長に830万人分の署名目録を提出した様子などを、実際訪米した東友会の濱住治郎執行理事(日本被団協事務局次長)が報告しました。
その後、内藤雅義弁護士の講演を聞いて、核兵器禁止条約の内容と最近の国際情勢、日本政府の態度について学び、生協連や東都生協と東友会、世田谷・練馬・青梅の地域連絡会が活動報告。アピール採択の後、東京のうたごえ協議会のメンバのリードのもと、「青い空は」などを参加者全員で合唱し大いに盛り上がりました。(家島昌志)
第11回署名行動 千葉県署名連絡会
12月には「カフェ」開催

千葉県「ヒバクシャ国際署名」推進連絡会は、11月17日午後1時半から1時間、JR津田沼駅北口で第11回統一署名行動を行ないました。空模様が心配されましたが、素晴らしい日よりとなり、多くの人が行き交う中、10団体30人(うち被爆者11人)が参加しました。
各団体がリレートークで訴え、うたごえのリードで「青い空は」を歌いながら署名を呼びかけました。駆け寄って署名する人、署名しながら「私も長崎なの」としばらく話していく人、高校生らしいお子さんがお母さんを促し署名する姿などがあり、署名90筆と募金箱に1800円が寄せられました。
12月1日に「千葉平和のつどい2018~ヒバクシャと出会うカフェ」の開催を予定しており、そのチラシも配りながらの行動でした。
(千葉県連絡会)
ヒバクシャ国際署名 日本キリスト教団が賛同
2年に一度開催の日本キリスト教団総会の中日10月24日、日本被団協の田中熙巳代表委員と和田征子事務局次長が信徒交流会で、国際署名への賛同、協力のアピールを行ないました。同教団は全国のプロテスタント教会、伝道所1700が属する組織です。全国16教区の代表500人に、署名用紙と日本被団協の資料を配布しました。教団総幹事、教団議長から、署名が寄せられました。
全国空襲連第6回総会 ― 空襲被害者救済立法の早期実現を

全国空襲被害者連絡協議会の第6回総会が11月3日に都内・足立区北千住で開催され、約50人が参加しました。
黙祷に続き開会の挨拶で中山武敏共同代表は、「援護法実現は、世論の共感と支援に関わっています。意見の違いを乗り越えて運動を発展させ、空襲被害の民間人の救済立法を実現していきましょう」と述べ、早乙女勝元共同代表は、「どんなことがあっても決して諦めず、決して黙らず運動を続けていけば、状況の変化が起こり得る」と話しました。安野輝子運営委員長は、「73年間放置されてきた戦争被害への謝罪と補償について、空襲被害者の怒りと悲しみを国会に思いきりぶつけよう」とメッセージを寄せました。
日本被団協から濱住治郎事務局次長が出席し、核兵器廃絶と国の償いの実現にむけ連帯を呼びかけました。
続いて行なわれた活動報告では、昨年4月に超党派空襲議連で救済法案が了承され、その後国会への法案提出を訴えていることが報告されました。生存する身体障害者に50万円支給で進められているが「心理的障害を受けて精神上の障害がある人」も加えることが検討されていることや、「空襲で孤児になった人への救済」も課題となっている中で、政府与党への働きかけを強めていくことが強調されました。
沖縄戦・南洋戦・フィリピン戦の訴訟報告も
瑞慶山茂弁護士から、沖縄戦国賠訴訟、南洋戦・フィリピン戦国賠訴訟について報告がありました。最高裁判所第三小法廷は9月11日、沖縄戦国賠訴訟の上告棄却を決定。また、南洋戦・フィリピン戦で、国に謝罪と損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論が11月1日、福岡高裁であり、原告6人が家族を失った悲惨な戦争体験を証言しました。次回12月18日で結審されます。
なお、新人事が発表され、共同代表に宇都宮健児さん(弁護士)、吉田由美子さん(空襲被害者)が加わり、運営委員長に黒岩哲彦さん、事務局長は高橋俊敬さんです。
結成60周年記念集会開く 東友会(東京都原爆被害者協議会)
記念誌も刊行
 |
 |
| 東友会結成60周年記念講演会(左)と式典(右) | |
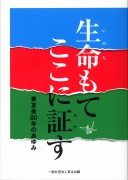
東友会は、今年11月16日に結成60周年を迎えました。11月18日に東京・千代田区のKKRホテルで記念集会を開き、被爆者と支援者149人が参加しました。
記念講演は国際反核法律家協会の山田寿則氏。山田氏は克明な資料と映像を使って、核兵器の現状、核兵器廃絶のために被爆者が果たしてきた役割、核兵器禁止条約の内容とこれからの運動についてわかりやすく講演。多くの被爆者から「励まされた」という声が届きました。
記念式典では、東友会の60年を紹介するスライドが上映され、東京都と広島・長崎両市のあいさつに続き、東友会を支えてきた7団体と協議会理事として10年以上活躍した93歳から72歳の被爆者26人などに感謝状が贈呈されました。スライドを見た医療関係者から「改めて被爆者運動の奥深さと医療者である私たちの役割を痛感した」との感想が届きました。
祝賀会の開会は「ご一緒に平和を願って」のタイトルで東都生協の松林潤子さんの手遊びや合唱で参加者和気あいあい。日本被団協、近隣の県被団協をはじめ支援団体の人びとが次々に挨拶しました。なかでも黒い雨の研究で著名な気象学者の御年95歳の増田善信氏のかくしゃくとしたスピーチには、一堂から喚声が上がりました。
この日東友会は、東京で生きた被爆者の記録を掲載した記念誌『生命もてここに証す』(A5版291ページ)を刊行、参加者などに頒布しました。(村田未知子)
高松高裁が原発運転容認 愛媛・伊方原発3号機

愛媛県の住民が伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審において、高松高裁は11月15日、住民の訴えを棄却する決定を下しました。原発推進の国策に追随するものと受け止めざるを得ません。
決定は、住民の避難計画(各自治体が作成)に実効性がないことを認めながら「その一事をもって(中略)、周辺住民等に対して、違法な侵害行為の恐れがあるということは出来ない」と述べています。要するに、住民の命の危険は無視する、というのです。
また決定は、原発事故が巨大で取り返しのつかない被害を長期間にわたって生み出すため、一般の科学技術と質的に異なることを認めて、「原子力発電を一切利用しない選択も十分あり得るものと思われる」と述べつつも、「(それは)政策論・立法論であって司法判断の範疇を超える」として、国民の命と安全を守るべき職責を放棄した、司法の自殺行為とも言うべきものでした。
11月20日、弁護団と伊方原発をとめる会は、法律判断だけの最高裁への特別抗告をせず、松山地方裁判所の本訴(仮処分申請で中断)を再開させ、伊方原発の危険な実態についての事実審理を重ねて勝訴を目指すことを表明しました。
(松浦秀人)
第11回被爆者運動に学び合う学習懇談会 ― 現行法制定後の熱い議論
映像と資料でふり返る
 |
 |
| (左)映像には故・伊藤サカヱさん(当時代表委員)も (右)話し合う参加者 | |
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は日本被団協と共催で10月27日、11回目の「被爆者運動に学び合う学習懇談会」を開きました。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の制定から24年。この法律は被爆者運動が求めてきた援護法なのか。法制定直後の緊急全国代表者会議(1994年12月23日)における議論を、濱谷正晴さん(一橋大学名誉教授)制作の映像と資料で振り返りました。
緊急代表者会議の議論の中心は、国家補償をめぐるものでした。「この法律で国家補償を認めなかったのは国が戦争責任を否定するから」「この法律は、基本懇の受忍論を再確認したもの」「国がした戦争の責任を、なぜ私たちがとらねばならないのか」と怒りの声が渦巻きました。「援護法という言葉が独り歩きしている」と、地方からの悩みも出されました。
「できた制度は国民の支持と世論に押された矛盾の反映」「国家補償の実現は簡単ではない」が「あの被害を許すわけにはいかない」「実現するには、他の戦争被害者やさらに多くの国民と結びつけるよう、工夫して運動する必要がある」と、今後への積極的な意見も出されていました。
学習懇談会の24人の参加者は、当時を知る人も初めて知った人も、本質に迫る熱心な討議が行なわれていたことに感動。こうした議論がその後の運動でなぜ深められなかったのか、各地で寄せられていた被爆者の声を掘り起こしながら、もう一度総括してみようなど、熱心に話し合いました。
薬の容器代など保険外部分は被爆者も自己負担になります
【問】薬局で目薬を受け取るときに容器代が請求されました。いったん支払ったのですが、被爆者健康手帳を提示したのに、なぜ請求されるのか納得できません。
* * *
【答】被爆者健康手帳での医療に関しては「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第14条で「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による」とされています。ですから医療機関では、被爆者の診療にあたっても健康保険の診療方針や診療報酬に基づいて治療をしています。こうした診療方針や診療報酬については、厚生労働省が通達として出しているものです。
入院時の差額ベッド料(4人部屋でも請求されることがあります)や「保険外サービスの自己負担の導入」も1984年の「健康保険法改正」とあわせて、当時の厚生省が認めたものです。国民には十分な説明をしないまま、保険診療から外された自費部分が広がってきました。被爆者は医療機関で受診した時、被爆者健康手帳と医療保険証を提示すれば無料と思っていたのが、気がつかないうちに次々と自己負担が導入され、その範囲が広がってきたのです。
ですから、点眼薬や塗り薬など外用薬の容器代が請求されるとか、包帯などの治療材料も「薬局で買ってね」と言われるようになったのです。
被爆者も国民と共に命を守る運動に参加することが求められています。
投稿 「集団証言」の経験
愛媛 松浦秀人
被爆体験の語り部活動は、独り語りの場合30分から1時間の話を事前に組み立てることが結構難しいものです。でも、インタビュアーがいて質問すれば誰でも話し易いはずと、私たちは実践してきました。
愛媛では胎内被爆の私が単独で語り部活動を行なうこともありますが、二人組で行なう場合は体験者がご自身の身に起きた出来事を語るとともに、戦争や原爆の全体状況や放射線被害(後障害)のことなどを私が織り込みます。また、新居浜市では3~4人がかりでの証言も行なっています。
10月14日、今治市立図書館の平和講演会に中路義教さん(91歳)と私の二人が招かれ、丁寧なお礼状をいただきましたので、抜粋してご紹介します。
「気が付くと、おふたりの熱のこもった語りに夢中になり、1時間があっという間に感じるほどでした。原爆のむごさ、戦争の恐ろしさを改めて思い知らされました。以下は、受講していただいた方の感想です。『松浦さんが中路さんの体験をうまく引き出してわかりやすい話になっていた』 『恐ろしい戦争について再認識しました。忘れてはならない。声を出して戦争の恐ろしさを忘れてはならないことを呼びかける』… こうした感想をいただけると、平和講演会を続ける意義深さを感じることができ、当館の活動によって、ひとりでも多くの方に、戦争の悲惨さ、平和の大切さについて考える機会を持ってもらえたらと改めて感じました。これからも末永くお元気でご活躍されることをお祈りしています」。
