「被団協」新聞2018年5月号(472号)
2017年5月号 主な内容
憲法9条を厳守し戦争によらない国づくりを
「被爆者として言い残したいこと」
 |
|
衆院議員会館前でプラカードを 掲げて立った被爆者ら(4月19日) <写真=亀井正樹> |
 |
72年前の夏、広島と長崎に投下された原爆の惨劇は、想像を絶するものでした。
この惨状を体験し、あるいは目撃した被爆者は、その衝撃を脳裏から決して消し去ることができず、死を迎えるまでつづく苦しみを背負わされることになりました。
このことが「決してふたたび同じ苦しみを世界の人々に、人類の誰にも味わわせてはならない」という叫びになり、「核兵器を一発たりとも地球上に存在させてはならない」と、さまざまな行動へと被爆者を突き動かしてきました。
日本被団協とノーモア記憶遺産を継承する会が共同して、“被爆70年を生きて「被爆者として言い残したいこと」”と題する調査を行ない、昨年10月報告書を発表しました。見出しの一文は、調査報告の一節です。
現在の政権党、自民党が現行憲法の解体、修正をねらっています。昨年の憲法記念日5月3日、安倍首相が、憲法9条について条項はそのままにし、第3項として自衛隊を明記すると表明しました。それまでは、9条第2項にある「戦力不保持」を削除し、自衛隊を明記するとしていたことの突然の変更です。
「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」を明記する現行憲法のまま「自衛隊を明記する」とは、どういうことでしょうか。
憲法や法律について、国際的にも、国内的にも後で追加された条項は、前項を上回ることになっています。
現行憲法の「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」を残しても、自衛隊を追加・明記することによって、従来の9条を破壊することが可能になります。
「被爆者として言い残したいこと」調査では、「再び被爆者をつくらないために、今、日本政府に求めたいことは何ですか」との問いに、回答者数706人のうち546人(77・3%)が「9条厳守」をあげ最多でした。つづいて「核兵器廃絶」(72・2%)、「実相普及」(67・5%)でした(別表参照)。
◎言い残したいこと
憲法9条厳守を政府に求めた被爆者の声が多数寄せられています。
「被爆者である私は憲法とりわけ9条があるから、家族を失っても我慢して戦後を生きてまいりました。もう二度とない戦争の恐怖を体験しなくてよいからです。しかし今、戦争をする国づくりを進めています。安倍内閣を絶対に認めたくありません。国会議員は憲法を順守せよ!」(広島 直爆 3・3㎞ 女 被爆時17歳)
「今の政治家は、戦争の恐ろしさや、貧乏の苦しみなど、味わったことのない人たちだから、人の心の痛みや、苦しみなどが分からないのではないでしょうか? 海外の方々が、核廃絶に賛同してくださったのに、日本政府は、今にも、戦争がおきても、おかしくない状態を、つくりつつあります。国民は、不安でいっぱいです。早く何とか、ならないものですか…」(長崎 直爆 3・2㎞ 女 被爆時10歳)
坪井代表委員が広島市名誉市民に
 |
| (写真提供=広島市広報課) |
日本被団協の坪井直代表委員に4月5日、広島市名誉市民の称号が贈られました(写真)。長年にわたる被爆体験の証言活動と、国内外での核兵器廃絶に向けた活動が称えられました。
贈呈式で坪井代表委員は「名前の通り、素直に燃えて燃えて燃え尽きるまで頑張ります」と話しました。
【福島】ステップアップ集会

ヒバクシャ国際署名推進連絡会
ヒバクシャ国際署名推進福島県連絡会は、3月31日福島市の福島テルサで「ステップアップ集会」を開き、県内各地から40人が参加しました。福島県原爆被害者協議会の木幡吉輝さんの開会あいさつに続いて、日本被団協の藤森俊希事務局次長が、自らの被爆体験の話や戦後GHQによって7年間原爆について報道規制されたこと、原水爆禁止運動、日本被団協結成によって非人道的な被爆の実相を世界に訴えてきたこと、国連で核兵器禁止条約が採択された時の様子、ノーベル平和賞授賞式でのエピソードなど講演。映像をまじえての臨場感あふれるお話しでした。
推進連絡会事務局が県内各地で署名推進の行動を呼びかけ、日本被団協の田中熙巳代表委員のメッセージ動画、原爆をテーマにした演劇「あの夏の絵」(6月28日に福島市で上演)のプロモーション映像が紹介されました。
地域での「署名推進連絡会」結成に取り組んでいる方から、集めた署名の取り扱いに関する質問や、県内の非核宣言自治体首長へ積極的に署名を進めようとの意見が出されるなど今後の活動について話し合いました。
(石堂祐子)
【三重】1周年記念集会
ヒバクシャ国際署名県民の会

4月8日、三重県津市でヒバクシャ国際署名をすすめる三重県民の会設立1周年を記念して講演会を開きました。県内各地から120人が参加しました。
合唱団の美しいコーラスに続き、三重県原爆被災者の会の山口詔利会長、県民の会よびかけ人の中村進一県議会元議長があいさつ。県議会での「核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書」採択という嬉しい報告がありました。この動きが全国に波及し、世論と政府を動かすことを望みます。コープみえの取り組み、地域で地道に署名を集めている伊勢市の経験報告もありました。
メインは「子どもたちの明るい未来へ 核兵器のない世界をわたしたちの力でつくりだそう」と題した藤森俊希日本被団協事務局次長の講演。被爆の実相と戦後史、条約の意義など、わかりやすいお話でした。母の涙の記憶、禁止条約採択やノーベル平和賞受賞に寄与した女性の大活躍の話は共感を呼びました。被爆の実相を世界に伝える活動と署名運動の広がりが禁止条約の採決に結びついたことに、あらためて意を強くしました。
最後に、三重県での運動の現況と今後のすすめ方について訴えました。署名運動から生まれた「一人から一人へ」の歌声で締めくくりました。
(三重県民の会)
【北海道】国際署名55万筆超える ステップアップ集会

4月21日、札幌市でヒバクシャ国際署名ステップアップ集会が開かれました。昨年9月に結成された幅広い共同の組織、国際署名を進める北海道民の会の主催です。
被団協の藤森俊希事務局次長は、核兵器禁止条約交渉会議やICANのノーベル平和賞授賞式などに立ち会った豊富な国際経験をおりまぜながら、「憲法9条を輝かせ核兵器のない世界を」と題し、核兵器禁止条約に至る世界の流れ、条約の意義などについて話しました。「歴史的な流れの中で条約の意義がよくわかった」「もっと聞きたかった」などの感想が寄せられています。
ついで道民の会が集約した署名数が3月末で55万筆を超えことが報告され、コープさっぽろ、平和運動フォーラム、新婦人札幌北支部、非核平和都市宣言の帯広市の推進実行委員から、それぞれ創意あふれる取り組みが報告されました。そして被爆二世の松田ひとえさんが、二世としての思いを語ってシャンソン「ヒロシマ」を歌い、会場の人々と核兵器廃絶への思いを共有しました。
集会には約130人が参加、2020年までに道民過半数の署名を集めようと確認し、街頭での署名行動に移りました。30分余りで121筆の署名が寄せられました。
(北明邦雄)
被爆地域拡大を長崎市に要請
長崎被爆地域拡大協議会

長崎被爆地域拡大協議会(峰松巳会長)は、2月19日「被爆地域拡大の早期実現を求める要請書」を長崎市に提出、長崎被災協の田中重光会長も同席しました(写真)。
田上富久市長は3月28日文書で回答。「日本政府に憲法九条堅持し、核兵器禁止条約加盟要請」について「日本政府に被爆国の責務を果たし、核抑止力に頼らない安全保障の確立、核兵器廃絶に向けた強力なリーダーシップを取るよう求めている」。被爆地域拡大については「被爆体験者は高齢化し、様々な病気に苦しんでいる状況は、十分認識しているが、国が求める科学的・合理的根拠を示すことは、非常に高いハードル。専門家の情報収集と情報交換を重ねていただき、科学的・合理的根拠への糸口を見出せるよう努力する」。「平成27年度から国に『被爆地域拡大』と併せて『被爆体験者支援事業の対象合併症の大幅な拡充』を要望した結果、昨年度から対象合併症に『認知症』が、今年度から『脳血管障害』が、平成30年度から『糖尿病の合併症』が追加。医療受給者証の毎年更新は平成30年から3年に1回に改正。県外居住者や胎児への見直しは引き続き国に強く要望する」と答えました。
(山本誠一)
院内集会 裁判の全面解決を
各党に要請

裁判の全面解決と原爆認定制度の抜本的改善を求める院内集会が4月18日、参議院議員会館で開催されました。
集団訴訟とノーモア・ヒバクシャ訴訟の原告、被爆者、弁護士など全国から130人が会場いっぱいに集まり、各党代表に要請しました。
今回は、日本被団協の「提言」による抜本改正を軸としつつも、裁判の判決にあわせた認定基準の改正を「当面の要求」として打ち出しました。積極認定に狭心症、甲状腺機能亢進症、脳梗塞なども加えるよう、また要医療性も幅広く認定するよう求めています。各党には被爆者の意見を聞く議員の会合開催などを要請しました。
自民、立民、民進、希望、公明、共産、社民の各党から国会議員15人が激励に訪れ「認定問題はいよいよ解決の時。被爆者と連帯して取り組んでいく」など話しました。
原告の一人で、高裁で勝利後に国が上告した、愛知の高井ツタエさんは「同じ場所で被爆した姉はがんで、私は慢性甲状腺炎。私だけが上告されたのはどうしてですか。毎日地獄のような日々です」と訴えました。
長崎の横山照子さん(日本被団協代表理事)は「松谷訴訟、集団訴訟を経ていま、地裁で9人がたたかっている。最近、法廷では異様な感じがするほど、原告の被爆者にいじわるな質問をする。認定拒否で国にいじめられ、法廷でまたいじめられる。絶対にやめさせるべき。一日も早く裁判を終わらせるため、超党派で頑張ってほしい」と訴えました。
「これすごく大事だ!」小学生も”訴え”に共感
「アースデイ東京」でヒバクシャ国際署名

4月21日と22日、代々木公園で開催されたアースデイ東京に、ヒバクシャ国際署名連絡会として参加し、2日間で132人分の署名を集めることができました。テントブース内で、署名した方々とじっくりとお話しできました。
スイス出身の夫婦は「私たちの故郷は核兵器廃絶へ舵をきった。被爆国日本がこの条約に入ることを期待している。頑張って!」と応援メッセージをくださいました。
小学5年生の男の子は訴え文を何分もかけて読んだ後に「これ本当に凄く大事だ。国連に届けるなんて凄い!」と署名してくれました。その30分後に今度はなんとおじいちゃん、おばあちゃんを連れて戻ってきました。「自分に今できることはこれだから」という彼の言葉に励まされました。
2日間で若い親子連れの方も多く署名してくださいました。「子を想う」気持ちを通して広島・長崎と現在の核問題をつなげてとらえる目線は、この問題を語る時に非常に重要だと再認識させられました。
初日に、メインステージ、トークステージと二度も登壇の機会を与えていただきました(写真)。夕方行なわれたパレードは、水陸両用バスに首都圏から5人の被爆者に乗っていただくことが出来ました。(林田光弘)
アメリカで「原爆と人間」展
デイトン国際平和ミュージアム(オハイオ州)
 |
| カルター館長 |
 |
| カツヤ博士 |
日本被団協の「原爆と人間」パネルが、「平和のための博物館国際ネットワーク」理事の安斎育郎、山根和代両氏の手を経て米国オハイオ州のデイトン国際平和ミュージアムに贈られ、2月から4月、展示されました。マイケル・カルター館長からの報告です。
*
展示の開会式はとても感動的でした。2月24日の夜7時から開始され、約50人が参加。私がバイオリン奏者とベース奏者と共に音楽を演奏し、展示の重要なメッセージのために、静かな雰囲気が生み出されました。
音楽の後、カート・ミヤザキ博士を紹介しました。日系アメリカ人市民連盟の理事でもあるミヤザキ氏は、第二次世界大戦下の日系アメリカ人について話しました。
基調講演者はロン・カツヤ博士でした。カツヤ氏は、以前デイトンの日系アメリカ人市民連盟代表で、アジア系アメリカ人協議会の会長です。力強い講演に参加者は深い思索をするようになり、カツヤ氏と多くの参加者は、イベント終了後も長い間話し合いました。
展示の公開日以降、何百人もの訪問者があります。展示を通して多くのことが討論され、現代における核兵器の危険性と現実について新たに知る機会となっています。
私たちはこの展示物を送ってくださった日本被団協と山根和代氏に大変感謝しています。
ミュージアムの活発な活動については、ウェブサイトをご覧ください。
www.daytonpeacemuseum.org (翻訳:山根和代)
60年代の被団協運動

被爆者運動に学び合う学習懇談会10
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は4月14日、第10回「被爆者運動に学び合う学習懇談会」を、東京・四ツ谷のプラザエフで行ないました(写真)。
継承する会が行なっている日本被団協の運動資料整理に、歴史家の立場から助言・指導をしている松田忍さん(昭和女子大学准教授)が、「被団協関係文書調査報告~『被団協連絡』を読む/『被団協速報』の誕生~」をテーマに問題提起しました。
現在収集・整理された2700点を超す日本被団協文書の中から、1957年から73年にかけて発行されていた『被団協連絡』に着目し、『日本被団協50年史』の同時代の記述とあわせて読み込んでの報告でした。特に60年代、原水禁運動の分裂を受け、日本被団協内部ではどのような議論がされたのか、『被団協連絡』で公表されている代表理事会「議事要録」から読み解きました。
参加者は、「当時、開かれた議論が活発にされていたことがわかった」「『核兵器廃絶』に関わることが”政治的”であると回避され、『国家補償』要求で結束し自立した運動を作り出していった」など、運動の歴史への理解を深めました。
松田さんは引き続き「被団協関係文書」の読み込みを続ける予定です。
相談のまど ショートステイ利用時の「食費」「居住費」の負担額
【問】夫が先月下旬からショートステイを利用しています。先日、請求書が届きました。「利用者負担額」という項目と「介護サービス費」という項目があって、さらに請求金額があります。どれを支払えばいいのかわかりません。
* * *
【答】利用料の請求明細書には介護サービス費と食費や雑費などの利用者負担とがあります。被爆者の場合、介護サービス費は、被爆者健康手帳により自己負担はありません。請求明細書に介護報酬単位が書かれていても支払いはありません。
「食費」と「居住費」について、何日分で合計いくらという金額だけを支払うことになります。その額と請求金額が同じになっていると思います。確かめてみてください。食費は1日1380円です。居住費は多床室やユニット型準個室、個室など種類により負担額が違います。どんな部屋に入所しているかで決まります。
食費や居住費は所得による軽減措置もありますが、貯蓄額が一人1千万円、夫婦では2千万円以上あると、軽減の対象にはなりません。
ドイツからのお便り 平和のたまご

ミュラー・柴 勵子
ロンドンで始まった反核兵器デモが「イースター平和行進」として定着し、今年で60年を迎えました。3月31日のデュッセルドルフのデモ・集会で見つけた、平和のたまごをおすそ分けいたします(写真)。
日本は初夏の陽気とか。こちらはまだ肌寒く、昨日のイースター聖日は小雪がちらついたところもありました。春の到来が待たれます。みなさまどうぞお元気で。
〈追伸〉罌粟(けし)の花がついた小皿は何回目かの私の誕生日に息子たちが、小遣いを出し合ってプレゼントしてくれたもの。まだ小遣いも少なかった次男は「小さいお皿なのにアレ高いんだ」とポロッともらしていました。
『日本被団協60年のあゆみ』発行
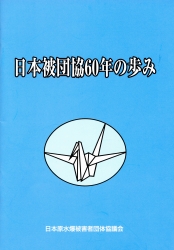
日本被団協は、小冊子『日本被団協60年の歩み』を発行しました。
2016年10月に行なった結成60周年記念式典で配布したものを、内容を見直し、昨年末までの出来事も追加して完成したものです。日本被団協の運動の歩みを、年代順に写真と文で構成。1ページごとに「日本被団協結成」「度重なる全国行脚と国会請願デモ」などのタイトルを入れ、巻末には略年表も掲載しました。運動を学習する、あるいは紹介するときの参考文献として、手軽に利用できる1冊です。
A5判、カラー、60ページ。頒価1冊400円(送料別)。申し込みは日本被団協事務局まで。
日本被団協のバッジ2種
 |
| ①つるバッジ |
 |
| ②60周年記念バッジ |
日本被団協は、シンボルマークのバッジ2種類を頒布しています。
①つるバッジ
楕円の長径が25ミリ。裏面に「No More HIBAKUSHA」の文字があり、透明ビニール袋に説明書(日文英文両面刷り)とともに封入。赤、黄、青、紺、緑の5色で1個300円+送料。
②結成60周年記念バッジ
楕円の長径が30ミリ。七宝焼きで、赤、紺、セルリアンブルーの3色です。裏面に「被団協60周年 NO MORE HIBAKUSHA」の文字があり、透明プラスチックケースに入って、1個500円+送料。
ご希望の種類、色、個数と送付先の住所、氏名、電話番号を明記して、郵送またはFAX(03―3431―2113)でお申し込みください。
