��c���V��
�u��c���v�V��2016�N�@7�����i450���j
2016�N7�����@��ȓ��e
�j����p��ց@�q�o�N�V�����ۏ����𐬌������悤
���{��c����61��������
����60�N�@�����ێ�������J�n

�@���{��c���͑�U�P����������U���P�T�A�P�U���A�����E�䒃�m���̃z�e���W�����N�ŊJ���܂����B�S���R�T�s���{�������P�O�O�l���o�ȁB�����U�O�N�̉^���̐��ʂ����ƂɁA����̕��j���c�_���A�����A�^�����j�A�\�Z�A�����l���A����c���̑��E���F���܂����B
�I�o�}�đ哝�̂̍L���K����߂�����
�@�T���Q�V���̃I�o�}�đ哝�̂̍L���K��ɂ��đ���c�́A�����̕đ哝�̂Ƃ��ď��߂Ă̍L���K��Ɍh�ӂ�\�������A�����͔픚�n�L���ɑ����������Ɩ₢�����܂����i�v�|�ʍ��j�B�c�_���o�Ċj�Ȃ����E��̓I�ȍs�����Ƃ�悤�������߂���e���܂ތ��c���̑����܂����B
�U�O�N�̉^���̐��ʂ̏�ɐV���ȓW�]���J����
�@�c�������ǒ��͊�Łu����Ȃ�^���̔��W���߂����A�l�ގj�I�ۑ�ɉ����鍑�ۏ����𐬌������悤�B�픚�҉^���𐄐i���Ă��������̔픚�҂̍����u���p�����v�Ƒi���܂����B
�@�^�����j�͎��̂R�̒����N�A�����ɋc�_���܂����B
�q�o�N�V�����ۏ����𐬌������悤
�@�u�q���V�}�E�i�K�T�L�̔픚�҂��i����j����p�⍑�ۏ����v�́A�^������l�ƒc�̂��͂����킹�i�߂鍑�ۓI�^���ł��B
�@���A�����̔����������j������֎~���p�₷��������߂����A�č��ȂNJj���퍑�Ƃ��̓������ł�����{�Ȃǂ��j����p����͎��������Ɣ����Ă��܂��B���ۏ����̓q�o�N�V���̌Ăт����Ƃ��č����O�Ŋ��}����Ă��܂��B�L���A������͂��ߑS���e�n�ŏ����^�����n�܂��Ă��邱�Ƃ�����܂����B�j����̂Ȃ����E���߂����A�^���̐����ɗ͂�s�������Ƃ��m�F���܂����B
���{��c�������ێ�����ɋ��͂��I
�@��c���̍�������@���}���Ă��܂��B���̂܂܂ł́A���j���������銈��������Ȃ��Ă��܂��B�������픚�҂́u������~���ƂƂ��ɐl�ނ̊�@���~�����v�Ɨ����オ��܂����B�͂�s�����O�i�����Ă��܂��������͂܂����ł��B��߂�킯�ɂ͂����܂���B����A�a�㉻�����������̌�����l����Ɨe�Ղł͂���܂��A�w�͂𐾂������܂����B
�@�V���Ɏ��g�ފ����ێ�����́A�T�N�Ԍp�����ĕ�W���܂��i�T�v�͂Q�ʁj�B
�����U�O�N�L�O����
�@�����U�O�N���L�O���鎟�̂W�̎��Ƃ���Ă���A�������܂����B
�@�@���E�ւ́u�A�s�[���v�A������Q�҂Ƃ̘A�тƌ𗬃c�A�[�B�j�ۗL����g�قւ̗v���C�j���i����j�E�L�O���T�i�����j�D�L�O�o�ŇE�f���̐���ƕ��y�F�픚�S�������G�L�O���ƕ��
�،��E�p���E���k������i�߁A�m�[���A�E�q�o�N�V���i�ׂɏ������A���@����芈������
�@����ł͂܂��A�m�[���A�E�q�o�N�V���i�ׂ̏����A�S���̔픚�҉^���Ɋւ��鎑���̐����Ǝ��W�A���k�����k���̕�[�A���@����芈�������ƂȂǂ��m�F���A����������I�o���܂����i����Q�ʁj�B
����c�i�v�|�j
���E�̑������_�ƂƂ��Ɋj����̔p���
�@�T���Q�V���A�I�o�}�đ哝�̂��L����K��܂����B�����́A�픚�n�L���ɂӂ��킵�����e�������ł��傤���B�A�����J�������𓊉����Đ������M��ɐs�����������S���ɂ��āA�u�玀���~���Ă��Đ��E����ς��܂����v�ƁA���R���ۂ̂悤�Ȃ��ƂŁA�A�����J�̐ӔC���������\���ł����B��т��āA�����u�������v�Ƃ��A�đ哝�̂Ƃ��Ă̐ӔC�͌��܂���ł����B�v���n�����Łu�j������g�p����������̊j�ۗL���Ƃ��āA�s�����铹�`�I�ȐӔC�������Ă���v�Ƃׂ̂��З�����ꂸ�A��̓I�ۑ�̒�N������܂���ł����B�A�����J�̓����ɑ���Ӎ߂̏Ƃ��Ă��A�j����p��ւ̐ӔC�ƍs������w�[�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗm�F���܂����B
�@���{��c�������U�O�N�̊����̐��ʂ܂��A��{�v���̎����ւ���Ȃ�^���̎��g�݂��c�_���܂����B���ې����́A�j����̔�l�����ɏœ_�����Ċj������֎~���p�₷����̒����Ɍ����傫���O�i���Ă��܂��B�j�ۗL���Ɠ������́A�j�}�~����ɌŎ����Ă��܂��B���{���܂߂����̐�������肷�鍑�̐��_�����قǏd�v�Ȏ��͂���܂���B���_�Ɖ^���������傫�����܂��傤�B
�@�u�q���V�}�E�i�K�T�L�̔픚�҂��i����j����p�⍑�ۏ����v�́A���X���d�v�ȉ^���Ɗm�F���A���E�I�K�͂̉^���ɔ��W�����錈�ӂ��ł߂܂����B�j����̔�l�����������Ŏ����픚�҂̏،��͈�w�d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���{�������N�������푈��[�����Ȃ��A���{�����@�́A��X���ŁA�푈�����E��͕s�ێ��E��팠�̔۔F���߂܂����B���@�ɔ������E�̊e�n�ɏo�����Đ푈����Ԑ��Â��肪�i��ł��܂��B���@�X���������@�ɂ��邱�Ƃ��m�F���܂����B
�@����A�a�㉻����e����c���y�ѓ��{��c���̑g�D�ƍ����̋������}����܂��B���{�I�ȕ�������ɑS�͂Ŏ��g�ނ��ƁA�u�������f���O�i���邱�Ƃ��m�F���܂����B
���{�A���}�ɗv���@���{��c�������s��
�@���{��c���͂U���P�V���S���̔픚�ҁA�픚�ق���W�O�l���Q���������s�����s�Ȃ��܂����B���t�{�A���J�ȁA�O���ȁA�o�Y�ȂƊe���}�ɑ��A�j����p��̐擪�ɗ����ƁA������Q�ւ̍��̏��������A�����p�~�Ȃǂ�v���B�n���c���ւ̗v���ɂ����g�݂܂����B
�m���t�{�n��b���[�����ەy�i�N�j��劯�ق����Ή��B������b�ɁA���{��c����\�ƒ��ډ���Ęb���������ƁA�����������ł���č��Ɣ픚�����{�����͂��Ċj����p���i�߂�悤�i���܂����B�y�i��劯�͑����ւ̓`�B����܂����B
 �o�Y�� |
 ���J�� |
 ���t�{ |
 �O���� |
 ���i�} |
 �����} |
 �Љ��} |
 ���{���Y�} |
�m���J�ȁn���V�m�@�픚�҉�����ق����Ή��B�����ǔF���픚���f�Ȃǂɂ��āA��̓I�ȗ�������ėv�����܂����B��N�s�Ȃ��Ȃ�������b�Ƃ̒�����c�̎��s�����߂܂������A�u���x�̉��P��O��Ƃ����`�ł̊J�Â͗e�ՂłȂ��v�Ɖ��܂����B
�m�O���ȁn�����g���R�k�s�g�U�Ȋw���R�c���ق����Ή��B�v�����ڂɂ��ẮA���̍��ۏ����݂ē���Əq�ׂ܂������A�ȓ��ł̌����W�J�Â��Ă���ƁA�u����͗ǂ����Ɓv�ƑO�����ȉ�����܂����B
�m�o�Y�ȁn�����G�l���M�[���d�̓K�X���ƕ��̋����Y���W���ق����Ή��B�G�l���M�[�̃o�����X���K�v�Ƃ��Č��������������ғ������闧����������܂����B
�m���}�n�����}�A���i�}�A���Y�}�A�Ж��}�̊e�}���v���ɉ����A���k���܂����B
�F�{�n�k�~������@�F�{�Ƒ啪�̌���c���ɑ���
�啪���炨��̎莆
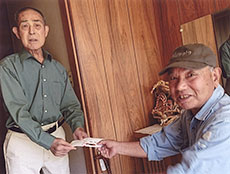
�啪�̔�Љ���i���j�Ɖi����i�E�j
�@�S���ɌĂт������F�{�n�k�ЊQ�~������́A�U���Q�V�����݁A���z�Q�S�T���~�]�ƂȂ�A�Q�Q�O���~���F�{�ɁA�Q�O���~��啪�ɑ������܂����i���F��͂Q�O�O���~�ƂQ�O���~�����ꂼ��ʓr�����j�B
�@�啪����c������̂��������Љ�܂��B
���@�@���@�@��
�@�`���������������āA��ϊ��ӂ��Ă���܂��B
�啪�ł͍K���ɂ��A�Ƃ̑S��A����Ƃ�������Q�͂���܂���ł����B
�@���z�@�n��ƕʕ{�̈ꕔ�ɁA�Ζʂ̐Ί_�����ꂽ�A�u���b�N�����|���A�O�ǂ̃^�C���ɂЂт��������A���������������A�Ƃ������Ƃ�����܂����B�e�˂Ɍ������Ƃ��Ĕz�点�Ă��������܂����i�ʐ^�j�B��Q�҈ꓯ��ϊ��ӂ��Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�i��E�i���O�j
���{��c�����x�������ւ̂����͂����肢�������܂�
�@���{��c���͑�U�P��������ŁA�V���ȕ���Ɏ��g�ނ��Ƃ����߂܂����B�u���{��c�������ێ�����v�Ɓu�����U�O���N�L�O���ƕ���v�ł��B
�@�u���{��c�������ێ�����v�́A���p�̊�@�ɕm���Ă����c�������ً̋}�ۑ�Ƃ��āA�T�N�Ԍp�����ĕ�W���܂��B�E�̐\�������e�s���{���픚�҂̉�܂��͓��{��c���܂ł����肭�������B�K�v�ȏ��ނ����߂ėX�����܂��B
�@�܂������U�O���N�L�O���Ƃ𐬌������邽�߂̓��ʕ�������{���܂��B�]���̔픚�҉^����������i����z�̂R������������s���{���픚�҂̉�ɊҌ��j�͌p�����Ď��{���܂��B���̂Q��ނɂ��ẮA�����̐U���p���������p���������B
�@��c���^�����x���邽�߁A����w�̕���̋��͂����肢�������܂��B
���Ԑl�r���̐��x�̖���
�����ɉ�����Q�w�K��
�@���{��c���͂U���P�U���̑���I����A�z�e���W�����N�����̊ԂŁu������Q�v�ɂ��Ă̊w�K����J���܂����B
�@��N���́A�S����P��Q�҂瑼�̐푈��Q�҂Ƃ̋����̐ςݏd�˂̏�ɁA�����U�O�N�L�O���ƂƂ��Ċ�悷��u����𗬃c�A�[�v�i�P�Q���j�Ɍ��������O�w�K�̈��ځB�R�O�l�]�肪�Q�����ĔM�S�Ɋw�э����܂����B
�@�܂��A���ĕ��f���ꂽ�d�s�u���W�u����������ꂽ�����v�������B�n���Ɋ������܂ꂽ�Z����Q���R�l�R����Ƒ�������@�Łu�~�ρv���Ă�������ł́A�@�̓K�p����ɂ͎����ƈقȂ�u�푈���͎ҁv�Ƃ��Đ\��������܂���ł����B���̂��ߎ����̏،����������܂��ȂǁA���Ԑl��r���������̉��쐧�x�̖����A�ނ�������������ɂȂ�܂����B
�@������i�މ���̔픚�҂̌���ɂ��Č��픚�������ǂ̑�R���B�����̔�Q�҂�Ƃ̌𗬉�ł́A���ꂼ��̔�Q�ƂƂ��ɍ��̐ӔC�ƕ⏞�����߂Ă��������ɂ��Ă��𗬂��悤�Ƙb�������܂����B
�Q�O�P�U�N�x�@���{��c������
�q��\�ψ��r�؈䒼�@�J���Ş@�@�⍲���O
�q�����ǒ��r�c��ꤖ�
�q�����ǎ����r�،ˋG�s�@���ʎO�q�q�@���X�r��@�剺���T�@�_�Z���Y�@�a�c���q
�q��\�����r���c�ہ@�ؑ���юq�@�����A�@���{�O�@�����F���@�����j�i�V�j�@���Y�G�l�@���\�䕔�v�i�V�j�@���R�Ǝq�i�V�j�@���F���@���v��
�q��v�č��r�Δ����@�ؑ��M�q
�q�ږ�r��c�w���Y
�@�i�����ǎ����ɍ�ʂ����l�A��\�����ɍL�������l�A���̑�\������܂łɑI�o����j
�y����z�q�o�N�V�����ۏ����@�ӋC�����X�^�[�g�@�s����������b�Z�[�W
 ���蕽�a�����ŏ����s���i5��27���j
���蕽�a�����ŏ����s���i5��27���j
�@����ł͔픚�҂T�c�̂łS���ɉ�������A��v���āu�j����p�⍑�ۏ����v�����g�ނ��Ƃ����߁A�����A�A�����ցA�������A��Ћ��Ŏ����ǂ��\�����������i�ɂ������Ă��܂��B���̉�c�̒��Œ���̃X�^�[�g�W���đ哝�̂��픚�n�L����K�����Ƃ��A�I�o�}���ɂ����E�ɂ��픚�n����̎v�����A�s�[�����悤�A�ƌ��߂܂����B
�@�T���Q�V���P�O�����A�����X�^�[�g�W��a�����F�O���O�ŊJ�ÁB�����̑i������ǂݏグ�A�����ւ̎^�����Ăт����܂����B����s���̓c��x�v������́u�픚�҂��i����j����p�⍑�ۏ�����ʂ��Ċj����p��ւ̋@�^�����߂�v�Ƃ̃��b�Z�[�W����I���܂����B
�@�Q���̊e�c�̑�\�҂ɂ�郊���[�g�[�N�̌�A�����s�����J�n�B�R�O���ԂłQ�R�S�M�̏��������܂����B���̂����P�Q�O�M���I�[�X�g�����A��č��A�p���A�����ȂǂP�R�J���̊C�O�̐l����ł����B
�@�W��Q���͂V�O�l�B��Ћ��̔픚�҂P�R�l�ƓW�l�����C�ɏ�����i���܂����B�u���ۏ����v�̈ӋC�����X�^�[�g�W��ɂȂ�܂����B�i�`�c�x���}�j
�k�Č�����Q�҂̉�@�������̋C���������A��
�@�X���Ǝq����i�J���t�H���j�A�B�J���o�[�s�j����̂��莆�i�����j�ł��B
���@�@���@�@��
 �A�����J����͂�������
�A�����J����͂�������
�@���͖k�Č�����Q�҂̉�ʼn�v���тɎ����̂���`�������Ă���܂��B
�@�L���̌����ōň��̎o���l�S�����܂������A�����g�����s�픚�҂ŁA�j����p��͂����ƐS���狁�߂Ă��܂����B
�@�T���Q�V���A�I�o�}�哝�̂��L���ňԗ쓃�ɉԗւ����Ԃ����̂��e���r�����Ō��āA���͖S���Ȃ����o�����ɖ₢�����܂����B�u����Ō����𗎂Ƃ����A�����J�������Ă�������H�v�c�o��l�Ƃ��A�A�����J���܂�̓��n�ł��B�L���ł́A�푈���I�������A�����J�ɋA��ƁA���������Ă���܂����B
�@�I�o�}�哝�̂��A�哝�̂̔C�����I����Ă������Ɗj����p��ɋ��͂����̂ł���A�픚�҂��ꏏ�ɂȂ��Ĉ����̕�������̐����珜���˂Ȃ�܂���B����łȂ��ƁA���̂��߂̃m�[�x�����a�܂ł����H�@��������̗P�\�͂���܂���B
�@����݂̂Ȃ���ɁA�������ĕԑ����Ă��炤�悤�莆�����A�����p�����V�T�ʏo���܂����B����l�łV�O�l�̏����𑗂��Ă����������l������A�����̐l���珐�����Ԃ��Ă��āA�R�T�O�l�ȏ�̏������W�܂�܂����B��l�ЂƂ�̊j�p��ւ̋C�����̏W�܂�ł��B
�@�ǂ����A�������̋C���������A�Ɏ����čs���Ă��������B�S���牞�����Ă���܂��B
�픚�҉^���Ɋw�Ԋw�K���k��@��4��
���ƕ⏞�_�̔��W
�@�m�[���A�E�q�o�N�V���L����Y���p�������A���J�Â��Ă���s�픚�҉^���Ɋw�э����w�K���k��t�̑�S�A�U���S���A�u�u�v�����q�v����u��{�v���v�ց`���ƕ⏞�_�̔��W���ӂ�Ԃ�`�v���e�[�}�Ƀv���U�G�t�̂T�K��c���ŊJ����܂����B
�@����N�͌I���i�]����B��c���������O����̔픚�҂̗v���̕ϑJ�����ǂ�A���̔픚�Ҏ{��Ɛ茋�ԂȂ��ŗv�����i�荞�܂�A�u���ƕ⏞�v�̈Ӗ��⍪�������[���E���W���Ƃ��Ă������Ƃ�������܂����B
�@�^���̊T�����Љ�邾���ł����Ȃ�̎��Ԃ�v���A�\���ȓ��c�̎��Ԃ��m�ۂł��Ȃ��������߁A�_�_������ɐ[�ߋc�_�������A��S��\�A�Ƃ��ĂV���Q�R���ɐ݂��邱�ƂɂȂ�܂����B
�픚�҉^��60�N�i7�j�@��c���̍��ۊ���

���h�C�c�V���i1983.10.20�j
�@���{��c���̍��ۊ����́A�����Ɠ����Ɏn�܂�܂����B
�@�����錾�u���E�ւ̈��A�v�́A�^�C�g���������悤�Ɂu���E�v�̐l�тƂւ̌Ăт����ł��B�S�l�ޓI�Ȏ���ɂ������j����p��̑i���ł����B����̒ɋ�́u�̌����Ƃ����Đl�ނ̊�@���~�����v�Ƃ������ӂƁu�j����̂Ȃ����E�v�ւ̔ߊ肪���߂��Ă��܂��B
�@���{��c���́A�s���{���̔픚�ґg�D�ō\������c�̂ł����A���̖ڕW�́A�u���E�̂ǂ��ɂ���x�Ɣ픚�҂�����ȁv�u�j����̂Ȃ����E�����낤�v�Ƃ������E�I���i�������A�^���͖{���I�ɍ��ۓI�Ŕ�c���^���̊j�S���Ȃ��Ă��܂��B
�@��������U�O�N�A���{��c���͐��E�e�n�֔픚�ґ�\�𑗂�A�j����̎g�p�������炷�c������܂�l�Ԕ�Q�̎��������L���邱�ƁA�픚�҂̏،����O����ɖ|��Q�̉f���ƂƂ��ɍL�����E�ɔЕz���邱�ƁA�ɗ͂������Ă��܂����B
�@���������̓��{��c���́A�g�D����̂Ől�͂����͂��R�����A�C�O�ւ̑�\�h���͂��܂��܂ȕ��a�^���E�s���^���Ɏx�����Ă����\�ł����B�U�O�N�㔼�ɋN���������։^���̍����ɁA�C�O�ւ̔h���͈ꎞ���f�������̂̌����ȗ��C�O�ւ̔h���҂́A�R�T�J���U�S�P�l�ɂ̂�܂��B
�킽���ƃq���V�}�E�i�K�T�L�@���{��c������60���N�Ɋ�
���c�P�M����i�u�����J�v�̌����ҁj

�@�P�X�W�T�N�́u�����J�v�̍Ē����ȗ��A���{��c���ƈꏏ�ɁA�j����p��Ɣ픚�҉���A�щ^�����Ԃ̗��ւƂ��ē����A�����g���ؐl�Ƃ��ĎQ�����������ǔF��ٔ��ł͂Q�S�A���������Ƃ�܂����B�������A���{�͎c�����˔\�̉e�����ɔF�߂悤�Ƃ��܂���B����̓A�����J�̊j��͂̏�Q�ɂȂ邩��ł��B
�@�푈�@�ɔ����A������`�����߂��^���ƌ���ŁA�j����p��A�픚�҉^��������ɉ����ɐi�߁A�q���V�}�E�i�K�T�L�́u�����J�v�n��g����������邽�߂ɁA���������撣��܂��B
���R�[�q����i�N����E����Ɓj

�@���{��c�������U�O�N�A�����������݂ɐS����h�ӂ�\���܂��B
�@�픚�V�O�N�̍�N�A���߂ĂW���U���̍L���̊X������܂����B�����S�ݓX�����グ�āA�P�X�T�O�N�̂W���U���A���̉��ォ�瓻�O�g�炪�u�f�łƂ��Đ푈�����҂ǂ��ƕ��a�i��̂��ߓ����v�Ə������r�����T���A���̌���Ɏ��̕����������Ƃ��v���܂����B
�@�w�k�����ŏ��W����A���͂����Ɣ��j���a�̉^���̒��Ŕ픚�҂Ɋ��Y���Ă������̕��݂��A�����܂������p���ł��������Ǝv���Ă��܂��B
�@����Ƃ��o������育���͂����Ă������������Ǝv���܂��B
����͎q����i��B��w��w�@�y�����j

�@�ӂ����є픚�҂����Ȃ����Ƃ�����̎g���Ƃ��A���̎g�����ʂ������Ƃ������u����Ɏc�����Ƃ̂ł��邽������̈�Y�v�ł���B�u������Q�҂̊�{�v���v�ɂ��邱�̐M�O�������픚�҉^���̊j�S�Ƃ�����ł��傤�B������Q��������Ƃ����Ĕ�������i����K�R���͂���܂���B�ނ���A�������ւ̕�j�����������Ă����������Ȃ��͂��ł��B
�@�������A�����c�肽���͌�����Q�𖾂炩�ɂ��Ȃ���A��Q�ɑ���ӔC��Njy���A���������߁A�j����p���i���Ă��܂����B����́A���̐M�O�����L���鑽���̓����҂Ȃ����Ă͂ł��Ȃ����Ƃł����B�Љ�I�ɌǗ����Ă����Ȃ�A�����c�肪�u�m�[���A�v���u���u�픚�ҁ�������Q�ҁv�Ƃ��Ď�̉�����邱�Ƃ͂Ȃ���������ł��B
�@�����ɁA�L���̏d�ׂɊ����A�a�C�⌒�N�s��������A�Ό��ɂ��炳��Ȃ���������ƑΛ��������鐶���c��̎p�ɁA�����̐l����������Ă����̂������ł��B�u�����҂Ǝx���ҁv�Ƃ����W���z���āA�^���Ɍg���l���݂ȁu�����ҁv�ɂȂ��Ă��������炱���A�U�O�N���̒����ɂ킽��^���������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�픚�҂������҂��N�V���Ă����Ȃ��A�u�����{�v�Ƃ�������̗��j�I�����̉��Ō`�����ꂽ�^�����A���ꂩ��������Ă����\���͍����Ȃ���������܂���B
�@�������A�j����̓����҂ɂȂ邱�ƂŁA���E�̒N�����픚�҉^���������p����̂ƂȂ邱�Ƃ͂ł���̂ł��B
���k�̂܂ǁ@��Ó��ʎ蓖�@����̍X�V�ŕs�x���ʒm�@�s���\���͂ł��܂���
�y��z���͂P�T�����̎��A����̔��S�n����R�L���Ŕ픚���܂����B
�@�����Q�O�N�S������݂���ɂ���Ó��ʎ蓖�����Ă��܂����B�������A����̍X�V�ň�Ó��ʎ蓖�s�x���̒ʒm���͂��܂����B
�@����̏����ɂ��ĕs���\���Ă͂ł��܂����B�܂��O��͂���܂����B
���@�@���@�@��
�y���z��Ó��ʎ蓖�̍X�V�p�������ɑ���s���\���Ă͂ł��܂��B�[���ł��Ȃ���Εs���\���Ă����Ă��������B�O�������܂��B
�@��Ó��ʎ蓖�́A�����ǂ̔F����āA���̕a�C�����Â�K�v�Ƃ�����ԂɎł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�u�v��Ð��v�ƌ����A�݂���̎�p��̊Ǘ��A�]�ځE�Ĕ����Ȃ����Ȃǂ̌o�ߊώ@���ł���Ƃ������ƂȂǂ������ɂȂ�܂��B
�@����A��Ó��ʎ蓖�̍X�V���F�߂��Ȃ������̂́A���Ȃ��݂̈���́u�����v���Ă���A��Â̕K�v���Ȃ��Ƃ̔��f�̌��ʂ��Ǝv���܂��B��Ó��ʎ蓖���N�͂ɁA�u����I�Ɏ�f���s���Ă��Ȃ��v�ƋL�ڂ���Ă����Ǝv���܂��B�݂���̏ꍇ�A��p��T�N�����čĔ��E�]�ڂ��Ȃ��Ɓu�����v�ƂȂ�܂��B
�@�s���\���Ăɂ������ẮA�܂��������Ă��Ȃ��āA�o�ߊώ@���܂߂Ĉ݂���̎��Â��K�v���Ƃ������Ƃ����߂Ď咣���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���̓_�܂��āA�s���\���Ă����������������B�\���Ă��ł�����Ԃ́A������m�������̗�������R�����ȓ��ƂȂ��Ă��܂��B
�܂ǂ���
�@���N�̂S������s���s���R���@�̕s���\���Ă̊��Ԃ��A�U�O������R�J���ɉ�������܂����B�܂��A���܂ł́u�Ӌ`�\���āv�͔p�~����A�s���s���R���@�ɂ��u�R�������v�ɂ���čs�Ȃ��܂��B
�������k���ɐV���k���@���@��q����
�@���{��c�������픚�Ғ������k���ł́A���T�ؗj���Ɉɓ����q���k�������k���Ă��܂����A�V������͂���ɉ����ĉΗj���ɁA����q���k�������k���邱�ƂɂȂ�܂����B
�@����q����́A��w���ƌ�P�X�U�V�N����N�ސE����܂ő�X�ؕa�@�i�����j�̈�Ã\�[�V�������[�J�[�Ƃ��ċΖ��B�픚�҉��쐧�x���ɂ߂ĕs�\���ȂȂ��ŁA�S����t�Ǝ�T���ԂŁA�����̔픚�҂̌��N�f�f���͂��߁A�픚�҈�Â�픚�҂̑��k�ɁA���N���g��ł��܂����B
�@�܂��A���x�����ψ��i�P�A�}�l�W���[�j�Ƃ��āA��쎖�Ƃɂ��ւ���Ă��܂����B
