「被団協」新聞2013年 11月号(418号)
2013年11月号 主な内容
![]()
原爆被害への国の償い実現求め19万5754人分の請願署名各党に託す

院内集会で各党議員に要請。右上ホワイトボード前に積まれたダンボールが19万余人分の署名
集会では、日本被団協が取り組んでいる核兵器廃絶、原爆被害への国の償い、原爆症認定制度の抜本改正への尽力を求める各党首への要請書も各党代表に手渡しました。
自民、民主、社民、共産、公明(受付順)各党の衆参議員があいさつ、安倍総理大臣が8月6日、9日、広島、長崎での平和記念式典でのあいさつで原爆症認定制度の改善を急がせるとのべたことに超党派で取り組み実現させようとの発言など各党とも促進させることを約束しました。核兵器絶についても努力が語られました。
7月の参院選で議席を回復し集会に参加した日本共産党の小池晃参院議員が、自身の現行法改正に賛同する議員署名をあらためて被団協に手渡しました。
これに先立つ被爆者集会では全国都道府県代表者会議の内容や2つのアピールなどの報告が行なわれました。
国の償い実現へ活動強化を
全国都道府県代表者会議

来賓あいさつした日本原水協の高草木博代表理事は、今年の国連総会で初めて開かれた核軍縮を議題にしたハイレベル会合での議論を紹介し「世界は間違いなく核兵器廃絶の方向に動いている」とのべ、被爆者の運動が力になっていると激励。原水協からの寄付金目録を坪井直代表委員に手渡しました。
田中煕巳事務局長の基調報告をうけ初日は、国の償い実現運動、原爆症認定制度の抜本改正、被爆二世の活動、2015年・被爆70年にむけての4つの議題で議論しました。
国の償い実現運動では活発に議論し、運動本部提案の国会請願署名、募金など目標を各県で自主的に決め、学習を深め運動をひろげる、中央集会や全国いっせい行動、支援団との会議を開くことなど確認しました。
2日目の冒頭、「脱原発のドイツから学ぶこと」と題して松浦秀人代表理事が特別報告。今春のドイツ訪問をもとにドイツのエネルギー政策や、福島原発事故直後からのメルケル政権の素早い対応と、その背景に長年にわたる国民の運動があることなどを紹介しました。
今秋、中央相談所の法人格がなくなることにともなう相談事業について各県の活動を交流。ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産の会、ノーモア・ヒバクシャ9条の会の取り組みについても報告がありました。
核兵器不使用の共同声明 125カ国が署名
日本賛同も核抑止力政策変えず
10月21日(日本時間22日)ニューヨークの国連本部で開会中の国連総会第1委員会(軍縮)で、ニュージーランド政府代表が「核兵器の人道上の影響に関する共同声明」を発表し、125カ国が署名、日本政府も初めて署名しました。
共同声明は、「いかなる状況下でも核兵器が2度と使われないことが、人類存続の利益になる」と明記しています。
日本政府は今年4月、ジュネーブで開かれた2015年NPT再検討会議第2回準備委員会の共同声明では「核兵器不使用」の文言が自国の安全保障政策と合致しないとして賛同しませんでした。今回賛同した理由として、共同声明に「核軍縮に向けたすべてのアプローチと取り組みを支持する」という文言が盛り込まれたことから「適切な国家安全保障政策を引き続き採用する必要性を再確認する」として、核抑止力政策を変更しないことを強調しています。
日本被団協は同日、「『いかなる状況下でも核兵器不使用』を日本政府は厳守せよ」との声明を発表しました(要旨別項)。今回の共同声明に賛同した日本政府に求められるのは、「具体的措置として、核の使用を前提とする核抑止力政策を改め、速やかにアメリカの核の傘から離脱し、核保有国に核兵器廃絶を迫り実現する責務を果たすことです」と指摘しています。
 |
| 厚労省 |
 |
| 内閣府 |
 |
| 外務省 |
 |
| 経産省 |
各省に要請 被爆二世施策に関する要請も
日本被団協は院内集会を行なった10月10日午後、内閣府と厚生労働省、外務省、経済産業省に対し要請を行ないました。
内閣府では、安倍晋三内閣総理大臣宛の要請書を佐野美博調査役に託し、核兵器廃絶と原爆被害への国の償いを求め訴えました。
厚労省では、榊原毅被爆者援護対策室長ほかが対応しました。日本被団協の要請書のほか、日本被団協二世委員会として二世施策についての要請書を用意し、被爆者、二世が共に訴えました。
外務省では、野口軍備管理軍縮課長が対応。核兵器廃絶にむけ、日本が主導的役割を果たすよう要請しました。
経産省では、資源エネルギー庁の安藤尚貴係長ほかが対応。原発の再稼働と新増設、輸出の中止、福島第一原発事故への対策などを訴えました。
秋の相談事業講演会
北海道、東海北陸で開催
 |
| 北海道 |
 |
| 東海北陸 |
伊藤直子中央相談所理事による「被爆者支援と相談会」の講義があり、具体的なお話をききました。講習会の教材も用意されて、参加者一同とても助かりました。健康管理手当更新時の診断書の作成などについて、参加者からの質問も多数出されました。今回23人が参加しましたが、被爆者も高齢者が多くなり、参加することがだんだんと厳しくなっている状況です。(北海道・鳴海典子)
[東海北陸]10月20日〜21日、愛知県蒲郡市のホテル明山荘で開かれ120人が参加しました。
初日に原爆症認定訴訟弁護団の樽井直樹弁護士が新訴訟について講演、原爆症認定訴訟での、国の態度と被爆者運動の重要性を話しました。集団訴訟の記録映画「おりづる」が上映されました。
2日目は、まず田中熙巳日本被団協事務局長が原爆症認定制度あり方検討会と日本被団協の提言について講演。検討会の趣旨は司法と行政の判断の乖離を解消することにあったのに、厚労省が乖離の現状を示さないまま推移してきたこと、日本被団協として「提言」を出した経緯とその内容が詳しく説明されました。
伊藤直子被爆者中央相談所理事が被爆者対策の現状と原爆症認定、介護保険制度の活用について報告。相談の実際に即して具体的な内容が報告、説明されました。
最後に各県被団協の代表がそれぞれの取り組みを報告。来年、福井県での再会を誓い合いました。
議員署名
現行法改正への国会議員の賛同署名、10月の追加分です。
参議院議員=小池晃(共産・比例) 仁比聡平(共産・比例) 吉良よし子(共産・東京) 倉林明子(共産・京都) 辰巳孝太郎(共産・大阪)
現行法改正意見書採択
現行法改正を求める地方議会の意見書採択は、9月議会で秋田県の五城目町と大潟村が採択しました。
引き続き、要請を積極的にしていきましょう。
伝えたいこと ―― 扉を軽くたたいてください(下)
長崎被災協 大塚一敏さん(79)

長崎のつどいで発言する大塚さん(8月8日)
俊宏の死で、問題となったことが2つありました。1つは、被爆二世について国は一度も実態調査をしていない。原爆病院に二世が何人も入院しているのに遺伝的影響の医学的研究もやっていない。2つは、放射能障害の遺伝的影響が絶対にないと証明されるまで、国は被爆二世に援護措置をとること。医療費が月に70万円も90万円もかかったのです(月給8万円時代)。金がなければ「二世は死ね」ということか。この2つは今日に至るも解決されていません。
今春、ジュネーブで80カ国が共同し「核兵器の残虐性、非人道性」を指摘し「核兵器が2度と使われてはならない」との声明を出しました。これは被爆者運動の原点です。長年、被爆の実相を語り続けてきたことが大きく貢献しています。
日本政府は、この声明を拒否。あろうことか、核兵器使用もあり得ることを想定して、憲法9条を変えて戦争の準備をする、原発再稼働・輸出で核被害を拡散する道を取り、歴史の歯車を逆に回そうとしています。
被爆者は、核兵器使用という極悪非道の犯罪を告発し続けてきました。人間の尊厳を守って生き抜いてきました。人生そのものが被爆体験だし、「語る」ことで歴史の逆行に立ち向かってきました。わたしも微力ながら「核兵器廃絶、政府が戦争被害の受忍政策をやめ、被爆者に償うまで、簡単に死ぬものか」という思いで語ってきました。
遠からず被爆者がいなくなるのは避けられません。もう1回人生があれば、もう1回やってやるぞと思ったり、いや、二世、三世のみなさんの出番だ、今がバトンタッチだぞと思ったりします。
被爆者は、戦時中から戦後の波乱にみちた生涯の終末にあたって、誰もが何かを伝えたいと思っているはずです。
もし心が閉ざされていたら扉を軽くたたいてください。被爆者が何を求め、何を考えて生きてきたかを「知る」ことができるでしょう。それに自分の思いを重ねて語ってください。話の中身も方法も自分流で。
歴史の現実は「今日聞いたら、明日語ってほしい」と迫っています。「継承」で若いみなさんががんばることは、戦争・被爆を知らない人々の心を動かし、「核兵器のない世界」への扉を開く世論を飛躍させるでしょう。 被爆者はそれを心から願っています。(おわり)
手記 ―― 被爆70年へ 生きぬいて(6)
二度の胃がんに負けず語りつづける
田中信之(たなか・のぶゆき)さん 85歳〈広島被爆 当時17歳 久留米市在住〉

小学校で被爆の証言をする田中さん(1999.11.8)
昭和16年12月8日日本軍の真珠湾攻撃に始まり未曽有の戦争に突入、これから先いかなることかと不安に思いました。連戦連勝も束の間のことで時が経つにつれ戦況不利の声も聞かれるようになりました。
4年生になると海軍予科練習生の募集が盛んになり多くの友が特攻隊の要員となっていきました。内地でも米軍の空襲が次々と主要都市を焼け野原と化していきました。学習する暇もなく男は軍人へ女は挺身隊として軍需工場へと動員される中、私も学校卒業前に従軍特別幹部候補生として陸軍兵器学校広島分教所へ昭和20年2月に入隊。厳しい訓練の中で8月6日を迎えました。
* * *
暑い朝1発の原爆により生き地獄と化した中で私は九死に一生を得たのです。校庭に集まった戦友はほとんど負傷していました。無傷だった私を上官が見て直ちに市内の状況を調べてくるように命じられました。学校はちょうど爆心地より3キロの地点でした。校門を出ると市街地は完全に破壊され、四方から焔が燃えあがっていました。続々と避難してくる人々は、皮膚は焼けただれ衣服はぼろぼろでこの世の人と思えない姿で泣き叫びながらいつまでも続きました。市内に進むにつれ死体も多くなり焔も目前に迫ったので学校へ帰ると、食事に餅1個与えられました。すぐそばの天満川の堤防へ行ってみると、砂利道の両側に無数の患者が敷物もなく直に並べられ、焼けた体に小さな石が食い込んで悲鳴をあげている。水をくれ、と立ち、川へと走っている、そのまま水の中へ。川は一面に死体で覆われている…。
1週間死体処理を続けました。火葬にするにしても燃料が不足していました。誰のものともわからない生焼けの骨を拾っていく遺族。ただ合掌するのみでした。
* * *
終戦を迎え9月に福岡県三潴郡城島町に帰郷しましたが、暫くの間体調不良で仕事につけませんでした。
昭和37年に隣の久留米に原爆被害者の会ができました。その後久留米の会や大牟田の会の助言を受け、地元の会をつくろうと尽力し、昭和52年に三潴大川の会(市町村合併により現在は久留米市の会に合併)を設立しました。温泉旅行で熊本県のホテルに予約していたのに、当日「被爆者はだめです」と本館に入れられず古い民家のような所へ入れられ悔しい思いをしたこともあります。
そんな中近くの小中学校より被爆体験談の要請があり数年間は毎年依頼されるのが増えていましたが、最近はまた少なくなってきました。
生徒から贈られた感想文や手紙をくり返し読んでいます。心がいやされる楽しみの一つです。
二度の胃がんにも負けず私の使命である「語りべ」を続けています。命ある限り、焼けただれて死んだ人、一生傷を負った人のためにも。
祈平和!
長崎で山口仙二さんを偲ぶ会

まず参加者全員が思いを込めて、山口さんの遺影前の祭壇に献花。つづいて山田拓民長崎被災協事務局長の挨拶があり、生前の山口さんの映像が流されました。被爆直後の山口少年、青年乙女の会を結成した仲間との活動、日本被団協運動、そして1982年の国連での訴えなどです。
親交の深かった方々の挨拶ですべての人が語られたことは、山口さんの優しさです。人なつっこく相手を包みこむ気さくな人柄です。そして、核戦争と核兵器への、山口さんの激しい怒りです。
高橋眞司長崎大学客員教授は記念講演で「仙二さんは核暴力のない世界へ向かって人類が営みを続けている象徴であり、さきがけだった」と語り、岩佐幹三日本被団協代表委員は挨拶で「仙二さんの遺志をつぎ、核兵器のない世界をめざす国際世論を起こし、アメリカに追随し核抑止論に頼る国に政策の転換を求めよう」と訴えました。
「はむingはーと」の平和の歌、長崎被災協二世の会長崎・諫早の「山口さんの被爆体験」の群読がありました。
遺族挨拶で幸子夫人が「仙二は核兵器廃絶のために生き、被爆者として死ぬと語っていた」と紹介。「もう一度あなたに会いたいと」と話され、参加者一同涙しました。
日本被団協から岩佐幹三代表委員、田中煕巳事務局長、木戸季市事務局次長が参加しました。
被爆者の願い知り、継承を
日本被団協 被爆二世被爆者交流会

会の前半は、被爆二世の佐藤直子さん(長崎)と田崎豊子さん(東京)、被爆者の藤森俊希さん(長野)がそれぞれの思いや現在の活動について発言しました。
後半は、(1)親から子への継承をどうするか(2)二世の組織化や要求実現、被爆者運動の継承をどうしていくか、という論点で経験や意見交流を行ないました。二世からは「父が被爆者であることを語ったのは被爆後50年経ってからだった。以来、体験を少しずつ聞き取ってまとめている」「父の死を境に活動を始めた。親の生きざまを見てきたことを平和活動につなげたい」などの発言が、被爆者からは「親や家族の被爆体験とその後の人生を知り、原爆が人間に何をもたらしたのかを理解してほしい。被爆者が何を願ってどうしてきたのかを知ってほしい。それらは二世だけが背負うものではない」「二世も被爆者の会の会員になってもらい、一緒に運動をしていきたい」などの発言がありました。
初めて知る被爆者の思い
被爆者の証言を聞くつどい
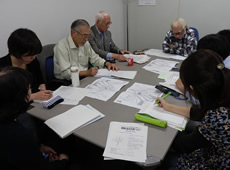
首都圏から被爆者10人を含む31人が参加。4グループに分かれてそれぞれ1人の被爆者の証言を聞き、ディスカッションを行ないました。証言について「生々しく、臨場感があった。被爆者の思いを初めて知った」「文字で読むのとは全く違う。直接聞くことの大切さがわかった」「痛くて言葉がでないけれど、聞いてよかった」などの感想がだされました。参加者アンケートには「参加者それぞれの思いや体験があり、証言を深めることができた」「若い人たちのまっすぐな受けとめ方に感心した」などの感想が寄せられました。
継承する会では日本被団協と協力し、証言の聞き取りを全国に広げたいと取り組んでいます。
相談のまど 肝機能生涯での身体障害者手帳交付
【問】肝機能障害があると身体障害者手帳が交付されると聞いたのですが、本当でしょうか。交付される場合の手続きなど教えてください。
* * *
【答】平成22年4月から、肝臓機能障害がある場合、身体障害者手帳が交付されることになっています。これは被爆者対策として行なわれるものではありません。
肝障害は肝炎ウイルスに起因する肝炎、薬剤性肝障害、アルコール性肝障害など法律が定める認定基準に該当することが必要です。
手続きは、所定の身体障害者手帳交付申請書、身体障害者手帳指定医が作成した診断書、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)を、居住地の市区町村の担当窓口に提出します。
指定医がいる医療機関については、市区町村の担当窓口に問い合わせてください。また、自治体によって提出書類が異なる場合がありますので、市区町村に確認してください。
認定基準に該当すると、障害の程度によって、1級から4級までの手帳が交付されます。
身体障害者手帳が交付されると、所得税、住民税など各種税制優遇措置の対象になります。また、手帳の等級によって異なりますが、鉄道運賃、航空旅客運賃、有料道路料金などの割引措置が受けられます。
まどから
「相談のための問答集」No.29ができました。1冊400円(50冊以上のとき300円、送料別)です。お申込みは中央相談所まで。
こんなこと聞いてもいいですか…?受け継ぐための質問部屋
戦争を終わらせる方法は
「原爆と人間」のパネルを見学しました。こんなおそろしいことが起きる前に戦争を終わらせる方法は無かったのでしょうか。一瞬で何万人の人々の命が消えた場所を、誰が片付けたのでしょうか。(兵庫・中学3年生)
読者からの回答
◆中学生の君に 広島・主婦・55歳
被爆者の方のお話を聞いたり証言集を読んだりすると、無残な遺体を荼毘に付したときの痛ましい様子が出てきます。自然災害のときに遺体を集めるのは、おとなのしごとです。でも戦争のときは違います。小学生や中学生の子どもたちも、家族の亡きがらを捜し集めて火葬しています。中には学校の先生の指示で、同級生の遺骸を生き残った生徒が素手で拾ったという話もあります。
「戦争」はこんな酷いことが山ほどあっても、いったん始まってしまうと、なかなか終われないものです。私たちには想像のできないような巨万の利益や権力を手にしたい人たちがいて、そのために国のしくみ(法律・予算・交通・情報・産業・人の組織など)を順々に変えていき、「国」として始めるのが「戦争」だからです。
「戦争」は始めさせないことが一番です。戦災の事実を知り、何より「日本国憲法」を学んでください。「利益や権力」よりも、ひとりひとりの基本的人権、平和のうちに生きる権利を大切にし、そのためには、たとえ「あらそいごと」があっても話し合いで解決する方途が、現在ではいくつもつくられていることを知ってください。
◆小さなことから 熊本・長崎被爆・72歳
私は3歳のとき長崎原爆に遭い、その時の様子はパネルでは表せないくらいの地獄図でした。しかし周囲の人のお蔭で、今日まで生きてきました。戦後は、市民の一人一人が「自分たちがやらなければ」という強い思いで行動し、市や県、そして国を動かしていったのです。金儲けのためではなく、皆が喜ぶようにという純粋な思いで頑張ったので、今の繁栄した長崎があるのです。
若い皆さんへ伝えたいことは、「良いことはどんな小さなことでもする」ということです。誰も見ていないからといって、ポイ捨て、いじめ、差別をしないことです。小さなひとつひとつが大きなことにつながり、国内紛争や国家間の戦争もなくなると思います。
お答えまっています
日本政府の態度について
憲法で戦争はしないとしていて、平和のために力を尽くすと言っているのに、政府は被爆者には「原爆被害はがまんせよ」と言っていると知りました。平和な世界をつくるためには国民は大切なのに、ガマンしろというのは変だと思います。(長野県・高校2年生)
被爆体験の継承に関する質問と回答を「質問部屋」係までお寄せください。次回は1月号に掲載する予定です。
