「被団協」新聞2013年 3月号(410号)
2013年3月号 主な内容
![]()
原爆被害者に国の償い求め 全国でいっせい行動
2月6日〜2月8日 宮城、首都圏、千葉、東海、熊本、新潟
 |
 |
| 宮城街頭行動 2月6日 | 首都圏院内行動 2月7日 |
 |
 |
| 千葉街頭行動 2月8日 | 東海北陸ブロック街頭行動 2月6日 |
 |
|
| 熊本街頭行動 2月6日 |
7日、衆院議員会館で開かれた院内集会には首都圏の東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心に茨城県、愛知県、岐阜県の被爆者と弁護士が参加。国会内のほとんどの党派にあたる7つの党派から代表が出席し挨拶、決意をのべました。各都県の被爆者代表が各党派代表に党首あての要請書を手渡しました。
被爆70年を前に『生きぬいて』手記募集
再来年の2015年は広島・長崎に原爆が投下されて70年になります。被爆70年を前にして、被爆者のみなさんから「生きぬいて」をテーマにした手記を募集します。ふるってご応募ください。
1945年の8月6日と9日、アメリカが投下した原爆によって、地獄の苦しみを味わった被爆者は、その後もたくさんの苦しいこと悲しいことに直面してきました。原爆被害とたたかい「ふたたび被爆者をつくるな」と、核兵器のない平和な世界を願ってこられたみなさんの思いのたけをお書きください。
苦しいことばかりではなく、心なごむひとときもおありだったと思います。被爆のまえ、被爆直後、被爆のその後、激変した人生を送られたみなさんが、後世に伝えたいこと、引き継いでほしいこと、どうしてもこれだけはと思うことを、率直に綴ってください。
1956年、被爆者は日本原水爆被害者団体協議会を結成し、「ふたたび被爆者をつくるな」と全世界に訴え、「核兵器のすみやかな廃絶」「原爆被害への国の償い」の実現を求めてきました。
2つの大きな目標は実現していませんが、被爆者の訴えは、核戦争回避の力となり、血のにじむような運動で被爆者対策は少しずつですが前進してきました。旗をかかげつづける被爆者の思いをお書きください。
応募要領
[原 稿]手記=千字以内。筆者の顔写真、関連写真を可能な限り添えてください。紙面の都合上、編集を加えることをご了承ください。短歌、俳句=3首(句)以内、絵手紙=1枚も募集します。なおいただいた原稿は原則として返却しませんが、貴重な写真など返却を希望されるときはその旨お書き添えください。
[書 式]原稿の最初か裏面に次のことを記入してください。(1)筆者名(2)住所(3)電話番号(4)所属組織。
[送付方法] (1)原稿用紙に書いて送る(2)パソコン原稿をプリントして送るかEメールで送信する。
[送 付 先] 日本被団協=住所(〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3-5 ゲイブルビル9階)、Eメールアドレス(kj3t-tnk@asahi-net.or.jp)へ。
座標 ―― 原発ゼロへ 急ぎ被害者救済を
東京電力福島第1原子力発電所事故から3月で2年になります。事故はいまだに収束していません。15万人余の福島県民が避難生活を余儀なくされ、放射能被害は国民に計り知れない影響を与え続けています。
2月下旬訪米してオバマ大統領と会談した安倍総理大臣は、前政権の「2030年代原発稼働ゼロ」というきわめて不十分な方針すら「ゼロベースで見直す」と約束しました。「米国とは原子力協力のパートナーとして緊密に連携していきたい」というのが理由です。原発再稼働や新増設、原発輸出も行なう方針です。国民の不安に寄り添い、安心して暮らせる社会をつくる一国の最高責任者としての確固とした姿勢をうかがうことはできません。
2月中旬に行なわれた新聞の世論調査でも原発稼働を「すぐにやめる」「30年代より前にやめる」など「やめる」と答えた人の合計は7割を超えました。
日本被団協は、放射能被害の体験者として、福島原発被害者の健康を守るため健康手帳を発行し長期間にわたる健康診断と医療を提供するよう政府、自治体に提案してきました。一部の自治体で実施されていますが、国として一切取り組んでいません。被害者の要求は切実です。2月国会内で被害者と国、東電との交渉が行なわれました。被害者が子どもの尿からセシウムが検出されたことなど示し被ばく検診費用の全額負担を求めたのに対し、東電側は「不安に思って検査に行こうとすることが合理的かどうか」などと事故を引き起こした責任をまるで感じていません。
事故2年にあたって原発ゼロへ3月9日〜11日の東京をはじめ全国で集会や行動が予定されています。被害者救済も原発ゼロを実現させるのも世論です。力を合わせましょう。
マイクで訴え署名集め 全国いっせい行動 各地の取り組み

首都圏院内行動、地元選出国会議員への要請書等を準備
[宮城]6日12時〜13時、仙台市の中心部で街頭行動を行ないました。雪が降る寒さの中被爆者4人を含む12人が参加。マイクで訴え、111筆の署名を集めました。
[千葉]8日13時〜14時15分、松戸駅前で街頭行動を行ないました。冷たい強風の中被爆者22人を含む30人が参加。パネルを持ち、マイクで訴え、ビラを配布し、109筆の署名を集めました。
[東海北陸ブロック]6日14時〜15時、名古屋市内で街頭行動を行ないました。愛知、三重、静岡、岐阜の4県から18人が参加。北陸3県からは激励のメッセージが届きました。ビラを配布しマイクで訴えながら93筆の署名を集めました。
[熊本]6日12時〜13時、熊本市内で街頭行動を行ないました。被爆二世3人を含む13人が参加し、マイクで訴え、ビラ250枚を配布し、署名103筆を集めました。お菓子の差し入れをくれる人がいるなど、元気の出る行動となりました。
[首都圏]7日、茨城1人、千葉13人、埼玉12人、神奈川11人、東京28人、愛知3人、岐阜1人と弁護士ほか合わせて80人余が参加して、院内行動を行ないました。午前10時に集合し、地元選出国会議員への要請書等を準備、午後から議員室を訪れ要請しました。11時30分から1時間行なった院内集会に、寺田稔(自民)、谷合正明(公明)、高木義明、柳田稔(民主)、井上哲士、田村智子、赤嶺政賢(共産)、吉川元(社民)、はたともこ、玉城デニー(生活)、坂元大輔(維新)の各議員が参加しました。
伊方原発運転差し止め訴訟 第3回口頭弁論

この日は、原告側弁護団が5つの準備書面について口頭で説明し、3人の原告が意見陳述しました。
原告側は、四国電力がまともに書証を提出しない不誠実な態度をとっていることについて、裁判遅延行為だと厳しく指摘してきました。
松山地裁は、1月28日付文書で、四国電力に対し、原告から申し立てのあった項目のうち12項目について書面や資料を出すよう指示しています。
北朝鮮の核実験に抗議声明
第371回代表理事会が2月13日〜14日、東京港区のKCDホールで開かれました。
会議前日の12日午後、北朝鮮が核実験を強行したことが明らかになり、代表理事会の議論を経て直ちに「北朝鮮の核実験に厳しく抗議する」との声明を発表しました。また、国連代表部を通じて北朝鮮政府にも声明(全文別項)を送りました。
代表理事会では、昨年末の衆院総選挙で政権が交代したことなどを受けた情勢について議論しました。原爆被害への国の償い実現運動、原爆症認定制度の抜本改善、実相普及、相談活動、原発・エネルギー問題、被爆70年に向けての企画、被爆二世問題など活発に議論しました。
3月4日、5日とノルウェーの首都オスロで開かれる核兵器の非人道性について議論する国際会議に、田中熙巳事務局長と藤森俊希事務局次長を派遣することを確認しました。
“グレーゾーン”取り下げへ
第19回原爆症認定制度の在り方に関する検討会
第19回原爆症認定制度在り方検討会が2月21日午前10時から正午前まで厚労省会議室で開かれました。神野直彦座長は冒頭、山崎康彦委員提起の「グレーゾーン」の議論を求めました。
グレーゾーンは、認定申請を却下された人の救済案として提起されたものですが、疾病の範囲など具体案が示されていません。議論では、行政認定と司法判断の乖離で一番大きいのは放射線の起因性を認めるか否かだとして、現行の科学的知見、新しい審査の基準内で対象疾病を広げられないかとの意見が出、山崎委員も同意、同案は実質上取り下げられました。
田中熙巳委員は、現行制度の放射線起因性は、放射性降下物の残留放射能の影響を全く考慮していない、被爆者は家族を探し残留放射線の強い爆心地近くに行くなど移動しており、個人別の被曝線量の計算は不可能だと指摘し、現行の放射線起因性の認定可否判断に強く反対。この指摘に同意する委員もいました。
現行法改正賛同議員署名(2月22日現在)
| 衆議院 | |||
| 生方 幸夫 | 民主党 | 南関東 | 比例 |
| 松原 仁 | 民主党 | 東 京 | 比例 |
| 長島 昭久 | 民主党 | 東 京 | 21区 |
| 牧島かれん | 自民党 | 神奈川 | 17区 |
| 松本 文明 | 自民党 | 東 京 | 比例 |
| 吉川 元 | 社民党 | 九 州 | 比例 |
| 杉本かずみ | みんな | 東 海 | 比例 |
| 田中 良生 | 自民党 | 埼 玉 | 15区 |
| 参議院 | |||
| 中川 雅治 | 自民党 | 東 京 | 22 |
| はたともこ | 生 活 | 比例 | 19繰 |
| (数字は選出年度=平成) | |||
非核三原則法制化と新パネル購入訴え
県内全自治体・議会を訪問 ―― 宮城県原爆被害者の会 木村緋紗子

大郷町議会議長(左)に要請する木村事務局長
見本用にとパネルを新たに1セット購入して持参し、パンフレットを要請先72カ所に1部ずつ寄贈しました。
福島第1原発が事故を起こしているだけに、被爆の問題については非常に高い関心を持って受け止められました。
パネルは、「購入を検討し、多くの市民の目に触れることができるように工夫したい」などと積極的に受けとめる自治体がかなりありました。
非核三原則法制化については「日本は唯一の被爆国だ。皆さんの期待に応えられるように努力したい」との、圧倒的多数の議長さんたちの声を聞くことができました。
大衡村の萩原達雄議長は「皆さんがこうして訪問して来てくれたことの重みを考えます」と話していました。このように受け止めていただいたことは本当に嬉しく思いましたし、自治体訪問の重要性を感じました。川崎町の大浪俊憲議長は「家内の実家は飯館村で、一家は離散状態、娘は女川にいる、原爆だけでなく原発もだめだ」と強調していました。原発の本当の怖さを知った人の言葉だと感じました。
南三陸町は、幹部が出張のため、町と議会の担当職員が応対しました。1人は震災で母親を亡くし自宅を失ったとのことでした。その担当者が「平成22年度に非核平和都市宣言をした、23年度に原爆パネル展を計画し、啓発の決意を新たにしていた、パネル購入を検討したい」「非核三原則は町のスタンスとして必要と考えている、議会もそうなので相談したい」と話しました。震災、津波で壊滅的被害を受けた自治体の職員からのこの言葉は、ヒロシマ・ナガサキの被害とは質は違うが、おびただしい人命が失われたことに対する悼みを共有できることを感じました。
駐広島大韓民国総領事・辛亨根が日本被団協訪問

辛総領事は、韓国原爆被害者協会初代会長の故辛泳洙氏の子息です。同協会は1994年に辛会長を代表に日本被団協を正式訪問、翌年8月の韓国での慰霊式に日本被団協代表(山本事務局次長他2人)が初参加して以来毎年日本被団協から役員が参加しています。
二世支部が映画会『はだしのゲンが見たヒロシマ』
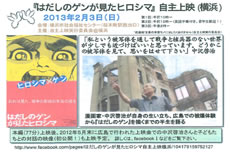
上映会案内
10月の運営委員会で企画を決定。原爆のことは8月の季節行事ではない、多くの人に被爆者のことを知ってほしいとの思いでプレスリリースも行ない、地道な声かけもして当日を迎えました。
今回の取り組みは二世支部として初の外に向けた活動でした。今後、活動の幅を広げていきたいと思います。
海外からの見学者、今年も 北海道ヒバクシャ会館

証言をきく海外からの来館者
北海道被爆者協会の越智晴子会長の被爆体験を通訳を介して聞き、その後展示室でパネルや被爆遺品を見学していきました。日本被団協のHIBAKUSHAパンフを、参加者全員に贈呈しました。参加者からは、お国の民芸品を頂きました。
JICAによる北海道ヒバクシャ会館見学事業は2004年から始まり現在まで毎年継続されています。
被爆70年聴き取りの取り組みに向けて
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が学習懇談会開く
ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は2月23日、被爆者、研究者など約30人が参加して被爆70年の聴き取りの取り組みについて考える学習懇談会を開きました。
浜谷正晴一橋大名誉教授から、1977被爆問題国際シンポジウムの一般調査の経験について報告を受け、被爆70年を迎えようとしている今の時点で何を語り、聴き取るのかを話しあいました。長年「聞き書き」を行なってきた参加者から、聴く人の層を広げたいとの発言もあり、取り組みへの期待が高まりました。
国連軍縮会議で原爆展
5日間で2800人来場 静岡

日本平ホテルロビーで原爆展
世界18カ国の政府代表や有識者が議論を交わした会議には、静岡市民4000人が傍聴を希望しましたが、抽選で560人が7つのテーマの議論を傍聴しました。
日本の天野万利軍縮大使は「1度に核廃絶を求めるのではなく、議論してきた段階的なアプローチを大切にすべきだ」と発言しました。
静岡県被団協は会場のホテルロビーに「原爆と人間」パネルほかを展示。5日間で2800人以上の見学者があり、900人からコメントが寄せられました。
相談のまど 健康管理手当の更新 白内障の場合は
【問】白内障で健康管理手当を受給しており、7月で5年の支給期間がきます。健康管理手当は「更新」の必要がなくなったと聞きましたが、私の場合も手続きをしなくていいのでしょうか。
「更新」が必要な障害・疾病は、鉄欠乏性貧血、潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病、貧血、白内障、甲状腺機能亢進症です。これらの病気は治癒する可能性があるため、「更新」しなくてはなりません。特に白内障の場合は、手術で混濁した水晶体を摘出すると、水晶体混濁による白内障ではなくなります。このため、支給期間があるのです。
白内障の手術をしていない間は、「更新」手続きをすれば手当を受給できます。もし「更新」しなくてよい疾病にかかっているなら、その疾病で申請すれば、後の「更新」は不要です。
「更新」しなくてよい疾病は、がん、糖尿病、甲状腺機能低下症、脳血管障害、高血圧性心疾患などの循環器機能障害、腎臓機能障害、肺気腫などの呼吸器機能障害、変形性脊椎症などの運動器機能障害などです。そして病状について、健康管理手当の診断書にある「1.固定している」「2.固定していない」のうち、「1.固定している」を医師に選択してもらえば、今後「更新」する必要がなくなります。
受け継ぐための質問部屋 こんなこと、聞いてもいいですか…?
小さいころに被爆した人の証言
幼かったために当時の記憶がほとんど残っていないと言って、証言するのを遠慮する方がおられます。そうした方のお話もうかがいたいと思うのですが、どんなことであれば話していただけるでしょうか。(東京・会社員・35歳)
◆実相を勉強し伝えたい 東京・広島被爆・71歳
「どんなことなら話せるか」との質問ですが、これは個人によってさまざまだと思います。
私は3歳の被爆体験で、全くと言っていいほど記憶はありません。母から聞いた話や、先輩から聞いた話の中から心に残っている事柄を伝えること…実相が一番です。それと、原爆に関する資料はたくさんありますから、自分で勉強することが大切と思っています。
自己紹介から始まり、当時の世界と日本の状況、原爆開発の経緯、原爆の3つの特徴、人間に与えた影響など、11項目を話します。A0、A1の画用紙4枚に原爆投下後の広島の地図、テニアン空港から広島までの地図、ラジオゾンデの投下、飛行経路などの展示もします。原爆瓦も持参し、最後は、事前に譜面を渡しておいた「原爆を許すまじ」をみんなで歌います。
話と歌で、どこか記憶にとどめてもらえるようにと思っています。
◆語らねば後が無い 愛知・広島被爆・70歳
私も3歳被爆ですから被爆の実相はわかりませんが、被爆者です。5、6年前まで実相については何も語ることができませんでした。当時思ったことは、被爆者であって被爆者ではないということです。なぜなら、何も実体験が無いからです。
しかし、今は少し違います。今日まで3回ぐらい体験を話しました。先輩の、また母親・父親の体験記を読みながら、かなりの努力が必要です。
でも、やりましょうよ! やらなければ後が無いと思います。後には誰もいないのです。被爆者としてやれることは、あとわずかです。
◆語るときまで待って 熊本・長崎被爆・71歳
私は3歳のときに被爆しました。記憶は今でも鮮明です。無声映画に嗅覚・味覚が加味されたものです。音は何一つ残っていないのに、周囲一面の倒壊の様子、倒れた家の壁土の臭い、仮設病院の消毒薬の臭い、そしておにぎりの酸っぱい味は生涯忘れないでしょう。当時1〜2歳の人は、まったく記憶がないと聞きます。
私が被爆者として証言を始めたのは、定年後です。被爆者の事情で遠慮する方もおられます。本当の苦しみ、思い、訴えはご本人しかわかりませんから、そっとしてあげることが賢明です。きっと語るときが来ます。出会いの機会を純粋な思いで待つ姿勢が大切です。
原発事故後、今、思うこと
福島第一原発で事故が起きてから、2年が経とうとしています。被爆者として今、どんな思いを抱いておられますか。事故が起こる前と後で、生活や考え方など変わったことはありますか。また、変わらなかったことは何ですか。(東京・主婦・40歳)
※被爆体験の継承に関する質問と回答を「質問部屋」係までお寄せください。次回は5月号に掲載する予定です。
