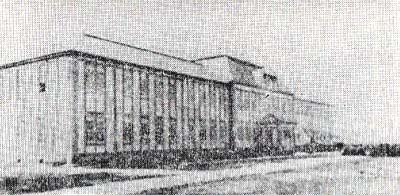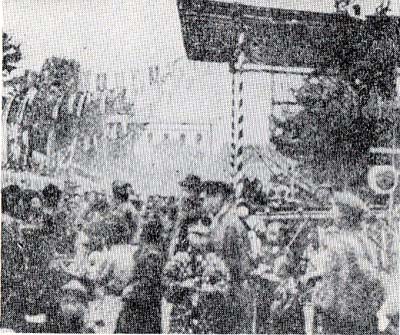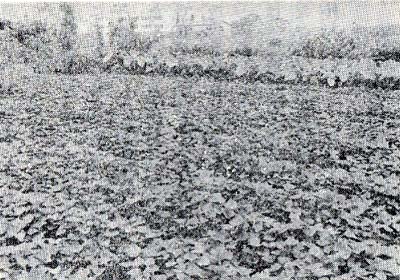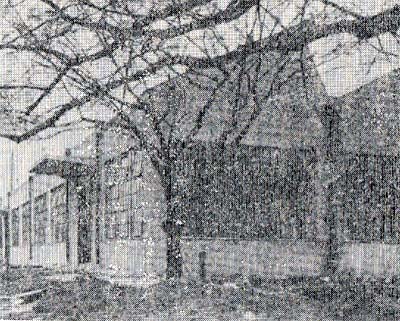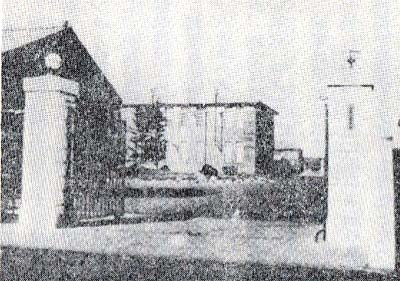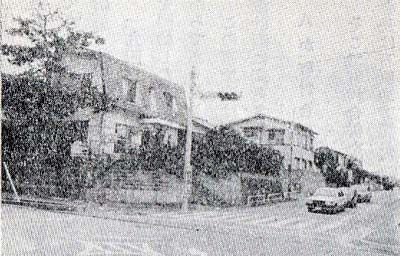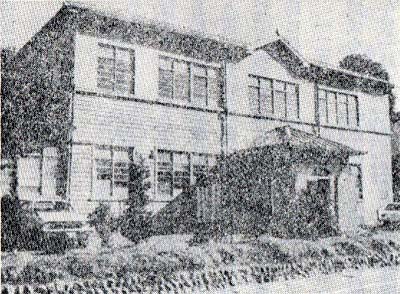|
****************************************
Home 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付録
九章 両大戦間の相模原
1 不況下の農村
第一次世界大戦の影響/関東太震災/恐慌に苦しむ農村/
不況下の小作問題/農村の不況対策
2 強まる軍国色
農村に浸透する軍円主義/陸軍士官学校の転入/軍施設の町に
3 相模原町の誕生
農村から軍都へ/一〇万人の都市計画/八か町村合併
4 開戦から敗戦まで
戦時休制に突入/日常生活への圧迫/首都防衛の陣地として |
1 不況下の農村 top
第一次世界大戦の影響
一九一四(大正三)年六月末、ヨーロッパに勃発した第一次世界大戦では、日本はイギリスとの友好関係上、八月二三日にドイツに対し宣戦を布告した。
この大戦の影響は相模原市域にもただちにおよび、八月三日の上溝市場は大暴落した。
各村では八月下旬からお宮やお寺で戦勝祈願祭を行なった。動員召集は小規模ながら九月初めに行なわれ、馬匹(ばひつ)徴発は九月五日に通達された。
麻溝(あさみぞ)村は配当九頭で五頭合格、相原村は配当二〇頭で六頭合格した。
中国山東省の労山(ラオサン)湾に上陸した陸軍部隊は一一月七日に青島(チンタオ)要塞を陥落させ、第一艦隊の南遣(なんけん)部隊は一〇月一九日までにマーシャル・マリアナ・カロリン諸島を占領した。
応召兵は一一月下旬には帰還した。
この大戦は一九一八(大正七)年一一月、ドイツの全面降伏までつづくのであるが、日本はこの諸戦(しょせん)に参加しただけで、全く漁夫の利を得た形となった。
大戦中、交戦国への軍需物資を中心に、その植民地へも日本商品はどんどん進出した。
このため日本工業は重工業の機械工業や金属工業と共に、化学工業とくに染料工業が創業され確立した。
工業生産額は一九一四(大正三)年に一三億円であったものが、一九(大正八)年には一気に六五億円と五倍にのしあがり、一四年に約一一億円の債務国が二〇(大正九)年には約二七億七〇〇〇万円の債権国となった。
このような戦時景気は、一面さまざまな成金を輩出させ、また暴利が横行して物価は底知れずあがり、一般民衆は生活難におちいった。
一九一四(大正三)年の物価指数を一〇〇とすると、一九(大正八)年は三〇三・四と三倍になったのに対し、所得は一六平均五割三分のアップにとどまった。
このため、一時は職工成金といわれた工場労働者も、賃金収入が物価騰貴に追いつかず、しだいに生活難におちいるようになった。
しかし農家は、農業生産物が比較的高価であったので、開戦初年をのぞいては不景気で困ることはなかった。
しかし日本の社会では、この第一次世界大戦を画期として社会問題は著しく深刻化し、農村における地主制にも動揺を与えることになった。
このような事態に対処するため、一九一七(大正六)年の臨時教育会議では、一般民衆とくに青年層に対する社会教育が諮問案の重要な項目の一つとなった。
答申の結果、政府のその方面における機関は拡充強化され、その活動は活発になった。
なかでも政府の最も留意したのは青年団体の統合であった。
これには対内事情と共に、引続く対外政策の遂行や、それに伴う天皇制を中心とする軍国主義の推進により、国民の精神的肉体的陶冶(とうや)の必要が極度に要請され、その対象として一般勤労青年がとらえられたのである。 このためまず実業補習学校の拡充施策が行なわれ、ついで二六(大正一五)年四月、青年訓練所令の公布により現役将校による兵式訓練の実施となった。
この間、一九二三(大正一二)年四月、橋本に県立相原農蚕学校が創立されたため、上溝の鳰川実業学校は廃校となり、鳩川実科高等女学校に切換えられた。 また、一九二三(大正一二)年四月から郡制は廃止されたが、郡長・郡役所は二六(大正一五)年六月まで存在した。 |
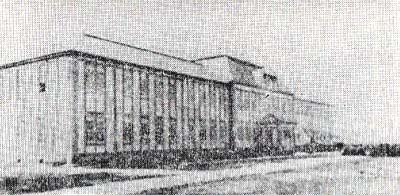
開校当時の相原農蚕学校
|
この年一月一日から、溝村に町制がしかれ、上溝町となった。
関東大震災
一九二三(大正一二)年九月一日午前一一時五八分四五秒に起った関東大震災は、震源地が東京南方二六里(約一〇四キロ)、伊豆大島の東方四・五里(約一八キロ)の海底であったため、その地点に近い神奈川県沿海地帯の被害は甚大であった。
高座郡では南部の茅ヶ崎・藤沢が最も激しく、北上するに従い軽くなり、相模原市域も激震地に比較すれば被害は軽微であったが、それでも倒潰破壊家屋のない村はなく、土蔵はほとんどつぶれ道路・橋梁・堤防などの被害も多かった。
とくに相模川沿岸の新磯・麻溝・田名・大沢などの段丘上では、道路の亀裂や崖崩れがはなはだしく、下溝はけ通りの断崖は約二〇〇間四〇〇坪が崩壊して人家三尺が十数メートルの崖下に墜落し、なお数戸に被害があったが、さいわい死傷者は出なかった。
二日午後、一部機関の作為的デマによる“不逞鮮人騒ぎ”が起り、市域でも動揺があったが、この月第二次山本権兵衛内閣の親任式が行なわれ、翌三日関東戒厳司令部が設けられた。麻溝村下原には横浜水道警備のため騎兵部隊が註屯し、下鶴間には憲兵分遣所(ぶんけんしょ)が置かれて騎馬の憲兵が市域諸村を巡回した。
甲府四九聯隊では、出身兵士を一泊帰休させ、移動部隊も頻繁に各村に立ちよった(駐屯していた諸部隊は、大体九月いっぱいで引きあげ、下鶴間憲兵隊は翌年三月までいた)。
市域各村では、四〜五日ころからぞくぞくと通過する罹災避難者のために、街道の要所に休憩・救護所を設け、社寺・公会堂を仮宿泊所として、その世話には救護班(青年団・保安組合・在郷軍人団により結成)があたった。
この仮泊・通行罹災者・救護人員は七日までに一三五〇人に達した。
市域農家では甘藷(サツマイモ)の出荷時期であったが、輸送の関係上それができなくなり、飼育中の二期三期の秋蚕も地震騒ぎで収繭が不可能になった。大島の漸進(ぜんしん)社では東神倉庫へ寄託中の生糸が全部焼失した。これらの損害も甚大であったが、震災の爪痕はのちのちまで残され、堤防の亀裂や地盤沈下・崩壊による耕地の喪失荒廃も多かった。
このため各村では起債や基本財産繰入れで応急処理し、また耕地整理法により国と県との援助のもとに復旧に努力した。
余震はたえまなく続き、歳末までに三〇〇〇回におよび、翌二四(大正一三)年一月一五日早暁、丹沢山付近を震源とする大地震があった。
恐慌に苦しむ農村
普通選挙法による最初の衆議院議員選挙は、一九二八(昭和三)年二月二〇日に行われた。
相模原市域が属する神奈川県第三区の当選者は、政友会は鈴木英雄・胎中(たいなか)楠右衛門、民政党は岡崎久次郎・平川松太郎の各党二名ずつで、投票率は八〇パーセント以上であった。
全体的には田中義一総裁の政友会は二一九名で、浜口雄幸総裁の民政党をわずか二名上まわるにすぎなかった。
なお無産党は八名当選した。田中内閣の激しい弾圧の結果としては、与党の伸び具合はきわめてわずかであった。
昭和初期はその当初からすでに経済悪化の状態を続けていた。
それは第一次大戦中の日本の一時的な輸出景気が、戦後になってその市場を失い、輸入のみ拡大して国際収支が不均衡になったためである。
しかも十分な財政緊縮と財界整理かできないところへ、大震災による打撃をうけ、震災手形の処理という大問題を生じた。
一九二七(昭和二)年三月、この震災手形処理問題審議中の国会で、片岡蔵相が失言したことから銀行の取付け騷ぎが起り全国銀行の一斉休業とまでなった。
政府はその救済策として四月二二日から五月一二日まで、金融モラトリアム(支払猶予令)を制定し、また日本銀行は特別融資の非常策をとった。
この金融恐慌で、郷土銀行の大手筋であった左右田(そうだ)銀行が休業し、結局立直れず横浜興信銀行に吸収された。
この銀行の預金者の大部分は小売商人や俸給生活者だったので、預金の払戻しができないことは死活の問題で、そのため一家心中や自殺、発狂するという悲惨事が生じた。
ついで一九二九(昭和四)年からは世界恐慌が始り、一〇月ニューヨークのウォール街で株式が大暴落した。
この影響はただちに全世界に波及したが、とくに日本は生産生糸の七〜八割をアメリカへ輪出していただけに、農村への打撃は大きかった。
二九年に約五八万担(七億八〇〇〇万円相当)に達した輪出生糸は、翌三〇(昭和五)年には約四八万担(四億二〇〇〇万円相当)に急落し、三一(昭和六)年には輸出量では五六万担ともちなおしたが、価格の方は三億六〇〇〇万円となり、二九年と比べると半値以下に暴落した。
|

養蚕農家 昭和初期の古木家。(合木家蔵)
その後、養蚕は日中戦争、太平洋戦争と進む中で、
人造繊維の技術の進歩で、戦後も再生することなく終った。
繭価も一九二九(昭和四)年の一貫目七円五八銭から翌年には四円二銭、三一(昭和六)年には三円一二銭、三二(昭和七)年には二円五〇銭までさがった。 |
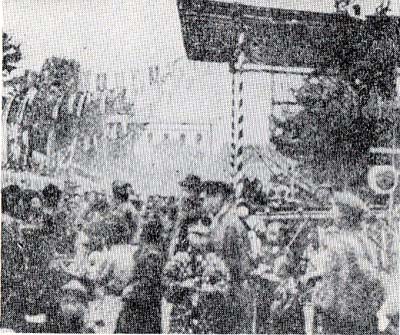
関東大震災前の上溝の商店街の賑わい
1919 (大正8)年ころ
|
繭の生産費は上繭で四円一九銭から三円九一銭となっているので、生産費さえつぐないえない有様であった。
上溝市場の糸況をみると、一九二五(大正一四)年一円に八匁(もんめ)台の生糸相場が、翌年には一三匁〜一六匁にさがり、二九(昭和四)年には一二・七匁であったのが、翌三〇(昭和五)年一〇月三三匁〜三八匁に暴落した。
その後、時によって二〇匁台になったこともあったが、三五(昭和一〇)年までは大体三〇匁台であった。
養蚕(ようさん)農家は全農家の四割をしめ、繭・生糸は現金収入の主要なものであったから、農家経済への影響は甚大であった。
また米作状況も市域で最も広い水田をもつ新磯村の一九三四(昭和九)年の事務報告をみると、
「米ノ収穫旱害(かんがい)風害ニヨリ平年ノ五割減収、価格騰貴(とうき)ノ為メ損害ナキモ、村内大多数ノ中産者以下ノ生産者ハ自家用米不作、政府米ノ払下ゲヲ受ケ補給、結局大損害」とある。
市域農村はほとんど水田をもたないので、米価騰貴にはどの村でも新磯村以上に苦しんだ。
不況下の小作問題
深刻な農村の経済不況により、地主・自作・小作農ともども苦境に追いこまれた。
一九三〇(昭和五)年頃の地域の小作料は、地主・小作人が協調して二〜三割から五割程度値下げしていた。
しかし小作人の生活向上はこの程度では無理な状態にあり、地主側もこの収入減によって苦しくなっていた。
このような状態が続けば、やがて小作農民の思想悪化を来たすようになるので、その緩和策として一九二六(大正一五)年、農林省令第一〇号として「自作農創設維持補助規則」が公布された。
これは、不安定な小作関係と高い小作料に苦しか小作農民に自分の土地を持たせようとするのが主眼であったが、従来の土地所有制度の上に立っているので、やはり地主に有利という一面もあった。
市域でこの貸付けをうけたのは、一九二七(昭和二)年からである。
村によってとぎれた年もあるが、三九(昭和一四)年までの貸付け金累計は、相原村二万八六三〇円、大野村五七九〇円、大沢村三万一七二円、上澣町二〇〇〇円、麻澣村一万一四七〇円、新磯村七八〇円で、借受人数は総計一三〇〜一五〇名と推定される。
小作戸数の少ない田名村は貸付けをうけていない。これらの償還は、四八(昭和二三)年に完了した。
神奈川県下の小作争議は、一九三三(昭和八)年には一八件にのぼり、前年度の一二件に比べ六件増加した。
最も多かったのは高座郡で、ついで橘樹(たちばな)・都筑(つづき)両郡、少ないのは鎌倉・中・愛甲・津久井の各郡であった。
市域でも同年から翌年にかけて活発に行なわれた。
一九三三(昭和八)年四月二日、新磯村磯部部落小作人組合は総会を開き、小作料低減運動を起した。理由は、地租改正の結果、従来の課税標準である地価が土地賃貸価格で押さえられることになり、都市地主の負担が重くなったのに対し、農村地主は平均二割から二割五分税金が軽減されることになったので、総会の結果、各地主に対する小作料引下げ方を決議し、交渉した。
結果は調停委員の調停により円満に解決した。
同年一二月、武相小作農民組合が結成され、小山部落の地主原清兵衛方へ小作料五割減の要求をした。
原家では、はじめから事態の円満解決を希望しており、堺・相原両村長も調停に立ったので、調停案を全面的に受入、無事解決した。
ついで前記組合に加盟しなかった小山宮上部落の小作農民も、同様に値下げを申入れ、これもとどこおりなく解決した。
翌一九三四(昭和九)年三月、武相農民組合では相原小川康明家の小作料を不当として、六割五分減を要求し交渉を開始した。
問題は一時紛糾したが、武相協議会代表佐藤吉熊と小作人代表が小川家といろいろ折衝の結果、地主側は貸金代償として取上げた一部の土地は返還して適当価格で譲渡することにし、また一部小作人の年貢免除・減額・月賦償還などを認めて妥協が成立し、円満に解決した。
農村の不況対策
市域の各農村は、このような経済非常時を切抜けるために、一九三〇(昭和五)年七〜九月頃、急遽、町村議会を開いて追加更正予算を決定し、財政規模を縮少させた。
これは直接に農民の経済能力を示す村税・戸数割収入が前年度に比べて、相原・大野両村は五割も急減し、他の各村でも著しく減少したためである。
各町村の歳入決算額を前年度に比較すると、上溝町では一九二九(昭和四)年に校地買入や鳰川高女への寄付があったので五〇パーセント減となっているが、これは特別で、大野村一三パーセント減、相原・田名両村二六パーセント減、大沢村二九パーセント減となる。
翌三一(昭和六)年にはさらに縮小し、三二、三三(昭和七、八)年には、当初から戸数割予算を大幅に低く見積っているが、それでも予定どおり徴収できなかった。
当初予算と決算との差がちぢまったのは三五(昭和一〇)年からである。
その間、政府の施策として、一九三一(昭和六)年度に「失業救済農山漁村臨時対策低利資金貸付」、その元利支払資金のため翌三二(昭和七)年「農村及中小商工業関係元利支払資金貸付」、同年から三四(昭和九)年にわたり「農村振興土木事業補助」などがあった。
一方、自力更生運動も盛んになり、一九三三(昭和八)年、新磯村が経済更生樹立村として県指定になったのを手始めに、各村も同じく指定村として自力更生に努力した。
これらの結果、一九三四、三五(昭和九、一〇)年頃になり、ようやく景気好転のきざしがみえはじめ、三六(昭和一一)年度からは臨時町村財政特別補助金が国から交付されて、窮乏を続けた農村財政もやっと息をつくことができた。
不況対策としては、農家自体としてもその苦境から脱出するため、経営上の転換が試みられた。
組合組織の強化がそれで、中和田の園芸組合、鵜野森(うのもり)の共同出荷組合、上大島平新磯(あらいそ)の蔬菜組合、上溝の農事改良組合、淵野辺の養蚕組合などがあり、相当の成果をあげた。
神奈川県経済部は、一九三五(昭和一〇)年、政府の桑園整理の方針により、県下一万一〇〇〇町加の桑園のうち七〇〇町歩を整理することにした。
このため、まず県下から六つの実行組合をあげ、模範経営を指導することにした。
市域では田名村塩田と大野村上矢部の養蚕実行組合がその選に入り、県係官の指導により総会を開いて、それぞれ養蚕農家の経済更生の策を講じた。
この桑園整理はすでに所々で行なわれており、相原村当麻田は用水の関係上畑となっていたが、一九三二(昭和七)年開田作業がすすめられ、三町九反の水田となった。
また開拓事業としては一九三五(昭和一〇)年、大野村谷口(やぐち)山野耕地整理組合が一〇町歩の山林を切開いた。
窮乏脱出のための多角式経営も、一九三〇、三一(昭和五、六)年から行なわれていたが、養豚(ようとん)も養鶏(けい)も生産物の安値に比べて飼料が高騰していたので、三二(昭和七)年には進退きわまる農家が多かった。
しかし三四(昭和九)年から三五(昭和一〇)年になると、当局の奨励もあっておおいに躍進し、農村不況の打開に大きな貢献をした。
畑作物では、一九三〇(昭和五)年以来、橋本穀物検査所で主として相原・大野・大沢各村へ甘藷(サツマイモ)栽培を奨励し、穀物と同じく生産検査をして品質を統一した。
なかでも「高座赤」という品種の甘藷は、高座郡具会の斡旋で北日本へ出荷し大好評を博したので、市域全体にわたり大々的な出荷計画か続けられた。
そして三五(昭和一〇)年には県農会の手に移り、各村三名ずつの斡旋係を置き、出荷統制した。
農村の人手不足を補うため、県では機械化の導入をはかり、指導員を派遣して実験や講習を行なった。
一九二九(昭和四)年六月、麻溝村当麻宿電化組合では運転式を行ない、上鶴間中和旧脱穀組合では三三(昭和八)年共同出資でクボタ四馬力軽油発動機・大貫式大型脱穀機を購入し能率をあげた。
改良された回転除草機は当時盛んに用いられた。動力耕転機の使用は終戦後のことである。 |
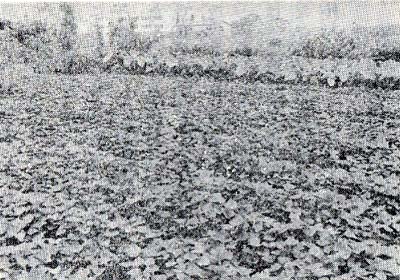
甘藷栽培 いまも市域のあちこちにみられる甘藷畑。
塩田付近にて。
|
なお、うちつづく経済不況のあおりをうけて、経営困難におちいっていた組合立鳩川高等女学校は、関係者必死の運動により、一九三三(昭和八)年四月から県に移管され、県立上溝高等女学校となった。
また業務不振を続けていた大島の漸進社は、一九三五(昭和一〇)年県の聯合会に統合された。
2 強まる軍国色 top
農村に浸透する軍国主義
一九三一(昭和六)年九月一八日午後一〇時半、奉天(ほうてん、現在の瀋陽)郊外柳条溝で、いわゆる“満州事変”が勃発した。
これは実はわが参謀本部と関東軍一部将校が中国東北地区を占領するために仕掛けた謀略行動であって、いわゆる一五年戦争の発端となったのである。
戦火はたちまち全満州(中国の東北区)に拡大し、翌一九三二(昭和七)年三月一日には早くも満州国が発足する運びとなった。
そして三三(昭和八)年三月、日本は国際連盟を脱退した。
当時、国民の戦争意識は非常に高まり、“皇軍”が大陸に進出して満州国独立を助けることは正義の行動であり、それを阻(はば)む西欧列強諸国は断固排撃されなければならぬ、と信じるようになっていた。
県下では、一六〇万県民を結集して国防協会設立を企図し、また防護団など軍事関係各団体の統制強化をはかった。
当時都市の知識人のなかには、このような状勢に対して批判的なものもいたが、その多くは沈黙し、逃避した。
しかし農村部では大部分の人々は、全面的に政府・軍部の指示に従い、軍国主義を推進した。
とくに村の有力者・名誉職・在郷軍人・消防団員・小学校教員・役場吏員らは、農民大衆を戦争目的に協力させるため先頭に立って活躍した。
なお団体統制を強固にするための下部組織として、部落会・隣組などの隣保制度がつくられ、利用された。
このようか態勢下に、一九三三(昭和八)年八月、四日三晩にわたって関東防空大演習が行なわれ、戦時意識を高揚させた。
一方、青少年に対する軍国教育の実施も、着々と準備されていた。
一九三五(昭和一〇)年一一月、文部省は大臣の諮問機関として教学刷新評議会を設置し、委員は軍部代表・元枢密顧問官・高級官僚・日本精神派など約六〇名であった。
これらの答申にもとづき、学校教育の精神としては、わが国古来の敬神崇租の美風を盛んにし、学校を国体に基づく修練の場として、教師と生徒・生徒相互間の精神的人格的連関をはかり、宗族的精神を学校教育に実現させることが肝要であるとした。
各校教員はこの趣旨を実現するために努力をしいられた。
青年訓練所はすでに一九二六(大正一五)年に開所しており、軍部はこれを軍隊教育の予備教育機関として重視した。
しかし同一年齢層の青少年が実業補習学校にも所属しているので、文部・陸軍両者はこれを一本化することにした。
そして三五(昭和一〇)年、勅令により青年学校令を公布した。
市域の七か町村は、同年七月から青年訓練所を廃止し、実業補習学校の校名・学則を変更して、青年学校として発足した。
すべて小学校と併置され、校長・職員は兼任だった。地域の青年学校は連合行事が多く、学校教練の研究会・査閲(さえつ)・野外演習などすべて合同で行なわれた。
陸軍士官学校の転入
一九三六(昭和一一)年六月二七日、座間・新磯・大野・麻溝四か村の村長は、第一師団経理部からの電話で座間村役場に集まった。
軍からは川上三等主計正・高山一等主計が来て、陸軍士官学校敷地と練兵場用地の買収について要望した。
一同は突然の話におどろいたが、一応帰村のうえ、地主と相談し考慮する旨を述べて解散した。
四か村のうち、座間は軍の学校をむかえて土地の発展にもなることだからとむしろ歓迎し、大野も面積がわずかなので支障はなく、問題は新磯・麻溝の二村であった。
両村の耕地の大半は台地上にあるので、これが買収されるのは生活上の死活問題であった。
村長の話を聞いた農民たちは、はたして大騒ぎとなった。
しかし時局がら、あまり強硬な反対運動もできず、県令軍へ陳情する以外方法はなかった。
結局、軍が地主と話合いのすえ、用地を縮小して同年七月一五日麻溝は了承し、新磯では失業対策の件などで一時話がもつれたが、これもやがて承知した。
買収面積は、新磯村が士官学校と練兵場で二六六町歩(約二六四ヘクタール)、麻溝村は二〇〇町歩(約一九八ヘクタール)であった。
買収の際、地主から小作人へ払う離作料の件がなかなか折合いかつかなかったが、一一月末にまとまった。
失地を補う山林開拓作業は翌年一月に両村とも行なったが、失地補充にはほど遠かった。
士官学校建築工事は一九三七(昭和一二)年九月完了して転営が行なわれた。
その敷地は、現在の相武台団地からキャンプ座間のあたり一帯にあたる。
同年一二月二〇日、同校五〇期卒業式には天皇が行幸され、相武台と命名された。
座間村はこの日を記念して町制を施行した。
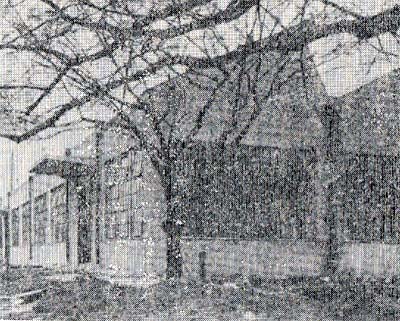
相模陸軍造兵廠(樋口家蔵) |
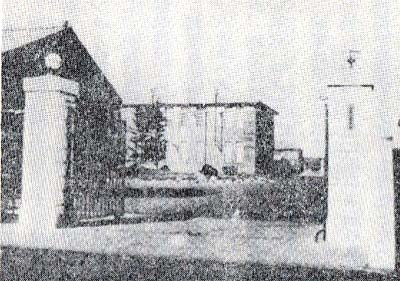
陸軍兵器学校正門 |
軍施設の町に
この陸軍士官学校の転入に前後して、昭和一〇年代には、相模原の台地上に、軍関係の施設がぞくぞくと移転、設置された。
現在は、国立相模原病院の敷地となっている臨時東京第三陸軍病院は一九三七(昭和一二)年一二月から翌年三月一日までの間に、あの七〇棟近い大工事を完成し開院したのだから、まさに昼夜兼行の突貫工事だった。
当時の面積は約三六町歩(約三六ヘクタール)、病院本部の玄関のところが大野村分で、大部分は麻溝(あさみぞ)・新磯(あらいそ)両村練兵場用地だったから買収には問題なかった。
収容患者数は四〜五〇〇〇名の予定だったが、六〇〇〇名をこえたこともある。
ほとんどが戦地からの傷病兵だった。
職員は二二〜二三〇〇〇名いたが、看護婦は五〜六名にすぎなかった。現在の国立相模原病院である。
相模陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)の前身の相模兵器製造所は、一九三七(昭和一二)年一二月に起工し、翌年八月に完成し開所した。
現在は相模原駅の北側一帯の米軍補給廠(しょう)となっているが、用地のなかば以上は山林だったので、小作その他の問題はなかった。
面積は大野村約七一町歩(約七〇ヘクタール)、相原村約五〇町歩(約四九ヘクタール)で、後、約六七町歩(約六六ヘクタール)拡張した。
四〇(昭和一五)年六月相模陸軍造兵廠に昇格した。
ここの仕事としては、第一製造所は戦車の製造、第二製造所は中口径砲弾弾体搾出(さくしゅつ)作業だったが、なお全国とくに京阪地区の陸軍車輔部門生産諸工場を監督し、その作業の統制にもあなった。
戦時中の軍人・軍属(軍にやとわれた事務官・労働者)の実数は、養成工を含め一万一三〇〇名だったが、戦争末期には徴用工・動員学生・挺身隊員などが多数かり出され、国民学校男子児童を収容する技能養成所には一か年一〇〇〇名(二か年寮生活)も集められ、最後には女子五〇〇名を採用した。
月産二〇台目標の戦車(チハ車)・装軌牽引車(ロケ車)の生産は一五台をこえることができなかったが、完成したものは直接戦地へ送られたが、一部は下九沢横山上の石宮格納庫へ置かれた。
一方、中口径砲弾弾体搾出作業は順調にすすみ製品は製造所周辺の空地に山をなしていた。
造兵廠のとなりの陸軍工科学校用地買収は、他の施設と同じく、造兵廠と同時に行なわれ、面積は大野村分五二町歩(約五一ヘクタール)であった。
一九三八(昭和一三)年八月末工事が完成し、学生は小石川から移ってきた。
四〇(昭和一五)年八月には陸軍兵器学校と改称し、敷地を二六町歩余(約二六・四ヘクタール)拡大した。
戦争末期には学生二〇個中隊四〇〇〇人、軍属一〇〇〇人が収容されていた。
電信第一聯隊の面積は大野村分約二九町歩(約二八・七ヘクタール)で、なかに篠原新開(しんかい)宅地一一反歩(約二〇アール)が含まれている。
これはいまの米軍相模原住宅地区にあたる。兵舎が完成して中野から転営したのは一九三九(昭和一四)年一月末であった。
同聯隊は、四一(昭和一六)年一一月、第二五軍山下兵団指揮下に入り、大平洋戦争に参加した。
留守部隊は電信第一聯隊補充隊を編成し通称東部八八部隊と称した。
陸軍通信学校の面積は大野村分約三七町歩(三六・六ヘクタール)で、なかに一九三四(昭和九)年谷口山野開墾組合が苦心して切開いた一〇町歩(約九・九ヘクタール)が含まれている。
米軍医療センター跡地と相模女子大学とがその敷地である。
校舎の第一期工事は三八(昭和二一)年一一月完成し先発隊は一二月到着したが、全員が移転したのは翌年四月である。
小田急線は前年四月から「通信学校駅」(現在の相模大野駅)を設置していた。
相模原陸軍病院は、最初の面積は五町歩(約四・九ヘクタール)だったが、終戦時には一九町歩(約一八・ハヘクタール)になった。
一九四〇(昭和一五)年三月開院式の際には原町田陸軍病院と称したか、地元の強い要望により、翌年相模原陸軍病院と改称した。
収容人員は終始一五○名であった。この跡地は、現在米軍医療センター跡地となっている。
陸軍機甲整備学校は。面積九八町歩余(約九七ヘクタール)で、移転は一九四二(昭和一七)年以降と思われる。
学生に機甲車輔の整備や補給勤務に必要な学科を修得させるのが目的であったが、十分機能を発揮しなしうち終戦となった。
このほか、軍の施設としては、現在市消防署淵野辺出張所の地点に、一九四〇(昭和一五)年原町田憲兵分隊が転営した。
また造兵廠西の一角に東京兵器補給廠相模出張所、東の一角に陸軍第四技術研究所ができた。
このほか矢部新田に陸軍航空技術研究所淵野辺飛行機速度検定所、淵野辺には同大野検定所があった。
なおこれら軍諸施設の設置に伴い、これに関連のある会社工場の転入も多かった。
以上みてきたように、一九四一(昭和一六)年の太平洋戦争を直前に、日本の軍備増強の現れとして、相模原市域の台地には、多くの軍施設が大きな面積を占拠することとなった。
首都圏東部の習志野(ならしの、千葉県)のような戦闘部隊の駐屯地こそなかったが、市域は軍隊の町としての一面をみせるようになっていたのである。
3 相模原町の誕生 top
農村から軍都へ
軍諸機関転入に先立つ一九二七(昭和二)年四月一日、小田原急行電鉄が敷設され、相模原発展のため寄与した。
なお二九(昭和四)年には江の島線が相模大野から分岐した。
また三一(昭和六)年四月には相模鉄道が橋本〜厚木間に通じ茅ヶ崎から全線開通の運びとなった(現在の国鉄相模線)。
沿線住民の待望していた横浜線の全源電化は四一(昭和一六)年四月実施され、一一〇年来の夢がかなった。
このように三路縮が集まり、交通の便が飛躍的によくなった上に、軍関係施設の移転・設置が続き、純農村的色彩の濃かった市域の村々は、ようやく町(都市)へと変り始めていた。
こうした現象に対処するため、まず陸軍士官学校の移転に伴い、座間村は一九三七(昭和一二)年一〇月二日に都市計画法の適用をうけ、同年末には町制を施行した。
これを皮切りに近接地域では三八(昭和一三)年一一月から翌年一二月末までに、上溝・大野・相原・新磯・大沢・田名・麻溝の順序で同法の適用をうけた。
同時に、それらの町村長は自動的に都市計画神奈川地方委員会委員になり、町村会議員のうちからも同委員を選出することになった。
定数は座間・大野各二名、他は一名ずつであった。
都市計画神奈川地方委員会は県知事を会長に、県下の国の出先機関の長、軍関係者、県会議員と前記町村長・議員ら約一一〇名で構成され、野坂相如県都市計画課長他三名が幹事となった。
昭和一四年度に入り、県は予想外の発展を続ける相模原地域に対し、ただちに軍都建設事業実施に踏切ることにした。
一九三九(昭和一四)年五月一二日、東京日日新聞社主催の相模原軍都建設座談会が淵野辺駅前の守屋旅館で開かれ、ついで六月二六日には大村知事の招請で、相模原開発計画に関する協議会が県庁第一会議室で開かれた。
出席者は知事以下関係部課長・都市計画神奈川地方委員・軍諸機関代表ら四二名であった。
横山土木部長から、士官学校中心の部分と相模兵器製造所中心の部分と二分して計画を立てている旨の大綱方針が示され、野坂都市計画課長が五五〇万坪(約一八平方キロ)におよぶ区画整理事業について詳細を説明した。
地元町村長らは、地元負担や減歩(げんぷ)について不安な点を質問したが、渡辺相模兵器製造所長は「地元の人々は銃後でご奉公できる工場がこの地に来たことを心から喜び、どんな犠牲を払っても利害を超越してご奉公の一端をつくして欲しい」と強調した。
その後、県では都市計画案を急いでまとめ、七月二八日に相原の旭小学校で地元民に対する説明会を開いた。
そして九月八日の臨時県会に、相模原都市建設区画整理事業関係議案が上程された。飯沼一省知事は提案理由を次のように述べた。
「座間町に陸軍士官学校が移転以来、隣接する相模原地方には数多くの軍関係諸施設が建設され、急激な発展が予想される。
しかしこの情勢を自然のままに放置すれば、広大な地域は無秩序乱雑な集落となり、種々の弊害を生じて、同地方発展の好機を永久に逸すると同時に、国家重要政策の遂行にも支障をきたすことになる。
よって同地域に都市建設の基本計画を樹立し、本事業を施行しようとするものである」と。
一〇万人都市計画
その計画とは。相原・大野・上溝にまたがる都市計画区画整理区域に事業区域を以下のように設定した゜
まず街路は、造兵廠(ぞうへいしょう)と上溝をつなぐ路線を縦の幹線(現在の市役所前通り)とし、府県道横浜中野線を横の幹線(現在の国道一六号線)とし、これに上溝世田谷線・厚木八王子線や既設の町村道を考慮して、約五〇〇メートル間隔に幹線を設けて幹線街路網とする。
住居地域三四五万坪(約一一三八ヘクタール)、商業地域三五万坪(約一一五ヘクタール)、工業地域一七五万坪(約五七七ヘクタール)と分け、住居地域は一人あたり五〇坪(約一六五平方メートル)、商業地域は三〇坪(約九九平方タートル)、工業地域は軍施設を除き三〇坪ずつの見当で、推定一〇万人の人口を配分した。
公共用地としては、小学校は一校一〇〇〇人で一四校を予定、一校四〇〇〇坪(約一・三ヘクタール)と仮定して計五万六〇〇〇坪(約一八・五ヘクタール)、中学校は三校を予定、以上の学校・官公衙(が)用地に計七万坪(約二三ヘクタール)、公園約一八万坪(約五九ヘクタール)を予定する。
このような計画の実行には、まず区画整理をしなければならない。事業遂行の費用は地元負担が建前なので、事業施行後、事業費充当用地七〇万坪を坪一一円で、また公共用地のうち学校官衙用地五万五〇〇〇坪を坪三円で売却し、計七八六万五〇〇〇円を得て、事業費にあてる方針であった。
このため地主にとっては減歩になるが、それは地価があがるので十分に補いがつくというのが予想であった。
以上の計画について、担当部課長の説明があり、県営相模原都市建設区画整理事業のため特別会計が設けられ、昭和一四〜二〇年度の七か年にわたる継続事業として、総計五七五万円の事業費が可決された。
その後、所定の手続きを経て、一一月三日内閣の認可がおり、ついで同月二八日内務省告示により公示され、翌一九四〇(昭和一五)年二月二七日付で児玉秀雄内務大臣から五五四万七〇〇〇坪(約一八三〇ヘクタール)の区画整理事業区域が公示された。
その図面は、各町村役場に備えられ、地域住民の縦覧に供せられた。
県ではとりあえず旭小学校内に仮事務所を置いて業務を開始したが、七月二二日淵野辺駅裏に相模原区画整理事務所(旧大野北出張所)の地鎮祭が行なわれ、完成移転後、同年一二月二三日事務所前の広場で区両整理事業の起工式が盛大に行なわれ、内務大臣代理・軍諸機関代表・知市以下関係県官・県会議長ほか各界名士・有志が六〇〇余名参列した。
こうして相模原軍都計画の第一歩はふみだされたが、翌一九四一(昭和一六)年一二月八日、太平洋戦争が勃発し、その後の戦局の苛烈化に伴い、物資・労力の不足をきたして、当初計画の延期をよぎなくされた。
軍諸施設の設置に伴い、多数の従業員のために宿舎が必要になっていた。
そこで軍では隣接町村に対し従業員宿舎の確保について依頼した。
相原村今上溝町では、さっそく町村会を開いて公営住宅建設を決定した。
いずれも大蔵省預金部から資金を借りうけ、特別会計を設け償還するのである。
県でも一九三九(昭和一四)年九月の臨時県会で、県営住宅を設置することにしたが、物価騰貴や物資・労力の不足で着手は四一(昭和一六)年になり、入居できたのは四二(昭和一七)年一二月から翌年にかけてであった。
陸軍のマークである星にちなんで、その地域を星が丘と名づけた。
なおこれらの公営住宅のほかに、民間経営のアパート・貸家も多く建てられた。
住宅についで要求されたのは水道であるが、この方はすでに相模原開田開発のための相模川河水統制事業の一環として分水は確保されていたので、緊急施設を要するのは送水・配水・給水などの設備であった。
これについて一九三九(昭和一四)年一二月の県会へ追加予算が提出され、活発な論議の結果、特別委員会へ付託し可決した。
一九四二(昭和一七)年七月、配水池から造兵廠正門前まで幹線が通じ、八月一日から同廠へ給水を開始した。 |
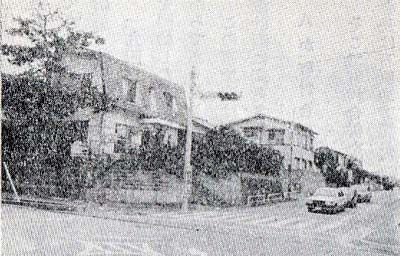
星が丘
現在は住宅地となっている星が丘の一角
|
ついで上溝県営住宅(星が丘)へ給水したが、その他への給水は四五(昭和二〇)年三月からであった。
この事業費は軍から一〇〇万円の交付金をうけ、それ以外は県債によった。
なお開田の方は畑地灌漑計画に変更され、一九六一(昭和三六)年に完成した。
八か町村合併
都市建設区画整理事業の進行と共に、関係町村の間に町村合併の機運が高まり、軍側でも当然それを希望した。
そこで町村合併を促進するための相模原軍都建設連絡委員会が結成され、会長は安岡総務部長、副会長は石原地方課長、会員は関係県官・地元県会議員・地元八か町村長と各町村三名ずつの代表など五一名であった。
第一回総会を一九三九(昭和一四)年一二月二二日県庁で開き、規約や予算をきめた。
以来数度の会合を開き、四〇(昭和一五)年七月二九日に県から合併二案が提出された。
第一案は士官学校を中心とした座間・新磯・麻溝・大和四か町村と、造兵廠を中心とした大野・相原・上溝・大沢・田名五か町村を別個に合併する二町案、第二案は以上九か町村を一つに合併する案であった。
これについての各町村の意向は、八月一六日の会合で報告されたが、合併についてはみな異存はなく、両案のうちでは九か町村合併案を選ぶものが多かった。 |
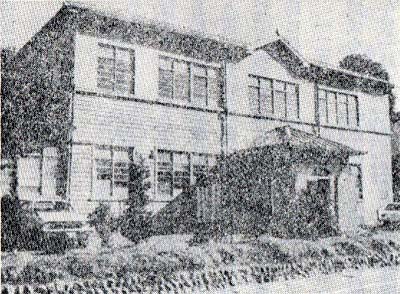
旧上溝町役場 1960 (昭和35)年ころの写真
|
ただ大和だけは反対が多く態度不定であった。
各町村は一九四一(昭和一六)年二月六、七の両日中に町村会を開き、九か町村合併を知事に上申した。
しかし結局、大和村のみは合併に同意せず、同年四月二九日に八か町村が合併し、面積一〇八・七一平方キロという日本最大の相模原町が誕生した。
合併当時の人口は、四万五四八二人であった。
なお町村合併と同時に市制施行の運動もしたが、時期尚早として当局の認可が得られなかった。
また町名については、地元町村としては相模町を希望していたのだが、県の意向で相模原町となったので、不満のむきもあった。
町役場は最初淵野辺の区画整理事務所にあったが、同年九月一日から上溝出張所に移転した。
第一回町方議員選挙は五月三〇日に行なわれ、三六名の新議員が選ばれて、第一回町会は六月三〇日に町役場で開かれた。
4 開戦から敗戦まで top
戦時体制に突入
一九四一 (昭和一六)年三月二〇日に国家総動員法が大幅に改正され、七月には横浜聯隊区司令官から「動員下令ニ関スル厳守事項」が通牒(つうちょう)された。
銃後後援会はすでに三九(昭和一四)年一〇月から各町村で結成されていたが、四一年八か町村合併後の九月一日に相模原町銃後後奉公会が発足した。
このような緊迫のうちに同年一二月八日、真珠湾の奇襲により第二次世界大戦が勃発した。
ちょうどその日は、午前一〇時から県下の市町村長会議が開かれていた。
この開戦第一報に会場内は一瞬さっと緊張感がみなぎり、皇軍の健闘を祈る決議をして午前一一時に閉会した。
一二月一五日には町内二六〇〇名の中堅青壮年が上溝国民学校に集合して、相模原翼賛壮年団の結成式をあげ、時艱克服・困難突破を誓約し、若き相模原町の推進力として発足した。
ついで同二二日午後一時から大詔奉戴(たいしょうほうたい)米英撃滅必勝町民大会が同じく上溝国民学校講堂で開かれた。
町長以下一五〇〇名が出席し、感激をこめて宣言決議を行ない、首相・陸海両相に祝電を発した。
翌一九四二(昭和一七)年二月一五日シンガポール陥落、町議会では同一七日に陸海軍将士に対する感謝決議案を可決し、ただちに陸海軍大臣あてに感謝状を発送した。
同年四月三〇日、翼賛選挙が行なわれ、推薦候補者の八二パーセントが当選し、軍人や右翼の進出が多かった。
同一二月一日午前上溝国民学校で相模原翼賛会と翼賛壮年団の共同主催で隣組長大会を開き、貯蓄増強や金属回収の徹底などを申しあわせた。
ついで同月一〇日町議会は相模原町翼政委員会規程を決定し、企画・経済・教化の三部を置いて、戦争目的の完遂を期した。
こうして市域には、戦争遂行の緊張した雰囲気が充満してきた。
日常生活への圧迫
当時、あらゆる物資は国家総動員法によってきびしい統制をうけ、中央・地方一貫しての組織で需給の調整がはかられ、軍需方面へ重点的に向けられた。
このため、すべての生活物資は一九三九(昭和一四)年頃から一般人の手に入りにくくなったが、四一(昭和一六)年四月からは生活必需物資統制令が公布され、配給制度はさらに厳重になった。
町役場ではこれを勧業課で扱い、厳密な世帯調査を行なって配給の公正を期した。
同時に労働統制も強化され、一般産業の労務者はすべて軍事関係方面へかり出された。
農家では働きざかりの男子は入営・応召と軍需産業にとられて人手不足なうえに、農具や肥料の不十分なのを克服して、いわゆる「ぢいちゃん・ばあちゃん・かあちゃん」の三ちゃん農業で食糧増産にはげみ、主食その他の供出義務をまっとうするために努力した。
その間、一九四二(昭和一七)年一〇月、文部次官通牒で学生生徒の長繁期勤労動員が指令され、四四(昭和一九)年二月には農民の徴用を免除するための農業要員指定制度ができた。
緒戦の戦果ははなばなしかったが、一九四二(昭和一七)年六月、ミッドウェー島の敗戦から戦局は徐々に逆転した。
四三(昭和一八)年二月ガダルカナル島から撤退し、太平洋全戦線にわたって敗退をよぎなくされてきた。
そしてついに四四(昭和一九)年七月にはマリアナ諸島のサイパン島を占領され、B29の本土空襲を可能にした。
上溝の町役場屋上の監視所から昼夜兼行で空の護りに任じていた上溝監視哨は、さらに一段の緊張を加えた。各戸では防空壕掘りに念をいれ、爆風避けのためガラス窓に十文字の目ばりをした。
各戸ごとに用水桶・砂袋・バケツ・火ばたき・梯子などを備えつけた。
町では防空衛生隊を組織し、婦人会・女子青年団へは救急療法を指導した。
人々は防空頭巾(ずきん)をもち歩き、胸には住所・氏名・年齢・血液型を記した名札をつけた。
一九四四(昭和一九)年五月以来、市域も連日空襲されたが、被害はほとんどなかった。
ただ焼夷弾で下溝大橋の農家が一戸焼けた。なお日本軍飛行機同士の衝突事故のため、清兵衛新田で家屋が焼失し二名が死亡した。
同年一月以来、都市からの疎開が始り、町ではその受入のため町内一万戸の畳数を調べ、家族人員と対照のうえ、地域別による収容人員の割当を行なった。
学童疎問は同年八月、地域各寺院へ横須賀の各国民学校児童をむかえいれた。
首都防衛の陣地として
一九四四(昭和一九)年一〇月末、フィリピン沖で敗れた日本軍は敗色いよいよ濃く、四五(昭和二〇)年二月一九日の硫黄島、六月二三日の沖縄玉砕によって本土決戦は必至となった。
それに備えるため、東海以北の第一総軍、西日本の第二総軍・航空総軍に対し、四月までに大動員が行なわれた。
五月には農漁村生産防空強化要項が発令され、ついで国民義勇隊が編成された。
町長が隊長で、各出張所管内が中隊、出張所管内の各部落が小隊となった。
五〇名以上の官公署・会社・工場などでは、職域の義勇隊を組織した。
義勇隊各隊長の辞令は五月二六日に発令され、八月一二日には戦闘隊役員が選任された。
学徒隊はすでに五月二二日戦時教育令により組織されていた。
相模原から多摩丘陵にかけては、首都を守るための第三防衛陣地となっていた。
在郷軍人団員は中津防衛隊の分屯隊として上溝国民学校に駐屯し、一八歳前後の青年を待命者とする郷土防術隊も組織された。
こうして本土決戦体制を整えつつあった一九四五(昭和二〇)年七月二六日、米英中国首脳部はベルリン郊外のポッダムで、対日宣言を発表して日本に降伏を勧告した。
これに対し政府・軍部間に激しい対立があったが、広島・長崎への原爆投下やソ連の参戦もあり、ついに天皇の裁断によって八月一五日の全面降伏の玉音放送となった。
厚木航空隊や士官学校の一部には抗戦の意気盛んな者があったが、一七日、陸海軍人に対する「出処進退ヲ厳明ニスペキ」勅語がくだり、各機関首脳部の説得もあって事なきを得た。
防衛各部隊も二三日夕方までに所定地域外に移駐した。
八月二三日、米占領軍先遣部隊の到着、三〇日マッガーサーの厚木飛行場着陸、九月二日横浜沖停泊中のミズリー号上での降伏文書調印、地域軍諸施設の米軍による接収……と、着々と展開される敗戦の現実の前に、人々はむなしく虚脱と混迷と飢餓の中に彷徨(ほうこう=さまよう)し、一〇万都市を目ざした軍都の夢は完全に消えさった。
top
****************************************
|