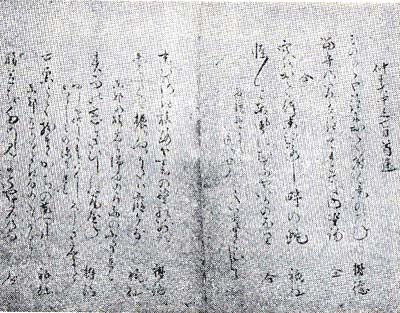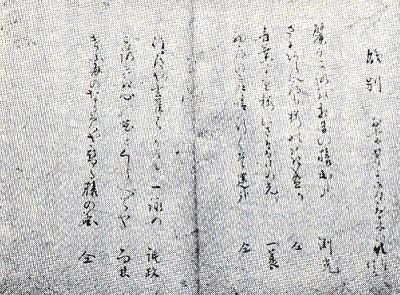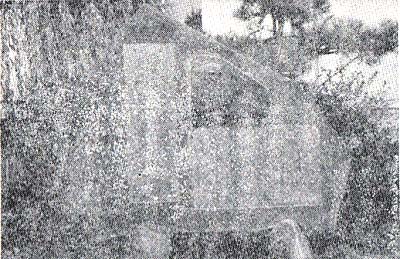|
****************************************
Home 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付録
五章 相模原農村の文化
1 村の俳人たち
宝寿堂樹徳/水月堂測光/俳諧の普及/江戸文化の流入
2 村の教育・学問
寺子屋と塾/農民の剣術けいこ/南山古梁/河津省庵 |
1 村の俳人たち top
近世の相模原における俳諧は、草深い農村としてはわりあいに早く、一七四〇年代の寛保・延享頃、自在庵派の俳諧が入っている。
それは下溝村の宝寿堂樹徳(じゅとく)や当麻村の水月洞渕光(えんこう)が江戸に出る機会が多く、その際、初代自在庵祇徳(ぎとく)に師事していたからである。
また祇徳は、弟子が八王子にいた関係上、それを訪ねてきて句会を開いたりした際に、相模原市域の大島・相原あたりに住んでいた渭水(いすい)・祇童(ぎどう)・水徳(すいとく)・桂秀(けいしゅう)・桃里(とうり)・艤角(ぎかく)らの俳人がその俳席に列している。
初代祇徳は芭蕉門の祇空の門人で、江戸浅草蔵前の札差であった。晩年に剃髪して来蔵法師と袮した。
水光洞・竹隠子などの別号があり、著書には『俳諧句選』『竹隠集』などがある。一七五四(宝暦四)年五三歳で没した。
宝寿堂樹徳
市域における自在庵派の中心的存在である樹徳は、下溝村大下に住んで代々小山儀右衛門を名のり、屋号を綿屋といって農業のかたわら酒造業と質屋とを営み、瓊玉円(けいぎょくえん)という家伝の薬も売っていて、名主その他の村役人を勤め、一七六〇(宝暦一〇)年に没している。
小山家では天明初期に江戸日本橋通り三丁目武右衛門店に薬種の支店を出したが、樹徳の頃からすでにしばしば江戸に出、師祗徳のもとに出入りしていたのである。
一七五一(寛延四)年一一月に樹徳は師を下溝村のわが家にむかえている。
待ち待ちて笠やあられの旅姿 樹徳
この時、祇徳はついでに足をのばして当麻村の渕光もたずね、次の句を詠んでいる。
絶え間なくとはれつ問ひつ星の霜 祇徳
この句から、樹徳・渕光らが江戸に出る膽会がしばしばあったことがわかる。
樹徳の俳諧活動が盛んであったのは一七四九(寛延二)年頃であったと思われる。
その年二月一七日に同村の祇仙と日光東照宮参詣におもむき、『日光紀行』の一編を残している。
東照宮では次の句を詠んだ。
いとゆふの空にたふとき日の出山 樹徳
東照る神の恵みや世にのどか 祇仙
同年六月には箱根に遊んだ。
また磯部から相模川を河口の大住郡馬入(ばにゅう)まで舟でくだり、
百合(ゆり)に眼を残して行くや下(くだ)り船 樹徳 |
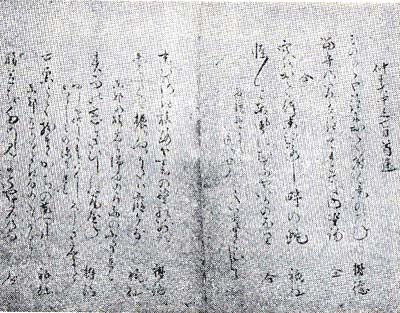
樹徳の句集
|
温泉は宮の下・堂が島・宮城野へと転々し、俳友と数巻の歌仙(三六句で構成される俳諧)を巻き『温泉の日記』の稿を残している。
一八一一(文化八)年にできた、代表的な箱根の地誌である弄花(ろうか)編『箱根七湯の栞(しおり)』には、塔の沢から宮の下へのくだりの崖道にある高さ四尺五寸の自然石の樹徳の句碑を図示している(現在は不明である)。
月に名のあれや箱根の青葉ごろ 樹徳
この句は前記『温泉の日記』に出ている。
樹徳の句稿をみると名言遍歴や社寺参詣の句が多く、風流三昧に日を送ったようであるが、事実は彼が『日光紀行』の序文中に「予は老いたる父母につかえて、風月より重き家業の余力をもとめず、云々」と記しているように、専心家業の進展に力をつくしていたのである。
師の祗徳もまず家業を第一に勤め、十分に生計を安定させてのち、その余力で風流の道を楽しむように指導していた。
樹徳もこの師の教えを生活の信条としていたのである。
なお当時の下溝・当麻両村の俳友には渕光・祗仙・祗国・一蓑・惟徳・祗全・雨林・艸玉(そうぎょく)らがいた。
水月洞渕光
樹徳と共に、市域の自在庵派の重鎮には、水月洞渕光(えんこう)がいる。
渕光は当麻村八瀬川に住み、関山宗右衛門通利と称し、家は代々名主を勤め、江戸大塚小日向(こびなた)台町に屋敷をもつ地頭大久保江七兵衛教平(旗本)の知行所の事務を取扱い、土地の者からは「お代官」とよばれていた。
彼が祇徳に師事して渕光の号を贈られたのは一七四二(寛保二)年頃と思われる。
四八(寛延元)年九月はじめ、祇徳をたずねて水月洞の別号を許され、その喜びを次のように詠んでいる。
えんこうも望んで得たり水の月 渕光
この年同じ月の一八日に、地頭大久保教平が駿府定番に転任して赴任するのに、侍姿で供ぞろいの中に加わっている。
駿府には二三日の朝着き、次の句を詠んでいる。
ときに逢ふ竹の春にや竹細工 渕光
しゃちほこも霧に泳ぐや城がまへ 同
一〇月三日に帰宅した。道中自詠の句二六句をまとめた『駿府への旅』という稿本を残している。
留守を守ってくれた長男の伊助は、その年の暮、ふとした風邪がもとでわずか一五歳でなくなった。
旅への出がけに「留守は少年のせがれに預けて、
花はまだ莟(つぼみ)がちなり留守の菊 渕光 |
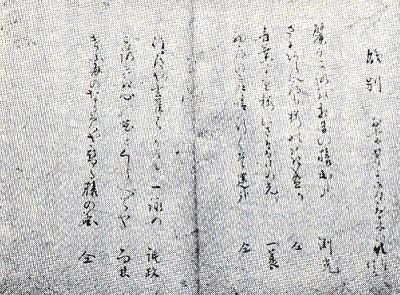
渕光の句集
|
と詠んだが、花も開かずつぼみのままで散ってしまったのである。
彼の悲嘆は想像するにあまりある。
渕光は非常な勉強家で、多くの俳書を筆写しており、樹徳はそれを借りてまた筆写している。
現在、『奥の細道』『続猿蓑(さるみの)』『笈(おい)の小文』など一〇数冊を残している。
渕光は一七八〇(安永九)年五月一九日に没した。
二代渕光は、初代渕光の婿(むこ)新右衛門の長男の佐市通昆(つうこん)である。
初代渕光は長男伊助が早世したので、その姉に新右衛門をむかえて跡継ぎとした。
釿右衛門は一八〇〇(寛政一二)年春七七歳をむかえて、長男佐市に名主役をゆずり、同年夏に没した。
佐市は二代渕光を名のり、句稿は年次のとんでいるところがあるが、一七八三(天明三)年から一八〇九(文化六)年におよんでいる。
表紙を欠き署名もないが、彼の句稿の中にみられる句を初代渕光の没後に、他の俳人の句集へ渕光の名で投句しているので、二代渕光のものであることは確実である。
あとに出てくる五柏園丈水(ごはくえんじょうすい)とは親交があり、丈水関係の句が多い。
一七九八(寛政一〇)年丈水八十賀(はちじゅうのが)、
彦ばえの世も花ならん八重さくら
一八〇〇(寛政一二)年丈水旅立、
見送りや笠と蝶とのわかる迄(まで)
一八〇八(文化五)年五柏園を悼(いた)みて申送る、
郭公(ほととぎす)わすれぬ空となりにけり
俳諧の普及
樹徳(じゅとく)・渕光(えんこう)の二人を中心として、市域の村々では句会などが盛んに開かれ、句作の趣味は農民の中に浸透していったと思われるが、他にも名のある俳人が市域にはいく人もいた。
渡辺崋山(かざん)の『游相(ゆうそう)日記』に「当麻というに日宗(にっしゅう)の寺あり、これを当麻山無量光寺といふ、寺主陀阿(他阿の誤り)俳諧を好くす名あり」とある。
この他阿は当麻山五二世南謨(なんぼ)霊随和尚である。彼もまた自在庵派の俳人で、高徳の名が高く、各地に名号石を建立した。
彼の句として当時の句集に残るものは、
田を植る土地に生れし果報かな 南謨
あさがほにものいふ年と成りにけり 同
虫はただ啼(な)くであらふに秋の声 同
現在、当麻山境内の鈍楼の前に「世にさかる花にもね仏まうしけり」の芭蕉句碑があるが、これは南謨が建てたものと思われる。
この芭蕉句碑の付近に丈水(じょうすい)の「花よ花念仏よ念仏当麻山」の句碑がある。
丈水は愛甲郡依知(えち)村猿が島(厚木市猿ヶ島)の人で、自在庵社中に名を連らね、南謨とは親交があった。
一八一〇(文化七)年、丈水の三周忌に刊行した『遠ほととぎす』はすべて南謨の企画によって成ったものである。
この句集には下九沢の利角の次の句がのっている。
はつ秋といふ斗(ばかり)なる暑哉(あつさかな) 利角
利角は小泉茂兵衛幸隆と称し、天然理心流の撃剣(げきけん)師範で、自宅で遠近の子弟を教授した。
現在、小泉家庭前に「陽光(かげろう)や柴胡(さいこ)の原の薄曇 芭蕉」の句碑があるが、これは利角が最初相模原入会(いりあい)野の一角に建てたものである。
『遠ほととぎす』にはまた同じ下九沢の西孤(さいこ)の次の句がのっている。
ふた親のわがままうれしくすりくい 西孤
西孤ははじめ青湖と号し、姓は安西、通称は庄兵衛。晩年出家して一八一〇(文化七)年没した。
墓碑は下九沢部落東側の横山下にあり、左側面に次の辞世(じせい)の句が刻まれている。
ゆくゆくは雨とならふか秋の風 西孤
下九沢の西北端の天王森に「秋深き隣りは何をする人ぞ」の芭蕉句碑があり、背面に西孤の次の句が刻まれている。
彼の没年の句である。
ものうきも是におさまれ虫の声 西孤
自在庵派以外の俳人として知られた者には、加舎白雄(かやしらお)の門下に淵野辺の柏樹がいる。
伊奈の伯先が白雄の弟子三〇〇〇人のなかから六二人の句を選んで、白雄二七回忌の追善の祭文にかえたなかに、 「釈(しゃく)柏樹 淵野辺大椿庵(だいちんあん)」として句を出している。竜像寺住職である。 |

下九沢の芭蕉西孤句碑
|
白雄の『春秋稿』には、
くもの子のちるや風呂屋の夕けふり 柏樹
やなぎ植しその夜を月の朧(おぼろ)かな 同
都辺や海をうしろに瓦やぎ 同
の諸句が掲載され、同郷の志計の句心ある。
あさがおや馬に鞍おく木賃宿 志計
江戸文化の流入
江戸との関係で地域に流入した文化は、俳諧だけではなかった。その一例を紹介しておこう。
古くから地元に伝わる穂打唄に「鎌倉見たか江戸見たか、江戸は見た、鎌倉名所はまだ見ない」というのがある。
近世における相模原市域と江戸との関係は、わりあいに密接だったのである。
村役人はもちろんのこと一般農民におよぶまで、地頭(じとう、知行地をもつ旗本領主のこと)御用や公事(くじ)出入(訴訟)・季節奉公や生産物の納入のため江戸へ出府の機会は多かった。
とくに訴訟事件の場合などは、盆といわず暮といわず、一〇日二〇日はさておいて月余におよぶ江戸逗留を余儀なくされ、滞在費用や農繁期の人手間に困り、帰村を懇願することもしばしばあった。
このような、いつ評定所(裁判などを司どる幕府の役所)から呼出しがあるかわからないような滞在の際、時間つぶしや事件経過の不安をまぎらすため、読本(よみほん)や草双紙(くさぞうし)類をもて遊ぶこともあったであろう。
現在でも、資料採訪の際、村役などを勤めた旧家の古文書(こもんじょ)のなかから江戸市井(しせい)の読物類が見出されるのは、こうした理由によるものである。
江戸文化が近郊農村へ流入した一つの経路である。
さて、この草双紙作者に、市域磯部の仙客亭柏琳(さんかくていはくりん)がいる。柏琳の作品で出版されているのは次の三種である。
一八三二(天保三)年『花吹雪縁ノ柵』
一八三四(天保五)年『星下り梅ノ早咲』
一八三六(天保七)年『紫房紋ノ文箱』
版元は江戸通油町(とおりあぶらちょう)鶴屋喜右衛門、通称「鶴喜」(つるき)である。
柏琳は通称を荒井金次郎といい、柳亭種彦の門人とされているが、直接の門人ではない。
最初の出版のときは種彦は柏琳の名前も知らず、もちろん面識もなかった。
ただ誰かに頼まれて稿本(原稿)を校閲し、書肆(しょし)へ出版の紹介をしたにすぎなかった。
当時、『偐(にせ)紫田舎源氏』の作者として江戸の流行作家であった種彦に出版の斡旋をさせるについては、よほど有力な紹介者があったことと思われる。
作品中の『星下り梅の早咲』は、「妙伝寺利生物語」と副題にあるように、日蓮上人の遺跡である愛甲郡上依知(えち)の妙伝寺について書いたものである。
柏琳の菩提寺は廃寺となったため、墓石の存在ははっきりしていない。
芸能もまた、江戸から伝来している。
下九沢御嶽(みたけ)神社・大島諏訪神社の獅子舞いは、神奈川県の無形文化財である。
一人立ち三頭獅子で、山崎角太夫からはじまるといわれる。 文化・文政頃、江戸ではこの種の獅子舞いが流行して、それがだんだん地方へとひろがった。
市域への伝来の経過は、下九沢の「日本獅子舞来由」によると、一八二一(文政四)年八月、武州多摩郡三田領小留浦(ことずら)村の村木家伝来のものを写しとったとして、名主榎本重蔵の署名があり、ついで獅子世話人として小川忠三郎・内山次郎左衛門・榎本仁左衛門・同幾八・島田市郎右衛門・久野太左衛門の名が連記されている。
舞踊はこの秘巻と共に伝授されたものである。
大島への伝来は、獅子舞い諸道具を入れる箱の蓋に、一八二二(文政五)年五月とある。
現在、八月二六日御獄神社、八月二七日諏訪神社祭礼に挙行される獅子舞いの手振りをみると、多分に江戸舞踊の要素が含まれている。 |

御嶽神社の獅子舞
|
しかし市域への流入は前述のように、直接ではなく、江戸近郊を経由したものである。
2 村の教育・学問 top
寺子屋と塾
近世の農民たちのうちで詩歌俳諧などを楽しむことのできた者は、主としてわずかな富民層だけで、一般農民は日々の労作に追われてそれどころではなかった。
しかし相模原市域の農村では。田畑の生産物はほとんど自給自足の域を出ず、現金収入の多くは製茶・製炭・養蚕・製糸・機業などにたより、東海道筋・江戸近郊・八王子方面などの範囲における商品経済圏に参加していた。
そのため自活の必要上、最少限度の文字算用が要求されていた。
それで大部分の農家の子弟は、当然、読み書き算盤の基礎的な能力が必要となり、寺子屋・塾への積極的就学となった。
寺子の通学範囲は、だいたい一村落(のちの大字)ぐらいの区域であった。
当時の市域の寺子屋は寺院がその役目をはたしているのがほとんどで、相原の昌泉寺・橋本の瑞光寺・小山の蓮乗院・武州小山の福生寺・淵野辺の竜像寺・上鶴間の青柳寺・下鶴間の定方寺・大島の長徳寺・上九沢の梅宗寺・下九沢の金泉寺・田名の南光寺・同宗祐寺・上溝の宝光寺・同八幡宮別当圉覚院・同安楽寺・番田の感応院・下溝の天応院・新戸の長松寺・同常福寺・磯部の能徳寺・同勝源寺その他であった。
塾としては幕末に上鶴間村中和田の古木吉弥、上溝村番田の井上篤斎の塾などがあったが、維新後も引続いて行なわれていたおもなものは、上鶴間の渋谷久左衛門・小方深右衛門、下九沢の佐藤善右折門(和算)、田名の篠崎台右術門、上溝の四谷吉川文左衛門、当麻の天満宮別当杉崎梅明、磯部の栗山半左衛門の塾などであった。
新しく開拓された新田では、本村(ほんむら)の菩提寺(ぼだいじ)へ行くか、入植した百姓のうち多少文字を解する者のところ、すなわち大沼新田の文右衛門屋敷、淵野辺新田の喜右衛門宅、清兵衛新田の氷川神社境内などで読み書きを習った。
これらに学ぶ者は、毎月二五日に月並および天神神酒代として僅少の謝礼を師匠に呈した。
教える内容は、読み書き算盤で、平仮名にはじまり、村名・国尽(くにづくし)・商売往来・今川・古収輯・実語教(じつごきょう)・童子教(どうじきょう)・塵劫記(じんごうき)などで、きわめて少数の者は庭訓(ていきん)往来・四書・五経・文選(もんぜん)などまですすんだ。
寺子の年齢は六〜七歳から通い始め、普通は三〜四年ほどで終えて、それ以上は特別の塾で勉学した。
女子の通学はきわめて少なく、農閑期に裁縫の達者な者のところへお針子としてかようのがせいぜいであった。
一村の就学の割合がどの程度で、文字を知る者の割合が全人口のどのくらいに及んだか、適確な資料がないので不明である。
そう多くはなかったと思われる。
しかし借金証文などをみると、幕末になるに従い、借主自身の筆跡と思われるものが多くなっているのは、寺子屋教育の普及を示す一つの例であろう。
農民の剣術稽古
幕末の市域では農民の剣術稽古が盛んであった。
前述した俳人利角の小泉茂兵衛幸隆は、近藤内蔵之助から天然理心流の免許をうけて、下九沢作の口(さくのくち)の屋敷内に道場を構えて弟子に稽古をつけていた。
市域内はもちろんのこと、隣接する愛甲郡・武州多摩郡にかけて、一八四名の者が門弟連名簿に名を連らねている。
また武州相原の資本家などにも剣客が逗留し、付近の若者たちを指導していた。
それに対し幕府の武芸禁止の触書は、すでに一八〇五(文化二)年に出され、三九(天保一〇)年に百度出されて、各村方(むらかた)ではそれに対する請書(うけしょ)を提出している。
このような触書があるにもかかわらず、あえてその禁止をおしきって行なわれた農村青年の武術稽古は、自己の身心鍛練の必要を感じての目的であったか、常に封建支配に抑圧されていた鬱憤ばらしのためであったか、あるいは幕府崩壊の日を暗々のうちに感じ、明日への百雲の志を夢みて行なっていたものか不明であるが、ときの為政者からは「農業妨げのみにもこれ無く、身分志気がさつに成り行き候基(もとい)」としばしば禁止されていたのであった。
いずれにしろ当時としては士農工商の階級制度の鉄壁を打ち破ることはひじょうに困難なことであった。
そのため天性才能に恵まれ、学問に一生をささけようとする農村の子弟たちは、僧侶になるかあるいは医者になるのでなかったら、その志は達することはできないとされていた。
そしてそれを実際に示したのが、上九沢村の南山古梁であり、上相原村の河津省庵であった。
南山古梁
南山は諱(いみな、本名)は昭眠(しょうみん)、字(あざな、ふだんのよび名)は古梁(こりょう)といい、南山は号で、山庵または南昇山人(なんへいさんじん)とも袮した。
この人は僧侶として名僧知識のほまれが高かったばかりでなく、当時の状勢に対しても常にすぐ
れた見識をもち、行政の才もあるところから、仙台伊達家の顧間格として、いつも重要な問題がある時は参与していた。
またその深い学殖と豊かな詩藻にいたっては、まさに当代に比類がなく、著書も数多く、詩二〇〇○余首、文四〇〇編があげられ、なかでも松島の五絶(五言絶句)は古来絶唱といわれている。
天下有山水 各擅一方美 衆美帰松島 天下無山水
(天下山水有り おのおの一方の美をほしいままにす 衆美松島に帰し 天下山水無し)
書はよくその性格をあらわして一家の風をなし、世人に珍重された。
南山は市域上九沢の出身で、俗姓を笹野といい、一七五六(宝暦六)年の生まれである。
名主政右衛門の次男である。
出家したのは九歳る時で、最初に菩提寺の大島村長徳寺に入ったといわれる。
ついで田名の南光寺に移り六六(明和三)年一一歳の時、江戸高輪の東禅寺に行き九世洪道の弟子となった。
一七六八(明和五)年一三歳のとき、仙台藩主伊達重村が父宗村の一三回忌法要のために東禅寺に詣でた。
この時南山は茶を給仕したが誤って茶碗をくつがえし、公の袴(はかま)の裾にかけてしまった。
公は怒って刀を擬(ぎ)したが、落ちついて過(あやま)ちを謝す南山の態度に感じ、これを許して学禄二人扶持(ぶち)を給し、将来を約束した。 南山はその後ますます修行につとめ、仏典や漢籍を勉学した。 |
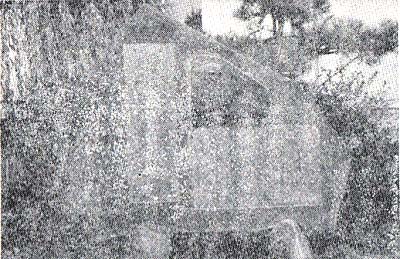
南山古梁の顕彰碑 上九沢他宗寺門前
|
そして全国を周遊して良師を求め、良友と共に才学をみがきあった。
一七九三(寛政五)年、重村の召しに応じ、伊達家三代の廟付である仙台瑞鳳寺一四世の住職となった。
一八〇九(文化六)年には、本山京都妙心寺の一夜住職となって勅旨による紫衣(しえ)をたまわり、帰来引続き瑞鳳・覚範両寺に住した。
八〇歳になって、山庵茶寮を支院内にいとなんで老いを養い、ますます学徳を大成したが、三九(天保一〇)年一一月八四歳で瑞鳳寺支院雄心院で遷化(せんげ)した。
帰郷はあまりしなかったが、いつも郷里のことは忘れず、一七九八(寛政一〇)年には、仙台で父政右衛門の八〇の寿を祝い、著名の士の参集を請うて祝賀の詩文を求め、父のもとに贈っている。
また同年、実家の姉そのが病没のときは、訃報到着の晩と翌朝、瑞鳳寺で衆僧を集めて心からの法事供養をした。
その翌年政右衛門が八一歳で死去した時は、悲痛の情を二首の詩に託している。。
一九六二(昭和三七)年、郷里が中心になり市内外あげての顕彰会が組織され、郷里梅宗寺門前に偉徳顕彰碑を建立した。
河津省庵
河津省庵は、上相原村の河津玄栄の孫で、一八〇〇(寛政一二)年に生まれた。
名は卓、字は子立、省庵は号である。
河津宗は代々医を業としたので、医術修行の後、いったん郷里で開業したが、感ずるところがあり、さらに研究をすすめるため家を出た。
はじめ志摩国鳥羽(とば)で漢法を学び、ついで蘭学を宇田川榛斎(しんさい)・緒方洪庵(こうあん)に学んだ。
一八二三(文政六)年長崎に遊び、おりよく来朝したオランダ医師シーボルトに学ぶ機会を得た。
その後、芳川波山(はざん)を伊豆にたずね漢学を学んだが、波山が忍(埼玉県行田市忍にあった松平氏一〇万石、現在は行田市内)の藩儒(藩につかえる儒者)となるにおよんで、あとをしたって行田(埼玉県)に来た。
行田本町の薬屋大島屋喜兵衛のすすめによって開業し、門前市をなす盛況であった。
やがて藩主松平忠尭の耳に達し、侍医として召しかかえられることになった。
これにはもちろん師波山の推挙があった。
省庵の業績の第一は、当時流行の天然痘に対し、忍藩で最初に牛痘接種に成功したことである。
他に兵器の改良などでも貢献している。一八五二(嘉永五)年五三歳で没した。
著書には『医則発揮』その他八種ある。
top
****************************************
|