|
****************************************
Home 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付録
序章 相模原の大地――その地形と地史――
段丘上の原野
わが町相模原は、神奈川県の北部、多摩丘陵と相模川とのあいだの烏帽子(えぼし)状の相模原台地という台地上に位置している。
この本の目的は、相模原市域の歴史をわかりやすく描くことであるが、そのまえにまず、次の章以下で述べられる歴史の舞台ともいえるこの台地の成立ちについて、簡単に説明しておかなければならない。
さて、この台地は、津久井郡城山町川尻から始り、南東に向かってのびているが、相模原市の南端でその向きを変え、藤沢市・茅ヶ崎市に達している。台地の延長は約三〇キロメートル、幅は四〜八キロメートルである。
この台地には、相模川の浸食・堆積作用による河岸段丘が形成されており、台地の北部をしめる相模原市域には、北東から南西にかけて、それぞれ形成された年代の異なる二つの段丘面――上段・中段・下段――がはっきりとみられるのが、特徴である。
もっとも高く、そして広い面積をもつ段丘面を相模原面(上段)とよび、市域の七〇パーセントをしめている。
この段丘面は水の便が悪く、近年まで開発の手が入らなかったことから、「相模野」とよばれる原野の様相をみせていた。
江戸幕府が、一八三〇(天保元)年から四一(天保一二)年にかけて、昌平黌(しょへいこう)地理局で編さんした『新編相模国風土記稿』という書物の巻之五十九「村里部高座郡巻之口によると、当時の相模野のようすは、
相模野 郡の中程より北端に及ぶ迄一円の曠野なり。
東西一里半に余り南北五里余、過半草莽に属し小松など生ぜし所あり。
野の形状を概していはば、東方(原文のまま)上溝村と西方(同上)上矢部新田の間、殊に狭まり(注を省略)、
宛(あたか)もひさこ(ひょうたん)の如し。
四辺の村々は己が村名を以て接する所に名づく。鶴間野・相原野の類これなり。(以下略) |
とあるように、広々とした原野であった。
このような地形の上にひろがっている相模原市に山がないのは当然であるが、例外的に新磯地区に小高い丘陵が形成されている。
この丘陵は座間丘陵とよばれ、相模原面より一〇〜一五メートルも高い。
さて、このような市域の地形は、どのようにしてできたのであろうか。
市域の地質を探りながら、この地に人間が登場する以前の歴史――いわば相模原の地史をながめてみよう。
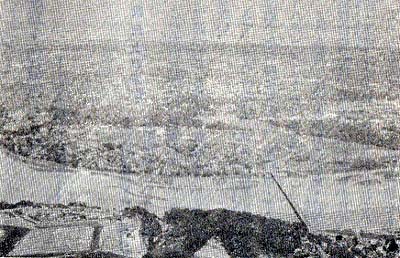
空から見た相模原市 |

小仏層の露頭 写真の中央部、樹木の根元に露岩がみえる。 |
台地の成立ち
相模原市域の地層で地表に露出しているもっとも古いものは、小仏(こぼとけ)層と呼ばれるものである。
小仏層は硬砂(こうさ)岩・粘板岩などからなる黒い岩の層で、大沢地区上大島付近の相模川にのぞむ崖下にわずかにみることができる(右の写真)。
この地層は、中世代白亜紀末期ヽ(約六五〇〇万年前)に堆積したものと考えられている。
小仏層の上に堆積している白い岩の層は、凝灰(ぎょうかい)質の砂岩と泥岩からなるもので、中津層とよばれている。
中津層は、大島から相模川ぞいに、田名(たな)地区の塩田までのあいだで観察することができる。
この地層には多くの貝の化石が含まれ、とくに冷たい海にすむ種類の貝が多い。
この地層が堆積した時期は、鮮新世後期の約二〇〇万年前ころと考えられている。
小仏層と中津層はともに水成堆折岩であることから、当時の市域は海中にあったことがわかる。
またこの時期は、地殻運動の活発な時期で、地層の隆起・沈降が繰返された。
中津層をおおっているのが相模原礫層で、これをさらにおおうのが、関東ローム層とよばれる、いわゆる赤土である。
礫層・ローム層の堆積した時期は、第四紀の洪積世で、多くの段丘はこの時期に形成されている。
関東ローム層は、関東地方に広く分布している地層で、六万〜一万年前に、浅間山・箱根山・富士山など関東平野周辺の火山から噴出した火山灰が堆積してできたものである。
これは、市域全体をおおってはいるが、すべての段丘面に平均に堆積しただけてなく、高い段丘面ほどロームを厚く堆積している。
このことから、高い段丘面ほど陸化が早く、低い段丘面ほど河床となっていた期間が長いと思われている。
もっとも高い段丘面である相模原面(上段)をおおうローム層の厚さは一六〜二〇メートル、中位の段丘面(中段)のうち高い方の中津原面では一〇〜一二メートル、低い方の田名原面では五〜七メートル、もっとも低い段丘面の陽原図(下段)では三〜四メートルとなっている。
ローム層をのせていない沖積面は市域ではきわめて少なく、相模川ぞいの一部にみとめられるにすぎない。
相模原市の歴史は、これまで述べてきたような地形や地質におおいに制約され、消長してきたといえる。
それは、高度に機械化された現代でも同様で、近年の相模原のめざましい都市化現象も、首都圈に属しているという地理的条件と、広大な平坦面という地形的条件とが結びついた現象――つまり、急激に増加した首都圜人口のべッドタウンとして、未開発のまま残されていた広い台地が着目されることとなったのである。
さて以上、相模原市域の地史を大まかにみてきたわけであるが、この関東ローム層の台地の上に、どのようにして、いつごろ、人間の生活が始り、発展していったかを、次にみていこう。
top
****************************************
|