柳生伸也 web
DiscographyScarborough Fair(single)
CD Data
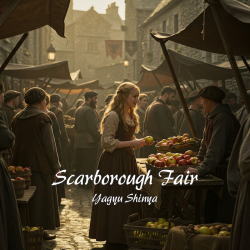
10th Single
6 Tracks
2025年8月13日発売
01 Scarborough Fair
02 スカボローフェア
03 竹田の子守歌
04 Scarborough Fair(Instrumental)
05 スカボローフェア(Instrumental)
05 竹田の子守歌(Instrumental)
Self Liner Notes
Scarborough Fair ライナーノーツ
スカボローフェアと言う歌を知ったのは、父の影響です。
僕の父が『自分が好きな歌』としてこの歌を教えてくれたんですけど、とても不思議な歌だと話をしてくれました。
メロディーラインはとても美しいのに、何かとても不思議な歌、と教えてくれたんです。
成長して英語がわかるようになって、その歌詞を翻訳してみると、確かにすごく不思議な歌詞だったんですね。
この歌では、主人公に誰かが『スカボローフェアに行くんですか?』と尋ねてきます。
そして『そこへ行くならそこに住む人(恋人)にこう伝えてください』と言う訳ですが、その伝えて欲しい内容がとても不思議なんです。
その内容は『自分のために針を使わず縫い目もないシャツを作ってほしい』と言うものや『海と波打ち際の間に1エーカー(約1210坪)の土地を見つけて欲しい』と言うもの、『革の鎌で草を刈ってそれをヒースのロープでまとめて欲しい』と言うような感じで、とにかく『できもしなさそうなこと』ばかりなんです。
それができれば彼女は私の最愛の人になる、という訳ですけど、だとしたらそういうことは難しい、と考えるのが妥当ですよね。
だって、できないことが叶うなら、という事は遠回しに『それはかなわぬ夢』という事なんですから。
そして象徴的に唐突に入れられる『パセリ、セージ、ローズマリーにタイム』と言う、ハーブの名前を連呼したものがまた不思議な雰囲気を際立たせます。
スカボローフェアはアイルランドの民謡なんですけど、アイルランドなどではこうしたハーブ類は魔よけとして使われることもあるという事で、つまり『パセリ、セージ、ローズマリーにタイム』と言うのは穏やかに日本語に訳すとすれば『くわばらくわばら』とか『南無阿弥陀仏』みたいな言葉と考えることができます。
だとすると、主人公に語り掛けてくる誰かは、この世の物ならぬ存在、と考えてもいいかもしれない、と思ったんですね。
何かしらの事情で亡くなった人が『自分はもう帰れない』という事を伝えてもらうがためにそう言う言伝を依頼していると考えられますよね。
こんな話をすると、何だかすごく不気味な世界みたいになってしまいますけど、僕としてはもう一つ解釈があって、それは、本当はお互いが好き同士なのに素直になれないカップルがじゃれ合っている、と言う感じの解釈です。
つまり、お互いがお互いに好きだと伝えたいけど素直になれなくて、何とか相手から好きだと言わせたくて『こういうことができたらお前の恋人になってやる(結婚してやる)』と言っているのかな、という事です。
相手にそれができるなら、自分はあなただけの恋人になるよ、と言うわけで、簡単に言えば『できないなら好きって言いなよ』と言っているという訳です。
それはそれでじれったくて鬱陶しいような気もしますけど。
この解釈だとパセリの意味が分からなくなってしまいますけど、これは合いの手みたいなものですかね、多分。
スカボローフェアと言う歌のメロディーラインは様々なものが伝えられていますけど、僕はその中でももっとも有名と思われるメロディーラインを採用しました。
ちょっと切ないメロディーラインで、僕が最も好きなメロディーラインです。
コード進行に関しては、ちょっと自分なりに作っている部分があって、それはその方がより劇的な感じになると思ったからです。
この辺はアレンジする人の感覚によるところだと思いますし、人によってはまた違うコード進行を採用することもあるんだろうと思います。
アレンジで気を付けたというか、どういう雰囲気でアレンジするかという事を考えた時に、やっぱりもともとアイルランドの民謡だという事で、アイルランドの雰囲気が出るような音にするという事を念頭に置いてアレンジしました。
ですから、アイルランドの民族楽器を比較的多く使っているんです。
具体的に言うと、ケルトの笛の音やハンマーダルシマーも使っているんですけど、これらの楽器の音がアレンジ全体を非常に幻想的な雰囲気にしてくれていると感じています。
その幻想的な雰囲気をさらに高めるために、この楽曲でも主に間奏の部分でドリアンスケールを使っています。
ドリアンスケールは実は前にリリースしたGreen Sleevesにも使われているスケールで、この楽曲も元々はアイルランドの民族ですから、僕の中のアイルランドと言うのは何だかファンタジーの世界みたいな感じなのかもしれません。
実際、日本とアイルランドは地球の表と裏くらいに離れていて、僕にとってはかの国はまだ見ぬ幻想的なあこがれの地だからです。
ちょっとスカボローフェアについてのライナーノーツが長くなってしまったので、そろろろ竹田の子守歌に移ります。
竹田の子守歌は京都の民謡で、描かれている情景は子守をする子供です。
子供が子守なんて、と思うのは現代の感覚で、この歌が作られた当時の日本では、貧しい家の子供は子供と言えども働き手で、10歳にも満たない小さな子供が親元を離れて裕福な家で働くというのは良くあることでした。
そう言う子供たちの仕事の一つがその家の子供の子守だったんです。
ですから、この歌の歌詞に出て来る『守(もり)』と言うのは主人公の子守を仕事にしている子供のことです。
『子守歌』と言うと、普通は赤ちゃんを寝かしつけるための歌、というイメージですけど、今も書いたとおり、この歌はそういう性質の歌ではありません。
あるいはこの歌を聴いた赤ちゃんが、その優しい美しいメロディーで眠ってしまう事もあるのかもしれませんが、この歌はそもそもそう言う目的で歌われていたものではなくて、子守をする子供が仕事をしながら口ずさんだ歌であって、つまり、労働歌と言う性質の歌です。
この歌は実は、ある理由から放送禁止になっていた時期があるという事ですけど、ここでその詳しい内容を書くのは差し控えます。
その歴史は、当事者としては忘れがたいものであると思いますし、今もなお尾を引く問題ではあるんですけど、僕としては個人的にはその問題は『知っている人』が極端に少なくなるかいなくなってしまえば無くなる可能性もあると思う問題ですので、これまでのことを考えれば許しがたいと考える当事者の方がいるとしても、できればそのまま歴史の中にうずもれて、それがどこの問題なのか、という事も歴史の中に消え去ってしまえば良いと思っています。
もちろん、それで過去が全てなくなるわけではないですが、少なくとも未来へ続くものではなくなる可能性はあると思っています。
さて、僕のアレンジ版ですが、ともかくこの歌の情景を音で描きたいと思いましたので、ただのアコースティック・アレンジではなく、より鮮やかに情景を描けるようにシンセサイザーの音も加えてみました。
イントロ部分のきらびやかなシンセサイザーの音は、深々と降る雪をイメージしたもので、聴いてくれる人がそんな情景を思い浮かべてくれたらと思っています。
スカボローフェアと竹田の子守歌は、どちらも今年の春先にレコーディングした楽曲なんですけど、竹田の子守歌をレコーディングするときは頭の中に雪の降る寒くて静かな街並みをイメージしながら歌いました。
かじかむ手で一生懸命仕事をする子供の姿、一日も早く親の待つ実家に帰りたいと思いながら一生懸命働いている子供の姿を思い描いて歌いました。
聴いてくれるあなたの心にそんな情景が浮かぶことを願っています。
ダウンロードはこちらから
・Spotify
Blue Sky
Scarborough Fair
千と一夜の物語
Green Sleeves
Voyager
The 2nd Take Vol.03
The 2nd Take Vol.02
The 2nd Take Vol.01
3月26日
Time Machine
まだ見ぬ君に
記念碑~夏の庭~
Collage
夢よりも儚き
蒼い月
春、広小路にて
Portrait-Acappella
Portrait-Vocodacappella-
I'm on your side
synclassic relax
synclassic02
SORT
1999
翼をください
Mayim Mayim
synclassic
ありがとう
約束
塞翁が馬
青空
SPUTNIK

