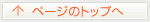よくお客様からこのようなご質問がありますが、決してそんなことはありません。
作業している様子を見ていてはいけない、と思っていらっしゃる方も多いようですが私の場合はまったく気にしません。
というより、むしろそばでずっと見ていていただきたいと考えています。
なぜなら、ピアノの内部がどうなっているのか、どうして音が出るのか・・・などなど、大切なピアノをじっくりと眺めてみることが興味と愛着を増し、
演奏レベルの向上にも役立つものと考えているからです。
また、音をたててはいけない、静かにしていなければいけない・・・これも間違いではありません。
確かに、調律をしている横で、大音量のテレビや音楽をかけられると、それは困ってしまいますが、
し~んと静かにしている必要はありません。例え作業中でも、何か疑問を感じた時は気軽に話し掛けてください。
これらの話は、大人はもちろん、子供たちに声を大にして言いたいですね。ピアノのメカニズムについてなど、学校では教えてくれない大変貴重な
勉強・経験になるからです。たいていの子供たちは、作業前にピアノを分解し始めると、非常に興味津々な目で近づいてきます。
ここで、「邪魔になるから近くに寄っちゃだめ!」と叱ってしまうと、せっかく興味を持ち始めたピアノも、ただの”難しい楽器”になってしまいます。

左の写真は、あるお客様宅でのショットです。まだ私も若かりし頃の写真で、恥ずかしいので少々ぼかしてあります。すみません…。
初めて伺った時のピアノの状態は、何年も放置されていたため音が狂っているどころか、正しく音が出ない鍵盤がいくつもあるという状態でした。
当然、作業も長時間に及びました。
作業開始前、お子さんたちに「見てていいよ。」と、声をかけると、それから終了までず~っと見ていてくれました。
なわとびで床に線を引いて、「ここからは入っちゃダメ!」というお姉さんの礼儀正しい言葉も印象的でした。
しかも終わるころには、「鍵盤が汚いから私が磨こう!」と、もう涙が出てきそうな言葉が…。
共同作業(?)の後は、下の写真のようにすっかり仲良くなってしまいました(笑;)

ピアノの調整作業は、決してきれいなものではありません。
時には叩いたり削ったりと、非常にやかましい騒音をたてたりします。その様子を見ていた子供たちが、私のことをこう命名してくれました…
「ぴあのこうじのおじちゃん」と。
なるほど、確かに「工事」かもしれません(笑)
この子たちは、ピアノが生き返った直後から早速練習を始め、翌日からの練習時間も増え、
さらにタッチにも気を遣うようになったとのことです(レッスン教室の先生:談)
時たま練習をさぼっていると、先生はこうハッパをかけるそうです。
「ぴあのこうじのおじちゃんがくると、今日までどれくらい練習していたのかが、すぐにわかっちゃうんだよ。」と。
う~ん、意外と効果的らしい…。