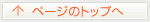えっ、国産ピアノからヨーロッパの音?!

皆さんは、「ヨーロッパ製ピアノ」の音を聴いたことがありますか?
初めて聴いた時、ほとんどの人はその音の違いに驚かれたことでしょう。
「スタィンウェイ」や「ベヒシュタイン」といったピアノと、国産品の音が同じピアノであるにもかかわらず、そこまで違う原因は、基本的な設計思想の違いのほかに、
実はもうひとつ、この「整音」の技術と理論の差にあるのです。
ピアノから鳴る音楽に、人が感じ、感動を呼ぶためには「香り」と「響き」が重要な要素です。
これらがない、もしくは少ないピアノは、表現力に乏しいピアノと言えます。そして、この要素を作り出す作業こそが「整音」なのです。
国産メーカーのピアノは、子供からピアニストまで、誰でも弾けることを前提としていることもあって、残念ながら 本来の良さは秘められた状態になっています。そこで、まず「整調」、「調律」によって、年月による部品の劣化を、 出荷時の状態まで戻しておくことが必要です(※)。その上で、ピアノの秘められた能力を徐々に引き出していきます。 この技術を施したピアノは、メーカー独特のクセが消え、全く別物として生まれ変わることに、皆さんは驚かれることでしょう。
(※)ピアノのメンテナンスに「整調」「整音」「調律」がある。
ここでは、アクション各部の調整である「整調」、音律を正す「調律」が完了していることを前提とし、
その上でハンマーの硬度分布を調整する「整音」を施すことを意味する。
それにはもちろん根拠があります

日本のピアノメーカーの技術はかなり高度なものです。 特にY社やK社製は、工業製品的な精度の高さを誇り、定期的なメンテナンスさえ行っていれば、 何十年でも健康な状態を保つことが可能です。 つまり、これらのメーカー製は壊れにくく、適正な湿度環境さえ保っていれば、長期放置からの復活作業においても、 最低限の修理で修復可能なのです。
写真はドイツにある某大手メーカーの工場でのひとコマですが、重要な作業は現在でもその多くが手作業です。
もちろん欧州製でも機械化されているメーカーもありますが、一流と言われるメーカーほど、手作業・人間の手による
調整を重視しています。伝統を受け継いだノウハウを継承した結果、前述した「香り」や「響き」という点では
国産とは比べものにならないアイデンティティが生まれます。
これは、ピアノや楽器だけでなく、自動車や家具、ファッション界などでも欧州品が優れていることに、多くの共通点があります。
例えば、ドイツの自動車は、コーナリングフィールや高速走行での安定性には目を見張るものがあり、
何より非常時の安全性レベルの高さは、国産メーカーには真似できない技術とノウハウを持っています。
反面、欧州の自動車は、国産オーナーの予期せぬところが壊れますが、国産車はある程度の年式を超えなければ故障はほとんどありません。維持管理が難しいことも、ピアノと自動車では共通している点です。
また、欧州の自動車は、同じメーカーあればすべてが同じ乗り味です。 例えば、メルセデスの普及価格帯であるCクラスに乗った方が、「このクルマのゆったりした走りは好きではない…」と思われたら、 最上級グレードのSクラスに乗っても、メルセデスが気に入ることはなく、気に入ったクルマを探すにはメーカーを変えるしかないのです。 ピアノも同様に、例えばスタインウェイは、アップライトもコンサートグランドもどれも同じ傾向の音がします。 正確には、時代によって音はかなり違うのですが、それでもどのスタインウェイにもスタインウェイにしかない音の要素が存在します。 もし、スタインウェイの音が好きではないとおっしゃる方がいらしたら、その方の好みはベーゼンドルファーやベヒシュタインであるはずです。
話が少々横に反れてしまいましたが、つまりは「日本の技術と欧州の技術とでは、考え方に大きな違いがある」、ということです。
その根拠についてですが、国産メーカーの技術は、いわゆる「数値第一主義による工業製品」としての性格が強く、
そのため楽器として肝心な「音色」が犠牲になっているわけです。
いくら 「数値」に合わせても、決して良い音がするはずはないのに、日本における技術者研修では、「数値」に合わせるように教わります。
私はこのことに大きな疑問を抱き、ドイツの三大名器であるグロトリアン社、ベヒシュタイン社にて学ばれた師匠に弟子入りしました。
そして、欧州の主要なメーカーの工場を訪問し、その方法が実際に行われていることをこの目で確認してきた上で、
現在も更に技術を吸収すべく、定期的な修行を続けております。
国産ピアノのほとんどは、欧州のピアノを基に設計してあるため、調整方法を欧州式に改めると、本物には及ばないまでも
数値第一主義による調整では出てこなかった、音の香りや響きが現れてきます。
では、具体的な調整方法について、以下で解説していきましょう。
具体的な調整方法と作業の流れ
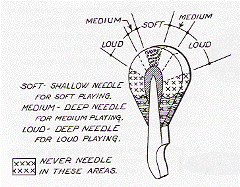
まず最初に行なうのは「掃除」です。何だ、まだ整音じゃないのか・・・とガッカリしないでください。埃が残ったままにしておくと、高次倍音が失われてしまうばかりか、ノイズの原因にもなるため、まずは鍵盤の下からアクションの細部まで、埃を取り去り、磨きます。更にピアノの裏側 (グランドは下側)の埃も取ります。
過乾燥や多湿によるものなど、故障が起きていれば、先行して修理をしておきます。
その上で、鍵盤のタッチを最適な状態に戻していくためにアクションが正しい動きをするように調整します。
加えて、ハンマーが弦に当たる位置や角度(水平)も調整します。
(ここまでの作業を「整調」といいます。)
次に、調律によって正しい音律を取り戻します。ここまでくれば、出荷時の音質は随分戻ってきますが、
まだまだ「いつまでも弾いていたい音色」とは言えない状態です。
このあと、本命の「整音」作業に入る訳ですが、その前に弦の振動をボディにきちんと伝えることを目的とした作業を行ないます。
つまり、ハンマーやアクション部分だけではなく、ピアノのボディにまで手を入れていくわけです。
※師匠直伝・当事務所独自のノウハウです。
これは弦楽器ではもっとも重要な要素である「倍音」(特に高次倍音)を取り戻すためのもので、結果として「鳴るピアノ」に生まれ変わりますから、
この段階でも既に別のピアノになったように感じます。バイオリンやギターなど弦楽器を演奏される方は、ボディの振動を
身体で感じていらっしゃいますよね?
実は、ピアノにおいてもこの要素が非常に重要なのです。
ここからいよいよ、ハンマーのフェルトに存在する「硬度分布」を、針を使って調整します。
いわゆる「音色作り」の作業で、ここが一般的に整音と言われている作業です。
しかし、ハンマーのどの位置に針を入れるか、これも国産と欧州機メーカーとでは、考え方が大きく異なります。
上右図は、標準的な欧州式整音のポイントです。
国内メーカーは、一般的に図のMEDIUMポイントのみに針入れを行いますが、国産ピアノでフォルテ時の和音がひとつにまとまって聞こえないのは、
これが大きな原因のひとつであると考えます。
国産メーカーの手法による整音は、主として隣の音との音色を揃えることにあります。もっとも、これも整音において重要な要素ではありますが、欧州式の整音を学ぶと、これは最終過程における調整のひとつに過ぎないことがわかります。音を揃えただけでは、国産ピアノから欧州機の音がする、とは言えません。
ではどうするかと言いますと、整音作業の本来の目的とも言える、音色変更という部分にまで踏み込むのです。
ハンマーの針を入れるという手法としては同じですが、1本当たりのハンマーに針を入れる回数は、国産メーカー手法とは比較にならない程多く、針を入れる深さもハンマーの奥深くにまでしっかりと入れていきます。
国産メーカーの技術者氏にこう言うと、「そんなことをしたらハンマーがブヨブヨになって、音がこもっちゃうよ!」という答えが返ってきますが、それは針を入れる位置が違うためで、適切な位置に針を入れると、実は音はこもることなく、逆に立ち上がりの良い音が出てくるのです。物理的に言えば、空気の層を適切な箇所に適切な量で作り直すということですが、もちろん刺し過ぎるといわゆるオーバーブッシングという状態になり、音はこもってしまいますので、適量の空気層ができたことを、針を入れる時の「感触」で見極めることが重要です。
ところで、ピアノの音をひとつ弾いてみると、それぞれの音に「母音」があることをご存知ですか?
「イー」と聴こえたり、「エー」だったりしますね。
しかし、これらの母音の音では弾いていて疲れてしまいませんか?
理由は、音像そのものが「開いて」聴こえるためで、この開いた音を「オー」という、閉じた母音の音像に揃えておかなければなりません(※)。
音像がすべて閉じたピアノは、長時間弾いていても耳の疲れない音色になります。さらに、最終調整における「香り」がプラスされることで
そのピアノの持つ本来の音が蘇ってくるわけです(※)。
あなたのピアノからヨーロッパの香りがすることを想像してみてください。
きっと、ピアノの前から離れがたい気持ちになってしまうでしょう。
ここまでご覧になって、信じられない方は是非一度体験してみてください。決して後悔されることはないと確信しております。
(※)これら整音・音色の説明については、我が師独自の解釈と表現が含まれます。
なお、ヨーロッパピアノのご購入を検討されている方は、各社取扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
整音料金のお見積もりについて

当方での整音とは、上述のように「ハンマーに針を刺す」作業だけではありません。
まず整音ができる状態まで基本的なメンテナンスを施す必要があります。
加えて、国産ピアノに多く見られる、ボディ全体が振動しなくなっているものは、まず弦の振動を、
響板>ボディにきちんと伝えるための修復を行います。この修復を怠ると、せっかくの
弦の振動が途中で止まってしまい、結果として美しい倍音が死んでしまうのです。
つまり、整音を施すためには、故障修理 > タッチ調整 > 調律が完了していることが前提であり、
これらどの過程にも音色が変化(劣化)する要素があるため、どの作業を省いても良い結果は得られないのです。
以上のことから、まずは故障やタッチ調整の不良を修復し、整音が行える最低限の状態に持って行くことが必要であることが
おわかりいただけたと思います。そのため、整音をご希望の方には、まずメール等で現在の状態を詳しくお尋ねし、
完成レベルのご提案と、おおよその料金をご提示します。そして、実際にピアノを拝見した上で、そのピアノにあった調整方法をご提案しております。
また、いきなりお持ちのピアノの限界までチューニングすることも可能ですが、初回は欧州式タッチ調整による音の変化を楽しんで頂き、
次回以降徐々に手を加えて2~3年計画で段階的に良くしていくこともオススメです。
まずは整音に入る以前の段階である、整調という最低限のチューニングからでも音は確実に良くなりますから、是非お試しください。
ちなみに、お持ちのピアノが以下の症状に該当する場合は、整音までは必要ないケースがほとんどです。
・多湿によって音の伸びが妨げられている場合>>故障修理と環境改善
・乾燥によって音が甲高い方向へ向いている場合>>故障修理と環境改善
・各音にバラツキがあり、その原因が各部動作範囲のバラつきにある場合>>整調、または修理
・同様に各音にバラつきがあり、その原因がハンマーの摩耗にある場合>>修理後、整調
・音量のコントロールが難しい>>整調、または修理
・調律が不安定であることによる音色の不良>>調律と場合により環境改善
・前任者の流派的要素による、ユニゾン調律の音色がお気に召さない場合>>調律
逆に整音が必要なピアノの条件とは、
調律が安定していてタッチ調整にも不満がないにもかかわらず
・音の表現力に不満を感じる
・音色が味気なく、色気がない。音が痩せている
・もっと馬力や派手さを求めている(耳障りな要素ではありません)
・弾いていて疲れる音がする(平たく言えばうるさい音。良い音は疲れません)
・基音に、本来あるべきではないノイズに分類される倍音が乗っている
・和音がひとつにまとまらず、バラバラに聞こえる
これらの要素は、いずれも整音が必要な可能性が高いものです。
お持ちのピアノが該当するようでしたら、是非お気軽にご相談くださいませ。
お見積り・ご提案は、メール、ご自宅訪問とも無料です。
見積り結果で折り合いがつかなかった場合、料金は発生しません。
ただし、有料道路経由での見積り出張は、交通費のみご請求させていただく場合がございます。
本当に音が変わるのか?

これまでご説明してきたように、当方における整音は、あなたのピアノの音色を確実にグレードアップさせることが可能です。 とは言え、いくらネット上でご説明申し上げても、所詮自画自賛的広告でしかありませんので、ここでユーザー様のブログをご紹介しておきます。
まず1件目は、リンク集でもご紹介している、ピアノ教室ぴこ先生の日記です。ご使用ピアノはドイツの名器ブリュートナーのグランドです。 整音によって音が変わる様子はもちろん、日頃のメンテナンスについても作業の様子を大変わかりやすく記録していただいています。
お勧め記事(更新の新しい順に並んでいます。)
ブリュっち調律!! http://picopico129.blog.shinobi.jp/Entry/207/
GW (整音最終仕上げの記録) http://picopico129.blog.shinobi.jp/Entry/117/
変身!!(整音作業過程の記録) http://picopico129.blog.shinobi.jp/Entry/114/
ブリュちゃん調律!!(整音前の調律記録) http://picopico129.blog.shinobi.jp/Entry/68/
続いて、ピアニスト・作編曲家であり、最近は音楽療法士としてもご活躍の大塚彩子先生のブログでも、
当方の作業記録を取り上げていただいています。
当サイトの名器コーナーでもご紹介している、イースタイン製アップライトの最高峰であるB型をお持ちですが、
他社様から中古でご購入後の音がお気に召さないというご相談から、徹底的に手を入れてみました。
国産ピアノが整音でどこまで変わるのか、プロのご意見をご覧ください。
ブログトップページ
お勧め記事(更新の新しい順に並んでいます。)
ピアノの大修理 http://todaysseaway.ttcbn.net/?p=1639
イースタインというピアノ http://todaysseaway.ttcbn.net/?p=468