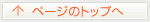ピアノ調律師 砂田一樹 プロフィール
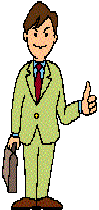
1960年代後半生まれ。7歳より クラシックピアノを始める。
ピアノ調律技術・整調・整音技術を、業界で唯一の整音理論論文
『整音の理論と実際』の著者である田中英資氏に師事。
また、『ピアノ調律・整調・修理の実技』の著者、故 竹内友三郎氏の孫弟子に当たる。
学生時代は中国語(普通話)を専攻する傍ら、ロックバンドに熱中。
しかし、なぜかキーボードではなく、ドラムスを担当。
演奏ジャンルは、一見調律師のイメージとはほど遠いヘビーメタル。
この手の音楽に詳しい方には、スラッシュメタルと言えばおわかりいただけるだろう。
学生時代からのメンバーとともに、結成から20年以上の活動期間を経て、現在はメンバー全員が子育て世代であることなどから規模縮小傾向にある。
大学卒業後、一旦は専攻を活かして半導体貿易商社へ勤務するが、組織の一員であることに違和感を感じ、数年後に退社。
退社後は自分にあった職業を模索。結果、<好きなことを職業に>と考える。
やはり大好きな音楽で生きていこうとロックバンドでのプロデビューを目指し、実現できそうになった時期もあったが、現実はそう甘くはなかった。
もうひとつの選択肢として、幼少の頃より模型作りに熱中していたことから、
手先の細かな物づくりを職業としようと考えるが、理科系を進んでいないことと、やはり音楽を捨てられずに悩む。
悩んだ末に到達したのが、音楽性とメカ的要素を兼ね備えた調律師という選択。
しかし、調律学校の学費の高さや年齢制限がネックとなり、昔ながらの師匠への弟子入りという選択で目指すことを決意。
某大手メーカー出身の(前)師匠が、弟子を募集していることを知る。
入門後、師の仕事に同行しながら数年の修行を続け、社内の修了試験に合格することを目指す。
修行期間中は当然収入はほとんどなく、アルバイトをしなければ生活が成り立たない日々が続く。
無事終了試験にも合格し、ようやく少しずつ仕事を任せていただけるようになった頃、晴れて独立することになるが、
この頃運命的に新たな師匠と出会う。今まで自分がやってきた技術がいかに次元の低い物であったかを思い知らされ、
改めてピアノの世界の奥深さを痛感する。
その後、更なる技術向上のために、新たな師の元で修行を開始。欧州の歴史に残る世界的名器を完全な状態に復元する、
いわゆるオーバーホール技術、および国産ピアノにおける更なる技術力の向上、ピアノの持つ潜在能力を最大限に引き出す
整音技術を習得するため、師の厳しい指導が始まった。
師の元へ入門して早20年近くが経過した現在も、定期的に師の工房を訪れ、師の手掛ける名器の修復に係わりながら、
さらにはヨーロッパでの定期的な研修や、イェルク・デームス先生を始めとした一流ピアニストとの交流の場を与えてくださる恵まれた環境の中で、
日々精進を続けている毎日である。
「音作りのコンセプト」 は、教科書通りの「数値第一主義」という概念を排除し、あくまでもすべての作業において「音色」を重要視すること。
加えてアコースティック楽器であるピアノにも、PCやスマートフォン等のデジタル技術を積極的に取り入れ、デジタルとアナログの限りない融合を目指す。
また、調律師としての最も大切な仕事とは何か・・・お客様がピアノをお弾きになるに当たって、メカ的な原因のあるストレスがあってはならない。
言い換えれば、「ピアノが続かないのは、ピアノの音が悪いからである」と考え、プロならではの視点でピアノを選定し、
素晴らしい調律と整音を施すことで、「ピアノに触れたい、弾いていて楽しい、いつまでも弾いていたい」と、日々感じていただけるピアノを作り出すこと。
これは我が師匠の口癖であると同時に、非常に厳しく身をもって教えられ続けているモットーである。