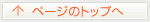調律の技術解説や料金のご案内です。調律の必要性や料金のしくみ、出張可能エリアや費用についてもご案内します。
ご相談やご用命は、かんたん見積もりフォーム・電話・メールなどからお気軽にどうぞ。
当事務所では、確かな技術をご提供します。調律技術解説

ピアノは非常にデリケートな楽器です。
他の楽器はたいていの場合演奏者自身がチューニング(調律)しますが、
ピアノの調律には1/100秒単位での調整が必要であることや、調律以外にも様々な調整が必要であることから、 専門の調律師が必要なのです。
しかし、調律師によってできあがる音は十人十色で、その技術力や手法をみても、皆同じではありません。
ピアノの調律は、次のような手順で行います。
1. まず、中央のオクターブを使って 音階作り (割振り) を行います。
2.できあがった音階を全体にばらまきます (オクターブ調律)
3. 最後に弦が複数あるものを 同じ音にそろえます。 (ユニゾン調律)
これらの作業には、もちろん教科書的なマニュアルが存在します。
調律師を目指す場合、通常その教科書に沿って技術を習得します。
ところが、教科書通りに技術が習得できれば皆同じ音になるかというと、実際はそうではないところが、アナログの奥深さでもあります。
では、調律師によって音に違いが出るポイントはどこ にあるのでしょうか。
まず、1:音階作りにおいて、 中央のオクターブ12音を使用して各音の間を均等に分割することで、音階を作る作業を行います。
これを平均率による割振りといいます。
どの技術者も「オクターブ12音の間隔を均一にする」という目指すところは同じなのですが、
この手法が実は多種多様であり、技術者によって使用する音域や基準音が異なるために、
結果的に作られるその音階には違いが現れてくるのです。
次のポイントは、2:オクターブ調律です。
人間の耳は、正しく合った高い音は低く聞こえ、正しく合った低い音は高く聞こえる特性を持っています。
そのため、この特性を補正するために高音は高めに、低音は低めに調律した方が音楽的に美しく聞こえます。
どの音から高くする(低くする)か、どの程度上げる(下げる)かという明確な基準はなく、技術者の感性が要求される部分です。
これを「調律曲線」といいます。
大手メーカー推奨の手法は、限りなく調律曲線のカーブがフラットですが、当方における調律曲線は、基本的には若干きつめのカーブを描きます。もちろん、ご要望や演奏レベル、演奏される曲やジャンル等によって加減させることも可能です。
例えば、よくお弾きになる曲がリストとバッハでは、調律曲線のカーブも異なるというわけです。
最後のポイントが、最も重要な 3:ユニゾン調律です。
これは簡単に言えば、ひとつの音に複数ある弦を、いずれも同じ音に合わせることです。
調律師を目指す時に一番最初に教わる技術ですが、最初は当然ながら合わせる事の練習に集中し、ある程度合わせられるようになってくると、今度は一定期間調律を保持するという、大きな壁が待っています。
そして、一定基準で保持ができるようになって早ければ数年後、2つの音がピッタリ合ったポイントからの狭い範囲に、
実は音色がいくつも存在していることに気付きます。「音色を調整」する必要性に気付いてからが実は長い道のりで、
コンサートでの調律を任せられるレベルに到達するには、少なくとも5年~10年は楽に掛かります。
このことから、<調律はユニゾンに始まってユニゾンに終わる>と言われるほどで、ユニゾンの音色調整には明確な基準がありません。
当然教科書にも載っていませんから、技術者が師匠の音を何度も繰り返し聞きながら、経験的に培っていくしか方法はなく、結果的に調律師には十人十色の音色が存在しています。
感性の良い方は、このユニゾンの音色で調律師を当てることができるほどで、それほどピアノの音色を決定づける重要な要素です。
当方によるユニゾン音色をあえて言葉にしてみますと、師匠直伝による<明るく立ち上がりの良い音><倍音の持続時間が長い音>というのがが最大の特徴であり、
なおかつ<良い音は決してうるさくない>という持論を元に音作りを行います。

ここまで、調律によって美しい音色を作り上げるポイントをお話ししてきました。できあがった音色が美しいことはもちろん重要ですが、
それ以上に大切なのは、「美しい調律が狂わないこと」です。
いくら上手く調律ができたピアノでも、翌年の調律までに、メチャクチャに狂ってしまうようではとても実用に耐えられませんね。
調律の作業そのものは、ただ「チューニングピンを回している=ネジを回している」だけに見えますが、
この張力の保持ができ始めるまでに、どんなに早くても数年の経験が必要です。
つまり、経験数年までは狂いやすい調律になってしまうのが当然なのですが、台数を重ねることによって、だんだんと「狂わなくなる」のです。
ピアノの張力は、温湿度変化によって常に変化しているため、「狂わなくなる」というより、全体に平均して下げることによって、<(ピッチが)下がったことがわからない調律をする>、という方が正解です。さらに何十年も経験を積まれた師匠ほか先輩諸氏は、
<下がる速度が一定の上に極めて遅い>、という調律をされますが、これは私が調律師として日々切磋琢磨している最終目標でもあります。
なお、調律の保持をするためには、適切な湿度管理が必須条件です。
床暖房をご利用の環境や、エアコンの直風、直射日光が当たっているピアノは、過乾燥によってチューニングピンが緩くなってしまうため、
調律の保持ができないピアノになってしまいます。
ところで、ピアノという楽器は、その構造上 「数値による調整」 のみでは、その能力を 100%引き出すことはできません。 確かに、メーカーの推奨する「数値」 にあわせることも大切ですが、このような音作りのされたピアノは いわゆる 「味気ない音」 を出し、長時間聞いていると疲れてしまいます。 ピアノの調整において、この 「数値」 を超えた「香り」を作り出すことが最も重要な要素で、調律師の芸術的感性が一番大きく現れるところ でもあります。 いくらピアニストの演奏テクニックが優れていても、この要素がなければ、感動は半減してしまうことでしょう。
私は、入門当初 Y社出身のコンサートチューナーである師匠に弟子入りをして、調律技術を学びました。
その師匠の元で数年の実務経験を経たある日、欧州ピアノとの出会いが訪れます。その音と技術の差に、ある種のカルチャーショックを受けてしまった私は、疑問追求のため、その道の第一人者である新たな師匠の門を叩きました。
ピアノを本当に知り尽くすためには、まだまだ勉強することが山の様にありますが、師匠の援助もあって、お客様には今まで以上に満足のいく音をご提供することが可能になりました。
音の違いを自信を持ってお勧めできるのは 上記の理由からです。
是非、あなたの耳でこの音を確かめて下さい。
なお、本格的に「音の香り」を求められる方、「調律しても音が悪い」「うちのピアノは音がこもっている」等のお悩みをお持ちの方は
是非「整音のご案内」 をご覧下さい。
作業前には十分なご相談をお願いしております。

当方では、ピアノの調整をお任せいただく際、 作業前に十分なご相談のお時間をいただいております。
例えれば、病院におけるインフォームドコンセントのように、故障状況や修復方法を分かりやすくご説明し、
お客様の同意を得ることが、ピアノの調整に当たって重要であると考えます。
ピアノは設置環境や使用頻度の違いから、1台1台異なった個性を持っていますので、特に初めて出会ったピアノは、
念入りに内部の状態を点検し、状態に応じた必要な修理や調整の方法を十分にご説明の上、作業に入らせていただきます。
故障していることが既にお気づきの場合はもちろん、「治らないもの」とか「こういうものだ」と、諦めていらっしゃるお悩みも、どうぞお気軽にご相談下さい。
解決の余地がある問題であるか、構造や環境上仕方のないものであるか、どのような点に関しても明白な根拠の上で、ご説明申し上げます。
また、更なる音色やタッチのレベルアップをお望みの場合、現状ご不満な点や音の好みの傾向を正確に把握する必要があります。
お客様とご一緒に現在の状態を検証し、その上でどのような状態に仕上げるか、ご予算とお好みに応じた調整内容をご提案致します。
長期間放置をされたピアノについても、必須調整項目と推奨調整項目に分けてご提案を申し上げますので、ご予算に応じて、
場合によっては数年かけて段階的に良くしていく方法もご選択いただけます。
以上のことから、特に初回は作業前に十分なお時間をいただきたく、調整内容の確定までは、是非ご一緒にピアノの側でご覧ください。
もちろん、作業中引き続きご覧いただくことも大歓迎です。
調律の必要性、および料金のしくみ

プロピアニストの調律は演奏会ごとに毎回行いますが、一般のご家庭ではアップライトは年に一度、グランドはできれば半年に一度行う事をお勧めします。
また 音大生の方やピアノを職業とされている方の場合は半年に一度、 店舗で営業用にご使用のピアノは3ヶ月に一度以上をご検討下さい。
ピアノの弦の数はモデルによって異なりますが、全長180cm程のC3タイプのグランドで約230本、フルコンサートグランドにおいては240本以上もあり、1本当たり平均90kgの力で張られています。そのため弾かなくなったピアノも次第に張力がゆるんできます。
つまり、調律から時間が経過するとだんだん音が下がってくるわけです。更に、日本のピアノには湿気という大敵が存在するため、弦にサビが生じてきたりします。
毎年定期調律を行っていれば、このような害も最小限に食いとめることができますが、10年以上も放置しておいたものなど、
元の状態に戻す事は決して容易ではありません。当然、料金もその分多くかかります。
以上の観点から、当事務所の料金は以下のようなしくみとなっております。
| 調律料金 | 基準により定めています。詳しくは後述します。 |
| 修理料金 | 故障箇所がある場合、別途修理料金が必要です。 |
| 整調(タッチ調整)料金 | 鍵盤を弾いた感触を整え、正しい運動性能を回復します。 |
| 部品・用品代 | 修理に使用した部品や、防音用品等の商品代金です。 |
| 消費税 | 上記金額の合計に、別途消費税が掛かります。 |
| 出張費用 | 東京23区内は無料です。その他の地域については後述します。 |
| 駐車料金 | 有料駐車場を利用した場合、ご負担をお願いいたします。 ご利用金額に応じて割引きがあります。 |
調律料金は、 ピッチの低下基準により決定致します。
前回調律日がある程度の目安となりますが、設置環境やピアノの状態により前回調律日とピッチの低下基準は、必ず一致するものではありません。
調律料金の決定は、チューニングメーターを使用してお客様に現状のピッチ(音の高さの基準)をご確認頂いた上で 決定させて頂いております。管理状態等により、ピッチ低下率は異なるため、経過年数による数値は目安となります。
また、ピッチ低下率と未調律期間を比較し、年数の基準より低下していない場合でも、長期間の放置はピッチを安定させることが難しいため、
年数相当の料金がかかります。
逆に、定期調律を繰り返していたにもかかわらず、ピッチが下がってしまうものは、設置環境や前任者の技量問題等、
何らかの原因があるはずですので、この場合はピッチ低下基準を優先させていただきます。
定期調律時のピッチ変更について、現状からピッチを上げる場合は、下記料金表の基準にて適用させていただきます。例えば、10セントまでは割り増しは不要ですので、440Hzから442Hzへの変更では料金は変わりません。現状からピッチを下げる場合は、別基準による料金となりますので、詳しくはお問い合わせください。
(※注1)当方による定期調律では、ピッチ低下率は問いません。ただし、床暖房等ピッチを低下させる要因がある環境を除きます。
なお、ピアノのメンテナンスにおいて、調律は最後の仕上げです。 調律を行う以前に、故障修理はもちろん、打弦の運動をスムーズにするタッチ調整を行なう必要があります。 下記調律料金には、音が出ないなどの故障、タッチ調整については含まれておりません。 ただし、当方による毎年の定期調律においては、無料調整項目を定め、その範囲でのタッチ調整の点検、 部分的な故障や調整等軽微な内容の調整は、調律料金内で行わせていただきます。
| ピアノの種類 | 前回調律日 | ピッチ低下基準 | 料金(税込み) |
| アップライト | 1年前(当方による定期調律) | 不問(※注1) | 13,000円(14,300円) |
| 1年前(新規の方) | 10セントまで | 13,000円(14,300円) | |
| 2~3年前 | 10~15セント | 15,000円(16,500円) | |
| 3~5年前 | 20セントまで | 16,000円(17,600円) | |
| 5~10年前 | 部分25セント | 18,000円(19,800円) | |
| 10年以上前 | 下記をご覧下さい | ||
| グランド | 1年前(当方による定期調律) | 不問(※注1) | 16,000円(17,600円) |
| 1年前(新規の方) | 10セントまで | 16,000円(17,600円) | |
| 2~3年前 | 10~15セント | 18,000円(19,800円) | |
| 3~5年前 | 20セントまで | 20,000円(22,000円) | |
| 5~10年前 | 部分25セント | 23,000円(24,300円) | |
| 10年以上前 | 下記をご覧下さい | ||
| コンサート調律 | 不問(フルコンサートグランド) | 不問 | 20,000円(22,000円) |
| (発表会を含む) | 不問(セミコン以下のグランド) | 不問 | 18,000円(19,800円) |
| アップライト | 上記基準通り | 上記通常調律と同額 | |
| 立ち会い料金(リハ終了まで) | 10,000円(11,000円) | ||
| 立ち会い料金(本番終了まで) | 15,000円(16,500円) |
業務用にご使用のピアノは、短期間割引がございます。
放送局・スタジオ・飲食店等の営業用 、ピアニスト・作曲家等ご職業でご使用の方で、
頻度の多い定期調律(概ね3ヶ月以内)は、ご予算に応じて承ります。
ただし、年間定期調律料金に含む軽微なタッチ調整等は、調整のレベルやズレの度合いに応じて別料金となる場合がございます。
詳しくはお見積りいたしますので、お気軽にご相談下さい。
ピッチ低下基準の単位=セント
音の高さ(ピッチ)を表す周波数の単位がHz(ヘルツ)であり、調律を行うにはピッチをA(ラ)の音を基準に、440Hz、441Hz、442Hz等ご希望の高さに合わせます。
ピッチの世界基準は440Hzですが、クラシックピアノの場合は、主に442Hzが使われます。
声楽曲の場合は440Hzも多く使用され、ジャズやポップス等ポピュラー界では441Hzが標準です。
最近では、古典調律時代の低いピッチが心地良いとか、DNAを修復すると言われる高い周波数が癒やされるなど、上記3種類のピッチに拘らない動きもあります。
このように、ピッチをいくつに設定するかは様々ですので、いずれのピッチからでも調律が低下している基準を設ける必要があります。
その単位が「セント」で、各音程がどのくらい下がっているかを判断する基準とします。
セントとは、その名の通りパーセント(%)のセントで、1/100を表しています。
1ドルの1/100が1セントであるように、貨幣の単位ではお馴染みです。
もう少し詳しく説明しますと、ピアノは通常「平均率」という方法(音階の作り方)で調律しますが、平均率においてはオクターブ12音間を等間隔で分割します。
つまり、12の等しい間隔の半音を持っているのが平均率です。このオクターブを12等分したものもセントで表し、
各半音間が100セント、全音間が200セント、1オクターブが1200セントということになります。
調律の料金をご提示する際、例えば長期間調律をしていないピアノを前に、「416Hzまで下がっていますね。」と言われても、
専門家でなければどの程度下がっているのかイメージがわかないと思います。
しかし、白鍵と黒鍵の間を100セントとして、「80セントも下がっていますね。」と言われると、
ラの音が限りなく隣のソ#の音に近くなっているということですから、どなたでもその下がり方の著しさが想像できると思います。
ちなみに、1Hzはおおよそ4セントです。
複数台同時の定期調律を割引します。
2年目以降の定期調律において、複数台同時にご依頼の場合は、以下の基準にて割引いたします。
(同設置場所、同時期作業の場合のみ)
アップライト 1台目13,000円、2台目12,000円、3台目以降11,000円。
グランド 1台目16,000円、2台目15,000円、3台目以降14,000円となります。
グランドとアップライト同時の場合は、1台目をグランドとして計算します。
ただし、床暖房等ピッチ低下の要因がある環境を除きます。
長期間(10年以上)調律をしていないピアノについて

長期間調律をしていない場合の料金は、下表の通りです。
ただし、これは調律料金としての一覧であり、修理やタッチ調整といった調律を行うために必要な付帯作業料金は含まれておりません。
つまり、長期間にわたってメンテナンスをされていないピアノは、調律のほかに修理を伴う場合がほとんどですので、
このほかに修理や調整料金が必要です。
写真のキャラクターがジッと見つめているのは、一見何ら故障はないように思われたピアノが、裏から覗くと
ハンマーがこのようにパックリ口を開けていた様子です。
上記の繰り返しとなりますが、ピアノのメンテナンスにおいて、調律は最後の仕上げです。調律を行う以前に、このような故障修理はもちろん、
打弦の運動をスムーズにするタッチ調整も合わせて行なう必要があります。
下記調律料金には、音が出ない、ノイズの発生などの故障、
タッチの再調整については含まれておりません。
このように、当方では<調律のみ>という調整ではなく、故障の修理はもちろん、タッチ調整や音色調整といった、
ピアノを演奏するために必要なすべての修復・調整項目をご提供いたしております。
長期間放置されたピアノの「修理を含んだお見積り」は、一度拝見させて頂かなければ正確な金額をご提示できないのが現状です。
お問い合わせを頂いた時点で過去のデータを参考におおよその金額をお知らせしますが、正確なお見積りをご希望の方は、
無料にて出張いたしますのでお気軽にお申し付け下さい。 もちろん、ご予算を超える金額の場合は、キャンセルして頂いても結構です。
湿度管理が良好な場合は、長期間の放置でもコンディションの良いピアノも多数存在しますので、まずはご相談ください。
(ただし、事前の見積り額がご予算以上であっても、出張による正確な料金算出をご希望の場合は、有料によるお見積りとさせていただく場合がございます。また、出張費用が必要な地域への見積り出張については、規定交通費のご負担をお願いいたします。)
| ピアノの種類 | 前回調律日 | ピッチ低下基準 | 料金(税込み) |
| アップライト | 10~20年前(当日仕上げ) | 部分30セント | 20,000円(22,000円) |
| 10~20年前(2回訪問) | 全体30セント | 25,000円(27,500円) | |
| 20~30年前(2回訪問) | 40セント | 25,000円(27,500円) | |
| 30年以上前 | 50セント以上 | 25,000円(27,500円) | |
| グランド | 10~20年前(当日仕上げ) | 部分30セント | 25,000円(27,500円) |
| 10~20年前(2回訪問) | 全体30セント | 30,000円(33,000円) | |
| 20~30年前(2回訪問) | 40セント | 30,000円(33,000円) | |
| 30年以上前 | 50セント以上 | 30,000円(33,000円) |
長期放置からの回復については、ピッチ低下30セントまでは基本的に一度のご訪問で仕上げます。
ただし、部分的に下がっている場合に限り、特に下がりやすい高音側の下がり具合によって検討します。
全体に30セント程度下がっている場合は、二度のご訪問により仕上げた方が調律の安定性が向上します。
これらの手法については、ご予算等ご相談に応じます。
30セントを超えて下がっている場合や、30セント以内であっても、ピッチを下げる要因(床暖等)がある場合は、期間を空けて二度ご訪問します。
長期放置料金二種類の差は、一度のご訪問でピッチを回復できるかどうかが基準となります。
放置期間とピッチ低下基準はおおよその目安ですので、単純に期間と料金が一致しない場合もございますので、あらかじめご了承下さいませ。
また、上記料金基準でピッチを回復した場合において、すべてのピアノの調律が完全に安定するわけではありません。
年間1回の定期調律でコンディションを保てるピアノになるまでには、ピッチ回復の直後は半年後、次に1年後と、
次第に期間を長くしていきながら、調律を繰り返す必要があります。
このように、いわば「ピアノを育てていく」ことによって、年間を通じて調律の狂わない安定したピアノになるのです。
出張エリアと費用について
適切なピアノのメンテナンスを行うためには、一般の方がご想像される以上の工具が必要です。
特に古いピアノや長期間放置されたピアノの調整には、調律作業に必要な工具だけではなく、各種交換部品等も合わせて携行する必要があります。また、内部打弦機構(アクション)をお預かりしての修理が必要な場合もあるため、当方では自動車で訪問させて頂いております。
出張エリアは、関東地方一都六県をメインとして、全国どこへでも出張致します。
関東近県への出張費用は、往復の有料道路料金のみ、実費のご負担を頂いております。
ただし、片道100キロを超える場合は、鉄道料金と同額でのご請求等、個別にご相談申し上げます。
東京23区内への出張は、有料道路利用の場合も含め、全域出張費用無料にてご訪問いたします。
各方面への出張経路(利用有料道路)についての詳細は、以下の一覧表をご参照ください。(表にない地域への出張も可能です。)
なお、出張費用無料地域内でも、有料駐車場を利用した場合は、原則実費のご負担をお願いいたします。ただし、調律・修理等のサービスご利用金額に応じて割り引きがございます(最大無料)。近年の駐車法改正に伴い、駐車スペースの確保にご理解・ご協力をお願いいたします。
| 出張費用および出張経路(利用有料道路)地域別一覧 | |
| 東京都 | 23区全域(無料) 三鷹市・武蔵野市・西東京市・狛江市(首都高速) 調布市以西(首都高速+中央道) |
| 千葉県 | 市川市・浦安市・松戸市・柏市・我孫子市(以上無料) 流山市・野田市(常磐道経由に一部有料地域あり) 船橋市・千葉市(京葉道路) 四街道市・佐倉市・成田市(京葉道路+東関道) |
| 埼玉県 | 八潮市・三郷市・吉川市・川口市・草加市・和光市(以上無料) 越谷市(一部有料地域あり) 所沢市(首都高速+外環道+関越道) |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区(首都高速) 川崎市多摩区・横浜市青葉区(首都高速+東名高速) 横浜市中区(首都高速) 鎌倉市(首都高速+横浜横須賀道路) 小田原市(首都高速+東名高速+小田原厚木道路) |
| 茨城県 | つくば市・土浦市(首都高速+常磐道) 取手市(一部無料) |