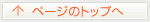ご存知のように、日本は湿度の大変高い国ですので、湿気がピアノに及ぼす悪影響は、ピアノを管理する上で大きな問題となっています。
このようなピアノへの湿害は、最近の住宅事情、生活様式の変化によって益々増加の傾向にあります。
例えば、鉄筋住宅の増加による部屋の密閉化などで、室内の風通しは悪くなり、外気と室内の温度差による
結露現象が発生することなど、ピアノの防湿・防錆管理の必要性が高まっています。
また、ピアノの湿害は湿度が高いことだけではなく、その逆に湿度が低すぎることも大きな問題です。
一般的には湿度が高い方が重要視される傾向にありますが実は湿度が低い、いわゆる過乾燥もピアノにとっては深刻な問題なのです。
そこで当事務所では、調律と同時に、ピアノの管理についての適切なアドバイスを行っています。
次項より、日頃お客様よりよくご質問をいただく点を中心にまとめまてみました。
防湿・防錆管理ページ内目次
ピアノにおける主な湿害(多湿と最も恐ろしい過乾燥)

木材部、フェルト等の含水率変化による故障(スティック等動作不良)
ドアや引き出しが湿度が高いと開けづらくなり、乾燥すると緩んでしまうのと同様に、ピアノも鍵盤が戻らなくなったり、
乾燥してガタガタ音をたてるようになってしまうことがあります。また、アクションという鍵盤がハンマーに弦を叩くしくみも、
何千点もの木製部品の組み合わせですので、湿気により動きが鈍くなります。
弦、チューニングピン等への結露 ( 錆の発生 ・ 音質の劣化 )
弦が錆びてしまうのは一般的にもよく知られていますが、その弦が取り付けられているチューニングピンに錆が進行すると、 調律の際に弦が切れてしまうことがあります。
調律ピッチの変化と保持不良の発生
湿度が上がるとピッチも上がり、乾燥するとピッチは下がります。これは響板が湿気によって膨張>収縮するため、 弦の張力が変化してしまうために起こります。本来は湿度変化によるピッチの上下を抑えるために、響板が膨張伸縮するわけですが、 許容範囲を超えると抑えられなくなります。
また、床暖房をご使用になると過乾燥を起こし、ピッチが下がって調律を保持することが不可能になるだけでなく、 ハンマーの打弦にも支障を来すようになります。
各部品に亀裂が発生
湿度が絶えず変化すると、木材が収縮膨張を繰り返して強度を失い最終的に亀裂が生じて割れてしまいます。 響鳴板やそこに弦の振動をを伝える駒、さらにチューニングピンを支えているピン板が割れてしまうと、修理には多額の費用がかかります。
ピアノの理想的な管理環境は、エアコンで室温20℃、湿度40~60%に保ち、更に空気清浄器でクリーンな状態を保てば良い訳ですが、 一般的には不可能です。そこで、湿害発生のポイントに対して、効果的で簡便な対策を行なう ことになる訳ですが最近では新しい 湿害対策法も考案され、状況に合った対策を行なえば、かなりの効果を発揮することが様々な実験によって実証されています。
ピアノ湿害防止方法とそのポイント
| 湿害発生原因を把握 | ピアノ設置環境から分析 |
| 換気の必要性 | 湿害最大の原因であることが多い |
| 湿度差の少ない環境に保つ | 暖房の方法を見直す等>>床暖房はピアノの大敵! |
| 防湿剤・防錆剤をセットする | 湿度の低過ぎも悪影響であるため、必ず楽器専用品を使用のこと |
| 電気式防湿器具を用いる | 近年ではピアノ内部に装着する除湿器も登場 |
| 恒温・恒湿の環境をつくる | 除湿器の常時運転やエアコンによりコントロールを行う |
また、最近の傾向で特に配慮したいこととして、以下のことが挙げられます。
- 床暖房環境による過乾燥。調律の保持ができなくなる。
- LDKへの設置が増え、キッチンの湿気が悪影響を及ぼす。
- 寝室等、ホコリの多い部屋への設置で、ホコリに湿気が吸着してピアノ内部に侵入。
- 新築の建材から排出される、化学成分を含んだ湿気による塗装への弊害
いずれも湿度の高い夏期に限らず、冬期でもピアノは湿害の危険に晒されています。
推奨する防湿・防錆方法について

ここでは、まず一般的な ピアノ専用乾燥剤を使用する方法をご紹介します。
乾燥剤といっても どんなものでも良い訳ではなく、楽器に適した理想的な特性の製品をご使用下さい。
洋服ダンス用や菓子類に用いられるものは楽器用とは異なった特性を持っています。
特に押し入れや玄関用の強力な乾燥剤(商品名水取りぞうさん等)は、絶対にご使用にならないよう、くれぐれもご注意下さい。
(過乾燥状態になります。)
ピアノ乾燥剤としての必要条件
| 1. | ピアノの管理で理想的な湿度は40~60%です。 60%以上になった時点で吸水効果を発揮し、40%以下になった時点で放湿する 湿度調整作用を持っていることが理想です。 |
| 2. | 湿度70%以上の吸水量が多いほど良い。 ただし、吸水の結果ピアノを汚染しないもの。 |
| 3. | 50%での吸水量が弱いほど良い。 過乾燥の危険から守るため。 |
乾燥剤に用いられるシリカゲルの性能比較(楽器用と一般用の成分比較)
| 必要条件 | Bゲル(スーパーD) | Aゲル | |
| 1. | 湿度70%以上時の吸水力 | 極大 | 小 |
| 2. | 湿度70~100%までの吸水量(g) シリカゲル500g 25度 |
35ml(30ml×8杯) | 30ml(30ml×1杯) |
| 3. | 50%での吸水量が弱いほど良い。 過乾燥の危険から守るため。 |
小 | 大 |
| 4. | 使用例 | 楽器用(ピアノ・ギター等) | 食品・医療用等 |
推奨するピアノ湿度調整剤 「スーパーD.(ドライ)」
ピアノの適湿は、50~70%ですので、 過度の乾燥は湿害以上に危険です。
「スーパーD. ® 」は除湿作用の他、ピアノ適湿範囲へ自動調節する、湿度コントロール作用をもっています。
ここが、一般用の乾燥剤と大きく異なるポイントです。
主な特徴
- 湿度70%以上のとき、抜群の吸水効果を発揮します。
- 従来品に比べて、吸水力を2倍に強化 (従来製品比)
- 低湿度では吸水能力が弱いため 乾燥しすぎることがない。
- 吸水後も、ゲルに変化がなく、濡れた感じ等全くない。
使用方法と有効期限
使用方法はとても簡単。 ビニール袋から取り出してピアの内部にセットするだけ。
有効期限は6ヶ月から1年ですので、定期調律の際にお取り替えください。
推奨するピアノ防錆・防虫剤「ピアノペット」
ピアノ防錆・防虫剤の使用
乾燥剤とともに防錆・防虫剤を併用して頂くと、金属部分の錆やフェルト部分の虫食いを防止することができます。
主な特徴
- 錆止めと防虫効果を同時に、しかも早く発揮する。
- 金属表面に湿気があっても効果を発揮する。
- 固体から直接ガス化することで 金属表面に見えない皮膜をつくる。
- 昇華が早いので、取替時、ピアノの中に粉が残らない。
- すでに生じている錆の進行をストップさせる。
使用方法と有効期限
使用方法は、ピアノペットのタブレットを取り出し、付属の専用袋でピアノ内部にセットします。
GPでは、フレームに直接セットせず、付属のGP用シートを使用することが必要です。
有効期限は、乾燥剤と同様、6ヶ月~1年です。
電気式ピアノ防湿器「ダンプチェイサー® 」について

最近では、電気式防湿器もかなり進化し、普及も進んできました。
前述の乾燥剤や防錆剤、一般の除湿器設置で効果のない環境の方
温度差の激しい場所にあるピアノ(寒冷地の方など)
地下の防音室など密閉された場所にあるピアノ
沿岸地域や湖沼地域の方等は、電気式防湿器もご検討をお勧めします。

「ダンプチェイサー® 」の主な特徴
・ピアノ内部温度を弱いヒーターで室温より僅かに高めることで、結露を防止すると共に、徐々に湿気を追い出します。
・湿度を自動的にコントロールすることも可能です。
・別売の自動湿度調整器と接続して使用すれば、セットした湿度より高くなると電源が入り、
下がってくると切れるため、理想的・経済的に使用できます。
・手動で長時間使用しても過乾燥の心配はない様、設計されています。
・ピアノ内部に取り付けるため、目立たず、確実に除湿を行ないます。
・この仕様で費用は8,500円! 自動調整器と併せても17,500円で、湿度管理の煩わしさから開放されます。
本体 直径20mm×長さ1200~1500mm 消費電力25W
調整器 縦110×横55×高さ33mm
更にこの商品には、除湿だけでなく加湿も行い、年間を通して湿度管理のわずらわしさから解放される、除加湿両用タイプもございます。
やむをえず強い暖房が必要な環境でご使用中のピアノに最適です。
費用は5~6万円程と、一般の家電除湿器並みのお値段です。
(ただし、床暖房をご使用の弊害を抑える効果はありません。)
●(赤) 除湿器 ●(青) 加湿器 ●(紫) 自動調整器
上記商品説明は、輸入元の認可を得て掲載しておりますので無断転載、複製を禁止します。
お問い合わせ、ご用命は砂田ピアノ調律事務所まで
電話 (03)3695-4815(10時~21時)・ FAX (020)4668-2017
またはE-Mailにてお願いいたします。
©Copyright 1997-2001 Kyoiku Gakki Hanbai Co., Ltd. All Rights Reserved
©Copyright 1997-2001 Sunada Piano Tuning, Ltd. All Rights Reserved