 |
1997年2月9日
50mm標準レンズ(JPEG:82KB)


この日のしらびそ峠は夜半過ぎより快晴となり、素晴らしい星空となった。
山際から姿を現した、ヘールボップ彗星は、肉眼でも尾が認められ、双眼鏡では約5゜近くのイオンテールや、
輝く彗星核とその複雑な構造が印象的だった。彗星の光度は約1.6等程度であった。
この作品は標準レンズによるものですので、肉眼で見たヘールボップ彗星のイメージに近いものとなっています。
1997年2月9日、午前5時15分に撮影。アサヒペンタックスMX+SMC PENTAX−M50mm
F1.7−>F2、10分露光。フィルムはKodak Gold400(標準現像)。
撮影地は長野県下伊那郡上村しらびそ峠。 |
 |
1997年2月9日
300mmシュミット・カメラ(JPEG:127KB)


及川聖彦先生より20cmF1.5シュミットカメラによる写真を掲載させて頂けることになりました。
最高の星空の元での、最高の彗星のイメージを、ぜひご覧ください。
1997年2月9日午前4時54分に撮影、口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。
フィルムは Kodak Ektachrome E100S(コダックE6処理による標準現像)にて12分露光。
撮影地は長野県下伊那郡上村しらびそ峠。撮影者:及川聖彦 |
 |
1997年2月15日
魚眼レンズ(JPEG:98KB)


この作品は、明け方近くの銀河に浮かぶヘールボップ彗星の姿を魚眼レンズで連続撮影したものです。
1997年2月15日午前4時37分、午前5時0分、午前5時11分にシグマ16mmF2.8にて撮影。
フィルムは Kodak Ektachrome 1600P(標準現像)にて各8分、8分、5分露光。
撮影地は千葉県九十九里浜東浪見海岸。撮影者:及川聖彦 |
 |
1997年2月17日
50mm標準レンズ(JPEG:60KB)


この日のしらびそ峠は数日前に発生した雪崩により道路が埋没し、通行不能であった。
このため急遽、長野県原村へ観測地を移動しAM3:30頃から若干の薄雲が流れる中、どうにかヘールボップ彗星を撮影することができた。
原村は、しらびそ峠に比べて若干光害が見られたが、肉眼でもはっきりと尾が認められ、双眼鏡では約10゜近くのイオンテールや、
急激に発達したダストテールが見られた。彗星の光度はアルタイル並の約1.0等であった。
この作品は標準レンズによるもので、肉眼で見たヘールボップ彗星のイメージに近いものとなっている。
1997年2月17日、午前4時46分に撮影。アサヒペンタックスMX+SMC PENTAX−M50mm
F1.7−>F2、10分露光。フィルムはKodak Gold400(標準現像)。
撮影地は長野県原村。 |
 |
1997年2月17日
165mm望遠レンズ(JPEG:179KB)


この作品は上記の標準レンズによるものとほぼ同時刻に、望遠レンズで撮影したもので、
湾曲したダストテイルや天の川に溶け込むように伸びたイオンテールの構造がより詳しく表現されている。
1997年2月17日、午前5時10分に撮影。
マミヤRZフィルムフォルダー利用自作ペンタックス67マウントカメラ+PENTAX67・165mmF2.8−>F3.2
フィルムは Kodak Ektachrome E100S(+1増感現像)にて10分露光。
撮影地は長野県原村。 |
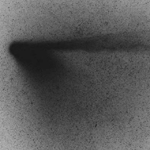 |
1997年2月20日
300mmシュミット・カメラ(JPEG:116KB)


この作品は、写野をずらして撮影した2コマの原板を繋ぎあわせて、1枚の画像に合成したものです。
また、尾の淡い広がりを強調するために階調の反転処理も行っています。
20cmF1.5シュミットカメラにより捉えられた、ヘールボップ彗星の淡い尾の広がりとその構造がみごとに表現されています。
1997年2月20日午前4時40分30秒と午前5時05分10秒に撮影した2コマの原板から合成。
口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。
フィルムは Kodak Technical-Pan4415(D−19・20℃4分現像)にて3分と、4分露光。
撮影地は千葉県九十九里浜東浪見海岸。撮影者:及川聖彦 |
 |
1997年2月20日
300mmシュミット・カメラ(JPEG:149KB)


この作品は、上記のモノクロ反転画像とほぼ同時刻に撮影されたヘールボップ彗星のカラーフィルムでのイメージです。
F1.5という明るい光学系で捉えられた、ヘールボップ彗星の微妙な色調が、みごとに表現されています。
1997年2月20日午前4時50分40秒に撮影、口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。
フィルムは Kodak Ektachrome E100S(コダックE6処理による標準現像)にて7分露光。
撮影地は千葉県九十九里浜東浪見海岸。撮影者:及川聖彦 |
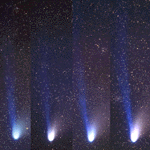 |
1997年2月のヘールボップ彗星の尾の変化
300mmシュミット・カメラ(JPEG:146KB)


この作品は、2月中に撮影された4枚のヘールボップ彗星の写真を1枚の画像に合成し、ヘールボップ彗星の尾の変化を分かりやすく表現したものです。
口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。撮影者:及川聖彦
|
 |
1997年3月8日
50mm標準レンズ(JPEG:75KB)


2月17日より約2週間ぶりに見たヘールボップ彗星は急激に発達しており、
肉眼でも15゜以上のイオンテールと湾曲した5゜以上のダストテールが楽に確認できた。
また双眼鏡や天体望遠鏡では核付近の複雑な構造や、尾の微細な構造が手に取るように見え、
本当に感動的な光景だった。
昨年の百武彗星に続き、この光景は一生、目に焼き付いて離れないだろう。
彗星の光度も確実に増光しており約0等であった。
この作品は標準レンズによるものですので、肉眼で見たヘールボップ彗星のイメージに近いものとなっています。
1997年3月8日、午前4時10分に撮影。アサヒペンタックスMX+SMC PENTAX−M50mm
F1.7−>F2、10分露光。フィルムはKodak Gold400(標準現像)。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。 |
 |
1997年3月8日
300mmシュミット・カメラ(JPEG:144KB)
 
この作品は、写野をずらして撮影した2コマの原板を繋ぎあわせて、1枚の画像に合成したものです。
ヘールボップ彗星の発達したイオンテールやダストテールの淡い尾の広がりの部分まで、みごとに再現されています。
1997年3月8日午前4時48分50秒と午前4時57分50秒に撮影した2コマの原板から合成。
口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。
フィルムは Kodak Ektachrome E100S(コダックE6処理による標準現像)にて8分と、7分露光。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。撮影者:及川聖彦 |
 |
1997年3月8日
105mm標準レンズ(JPEG:186KB)


同日に長野県浪合村蛇峠山に観測に同行した青鹿俊幸氏の作品を提供していただけることになりました。
美しく発色した青いイオンテールの美しさと、ガーネットスターから北アメリカ星雲にかけての天の川と彗星の構図の妙がみごとな作品です。
1997年3月8日、午前4時38分に撮影。
PENTAX67+PENTAX67・105mmF2.4(開放)
フィルムは Fujicolor Super G400(標準現像)にて15分露光。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。撮影者:青鹿俊幸 |
 |
1997年3月17日
50mm標準レンズ(JPEG:52KB)


この日は、飯田市上空を覆うようなうす曇に阻まれ、見事な彗星の姿を見ることはできなかった。
晴天域を探して観測地を渡り歩いたがとうとう彗星撮影のタイムリミットが迫り、不満足ながらも飯田市郊外の喬木村を撮影地とした。
急いで機材のセッティングを行ったが、薄明かりの中での撮影となった。輝星がにじんで見えるのは、薄曇が通過した為。
この作品は標準レンズによるものですので、肉眼で見たヘールボップ彗星のイメージに近いものとなっています。
1997年3月17日、午前4時15分に撮影。アサヒペンタックスMX+SMC PENTAX−M50mm
F1.7−>F2、10分露光。フィルムはKodak Gold400(標準現像)。
撮影地は長野県喬木村。 |
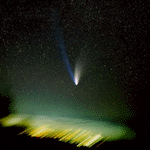 |
1997年3月18日
105mm標準レンズ(JPEG:130KB)


前日は薄曇に邪魔されはっきりとした彗星のイメージは見られなかったが、
この日は撮影直前に透明度もあがり素晴らしい彗星の姿を見ることができた。
ダストテールは先週のイメージよりも格段に発達し、15度近くの尾が肉眼でもはっきり認められた。
月齢や、彗星の高度の関係から、早朝にこのようなイメージで彗星を見られるのは、この日が最後になるだろう。
飯田市の街明かりが雲海をやわらかに照らしている光景が印象的だったので、標準レンズを使って彗星と同時に撮影した。
1997年2月17日、午前3時40分に撮影。
マミヤRZフィルムフォルダー利用自作ペンタックス67マウントカメラ+PENTAX67・105mmF2.4−>F3
フィルムは Kodak Ektachrome E100S(+1増感現像)にて15分露光。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。 |
 |
1997年3月18日
165mm望遠レンズ](JPEG:206KB)


この作品は上記の標準レンズによるものとほぼ同時刻に撮影したものです。
ダストテール中に見えている、大彗星特有のシンクロニックバンドや、発達したイオンテール・ダストテールの構造が観察できます。
1997年3月18日、午前4時05分に撮影。
マミヤRZフィルムフォルダー利用自作ペンタックス67マウントカメラ+PENTAX67・165mmF2.8−>F3.2
フィルムは Kodak Ektachrome E100S(+1増感現像)にて15分露光。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。 |
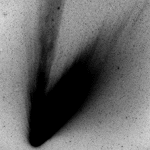 |
1997年3月18日(反転モノクロ画像)
300mmシュミット・カメラ(JPEG:108KB)


この作品は、写野をずらして撮影した2コマの原板を繋ぎあわせて、1枚の画像に合成したものです。
また、尾の淡い広がりと微細な構造を強調するために階調の反転処理も行っています。
大彗星特有のシンクロニックバンドや淡い尾の広がりとその微細な構造がみごとに表現されています。
1997年3月18日午前3時42分40秒と午前4時21分50秒に撮影した2コマの原板から合成。
口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。
フィルムは Kodak Technical-Pan4415(D−19・20℃4分現像)にて各3分露光。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。撮影者:及川聖彦 |
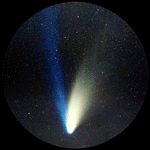 |
1997年3月18日
300mmシュミット・カメラ(JPEG:123KB)


この作品は、上記のモノクロ画像とほぼ同時刻に撮影されたカラーフィルムでの彗星のイメージです。
1997年3月18日午前4時27分40秒に、口径20cmF1.5シュミットカメラ(焦点距離300mm)にて撮影。
フィルムは Fujicolor Super G400 Ace(標準現像)にて3分露光。
撮影地は長野県浪合村蛇峠山。撮影者:及川聖彦 |
 |
1997年3月30日
854mmε-250型アストロ・カメラ(JPEG:110KB)


この作品は、長焦点距離のアストロ・カメラにより撮影された彗星の頭部付近の拡大画像です。
彗星核より吹き出すイオンテールの複雑な構造やダストテール中のシンクロニックバンドの構造が見事に表現されています。
1997年3月30日午前19時30分50秒に、口径25cmF3.4ε-250型アストロ・カメラ(焦点距離854mm)にて撮影。
フィルムは Fujicolor Super G400 Ace(ナニワカラーキットN30℃6分)にて10分露光。
撮影地は長野県下伊那郡上村しらびそ峠。撮影者:久保田宏 |
![]()