セミクジラ科 ホッキョククジラ
北極海にすむクジラ。商業捕鯨でまず獲りつくされたのがこのクジラです。別名グリーンランドクジラ。数十頭のレベルまで減ったといわれます。
大きな口で、プランクトンなどを濾しとって食べます。
セミクジラ科 セミクジラ
ホッキョククジラが獲れなくなった後、捕鯨の対象となり、世界中の海にすんでいたのが数百頭に減ってしまいました。近年は多少、回復しているようです。
頭部にある白いものは、皮膚がこぶのようになり寄生生物がついて白くなっているもので「ボンネット」といいます(痒くないのかな)。こぶは生まれつきありますが、成長するにしたがって大きくなります。これの位置や大きさで個体識別をします。
「セミ」は「背美」で、背びれがないので背美なんだそうです。
コククジラ科 コククジラ
北太平洋に棲むクジラで、沿岸で海底の泥の中のエビやゴカイなどすくいとって食べています。南の海で繁殖、夏には北極近くまでへ回遊します。
身体にあるボツボツはフジツボなどの寄生生物で、子どものときはツルツルなのが年とともに増えていきます。一杯くっついているので、描いているだけで痒くなりそうですが、当人はどうなんでしょうか。
「コク」クジラという名は、ヒゲクジラの中では小型なのでコクジラといっていたのを、子どものクジラと間違えないようにコククジラと言うようになったんだとか。
ナガスクジラ科 シロナガスクジラ
地球上最大の生物。33メートル、170トンというのが最大の記録。
壮大な大きさですが、実感がわきません。電車の1両が約20メートルですから、その1.5倍です。餌はちいさいオキアミ、ただし量は半端じゃなくて、1日5トンほど食べる。
寿命は100年といわれますから、老体ではずいぶん知恵がついていそうです。それを捕ってしまう人の力も偉大ではありますが、やはり、この巨大な生き物を捕獲すること自体が乱暴な行為のように思います。
ナガスクジラ科 ナガスクジラ
シロナガスに次いで大きなクジラ。餌はオキアミのほか、魚やイカも食べる。
シロナガスが獲りつくされた後、このナガスも獲りつくされました。残っているのはいずれも少数で、長命で1世代が長いため回復には何十年もかかるでしょう。
ナガスクジラの体色・形態は左右対称ではありません。上のアニメで違いを探してみてください。
ナガスクジラ科 イワシクジラ
このクジラが見られるとイワシが捕れるというのでイワシクジラと名づけられたというのですが、実は後でわかったのは、そのクジラは長くイワシクジラと同一だと考えられていたが1931年に別種と確認されたニタリクジラ(下記)だったのです。イワシクジラは魚はほとんど食べずにプランクトンの一種を食べています。
イワシクジラとニタリクジラの外見上の差は、腹の畝(スジ)の長さで、ニタリのほうが長くへそまで達するところです。
ナガスクジラ科 ニタリクジラ
上記のようにイワシクジラの一種と思われていたのが別の種類と認定されたクジラ。ニタリというのはナガスクジラに似ているというので「似たり」です。学術的に別種とされる以前から、捕鯨業者は、イワシクジラなんだけれどナガスクジラに似ていてイワシクジラとはちょっと違うというので、ニタリクジラと呼んで区別していたそうです。日本の沿岸で見られるのはほとんどがニタリです。魚(カタクチイワシ)やプランクトンを食べます。
クジラは、ブリーチングといって水面にジャンプしたり身体を突き出したりしますが、ニタリクジラのブリーチングは、上半身をほとんど垂直に突き出します。
ナガスクジラ科 ミンククジラ
ヒゲクジラの仲間ではもっとも小さいクジラです。
ミンクというのはイタチ科のminkと違ってminkeで、英語ではミンキーと発音します。その由来は、昔ドイツにMeinke(マインケ)という新米の捕鯨船の砲手がいて、シロナガスと間違えてこのクジラをたくさん獲ってきたので、商品価値のない小さなクジラの蔑称としてマインケのクジラと呼ばれ、それがなまってミンキーになったという話が伝わっています。
その小ささが幸いして、効率が悪いと商業捕鯨の対象にならなかったため、シロナガスやナガスのように激減をまぬがれました。
ナガスクジラ科 ツノシマクジラ
1998年に山口県の角島(つのしま)のそばで漁船と衝突して死んだクジラを引き上げて調べたところ、ナガスクジラ科の新種のクジラであることがわかり、2003年にツノシマクジラと命名して発表されました。改めて調べてみると、1970年代に捕獲されて小型のニタリクジラと同定されて保管されていた8体の標本もツノシマクジラらしいとわかりました。学名は Balaenoptera omurai で、日本の鯨学の大家の大村秀雄氏を記念してつけられました。
体色は、ナガスクジラと同様、左右対称ではありません。このように左右非対称で左の体側が黒っぽいのは、泳ぐときに左を上(水面方向)、右を下(海底方向)に向けて傾いたまま泳ぐからではないかという説があります。ただし、このアニメは、なにしろ生体の様子がわかる写真が少ないので、とくに右体側は想像で補った部分があります。

ナガスウクジラ科 ザトウクジラ
胸びれの大きなクジラ。日本近海では小笠原や沖縄、アメリカではハワイとカリフォルニア沖に繁殖水域があって観察しやすいので、繁殖期の冬にはホエール・ウォッチングの対象になります。この巨体で豪快に海面にジャンプします。
尾びれの裏側は白い斑紋になっていて、これが1頭ずつ違うので、写真にとって個体識別して研究されています。
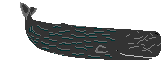
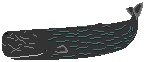
マッコウクジラ科 マッコウクジラ
歯のあるハクジラの仲間では最大のクジラ。
水深1000メートルもの深海にすむダイオウイカが好物らしく、よく胃の中から発見されます。ダイオウイカは体長10メートルを超えるものもいて、捕まえるときはかなり壮絶な死闘がくりひろげられるらしく、マッコウクジラの体にはイカの吸盤の跡がよく残っています。
巨大な頭には、名前の由来となった抹香臭のある脳油がつまっています。脳油は温度によって液体〜個体に変化するので、潜るときは海水で冷やして比重を重くし、浮き上がるときは血液で暖めて軽くします。
コマッコウ科 コマッコウ
マッコウクジラと比べるとはるかに小さいクジラですが、頭の脳油はマッコウクジラと同じ仕組みです。
イカや魚を食べています。
姿はサメに似て、鰓のような模様までありますが、性格は臆病らしい。擬態の一種でしょうか。
コマッコウ科 オガワコマッコウ
クジラと呼ばれる中では一番小さなクジラ。中型のイルカより小さい。
イカを食べています。
同科のコマッコウとともに、危険を感じると液状の糞を大量に出して煙幕として逃げます。
マッコウクジラ類の大きさ比べ
マッコウクジラ科とコマッコウ科は、一つ上のレベルの類では同じマッコウクジラ類に属していますが、大きさは全然違います。同じ縮尺で描くと、このくらいになります。
(上から)
マッコウクジラ、コマッコウ、オガワコマッコウ
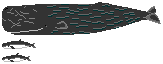
アカボウクジラ科 アカボウクジラ
世界中の海にすんでいるらしいのですが沿岸にはあまりいなくて、水深1000m以上の外洋でくらしています。深海でイカなどを食べているらしい。
アカボウというのは「赤ん坊」のことで、顔が薄桃色で、おでこと笑ったような口が正面から見ると赤ん坊のように見えるからついた名前です。
アカボウクジラ科
タイヘイヨウアカボウモドキ
最近まで、世界中でも6例しか記録がなかった珍しいクジラ。頭骨の標本しかなく、幻のクジラでしたが、2002年に鹿児島県の海岸に座礁しているのを発見されたクジラを詳しく調べたところ、タイヘイヨウアカボウモドキであることがわかりました。体長や体色などは、このとき初めて確認されました。
必ずしもアカボウクジラと似ているわけではなさそうで、改名すべきとの提案もあります。
アカボウクジラ科 オウギハクジラ
北太平洋の寒冷海域にすむクジラ。「オウギハ」は「扇歯」、オスの下あごにある扇形の大きな歯のことです。メスを争うときに、この歯で闘うらしく、オスの身体にはたくさんの傷があります。
イカを食べているらしいのですが、座礁した個体の胃からビニールやプラスチックがたくさん出てくることから、これらを誤飲し、かつ座礁の原因にもなっているのではないかと考えられています。
アカボウクジラ科
ハッブスオウギハクジラ
北太平洋の温帯海域にすむクジラ。ごくまれに日本の沿岸にも座礁します。深海でイカや深海魚を食べているらしい。オウギハクジラと同様、下あごに1個の歯が突き出ていて、これでオス同士争った傷が身体中にあります。
1963年に新種として記載され、アメリカの海洋生物学者ハッブス(Carl L.Hubbs, 1894-1979)にちなんで命名されました。このハッブス博士は、ずいぶんたくさんの新種を発見した人らしく、22種の生物(主に魚類)にその名が冠されています。
アカボウクジラ科 コブハクジラ
熱帯〜亜熱帯の世界中の海域に分布しているらしく、世界中で座礁記録があります。深海でイカを主食にしているらしい。
図鑑を見ると、体中にダルマザメに噛み取られた傷痕があると書いてあります。人知れぬ深海で、さぞや壮絶な死闘が繰り広げられているのかと思って調べてみると、死闘の相手にしてはダルマザメというのはずいぶん小さく、体長30〜50cm程の小さなサメだそうです。ところがこのサメ、なかなかすばしっこいようで、クジラやアザラシなどに近寄っていって、すばやく直径数cmほどの肉を噛み取って主食にしているのです。クジラにとっては、多少は痛いでしょうが、アブに咬まれたようなものでしょうか。それにしても、このダルマザメ、原子力潜水艦のゴム製の外装部まで噛み取ってしまうそうで、ずいぶんと勇敢なサメです。
なお、ダルマザメが噛み取っている上のアニメは「想像図」で、本当かどうか保証の限りではありません。
アカボウクジラ科 イチョウハクジラ
温帯〜熱帯の海に分布しているらしく、日本でも北海道から沖縄まで何例かの座礁記録があります。オウギハクジラ属のクジラと同じで、深海でイカを食べているらしく、身体にはダルマザメの噛み跡がたくさんあります。
「イチョウハ」は「銀杏歯」で、歯がイチョウの葉のような形をしているという解説をしている本もありますが、命名者の一人の神谷敏郎氏の著書によると、歯は木の葉のようではあるが必ずしもイチョウの葉に似ているわけではなく、当時在籍していた東大の紋章にちなんでつけられたとあります。1958年に新種として発表されました。日本人が命名したクジラは唯一でしたが、2003年にツノシマクジラが加わりました。
アカボウクジラ科 ツチクジラ
北太平洋の大陸棚海域にすむクジラ。1000〜3000mの海で深海魚やイカなどを食べています。夏に沿岸近くに現れ、むかしから沿岸捕鯨の対象になっています。ツチは槌で、はっきりとしたおでこの形状から来た名前でしょうか?
(注! ツチクジラはかなり大型なので、アニメは上のオウギハクジラ類と縮尺が違います。体長はオウギハのほぼ倍です。)