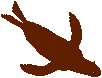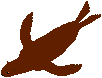イノシシ科 イノシシ
ヨーロッパからアジアまで広く分布していますが、足の短い体形や地面を鼻で掘って餌を探す習性から、雪深いところでは生息しにくいようです。
日本でも北海道にはおらず、東北、北陸、中部には少ない。
畑を荒らすので、西日本では昔から農民との知恵比べが続いてきました。各地に防護のための“シシ垣”が残っていいます。
こどもは可愛いタテ縞もようの“ウリ坊”です。




シカ科 ニホンジカ
シカは、北海道から本州、四国、九州、屋久島、慶良間諸島にまで分布しています。
エゾシカ、ホンシュウジカなどと呼び分けても、種としてはみな同じシカです(異説もある)。
身体は北に行くほど大きく、南のヤクシカと北のエゾシカでは体重が3倍くらい違います。メスには角はありません。
警戒すると白い尻尾を立てて仲間に知らせます。
狩猟獣としてちょうどよい大きさと美しさのため、ヨーロッパ、ロシアからニュージーランドまで世界中に移入され、「Shika deer(シカ・ディア)」と呼ばれて親しまれているそうです。撃たれてしまうものを「親しまれている」というのもちょっと酷ですが…。
シカの大きさ比べ
寒いところでは、体が大きく、凸凹が少ない方が、体重(体積)に対する表面積の割合が少なくなり、体温を一定に保つのに有利だからです。
シカの大きさで比べてみました。
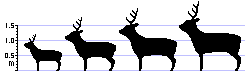
シカ科 キョン(移入種)
飼われていたものが逃げ出し千葉県の房総半島で野生化しています。中国南東部と台湾が原産地。
小型のシカで、大きさは中型犬くらい。オスには角とイノシシのような牙(犬歯)があります。
農作物への被害が報告されています。


ウシ科 ヤギ(移入種)
小笠原では200年近く前に持ち込まれたものが、無人島で非常に数が増えて被害も深刻です。固有の植物、動物、昆虫等への影響のほか、島の植生を食べつくしてしまうので土壌の流出がおこり、サンゴ礁にも影響がでています。


ウシ科 カモシカ
特別天然記念物。近似種は台湾にしかいない世界的にも珍しい動物だそうです。
山で何度かカモシカと出会ったことがありますが、いつも一瞬で視界から消えてしまいます。
「寒立ち」といわれる、寒風のなか崖の上でじっと立ち尽くしている姿は、なかなか威厳があリ哲学的な風貌だと本で読んだことがあります。ウシ科だから立ち尽くしながら反芻してるんだと思いますが、思考の方も反芻しているように見えてしまうのですね。
なお体色は全身白や灰色、こげ茶色など変化が大きく、アニメはその1例です。