翼手目の測定には、他の動物でつかう頭胴長・尾長にくわえて前腕長を用います。
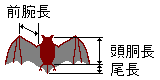
きつつき工房だより(top) > 日本の野生動物 > (2)翼手目1
コウモリの仲間の測定
翼手目の測定には、他の動物でつかう頭胴長・尾長にくわえて前腕長を用います。
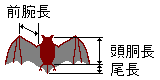
オオコウモリ科 クビワオオコウモリ |
|
前腕長12-15cm。頭胴長19-25cm。尾はない。 沖縄など南西諸島にすんでいるオオコウモリ。大きいといっても身体はリスくらい。 コウモリの仲間は、超音波を出してその反射をとらえて暗闇でも飛べるのが特徴ですが、このコウモリは目視飛行です。眼をつかうせいか他の哺乳類の顔に近く、ネズミかイヌのようです。英語では flying fox 空飛ぶキツネ。 主食は果物や花。なんか優雅な食生活ですね。 |
  オオコウモリ科 オキナワオオコウモリ |
|
前腕長14cm。頭胴長記録なし。尾はない。 沖縄本島で1870年に捕獲された標本2体が英国自然史博物館に保管されているだけで、以来、まったく記録がないので絶滅したと考えられています。 図鑑で見ることができるのは100年以上前の標本の写真ですから、生体の色がどんなだったのか、はっきりはわかりません。クビワオオコウモリと似ているとありますので、想像してみてください。このように大きな飛膜を広げた姿はもう見られないんですね。 |
オオコウモリ科 オガサワラオオコウモリ |
|
前腕長13-15cm。頭胴長20-25cm。 クビワオオコウモリに似ていますが、小笠原諸島だけにすんでいるオオコウモリ。 日本固有種。天然記念物。絶滅危惧種。 大洋の孤島である小笠原諸島には固有の植物や鳥などがいますが、陸生哺乳類は海を渡れないので、自然分布の土着種はほとんどいませんでした。唯一の例外がこのオオコウモリです。飛んで渡ってきたんでしょうね。諸島全体でも数百頭しかいません。 |
キクガシラコウモリ科 キクガシラコウモリ |
|
前腕長5.6-6.5cm。頭胴長6.3-8.2cm。尾長2.8-4.5cm。 オオコウモリと違って、他の哺乳類とはかけ離れた顔つきです。鼻が花びらのようにヒダになっていて(鼻葉というらしい)、ブタの鼻をさらにつぶして、くしゃくしゃにしたような感じ。初めて図鑑で見たとき、正直言って、なんて不細工な…、と思いました。 でも、その鼻から超音波を出してその反射で周囲の状況を把握しているんです。 不細工でもエコロケーションというハイテク機能をもった鼻なんですよ。 |
キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ |
|
前腕長3.6-4.4cm。頭胴長3.5-5.0cm。尾長1.6-2.6cm。 姿はキクガシラコウモリとそっくりですが、大きさは半分位。 国内ではキクガシラ…とほぼ同じ地域に分布しています。キクガシラ…が大陸にも分布しているのに対し、コキクガシラ…は日本固有種と考えられています(中国大陸にもいる可能性あり)。 寝るときに、キクガシラ…は飛膜で身体を覆うのに対し、コキクガシラ…は飛膜で身体を覆いません。 |
キクガシラコウモリ科 オキナワコキクガシラコウモリ 前腕長3.8-4.2cm。頭胴長3.8-4.6cm。尾長1.8-2.4cm。 キクガシラコウモリ科 ヤエヤマコキクガシラコウモリ 前腕長4.0-4.4cm。頭胴長4.1-5.0cm。尾長1.8-2.2cm。 |
|
大きさも姿かたちもコキクガシラコウモリとほとんど同じですが、分布域が違います。オキナワ…は沖縄本島〜宮古島、ヤエヤマ…は石垣島〜西表島。 現地で見ればどちらか区別できるでしょうが、この小さなアニメで描き分けるのは困難です。上の2種のアニメはポーズが違うだけ。区別がつかないので、数でごまかしときます。アニメのように洞窟の天井でくっつきあって密集しています。 (おまけクイズ=上のコウモリの群の中で、最後まで振り向かない個体が1匹います。左から何番目でしょうか?) |
カグラコウモリ科 カグラコウモリ |
|
前腕長6.5-7.2cm。頭胴長6.8-8.9cm。尾長4.0-5.2cm。 沖縄・八重山諸島にすむコウモリ。 洞窟で数百から千頭の大群となりますが、それぞれが身体を触れ合うことなく、少しずつ間隔をあけて天井に止まるそうです。 鼻葉がお神楽の面に似ているというのですが、はっきりした写真や絵を見たことがなく、よくわかりません。 暖かい南の島でも、20℃以下で、もう冬眠してしまう極端に寒がりな哺乳類です。 |
ヒナコウモリ科 クロアカコウモリ |
|
前腕長4.5-5.0cm。頭胴長4.5-7.0cm。尾長4.3-5.2cm。 アフガニスタンからインド、中国、朝鮮半島に分布するコウモリ。日本では対馬で少数が捕獲されたことがあります。 派手なオレンジ色の体毛、赤と黒が鮮やかな飛膜で、特徴がはっきりしています。 |
ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ |
|
前腕長3.4-4.1cm。頭胴長4.4-6.3cm。尾長3.2-4.5cm。 日本全土に分布するコウモリで、洞窟などに100頭以上の集団で棲み、夜になると洞窟から出てきて活動し、日の出前に洞窟に帰るという、人々がコウモリにもつイメージどおりのくらしをしているコウモリです。コキクガシラコウモリなどと混群になることもあるそうです。 |
ヒナコウモリ科 ドーベントンコウモリ |
|
前腕長3.4-3.9cm。頭胴長4.4-5.6cm。尾長3.3-4.2cm。 上のモモジロコウモリとよく似たコウモリで、日本では北海道だけに棲んでいますが、世界ではヨーロッパからシベリアにまで分布しています。 モモジロとの違いは、モモジロは腿の部分が白っぽいということと、足首部分への飛膜のつき方という微妙な違い。体色は個体差が大きいので、アニメはあくまで一例です。 ドーベントン(Louis-Jean-Marie Daubenton、1716-1800)は、フランスの生物学者・比較解剖学者で、骨格を測定して動物を分類する分野の開拓者だったようで、生涯に182種類の動物を種として記録したそうです。このコウモリの名前は、ドーベントンによって記録されたものか、ドーベントンの功績を記念してつけられたのか、調べたんですがよくわかりません。 |
ヒナコウモリ科 ホオヒゲコウモリ |
|
前腕長3.4-3.7cm。頭胴長3.8-5.0cm。尾長3.0-4.0cm。 ヨーロッパからシベリアまで分布するコウモリで、日本では北海道だけに棲んでいます。 全体に黒褐色ですが、背中の毛の先端が金色の光沢をもっているのがヒメホオヒゲ…との違いです。 |
ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ |
|
前腕長3.0-3.4cm。頭胴長3.8-4.4cm。尾長3.3-4.0cm。 日本固有種で、本州・四国・九州から、わずかに数十頭しか採集された記録しかありません。 全体に黒色で、背中の毛の先端が銀色の光沢をもっています。日本のコウモリの中では最小。 |
ヒナコウモリ科 ヤンバルホオヒゲコウモリ |
|
前腕長3.7-3.8cm。頭胴長5.2-4.3cm。尾長3.3-4.0cm。 1996年に沖縄本島北部のヤンバルの森で新発見されたコウモリ。同時にリュウキュウテングコウモリも発見され、日本のコウモリは一気に2種増えました。 全体に黒色で、上のクロホオヒゲコウモリと近縁と考えられますが、身体が大きく、歯も大きい。 ヤンバル(山原)の森は、照葉樹の原生林で、ヤンバルクイナやヤンバルテナガコガネなど、鳥類・昆虫類の新種も発見されています。米軍演習場がかなりの面積を占めているため、開発もされていなかったことが幸いした面があるのですが、名護の軍民共用空港建設のように、基地は軍事上の必要とあれば、たちまちサンゴを埋め、木も切られてしまいます。世界遺産にふさわしいヤンバルの森を自然保護区として永遠に残せるようにしたいものです。 |
ヒナコウモリ科 ヒメホオヒゲコウモリ |
|
前腕長3.3-3.6cm。頭胴長4.2-5.1cm。尾長3.1-4.0cm。 シベリアから朝鮮半島に分布するコウモリ。日本では北海道・本州に棲んでいます。 全体に黒褐色ですが、背中の毛の光沢はホオヒゲ…のように目立たない。 |
ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ |
|
前腕長3.6-4.1cm。頭胴長4.4-5.6cm。尾長3.8-4.7cm。 最初に竹薮で発見されたから「カグヤ」コウモリ。なかなかロマンチックな命名だったのですが、じつは竹薮が本来の棲家というわけでもなくて、森に棲んでいるコウモリです。 シベリアから中国東南部に分布。日本では北海道・本州に棲んでいますが、数は少ない。 なお、東南アジアやインドには、本当に竹の節の中をねぐらにしているタケコウモリというのがいます。柔らかい竹の子の時に虫が空けた穴を利用して節の中に出入りするそうです。 |
ヒナコウモリ科 ノレンコウモリ |
|
前腕長3.8-4.2cm。頭胴長4.7-5.5cm。尾長3.9-4.8cm。 洞窟に棲むコウモリで、日本の各地に飛び飛びに分布しています。 オスとメスが別々の集団をつくって暮らしているそうです。 洞窟で他のコウモリと一緒にいる集団でも、お腹が白っぽいのがよく目立つそうです。 |
|
コウモリと蛾の知恵比べ |
|
小型コウモリの仲間は、超音波を発してその反射波を捉えて暗闇のなかでも獲物の位置を把握し、すばやく飛翔して空中で虫を捕らえて食べます。 ところが敵もさるもので、蛾の中にはコウモリの出す超音波を感じると羽を縮めてストンと落下するヤツがいる。単なる条件反射なんですが、これが意外と効果的で、コウモリは脳で相手の飛ぶ軌跡を予測しながら飛んできますから、予想外の動きに狙いをはずしてしまう場合もあるのです。 脳で身体をコントロールする高等動物が単純な条件反射で動く虫に騙されるのも自然の妙ですね。 次はコウモリが失敗を教訓に急下降や急転回の飛翔術を磨くようになるのでしょう。 |