|
|
|
|
![]()
手袋くん。.... 佐久間學
「マタイ」の時とは、パッケージのデザインがすっかり変わっていますが、これはその間にベルリン・フィルが正式なレーベルを発足させたからです。これに合わせて、「マタイ」の方もこの新しいパッケージでリイシューされています。 このパッケージは、表紙が布張りという豪華なもの、なんか、ものすごい存在感を主張しています。これを開くと、こんな感じで右側がブックレットになっているのですが、肝心の左側がいったいどうなっているのか、しばらく分かりませんでした。普通だと引き出しみたいにトレーが出てくるのでしょうが、どこを押しても動く気配がありません。いろいろやっているうちに、何かのはずみで下から開くことが分かりました。ただ、これは普通は開かないように磁石で固定されているので、意識して力を入れないと開きません。知らない人がいたら自慢して開けてあげたいような「特別な」仕掛けですが、ちょっとこれはやり過ぎ。それより、BD1枚とDVD2枚が、間に紙は入っていますが、そのまま重ねられているというのは、ちょっと嫌な感じです。  ↓  ↓  そんな特殊な演技を要求されても、ソリストたちの声はとても明瞭に録音されていました。そもそも、パドモアがステージの下から登場してきた時からきっちりとオンマイクならではの音だったので、気を付けて見てみたら、やはりみんなおそらく客席からは絶対に見えないほどの巧妙さでピンマイクを装着していましたね。多分、これは録音だけではなく、ホール内でもしっかりPAで流していたのではないでしょうか。オペラでは鬘の中にマイクを仕込むのはもう常套手段になっていますが、パドモアではそれは無理ですから、こういう形を取ったのでしょう。もちろん、これで「演技」と「演奏」の両立が図れるのですから、こういうことをやるのは大歓迎です。 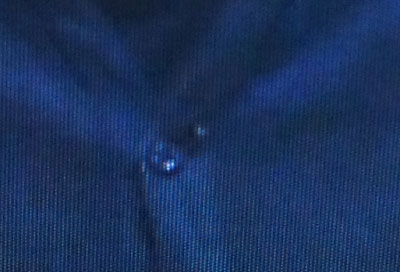   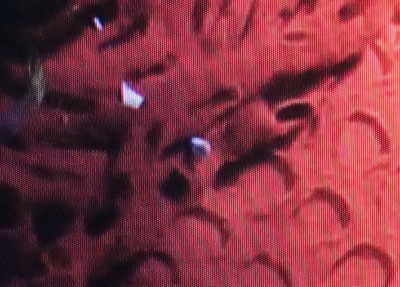 ラトルは、時折聴きなれない表現で観客を驚かせていたようですが、それらは全部最近の他の演奏家の録音で聴いたことのあるものばかりでした。特に、11番のコラール「Wer hat dich so geschlagen」で、2番の時にア・カペラにするというのは、レイトンのアイディアを「参考にした」と思われても仕方がありません。 BD & DVD Artwork © Berlin Phil Media GmbH |
||||||
そして、この「フルート・ソナタ」も、そんなたぐいの限りなく「贋作」に近い代物です。ただ、贋作者には贋作者なりのプライドがあったとみえて、ハイドンの「真作」を素材にする、というところで最低限のモラルは果たしたつもりにはなっているところが、かわいいというか、図太いというか。 その「贋作者」の名前はアウグスト・エバーハルト・ミュラー。ライプツィヒの聖トマス教会のカントールを務めたという立派な音楽家ですが、有名な音楽出版社、ブライトコプフ・ウント・ヘルテルの顧問としての「仕事」も数多く手がけていました。そのひとつが、この「ハイドンのフルート・ソナタ」と言われるものです。 ハイドンのウィーンでの晩年は、まさに「人気作曲家」で、弦楽四重奏曲の楽譜などはとてもよく売れたそうです。ですから、出版社としてはさらに「新作」でウハウハ儲けたいところなのですが、もはや作曲家は多作には耐えられないような健康状態だったために、なかなか思い通りの「原稿」は手に入りません。そこで、出版社は「顧問」の力を借りて、作曲家のすでに出版されていた弦楽四重奏曲の中から3曲を選んで、それをフルートとピアノのためのソナタに編曲した楽譜をでっちあげ、それを「ハイドン作曲」ということにして出版したのです。もちろん、その際には今まで付けてきた作品番号に続けて、「ハイドンの新作」としての作品番号を付けたことはいうまでもありません。それぞれの「元ネタ」は、1797年に出版したハ長調のソナタ「Op.87」は、1793年に出版されたOp.74-1(Hob.III:72)、1803年に出版した変ホ長調のソナタ「Op.90-1」とト長調のソナタ「OP.90-2」は、それぞれ1797年のOp.76-6(Hob.III:80)と1799年のOp.77-1(Hob.III:81)という弦楽四重奏曲です。 ミュラーの作った「フルート・ソナタ」は、元の弦楽四重奏曲をほぼ忠実にフルートとピアノに編曲したもので、それぞれの楽器がほど良く活躍するようになっている、なかなかの「職人技」が感じられるものです。ただ、その際にオリジナルの第3楽章のメヌエットをカットして、4楽章形式だったものを3楽章形式にしてあります。 そんないわくつきの作品の全曲をこのイタリアのレーベルに録音したのは、イタリア国内では確固たる名声を誇っているフルーティストのニコラ・グイデッティと、自身も作曲家で現代曲の初演なども手掛けているピアニストのマッシミリアーノ・ダメリーニです。このピアニストの名前を見ただけで、なんだか力が抜けてしまいますが、フルーティストのもはやピークは過ぎたテクニックと音楽性は、いかにもこのレーベルらしい薄っぺらな音と相まって、これらの「贋作」を聴くも無残な姿にさらけ出していました。 ちなみに先ほどのホーボーケン番号にも反映されている83番まである弦楽四重奏曲の番号は、もはや現在では偽作があったり作曲順ではなかったりと、正しい番号とは言えなくなっていますが、それがきちんと直された68番までの番号が広く使われるようになることは、まずあり得ないでしょう。だから、別に「贋作」だからと言って騒ぎ立てることもないんですよ。 CD Artwork © DYNAMIC S.r.l. |
||||||
そのニューイヤー・コンサートの中継の楽しみの一つが、管楽器のトップが誰なのか、というものではないでしょうか。例えばウィーン・フィルのフルートには現在はフルーリー、アウアー、シュッツという3人の首席奏者がいますが、それが毎年変わるので、それだけでオーケストラの音色まで変わってしまうのですよね。今度は、誰が「出番」なのでしょうか。 ここに書いた3人の順序は、ウィーン・フィルの公式サイトのメンバー表と同じで、おそらくこのポストの在任期間が長い順なのでしょう。ただ、これはあくまで私見ですが、今の時点では「腕」の順番はちょうどこの逆になっているような気がします。 そんな、今までのアンサンブルのCDを聴いた限りでは間違いなくウィーン・フィルの中では最高の演奏を聴かせてくれていたカール=ハインツ・シュッツのソロ・アルバムが登場しました。ただ、これは2011年と2012年に録音されたもので、おそらくシュッツ自身がプロデュースしてリリースしたCDの音源を日本のメーカーが買い取って、自社製品として再リリースしたものです。4人の作曲家の代表作が収められています。 まずは、プロコフィエフのソナタです。ヴァイオリン・ソナタとしても知られていますが、こちらの方がオリジナルです。第1楽章のテーマがずいぶんとおとなしい感じだったので、ちょっと意外だったのですが、しばらく聴いているとそれは意図的に抑えた表現であることが分かります。続く展開部になったとたん、フルートの音色がまるで変っていたのですよね。特に低音が、それまではほんのりとした柔らかい音だったものが、とても鋭角的でエネルギッシュなものに瞬時に変わってしまったのですよ。こんな見事な使い分けができる人なんて、なかなかいませんよ。しっとりとした第3楽章も素敵。特に三連符だけのフレーズでの低音のピアニシモなどは、この世のものとは思えないほどの美しさです。そして、その演奏は決して感情に溺れることはなく、冷静に自分自身を見つめてコントロールしているもう一人の自分の姿がはっきり感じられるという、とても次元の高いものなのですから、すごいです。 ヒンデミットのソナタも、これまで聴いてきた演奏で与えられた「なんてつまらない音楽なんだ」という印象を根本から覆すような鮮やかなものでした。 ところが、次のヨゼフ・ラウバーという初めて聴くスイスの作曲家のソナタになったら、音がガラリと変わっていました。アルバムの中でこれだけ2011年の録音で、会場もエンジニアも他の曲とは異なっているせいなのですが、これがあまりにもひどい音なのですよ。ピアノはまるでおもちゃみたいな安っぽい音ですし、フルートも妙にキンキンしていて、さっきまでの繊細さなどは全く伝わらない乱暴な音に録れていたのです。曲自体は後期ロマン派の音楽にフランス印象派の要素が少し加わっている、とても技巧的なものですから、これからはリサイタルなどでは需要が出てくるのではないでしょうか。 最後のマルタン(実は、ラウバーの弟子)の「バラード」も、多くの凡庸な演奏とは一線を画した、考え抜かれた表現と、それを音にできるスキルが融合した素晴らしいものでした。 CD Artwork © Camerata Tokyo, Inc. |
||||||
そう言う意味で、このヤンソンスの演奏は、そんな浮ついたところなど全くない、とても真摯に作品に向かい合って、必要なことを一つ一つきちんと成し遂げたという満足感が伝わってくるものでした。やはり、それがプロでもアマチュアでも最低限求められるものだと、気づかされてくれたCDです。 なによりも、バイエルン放送合唱団の地に足の着いた堅実な歌い方が、光ります。ダイナミック・レンジから言ったら、とてつもないものをもっているこの作品で、そのピークはもちろん「Dies irae」の頭でしょうが、逆にその最も小さな部分が曲のど頭です(どんなCDでも、ここは目いっぱい小さい音が録音されているので、ちょっと聴こえないな、といってボリュームを上げ過ぎると、次の曲が始まった時に後悔することになってしまいます)。ここの本当に聴こえるか聴こえないかの弦楽器に乗って、この合唱がまるで包み込むように歌い出す「Requiem」を聴いただけで、この演奏は合唱に関しては満足が得られるという確信を持つことが出来ます。それは、ただ「小さい」だけではなく、その一言の中にしっかりとした「表現」が宿っていたのです。もちろん、ほどなく登場するベースのパート・ソロ「Te decet hymnus」も、よくある粗野な歌い方とは無縁のひょっとしたら「高貴」と言っても構わないほどのたたずまいです。 期待にたがわず、この合唱は最後までそれぞれのパートがしっかり自信を持った歌い方で、冷静な中にも熱気を感じさせるという素晴らしいことをやってくれていました。これは、この作品における一つの理想的な合唱の形だったのではないでしょうか。 ソリストたちは、そんな合唱に支えられて羽目を外さない程度に奔放な歌い方をしていたような気がします。ただ、ソプラノのストヤノヴァは、勢い余ってピッチが常に上ずっていたのがちょっと耳障りだったかもしれません。テノールのピルグも、最初はどうなることかと思うほどのハイテンションでしたが、徐々に落ち着きを取り戻してきて、「Hostias」では見事なソット・ヴォーチェを聴かせてくれました。この、ほとんどファルセットと地声との境目が分からないような歌い方は、妖しすぎます。仙山線で居眠りをしたら、愛子過ぎました。 ブックレットを見ると、なぜかこの録音が行われたミュンヘンのガスタイク(帯にある録音日は間違っています)ではなく、その数日後に行われたウィーンのムジークフェラインザールでの写真が載っていますが、そこにはチューバではなく「チンバッソ」の姿があります。ヴェルディ本人はオフィクレイドを指定していますが、この楽器でもトロンボーン・パートと見事に融合したリリカルな低音が聴こえてきます。 実は、この、ウィーンでの演奏が、別のレーベルから映像(DVD, BD)で発売されています。こんな素晴らしい演奏なのですから、音だけではなく映像でも楽しんでみたいですね。会場が違えばまた印象も変わってくるかもしれませんし、このチンバッソの姿も見てみたい気がします。CDでは、合唱が「Sanctus」の入りで、おそらく立ち上がるタイミングもあってちょっともたついているのですが、ウィーンではどうだったのでしょう、とかね。でも、かなり強気の価格設定なので、ちょっと手が出ません。でも、欲しいなぁ。今年のクリスマス・プレゼントに贈ってくれる人でもいればいいのですが。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |
||||||
今回の「レクイエム」は、それとはだいぶ様子が異なっています。作曲家がこの曲を作ろうとした動機は、彼の親友が若くして亡くなった時に、その思いをなんとしても言葉と音楽によって表現したいという、作曲家としての使命感のようなものだったというのですからね。 その時に彼が考えたのが、通常の「レクイエム」の典礼文の他に、彼のパートナーであり、「マルコ」のテキストも作っていた詩人ベンクト・ポーヤネン(きっと間違っている表記)によるスウェーデン語のテキストを用いることでした。ただ、これはラッターやブリテンの同名曲のような、全く別の曲としてそのテキストを使った曲を作るのではなく、あくまで古典的な「レクイエム」の形式は守った中で、それぞれの曲の中に、そのポーヤネンのテキストによる音楽を挿入するという手法です。 曲の構成は、フォーレやデュリュフレと同じタイプ、編成はソプラノとバスのソリストと混声合唱に弦楽器にホルン2本とティンパニが加わったオーケストラにというものです。 不気味なティンパニに乗って始まる「Introitus」などは、まるで無調かと思われるような刺激的なフレーズを演奏、それは緊張感あふれるスウェーデン語のテキストを導き出すもので、ネイティヴにとってはかなりのインパクトとなったことでしょう。そこに、「Requiem aeternam」というラテン語のテキストが入ってくると、音楽はほんの少し安らかなものに変わります。そんな感じで、この異種のテキストの混在は、ラテン語だけの時よりも立体的、あるいは具体的な情感を聴衆に与えることになっているのではないでしょうか。スウェーデン語には全く縁のない我々でも、その音楽の持つ緊張感によって、それはきちんと伝わってきます。 しかし、その2つの言語は、やがて収斂の方向に向かっているようです。まるでフォーレの作品のような美しいソプラノ・ソロによる「Pie Jesu」では、合唱によるスウェーデン語のテキストは、ラテン語のソプラノをやさしく包み込みます。そして、弦楽器によるこの曲のエンディングが終わらないうちに、アタッカで無伴奏の「Agnus Dei」が始まります。これは、まさにこの作品の白眉でしょう。 同じように最後の「In paradisum」も、とても美しい音楽に仕上がっていました。スウェーデン語の部分がすでにいかにも北欧のフォーク・ミュージックのようなとてもキャッチーな音楽に変わっていますが、それがひとくさり盛り上がった後に、まるでデュリュフレのあの最後の合唱のような透明感あふれる音楽がラテン語で歌われます。その瞬間、シクステンによってもたらされた北欧音楽とラテン語の宗教音楽との見事な融合が見事に感じられました。同時に、彼の亡き親友に対する思いも。 カップリングは、同じコンサートで歌われていたエリック・ウィテカーの「When David heard」です。英語のテキストは旧約聖書に登場する、ダヴィデ王が息子アブサロムの謀反に対して反撃を講じた際に、そのアブサロムが殺されたことを知って嘆き悲しむ部分から取られていて、無伴奏のクラスターの中でひたすら「My son」という言葉を繰り返すという印象的な作品です。 残響の多いライブ録音に対応できなかったエンジニアのせいなのか、ノーマルCDのせいなのかは分かりませんが、合唱の高音が明らかに頭打ちになっている録音は、かなり辛いものがあります。おそらく当日のスンズヴァルのグスタフ・アドルフ教会では、こんな糞詰まりのような音ではなく、もっと伸びのあるサウンドが響き渡っていたことでしょう。 CD Artwork © Intim Music |
||||||
今ではそういう「元アイドル」たちが活躍している場が、「歌番組」ではなく「バラエティ」というのが、悲しいですよね。「アイドル」というのは、いくら年をとっても「使い捨て」でしかないのでしょう。ですから、まりやがそういう道を自ら絶って、1982年にスッパリと歌手活動から退いた、というのは、なんとも潔い決断でした。 しかし、それから2年後、彼女は全くリニューアルした姿で音楽シーンに戻ってきました。かつては、世のアイドルの習いとして、他の職業作曲家、作詞家が作った曲を歌っていたものが、その時に発表されたアルバムには全て自分で作詞・作曲を手がけた曲を自ら歌ったものが収録されていたのです。たった2年で、彼女は「アイドル」から「シンガー・ソングライター」へと変貌していたのでした。というより、その時に彼女は本来「アイドル」ではなかったことを、世に知らしめたのです。 その時リリースされた記念すべき彼女の「ファースト・アルバム」が、今年で発売から30年経ったということで、最新のリマスターが施され、多くのボーナス・トラックも加えられた形でのCDがリイシューされました。そして、嬉しいことに、同時にLPもリリースされたのです(こちらにはボーナス・トラックはありません)。 このアルバムが最初に発売された1984年と言えば、まさにCDの黎明期でした。クラシックではその1年前にはCDが発売されていましたが、ポップスでの「CD化」は少し遅れていたようで、まだまだポップス・ファンにとってはCDは縁遠いものという状態だった頃なのでしょうから、もちろんこのアイテムもまずはLP、そしておまけみたいな形でCDが発売されていました。もちろん、「これからはCDの時代だ」と信じて疑わなかったものとしては、1枚3800円もするCDをありがたがって購入していました。   そんな「いい音」で全曲聴きなおしてみると、いまさらながらこのアルバムの完成度の高さが分かります。タイトル通りのとてつもないほどの多様性、これは、最近のアルバムでは失われてしまっているのだと、改めて思わされてしまうのが、とても残念です。 LP Artwork © Warner Music Japan Inc. |
||||||
今回の、やはり「コシ」も、前作と同じく、殆ど対訳で出来ている分厚いブックレットの中にCDが入っているという装丁、デザインも色違いで同じものが使われています。きっと、「ドン・ジョヴァンニ」も間違いなく同じデザインで別の色でしょう。こちらはなんたって色気違いの話ですからね。 と、お揃いのパッケージではあるのですが、何かが足りません。そう、「フィガロ」ではおまけとして同封されていたBD-Aがここには入っていなかったのですよ。これは、まさに予想通りのことでした。あの頃のSONYのBD-Aに対する盛り上がりは、いったい何だったのでしょう。仕方がないので、ノーマルCDで聴いてみましたが、やはりそのショボさにはガッカリさせられてしまいます。 とは言っても、このチームの演奏のテンションの高さは、そんなレーベルの気まぐれに左右されるようなことはなく、全く変わってはいませんでした。とにかく序曲のテンポの速いこと、「ミソファミレドシド」という管楽器の掛け合いなどは、もう崩壊する一歩手前、顔を真っ赤にして吹いているさまが見えるようです。しかし、レシタティーヴォが始まると、そこは雄弁な通奏低音に乗っての生き生きとしたドラマが展開されることになります。ただ、今回もハーディ・ガーディがクレジットされていますが、いったいどういう使われ方をされているのか、ちょっと分かりませんでした。 そして、なによりも素晴らしいのが今回のキャスティングです。よくもこれほど粒ぞろいのソリストを揃えたものだと、驚いてしまいます。もちろんそれぞれに上手なのは当たり前なのですが、それが適材適所なのがうれしいところです。よく、2人の姉妹の声が似ていて、いったい今歌っているのはどちらなのか分からなくなってしまうという状態に陥ることがありますが、ケルメスとエルンマンは、見事にタイプの違う声ですからそんなことはありません。その上、それが二重唱になると見事に融け合っているのですからね。このケルメスという人、最初に聴こえて来た時にはなんと頼りない声、と思ってしまったのですが、どうしてどうして、曲が進んでいくとびっくりするような表現力の広さでした。要は、「ちょっと奥手な姉が、次第に大胆になっていく」というドラマの過程を見事に演じていたのですよ。エルンマンの方は、最初からちょっとあばずれ、でしょうか。 もう一人、感服してしまったのが唯一のテノールのロールを歌っているケネス・ターヴァーです。この人はこちらのドン・オッターヴィオを聴いてとても感心したことがありますが、ここではまさに打ちのめされた感じ、彼は理想的なモーツァルト・テノールですね。特に、「Un'aura amorosa」での完全にコントロールされたソット・ヴォーチェは、言いようのない感動を与えてくれます。やっと、ペーター・シュライヤーを超える人が出てきました。 それにつけても、このフェランドはBD-Aだったら、もっともっと素晴らしく聴こえるはずなのに、と思いながら聴き続けているのは、並大抵のストレスではありません。ハイレゾ配信もないようですし、困ったものです。 CD Artwork © Sony Music Entertainment |
||||||
最近では、そのナガノのブルックナーもBD-Aにまとめるなど、このフォーマットにかなり熱心なところを見せているのは、さすがに音にこだわるレーベルならではのことです。そして、今回は2002年に録音されていた「ワルキューレ」のライブ録音が、BD-Aとなってリイシューされました。実は初出時には、CDだけではなく「DVD-Audio」という、今では全く忘れさられているフォーマットのものも同時に発売になっていました。音にはこだわっても、ちょっと先が読めなかったのでしょうね(でも、このDVD-Audioはまだちゃんと入手できます)。それがBD-Aになったことで、やっと当初の目論見が達成できたということになります。しかも、DVD-Audioでさえディスクが3枚(CDでは4枚)必要だったものが1枚に収まってしまったのですから、うれしいことです。おそらく、ワーグナーのオペラで、BD-Aになっているのはショルティの「指環」と、これしかないはずです。ワーグナーでこそ、例えば「ラインの黄金」とか1幕版の「オランダ人」のように、切れ目なく2時間近く演奏されるものではBD-Aが最適のフォーマットになるというのに。 今回のBD-A、もちろんジャケットはCD/DVD-Audioと同じですが、対訳などが入っているブックレットまで、それと全く同じものだったのには、笑ってしまいました。「DVD-Audioで新しい体験を!」なんて書いてあるのですから、おかしいですね。ま、その他に薄っぺらな、BD-Aのトラックが書いてある紙がケースに入っていますが。 したがって、出演者のプロフィールなども2002年の時点での記述になっています。例えば、藤本さんのところでは「2003年にはベルリン・ドイツ・オペラでクンドリーに初挑戦」みたいなことが書かれていますよ。実は、これが録音された2002年と言えば、藤本さんがバイロイトにデビューした年で、これと同じフリッカを歌っていました。こちらのライブが7月ですから、その頃はバイロイトのリハーサルなどもあって、二つの劇場を忙しく行き来していたのでしょうね。 このBD-A、さすが、リアルな音場が目の前に広がります。ザイフェルトのジークムントは、少々線が細いものの、揺れ動く若者の直情的な心情をしみじみ歌いあげます。マイヤーはさすがベテラン、堂々とした歌い振りは、当時最高のワーグナー歌いとしての地位を確立したことをまざまざと見せ付けてくれます。ブリュンヒルデ役のシュナウト、この人もメゾでデビューして、ソプラノに転向した人。来日も多く、この3年前N響の定期のソリストとして、シュトラウスなどを歌っていました。ちょっとヒステリックな声ですが、なかなかの表現力です。ただ、第3幕などは明らかにバテていることが分かります。トムリンソンのヴォータン、手元にバレンボイムのちょうどこれから10年前のバイロイトのCDがありますが、当時に比べると、確かにカッコよくなりました。貫禄ってものかも知れません。そして、お待ちかね藤村さん。いやぁ、確かに良い声です。高音から低音まで、ふくよかで滑らかな響き。とにかく良く通る声で、言葉のハンデも全く感じられません。これは本当に素晴らしい。皆が期待するのも頷けます。もちろん、現在では彼女は期待通りの活躍ぶりですね。 BD-A Artwork © FARAO Classics |
||||||
そのロイヤル・フェスティヴァル・ホールには、1954年に据え付けられたオルガンがあります。これは、当時としては珍しいドイツ・バロックの様式で作られたものでした。それはまさに、「シュニットガー」とか「ジルバーマン」といった、バッハご愛用のブランドの流れをくむものです。そのオルガンがこのたび大規模な改修工事を施され、めでたく今年の3月に完了の運びとなりました。徹底的なオーバーホールを施して、創建当時の音にリニューアルされたのですね。そのお披露目に、一連のコンサートが開かれたのですが、これもその一つ、オルガンの入るオーケストラ曲の代表格であるプーランクとサン・サーンスの作品が、3月26日に演奏されました。元のオルガンが最初に演奏されたのが3月24日でしたから、まさに丸60年目にその栄誉を担ったのが、レジデント・オーケストラであるロンドン・フィルだったのは言うまでもありません。 オルガンのソロは、ジェイムズ・オドネルです。彼は、現在はウェストミンスター寺院のオルガニスト兼聖歌隊の指揮者の地位にあります。非常に混乱しやすいのですが、彼が2000年にこのポストに就く前までは、「ウェストミンスター大聖堂」で同じ仕事をしていました。こちらを見ていただければ分かりますが、この2つの施設は宗派も異なる全く別のものです。オドネルは「大聖堂」時代にも多くのCDを出していましたから、無理もないのかもしれませんが、今回のCDの公式な紹介文では、見事に「大聖堂」と間違えています。これは、こちらを始め、多くの媒体にコピーされてどんどん増殖していますよ。おそらく、これを書いた人は自分のミスに気付かないだけではなく、こんな指摘をされても何のことかすらわからないのではないでしょうか。本当に困ったものです。 ま、そんな些細なことはさておいて、この新装なったオルガンの音を聴いてみましょう。プーランクのコンチェルトでまずそのフル・オルガンが聴こえてきた時には、まぎれもないドイツ・バロックのオルガンの音だ、という気がしました。その、一本芯が通っていて、モノクロームの音色は、ちょっとプーランクとはミスマッチのような気がしますが、しばらく聴いているとこれこそがまさに普遍的なオルガンの音なのだ、という確信に変わります。いかに時代や国籍が変わろうと、オルガン音楽の「原点」がここにある、という感じでしょうか。オドネルの演奏は、そんな自信に満ちたもののように感じられます。その上で、プーランクならではの瀟洒な味わいも、決して失われてはいません。ただ、ネゼ・セガンの指揮は、ちょっと四角張ってはいないでしょうか。 しかし、サン・サーンスの「オルガン交響曲」になると、今度はまるで暴れ馬のようにいったいどこへ行ってしまうのかわからない指揮ぶりに変わりました。もしかしたら、最初の部分にはオルガンが入っていないので、その呪縛から逃れられたせい?などと思ってしまうほどの、変わりようです。しかし、オルガンが加わった第1部の後半などは、うって変わってしっとりとした「歌」にあふれています。第2部はやはりイケイケの音楽、最後はまだ終わっていないのにフライングの「ブラヴォー!」ですよ。まあ、「お祭り」だから、これでいいのでしょう。 CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |
||||||
もっと現実的に、さるCDメーカーのFacebookページではクリスマス・キャロルやクリスマス・カンタータなど、これでもかというぐらいしつこく「クリスマス」の文字が躍っているアイテムを躍起になって売りつけようとしています。いったい、こんなものを見たからと言ってどのぐらいの人が購入するのでしょうかね。そんな「業界」のミエミエの企みなどには踊らされずに、もっと真摯にこの行事を祝いたいとは思いませんか? そんな、「クリスマス」というタイトルこそありませんが、「クリスマス」には決して欠かすことのできない作品が「マニフィカート」です。ご存知のように、ここではキリストを身ごもったことを知らされた聖母マリアが述べた感謝の言葉が歌われますから、まさに「生誕」へ向けての始まりということになります。テキストは新約聖書の「ルカによる福音書」から取られていて、その最初のフレーズが「Magnificat anima mea Dominum(私の魂は主を崇める)」ですので、その最初の単語が曲名になっています。 「マニフィカート」ではなんと言ってもバッハの作品が有名ですが、ここではあえて1980年生まれのノルウェーの作曲家、キム・アンドレ・アルネセンが2010年に作った最新のものを聴くことにしましょう。まだ若いのに、多くの合唱曲を様々な団体から委嘱されるなど、すでにノルウェーを代表する作曲家として認められているアルネセンは、ここで演奏しているニーダロス大聖堂少女合唱団と、その指揮者アニタ・ブレーヴィクからの委嘱によって、この広々とした空間を持つ大聖堂で演奏することを念頭に置いてこんなキュートな「マニフィカート」を作りました。一応女声合唱のためのものですが、多くの団体に歌ってもらえるようにとの配慮から、混声合唱のバージョンも用意されています。 全部で7つの曲から出来ています。まず1曲目の「Magnificato anima mea」は、チェロによる深いテーマで始まります。それを受けて、弦楽器に乗った少女たちのの無垢な合唱が広がります。途中のア・カペラの美しさはまさに絶品。最後にオルガンが登場して締めくくります。 2曲目の「Ecce enim」はまるで往年の映画音楽。後半には、テレビドラマの劇伴でおなじみのキャッチーなハーモニーが聴こえてきます。 3曲目の「Quia fecit」は、チェロによるプレーン・チャントが合唱に引き継がれ、シンプルな音楽が続きます。 4曲目の「Et misericordia」は最もキャッチーなナンバーでしょう。ソロによって歌いあげられたものを、合唱が受け、最後はソロ、合唱、オケが一体となってテーマを盛り上げます。 5曲目の「Fecit potentiam」は一転して、弦楽器がリズミカルなパターンを繰り返します。合唱もとても晴れやかなテーマ。その中の転調も、聴き慣れたものです。 6曲目の「Suscepit Israel」は、美しいソロで始まります。そこに、合唱団員によるソロが加わり、美しい二重唱が繰り広げられます。まるでフォーレの「Pie Jesu」のような感じです。 最後の「Gloria Patri」は、テンション・コードによるピアノのイントロ。これにもプレーン・チャント風のしっとりした合唱が続きます。 という具合で、言ってみればジョン・ラッターをベースに、アルヴォ・ペルトを少し加え、エリック・ウィテカー風に仕上げたテイスト、といった感じの曲でしょうか。難しいことを考えずに、すんなりと受け入れられる音楽です。これをクリスマスに聴けば、一人ぼっちの人も、「連れ合い」がいる人も、心から癒されるに違いありません。 SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |