ロック・ファンのためのジャズ案内のヘッダー
Rock Listner's Guide To Jazz Music
Larry Young
| Into Somethin' | ||
 曲:★★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★★★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1964/11/12 [1] Tyrone [2] Plaza De Toros [3] Paris Eyes [4] Back Up [5] Ritha |
Sam Rivers (ts) Grant Green (g) Larry Young (oeg) Elvin Jones (ds) |
| ジミー・スミスを追うオルガン奏者は何人か出ていたものの、今でも名を残している人というのは少なく、例外的に名前が知れているのがこのラリー・ヤングではないだろうか。また、この人には「オルガンのコルトレーン」というキャッチフレーズが必ず付く。でも、なぜなのか僕はよくわからなかった。確かに、本作(と「Unity」)にはエルヴィン・ジョーンズが参加しているし、テナー・サックスはフリー系のサム・リヴァース。そして時代は64年。コルトレーン黄金時代の流れに乗っているように見える。そして、ジミー・スミスのスタイルと比べると明らかにモダンなヤングのオルガン。そこがスミスのスタイルから抜け切れなかった後追いプレイヤー達と大きく違うところでもある。しかし、オルガンのフレーズや音色にはコルトレーンのような前衛性があるわけではなく、むしろ聴きやすいし、もちろんスピリチュアルな響きもない。このアルバムではグラント・グリーンのギターがまた親しみやすさを増長しているし、エルヴィンも抑え気味のプレイをしているために革新的なジャズをやるんだ、という力んだところがない。でもそこが良いところでもある。オルガン・ジャズってどんなものなんだろう、という人に意外と抵抗なく勧められる聴きやすい1枚。オルガンのコルトレーン的な音楽を求めている人はもう少し後の作品を。(2006年9月20日) | ||
| Unity | ||
 曲:★★★★★ 演奏:★★★★★ ジャズ入門度:★★★ 評価:★★★★★ |
[Recording Date] 1965/11/10 [1] Zoltan [2] Mink's Dream [3] If [4] The Moontrane [5] Softly As In A Morning Sunrise [6] Beyond All Limits |
Woody Shaw (tp) Joe Henderson (ts) Larry Young (org) Elvin Jones (ds) |
| 新進気鋭のウッディ・ショウとジョー・ヘンダーソンをフロントに迎えたこのアルバムではエネルギッシュな新主流派オルガン・ジャズが展開されている。ヤングのオルガンは、ことさら音数で攻めるわけでもスピリチュアルな響きがあるわけでもないところはここでも同様で、しかしその分純粋にカッコいいオルガン・ジャズを楽しめる。65年といえばハード・バップはとうに終焉を迎えて、いわゆる新しい60年代ジャズが発展していく真っ只中。アーシーなオルガンの音色が新主流派系ジャズに馴染むのかという懸念は無用。3曲のオリジナルを提供しているウッディ・ショウのややフリーキーでキレのあるトランペットが素晴らしく、ジョー・ヘンダーソンのテナーもアグレッシヴな響きで応酬。エルヴィンは重みとキレを持ち合わせたドラミングで力感を与えている。そんなメンバーに囲まれた主役は音色こそオーソドックスなオルガン・サウンドでありながらR&Bやソウル系のフィーリングとは一線を画し、60年代という時代のジャズに真っ向勝負しており、その個性が際立つ。フレーズだけで言えば初期のジミー・スミスの方は今の基準で聴いても斬新だと思うけれど、クリエイトしている音楽はラリー・ヤングの方が確実に新しい。(2006年9月21日) | ||
| Of Love And Peace | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★☆ ジャズ入門度:★ 評価:★★★★ |
[Recording Date] 1966/7/26 [1] Pavanne [2] Of Love And Peace [3] Seven Step To Heaven [4] Falaq |
Eddie Gale (tp) Herbert Morgan (ts) James Spaulding (as, fl) Larry Young (org) Wilson Moorman III (ds) Jerry Thomas (ds) |
| 一聴して前衛ジャズ。フロント・ラインのブローはフリー・ジャズ系そのものでこの種の音楽が好きな人を惹きつける魅力十分。暴れるツイン・ドラムがその印象を尚一層強いものにして、なるほどこれが「オルガンのコルトレーン」と評される所以なのか、とある程度納得できる。しかし、コルトレーンの音楽はフリー・ジャズであることに真価があるのではなくスピリチュアルな面がフリーな表現に昇華しているところにあると僕は考えていて、その点では、この前衛的なアルバムをもってしてもコルトレーン的だという印象を受けない。そういう例えをするのならむしろ「オルガンのセシル・テイラー」と言った方が適切なように思える。それはともかく、オルガンでこの種の音楽に挑戦しようとしたのは恐らくラリー・ヤングだけだっただろうし、その内容は非常に充実しているのは間違いない。ただし、そのサウンドとフレーズは、例えばライフタイムの「Emergency!」のようなロック的前衛さはなく、むしろ前衛ジャズにオーソドックスなオルガンを正面からぶつけたかのようなところにヤングの頑固さと自信を感じる。多人数編成のコンボが織り成す混沌に身を委ねて体で聴く1枚。(2007年2月8日) | ||
| Mother Ship | ||
 曲:★★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★★ 評価:★★★ |
[Recording Date] 1969/2/7 [1] Mother Ship [2] Street Scene [3] Visions [4] Trip Merchant [5] Love Drops |
Lee Morgan (tp) Herbert Morgan (ts) Larry Young (org) Eddie Gladden (ds) |
| 新進派、あるいは前衛的なイメージのあるラリー・ヤングの代表作とされている「Unity」は、確かにそれまでのゴスペルの匂いが残るオルガンと比べると一線を画す新しい感覚があるものの、今聴くと言われるほどには先進的という感じはしない。その後の「Of Love And Piece」は完全な混沌としたフリー・ジャズ狙いで極端な方向へ。その後に出た本作はわざとらしい前衛を狙わず、しかし感覚的には前衛に向かっていて、特にオルガン奏法は次の世代のジャズ・ロック的なフレーズになってきている。見慣れないメンバー2名がいることでクオリティの不安を案じるも骨太なテナーと重量級ドラムはこの時代ならではの勢いを感じさせるもの。強いて言えば、ここでどんな活躍を見せるか期待していたリー・モーガンが思ったほどには目立っておらず、自由度を与えられたように見える音楽ほどには自由に吹けていない。クオリティは決して低くなく、しかしもうひとつ突き抜けたところまで行っていないこの音源がオクラ入り(録音から11年後にリリース)していたのはブルーノートらしい選択。(2013年11月2日) | ||
| Lawrence Of Newark | ||
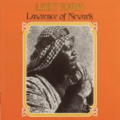 曲:★★ 演奏:★★★★ ジャズ入門度:★ 評価:★★★☆ |
[Recording Date] 1973 [1] Sunshine Fly Away [2] Khalid of Space, Pt. 2 Welcome [3] Saudia [4] Alive [5] Hello Your Quietness (Islands) |
Charles Magee (el-tp) Pharoah Sanders (ts) Dennis Mourouse (sax, electric sax) James Ulmer (g) Cedric Lawson (elp) Larry Young (org, bongoes, vo) Diedre Johnson (cello) Juni Booth (b) Don Pate (b) Abdul Shahid (ds) James Flores (ds) Howard King (ds) Art Gore (ds, elp) Abdul Hakim (bongo, per) Armen Halburian (bell, conga, per) Stacy Edwards (conga, per) Umar Abdul Muizz (conga, per) Poppy Laboy (per) Jumma Santos (conga, per) |
| ブルーノート時代から少し間を開けてマイナー・レーベルからリリースされたこのアルバムは、黙って聴いたらラリー・ヤングとわかる人が少ないんじゃないだろうか。サウンドはまさに70年代序盤という感じで、マイルスの「Bitches Brew」に端を発したクロスオーヴァー的なもの。そしてやはりこに時代に流行ったアフリカ回帰志向モノで、一定のリフを刻むベースを基盤に集団で代わる代わる奏者が乱れ入る。ヤングのオルガンは、旧来のジャズのあのアーシーなものではなく、同時代のロックも連想させる「ピヒャー」というサウンドで、運指でのフレージングはほとんどなくサウンド作りに徹している。大人数での演奏は確かに混沌としており、まだまだ終わる気配がないままフェードアウトする曲が複数あるなど、ジャム的に見えながら、全体的にはサウンドがコントロールされている感じがある。それ故に曲ごとに表現したいことの違いはあまり見えず、この時代ならではの混沌としたサウンド(なかなか騒々しいものではあるけれど)に身を任せて聴くアルバムと言える。(2024年3月10日) | ||
