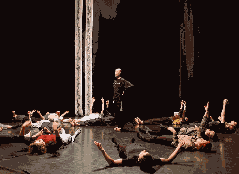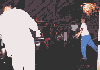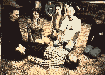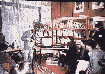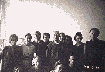�@1983�N�A���{�l�Ԑ��S���w���Ấu�J�[���E���W���[�Y�v���[�N�V���b�v�ɎQ�������ہA�|�����b�X���Œm���Ă����|���q���ɏo��A�g�̂�����ɓ��ꂽ���H�Ɏ䂩�ꂽ�̂����������Ƃ��Đg�̐S���w�I�ȕ������u���B
�@�����́A�G���J�E���^�[�E�O���[�v��|�����b�X�������߂Ƃ���l�X�ȃ��[�N�V���b�v�i�o�C�I�E�G�l���M�[�@�A�Q�V���^���g�E���[�N�A�g�����X�E�p�[�X�i���A���ϗÖ@�c�j�ɎQ��������A�D�y�ɂ����āu������Ƃ��炾�̉�v���J�n�����H�̏��ʂ��đ̌���[�߂��B
�@�@1988�N�A�Í������u�R�C�m�v�����o�[�̐�ۂɂ�镑�����h�ɎQ��������A�S�g�T���̕��@�Ƃ��Ă̕����ɈӋ`�������A�ȗ��A�����̕��@�Ɋ�Â����g�̐S���w�I�A�v���[�`��ςݏd�ˁA�����E�C�O�ł�Butoh Dance Method�̎w�����s���A�����Ɏ���B
�D�y�w�@��w�l���w�� �Տ��S���w�ȋ���(2004�N�l���`)�B
�D�y�w�@��w�S���w�� �Տ��S���w�ȋ���(2020�N�O����N�ސE)�B
�������N�Z�C�V������㩂ƃE�c��Ԃɂ��Ẳ�� �� ������b�N�X�̂��߂Ɂv(Apr.2009)
���g�̐S���w�Ɋւ���_��:
�r�̒E�͂ɂ��āi�|�����b�X���ɂ�����u�r�̂Ԃ牺����v����j-���ʓI����
- �����r�� and Zaluchyonova,E.A. "�r�̒E�͂̍���Ɋւ�������I����"
�@An Experimental Study of the Difficulty in the Arm Relaxation Task"
�l�Ԑ��S���w�����A195-202, Vol.14,No.2, 1996a
- �����r�� "�r�̒E�͂̍���ɂ��Ă̍Ċm�F" �Ö��w����, 34-40, Vol.41, No.1-2, 1996b
- �����r�� "�r�̒E�͂ɂ�����S���w�I����" �l�Ԑ��S���w����, 212-219, Vol.12, No.2, 1994
�����Ɛg�̐��ɂ���-�@
- �����r���@"�r�̂Ԃ牺������Љ�̑���"
- �l�Ԑ��S���w����,21-26,No.8,1990
- �����r���@"�g�̂̒E�Љ�ƕ���"
- Memoirs of H.I.T.,217-224, No.19,1991
- �����r���@"�E�Љ�g��"
- Memoirs of H.I.T., 265-273,No.20,1992
- Toshiharu Kasai "A Butoh
Dance Method for Psychosomatic Exploration"
- (�t�����X���E�|�[�����h���)
- Memoirs of Hokkaido Institute of Technology, No.27,309-316, 1999
- Toshiharu Kasai "A Note on
Butoh Body"
- (�t�����X���E�|�[�����h���)
- Memoirs of Hokkaido Institute of Technology, No.28,353-360,2000
- �����r���@"�g�̐��̓W�J�Ɍ����ā\�u�r�̗����グ�v���b�X���\"
- Memoirs of H.I.T.,134-150,No30, 2002
- �����r���E�|������ "�S�g�Z���s�[�Ƃ��Ă̕����_���X���\�h"
- �_���X�Z���s�[�����A1-8,Vol.2,No.1,
2002
- �����r�� "�{�f�B�[���[�N�ɂ�����ϗ����߂�����"
- �l�Ԑ��S���w�����A139-147,Vol.20,No.2,2002
- Toshiharu Kasai and
Kate Parsons "Perception in Butoh Dance"
- (�t�����X���E�|�[�����h���)
- Memoirs of Hokkaido Institute of Technology,257-264, No.31, 2003
- �����r��"�����_���X���\�h�ɂ�����X�s���`���A���Ȃ�����Ƃ��炾"
- �l�Ԑ��S���w�����A92-100,Vol.21,NO.1, 2003
- �����r��"�g�̐S���Ö@�̊�{�����ƃ{�f�B���[�j���O�E�Z���s�[�̎��_"
- �D�y�w�@��w�l���w��I�v ��90��,pp.85-141, 2006
- �����r���u�����̑n���ɂ��Ă̐V���ȗ����Ƒn���I�ŃI�[�g�|�C�G�e�B�b�N�ȕ����\
���ӎ��̉B�ꂽ�ώ@�҂���g�S�V�X�e���̐ۓ��܂Łv[���{�ꎎ��(�����͉p��)]
- �D�y�w�@��w�l���w��I�v 2009�N�x No.86, 21-36 new!
Psychosomatic and Butoh Workshop
�C�O�Ȃǂł̎�ȃ��[�N�V���b�v�w�� [2010�N�܂ł̎����ł�]
2009-2010�N �C�M���X�ł̈�N�Ԃ̌����Ǝw��
- �_���X���[�u�����g�E�T�C�R�Z���s�[�̌���
�C�M���X��Helen Payne����(University of Hertfordshire)�̂��Ƃł̌���
�����h���E���[�Y���C�a�@(���_��)�A�P���u���b�W�E�t���|�[���a�@�Ȃǂł̕����_���X���\�h�w�����܂ށB
- �����̃��[�N�V���b�v�w���E�������C�u
�C�M���X�A�I�����_�A�X�y�C���A���g�r�A�A�G�X�g�j�A�ɂďW���I���[�N�V���b�v�w���Ȃǂ��s�����B
���Ƀ����h���ł͑�����A�������b�X�����w���B
2007-2008�N
*���̂悤�ɍ����ł̊������[���������B
- ���{�_���X�E�Z���s�[����F��(JADTA)�_���X�Z���s�X�g���i�擾
�D�y�_���X���[�u�����g�Z���s�[�������^�c
�D�y�w�@��w�Տ��S���w�Ȃɂ����āAJADTA���i�u�_���X�Z���s�[�E���[�_�[�v�擾�\�ƂȂ�Ȗډ^�c���X�^�[�g�B
- ���I�S���w�����𐄐i���邽�߂ɁA�т̐��ʉ����_��p�������I���͖@�ł����u�֘A���]�莿�I���́v���J�n���A�������\��_���쐬�̎���������(�w��\�E�C�m�_���Ȃǖ�10����)�B
2006�N
- Nov.6-12 Boston, Amherst, U.S.A.
Supported by Japan Foundation and The Japan Society of Boston.
2005�N
- Jan.6-11 Bilbao, Spain at Bilbao Arte for Artedandando
2003�N
- Apr.3-13 Krakow, Poland at Solvay for International Conference "Human Body - A Universal Sign"
2001�N
- Apr.9-11 in Szczecine, Poland at Teatr Kana
- Oct.6-7 in Kalamazoo, MI, U.S.A. at Wellspring Theater
- Oct.8-9 in Asheville, NC, U.S.A. for Asheville Contemporary Dance
Thatre
- Oct.14, in Raleigh, NC, U.S.A. for 36th American Dance Therapy
Association
- "Mind-Body Learning by Butoh
Dance Method"
2000�N - Oct.28 in Seattle, WA for American Dance Therapy
Association
- Nov.3-4 in Vancouver, Canada for Vancouver International Dance
Festival
- Nov.6-7 in Asheville, NC, for Asheville Contemporary Dance Theatre
- Nov.8 in Asheville, NC, at Warren Willson College
�u���ՓI�L���Ƃ��Ă̐g�́v���ۉ�c�y�у��[�N�V���b�v
International Conference "Human Body - A Universal Sign"
Krakow, Poland. Apr.7-13, 2003�@
�u�S�g�̒T���Ɠ����̂��߂̕����_���X���\�h�v
"Butoh Dance Method for Psychosomatic Exploration and Integration"(in press)
�|�[�����h�̌Ós�A�N���R�t�ŊJ���ꂽ�u���ՓI�L���Ƃ��Ă̐g�́v���ۉ�c�Ɋ�u���҂̈�l�Ƃ��ď��҂���A���{�Ƃ̕����𗬉�فuManggha�v�ɂāA"Butoh Dance Method for Psychosomatic Exploration and Integration"�ɂ��ĂQ���ԋ߂��u�����s���A���ɍD�]�ł������B
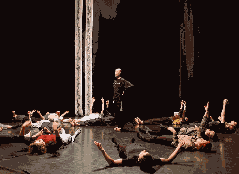 �Ȃ��A�����Ɋւ��钘��Œm����j���[���[�N��w�̖��_�����ASondra Fraleigh���ɂ�镑���֘A�̊�u��������ABUTOH�Ƃ������Ƃ����̒��S�e�[�}�ł������B
�Ȃ��A�����Ɋւ��钘��Œm����j���[���[�N��w�̖��_�����ASondra Fraleigh���ɂ�镑���֘A�̊�u��������ABUTOH�Ƃ������Ƃ����̒��S�e�[�}�ł������B
���̍��ۉ�c�́A�ߑO�́u��u���v�A�ߌ�́u���\�v�y�сu���[�N�V���b�v�v�A�[���̕����y�ѕ��x�E�����̌������g�ݍ��܂ꂽ��啶���v���W�F�N�g�ł���A���_���s�ψ��ɂ͍����ȉf��ēA�A���W�F�C�E���C�_�����̖���A�˂Ă����B
���Ԓ��́A�A���A���ۉ�c�ɎQ�������e���̎Q���҂�N���R�t�̊W�҂�ΏۂɁA�����_���X���\�h�̃��[�N�V���b�v�̎w�����s�����B�Q���҂���̊��z�ł́A���܂�����^�I�ȓ�����^�ɔ�����̂ł͂Ȃ��u�����v�Ɋ�Â��A�v���[�`���V�N�������Ƃ����B
�܂��A���̑��ɂ́A"Perception In Butoh Dance"�̋����҂ł��� Kate Parsons���j���͂��A�����J����삯�����\���s���Ă���A�e����g�߂邱�Ƃ��ł����B���Ԓ��A���[���b�p�ōŌÂƂ�����N���R�t�̃��M�F�E�H��w���{��Ȃ̊w���AAlicja����AGrzegorz����AFronchak����ɂ����b�ɂȂ�܂����B�L���Ċ��Ӓv���܂��B
����Butoh�V���|�W�E���y�у_���X�𗬃v���W�F�N�g Ex...it'99
Ex...it! '99 - 2nd International Butoh Symposium & Dance Exchange Project
Schloss Broellin,Germany. Aug.1-31, 1999
Psychosomatic Learning and Butoh Workshop
by Itto's Butoh Dance Method
Ex...it�́AEx��it�̊Ԃɕ��������āAExperiment it!/Excavate it!/Exceed
it!�Ȃǂ̂悤�ɃC���[�W���ӂ���܂���c�Ƃ����Ӑ}�����߂����̂ŁA1995�N�ɑ����ē��ڂ̃C�x���g�ƂȂ����B
�ꃖ���̒����ɂ킽�� Ex...it!'99�̃C�x���g�A���T�̓h�C�c�E�C�^���A�E�X�y�C���E�t�����X�E�C�M���X�E�A�����J�E�J�i�_�E�x�����[�V�E���V�A�E���{�i�X�c�ꓥ/�|������/��������/�A���V�i�E�W���W��
���ݏZ�j���珵�����ꂽ�P�S���̕����Ƃɂ�鑊�݃��[�N�V���b�v�ł������B���݂��ɏ��Ɏw���҂ƂȂ葼�̃����o�[�����b�X��������̂ŁA���ԓI���e�I�Ƀn�[�h�Ȉ�T�ԂƂȂ����BButoh�Ɋւ���f�B�X�J�b�V�����������s���A����͌���̍��ۃV���|�W�E���̂����������邱�ƂɂȂ����B
���T����O�T�ڂ́A���[���b�p�𒆐S�ɎQ�����Ă������h����T�O���ɑ��āA�����Ƃ����b�X�����s�����̂ŁA�Q���҂͏��Ȃ��Ƃ��S�|�T���̈قȂ��������Ƃ̎w�����邱�ƂƂȂ����B�ŏI���A���h���͕����Ƌ��X�A�u���[�������
Schloss Broellin �ɂēԂɂ킽��f�����X�g���[�V�������s���A�x����������̊ϋq�̊��т𗁂т��B
�܂��A�����Ɋւ��鍑�ۃV���|�W�E�����J�Â���A����W�̐��ƁA�N�w�ҁA�W���[�i���X�g�Ȃǂɂ���ăe�[�}������A�����ƂP�S���A���h���T�O���ɂ���哢�_��ƂȂ����B(�߁X���̓��e���o�ł����\��)
��l�T�ڂ́A�|�[�����h�̍`���V���`�F�`���s (Szczecin)�ɂāA���l�̕������\��Ɗe���̕����Ƃɂ��������s��ꂽ�B����Ɠ����i�s�I�Ƀx�������ɂ����Ă������������g�܂�AButoh�̕����I�ɑ��l�Ȃ������������ɈӋ`�[�������ƂȂ����B
���Ă̕����ƂƂ̏W���I�ȍ��h�P���̌��������Ƃ��M�d�ł��������A���m�N�w���Ƃ����ϓ_���猤�����Ă���h�C�c�̓N�w��Rolf Elberfeld�Ƃ̏o����ő�̎��n��������������Ȃ��B���̐��ʂ̈ꕔ���A"A Note on Butoh Body"(�����̂ɂ��Ă̊o������)�Ƃ����薼�Ř_���ƂȂ��Ă���B
�Ȃ��A���{�̃W���[�i���X�g�Ƃ��ăV���|�W�E���ɏ������ꂽ�������q���ɂ��̌��L�E�]�_���u�G���_���T�[�g�v�i�Q���P�O�����s�A2000�N�j�Ɍf�ڂ���Ă���B
Ex...it!'99
�u���U������́v by �������q

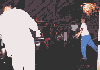



Seattle Butoh Workshops in 1999
Seattle, U.S.A., May 13-14, 17, 1999
Workshops of Itto's Butoh Dance Method
Joan Laage of Dappin Butoh in Seattle ����� D.Antonio�̋��͂ɂ���č��ە������[�N�V���b�v�Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ�BJoan
Laage�̓V�A�g���ɋ��_������Dappin' Butoh ����ɂ��A���{�ł̕��������Ɋ�Â������Ɋւ��錤���ɂ���Ĕ��m��Ph.D���擾���������Ƃł�����B1998�N����J�n���ꂽSeattle
Butoh Festival����Â��A���H�I�Ɋ�����W�J���Ă���B
�V�A�g���ł̃��[�N�V���b�v�ł́A�{�f�B���[�j���O�i�g�̊w�K Body Learning�j�y��Butoh Dance Method���Љ�w������Ɠ����ɁA1998�N���e�[�}�̈�Ƃ��Ă����u�����I�ɏ����t����ꂽ�S�g�����v�ɂ��ē��@��M�d�ȋ@��Ƃ��Ȃ����B�S�g�̐[�������N�Z�C�V�����Ȃǂ��A�Љ���I�����t������̒E�\�z��K�v�Ƃ��邱�Ƃ����炽�߂Ċm�F���郏�[�N�ƂȂ����B


��l��l�ԓI�S���w�Ƌ���w�̂��߂̍��ۃZ�~�i�[�@
4th International Seminar for Humanistic Psychology and Pedagogy
�E�N���C�i�E���u�l 6/14-18,1998 ���\�ƃ��[�N�V���b�v�@�u�����̕��@�ɂ��S�g�̓����v
"Congruence of mind-body through Butoh dance
method"
��s�L�G�t�ƌÓs���{�t�Ƃ̒��ԂɈʒu���郊�u�l�s�̓Z�~�i�[��S�ʓI�Ɏx�����A�L�G�t�E�R�X�e���[�N�S���w������
Kostiuk Institute of Psychology�̎�Âɂ��Z�~�i�[���J���ꂽ�B�E�N���C�i�A�|�[�����h�A���V�A�Ȃǂ̓���������̎Q���҂𒆐S�ɁA�����[���b�p�A�A�����J����̎Q���҂��������i�����͓��{����̏��Q���Ƃ̂��Ɓj�B
��c�ł̔��\�ɑ����āA���Z�Q���҂R�O�|�S�O���A���w�ҕS���\���̒��Ŏ��Z�w�����s��ꂽ�B���e�͏�������邽�߂̐g�̂ق����Ȃǂɂ�郊���N�Z�C�V��������n�߂ɁA�����̊�{�I�ȕ��@�ɂ��S�g�̐[�w�Ɍ��������@�������ꂽ�B�S�͔��ɍ����A���̌�̕����r�f�I����ւ̎Q���҂����Ȃ葽�������B
�L�G�t�̐S���w�������ɂĐS�����E�̃X�^�b�t��ΏۂɃ��[�N���s���A�S�g�����ւ̃A�v���[�`�̕��@�Ƃ��č����]������A����̌𗬂ւ̊�b�Â���ƂȂ����B





��Z��Η��������ۉ�c�@ 6th
International Conference on Conflict Resolution
�T���N�g�E�y�e���u���O�A���V�A 5/7-14,1998
���[�N�V���b�v�@�u�����̕��@�ɂ��S�g�̃s�[�X�t���Ȏ����v�@
�@"A peaceful dimension of mind-body through
Butoh dance method"
�A�����J�A���V�A�A����������̎Q���҂𒆐S�ɂ������ۉ�c�B��Â̓A�����J�ɖ{��������Association
for Humanistic Psychology�ƃy�e���u���O��Harmony Institute�Ƃ̋��Âɂ����̂ŁA�o�ρE�o�c�E�g�D�E�S���I�Ȗ��Ȃǂ̗l�X�ȃ��x���ł̊����E�Η����������邽�߂̕��@�E���H�Ȃǂ����\���ꂽ�i�y�e���u���O��w�ɂ�Conflictology�A�����w�ƌĂԂׂ��w��������j�B
�����͐S�g�����̊ϓ_������Z���[�N�V���b�v����悵�A�Q���҂R�O�|�S�O����ΏۂɂS���Ԃ̎w�����s���D�]���B�g�̂ق����Ȃǂ̃����N�Z�C�V�������Ƃ��āA�����̕��@�ɂ���ĐS�g�̐[�݂ւƌ��������@������Z�w�����s�����B���̑��A������̃C�x���g�Ƃ��ăy�e���u���O�̎�҂�Ώۂɓ����\�h���w���B
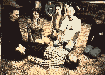

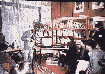
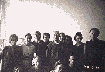
|

 (C) T.Kasai 2025. All Righsts Reserved.
(C) T.Kasai 2025. All Righsts Reserved.