暇人のカメラと写真
写真展ー鑑賞した写真展についての寸評
<最近観た写真展>
フジフィルムスクエア
フジフィルム・フォトコレクション展 日本の写真史を飾った写真家の「私の1枚」
日本新聞博物館
田沼武能/
戦後を生きた子どもたち
南良和/
秩父三十年 ―1957~1991―
立木義浩/
PIECE OF CAKE
<写真展寸評>
写真家順
<テレビ番組>
Hello!フォト☆ラバーズ
ミル・トル・アルク
<岩波写真文庫>とその時代(銀座 教文館ウェインライトホール、2013年6/23〜7/8)
 この展覧会は岩波書店の創業100年を記念して開催された。
この展覧会は岩波書店の創業100年を記念して開催された。
この展覧会も純粋な写真展ではない。もっとも題が「<岩波写真文庫>とその時代」なのだから、良く考えて見れば分かる事なのだが。
岩波写真文庫は、1950年から1958年まで6年半で286冊が刊行された。編集長格は名取洋之助で、内容は、”社会・産業”、”地誌・新風土記”、”美術・歴史・伝記”、”自然科学”、”趣味・スポーツ・芸能・その他”、と多岐にわたる。”百科事典の項目別写真版”、という感じである。啓蒙的な岩波の姿勢が打ち出されているが、今から見ると記録として貴重である。
私的な事だが、私は”
化学繊維”、”埼玉県”、”東京案内”、”総目録”を持っている。”宮城県”も持っているかも知れないが、家の中がごちゃごちゃになっているので、今は確認できていない。
(閑話休題)
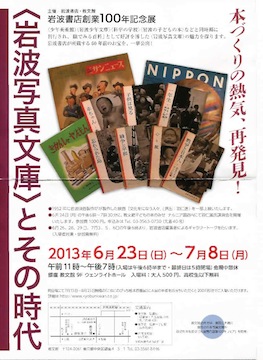 私はこの展覧会に”写真文庫”の写真の原板拡大プリントパネルの展示を期待していた。しかし、そのようなパネルは数枚しかない。
私はこの展覧会に”写真文庫”の写真の原板拡大プリントパネルの展示を期待していた。しかし、そのようなパネルは数枚しかない。
”その時代”と銘打っているように、主に”写真文庫”発刊の時代”及び”終刊の時代”背景が説明され、その資料が展示されている。
岩波書店が先取りはしたが、私はこの文庫が発刊されたのは時代的に必然的だと思う。つまり、戦争も終わり、経済が活発化し、カメラが普及し始め、活字で読むより写真で見る方が手っ取り早い、という人が増えて来た時代である。
しかし、1956年には”週刊新潮”が創刊され、1953年にはテレビ放送が開始、1958年には東京タワーが開業する。そして、”角川写真文庫”などの競合品も出版され、その役割を終える。
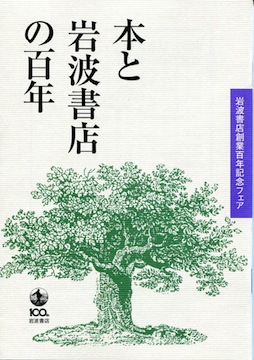 この展覧会には、”写真文庫”の原稿や、”競合品”とともに、”少年美術館”、”岩波少年文庫”、”科学の学校”、”岩波子どもの本”などの現品も展示されている。勿論、”写真文庫”全巻を手に取って見る事もできる。
この展覧会には、”写真文庫”の原稿や、”競合品”とともに、”少年美術館”、”岩波少年文庫”、”科学の学校”、”岩波子どもの本”などの現品も展示されている。勿論、”写真文庫”全巻を手に取って見る事もできる。
この展覧会でもっとも気に入ったのは、文化人70人余りが次から次へと出てくる岩波映画製作の「文化をになう人々」のダイジェスト版(約20分)。堪能しました。
料金は500円、入館時に「本と岩波書店の百年」という小冊子(非売品)を頂きました。
暇人のカメラと写真のホームページにようこそ!