 |
|
1893年6月、スリランカのヌワラエリヤでエリザベス・ホワイトは冊子を手にした。英国キリスト教伝道協会がコロンボで発行した'History of Ceylon'(セイロンの歴史)だ。115ページのコンパクトなハンドブック。そこにスリランカの歴史が丁寧にまとめられている。ナイトン、プライダム、ターナー、テンネント、ファーガソンという、当時のスリランカ研究第一人者たちの著作から歴史に関わる部分を集めている。言ってみればこのハンドブックはスリランカの歴史と文化の「まとめサイト」。
|
スリランカの歴史
序
|
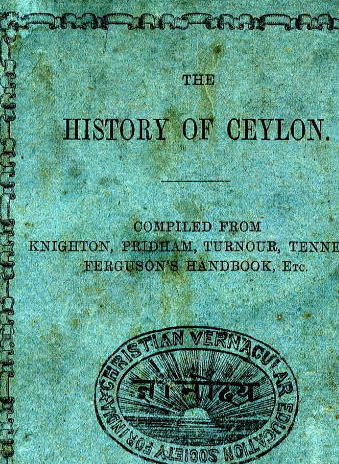
History of ceylon |
エリザが読んだ『セイロンの歴史』は3千刷の第5版で、そのとき総発行総数は1万4千部を数えていた。
それから110年を過ぎて、エリザが手にしたその冊子が今、私の手許にある。神保町の北沢書店の書棚にR.L. スピトルの『Far off Things』が無造作に平置きされていたことがあって、そりゃ、スピトルと聞いても日本では知る人も少ないし、値もかなり安かったが、そこに並んでこの『セイロンの歴史』も積まれていた。もう35年も前のことになるが、当時は特別な思いもなく『Far off Things』と一緒に買っておいた。でも、しばらくページさえ開かなかった。
『セイロンの歴史』は小さな冊子だ。安物の薄っぺらな体裁。発行はコロンボのキリスト教伝道協会とある。ページも開かずに放って置いたのはそうした風体から本を見くびっていたことによる。
ところが、スピトルを読み疲れたときにこの冊子のページを開いたらこれがなかなかに面白い。要を得てスリランカの歴史がまとめられていて、スリランカの歴史を神話の時代から英国植民地時代まで一気に概観する、という至難の業を難なくこなしている。
アングロサクソンって歴史に強いんだと詠嘆した。あちこちから資料を寄せ集めただけなのに、その語り口に講談調の熱がこもっている。
本の見返し上部にエリザ・ホワイトと署名がある。1893年とある。エリザ、どんな人だったろう。
ネットで検索した。同名の人物が何人かモニターに現れる。ヌワラエリヤと1880年代を条件に加えて検索の深度を深めると1881年の英国の国勢調査にその名とその地名が対になって記載されているのを見つけた。エリザ・ホワイトの出生地はセイロンとあった。
記録によればセンサスの年、彼女は42歳で、英国南西部のグロスターシャー州のセント・オーウェンに夫と二人の子供とともに暮らしていた。そして、センサスの12年後に彼女は薄曇の寒冷な英国を離れ、生まれ故郷のアジア熱帯の島セイロンの山中のヌワラエリヤに戻っている。彼女について知りえたのはこれだけだった。
エリザが戻ったヌワラエリヤは英国人が開発した街。英国人の個人資本家は東インド会社からヌワラエリヤの土地を買い、ここでコーヒーのプランテーションを始めた。後にコーヒーは紅茶に変わり、ヌワラエリヤはBOP紅茶の世界的生産地となる。
山上の都市ヌワラエリヤは英国ビクトリア朝文化に彩られる。英国流のフィッシングが楽しめる湖。その辺には華やかな競馬場とゴルフ場。ビクトリア様式の出窓を持つ暖炉つきの館が並び、赤レンガのコロニアルな郵便局が建っている。この街で1888年発刊の『セイロンの歴史』に1893年と書き込んで、エリザはページを開いた。
ビクトリア湖と競馬場を見下ろすゲストハウスに3週間ほど私は転がり込んだことがある。建物は英国植民地時代に、コロンボとカンディを結ぶ鉄道を敷いた英国人が別荘として建築され、茶畑が続くハドン・ヒルの中腹にあった。ゲストハウスのオーナーはシンハラ人だが、働いているのは調理人のシンハラ人を除いて総てタミル人だった。タミル人の客室係は茶園出身者で休暇にはヌワラエリヤの町へ歩いて下り、バスに乗って更に山を下り、エステートの中にある実家へ帰った。宿泊客は殆どなかった。私の滞在中、スリランカ人の新婚さんが泊まった。ドイツ人のエンジニアがシンハラ人のドライバーを連れて泊まった。私の滞在中、客は2組だけだった。
大きな暖炉のある居間に出窓があって街
が見下ろせる。遠くの風景は山また山である。ローカンタヤ(世界の果て)が窓の右端の辺りの山のかなたに位置する。ローカンタヤは荒涼とした高原である。その高原を行くと、突然に絶壁の上に出る。その先には何もない。世界はここで終わりだ。
スリランカの高山には神が住む。里山の麓や中腹には人が棲む。ヌワラエリヤは人の暮らす場所よりはちょっと上にあり、神々の世界の真下にある。コーヒーや紅茶のプランテーションのために英国人が作った町だからスリランカの人々はもともと住まなかった。
エリザはここで「セイロンの歴史」を開き、スリランカ2000年の過去を旅したのだろう。エリザが純アングロサクソンだったのか、英国人とシンハラの混血であったのか、あるいはそれ以外か。
詳しいことは何一つ分からない。分かるのは「スリランカの歴史」を知ろうとした。そのことだ。そして、その歴史はショッキングな内容を持っている。今読むと、その衝撃は1893年のときをはるかに上回るだろう。今世紀初頭にとって、スリランカの大きな問題はスリランカ北部東部の分離独立と、憎しみが憎しみを増幅させる終わりのない戦争である。ローカンタヤ。いま、スリランカそのものが「世界の終わり」に直面している。エリザが読んだ冊子には、当然ながらそんなことは書かれていない。
スリランカの歴史
スリランカの歴史を振り返るとき、その始まりが太古の絢爛とした暗黒の中にあることを知らされて多くの日本人は驚くものだ。神話に語られるスリランカはインドの歴史よりも鮮やかで美しい。この島を征服した民族も時期もこの島に人が書いた史書にはっきりと記憶されている。
混沌とした神話時代の後にインド・アーリア人が入植してスリランカの歴史が始まる。入植者は先住の人々や近隣の民族と集合・融合してシンハラという多・民族を構成した。そうした概観はスリランカの歴史を多少なりとも齧った人なら知っている。だが、その詳細については知らない方が大多数だろう。
エリザが読んだ「セイロンの歴史」に語られているのは、スリランカに生まれた多・民族国家の変遷である。19世紀の英国による島の開発が冊子の最後に並べ立てられるが、英国植民地時代に至る歴史の出来事を明瞭に踏まえた記述からは、ランカー島という小さな島の中でミレニアム二つの時間を経て今、新たに生み出された内戦・紛争が導く混乱の理由とその結末が推し測られるかもしれない。
「セイロンの歴史」はこう書き出している。「歴史とは地球上の諸国民が体験した特筆すべき個々の事件の記録である」と。そして、他国の歴史を学ぶことが、我らの英国の歴史への洞察力を高めると。
我ら英国の歴史への洞察力という言い回しを、我ら日本国の歴史への洞察力と言い換えてみる。すると「セイロンの歴史」は日本の歴史とどこかで交差し、平行する。もちろん離反もするし、無縁の事柄もある。スリランカは大航海時代以降400年に及ぶ植民地時代を苦渋し、また、甘んじて受けた。日本には、少なくとも歴史上知りうる限りは植民地という時代がなかったから歴史上作られた民族性は日本人とセイロン人で大きく食い違い部分を持つ。だが、その違いを知る以上に、アジア的な感性が生み出す同一性をわれわれはスリランカの歴史の中に見出すだろう。2007年に、アジア極東の島国でこの冊子を読むことは時代としての意味がここにある。
スリランカ復興という表看板を掲げて日本は今、この島の開発支援に関わっている。そうした業務の合間にスリランカの歴史を学ぶことは無駄ではない。スリランカの史書を通して英国人らが見出したこの島の有様を日本人が新たに振り返れば、この島の人々の行動に現れる独特のしぐさ、時に嫌悪を覚え、時に共感を覚えるそのしぐさが理解できるだろう。
「セイロンの歴史」をこれから紹介する中で、その本文に対してさまざまに注釈を書き加えるが、そのためにどれがこの冊子の元の文でどれが注釈であるのか判然としなくなるっことがあると思う。その意味で、ここに記される「セイロンの歴史」は新たな史書となるのかもしれない。
アダムス・ブリッジ
「セイロンの歴史」はスリランカの地勢をこう語る。
スリランカはアジア大陸に連なる島である。インドの南東に位置し、アダムス・ブリッジと呼ばれる砂州の隆起でマンナル島と結ばれ、インド側のラメスワラム島とは点在する島々で結ばれている。その隆起がラーマの架け橋、ナラ王の橋、はてはアダムスブリッジなどと様々に呼ばれたのは神話や古代の歴史の中でスリランカとインド南端の国々や人々が深く関係を持っていたことの証となる。
マンナル湾とポーク海峡をこの架空の「橋」が長さ48キロにわたって分けている。
スリランカ。その島の大きさは南北270マイル、東西140マイル、周囲760マイル。面積は2500平方マイル。人口は約300万人である。
?アダムス・ブリッジをグーグル・アースで見るとスリランカとインドを海が分けているという表現の妥当性が問われる気がしてくる。現在の海面上昇が始まる以前、島々は砂州で結ばれインドと結ばれていた時代があった。2015年、ここに36億usドルで高速自動車道を掛ける計画がインドから提唱されたがスリランカは同意していない。
歴史上、この島は様々に呼び習わされてきた。最古の名はサンスクリット語のランカーLankaである。英国の詩人ミルトンは古代ギリシアやローマで呼ばれていた名でこの島を呼んでいる。インドで最大の島-タプロバーネ、と。
タプロバーネの名はタンバ・パンニ(銅色の掌)から派生したもので、これもこの島の古い名称である。
またこの島はシンハラ・ドウィーパとも呼ばれた。これは「ライオン族の島」という意味で、現在、欧州で呼ばれるセイロンという名も、アラビア人が言うセレンディーブもこの名から派生したものである。
「聖なる(スリ)ランカー」という名は第二次大戦後、1948年に英国から独立した段階ではまだ用いられなかった。英語訛りのセイロンのままだった。セイロンが晴れて本来の名であるスリランカという名に帰るのは1970年代のことである。
スリランカという名称は、誰もが知りえない太古時代の復権を宣言する。人が神々の遊んだ常夏の楽園がこの島にはある。
この国には稲作を中心としたまばゆいばかりの古代文明が栄えた時代があり、そのときから古代ヒンドゥ教と仏教とはこの島の精神の真髄であった。その文化の香りは周辺諸国に広がり、遠く日本へも伝わった。
だが、1983年、この国ではシンハラとタミルという二つの民族の間に激しい衝突が起こり、20年以上も続いている。
最初は小競り合いに過ぎなかった。しかし、スリランカ北部でタミル過激集団による政府軍兵士への銃撃があった。絶えず起こっていた小競り合いの一つだったが、その報復がコロンボでのタミル人地区焼き討ちと言う凄惨な結果を導いた。少数民族タミルの独立派がスリランカからの分離独立を求めて武装を先鋭化させテロリズムを強化したのはこの後である。
それから20年が過ぎて、領土保全を唱えるシンハラ主導の政府はタミル独立派を武力で抑えようとクフィルやミグの最新鋭爆撃機を飛ばして空爆を繰り返すようになった。何故かアジアの最貧国グループに属するスリランカは有り余る軍事資金を有していて、最先端の軍備増強にに膨大な資金をつぎ込んでいる。日本はスリランカの内戦を終結させ経済復興を図るためカンボジア復興の経験を持つ復興支援使節を適時派遣しているが、その努力に反して内戦は深まるばかりだ。
忘れてはならないが、サンフランシスコ平和条約のとき、この国の代表が日本の再独立のために会議場のオペラホールで行った演説は平和条約締結を討議するために集まった連合国諸国の代表を感動させた。あの時スリランカは植民地のセイロンでありであり、英連邦の属領だったが平和を訴える力は日本を糾弾する連合国側の威勢を削ぎ日本再独立と和平の構築に大きく貢献した。
今、スリランカに平和はない。日本はこの島に平和をもたらし、復興をかなえ、新たな国際関係を構築しようとして、ノルウエー、英国、ドイツ、米国などと協調しながら和平交渉の道を探っている。
だから、2007年5月に、スリランカ政府が行ったタミル市民や兵士への非人道的な行為を非難して援助諸国が援助の凍結を打ち出したときにも日本は唯一つ、スリランカの市民を守るとして援助を継続した。日本にはスリランカを守り続けなければならない特別な理由(ニュアンスとフィロソフィ)があると、そのときスリランカ復興支援の日本政府代表はコロンボでプレス・リリースしている。
それは忘れてはならない現代の関係だが、振り返れば神話の時代にも民族の深層に関わる関連が二つの国の記憶に宿っているのである。
神話の中のスリランカ
スリランカは、まず、インドの神話「ラーマーヤナ」の中に美しい都のある島として語られる。島の中にシンハラ人による都市国家が建設されてからのことだが、それ以降は王朝史「マハーワンサ」が歴史を語るようになる。
「マハーワンサ」はシンハラ民族に多々様々に伝わる民族の起源伝承をまとめて一つに整え、それをシンハラ王族の歴史につなげる役割を果たした。その起源伝承には寓話が含まれていて、判然としない部分もあるのだが、シンハラ人という民族の心情を一つにまとめて、彼らを世界で唯一の民族として誕生させることになった。
シンハラという民族意識は今日にまで続いているが、その文化を支えるのはシンハラ語という世界にもまれな少数言語である。
シンハラ語はこの島だけで話されている。日本語と同様に言語による孤立は世界からの孤立に繋がる。シンハラ民族の孤立と孤独、そして、不安。それが危ない。
その危なさは、かつて日本が盲目的にグローバルな世界を相手にして、果敢な、向こう見ずな戦いを挑んだ危なさと似ている。日本という国は内に向かうとき、共同体としてこれほどに住みよい場所はない。だが、外に向かわざるを得ないとき、単一民族は他民族に対して、ときに行過ぎた優越感を抱き寛容を忘れる。盲目的に他者を排他する。自らの壊滅を省みず、自ら燃え盛る火に飛び込んでしまう。ちょっとした弾みで牙をむくシンハラ人をジャングルの野獣にたとえたのはレオナード・ウルフだったが、その国民性は同じ島国民族の日本人と、ほぼ完璧に一致する。
インディアン・サマーの幸福を長くその歴史の中に謳歌したシンハラ王朝。しかし、そのおだやかな午睡は15世紀に西欧からの侵略で目覚めさせられる。一発の大砲の音でシンハラ王朝は腰を抜かし、まんまと西欧諸国の植民地と化すのだ。
ポルトガル、オランダ、イギリスと領主が入れ替わった長い植民地時代はこの島に産業と西洋文化をもたらしたが、シンハラ王朝の築いた文化はその450年の間に根絶やしにされた。三代目の植民地領主となったイギリス国王領の時代、仏教再興の萌芽が見られ、また、好奇で博物の好きな英国人によって古代スリランカの栄光の数々が発掘されている。シーギリヤ王宮のフレスコ画に描かれた古代シンハラ王朝の王女たちはシバの女王のように大きなルビーを胸に輝かせ、薄絹を優雅にまとい、手に睡蓮の花を持っている。ラーマーヤナ神話の中でハニューマンが盗み見たシンハラ王宮の天上の暮らしそのままが、シンハラ王宮跡に残されていたのだ。
シンハラ民族の古代の栄華は1970年代からユネスコが中心になって調査を進めた。発掘が進むとシンハラ王統史「マハーワンサ」に書き記された逸話が歴史の事実として確認されている。
|