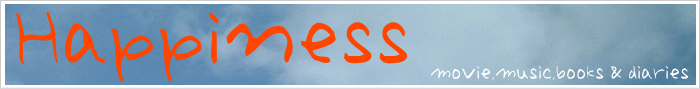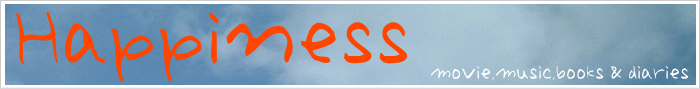| �^��̎�����̏��� |
| Girl with a Pearl Earring |
|
 |
 |
| �ēF |
�s�[�^�[�E�E�F�[�o�[ |
| ����F |
�g���C�V�[�E�V�����@���G |
| �r�{�F |
�I���r�A�E�w�g���[�h |
| ���y�F |
�A���N�T���h���E�f�v�� |
| �o���F |
�R�����E�t�@�[�X
�X�J�[���b�g�E���n���\��
�g���E�E�B���L���\��
�L���A���E�}�[�t�B |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j
 ��76��A�J�f�~�[���B�e��/���p�܂Ȃǃm�~�l�[�g ��76��A�J�f�~�[���B�e��/���p�܂Ȃǃm�~�l�[�g |
|
 |
| �Â��Ȉ��̃L�����p�X |
�������� |
����͂P�V���I���̃I�����_�B
�����Ŋ��Ă������n�l�X�E�t�F�����[���Ƃ�����Ƃ����
���̉ƂŎg�p�l�Ƃ��ē����A�t�F�����[���Ƃ̒W�����ɗ�����
���̎q�E�O���[�g�̕���ł��B
���̉f��A�����I
������A�ŋ߃n�}���Ă���A������u�����v���́B
������ƃI�g�i�̏����B
�R�����E�t�@�[�X������t�F�����[�����A
�X�J�[���b�g�E���n���\��������O���[�g��
���Ȃ������A�\��₵�����Ŋ��������Ă����
���炵���@�ׂȉ��Z�ł������܂��āI
�I���ɂ��g�Ɋo���������ł����A
�D���ōD���ł��܂�Ȃ��l�ł������قǁA
�߂Â��Â炭�A�b�����Ƃ������߂����B
�����炱���A�������E�ɓ���Ă��������āA
��x���Ă��܂��ƁA�����ڂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
����ȏ�
���肰�Ȃ��A�ł��ςĂ鑤�ɂ͎�Ɏ��悤�ɂ킩���Ă��܂��悤��
��l�̖����ł����ˁB
�����A���̉f��́A�Ƃ��Ă��Â��Ȃ̂ł��B
�Â��ŁA���₩��
�����炱���A���̉��ɂЂ��ޔM���z����
����w���������Ă�����������܂��B
���������u�Â��ŔM���v���̂��āA
���{�ɌÂ����炠����ӎ��ɒʂ�����̂������Ȃ�����
�v���̂ł����A�������ł��傤�H
�����āA�f���i�Ɩ��Ƃ������j���ˁA����܂��G��I�ł��āB
���Ɖe�̎g������������ۂ��Ȃ��A�}�C���h�ŃL���C�ł����킟�B
����������HP��ǂ�łĒm������ł����ǁA
�t�F�����[������Ƃ����l�͎��݂̐l�Łi�L���Ȃ�ł����āI�H�j
�u�^��̎�����̏����v�Ƃ����G�����݂�����ǁA
�O���[�g�Ƃ��������͉ˋ�̐l���Ȃ�ł����ĂˁB
�t�F�����[������̐l�����ɂ��Ă͂��܂�m���ĂȂ��āA
�����Ȃ��j�������ƂɁA����҂��O�O�ɐ��@���n�������̂�
�O���[�g�Ƃ��������������A�Ƃ������Ƃł����B
����Ȑ��炩�ŏ����ȃL�����N�^�[�ݏo���Ȃ��
����������Ȃ����I�����B
����ȏ��̎q���߂��ɂ�����A
�����A�|�p�Ƃ���Ȃ��Ă��A�P�V���I����Ȃ��Ă�
�܂������Ȃ��z�����ˁB�ق�ƁB |
|
| posted on 2004.06.14 |
|
| ��TOP |
| �[�ċz�̕K�v |
|
 |
 |
| �ēF |
���N�Y |
| �r�{�F |
���J��N�v |
| ���y�F |
���ѕ��j |
| �o���F |
������
�J���͉�
���{���M
���q���₩
�v�����₩
���V�܂���
��X��� |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |
|
 |
| �h���}�`�b�N�ł͂Ȃ��Ƃ���Ƀh���}������B |
�������� |
����̂��Ƃ����є��ɁA���n�i�������j�̃o�C�g�����邽��
����Ă����{�y�̎�҂V�l���A��P�����̋�����Ƃ̖���
�������̂́H�Ƃ����X�g�[���[�B�������ł��B
�f�掩�̂́A���̂��������̂�т�i�݂܂��B
�Ȃ�Ă����āA���ʂقǍL�����Ƃ����є���
�����Ђ����犠���Ċ����Ċ���܂���I�����Ȃ���B
���X�̎����͋N������̂́A�F�������͊F����
�o��l���͂قƂ�ǂ������̓��ʓI�ɂ����Ȋ�����
�����Ă��Ă��ł���ˁB������A���l�Ƃǂ��������Č�������
�����̒��̉����ɃP��������ق�����Ƃ����B
�Ȃ̂ŁA�����Ă��̃h���}�����h���}�`�b�N���͑啝�ɒႢ�ł��B
���́uDr.�R�g�[�f�Ï��v�ł���A�����������I�Ɏv����قǂł��B
�ł����A����Ȃ��������I
����Ȃ���A����Ȃ���B
������ЂƂ����̉��łP�����Q���肵�āA
��������ɓ������������
�����J���^���ɂ��݂��𗝉�����������A
�������n�܂����肵�Ă��܂邩�I���Ċ����ł���B�}�W�ŁB
������A���������f��̃X�^���X���A�I���͎x�����܂��B
�S�R����ł��B
���Ă������A���̃e���|���Ō�܂ŕ�����
�f��Ƃ��Č����ɐ��������Ă�ē���A
�A���^����������ł��I
-----
�I�������̉f����ς����Ȃ��Ǝv��������������
���́w���E�̒��S�ŁA�����������x��
�����I�ȉ��Z�������Ă��ꂽ
���V�܂��݂���o�Ă���Ă��Ƃ�������ł����ǁA
�I�������̉f����ςĂ����������̂�
���V�܂��݂����̃V�[���ł����B
�ޏ��́A���l�ƂقƂ�nj��𗘂����A�ڐG�����Ȃ�
�R�~���j�P�[�V�����E�u���C�N�_�E���ȍ��Z���̖��Ȃ�ł����A
���̎q���I�W�C����炨����������ł��ˁB
�u���肪�ƂˁA���肪�Ɓv
�ƁA�I�W�C�����Đ���������ƁA
���̎q�����߂ďΊ��Ԃ����A����ȃV�[���ł����B
�u���肪�Ƃ��v�̈ꌾ�����E��ς���I
���ăI���͎v�����ˁB
���肪�Ƃ�
���߂��
���͂悤
����ɂ���
�������傤�ԁH
����ȉ��C�Ȃ����t���A�ǂꂾ����Ȃ̂��B
���߂Ďv���m�炳��܂����B
-----
���������A����Ŏv���o�����I
�́E������Ⓑ���̎�������̐V���L����
������₳��̑��q����̃R�����g���ڂ��Ă���ł��B
����́A
������"���ꂾ���͎��悤��"�ƁA
�����������猾���Ă����Ƃ�����B
�E�u���肪�Ƃ��v�������ƌ�����l�ԂɂȂ�
�E�u���߂�Ȃ����v�������ƌ�����l�ԂɂȂ�
�E�E�\������
����Ȋ����̂��̂������ƋL�����Ă��܂��B
�I���͂��̋L�������āA���̂������������܂����B
-----
�R�R�����{���{���ɍr��Ă���Ƃ��ɂ�
��x�傫���[�ċz������
���ꂩ�Ɂu���肪�Ƃ��v���Č����Ă݂悤�B
���́u���肪�Ƃ��v�̈ꌾ���A
������ς��A���l��ς��A���E��ς���B
����A�����l����ƁA�Ȃ�ăh���}�`�b�N�Ȃ낤�I
�I���ɂ��q�����ł�����A���������Ă����悤�Ǝv���܂��B |
|
| posted on 2004.06.13 |
|
| ��TOP |
| �Q�P�O���� |
| 21 Grams |
|
 |
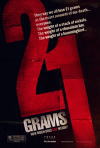 |
| �ēF |
�A���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D |
| �r�{�F |
�A���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D
�M�W�F�����E�A���A�K |
| ���y�F |
�O�X�^�[�{�E�T���^�I���� |
| �o���F |
�V���[���E�y��
�x�l�`�I�E�f���E�g��
�i�I�~�E���b�c
�V�������b�g�E�Q���Y�u�[�� |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j
 ��76��A�J�f�~�[���剉���D/�����j�D�܃m�~�l�[�g ��76��A�J�f�~�[���剉���D/�����j�D�܃m�~�l�[�g |
|
 |
| ������Ƃ������Ƃ͑I�Ԃ��ƁB |
�������� |
���̉f����ςĂ��āA�ɂ��قǎv�����̂�
�u�l�����āA�ЂƂЂƂ�"�I��"�̌��ʂȂȁv
�Ƃ������Ƃł��B
"�I��"�Ƃ������t��"���f"�ɒu�������Ă������B
��u��u�A���������̂Ƃ����߂����Ƃ�
�܂����̏u�ԂɂȂ���A�܂����̎��ɂ��Ȃ���B
�ǂ����Ƃɂ��A�������Ƃɂ��A
�ŏI�I�ɂ͂��ׂĈ�_�ɂȂ����Ă�����ł��ˁB
���A�������ď����Ȃ���킩�������Ƃ�����܂��B
���̉f��́A���Ԏ����o���o���ɕ`����Ă��܂��B
���̂����ŁA����V�[���ƁA���̃V�[���̂Ȃ��肪
���Ȃ�̋��Ԃ��o�Ă����肷��킯�ł��B
����ȍ\���́A�������҂̈Ӑ}�ɂ����̂Ȃ�ł��傤���A
����́A�o��l��������"�I��"�ɂ���
�ڂ������ϋq�����낢��ƍl���邱�Ƃ̂ł��鎞�ԁi�P�\�j��
�^���邽�߂ɍ��ꂽ�̂��Ȃ��Ǝv���܂����B
�����āA�I�������ۂ������Đ����Ă�
����܂ł��Ă���"���f"���A
���߂��u�Ԃ͔[���ł����Ƃ��Ă��A
���ƂɂȂ��Ă悭�悭�l������A���������킢�Ă�����
�����Ɏ������o�J�����������v���m�炳�ꂽ�肷�邱�Ƃ�
�����������B
���낢��Ɛ[���l�����邾���̓��]�Ǝv���[���Ǝ��Ԃ�����A
������I���̐l���A�ǂ�Ȃ������낤�H
����Ȃ��Ƃ��A���܍l���܂��B
-----
�V���[���E�y���A�x�l�`�I�E�f���E�g���A�i�I�~����b�c�Ƃ����R�l��
���̑s��ȃh���}�̎�l�������ł��B
�V���[���E�y���ƃx�l�`�I�E�f���E�g���ɂ��Ă�
���̑f���炵�������̖ڂŊς����Ƃ�����܂����̂�
���������猾���܂ł�����܂���B
�ł����A�i�I�~�E���b�c����ɂ��Ă�
���߂Ă��̎p��q�����邱�Ƃ��ł��܂����B
���₢��A�A�J�f�~�[���Ƀm�~�l�[�g����邾����
���|�I�ȉ��Z�ł����ˁI
���̑@�ׂŐ܂�Ă��܂������Ȕ��e�̗��ɐ��ވÂ��e��
�����ɕ\������Ă����Ǝv���܂��B
�������A�������Ƃ������I
�i����܂���A�Ƃ���G�������Ə����Ă܂����ǁc�j
�����ȈӖ��ň��|����܂����B�������������B
-----
�C�j�����g�D�ē̑O��w�A���[���X�E���X�x�̃��X�g�V�[���B
����͂ƂĂ��C���p�N�g������܂����B
���̃V�[����
�u�������낤�Ƃ��A����ł��l���͑�����v
�Ƃ������Ƃ��������������ƁA�������܂ł����v���Ă܂����B
�ł��A�Ⴄ�ȁB���̉f����ςĎv�������܂����B
�u�����u�A����"�l��"�̒��ɂ�
�@�傫�����Č����ĂȂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ڂ��ł��Ă��܂�
�@����Ȃ��Ƃ�����v
�Ƃ������Ƃ������ȁB
�w�A���[���X�E���X�x���w�Q�P�O�����x��
�����������Ƃ��������������ȁB |
|
| posted on 2004.06.12 |
|
| ��TOP |
| �f�C�E�A�t�^�[�E�g�D�����[ |
| The Day After Tomorrow |
|
 |
 |
| �ēF |
���[�����h�E�G�����b�q |
| �r�{�F |
���[�����h�E�G�����b�q |
| ���y�F |
�w�����h�E�N���[�T�[ |
| �o���F |
�f�j�X�E�N�G�C�h
�W�F�C�N�E�M�����z�[��
�C�A���E�z����
�G�~�[�E���b�T�� |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |
|
 |
| �L�~�����ɖ�����͂Ȃ��B |
���� |
���N���̎����̃A�����J�f��͑�ςȑ吷���B
���ꂩ��Ė{�Ԃ܂ŁA���T���T����삪�ڔ������ł��B
�����ςĂ����w�f�C�E�A�t�^�[�E�g�D�����[�x��
���݁A�A�����J�ő�q�b�g�������Ƃ��Ă���^���������ł��B
�ł��ˁA�I���I�ɂ͂���܂�Ȃ������c�B
�o�D���A�܂��������Z�����Ă��炦�Ȃ��悤�ȉf��ł��B����́B
�l�Ԃ̉��Z�����A��������A
�u�f���v���ŗD�悳��Ă��܂����f��ȂȁA
�Ǝv���܂����B
���̉f��̍����ɂ́u�n�����g���v�̖�肪����܂��B
����́A���̂ڂ������ɂƂ��āA�ƂĂ��傫�Ȗ��ŁA
�ƂĂ��傫��������ŁA�ł��A�ƂĂ��g�߂Ȗ��ł��B
������A���̂��Ƃɂ��Đ^���ɍl���邽�߂̖���N��
���̉f��͒��Ă���Ă���̂�������܂���B
����������ƁA�ˁB
�ł��A���̉f��ɂ�
�����܂ł̐^�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
���̂��Ƃ����A
���E�̒��S�ł���A�����J
�Ђ��Ă̓j���[���[�N�����v���A�X�����A
���R�̏��_���K�`�K�`�ɓ����Ă��܂���
���́u�f���v����������̉f��͖����I�[�P�[�I
�݂����ȋC��������ł���ˁB
�����āA�v���I�Ȃ̂́A
�z������l�ƃJ�l�𓊓����đn��グ��ꂽ
���́u�f���v���A
���̉f��̈���Ă��Ȃ��������ƁB
�w�c�C�X�^�[�x�Ŋς�������
�w�f�B�[�v�E�C���p�N�g�x�Ŋς���Ôg�ƁA
���̉f��̑�ЊQ�́A���ɑ傫�����Ȃ��������B
�債�����Ƃ˂������I���Ďv������ł��B
�i�w�f�B�[�v�E�C���p�N�g�x�̂ق������i�悩������B�j
���[�����h�E�G�����b�q�ē̑�\��Ƃ�����
�w�C���f�y���f���X�E�f�C�x�ł��B
������A�Ƃ�ł��Ȃ��j�V�r�ȉf��ł������ǁA
�A�����J�哝�̂��u�Ɨ��錾�v������A�I�Ղ̉����V�[���B
���̍��g�����A���̉f��̂��ׂĂł����B
�ł��A���́w�f�C�E�A�t�^�[�E�g�D�����[�x�ɂ�
�c�O�Ȃ���A�O�����Ɍ���Ƃ��낪����܂���ł����B
�c�O�B |
|
| posted on 2004.06.12 |
|
| ��TOP |
| �g���C |
| Troy |
|
 |
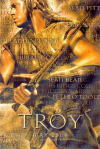 |
| �ēF |
�E�H���t�K���O�E�y�[�^�[�[�� |
| �r�{�F |
�f���B�b�h�E�x�j�I�t |
| ���y�F |
�W�F�[���Y�E�z�[�i�[ |
| �o���F |
�u���b�h�E�s�b�g
�G���b�N�E�o�i
�I�[�����h�E�u���[��
�s�[�^�[�E�I�g�D�[��
�V���[���E�r�[��
�_�C�A���E�N���[�K�[
�u�����_���E�O���[�\�� |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j
 ��77��A�J�f�~�[���ߑ��f�U�C���܃m�~�l�[�g ��77��A�J�f�~�[���ߑ��f�U�C���܃m�~�l�[�g |
|
 |
| ����ς�A�u���s����A�u���s�B |
�������� |
�R�Q�O�O�N�O������̃M���V�������������Ƃ�
�w�Q�T���x�̃f���B�b�h�E�x�j�I�t���r�{�������A
�w�G�A�t�H�[�X�E�����x�̃E�H���t�K���O�E�y�[�^�[�[�����ē���
�����P�O�O���~�ȏ�ƌ����钴���ł���܂��B
"�M���V���_�b"�ƌ����Ă��A
�킽�����ɂ͂܂������s���Ƃ��܂���B�ł����B
������Ɋς��F�l��
�u�w�O���f�B�G�[�^�[�x�Ɏ��Ă����ǁA������S�R�����I�v
�Ƌ����Ă��ꂽ�̂ŁA
"�����`�A�w�O���f�B�G�[�^�[�x�݂����Ȋ����Ȃ̂�"
�ƁA�M���V���_�b�ɂ��Ă��ꂱ��z��������������ƁA
�C���[�W�����₷���Ȃ�܂����B�i���肪�Ƃ��I�j
���āA�f��̒��g�ɂ��Ăł��B
�܂��A��f���Ԃ��Q���ԂS�O��������̂�
�܂������A�܂������I��ɂȂ�܂���ł����B
�d���T�{���ĉf��ςĂ�c�Ƃ������Ƃ���Y��Ă܂����B
�����ł��r�b�N���ł��B
��������ȂɃI�����W����������ł��傤�H
�@�P�������B
��قǗ�ɋ������w�O���f�B�G�[�^�[�x�̎���̓��b�Z���E�N���E�B
���̉f��̃g�[���ł���"�d����"��"�ߑs��"���A���̃q�Q�ʂ�
���R���R�̋ؓ��ƁA�ǖقȃ_�~���Ƃŕ\�����Ă��܂�����ˁB
���炵�������I
�����āA���̉f��̎���̓u���b�h�E�s�b�g�B
�����ɁA�b���ʂ��ꂽ���́A
���̐�m�Ƃ̃��x���̍����R�Ƃ�����g�̂��Ȃ��A
�D�����ƌ������ƗJ���������������̂���B
���̉f��̃g�[���ł���"�D�낳"��"�X�P�[����"��
�����ɕ\�����Ă��܂����ˁB
���炵�������I�܂��܂��������҂ɂȂ��Ă����ˁB
�A�f���������������e���̑��݊��I
����������̓h���}�ł́A
����ȏ�̑��݊������e�������邩�ǂ�����
���̏o���s�o�������܂��Ă���ƌ����Ă�������Ȃ����ȁB
�w���X�g�E�T�����C�x�̓n�ӌ���������ł��I
���́w�g���C�x�ł́A�Ȃ�Ƃ����Ă��s�[�^�[�E�I�g�D�[���I
�V���ĂȂ��A�܂������Ȑc�����B�R�Ƃ�������
�C�i�������ĉ����Ă����܂����B
�����āA�u���C�A���E�R�b�N�X��u�����_���E�O���[�\���A
�V���[���E�r�[���Ȃ�
�ŋ߂����ȉf��Ō�������o�D�������A
���̑��݊����[���Ɍ����Ă���Ă��܂����ˁB
���A�S�����A�G���b�N�E�o�i��Y��Ă��I�ނ��悩�����悧�B
���A�S�����A�I�[�����h�E�u���[�����Y����I
�ނ͂��낻���̓h���}�n�f��̃I�t�@�[��
�R�����ق��������̂ł́I�H
�B�X�P�[�����h�f�J�������B
�����ł�
�u�T���l�̃M���V���R���g���C�Ƃ����s�s�ɍU�ߍ��ށv�킯�ł����A
���́u�T���l�v�̕\���̎d���������`����ˁI
�w�G�s�\�[�h�P�x�̃h���C�h�̑�R��
�w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x�̃I�[�N�̑�R�ɕC�G���܂���B����́B
�C�����̂��ς��Ȃ��B
"�u���v�Ɓu���́v�Ɓu�����v��"�݂����ȌÓT�I�ȕ����
�i���₢��A���ꂼ�ÓT���̌ÓT������ˁI�j
��������ƁA�o��l���������Ȃ��A�Ȍ��Ɍ���Ă���܂����B
�ł��A�����炢�Ƃ����Ӗ��ł́A�����Ă���܂����B
����ɒu���������Ƃ��Ă��A���̈�a�����Ȃ��ł��傤���A
�ꉞ�u���b�h�E�s�b�g������A�L���X����l���ł����A
�����Ƒ��ʓI�ɃX�g�[���[���y���ނ��Ƃ��ł���͂��I
�R�O�O�O�N�O�ƁA���ƁA�l�Ԃ̗~�[���ɂ͕ς�肪�Ȃ���ł��ˁc�B
�]�_�Ƃ����Ȃ��قLj����f�悶��Ȃ��Ǝv�������ǂ��B
�D���ꂩ��c
���̉f����ς�"�g���C�̖ؔn"�̈Ӗ����킩�������A
���b�h�E�c�F�b�y�����̖���"Achilles Last Stand"�Ƃ�
���̂��Ƃ��I�Ƃ�
���ł�"�A�L���X�F"�ɂ��Ă��킩��܂����B
�ǁ[�ł��������ǁA�x���L���[�ɂȂ�܂������ |
|
| posted on 2004.06.08 |
|
| ��TOP |
| ���f�B�E�L���[�Y |
| The Ladykillers |
|
 |
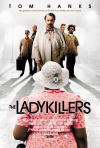 |
| �ēF |
�C�[�T�����W���G���E�R�[�G�� |
| �r�{�F |
�C�[�T�����W���G���E�R�[�G�� |
| ���y�F |
�J�[�^�[�E�o�[�E�F�� |
| �o���F |
�g���E�n���N�X
�C���}�EP�E�z�[��
�}�[�����E�E�F�C�A���Y
J�EK�E�V�����Y
�c�B�E�}�[
���C�A���E�n�[�X�g |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |
|
 |
| ���r���[�ȃo�J�͏��˂����c�B |
������ |
�R�[�G���Z��̌���Ƃ����w�t�@�[�S�x���������܂��B
��[���c�ɂ�ɁA
�o�J���o�J���ĂсA���̃o�J���o�J�꒼���Ƀo�J�����܂���A
�o�J�o�J�����܂ł̃o�J�b�Ղ�Ńo�J�Ȍ������}����̂ł����A
���̃o�J���̂����́A���̂�������S�s���ȃo�J�Ȃ̂�
�ςĂ邱�����́A����낵���Ȃ��Ă��܂��܂����B
�����ς��w���f�B�E�L���[�Y�x���A��{�I�ɂ́w�t�@�[�S�x�n�B
�����Ɂw�I�[�E�u���U�[�I�x�I�ȗv�f�i��ɉ��y�j�������A
�{���Ȃ炩�Ȃ�ʔ����Ȃ肻���Ȃ͂����������ǁc�B
�u�o�J���ۂ������r���[�I�v�Ƃ����̂��A�܂�����܂��B
�g���E�n���N�X������A���]������"����"��
�W�߂̃S���c�L�i�唼���o�J�j�𗦂���
����ƍ߂𐬌��ɓ����͂����c�Ƃ����X�g�[���[�Ȃ̂ł����A
�o�J�ȃS���c�L�ǂ��̒��˖Ґi�x������Ȃ��Ȃ��B
�o�J�ɂȂ��ĂȂ��I
���ꂾ���ɁA�����g���E�n���N�X�̖����������ĂāA
�f��̒��̐��E�ς��C�}�C�`����Ă����悤�ȋC�����܂����B
���̑���A�E���ꂻ���ɂȂ郌�f�B�i�Ƃ������o�o�A�j��
���˖Ґi�ȃ}�C�y�[�X�x�͐\�����Ȃ��I�T�C�R�[�B
�����āA�ςĂĎv�����̂��A
�u���̕���́A�����������̎�����Ă����ݒ�Ȃ�H�v
���Ă��ƁB
���̉f��A�P�X�T�T�N�̓����f��̃����C�N�Ƃ������ƂȂ��ǁA
�����炭�����ɏ��������Ă���Ǝv���܂��B
�ł��ˁA�ςĂ�Ƃǂ�ǂ�킩��Ȃ��Ȃ�́B
����Ȃ̂��A�Q�O�N�O�Ȃ̂��A�T�O�N�O�Ȃ̂��H
���ɂ��ƍ߉f��ł�����A
����ݒ肮�炢�͂͂����肳���Ă����Ȃ���
���̔ƍ߂ɑ���M�ߐ��Ƃ������A
���̔ƍ߂̎���ɂ��āA�ǂ��ŏ������̂�
�ǂ����}�W�Ȃ̂����A�킩��ɂ�����ł���˂��B
�w�I�[�V�����Y�P�P�x���炢�̃X�s�[�h���������
�b�͕ʂ�������ł����ǂ��c�B
���Ă��ƂŁA������Ə����s�ǂȈ�{�ɂȂ�܂����B
�R�[�G���Z��A�������낭�ăl�W�ꂽ�f������͗��݂܂���I |
|
| posted on 2004.06.06 |
|
| ��TOP |
| ��ԋ��� |
| Das Fliegende Klassenzimmer |
|
 |
 |
| �ēF |
�g�~�[�E���B�K���g |
| ����F |
�G�[���q�E�P�X�g�i�[ |
| �r�{�F |
�w�����b�e�E�s�[�p�[
�t�����c�B�X�J�E�u�b�t
�E�b�V�[�E���C�q |
| ���y�F |
�j�L�E���C�U�[ |
| �o���F |
�n�E�P�E�f�B�[�K���t
�t���f���b�N�E���E
�t�B���b�v�E�y�[�^�[�X���A�[�m���Y
�E�����q�E�m�G�e��
�Z�o�X�`�����E�R�b�z |
|
 |
 |
 �����T�C�g�i�h�C�c��j �����T�C�g�i�h�C�c��j
 �����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |
|
 |
| �P�X�g�i�[�̗D�������@ |
������ |
�L���ȃh�C�c�̎������w��ƁA�G�[���q�E�P�X�g�i�[��
�������f�扻�����̂����̍�i�B
�i�ق��ɂ́w�_�q�����ƃA���g���x�Ȃǂ�����܂��B�j
���鉹�y�w�Z��ɁA���{�ł͒��w���ɂ�����N���
�q���������D��Ȃ��A�F��Ɗ�]�ɖ��������b�ł���܂��B
���̃G�[���q�E�P�X�g�i�[�Ƃ����l�A�L���炵���̂ł���
����m��܂���ł����B�ł��A�f����ς����A
�u����̉������s���v������Ȃ̂��Ȃ��Ǝv���܂����ˁB
�Ȃ�ƂȂ��A����������ɂ悭�ǂ܂��ꂻ���ȁu����v���Ċ�����
���͋C�����肠��ƁB
�ǂ����Ƃ��������Ƃ��Ђ�����߂�
�傫�Ȏ������獱�ׂȏo�����܂ŁA
����̒��ł͂��낢��N�����ł����A
�i���Ԃ�j�G�[���q�E�P�X�g�i�[�̎��D�������@��
�X�N���[������ɂ��ݏo�Ă��ł���B
������A���̉f��������P�O�O���Ƃ��Ċς邱�Ƃ��Ȃ��A
���Ƃ����āu�P�b�A�����̖����ꂩ��I�v�ƂЂ˂���邱�Ƃ��Ȃ�
�����ɂ��̐��E�ɂЂ��邱�Ƃ��ł����̂��Ȃ��`�B�Ȃ�āB
���ꂩ��A��l���ł��鏭�N�����������˂��A
������ł���I�����������Ă�́I
�N�\���ӋC�Ń}�Z�Ă�K�L�ǂ��Ȃ�ł����A
�܂������Ƃ����Ă����قǃC���~���Ȃ��̂ˁB
���̑�������ӂ��̗v�f�𗼗������Ă��܂���
���̎q�������Ɗē͂��炵���Ǝv���܂��B
�������I
���܂�ɂ����@�̈З͂����������������A
�f��I�ɂ̓����n��������Ȃ������悤�ȋC�����܂��B
�Ō�̂ق��Ȃ�āA�����ƃK���K���ɐ���グ�Ă��ꂽ��
�����Ƃ悩�����̂ɂȂ��`�B�������c�O�B
�܂��A���y�̕��͋C��
�����h�C�c�f��ł���w�O�b�o�C�E���[�j���I�x�Ǝ������Ă���
�i�Ƃ������Ƃ́w�A�����x�ɂ����Ă���Ƃ������Ɓj
�܂��������ǁA������Ƃˁc���Ċ����ł����B
�ȏ�A�w�_�q�����ƃA���g���x�������^�����悤���Ǝv���n�߂Ă�
ketsu�������肵�܂����B |
|
| posted on 2004.06.02 |
|
| ��TOP |
 May,2004�@|�@back number�@|�@July,2004 May,2004�@|�@back number�@|�@July,2004  |