
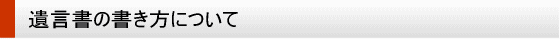

遺言書を作成すべきケース
遺言書の作成について
以下のようなケースでは、遺言書を作成することを強くおすすめします。
(遺言書が無くては不可能な場合もあります)
|
法定相続分と異なる配分をしたい場合
|
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。
|
|
遺産の種類・数量が多い場合
|
遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で作成、指定しておけば紛争防止になります。
|
|
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
|
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。
|
|
農家や個人事業主の場合
|
相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。
|
|
相続人以外に財産を与えたい場合
※遺言書の作成がなければ不可能と考えてください。
|
内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)
生前特にお世話になった人や団体
公共団体などへの寄付
|
|
その他遺言書を作成すべき場合
|
先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)
相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
相続人同士の仲が悪い
|
遺言書作成の方式
〜法律で定める方式以外の遺言書の作成は無効です。〜
民法によれば、遺言書は、この法律(民法)に定める方式に従わなければ、これをすることができない。と規定されています。つまり、民法の規定に従わない遺言書の作成は有効とは認められないということです。民法では普通方式の遺言書として、以下の3つを規定しています。
|
自筆証書遺言
|
遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名を自分で書いた上で押印します。これらが欠けたものは無効となります。問題点としては、法律的に間違いのない文章を作成することはなかなか困難なことですし、保管上の問題もあります。遺言執行の際には家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません。よく筆跡鑑定などで真実性が争われているのが、この遺言書です。
|
|
秘密証書遺言
|
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。この場合は自筆証書遺言と違い、本文は自筆でなくても構いません。やはりこの方式の遺言書も、内容の正確さの問題や検認手続の問題があります。
|
|
公正証書遺言
|
証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらった上で読み聞かせてもらいます。その筆記に間違いがないことを確認した上で署名・押印します。この方式の遺言書が一番おすすめできるものです。
|
遺言書の作成における種類と特徴
|
|
自筆証書遺言
|
公正証書遺言
|
秘密証書遺言
|
|
作成方法
|
本人が遺言の全文と日付・
氏名を書いて、押印(認印でもよい)する。( ワープロ・テープ不可。 遺言書が何通もあるときは、日付の最も新しいものが優先される。 内容を加除訂正する場合は、変更場所にその指示
を付記して署名・押印する。)
|
本人が口述し、公証人が筆記する。
〜必要書類〜
・印鑑証明書
・身元確認の資料
・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本
|
本人が遺言書に署名捺印後、遺言書を封じ、遺言書に使用したものと同じ印で封印する事。
公証人の前で本人が住所、氏名を記す。 公証人が日付と本人が述べた内容を書く。(ワープロ・代筆可)
|
|
場所
|
自由
|
公証人役場
|
公証人役場
|
|
証人
|
不要
|
証人2人以上
|
公証人1人、証人2人
|
|
署名捺印
|
本人
|
本人、公証人、証人
|
本人、公証人、証人
|
|
家庭裁判所の検認
|
必要
|
不要
|
必要
|
|
メリット・デメリットについて
|
|
メリット
|
証人の必要がない。
遺言を秘密にできる。
費用がかからない。
|
証拠能力が高い。
偽造の危険がない。
検認手続きが不要。
|
遺言の存在が明確。
遺言の内容は秘密。
偽造の危険がない。
|
|
デメリット
|
紛失、偽造の危険性がある。
方式不備による無効の可能性が生じる事がある。
検認手続きが必要。
|
作成手続が煩雑になりやすい。
遺言を秘密にできない。
費用がかかる。
証人2人以上の立会が必要になる。
|
作成手続が煩雑になりやすい。
費用がかかる。
検認手続きが必要。
|
「家庭裁判所の検認手続き」とは
公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を避けるため、遺言の執行前に、家庭
裁判所の「検認」を受けなければなりません。
家庭裁判所で、遺言書がどのように作成されているかを記録して調書を作成することを「検認」と言います。
「検認」を家庭裁判所に申し立てるときは、「遺言書の検認申立書」に必要事項を記入して、遺言者の原戸籍謄本(抄本)・除籍謄本、そして申立人と相続人全員の戸籍謄本(抄本)を添付する必要があります。
「検認」がなくても遺言の効力に影響はありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には過料に処されるので注意しなければなりません。
公正証書遺言とは
〜安全・安心・確実な遺言書〜
このような利点があります!
1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがありません。
2.家庭裁判所における検認手続が不要です。
3.法律の専門家である公証人が遺言書を作成しますので、内容に間違いがありません。
ただしこのような点もあります!
事前に原案を作成・準備しておく必要があります。
原案の段階で、具体的な配分なども決めておかなくてはなりません。行政書士などの専門家に依頼して作成することもできます。
証人が立ち会いますので秘密の保持が困難です。
行政書士が証人となった場合には、法律で守秘義務が課せられていますので安心です。(知人に証人を頼むことは避けた方が賢明です)
ある程度の費用がかかります。
遺言執行者について
〜遺言は執行されなければ意味がありません〜
遺言書を作成しても、その内容を実現してもらえるとは限りません。特に法定相続分と異なる配分を指定した場合や、相続人以外に遺産を与える内容の場合など、相続人が遺言執行に非協力的なケースが多く見受けられます。
そのようなときは遺言で遺言執行者を指定しておけば、その遺言執行者が遺言の内容を実現してくれます。遺言執行者は相続人でも第三者でもなれますが、信頼できる相続人かあるいは行政書士などの専門家を指定しておくことが賢明です。また遺言執行者の報酬についても、遺言で定めておくことが出来ます。
自筆証書遺言の作成例
この遺言書は必ず遺言者本人の自書(全文自筆)で、できるだけ内容をわかりやすく(明確に)記載し作成してください。(縦書きでも横書きでも結構です。)
|
遺言書
遺言者 北海 太郎は、次のとおり遺言する。
一、遺言者はその所有に係る次の不動産及び預金を妻、福岡 花子に相続させる。
(一)〇〇道△△市××町○丁目○番□号 宅地□□平方メートル
(二)同所同番地所在 家屋番号同所○○番 木造瓦葺二階建居宅一棟 床面積△△平方メートル
(三)遺言者名義の○○銀行○○支店の定期預金全部
二、 遺言者はその所有に係る次の不動産を長男、北海 一郎に相続させる。
〇〇道△△市××町○丁目×番△号
宅地〇□平方メートル
三、 遺言執行者として○○道△△市○○町○○番地の行政書士、****を指定する。
平成○年○月○日
(注)日付も自書です(○月吉日という書き方やゴム印は不可)
〇〇道△△市××町○丁目○番□号
遺言者 北海 太郎 印 (注)署名捺印は必ずする。
昭和〇〇年△△月□□日生
(注)遺言者を特定できるよう記載するのが望ましい。
|
遺言書の書き方へ
|

