
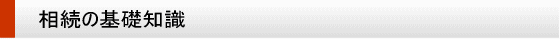

相続人とは?
相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ人のことです。
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になることができる者及びその順位は民法によって定められています。
|
配偶者
|
配偶者は、常に相続人となります。
この配偶者は、法律上の配偶者のことであり、内縁の配偶者は含まれません。
|
|
第1順位
|
被相続人の子です。
子が数人いる時は、同順位で平等に相続します。
ただし、非嫡出子の場合は、嫡出子の相続分の半分になります。
胎児にも相続権が認められています。
※配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します
|
|
第2順位
|
直系尊属つまり、被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。
|
|
第3順位
|
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
兄弟姉妹が数人いる場合には、同順位で平等に相続します。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります
|
※上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、「相続排除」をされた場合には、相続権はありません。
相続欠格事由
次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
(相続人となることができない人)
|
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
|
相続人の排除
「相続人の排除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。排除には、生前排除と遺言排除があります。
生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。
排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います。
代襲相続
相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡していたり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。
このような場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。
「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。
※ 相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。
代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。
子については、相続人の直系卑属であるだけでなく、被相続人の直系卑属でなければなりません。よって、養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。
再代襲相続
再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者の子が代わりに相続する制度です。
つまり、被相続人Aさんが死亡し、その相続人Bさんも死亡していた場合、「代襲相続」としてBさんの子であるCさんが相続することになりますが、このCさんも死亡していた場合には、Cさんの子Dさんが「再代襲相続」するということになります。
この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません。
相続財産とは
相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。
その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。
相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが、主なものは下記のとおりです。
|
積極財産
|
消極財産
|
|
1.不動産(土地・建物)
2.現金・預金・小切手
3.株式・社債・証券 投資信託
4.家具・自動車
5.貴金属・ゴルフ会員権
6.書画骨董
7.貸付金・売掛金
8.電話加入権・著作権
など・・・
|
1.借金・買掛金・未払金
2.税金
など・・・
|
※ 慰謝料請求権
判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしておりましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には、慰謝料請求権も相続されるとしております
※ 生命保険金
保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。
しかし、受取人を単に相続人と指定している場合には、判例は特段の事情のない限り被相続人の固有財産となるとしております。
※ 死亡退職金
会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。
ただし、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがあります。
※ 借家権・借地権
一般に財産権と理解され相続の対象になります。また、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など払う必要はありません。
相続財産を分ける相続分について
共同相続人が受ける持分の割合のことを相続分と言います。相続分の決めかたは、一般的に以下の方法がとられています。
|
遺言による相続分
の指定をする場合
|
遺産分割協議
による場合
|
|
被相続人が遺言によって相続財産の分け方を指定する方法です。被相続人は遺言によって、相続分を定めたり、第三者に相続分の指定を委託することを定めることができます。
また、被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ相続分を定めることを、遺言によって定めたり、第三者に相続分の指定を委託することもできます。この場合には、残りの相続人の相続分は、法定相続分によることになります。
※ このように被相続人は、相続分を指定することができるのですが、遺留分に反することはできません。
遺留分に反する相続分を指定した場合には、その遺言が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることによって侵害された部分を取り戻すことができます。
|
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話し合いによって相続分を決めることができます。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければなりません。
この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効になり、また全員の一致がなければ協議は成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。なお、生前に多額な贈与を受けていた場合や、被相続人と一緒に事業をしていて、被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等いろんなケースがあります。
|
相続の基礎知識へ
|

