
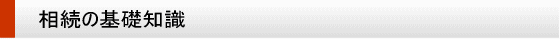

�@�葊�����ɂ���
�@�葊�����Ƃ͖��@�̋K��ɂ�莟�̂悤�ɒ�߂��Ă��܂��B
|
��������
|
�����l
|
������
|
|
��P����
|
�z���
|
�Q����1
|
|
�q
|
�Q����1
|
|
��Q����
|
�z���
|
�R���̂Q
|
|
���n����
|
�R���̂P
|
|
��R����
|
�z���
|
�S���̂R
|
|
�Z��o��
|
�S���̂P
|
���@�q�A���n�������́A�Z��o�������l�ł���Ƃ��́A�e���̎����͓������Ȃ�܂��B�������A���o�łȂ��q�̑������́A���o�ł���q�̑������̂Q����1�ł���A����̈���݂̂�������Z��o���̑������́A����̑o����������Z��o���̑������̂Q����1�ƂȂ�܂��B
|
�Ⴆ�Ύ��̂悤�ȏꍇ�́E�E�E
|
��Y�P�Q�O�O���~�@�@�ȁ@�@�q���@�`�i���o�q�j�E�a�i���o�q�j�E�b�i�o�q�j�E�c�i�o�q�j
|
�ȂƎq���S�l�̎����̊����͂Q����1���ƂȂ�܂��B
�q�S�l�̎����͑��������̂������ł����A�b�Ƃc�͔o�q�ł��̂ł`�Ƃa�̎����̂P/�Q�ƂȂ�܂��B
����đ����l�̎����䗦�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�ȁF�`�F�a�F�b�F�c���U�F�Q�F�Q�F�P�F�P�@
����āA�@�葊������
|
��
|
�@�P�C�Q�O�O���~�~�U/�P�Q���U�O�O���~
|
|
�q�`
|
�@�P�C�Q�O�O���~�~�Q/�P�Q���Q�O�O���~
|
|
�q�a
|
�@�P�C�Q�O�O���~�~�Q/�P�Q���Q�O�O���~
|
|
�q�b
|
�@�P�C�Q�O�O���~�~�P/�P�Q���P�O�O���~
|
|
�q�c�@
|
�P�C�Q�O�O���~�~�P/�P�Q���P�O�O���~
|
�ƂȂ�܂��B
|
�◯���Ƃ�
�◯���Ƃ́A�푊���l�̈⌾�ɂ���Ă��Q���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�����l�������Ɋւ��ĕۏႳ��Ă����Y�̈ꕔ�������܂��B
�܂�A�푊���l���s���Ȉ⌾�؏����c�����ꍇ�ȂǑ����l���~�ς�����̂ł��B
|
�◯��������
�z��ҁA�q�A���n�����i�e�j
���@�q�ɂ��ẮA��P�����ł����Ă��F�߂��܂��B
���@�َ��ɂ��Ă����܂�Ă���Έ◯����L���܂��B
���@�Z��o���ɂ͂���܂���B�@
|
�◯���̊���
�◯���̊����́A�N�������l�ɂȂ邩�ɂ���ĕς���Ă��܂��B
|
�����l
|
�����l�S��
�̈◯��
|
�z��҂�
�◯��
|
���������l��
�◯��
|
|
�z��҂�
�q
|
�P/�Q
|
�P/�Q�~�P/�Q
���P/�S
|
�P/�Q�~�P/�Q���P/�S
�Q�l����P�l������
�P/�S�~�P/�Q���P/�W
|
|
�z��҂�
���n����
|
�P/�Q
|
�P/�Q�~�Q/�R
���P/�R
|
�P/�Q�~�P/�R���P/�U
�Q�l����P�l������
�P/�U�~�P/�Q���P/�P�Q
|
|
�z��҂�
�Z��o��
|
�P/�Q
|
�P/�Q
|
�\
|
|
�z��҂̂�
|
�P/�Q
|
�P/�Q
|
�\
|
|
�q�̂�
|
�P/�Q
|
�\
|
�P/�Q
|
|
���n�����̂�
|
�P/�R
|
�\
|
�P/�R
|
|
�Z��o���̂�
|
0
|
�\
|
�O
|
�◯���̎Z��
�◯���̎Z����@�́A�u�◯���Z��̊�b�ƂȂ���Y�v�Ɂu�e�����l�̈◯�����v���悶�ĎZ�o���܂��B
|
�@�@�����J�n���ɗL���Ă������Y
�A�@�����J�n�O�P�N�ȓ��ɑ��^�������Y
�B�@�����J�n�̂P�N�ȏ�O�ł����Ă������ґo�����A�◯�������҂ɑ��Q��^���邱�Ƃ�m���čs�Ȃ������^
�C�@�����E�{�q���g�E���v�̎��{�Ƃ��đ��^���ꂽ���Y
�@�`�C�̍��Y�����v�����z����؋��Ȃǂ̍��������A�c�����z���A�u�◯���Z��̊�b�ƂȂ���Y�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
|
�◯���̕���
�����J�n�O�́u�����̕����v�͔F�߂��܂��A�u�◯���̕����v�͔F�߂��܂��B
�@�◯���̕����ɂ́A�ƒ�ٔ����̋����K�v�ŁA�u�◯�������̋��̐R���v�𐿋����邱�ƂɂȂ�܂��B�i�ƒ�ٔ��������������A���̕������{�l�̎��R�Ȉӎv�ɂ����̂ŁA���O�ɔ푊���l���瑡�^���Ă���Ȃǂ̐����ȗ��R���K�v�ł��B�j
�◯�����E����
�◯����N�Q���čs�Ȃ�ꂽ�푊���l�̈②�②�^�͓��R�ɖ����ƂȂ�킯�ł͂���܂���B���̏ꍇ�ɂ́A�◯�������҂���̌��E�����̑ΏۂƂȂ�ɂ����܂���B
�@���̂悤�Ɉ◯����N�Q����②�E���^�����ꂽ�ꍇ�ɁA�◯�������҂��◯������߂����Ƃ��u�◯�����E�����v�ƌ����܂��B
�◯�����E�����̎���
���E�̐������́A�◯�������҂������̊J�n�y�ь��E���ׂ����^���͈②�����������Ƃ�m���Ă���P�N�ԁA������s�Ȃ�Ȃ����́A�����ɂ���ď��ł��܂��B�܂��A�����̊J�n�̎�����P�O�N���o�߂����Ƃ������l�ł��B
�����̏��F�E����
�����l�́A�����J�n��A���̑��������F�i�P�����F�E���菳�F�j���邩�������邩�̑I������L���܂����A���̑I���͑����J�n�����������Ƃ�m���Ă���R�����ȓ��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������@�̋K�肪����܂��B
�@���̑����̏��F�E�����́A�����J�n�O�ɍs�Ȃ��Ă������ƂȂ�܂��B
�P�����F
�푊���l�̍��Y�����E�������ɏ��F���邱�Ƃ������܂��B�܂�A�v���X���Y�ł���y�n�E������a�����𑊑��������ɁA�؋��Ȃǂ̍��������p�����ƂɂȂ�킯�ł��B
�@�܂��A�P�����F�ɂ́A�u�@��P�����F�v�Ƃ������̂�����܂��B
���́u�@��P�����F�v�Ƃ́A�ȉ��̏ꍇ�ɂ͒P�����F���ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ���閯�@�̋K��ł��B
|
�P�����F�Ƃ݂Ȃ����s��
�P.�����l���������Y�̑S�����͈ꕔ�����������ꍇ
�Q.�R�����̊��Ԃ�k�߂����ꍇ
�R.�������Y�̉B���Ȃǂ̔w�M�I�s�ׂ��s�����ꍇ
|
���菳�F
�����l�������ɂ���ē����ϋɍ��Y�̌��x�ł̂݁A�푊���l�̍��E�②�Ȃǂ̕��S����Ƃ��������̈ӎv�\���̂��Ƃł��B
�@�܂�A�P�C�O�O�O���~�̗a���ƁA�R�C�O�O�O���~�̎؋������������ɁA���҂ɑ��ĂP�C�O�O�O���~�����x�Ƃ��ĐӔC���Ƃ��������̌`�Ԃł��B
�@���̌��菳�F�͑����l�����l����ꍇ�ɂ́A�����l�S���Ō��菳�F�����Ȃ��Ă͂����܂���B
�@���菳�F�̎葱���́A�����l�������̊J�n��m����������R�����ȓ��Ɉ�Y�̍��Y�ژ^�����ĉƒ�ٔ����ɒ�o���A���菳�F���s���|�̐\�p�����Ȃ���Ȃ�܂���B
���@��
�푊���l�̈�̍��Y�𑊑����Ȃ����Ƃł��B
�����l�́A�����̊J�n��m���Ă���R�����ȓ��ɒP�Ƃʼnƒ�ٔ����ɑ��Đ\���o�đ�����������邱�Ƃ��ł��܂��B
�������������ƍŏ����瑊���l�łȂ��������̂Ƃ݂Ȃ���A�������������l�Ɏq�����Ă��A���̎q�͑�P�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
��Y�������c�Ƃ�
�⌾���Ȃ��ꍇ�ɂ͋��������l�̋��c�i�b�������j�ɂ���Ĉ�Y�����܂��B
����́A�������J�n����Ă���A�������Y�͋��������l�̋��L���`�ƂȂ��Ă���̂ŁA�b�������ɂ���Ċe���̎������m�肷�邽�߂ł��B
�����̑O��Ƃ��Ĉȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
|
�i�P�j�����l���m�肷��
|
���͒N�������l�ɂȂ邩�킩��Ǝv���܂����A������ׂ̈ɁA�ːГ��{�Ȃǂ����Ē������܂��B
|
|
�i�Q�j�������Y�̒���
|
�푊���l�̏��L���Ă����s���Y��a�����A���邢�́A�؋��Ȃǂ̗L���ׂđ������Y���m�肵�܂��B
�i���Y�ژ^���쐬���܂��B�j
|
|
�i�R�j�������Y�̎Z��
|
�������Y�����������Ȃ���͂���܂��A�y�n�Ȃǂ̕]�����㉺���Ă��Č��߂ɂ������̂�����܂��B
|
��Y�������c�̓����҂Ƃ́E�E�E
|
��Y�������c�̓����҂ɂȂ���
�i1�j���������l
�i2�j�����l�Ɠ���̌����`����L��������
�i3�j�������̏���l
|
��Y�������c�́A�K����Y�������c�̓����ґS�����W�܂��čs��Ȃ���Ȃ�܂���B
���@�����҂̒��ɐe���҂Ƃ��̖����N�̎q������ꍇ�ɂ́A���v�����s�ׂƂȂ�A���ʑ㗝�l�I�C�Ƃ����葱�����K�v�ɂȂ�ꍇ������܂��B
�R������
�����l�Ԃŋ��c������Ȃ�������A�����l�̒��ɍs���s���҂Ȃǂ����ċ��c�ɉ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ƒ�ٔ����̒��▔�͐R���ɂ���ĕ������Ȃ���܂��B
�@�����l�́A�N�ł��\�����Ăł��܂����A���������l�y�ї��Q�W�l�������A����Y�̖ژ^���o���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�ƒ�ٔ����́A��Y�ɑ����镨���͌����̎�ށE�����E�e�����l�̐E�Ƃ��̑���̎�����l�����ĕ����̐R�����s�Ȃ��܂��B
�w�蕪��
�푊���l�͈⌾�Ŏ��番���̕��@���w�肵�A�܂��́A��O�҂ɂ��̎w����ϑ����邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�ɂ́A����ɂ��������ĕ������Ȃ���Ȃ�܂���B
��Y�����̋֎~
���̏ꍇ�́A�����ԕ������֎~���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�@�푊���l�̈⌾
�A�@���������l�̓���
�B�@�ƒ�ٔ����̐R��
�����l�����Ȃ��ꍇ
�����l�S�������i�E�p���E�����Ȃǂɂ���đ�������L���Ȃ��Ȃ����ꍇ�ȂǑ����l�����݂��Ȃ��ꍇ�́A�������Y�͂P�̖@�l�Ƃ��Ĉ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�����ė��Q�W�l���͌��@���̐����ɂ���āA�ƒ�ٔ������������Y�Ǘ��l��I�C���A���̌������s�Ȃ��܂��B
���̑������Y�Ǘ��l�I�C��������Q�������o�Ă������l�̑��݂����炩�łȂ��ꍇ�ɂ́A�������Y�Ǘ��l�͑������Y�̐��Z�葱���ɓ��邱�ƂɂȂ�܂��B
���������Y�̐��Z�葱����
|
�@�@�����̐\�o�����߂����
|
�������Y�Ǘ��l�͂Q����������Ȃ����Ԃ��߂āA��̑������ҁE���҂ɑ��Ă��̐��������߂�������s�Ȃ��܂��B
���̐������ԓ��ɐ\�o������A���Ԗ����̂̂����Z�葱���ɓ��邱�ƂɂȂ�܂��B
|
|
�A�@�����l�{������
|
��L�̌������Ԃ��I�����Ă��Ȃ������l�����݂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ƒ�ٔ����́A�Ǘ��l���͌��@���̐����ɂ��U����������Ȃ����Ԃ��߂āA�����l�ɂ��̌������咣����悤�������s�Ȃ��܂��B
�����l�̑��݂����炩�ɂȂ����ꍇ�́A���Z�葱���͏I�����܂����A���̊��ԓ��ɐ\�o���Ȃ������ꍇ�ɂ́A�����l�⑊�����ҋy�ю��҂͊m��I�ɑ��݂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
|
|
�B�@���ʉ��̎҂ւ̍��Y���^
|
�푊���l�Ɛ��v��ɂ��Ă����҂�푊���l�̗×{�Ō�ɓw�߂��҂��̑��푊���l�Ɠ��ʂ̉��̂��������҂�������ʉ��̎҂́A�����l�{�������̊��Ԗ�����R�����ȓ��ɁA�ƒ�ٔ����ɍ��Y���^�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�ƒ�ٔ����́A���ʉ��̎҂ɓ����邩�ۂ���̎�����l��������Ŕ��f���邱�ƂɂȂ�܂��B
|
|
�C�@���ɂւ̋A��
|
�����l�{���������Ԗ�����R�����ȓ��ɓ��ʉ��̎҂���̐\�o���Ȃ��A���͍��Y���^���s�Ȃ��Ă��Ȃ����Y���c��ꍇ�ɂ́A�������Y�͍��ɂɋA�����A�������Y�@�l�͏��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B
|
����������
�����l�łȂ��ɂ�������炸�����㑊���l�Ƃ��Ă̒n�ʂ̂���ҁi�\�������l�j�ɂ���āA�����l�����̑�������N�Q���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����l�͑��������咣���đ������Y�����߂����Ƃ��ł��܂��B
���̌������A�u�����������v�Ƃ����܂��B
������������
�����������ł���҂́A��L�������Ă���^���̑����l�Ƃ��̖@��㗝�l�ł��B�܂��A��������������҂��^�������l�Ƃ��Ă̒n�ʂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���邽�߁A�����l�ɏ����đ������������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�������A�������Y�̓��菳�p�l�̏ꍇ�ɂ͑������������s�g���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�����̊�b�m����
|

