
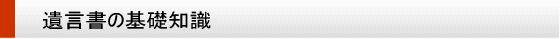

�⌾�Ƃ́H
�⌾���Ƃ́A�����ڑO�ɔ������Ƃ��ɍ쐬������̂��Ǝv���Ă��܂��H�@
���邢�͎����ɂ͕K�v�̂Ȃ����̂��Ǝv���Ă��܂��H
�⌾���Ƃ́A�e���r�h���}��f��ɏo�Ă���悤�ȁA����Ȏ��Y�������A���̈����Ƒ��B�Ɉ͂܂ꂽ�A�ǓƂȘV���Y�Ƃɂ����K�v�̂Ȃ����̂ł͂���܂���B�������ʂ̐l�ɂƂ��Ă��K�v�Ƃ������̂ł��B
�l�͐��O�A�����̈ӎu�Ŏ��R�ɍ��Y�������ł��܂����A����������̂��Ƃ����������ɁA�c���ꂽ�Ƒ��B�͌̐l�̈ӎv���m���߂邱�Ƃ͏o���܂���B�̐l�̈ӎv���ő�����d�������Ƃ��A���̈ӎv���m�F����p��������ǂ����悤������܂���B���̂Ƃ��Ɂg�⌾���h�Ƃ����A�`�ɂȂ������̂��c����Ă����Ȃ�A�Ƒ��B�͌̐l�̈ӎv���m�F���邱�Ƃ��ł��A���̓��e�ɉ������`�ł̍��Y�̔z�����\�ɂȂ�܂��B�⌾�����쐬���邱�Ƃɂ���āA�c���ꂽ�Ƒ��B�ɖ��p�̐S�z�������邱�Ƃ��������܂��B
���O�Ɉ⌾�����쐬���Ă������Ƃ́A�����āg�����ɂ͑S�R�W�̂Ȃ����Ɓh�ł��A�g���N�ł��Ȃ����Ɓh�ł�����܂���B
�c�����Ƒ��̂��߂̎v�����Ƃ��āA�����Ĉ��S�邽�߂ɁA�⌾�����쐬���Ă������Ƃ��������߂��܂��B
�⌾�i�u������v�܂��́u�䂢����v�j�Ƃ́A�⌾�����l�i�⌾�ҁj���A�����̎���̖@���W�i���Y�A�g���Ȃǁj���A���̕����ɏ]���Ē�߂�A�ŏI�I�Ȉӎu�̕\���̂��Ƃł��B
�킩��₷�������ƁA�����������ɁA�u���Y��N�X�Ɏc���v�Ƃ��A�u���͉B���q�������v�Ƃ����������Ƃ��A���ʑO�ɏ����Ďc���Ă������Ƃł��B�C�����Ȃ�������Ȃ��̂́A�⌾�̕����͖@���Œ�߂��Ă����̂ŁA����Ɉᔽ����⌾�͖����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B
�⌾�͎��ʑO�ł���A���ł��{�l�̈ӎu�Ŏ��R�ɕύX�i�P��j���邱�Ƃ��ł��܂��B�������ύX�i�P��j����Ƃ����A�@����̕��������Ȃ�������܂���B
�⌾�Œ�߂邱�Ƃ��o������e���@���Ō��܂��Ă��܂��̂ŁA����ȊO�̎����ɂ��Ē�߂Ă����̌��͂�����܂���B
�������u���l�̍��Y�𑧎q�ɂ�����v�Ȃ�Ă��Ƃ��F�߂��܂���B�⌾�Œ�߂���̂́A�����������Ă��錠���͈͓̔��݂̂Ƃ������Ƃł��B
�Ȃ��⌾���K�v�Ȃ̂�
�⌾�Ƃ́A�u�l�̍ŏI�ӎv�ɁA����@�I���ʂ�F�߂āA���̎�����ۏ��鐧�x�v�ł��B�ƒ�ٔ����Ɏ������܂�鑊�������̑����́A�����Ȉ⌾�����Ȃ����߂��Ƃ����Ă��܂��B
�����ɂ킽��ꐶ���������Ēz�������Y���⌾���Ȃ����߂ɁA�c���ꂽ���e���m����Y�������J��L����悤�ł͓V���ɂ���͂��̖{�l����肫��Ȃ����̂ł��傤�B
�q���̍K���̂��߂ɂȂ�ׂ���Y���A�����̑����������N�����A�s�K�̌����ɂȂ��Ă͂��܂�܂���B���Y�̂���l�́A���O�Ɏ����̍��Y�̏Ƃ��̍s�����߂��⌾���쐬����ׂ��ł��B
�⌾�͈�Y���߂���g���u����h���őP�̕��@�ł���ƂƂ��ɁA��Y�𐢂̂��߁A�l�̂��߂ɐ������o���_�ł�����܂��B�܂��A�c���͎̂؋��������Ƃ����ꍇ�ł��A�c���ꂽ�Ƒ����@�I�Ȏ葱�i���������j�ɂ��؋��̕ԍϋ`����Ȃ��Ă��ނ悤�A���̓��e���⌾�Ƃ����������ŏ����c���Ă����������̂ł��B
�⌾�ŏo���邱��
�⌾�ŏo���鎖���͖@���Œ�߂��Ă�����̎����Ɍ����܂��B
�i�P�j���`�̑����Ɋւ��鎖��
�@�@�@���葊���l�̔r���E������@
�@�@�A�������̎w��E�w��̈ϑ��@
�@�@�B���ʎ�v�̎��߂��̖Ə��@
�@�@�C��Y�����̕��@�w��E�w��̈ϑ��@
�@�@�D��Y�����̋֎~�@
�@�@�E���������l�̒S�ېӔC�̌��ƁE���d�@
�@�@�F�②�̌��E�̏����E�����̎w��@
�i�Q�j��Y�̏����Ɋւ��鎖��
�@�@�G�②�@
�@�@�H���c�@�l�ݗ��̂��߂̊�t�s�ׁ@
�@�@�I�M���̐ݒ�@
�i�R�j�g����̎���
�@�@�J�F�m�@
�@�@�K�����N�҂̌㌩�l�̎w��@
�@�@�L�㌩�ēl�̎w��@
�i�S�j�⌾���s�Ɋւ��鎖��
�@�@�M�⌾���s�҂̎w��E�w��̈ϑ��@
�i�T�j�w���ŔF�߂��Ă��鎖��
�@�@�N�c��̍��J��Ɏ҂̎w��
�@�@�O�����ی������l�̎w��E�ύX�@
�⌾�ɂ���č��Y��^���邱�Ƃ��u�②�v�Ƃ����܂��B
�⌾�ɂ���č��Y��^���邱�Ƃ��u�②�v�Ƃ����܂��B����́A���Y���鑤�̈ӎv�Ɋւ��Ȃ������܂�����A�u�����܂��v�A�u�͂��A���炢�܂��v�Ƃ��������̌_��ł���u���^�v�Ƃ͖@�����ʂ���Ă��܂��B�⌾�ɂ���Ĕ푊���l�̈ӎv�����m�Ɏ�����Ă���A�����̃g���u���̑����͖h�����Ƃ��ł���ł��傤�B
�⌾�łǂ��܂łł��邩�H
"�⌾�ɂ���Y�̏����ɂ����E������܂�"
�i�P�j�u�◯���v�ɒ��ӂ���B
�◯���́A�⌾�ł��ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�����l�����Y�����炤���߂̍Œ���̊����ł��B
�◯���������Ă���̂́A�z��ҁA�q���A�e�����ŁA�Z��o���ɂ͂���܂���B�����N�Q���Ă���ꍇ�́A�N�Q���������l����̐����ɂ���ĕԂ��Ȃ�������܂���i�������Ȃ���ΕԂ��K�v�͂���܂���B�m��ʂ����Ƃ������Ƃ�����ł��傤�j�B
���Ƃ��A�u���l�ɑS���Y�𑊑�������v�Ƃ������e�̈⌾������Ă��A�u�◯�������ҁv��
���̍��Y�̂������ꂼ��̈◯���ɑ���������Y���u���E�v����i�Ƃ���ǂ��j�悤�ɋ��߂�A�⌾�̂Ƃ���ɂȂ�܂���B������u�◯�����E�������v�̍s�g�Ƃ����܂��B
�u�◯�������ҁv�Ƃ� �@�葊���l�̂����A�Z��o���ȊO�̑����l�ŁA�◯����L����҂������܂��B
�l�I�Ȉӌ��ł����A�◯���̐���������悤�ł́A���łɓD����ԂƂ����ėǂ���������܂���B
�����l�̌����͑O�����ĕ������邱�Ƃ͂ł��܂��A�◯���ɂ��Ă͑O�����ĕ������邱�Ƃ��ł��܂��B�푊���l�����O�Ɉ⌾�Œ�߂����������u�w�葊�����v�Ƃ����A����́u�@�葊�����v
�ɗD�悵�܂��B���Y�̏��L�҂͂�������R�ɏ������Ă��܂�Ȃ�����ł��B �������A���Y�����̎��R���ǂ��܂ł��\�Ȃ킯�ł͂Ȃ��A�u�◯���v�Ƃ����āA���̑����l�Ɏc���Ȃ���Ȃ�Ȃ���������߂��Ă��܂��B�����̍��Y���ǂꂭ�炢���R�ɏ����ł��邩�Ƃ����܂��ƁA�◯���̊����������������c��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�i�Q�j�����l�Ɏc���Œᑊ�������Ƃ́B
�⌾�҂̍��Y�̂����A���̑����l�Ɏc���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������◯���Ƃ����܂����A�◯���̌����҂Ƃ��̊����͎����̂Ƃ���ł��B�����҂́A�@�葊���l�̂����q�⑷�Ȃǂ̒��n�ڑ��A���E��Ȃǂ̒��n�����Ɣz��҂Ɍ����Ă���A
�Z��o���ɂ͈◯��������܂���B
�Ⴆ�A�⌾�҂����S�A�@�葊���l���ȂƎq��l�Łu��Y�̑S�Ăj�ɗ^����v �Ƃ��������e�̈⌾���������ꍇ�A�ȂƂ�����l�̎q�ɂ͈�Y���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂�A�ȂƂ�����l�̎q�̈◯����N�Q���Ă���A�Ƃ����킯�ł��B
�i3�j�◯����N�Q���ꂽ��ǂ����邩�B
�◯�����N�Q����Ă��Ă��A�����l���⌾�ǂ���̔z���𗹏�����Ȃ�A���ɖ��͂���܂���B�◯����N�Q���ꂽ�l�́A�◯���Ɋ�Â����E�i�����j����������
�K�v������܂��B�������A�P�N�ȓ��Ɏ咣���Ă����Ȃ��ƌ����������܂��B
���E�̐������́A�◯�������҂������J�n����сA���E���ׂ����^�܂��͈②�����������Ƃ�m�����Ƃ�����A�P�N�ԍs��Ȃ��Ƃ��A�܂��͑����J�n�̂Ƃ�����P�O�N���o�߂����Ƃ��������ɂ���ď������܂��B
�i���E�����c�s���������߂����ߐ������邱�Ɓj
�◯��
�P�D���n���������������l�ł���ꍇ�͔푊���l�̍��Y��
�@�@�P�^�R
�Q�D���̑��̏ꍇ�͔푊���l�̍��Y�̂P�^�Q
�@�k��l�ȂƎq�Q�l�������l�̏ꍇ�A
�@�@�@�E�Ȃ̈◯���͂S���̂P�i�P�^�Q�@�~�@�P�^�Q�j
�@�@�@�E�q1�l�̈◯���͂W���̂P�i�P�^�Q�@�~�@�P�^�S�j
|
�@�葊���l
�̗�
|
�◯����
���v
|
�����l
|
�@�葊����
|
�◯��
|
|
�z��҂̂�
|
�P�^�Q
|
�z���
|
�P
|
�P�^�Q
|
|
�z��҂�
�q���Q�l
|
�P�^�Q
|
�z���
|
�P�^�Q
|
�P�^�S
|
|
�q��
|
�P�^�S����
|
�P�^�W����
|
|
�q���Q�l
|
�P�^�Q
|
�q��
|
�P�^�Q����
|
�P�^�S����
|
|
�z��҂�
����
|
�P�^�Q
|
�z���
|
�Q�^�R
|
�P�^�R
|
|
����
|
�P�^�U����
|
�P�^�P�Q����
|
|
�z��҂�
�Z��Q�l
|
�P�^�Q
|
�z���
|
�R�^�S
|
�P�^�Q
|
|
�Z��
|
�P�^�W����
|
�Ȃ�
|
|
��
��
|
�P�^�R
|
����
|
�P�^�Q����
|
�P�^�U����
|
|
�Z��Q�l
|
�Ȃ�
|
�Z��
|
�P�^�U����
|
�Ȃ�
|
�⌾���̊�b�m����
|

