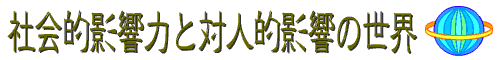業績の詳しい情報Additional Information
依頼と説得の心理学
『依頼と説得の心理学
−人は他者にどう影響を与えるか−』
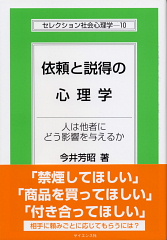
セレクション社会心理学 10 サイエンス社 \1,575
中国語版(華東師範大学出版社, 2011)が出版されました。
「はじめに」から 目 次 へ
−人は他者にどう影響を与えるか−』
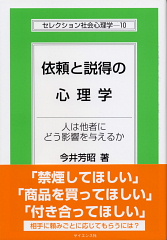
セレクション社会心理学 10 サイエンス社 \1,575
中国語版(華東師範大学出版社, 2011)が出版されました。
「はじめに」から 目 次 へ
| 私たちの生活において、人に何らかの頼みごとをしたり、人から頼まれごとをされたりすることがあります。例えば、次のようなことです。 * ファッションセンスのいい友人に、服を買いに行くのに一緒に行ってくれるよう頼み込む。 * 子どもに学校の宿題を忘れずにするように言う。 * 家族全体の健康のために、夫に禁煙するよう働きかける。 * 今度の選挙では、ある政党の候補者に投票するよう近所の知り合いにお願いする。 * 売れ筋商品を自分の店にも置かせて欲しいと懇意にしている卸売業者にお願いする。 * 販売強化商品である大画面テレビをどんどん売るよう部下の店員に指示する。 こうした事例を社会心理学において対人的影響と呼びます。個人間で相手に何らかの形で影響を与えるということです。対人的影響にはどのような種類があるのでしょうか。どのように相手に働きかけると、相手はこちら(与え手)の望むように行動してくれるのでしょうか。働きかけられた受け手はどのようなプロセスで自分の反応(例えば、応諾、拒否)を決めるのでしょうか。本書では、対人的影響に関わるこうした問題を取り上げていきたいと思います。  私たちはふだん何の不便も感じることなく、人に頼みごとをし、人からの頼まれごとに対応しているのかもしれません。私たちは、今までの体験に基づいて、どのように働きかければ相手に応じてもらえるか、頼みごとをするためには日頃からどのようなつきあいをしておくことが必要なのかを自然に学習しています。しかし、時として相手がなかなかこちらの言う通りに動いてくれなく、困ってしまったという経験もあると思います。最近、コミュニケーション、話し方、聞き方などの本が書店にたくさん横積みされているのを見ると、さらなるコミュニケーションのノウハウを人々が欲していることも確かなようです。できるならば、もっと効率的にコミュニケーション方法を身につけ、人とのコミュニケーションでつまらないストレスを感じずにすむようにしたいということだと思います。 本書は、コミュニケーションの中でも人に働きかける、働きかけられるという対人的影響に焦点を絞り、社会心理学の観点からまとめたものです。大学における社会心理学の授業を意識して、単なるノウハウだけを伝達するのではなく、その知識がどのような社会心理学的実験や調査に基づいて得られたのか、原典(学術雑誌に掲載された研究論文)にも当たりながら、できるだけ平易に書く努力をしました。また、理論的な議論は、抽象的でわかりにくい面がありますので、できるだけ図解し、イメージ的にも理解できるように努めました。 本書のキーワードは、対人的影響、依頼・要請、説得、コミュニケーションになります。本書の章立てを図解(PDFファイル)しておきました。 まず、第1章においては、そもそも人に影響を与えるとはどのようなことなのか、対人的影響にはどのような種類があるのかを概観します。対人的影響の分類です。その際、影響の与え手の意図性に注目することができます。つまり、意図的に人に影響を与えたのか、それとも意図せずに影響を与えたのかということです。 第1章は、対人的影響の概説ですが、第2章からは具体的な現象について見ていきます。第2章においては、無意図的な影響として、社会的手抜き、社会的促進、漏れ聞き効果、行動感染などの現象を見ていきたいと思います。 第3章以下で扱う対人的影響は、意図的なものです。まず、日常的によく起こりがちな依頼や要請、指示・命令について第3章で見ていきます。ここでは、依頼や要請時における働きかけ方(影響手段)、その効果性などについて明らかにします。フット・イン・ザ・ドア法やドア・イン・ザ・フェイス法などの連続的影響手段についても見ていきます。 残りの3つの章は、論拠(理由となる情報)を示しながら受け手の考えや行動を変えていく説得に関する章です。第4章において、説得の基礎となる態度の概念、態度の測定方法について理解します。 その後、第5章において、与え手の属性(特徴)、説得メッセージの構成、受け手に説得する際のメディア(対面、文章など)、受け手の属性という観点から説得に影響を与えている要因(規定因)を概観します。 最終章の第6章では、説得を受けた受け手の判断過程を理論化している精査可能性モデル、あるいは、認知的不協和理論や心理的リアクタンス理論についても目を向けます。 本書を通じて、読者の皆さんが対人的影響やコミュニケーション、社会心理学に関心をもつようになっていただければ幸いです。 |