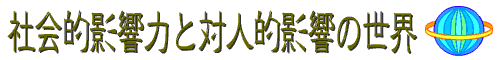業績の詳しい情報Additional Information
依頼と説得の心理学 **「目次」**
『依頼と説得の心理学
-人は他者にどう影響を与えるか-』
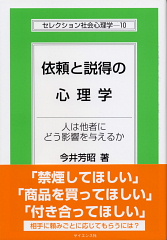
セレクション社会心理学 10 サイエンス社 \1,575
中国語版(華東師範大学出版社, 2011)が出版されました。
「目 次」 「はじめに」へ
-人は他者にどう影響を与えるか-』
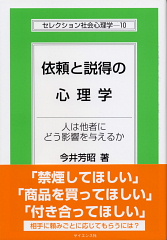
セレクション社会心理学 10 サイエンス社 \1,575
中国語版(華東師範大学出版社, 2011)が出版されました。
「目 次」 「はじめに」へ
| はじめに 目 次 第一章 人に影響を与える(対人的影響) (1) 対人コミュニケーション (2) 人に影響を与えるとは ●人に影響を与える ●対面状況における働きかけのメディア ●対人的影響の基本型 (3) 影響の与え手に関わること ①影響欲求 ②対人的影響の目標 ●支援を要請する(求援助) 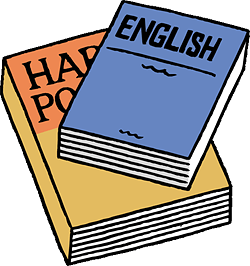 ●物品やサービスの購入を求める ●行動の変容を求める ●受け手の賛同や許可を求める ③受け手に影響を及ぼす際の賞と罰(コスト) ④情動(感情) ⑤受け手の選択 ⑥影響手段と言葉遣い ⑦メディア ⑧タイミング (4) 受け手に関わること (5) 対人的影響の相互作用性 (6) 対人的影響の種類 ①与え手の意図性の判断 ②意図的で明示的な対人的影響 ③意図的で隠蔽的な対人的影響 ④無意図的な対人的影響 <トピック1> リスク・コミュニケーション 第二章 意図的でない対人的影響 (1) 社会的手抜き ●リンゲルマン効果 ●ラタネらの実験 ●社会的手抜きの防止法 (2) 傍観者効果 ●痛ましい事件 ●ラタネとロディンの実験 ●傍観者効果を発生させる要因 (3) 社会的促進 ●ザイアンスのモデル ●マイケルズらの実験 (4) 漏れ聞き効果 ●ウォルスターとフェスティンガーの実験 ●漏れ聞き効果が生じる理由 ●アニメを用いた実験 (5) 行動感染 ●ミルグラムらの実験 ●日本での実験結果 ●行動感染の分類 ●そのほかの例 ●行動感染が生じる理由 ●モデリング ●バンデューラらの実験 (6) 情動感染 ●情動とは ●スィーらの実験 ●情動感染尺度 ●集団内の情動感染 第三章 依頼・要請 (1) 影響手段の種類 ①依頼・要請と影響手段 ②影響手段の種類 ③五つの影響手段 (2) 影響手段の用い方から見た与え手のタイプ ①与え手の四タイプ ②アサーション・トレーニング (3) 効果的な影響手段 ●組織場面 ●大学生の生活場面 (4) 連続的影響手段 ①フット・イン・ザ・ドア法 ●フリードマンとフレイザーの実験 ●フット・イン・ザ・ドア法の効果を高める要因 ●フット・イン・ザ・ドア法の効果が生じる理由 ●フット・イン・ザ・ドア法の効果を低下させる要因 ②ドア・イン・ザ・フェイス法 ●チャルディーニとアスカニの実験 ●ドア・イン・ザ・フェイス法の効果を高める要因 ●ドア・イン・ザ・フェイス法の効果が生じる理由 ●フット・イン・ザ・ドア法とドア・イン・ザ・フェイス法 ③その他の方法 ●ロー・ボール法 ●ザッツ・ノット・オール法 ●情報的・規範的影響 ●不安-安堵法 第四章 説得と態度 (1) 説得とは ●いろいろな説得の定義 ●依頼・要請、指示・命令と説得との違い (2) 説得と態度変容 ①態度とは ②態度対象と態度の三要素 ③態度の測定 ●質問項目作成時に重要なこと ④態度の測定法 ●リッカート法 <タバコに対する態度尺度Ⅰ> ●SD法 <タバコに対する態度尺度Ⅱ> ●サーストン法 <オープン・クラスに対する態度尺度> ⑤潜在連合テスト(IAT)による潜在的態度の測定 ⑥態度尺度の信頼性と妥当性 ●信頼性 ●妥当性 第五章 説得の規定因 -受け手の応諾を引き出す要因- (1) 与え手の属性 ①信憑性の効果 ②スリーパー効果 ③好感度 (2) 説得メッセージの構成 ①単一提示と両面提示 ②結論の明示 (3) 情報の提示順序 ①ホヴランドらの研究(初頭効果の規定因) ②受け手の熟知度 ③受け手の自我関与度 ④メッセージ混在効果 ⑤時間間隔 ⑥応諾することのコスト(負担度) (4) 説得メッセージのメディア (5) 受け手の属性 ①自尊心 ②知能 ③性別 ④パーソナリティー (6) 自己説得 第六章 説得のモデルと理論 (1)説得のプロセス ①態度や行動の変容を説明するモデル ②ヒューリスティック・システマティック・モデル ●システマティック処理とヒューリスティック情報処理 ●チェイキンの実験 ③精査可能性モデル ●中心ルートと周辺ルート ●ペティとカシオッポの実験 ●中心ルートと周辺ルートの関係 ④態度変容の単一プロセス ⑤計画行動理論 ⑥健康信念モデルと防護動機理論 ●健康信念モデル ●防護動機理論 (2) 説得に関連する理論 ①認知的不協和理論 ②コントロール感と心理的リアクタンス(押しつけに対する反発) ●コントロール感 ●心理的リアクタンス ●希少性の原理 <説得の具体例 夫に人間ドックに行くよう働きかける場合> 読書案内 引用文献 おわりに |