|
****************************************
Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録
三 新宿区の交通
1 日本鉄道、甲武鉄道と国鉄 top
官営鉄道の、新橋(現、汐留)−横浜(現、桜木町)間が開通したのは明治五年五月である。
そして日本鉄道会社線の上野−高崎−前橋間が開通したのは明治一七年八月である。
日本鉄道会社とは、明治一四年に岩倉具視(いわくらともみ)の斡旋によって、鉄道を全国に敷設するべく、まず東京より高崎および青森に至る鉄道を経営するのを目的に設立された会社である。
当時、明治政府は、新宿−横浜間の開通を機に、全国に鉄道を広げる計画を抱いていたが、明治一〇年の西南戦争による財政上の理由から鉄道の拡張に手が届かなかった。
そこで民間資本に頼らざるをえなかったのである。
政府が日本鉄道会社の設立を許可したのはそれなりの理由があった。
それは、岩倉具視などの華族や、豪農・豪商などからなる巨額な資本をもつ大規模な組織であったからである。
すでに開通している東海道、東北線と結ぶのに、赤羽(明治一六年七月開業)−品川(明治五年五月開業)を至急開通させる計画が立てられた。
明治一七年一月に工事は着手され、翌一八年三月一日には開通という、当時としては破天荒なスピードで完成した。
しかし、この工事には、沿線住民から反対の声があがった。それは次のような理由であった。
一、鉄道が敷けるとやがて電線が多くなるだろう、雀がそれにとまって穀物を荒らす(目黒)。
二、駅ができると宿場町がさびれる(品川、新宿、板橋)。
三、車の震動で稲のできが悪くなる。
四、外国の悪疫を運んでくる。
などである。
しかしともかく、後年の山手線の前身たるこの「品川線」(二六・一キロ)は開通した。一日三往復であった。
途中駅である新宿駅の所在地は南豊島郡角筈村。敷地は、一三二〇平方メートル、もと武家の下屋敷跡である。
この開通によって、翌一九年頃から、高崎地方と京浜地方の物資、主として生糸、米、鮮魚、雑貨などの輸送が活発になった。
明治二二年四月一日、今度は甲武鉄道会社線の新宿−立川間が開通し、同年八月には八王子まで延長された。
これが中央線の前身である。後年にいたり副都心の玄関となる新宿駅は、二つの線のターミナル駅となった。
甲武鉄道会社とは、当初は馬車鉄道敷設が目的で、横浜の商人岩田作兵衛らの発起で、明治一六年に出願されていた。
甲州街道沿いの産業の流通が目的であった。とくに八王子は、織物の町として人口二万を有していた。
開通当時の甲武鉄道の広告文には、
本路線は内藤新宿停車場において、日本鉄道会社の品川・赤羽間の路線につづきおれば上野又は新橋より乗車する本線に至るべし、
内藤新宿よりして品川にいで新橋・横浜間の汽車に乗り移るときは東海道に至るべく、赤羽にいでれば奥州、信州、両毛(りょうもう)、水戸などへも至るべくして交通もっとも自由なり(『新宿区立図書館紀要』豊多摩郡の内藤新宿)。
と、その利便ぶりをといている。
当初、路線は甲州街道沿いに計画されていたが、ここでも、鉄道が通ると宿場の客が減る、あるいは桑が枯れるなど沿線住民の反対があった。
青梅街道沿いの計画もあったが、同じ理由で反対された。
そこでやむなく、武蔵野の原生林のまん中を一直線に通したのである。これには地主も協力的であったという。
|

新宿駅の売店と売子(明治40年時代)
|
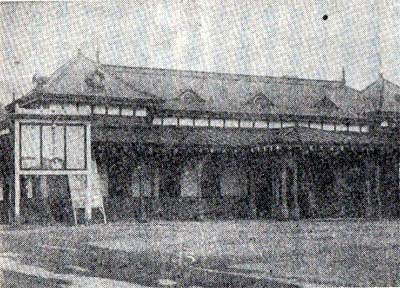 明治40年代の国鉄新宿駅 明治40年代の国鉄新宿駅
|
当時の甲武鉄道の「発着時刻表」を見てみよう。
下り列車の場合、新宿駅午前六時五二分発は、中野七時一分発、武蔵境七時二五分発、国分寺七時三六分発、立川七時四八分発で、八王子駅着は八時九分である。午前二本、午後二本の運転である。
次に運賃表を見ると、上等、中等、下等の三段階にわかれており、新宿−中野駅問は上九銭、中六銭、下三銭で、八王子までになると、上九〇銭、中六〇銭、下三〇銭である。八王子までは、当時の米の価格で換算すると、現在の一〇〇〇円ぐらいになる。
日本鉄道では、明治二六年から、距離に関係なく、一駅ごとに一等五銭、二等四銭、三等三銭とした。
ここで現在の山手線、中央線の、新宿区内と、隣接区および郡内の主要駅の開業時を列挙してみる。
上野
赤羽
池袋
目白
高田馬場
新大久保
新宿
代々木
原宿
渋谷
東京
神田
飯田橋
牛込
市ヶ谷
四ッ谷
信濃町
千駄ヶ谷
大久保
東中野
中野 |
明治一六年七月二八日
〃 一六年七月二八日
〃 三六年四月一日
〃 一八年三月一六日
〃 四三年九月一五日
大正三年一一月一五日
明治一八年三月一日(日鉄)
〃 二二年四月一一日(甲武)
〃 三九年一〇月二三日
〃 三九年一〇月三〇日
〃 一八年三月一日
大正三年一二月二〇日
〃 八年三月一日
昭和三年一一月五日
明治二七年一〇月九日(飯田橋開業と同時に廃駅)
〃 二八年三月六日
〃 二七年一〇月九日
〃 二七年一〇月九日
〃 三七年八月二一日
〃 二三年五月五日
〃 三九年六月一四日
明治二二年四月二一日 |
注=東京駅の開業は遅かった。さらに当初の秋葉原駅は貨物専用駅で、東京〜上野間の旅客の山の手線はさらに遅く、ここには記されていない。
東海道線と東北線の接続は、赤羽−新宿−品川のルートが先にできた。
明治三〇年代の新宿駅はどんな様子だったろうか。駅前の餅菓子屋で生まれた古老の談話を要約すると、
駅舎は北側の青梅街道よりにあった。木造で、改札口は一ヵ所で東を向いていた。
南側は貨物の集積所。
駅構内で田中、中島の二人が売子五、六人を使って中売りをやっていたが、父の饅頭が評判がよくて中売りの商品の一つに加えられた。
卸し値が一個一銭二厘で、小売りは二銭となる。これを直接手づかみで渡し、その手で金を受取っていた。
日露戦争の初めには東北から来たのだろうか、屋根に白く雪をのせた列車が陸軍の兵士を満載して来て、新宿駅で休み、町中の人が日の丸の小旗でその出征を送ったものだった。
また戦争の終り頃には、満洲から習志野(ならしの)の俘虜収容所に送られる露軍の兵士をみようと、大勢の人が集まったこともあった。
一汽車乗り遅れると、二、三時間は待たなければならない。
八王子や甲府に行く人は、次の列車が来るまで駅前の茶店で休む。
茶店には、その頃流行の赤毛布を敷いた縁台があって、そこで茶をのみ、菓子をつまんで待つ。
初夏の頃など昼寝している人もいた。
青梅街道と鉄道線路は平面交差だった(現在の地下道の位置にあたる)。たびたび事故があった。
踏切り番は、列車が通過する度毎に縄を引いて人や車を止めるが、時にはしめ遅れたり、無理に渡ろうとして事故を起した。
一日に汽車が五、六回しか通らなかったのだけど、事故が多かった。 |
甲武鉄道が、市街線として、市街地に乗入れて牛込駅まで延伸したのは明治二七年一〇月九日である。
前年の七月から着工したのであるが、当初の路線の計画は、新宿−坂町−市ヶ谷東村町−飯田町(現在貨物駅)であったが、用地買収が困難をきわめたため、人家の少ない千駄ヶ谷−信濃町−外堀に変更した。
それでも難問があった。まず、地形的に信濃町−四ッ谷間にトンネルを掘る必要が生じた。
ところがトンネルは現在の迎賓館、当時の赤坂御所の敷地の一部にかかるため、皇室に対し恐れ多いと問題になった。
しかし、明治天皇の、社会公衆のためなら、というお言葉で許可になったという。
このトンネルの正式の名称を御所隧道という。長さ二八九・六メートルである。
また、新宿御苑の南端を通過するが、車の音で鴨猟ができなくなるとか、外堀の土手を切り崩されては松並木が失われるという東京府の反対もあったのである。
明治三九年、「鉄道国有法」が公布され、一七の私設鉄道が翌四〇年までに買収された。
日本鉄道、甲武鉄道は三九年に国鉄となった。
明治四四年四月にできた「中央線鉄道唱歌」(作詩=福山寿久、作曲=福井直秋) のうち一〜四番まで紹介する。
一、霞たなびく大内や
御濠にうかぶ松の影
栄行く御代の安らけく
列車は出づる「飯田町」
二、花かぐはしき靖国の
やしろ間近き「牛込」の
牛の歩みも遅からで
「市ヶ谷」見付「四ッ谷」駅 |
三、東宮御所の壮観を
仰げばやがて「信濃町」
朝露清き練兵場
響く喇叭(ラッパ)の音高し
四、都を後に見かへりて
甲州街道「新宿」や
又行く春に「大久保」の
つつじの園ぞ美しき |
2 私鉄 top
京王線
京王帝都電鉄の前身である「京王電気軌道株式会社」が創設されたのは、明治四三年九月である。
新宿−八王子間を結ぼうというもので、すでに甲武鉄道会社によって敷かれていたが、京王線
の場合は甲州街道に沿い、分倍河原で多摩川を渡って八王子に至る路線であった。
それは、沿線の開発、町づくりを目的としたものであった。
鉄道敷設に着手したのは、明治四五年六月であった。
明治四〇年二月に、北多摩郡千歳村粕谷(世田谷区粕谷)に居を構えて、晴耕雨読の思索的生活を始めた徳富薦花は、『みみずのたわごと』(大正二年刊)の中で、
京王電鉄ができて地価が騰貴した、東京人が入り込む、要するに東京が日々攻め寄せる。
新宿八王子間の電車はわしの居村から調布まで鉄線を敷き始めた。
トンカンという鉄の響きが、近来警鐘の如くわしの耳にとどろく。
これは早晩わしをこの巣から追い立てる退去令の先触れではあるまいか。
電車が開通したらここにとどまるか、東京に帰るか、あるいは文明をのがれて山に入るか、今日において解き得ぬ疑問である。 |
と述べている。
大正二年四月、まず笹塚−調布駅間が最初に開通し、新宿へ延びたのは同四年五月である。
小田急線と西武線
昭和二年四月、新宿−小田原間の小田急線と高田馬場−東村山間の西武線が開通した。
小田急線は、当初、箱根などへの観光線が主目的であったが、関東大震災後の人口の西郊部移住に伴う田園開発という時流に乗りえたのである。
沿線の住民としては、東京との往復が日帰りでできるというのは福音であったが、一部農民のうちには、百姓に電車はいらぬ、若者が都会で身を滅ぼすなどの反対意見もあったという。
初めの頃は経営も苦しく、二年間、社員の昇給ストップといった苦境の時期もあった。
開通一二月後、西条八十作詞の「東京行進曲」に歌い込まれた。
シネマ見ましよか お茶のみましょか
いっそ小田急で 逃げましょか
変る新宿 あの武蔵野の
月もデパートの 屋根に出る |
西武鉄道の前身である武蔵野鉄道が、最初に営業したのは大正四年四月、池袋−飯能(はんのう)間である。
昭和七年、東京市が三五区となった時、朝日新聞付録の「大東京大観」に、文化村、翠丘住宅地などは良住宅地として著名である。
土地が高燥(こうそう)で展望が開け、省線目白駅の便や西武電車が町内を縦貫し、将来町の西北部に新たな交通機関でも出来れば、ますますインテリ層の集団地区として発展するだろうと、交通の便による土地の開発に注目している。
落合町の発展を決定的にしたのは、西武佚道の開通であった。
高田馬場駅から、新宿へ乗入れたのは、昭和二七年三月である。
top
****************************************
|

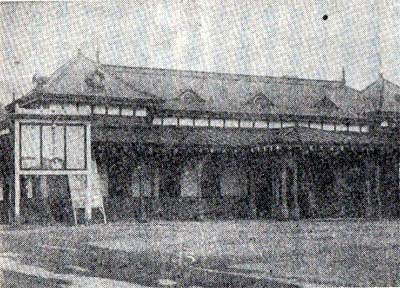 明治40年代の国鉄新宿駅
明治40年代の国鉄新宿駅