|
|
|
|
![]()
栄冠は地味に輝く。
この作品のメインタイトルは「Tuvayhun」ですが、これはアラム語で、「幸いである」という意味なのだそうです。それは、実際は新約聖書のマタイ福音書の中の第5章の有名な「山上の垂訓」と呼ばれるシーンで、この言葉で始まる第3節から第10節の、いわゆる「8つの教え」という8つのフレーズとなって語られています。それを、ここでは、その8曲をシリア出身のヴォーカリスト、ムハンマド・アル=マジャブが、このアラム語のテキストを、おそらく楽譜には書き表されてはいない民族的な歌いまわしで歌って(語って)いるのです。それは、まるでバッハなどの受難曲でのエヴァンゲリストによるレシタティーヴォのように感じられます。 そして、この作品のサブタイトルが「傷ついた世界のための『8つの教え』」です。これは、そんな「語り」の後に続いて、その「教え」にリンクして、「傷ついた現代社会」を表現したアメリカの詩人チャールズ・アンソニー・シルヴェストリによるリリックが、こちらは西洋的な記譜によるソロや合唱によって歌われます。もちろん、それらは受難曲でのアリアやコラールにしっかり呼応しているのではないでしょうか。 まずは、オープニングの「教え」から、BD-Aならではのとびっきりのハイレゾ・サラウンド・サウンドが堪能できます(例によって、同梱のSACDでは、それがすべての面でワンランク下がっているのが、悲しいですね)。そこで、リアに定位しているストリングスと打楽器の中の、ドラの超低音が響く中からチューブラー・ベルと?のような音が聴こえてくるのはものすごくリアルです。これは、この先に7回続く「教え」でも、基本的に同じ打楽器によるパターンが演奏されます。それを聴いていると、なんだかどこかで聴いたことがあるような気がしてきました。記憶をたどってみると、それはメシアンの大作「我らの主イエス・キリストの変容(La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ)」の冒頭、さらにはその後に何度も出てくる「福音書朗読」の部分と非常によく似た音楽であることに気づきました。その使い方もほぼ同じ、こうなるとほとんど「パクリ」の領域ですね。 あとは、とてもキャッチーなメロディが何度も出てくるのですが、それがスメタナの「モルダウ」に聴こえてしまうのは、なぜでしょう。ゴリホフみたいなダンスも登場しますし。 まあ、そのあたりは、この作曲家のそもそものスタンスなのですから、それほど気にすることはありません。そんな、甚だしくオリジナリティに欠ける音楽でも、ここでのミュージシャンたちは最高の演奏で楽しませてくれていましたから。なんと言っても、ソロから全員の合唱(左右とフロントを囲んで聴こえてきます)までを担当している合唱団の素晴らしさは絶品です。 そして、「フルート」とクレジットされている楽器を演奏しているのがこの人ですが、彼の楽器はこういうものでした。   SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |
||||||
もちろん、これはヤンソンス自身の歩んできた道を改めて展望するというとても興味深いものですが、それだけではなく、彼にかかわった周りの人たち、オーケストラのメンバーとか、あるいは行政関係の人たちといった人間の姿なども、ここではくっきりと浮き上がってきます。ですから、ヤンソンスが新しいコンサートホールをミュンヘンに作ろうとした熱意と、それにまともに取り合わなかった人々たちへの怒りが語られるあたりは、とても心に響きます。 そして、まるでドラマのように面白いのが、数年前のベルリン・フィルでの出来事についての裏話です。その時は、ラトルの次の指揮者を決めるための団員投票が行われることになっていたのに、その日の数日前に、候補者の最右翼と見られていたヤンソンスが突然バイエルン放送交響楽団との任期を延長することを発表したために、結局そこでは結論を出すことが出来なくなっていたのでしたね。その時、陰で何が行われていたかが、ここでは克明に語られています。あれは、ベルリン・フィルとバイエルン放響との間の駆け引きだったのですね。ついでに、前任者のラトルの正体までも暴露されていて、やはり、と思わされます。 ただ、今回の日本語訳に関しては、少なからぬ不満が湧いてきます。この小山田という人は、以前もこちらで、タイトルについて顰蹙を買っていましたが、今回も同じような、ちょっと理解できないことをやっているのです。ここでは「すべては音楽のために」となっているこの本のサブタイトルは、オリジナルでは「Ein leidenschaftliches Leben für die Musik」ですから、直訳すれば「音楽のための情熱的な人生」とでもなるのでしょうか。ただ、ここにはちょっとした「仕掛け」があります。ドイツ語の「leidenschaftlich」という形容詞は、単なる「情熱的」という単語ではなく、楽譜の中で使われる「音楽用語」でもあるのです。つまり、普通はイタリア語で「Appassionato」と書くべきところに、マーラーあたりはこのドイツ語を使っているのですよ。そういう含蓄が、この訳語からは、全く消え去っているのですね。 ですから、最初に驚かされるのが、ヤンソンスの父親の名前の呼び方です。翻訳者は、「アルヴィド・ヤンソンス」という表記で長いこと呼ばれていたそのファースト・ネームを、生国のラトビアの言語に忠実に「アルヴィーツ」と表記していたのです。最近ではエストニアの都市の名前などでも、きっちり母国語で表記するという流れになっていますから、これ自体は何の問題もないのですが、それに関しての直接のコメントが全くないというのは、困ったものです。ナンセンスです。と言うのもこの訳者(もしかしたら編集者)は、文中の音楽関係の単語に関しては、不必要だと思われるものにまでいちいち詳細な注釈を与えていますから、こんな重要なことでしたら当然その注釈があってしかるべきだな、と思ってしまいます。 もう一つ、やはり注釈がついていないのが「歴史考証型」という言葉です。普通は「ピリオド・アプローチ」とか「HIP」という、もっと知られている言葉に言い換えるのではないでしょうか。さらに「ザルツブルク祝祭」ですから、もう信じられません。 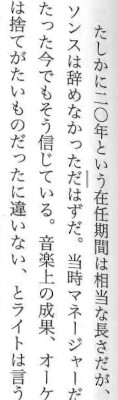 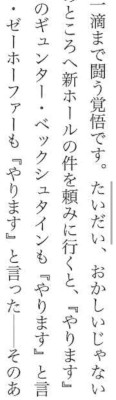 Book Artwork © Shunjusha Publishing Company |
||||||
テテルマンはその中のアリアを、2021年の11月に先ほどのアルバムで録音していたのですが、同じ年の3月に、ベルリン・ドイツ・オペラで実際に演じていて、そのBDとDVDもすでにリリースされていたというので、早速BDを購入して、「動く」テテルマンを見てみることにしました。 タイトルロールのフランチェスカは貴族の娘、そこに、政略結婚で別の貴族の長男との結婚話が持ち上がりますが、その長男のジョヴァンニというのがかなりのブ男なので、周囲の人間は一計を案じて、とてもイケメンの次男のパオロをまずフランチェスカに会わせて、彼が結婚相手だと思わせ、結婚契約書にサインさせます。ですから、フランチェスカは、結婚してもジョヴァンニは遠ざけ、パオロにも騙されたと思って、やはり会うことは避けていました。しかし、心の奥ではパオロを思う気持ちは強まるばかり、それはパオロも同じだったので、二人はついに「一線を越えて」しまったのです。それを知ったのが、パオロの弟のマラテスティーノです。彼もフランチェスカに思いを寄せていたので、その秘密を守る代わりに、「やらせてくんね?」と彼女に持ち掛けます。もちろん、相手にもされなかったので、ジョヴァンニに密告し、恋人たちの密会の現場を押さえ、ジョヴァンニは二人とも刺し殺します。 そんな、いかにも「ヴェリズモ」といったプロットですが、その音楽はプッチーニの流れをくんで、それをさらに壮大でカラフルにしたオーケストレーションを聴かせてくれています。途中でアルト・フルートのような音が聴こえてきたのですが、ちょっと違うような気がしたので楽譜を見てみたら、それは何と「バス・フルート」でした。  もちろん、テテルマンはパオロを演じています。そのパオロが最初に登場する場面の音楽がものすごいことになっていて、長い時間をかけて「来るぞ、来るぞ」と思わせておいて、いきなりクライマックスとなった時に颯爽と登場するのです。ですから、そこで例えばパヴァロッティなんかが出てきたりしたらブーイングの嵐でしょうが、テテルマンは、いかにもその音楽にふさわしい凛々しさと美しさを持っていました。演技も、とても細かいことまで考えながら、それをさりげなく演じる、という、目配りがきいたものでした。客商売ですから(それは「ホテルマン」)。そこにあの声が加わるのですから、これはもう文句なしの大スターです。 何よりも、濡れ場で半裸になった時のスタイルの良いこと。カウフマンでさえ、最近は少しぶよぶよになってきてますからね。 他のキャストも粒ぞろいでした。フランチェスカ役のサラ・ヤクビアクも、スタイルは抜群、最近バイロイトの中継映像でとんでもないデブ(さらに音痴)のブリュンヒルデを見たばかりだったので、その違いは際立ってます。もちろん、声も素晴らしいですし。さらに、端役の侍女たちまで、みんなソリスト級の素晴らしい声なのにも驚きました。 演出は、お決まりの現代への読み替えですが、そのメリットは全く感じられませんでした。そもそも、舞台装置が全く変わらないというのが、ちょっと問題です。フランチェスカはいったい今どこにいるの? と思ってしまいましたからね。 BD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |
||||||
現在では、ヨーロッパを中心に各地のオペラハウスで大活躍をしているテノールのホープです。何よりも、このジャケット写真に見られるいかにもラテン系という濃い顔立ちは、ステージ映えすることでしょうね。 最初に歌われていたのは、ポンキエッリのオペラ「ジョコンダ」からの「空と海!(Cielo e mar! )」というアリアです。正直、「ジョコンダ」と言えば「時の踊り」しか聴いたことがありませんでしたから、これは全く初めて聴く曲でした。しかし、そんな曲でも、テテルマンの声は、まるで何度も聴いたことのあるような親しみやすさを与えてくれました。それは、彼の声そのものが持っている魅力によるものです。彼の声には、あのヨナス・カウフマンのようなとても強靭な力があるのですが、その上に見事に磨き抜かれた音色と、繊細さがあるのですよ。そのカウフマンがこういう曲を歌う時には、常に「泣き」が入っていたものですが、テテルマンの場合はそんな小細工を弄さなくとも自然と悲しげな情感も出てきています。 正直なところ、カウフマンはドイツ物では完璧に思えていたものが、イタリア物になると、なにかちょっとした違和感がありました。というより、最近ではあまりにもレパートリーを広げすぎた結果、かつては確かに有った一途さのようなものが、どんどん希薄になっていくように思えてしまいます。 そんな時に現れたのが、このテテルマンです。彼は、カウフマンのような張りのある声を持ちつつ、そこからイタリア・オペラならではの叙情性をごく自然に発散させていたのです。 もう少し聴いていくと、ビゼーの「カルメン」からの「お前が投げたこの花は(La fleur que tu m'avais jetée)」という、超有名曲が出てきました。その曲を歌い始めた途端、テテルマンの声は、瞬時に「イタリア・モード」から「フランス・モード」に変わったのです。それは、音色、ダイナミズム、ディクションと、すべての面での完璧なシフトチェンジでした。 この頃になってくると、バックを務めるスペイン沖のほとんどアフリカに近いグラン・カナリア島にあるこのオーケストラの素晴らしさにも気づかされるようになってきます。なんと言っても、歌手にぴったり寄り添ったうえで、とても生き生きしたリズムを醸し出しているのがとても好感が持てます。ヴェルディの曲になると、そこでは今まではちょっと陳腐に感じていたこの作曲家特有の伴奏形から、とてつもないグルーヴを生み出していたのです。こんな、体が自然に動いてしまうようなヴェルディなんて、なかなか聴くことは出来ませんよ。 最後の曲は、そのヴェルディの「トロヴァトーレ」から、第3幕の幕切れの「見よ、恐ろしい炎を(Di quella pira)」です。このアリアは、オリジナルの楽譜ではテノールのソロは高音のGで終わり、そのあとにオーケストラだけのアウトロがあって幕が下りるようになっているのですが、慣習的に、そのGをハイCに上げて、オーケストラと一緒にそのまま延々と伸ばし、最後のフェルマータも存分に伸ばして大見得を切る、というやり方がとられています。ただ、あのパヴァロッティなども、録音ではしっかりハイCを出していますが、ネットではライブで半音下げて歌っている映像などを見ることもできるぐらい、リスキーなところなんですね。ウィスキーでも飲まないと、怖くて歌えないとか。 もちろん、ここでのテテルマンのハイCは、何のストレスもなく、余裕たっぷりでとても美しく歌われていましたよ。 モーツァルトなども、彼の歌でぜひ聴いてみたいですね。でも、ワーグナーまで歌おうというような色気は、出さないでくださいね。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |
||||||
このレーベルは、サラウンド再生が可能なハイブリッドSACDを専門にリリースすることが、当初のスタンスでした。SACDは、PHILIPS(レーベルの親会社)とSONYによって1999年に開発されたフォーマットですから、そのスペックをフルに活用できるようなメディアを目指したのでしょう。そこでまず彼らは、PHILIPSレーベルが1970年代に録音したものの、当時はいまいちパッとしなかった大量の「4チャンネル」のソースを、ハイブリッドSACDによって「サラウンド」として現代によみがえらせる、という画期的なプロジェクトを始めたのです。しばらくすると、同じUNIVERSALの系列となっていたDGの、やはり4チャンネルで録音されたものの日の目を見なかったカタログもSACD化され、世界中のほとんどの人にとっては初めてサラウンド体験を提供したのです。もちろん、新しい録音も行い、それらはすべてSACDでリリースされていたのでした。 ところが、そのSACDはメジャーレーベルからはそっぽを向かれ、リスナーにもいまいち支持されませんでした。そうこうしているうちにインターネット経由での音源の享受、という新しいメディアが爆発的に広がったことによって、そもそもCD自体が凋落への道を歩み始めていたのです。そんな中では、このレーベルもいつまでもSACDにこだわることはできなくなり、何の変哲もないCDのみのリリースに方針を変更せざるをえませんでした。 今回のアルバムは、2014年という、まだ当初のポリシーを貫けていた時代にリマスタリングが行われてリリースされた、1977年に録音されたDGの4チャンネル音源によるサラウンドSACDです。最初に出た時のLPのジャケットが、これです。  ところが、SACDを聴いてみると、そこにはDGのサウンドには必ずあった骨太なところが全くありませんでした。そこにあったのは、あくまでソフトで華麗な弦楽器の響きと、その豊饒さの中でちょっと居心地悪そうにしている管楽器の姿でした。これは、紛れもない、PHILIPSのサウンドではありませんか。いったいどんな技を使ったのかは分かりませんが、POLYHIYMNIAのエンジニアたちは、リマスタリングによって見事にDGの音をPHILIPSの音に変えてしまっていたのです。 現在では、たとえモダン楽器であっても、バッハのこの作品を演奏する時にはトゥッティでも少人数、場合によっては1パートは1人だけ、というやり方がほぼ定着しています。しかし、この時代、ズーカーマンたちのアンサンブルでは、弦楽器のトゥッティにはかなりの人数が用意されていたのではないでしょうか。それが、この華麗なサウンド、さらにはとても広がりのある音場定位によって再生されていますから、アダージョ楽章などはまさにとろけるように甘美な、それこそマントバ―二やポール・モーリアのようなゴージャスなサウンドが押し寄せてくるように感じられます。確かにこれは、あの頃の「バロック音楽」の典型的な姿でした。それが、現在ではもう少し角があって挑戦的なものが「正しい」バロック音楽だ、とされています。もはや顧みられなくなったサウンドだからこそ、懐かしさとともに、それはとても貴重なものとして聴こえてきます。 「5番」などでのフルート・ソロは、当時のLAフィルの首席奏者だったアン・ディーナー・ジャイルズです。アイドルだったのかも(それは「ジャニーズ」)。彼女の音は、見事にこの華麗さの中に溶け込んでいます。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
もちろん、それら以上に星の数ほどもあるマイナー・レーベルも、とても充実していますから、まず、普通に流通しているレーベルのものは聴くことができます。しかし、ここでも、このページではよく登場している2つの重要なマイナー・レーベルが参加していません。それはCOVIELLOとHYPERIONです。とりあえず、この2つがここに加われば、NMLはもう少し契約者数を伸ばすことができるのではないでしょうか。 ですから、HYPERIONレーベルからかなりの頻度でCDをリリースしてきている「ジェズアルド・シックス」というヴォーカル・アンサンブルを実際に聴いてみたいと思って、やむなくCDを購入しました。正直、サラウンド対応のハイブリッドSACDはサブスクでは聴くことができませんから欲しいものは購入していますが、普通のCDはよっぽどのことがなければサブスクで十分に楽しめますから、まず買いたくはありませんけどね。 このアンサンブルは、その名前の通り6人のメンバーから成るアンサンブルです。メンバーは全員男声、パートはカウンターテナーが2人、テナーが2人、ベースが2人です。作曲家としても多くの作品を世に送っているオワイン・パークによってロンドンの有名な合唱団のメンバーが集められ2014年に結成されました。彼は一応指揮者となっていますが、メンバーの中に入って歌う(パートはベース)こともありますから、実質的には7人編成のアンサンブル、ということになります。 同じようなサイズで、やはり男声だけのイギリスのアンサンブルというと、あの「キングズ・シンガーズ」が有名ですね。実際に、このジェズアルド・シックスの創設メンバーだったカウンターテナーのパトリック・ダナヒーは、2年後にはキングズ・シンガーズに移籍して、現在に至っていますからね。さらに、現在のメンバーも、すでにそのうちの5人は途中からの参加者ですから、結構メンバーチェンジは激しいようですね。というか、例えば日本の男声カルテットの「ダーク・ダックス」のように、あくまでオリジナルメンバーで続けるのだ、というようなポリシーはさらさらなく、それこそキングズ・シンガーズのように適宜メンバーを入れ替えて活動を継続させていく、というやり方なのでしょう。 ただ、キングズ・シンガーズとの一番の違いは、これまでのアルバムでのラインナップを見る限り、あくまでクラシック、というか、シリアル・ミュージックにこだわったスタンスなのではないでしょうか。もちろん、仏教音楽もありませんし(それは「数珠あるど」)、4ビートもありません(それは「ジャズあるど」。あちらがエンタテインメントをたっぷり盛り込んだ「明るい」アンサンブルだとすると、こちらは「暗くて真面目」なアンサンブル、でしょうか。 今回のアルバムは、タイトルからして「レクイエム」の中のテキスト「Lux aeterna」という、「永遠の光で、彼ら(死者)を照らしたまえ」というものですから、エンタテインメントの要素など全くありません。 とは言っても、ルネサンスから現代までの作曲家たちの、そのようなコンセプトの曲を、それぞれのスタイルでしっかり歌い上げることによって、音楽の持つ「力」をまざまざと感じさせる、という点では、エンタメとは別の意味での大きな喜びを与えられアルバムでした。ここでの現代の作曲家たちは、あるものは中世への回帰、あるものはミニマル・ミュージックへの傾倒と、さまざまな模索を試みていますが、パーク自身が作った「Sequence:In Parenthesis」という最も長い曲には、「コラージュ」と「サンプリング」が用いられていました。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |
||||||
このBRILLIANTというレーベルは、他のレーベルで「型落ち」したもののライセンスをとってリリースしていることが多いようですが、これはおそらく最初からこのレーベルから出ていたものでしょう。指揮者のニコル・マットという名前も、このレーベルでたびたび目にしたことがありました。 合唱団はヨーロッパ室内合唱団。1997年にそのマットを指揮者に迎えて創設された「ノルディック室内合唱団」が、2002年に今の名前に変わったという団体です。ですから、正確には、この「レクイエム」を録音した時はまだ「ノルディック」だったのですね。いずれにしても、ヨーロッパ中からプロも含めた優れた歌手たちを集めて作られている合唱団です。 ここで使われている楽譜は、ジュスマイヤー版でした。このころはすでにそれ以外の「新しい」楽譜が出そろっていましたから、選択肢はたくさんある中であえてジュスマイヤー版を採用した、ということなのでしょう。 そのジュスマイヤー版は、新モーツァルト全集の一環でベーレンライターから出版され、その青い表紙のヴォーカル・スコアは、今でも合唱団にとっては最も信頼のおけるエディションとして広く使われています。最近になって、そのベーレンライターから「オシュトリーガ版」という、全く新しい補筆稿が出版されて、ちょっとした話題になっています。なんでも、来年の3月にはその楽譜を使ったコンサートが地元でも行われるのだそうですね。 実際にその楽譜を見てみましたが、ジュスマイヤー版とは全然違っていました。とは言っても、それはこれまで出ていた他の補筆稿を押しのけてまでの優位点はないような気もします。ただ、何かがあるとすれば、それはベーレンライターが出した、という点ではないでしょうか。何しろ、装丁を見るとヴォーカル・スコアの色はジュスマイヤー版そっくりです。もしかしたら、もうジュスマイヤー版は見限って、こちらに一本化するという目論見なのかもしれません。 先ほどの地元の合唱団ではありませんが、ここしばらくはこのオシュトリーガ版で演奏することが「ブーム」になっていくのかもしれませんね。でも、ブームというものは必ず廃れる運命にあるものなのですけどね。スタレビは廃れませんが。 マットの演奏は、ジュスマイヤー版を、何の衒いもなく淡々と音にした、という感じでしょうか。まずは、合唱がかなりハイレベルであることがうかがえます。ベースあたりはちょっとソリストっぽい声が聴こえてくることがありますが、それが全体に悪影響を与えているほどのものではありません。のびのびとした声のテナーを中心に、とてもきれいなハーモニーを聴かせてくれています。「Agnus Dei」での細やかな表現力はまさに絶品です。 ソリストでは、「Tuba mirum」で最初に出てくるバスの人が、とても軽めのほとんどハイ・バリトンという音色で、心地よい印象を与えてくれます。それに続くテノールもとても素直で、甘ささえ感じる魅力的な声、アルトも張りのある声で存在感を誇っています。最後に入ってくるソプラノが、声を出す瞬間にちょっと変な歌い方になっていましたが、これはおそらく編集ミスなのではないでしょうか。彼女も柔らかい声が魅力的です。ですから、そんな4人が揃ったアンサンブルは、なかなかのものでした。 ただ、ソプラノの人はときおり不安定なところがあって、そのビブラートの深さがちょっと邪魔に感じられることもありますかね。 オーケストラはモダン楽器の団体ですが、さりげなくピリオド寄りの演奏を取り入れているあたりに、好感が持てました。肩ひじを張らずに、存分にモーツァルトの魅力を伝えてくれる、爽やかなアルバムでした。 Album Artwork © Brilliant Classics |
||||||
とは言っても、ご存じの通り、かつてはこのオーケストラは、もっぱらこのようなサウンドトラックを録音するために活動していて、なんでも300本以上の映画のための音楽を録音していたのだそうですから、別に意外でもないのかも。 ただ、現在の団体は、そんなオーケストラの名前だけを受け継いで、全く新たに世界中からメンバーを集めて作られた、言ってみれば「昔の」オーケストラとは縁もゆかりもないオーケストラですし、さらに、彼らの本拠地はその名の通りロンドンですが、ここで演奏されているのはハリウッド、つまりアメリカで作られた映画のためのサウンドトラックですからね。最近でこそ、ハリウッドで作られる映画でも、音楽だけはヨーロッパ、例えばロンドン交響楽団あたりが録音することも珍しくはありませんが、ここで取り上げられている映画が作られた20世紀前半には、映画のスタジオはしっかりオーケストラを用意して(メンバーはフリーランスの腕利きの人たちなのでしょうね)、映画のための音楽を日常的に「量産」していました。 このアルバムのジャケットには、そんな録音の様子がうかがえる写真が使われていますね。これは、1930年代後半にワーナー・ブラザーズのスタジオ・オーケストラが、エーリヒ・コルンゴルトの指揮で録音を行っているところなのだそうです。  クレジットを見ると、このオーケストレーションを行ったのはコルンゴルトではなく、ヒューゴー・フリードホーファーとミラン・ローダーという専門の「オーケストレーター」だったことが分かります。この時代から、しっかり分業制が敷かれていたのですね。その「伝統」は現在も続いていて、あのジョン・ウィリアムズも専門のオーケストレーターを抱えていることはよく知られていますね。 この曲は、ちょっとバージョンは違いますが、以前アンドレ・プレヴィンの指揮による録音で聴いていました(そこにも、先ほどのオーケストレーターたちと同じクレジットがありました)。それを改めて聴きなおしてみると、自らもハリウッドの「現場」で長らく仕事をしていたプレヴィンが奏でる音楽は、なにかノスタルジックで、まさに古き良き時代を彷彿とさせるもののように感じられました。 それを聴いた後で、このウィルソンの演奏を聴くと、そこにはそんな郷愁のようなものは微塵も見られない、とても精緻でキラキラに輝く世界が広がっていました。彼らがやろうとしていたのは、ですから、古のハリウッドのサウンドの再現ではなく、まさに21世紀ならではのヴァージョン・アップされたハリウッドだったのです。 例えば、「オズの魔法使い(The Wizard of Oz)」の音楽にしても、かつて見たパートカラーの映画から聴こえてきたローファイ感あふれるおずおずとしたしょぼいサウンドではなく、まさに4K、8Kの世界でこそ聴こえてきてほしいハイレゾでイマーシヴな「Over the Rainbow」だったのです。 最後のトラックの「百万長者と結婚する方法(How to Marry a Millionaire)」では、「スターウォーズ」とそっくりなフレーズが最初に聴こえてきて、びっくりしました。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |
||||||
彼は1723年にドイツのケーテンに生まれました。彼の父親はケーテンの宮廷楽団のチェロとヴィオールの奏者でしたが、当時の楽長が、あのヨハン・セバスティアン・バッハだったのです。この二人は良き友人同士でもありました。しかし、バッハはアーベルが生まれた翌年には、ライプツィヒに「転勤」してしまいますね。その後、1737年に父親のクリスティアン・フリードリヒ・アーベルが亡くなってしまうので、息子のアーベルはライプツィヒのバッハの元に引き取られ、バッハその人から作曲、さらにはヴィオラ・ダ・ガンバの演奏法も学ぶのです。その頃には、バッハの末の息子のヨハン・クリスティアン・バッハも生まれていました。 そのヨハン・クリスティアンも作曲家として身を立て、1762年にはロンドンに移住し、それ以来彼はイギリスで最も有名な作曲家となりました。アーベルは、1763年にロンドンへ赴き、そこでヨハン・クリスティアンと同じ家に住み、翌年からは、この二人によって先ほどの「バッハ・アーベル・コンサート」が開催されることになるのです。彼もまた、作曲家、あるいはヴィオラ・ダ・ガンバ奏者として幅広い人気を誇っていました。幼いモーツァルトがロンドンを訪れた時にも、彼はこの人気作曲家の交響曲を勉強のために写譜していたのです。 今回のアルバムで演奏されているアーベルのヴィオラ・ダ・ガンバのための作品は、このコンサートがピークを迎えた頃、1770年代に作られたものです。 メインとなっているのは、ヴィオラ・ダ・ガンバと通奏低音による6つのソナタです。ただ、「ソナタ」とは言っても、その構成はかなりシンプルで、技術的にもそれほど高度なものは要求されない作品ばかりですから、おそらく腕に覚えのあるアマチュアのために作られたものなのではないでしょうか。とは言っても、アーベルはしっかりとその中に、自らの作曲家としてのスキルを最大限注ぎ込み、演奏するものにとっても、そして聴く者にとっても十分な喜びが与えられるような作品に仕上げています。そんな、ある意味シンプルな曲調に合わせるかのように、ここでは、低音がテオルボ(低音用のリュート)によって演奏されています。 これらのソナタは、いずれもよく似た形に仕上がっています。それぞれ楽章は3つ、第1楽章はアレグロやヴィヴァーチェの速いテンポ、第2楽章はアダージョなどのゆっくりしたテンポ、そして第3楽章はメヌエットで、3拍子のかわいらしい舞曲になっています。 これらは、出版もされていたのでしょうが、それとともに演奏されているヴィオラ・ダ・ガンバのソロによる4つの小曲は、写本として残されたものです。これが、先ほどのソナタとは打って変わって、超絶技巧が必要とされる難曲になっているのです。ソナタでは単旋律を弾くだけでよかったのですが、こちらでは2声部以上のパートを1台の楽器で演奏するように作られているのです。これはもう、ガンビストの腕の見せ所、ここで演奏しているイタリアの有名な奏者、マルコ・カソナートは、いったいどんな指使いをしているのか分からないほど自然に、それぞれのパートをきっちりと浮き上がらせていました。 その最後の曲にはタイトルが付けられていないのですが、聴けばそれがモーツァルトのオペラ「魔笛」で歌われるザラストロのアリア「In diesen heilig'n Hallen」であることがすぐ分かります。モーツァルトがこれを作ったのは、アーベルの曲が出来てから20年ほど経ってからです。これはいったい・・・? CD Artwork © Brilliant Classics |
||||||
ですから、最後に残ったのは、全部で8つある交響曲の最後の2つですから、当然「7番」と「8番」という現在の音楽業界では完全に定着した表記がジャケットに見られるはずですが、ここでは「Unfinished & Great Symphonies」ですって。これはもちろん、いまだにこの2曲を「8番」、「9番」と呼ぶ習慣が音楽レーベルの中には根強く残っているものですから、なんとかそれを避けるための苦肉の策なのでしょう。ですから、このアルバムのジャケットやブックレットには、どこにも「No.8」とか「No.9」という表記はありません。 ところが、そんな配慮には全くお構いなしに、これを日本で販売している代理店(キングインターナショナル)はインフォではしっかり「8番」、「9番」を使っているのですから、何にもなりません。さらに、SPOTIFYやNMLでもこうですから、根は深いですね。というか、不快ですね。  まあ、それらは、異様に長いヤーコブス自身による曲目のアナリーゼ(35ページもあり、読む気にもなりません)とともに、曲を聴く上では何の役にも立ちません。これまでに出ていた彼のシューベルトの交響曲を聴く限り、彼はこのジャンルの指揮をするにはあまりに経験不足なのでは、という感が付いて回ったのですが、今回そんな策を弄したことによって、果たしてその印象をぬぐい去ることはできるのでしょうか。 まず「未完成」では、冒頭のコントラバスとチェロによる重低音には圧倒され、続く弦楽器のフレーズもとても神秘的だったので、そこにどんな風にテーマが歌われるのか期待していると、オーボエとクラリネットのユニゾンで出てきたそのテーマがとんでもないピッチだったのには思わずのけぞってしまいました。 次の楽章になると、そのあまりのテンポの速さには唖然とさせられます。一体、この指揮者はシューベルトの歌心を表現しようとする気があるのだろうか、とさえ思ってしまいます。 「グレート交響曲」はもっとひどいですよ。そもそも、ど頭で聴こえてくるホルンソロのお粗末なこと、音はブツブツ切れるし、味も素っ気もありません。 第2楽章になると、テンポが目まぐるしく変わるのがとても気になってしまいます。この楽章は途中でテンポを変えるという指示は一切ないのですが、ヤーコブスはそれを逆手にとって、もう好き放題にテンポを変えているのですね。もっとも、普通にイン・テンポで演奏すると眠くなってしまいますから(ベームとウィーン・フィルを生で聴いた時には、本当にここで寝てしまいました)、それを避けるには親切な配慮ではありますね。 3楽章などは、スケルツォが何とももったりとしたテンポで始まったのですが、トリオが終わった後の繰り返しでは、ものすごい速さに豹変してました。ただ、それが次第に遅くなっていくんですよ。これは、単にテンポのコントロールができていなかっただけなのでしょう。終楽章でも、テンポは出たとこ勝負です。 もちろん、これはサブスクで聴いたので寛容に受け止められましたが、CDを買ってたりしたら、叩き割っていたでしょうね。 CD Artwork © Pentatone Music B.V. |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |