|
|
|
|
![]()
DDT。.... 佐久間學
この幕は、出演者が3人しかいませんから、こんな風に手軽に演奏することはとても簡単です。もちろん、そのコンサートが成功するか否かは、ひとえにその3人の人選にかかっていることは言うまでもありません。ここでのソリストは、その当時のまさにドリーム・キャストですからとても楽しみです。指揮のテンシュテットも、キャリアの初めのころにはオペラハウスでの指揮も行っていて、ワーグナーも得意にしていましたが、実際のオペラの録音はほとんどありませんから(全曲録音は皆無)これはとても貴重な記録です。 まずは、そのテンシュテットの指揮ぶりを、前奏曲(日本語の帯には「序曲」とありますが、これは何かの間違いでしょう)から聴いてみましょう。録音状態もとてもよかったようで、低弦のエネルギーはものすごいもの、さらに金管の輝きが迫真の力で迫ってきます。ワーグナーはこうでなくっちゃ。さらに、普段はあまり聴こえてこない木管も、ここぞというところで顔を出してきますから、それはとても色彩的。そして、そのようなダイナミックなシーンと、もっと物語が進んでしっとり歌い上げるシーンとの切り替えがとても巧みです。ジークムントとジークリンデのデュエットのバックのオーケストラの柔軟さには、うっとりさせられます。 歌手では、やはりそのジークムント役のルネ・コロに注目でしょう。1969年に「オランダ人」のかじ取り役でバイロイトにデビューしてからは、ワーグナーのテノールのロールには無くてはならない歌手として世界中で活躍した人です。いわゆる「ヘルデン・テノール」として、オペラハウスに出演、もちろん多くの録音も残しています。さすがに晩年は声も衰えて往年の輝きはなくなっていましたが、このCDのコンサートが行われた頃はまだまだ現役として通用していたはずです。 ただ、ここで聴ける彼の声は、ちょっと「ヘルデン」というには力強さに欠けるような感じがしてしまいました。それこそカウフマンあたりが最近そのハイテンションぶりを見せつけてくれた「Wälse! Wälse!」という叫びが、あまりに弱々しいのですね。その代わりに、「Winterstürme wichen dem Wonnemond」からの甘いシーンでは、テンシュテットの指揮とも相まってまさに禁断の甘美さをおなか一杯味わうことが出来ました。これはこれで、幸福な体験です。 ちょっと気になったので、コロのデビュー頃の録音で、1970年の「マイスタージンガー」を聴いてみたら、大詰めのワルターのアリアは、カラヤンの指揮のせいもあるのでしょうが、ワーグナーの楽劇というよりは、ほとんどフランツ・レハールのオペレッタの世界でしたね。そう言えば、コロはオペレッタでも定評のある歌手でした。ということは、彼はまさに今や大人気の「えせヘルデン」、クラウス・フローリアン・フォークトの先駆けだったのですね。 他の二人、ジークリンデのブントシューとフンディンクのトムリンソンもワーグナー歌いとしては定評のある歌手でしたから、ツボを押さえた歌が聴けます。考えてみたら、ジークムントはまだ「英雄」ではないのですから、コロも適役だったのでしょう。 彼がノートゥンクを引き抜いた後は、テンシュテットは一気にシフト・アップしてエンディングへと向かいます。圧倒的な高揚感とともにこの幕の最後、トロンボーンのペダルトーンが響き渡る中、終止の直前に現れる何とも浮遊感が漂うCm6のコードの味わいは絶品です。G-durのアコードが打ち鳴らされた直後、瞬時に起こる拍手と叫び声、お客さんも大満足だったことでしょう。 CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |
||||||
同じく宗教行事のお祭りでも、クリスマスの場合はまだ節度が保たれたままこの国の風俗にもなじんでいるように見えます。少なくとも、音楽に関してはとても実り多いものをもたらしてくれたのではないでしょうか。ハロウィンには何か音楽的な貢献って、ありましたっけ? ですから、この季節のCDも、玉石混交ながら数多くのクリスマス・アイテムが登場することになります。「天国の歌」という、このSWRヴォーカル・アンサンブルにしては珍しいクリスマス企画のアルバムも、そんな「玉」の一つです。その中身はとても格調の高いもの、厳かに、真にこの世の平安を願いながらこの行事を祝うという思いが込められています。 まず、この合唱団のすばらしい女声パートだけで歌われるのが、ブリテンの「キャロルの祭典」です。よく少女合唱や児童合唱で歌われることもありますが、そのような、まるで天使の歌声のようなピュアな響きが、この大人の女声から聴こえてきたのは、とても幸せなことでした。録音会場は教会ですが、その豊かな残響をとことん利用して、この作品の最初と最後にある「入堂」と「退堂」のための曲で、実際に歩きながら(わざわざ靴の音をたてています)その遠近感を表現してくれています。確かに、コンサートホールで演奏する時にも、客席から登場するような演出もありますからね。 ただ、声はそのような無垢なものでも、表現にはいい加減なところは全くないのが、すごいところです。たとえば、ハープのソロの前の曲「この赤子が」では、大概の演奏では口が回らないために雑な演奏になりがちなところが、そんな難所は軽々とクリアして、いとも流麗な音楽に仕上がっています。 続いて、中世の聖歌が、男声だけによって歌われます。これはそれまでの女声とは全くテイストを変えて、粗野ささえも見せるような時代感を漂わせています。1曲目の「There is no rose」は2声、2曲目の「Verbum Patris humanatur」3声で歌われています。 次にフルメンバーが揃ってペルトの「7つのマニフィカト・アンティフォナ」では、普通にペルトといわれて思い浮かべるようなノーテンキなところの全然ない、とても強い意志の力が感じられます。ど真ん中の曲「おお、ダヴィデの鍵よ」でのハイテンションな叫びで、それは最高潮を迎えます。 ハインリヒ・カミンスキというドイツの作曲家が編曲した3つのクリスマスの聖歌は、いわば「箸休め」、手は込んでいてもあくまで素朴なアレンジからは、クリスマスへの敬虔な思いが素直に伝わってきます。 その後には、プーランクの「クリスマスのための4つのモテット」です。これも、ちょっと今までの印象を変えてくれるような、重量感のある演奏です。あくまで強靭なドイツっぽいハーモニー感がプーランクで味わえるのが、ちょっと意外。 最後は、スウェーデンの人気作曲家、ヤン・サンドストレムが、有名なプレトリウスの「Es ist ein Ros entsprungen」を素材にして、まるでリゲティの「Lux aeterna」のようなクラスターで再構築した逸品、こんなものをサラッと歌ってしまうのですから、本当にこの合唱団は油断が出来ません。というか、こんなひねりのきいたラインナップでクリスマスを楽しめる人は、ある意味ヘンタイ。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |
||||||
とは言っても、現役で活躍していたころには、FMの音楽番組ではかなり頻繁にその名前を聞くことが出来ました。なんせ「ルージッチコヴァー」などという、一度聞いたら忘れられない(いや、正確には「一度聞いても覚えられない」)不思議な名前ですからね。ラジオで彼女の名前を告げるアナウンサー(たとえば後藤美代子さん)や音楽評論家(たとえば大木正興さん)の口調には、この難しい名前を流暢に発音できることに対するなにか自慢げなニュアンスが感じられましたね。 彼女がそのようなメディアで紹介され始めた頃は、チェンバロ奏者と言えばヘルムート・ヴァルヒャかカール・リヒターといった重厚な演奏家が人気を博していたようですが、そんな中にちょっと「傍系」といった感じで、彼女は紹介されていたのでは、というぼけっとした印象があります。 チェコのミュージシャンですから、やはり当時の国営レーベルだったSUPRAPHONEへの録音がメインだったのでしょうが、なぜかフランスのERATOレーベルのプロデューサー、ミシェル・ガルサンは、彼女を使ってバッハのチェンバロ作品の全集を作ることを考えました。そして、1965年から1973年にかけて録音が行われ、1975年から22枚(品番はERA 9030からERA 9051)のLPとしてリリースされました。手元には1975年に発行されたERATOのカタログがありますが、そこにはマリー=クレール・アランが最初に作ったLP24枚組のオルガン曲全集と並んで、このルージッチコヴァーのチェンバロ全集が大々的に紹介されています。当時としては、それほど画期的な偉業だったのですね。確か、同じような全集では、DG(ARCHIV)のカークパトリック、EMIのヴァルヒャに次ぐ3番目のものだったのではないでしょうか。  彼女がこの録音を始めた頃は、世の中はモダン・チェンバロ一辺倒の時代でした。もちろん彼女も、ドイツのメーカー、アンマー、ノイペルト、そしてシュペアハーケという3種類の楽器を使っています。しかし、次第に訪れるヒストリカル・チェンバロの波にも敏感だった彼女は、このツィクルスのセッションの終わりごろ、1973年(資料によっては1972年)には「小さなプレリュード」(ERA 9049)と「組曲」(ERA 9050)のLP2枚分を、1754年と1761年に作られた2台のジャン=アンリ・エムシュの復元楽器を使って録音しています。 スリーブには録音年代と使用楽器が詳細に記載されていますから、モダンとヒストリカルの違いをはっきり確かめることが出来ます。最近ではほとんど聴くことのできないモダン・チェンバロの音はどういうものだったのか、これではっきり知ることが出来ることでしょう。こういう時代もあったのです。しかし、それに対してヒストリカル・チェンバロだとされている録音を聴いても、音色は確かに別物であるにもかかわらず、そのあまりにも非現実的な録音レベルの高さに驚かされます。モダンに慣れ親しんだエンジニアが、ヒストリカルの音を聴いて取った行動は、こういうものだったという、まさに「歴史的」な記録がここには残されているのです。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |
||||||
ということで、今回のアメリカ盤では、そのようなサービスは行っていないということが分かりました。なんか、納得できませんが仕方がありません。 今年は10月3日にライヒが80歳を迎えた記念の年ということで、新しいアルバムが続々リリースされているようですが、これもそのうちの一つ。2007年の「Double Sextet」と、2013年の「Radio Rewrite」のカップリングです。トータルで40分しか収録されていませんが、本当はそのぐらいが1枚のアルバムとしてはちょうど良いサイズなのかもしれませんね。いずれも、今回が初録音というわけではなく、どちらもライヒの作品では定評のあるNONESUCHレーベルですでに録音されていました。「Double Sextet」は2009年に、この作品を委嘱し、初演を行ったeighth blackbirdによって、「Radio Rewrite」は、初演者とは別の団体によって、2014年に録音されています。 このレーベルでは、以前同じ演奏家によるライヒの「Music for 18 Musicians」も聴いていますが、これはその第2弾、というか、「Double Sextet」の方はその時と同じ2011年3月のセッションで録音されていたものでした。「Radio Rewrite」だけが、今年の1月に録音されています。 「Double Sextet」を委嘱された時には、ライヒはそのeighth blackbirdというアンサンブルのメンバーの編成(フルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、ピアノ、打楽器)に忠実に合わせて、6つの楽器のための曲を作りましたが、それを演奏する際には、前もって自分たちが演奏した音源に合わせてライブで別のパートを演奏するというやり方で、12の楽器のための作品に仕上げてありました。今回は、それを実際に12人のメンバーを使って全てのパートを「生」で演奏するという形になっています。eighth blackbirdの「6人バージョン」もNMLで聴けますから、比較してみるのも一興でしょう。おそらく、「第2部」の、ちょっとできそこないのタンゴ、といった趣の曲では、同じ楽器でも音色や微妙な個性の違いぐらいは確認できるのではないでしょうか。 「Radio Rewrite」は、2013年に、委嘱を行ったロンドン・シンフォニエッタによって初演されておったのですが、その時に指揮をしたのが、このアルバムでの「アンサンブル・シグナル」の創設者で指揮者、ブラッド・ラブマンでした。これも、先ほどのNONESUCH盤との比較が可能です。こちらは、「元ネタ」のRadioheadからの引用に対するシンパシーが、微妙に異なって聴こえてくることがあるかもしれません。それは、初演者が必ずしも満足のいく結果を出せない場合もある、ということにもつながるのでしょうか。しかし、それは本質的な差異ではありません。 幸運にも、異なる演奏家による録音が多数存在するライヒの作品ですが、それらを比較してみても際立った違いが感じられないのは、そもそもライヒの作品には「表現」という要素が非常に希薄だからなのでしょう。というより、ある意味「表現」からは遠く離れたところから出発したのがライヒの音楽だったわけですが、それは同時に彼と、そして彼の技法の限界にもなっていたのかもしれません。 CD Artwork © harmonia mundi usa |
||||||
ですから、やはりこのオーケストラとは、格別の親密度で接しているのでしょう。この最新アルバムでのチャイコフスキーも、とても素晴らしい演奏が期待できるはずです。 ところが、まずはSACDということですし、以前のこのレーベルでは元DECCAのエンジニアが作った「Classic Sound」が録音を担当していたので、音に関してはまず間違いはないだろうと聴きはじめると、なんかとても物足りない気分にさせられてしまいました。実は最近、ここの録音でウラジミール・リアベンコ(?)という人がエンジニアとしてクレジットされるようになってから、それまでと全く音が変わってしまっていました。具体的には、弦楽器の音がとてもまろやか、というか、完全にエッジがなくなった甘ったるい音になっているために、パートとしての主張が全く感じられなくなっています。金管楽器が鳴り響いている間でも、前の録音ではしっかり聴こえてきたものが、ここでは完全に埋もれてしまっています。チャイコフスキーでは、こういう場面でこそ弦楽器の芳醇な響きを味わいたいのに、それが全然叶わないしょぼいサウンドになっているんですよね。 このエンジニアに最初に接したのが「ワルキューレ」のSACDを聴いた時。その時に抱いた違和感が、ここに来てまた頭をもたげてきたという感じです。 「くるみ割り人形」は、組曲版で満足している人がほとんどでしょうから、いまさら全曲版を聴くのもかったるいな、と思ってしまうかもしれませんが、今回のSACDを聴くと、やはり一度は全曲を通して聴いてみたいものだ、と痛切に感じてしまいます。組曲には入っていないナンバーが、全体のテーマとして重要な意味を持っていることがよく分かりますし、組曲版のそれぞれの曲の役割もきちんとわかります。 一つ、面白いのは、チェレスタの扱いです。チャイコフスキーは、この新しい楽器を他の作曲家に先駆けてこの作品の中で初めて披露しているのですが、それがメインでフィーチャーされている「金平糖の踊り」は殆ど終わり近くになって登場します。しかし、彼はあたかも「伏線」のように、もっと前の曲(第2幕の1曲目)の中で使っているのですね。これはかなり印象的に聴こえますから、ここで「この楽器は何だろう」と思った聴衆が、「金平糖」で初めてソロを聴いたら、その美しい音色に必ず酔いしれるはずだ、というしたたかな計算を、チャイコフスキーだったらやりかねないな、とは思いませんか? 「くるみ割り」全曲はハイブリッドSACD1枚にはちょっと収まらないので、これは2枚組、そのカップリングで「交響曲第4番」が入っています。これが、とっても柔軟な、自由度の高い演奏です。ゲルギエフは2002年にウィーン・フィルと同じ曲を録音していますが、その時のものとはとても同じ指揮者とは思えないような、細やかで思いの丈を存分に込めた演奏に仕上がっているのです。特に第2楽章では、演奏時間がウィーン・フィルでは9分35秒だったものが今回は11分28秒ですから、全く別のテンポでとても濃厚な音楽を味わうことが出来ます。 第4楽章は、演奏時間はそれほど違っていないのに、こちらの方が表情は豊か、フルートが難しいオブリガートを付ける部分では、まるで指揮者とフルート奏者がお互いの出方をうかがっているような絶妙のコンタクトが感じられます。こんなことをやられたら、フルート奏者はとても吹きやすかったことでしょう。録音のことを考えなければ、これは超名演。 SACD Artwork © State Academic Mariinsky Theatre |
||||||
そのインタビューでは、彼が若いころにウルム歌劇場でコレペティトゥールを勤めていた時の映像が挿入されていますが、そこではベルクの「ヴォツェック」のオーケストラパートをピアノで弾きながら歌唱指導をしている様子を見ることが出来ます。それは、はた目にはものすごいスキルを要求されるもののように見えます。このような実直な「下積み」の経験が、フランス最高のオペラハウスのシェフを長く務められるポテンシャルとなっていたのでしょうね。 ご存知のように、このカンパニーは主に2つの劇場を使って連日オペラやバレエの公演を行っています。それは、1875年に作られた「ガルニエ宮」と、1989年に作られた「オペラ・バスティーユ」です。したがって、付属のオーケストラも2セット必要になりますから、普通のコンサート・オーケストラのほぼ2倍の団員を抱えています。 このベートーヴェン・ツィクルスの場合、5回のコンサートが収録されていますが、そのうちの4回はバスティーユ、1回はガルニエ宮で行われたものです。 最近ではベートーヴェンはほとんど室内オケ程度の人数で演奏されることが多くなっていますが、ジョルダンとオペラ座のオーケストラはまずは普通のコンサート・オーケストラがとっている編成を採用していました。1番だけはちょっと少なめの12型(12-10-8-6-4と、30人の弦楽器)ですが、2番から8番までは14型(40人)、そして9番ではフル編成の16型(50人)になっています。 さらに、弦楽器の配置も、1番から8番までは下手からファースト・ヴァイオリン、セカンド・ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラと並び、上手の奥にコントラバスという標準的なものですが、9番だけはセカンド・ヴァイオリンが上手に来て、チェロとコントラバスは下手という「対向型」を取っています。もちろん、コントラバスの弓は全員「フレンチ・ボウ」ですね。 管楽器でも、今ではフランスのオーケストラでもなかなかその姿を見ることが出来なくなった「バソン」というフランス式のファゴットを使っている人が、ここにはまだいることが分かります。ただ、収録された5回のコンサートの中で、バソン奏者だけが参加していたのは2回だけ、そして2回はファゴットだけですが、残りの1回では、なんと1番がファゴット、2番がバソンという変則的なシーティングでした。 ジョルダンが使った楽譜は、おそらくベーレンライター版でしょう。9番の第4楽章でヴィオラがテーマを弾き始める時のバックでのファゴット(いや、バソン)のオブリガートのリズムが、ベーレンライター版以外にはない形でしたから。ですから、慣用版にあった明らかなミスプリントはすべて正しくなっています。さらに、ブライトコプフ新版にある5番の第3楽章のダ・カーポも、採用されています。これにはちょっとびっくり。 そのような楽譜によって、快速なテンポで運ばれていく演奏は、まず現代では最も標準的で受け入れやすいスタイルなのではないでしょうか。フォルテピアノからクレッシェンドという「臭い」表現が随所で頻発しているのは、我慢していただきましょう。それよりも、演奏者の中にまでカメラを入れて作り上げられた躍動的な映像には、興奮させられます。1、3、4、5、9番では、40年間首席フルート奏者を務めているカトリーヌ・カンタンの姿も、簡単に見られますよ。3番の大ソロで音をはずしているのは、ご愛嬌。 BD Artwork © Arthaus Musik GmbH |
||||||
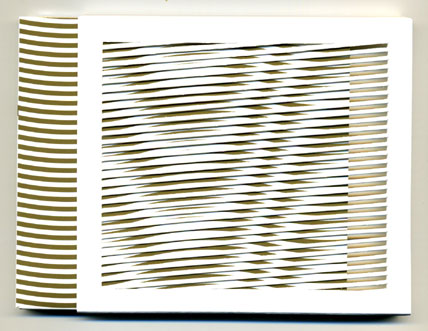 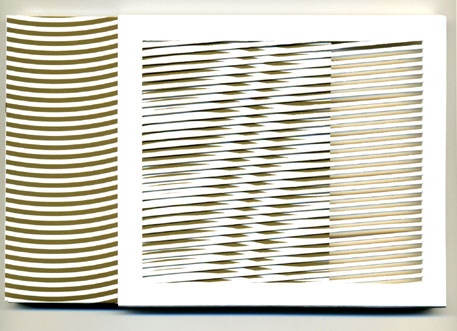 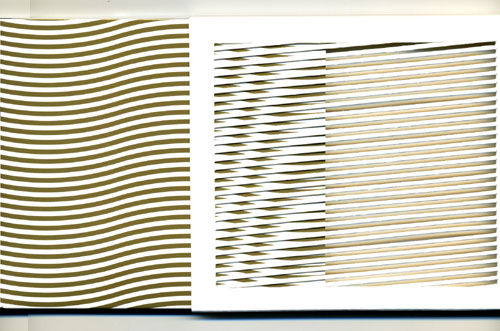  これは、その「ミニマル・ミュージック」の代表的な作曲家テリー・ライリーの、まさに代表的な作品「In C」が収められたアルバムです。1964年に作られたこの作品の楽譜には、53個のメロディの断片が書きつけられているだけ、それぞれは、最も短いもので半拍(十六分音符2つ)、最も長いものは休符も含めて32拍もあります。それを、任意の楽器を演奏する任意の人数のメンバーが、それぞれ最初から順番に、あるいは途中を飛ばしたりしてそれぞれの断片を好きなだけ繰り返す、というのが「ルール」です。この「楽譜」はIMSLPでも公開されていますから、探してみてください。 今回のCDのアーティストは、オランダの巨乳の女性ばかりの弦楽カルテット「ラガッツァ・カルテット」。これまでにこのレーベルから2枚のアルバムをリリースしていますが、それぞれにとてもユニークなアプローチが評判を呼んでいたようです。今回はライリーの作品が2曲取り上げられていて、そこに他の団体も参加しているというのが、やはりユニークさを際立たせています。その「他の団体」というのは、「デン・ハーグの打楽器奏者たち」という4人のメンバーによる打楽器アンサンブルと、「カポック」という名前のジャズ・トリオです。「トリオ」とは言っても、オーソドックスな編成ではなく、なんとホルンとギターとドラムスという、こちらもユニークなメンバーが集まった団体です。ですから、このアルバムの本当のタイトルは「Four Four Three」という、それぞれの団体の人数を羅列しただけというとてもシンプルなものでした。 「In C」では、「Four」と「Four」、つまり、弦楽四重奏に打楽器が加わった編成で演奏されています。そもそもライリーが指定した「音」は、その楽譜にあるフレーズだけですが、もちろん打楽器の中にはマリンバなども含まれていて、そこではきちんとそのフレーズが演奏されているものの、ここでは「リズム」としての参加が目立っています。もちろん、それは単なるメトロノーム的なパルスではなく、それ自身がライリーの指定を超えた自由なフレーズを作り上げているという、とても積極的な関わり方です。 ラガッツァ・カルテットのメンバーも、彼女たちの楽器だけでなく、「声」まで動員して、フレーズに彩りを添えています。それが、とても正確なソルフェージュなのには、感心させられます。こんなのを聴くと、合唱だけで「In C」を演奏したくなってきますね。 久しぶりにこの「古典」(実は、初演から半世紀経っています)で、「モアレ効果」を体験してみると、同じ「ミニマル」とは言っても、もう一方の雄、スティーヴ・ライヒとは根本的なところで音楽の意味が異なっていることに気づきます。そもそも、あちらは楽器も、そして楽譜も厳格に指定されていますし。 もう1曲は、1980年にクロノス・カルテットのために作られた「Sunrise of the Planetary Dream Collector」。この頃になるとライリーの作風もだいぶ変わってきて、これは北インドの民族音楽が素材となっています。これも、ホルンやコルネットが入ったジャズ・トリオとのコラボで、クロノスのものとは全く別の世界が繰り広げられています。 CD Artwork © Channel Classics Records bv |
||||||
録音されたのは、ノルウェーの西側に面した島にある港町、オーレスンにある教会です。そこはオーレスンでは最初に建設されたという三角屋根の古い教会で、外側は石造りですが、内装は天井に木が使われていて、なかなか鄙びた雰囲気を醸し出しています。ここにはオルガンが2台設置されています。祭壇に向かって左側のバルコニーにあるのが、1909年に最初に作られたオルガン。これはそもそもはストップが22という小振りのクワイヤ・オルガンでした。 しかし、1940年に教会に多額の寄付があったため、祭壇の向かい側に新たにJ.H.ヨルゲンセンによって、70のストップと4段の手鍵盤を持つ大きなオルガンが設置されます。その時に、このクワイヤ・オルガンは、ファサード(外側のケースで、この楽器の場合は音の出ないパイプで飾られている)だけを残して、オルガン本体は売り払われてしまいました。いや、この大オルガン自体も、第二次世界大戦中は別の場所に保管されていたのだそうです。 戦争が終わった1945年に、大オルガンは元通りに教会の中に設置されます。その時点で、これはノルウェー国内では3番目に大きなオルガンでした。それからは、教会の礼拝の時に演奏されるだけではなく、ラジオ放送やレコードで多くの人に聴かれるようになりました。 さらに、2009年までに、オーストリアのリーガー社によって、大幅な修復が施されます。その際には、空っぽだったクワイヤ・オルガンにも新たにパイプとコンソールが設置され、この教会のオルガンは94ものストップ(パイプ数は8000本近く)を持つ、国内で最大の楽器の一つとなったのです。  でも、この録音の凄いところは、そんな大げさな再生装置ではなく、たった2chでも十分に距離感、そして「高さ」までが感じられてしまうということでしょうか。もちろん、それはほんの些細なこと、それよりも、今まで聴いてきたオルガンの録音ではほとんど体験できなかったことなのですが、オルガンが「機械」ではなく「楽器」として聴こえてきたのには、感動すら覚えてしまいました。もしかしたら、天井が木の板で出来ていることで過剰な反響がうまい具合に減っているのでしょうか、金属のパイプから生まれた音は、とてもまろやかにミックスされて耳に届いているようでした。 演奏されているのは、シェル・モルク・カールセン、トリグヴェ・マドセン、シェル・フレムという、いずれも1940年代に生まれたノルウェーの作曲家の作品です。それぞれに、オルガン音楽の伝統をしっかり受け継ぎながら、現代でも通用するような確かな語法を持ったものです。特に少ないストップでしっとりとした情感を歌い上げる部分が心に染みます。日本で学んだこともあるというフレムの作品で、お琴の調律法である「平調子」のスケールが用いられているのも、懐かしさを誘います。「フロム・ジャパン」ですね。 SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS |
||||||
このプロジェクトが始まった時の告知では、指揮者がネゼ=セガンだということ以外は決まっていないような感じでしたが、今回のブックレットを読むと、「ネゼ=セガンとヴィリャゾンのプロジェクトだ」と書いてありました。これには驚いてしまいましたね。確かに、これまではキャストはほとんど重なることはなかったのに、なぜかヴィリャゾンだけが全ての演目で歌っていたので変だとは思っていたのですが、そういうことだったとは。 幸いなことに、今回の「フィガロ」ではテノールはあまり活躍しません。一応第4幕にアリアがあるのですが、実際のステージではその前のマルチェリーナのアリアとセットでカットされることが多くなっています。さる指揮者のご意見では、この2曲は「ほんとうにつまらない」からなのだそうです。とは言っても、やはり最近の原典主義の流れの中では、きちんと全曲演奏されるようになっていますから、このCDでもヴィリャゾンは歌っていますが、そんなものは慣例に従ってスキップしてしまいましょうね。 ただ、それ以外のアンサンブルでは何か所かの出番がありますから、そこではもう彼の異質なキャラの歌がはっきり聴こえてしまいます。困ったものです。ヴェルディやプッチーニだったら少しは我慢できるのかもしれませんが、モーツァルトでこういうことをやられると、どうしようもありません。 ですから、このシリーズの残りの3つの作品では彼がイドメネオとタミーノとティトゥスを歌うことなのでしょうが、それはいくらなんでもちょっとヤバいのでは。今ならまだ間に合います。どうか、そんな無茶なことはやめてください。というか、せっかくだから最後まで付き合ってやろうと思っていましたが、そういうことだったら、もうこれでお別れにしてもいいかな、と思い始めていますから。 メインキャストでは、ハンプソン以外の人はここで初めて声を聴きました。最近は、どんどんフレッシュな人が活躍を始めていますから、付いていくのが大変です。特に、伯爵夫人のソーニャ・ヨンチェヴァはいい感じでしたね。ありがちなちょっと重ためな声ではなく、とても若々しいすがすがしさに惹かれます。スザンナのクリスティアーネ・カルクと、ケルビーノのアンジェラ・ブラウアーも、やはり素直で軽快な歌い方が心地よく感じられます。こんな素晴らしい人がいくらでもいるのに、なぜヴィリャゾンなんかにこだわっているのか、本当に不思議です。 そして、オペラ全体を支えていたのが、いつものように思いっきりピリオド感を前面に押し出したネゼ=セガン指揮のヨーロッパ室内管です。もちろん、やはりいつものようにジョリー・ヴィニクールのフォルテピアノによる通奏低音が奏でる即興的なパッセージが、ここそこに新鮮な味を演出していました。 それと、合唱が素晴らしかったですね。これは、コンサート形式のメリットでもあるのでしょうが、芝居をしたりせずにオーケストラの後ろにきちんと並んで歌っていますから、本来の力が更にしっかり発揮できています。 そんな中で、アンネ・ゾフィー・フォン・オッターがマルチェリーナというのも、やはり時代の流れなのでしょうか。写真で見ると、まるで魔女のようになってしまった彼女にとっては、もはや第4幕のアリアは荷が重いものになっていたのでしょう。 いつものことですが、これはコンサートのライブなので、お客さんの笑い声などはしっかり入っているのに、最後の拍手だけはきれいにカットされています。それがとても唐突に思えます。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |
||||||
もっとも、この、毎年日本合唱連盟が開催している「合唱コンクール」というのは、ちゃんとした「コンクール」とは似て非なるものなのではないでしょうかね。だって、学生ならいざ知らず、メンバーがずっと変わらない「一般」の合唱団だったら、1回金賞を取ってしまえば、あとはもう参加する必要なんかないはずなのに、毎年毎年出てくるんですからね。 このアルバムは、今年の3月に行われた定期演奏会に先だって、同じプログラムをスタジオで録音したものです。ここではプーランクの1937年の「ミサ」から、1959年の「聖アントニウスの賛歌」まで、無伴奏の混声、男声、女声合唱のために作られたすべての宗教曲が演奏されています。 一応、品番はBRAINからリリースされたCDのものになっていますが、録音を行った「Sound Inn」名義でハイレゾ音源も同時に配信されていましたから、そちらの音を聴いてみました。ただ、それを購入する時に配信サイトに行ってみると、そこには24bit/96kHz PCMと1bit/5.6MHz DSDの2種類の音源が用意されていました。業界では、24bit/96kHzPCMは1bit/2.8MHzDSDと同等だ、というような基準が一般的なようですから、これだとDSDの方が上位のフォーマットになっています。ただ、両者は同じ価格で販売されている、というのがちょっと気になります。良心的なサイトでは、上位のフォーマットではそれ相応の価格が設定されているはずですから、それが同じだということは、どちらかがアップサンプリングである可能性が強くなってきます。何とも判断に苦しむところですね。 それを決めるために、オリジナルの録音フォーマットを知りたいと思ったのですが、どこにもありません。そこで、BRAINの公式サイトのメールフォームと、harmonia ensembleのFacebookページに「教えてください」と投稿したら、しばらくしてほぼ同時に「32bit/96kHzのPCMです」という答えが返ってきました。BRAINなどは直接電話がかかってきましたよ。今まで他のレーベルではこういうことはほとんど無視されていたので、全く期待していなかったのですが、なんという素晴らしい対応なのでしょう。ということは、配信音源はDSDの方がより元のデータに近いものが得られるのでは、という感触ですから、それにしましょう。 DSDで購入したのは、やはり正解でした。参考までに、単売されていたうちの「クリスマスのための4つのモテット」だけPCMでも購入して聴き比べてみたのですが、いくらか音の輪郭がざらついて、輝きがなくなっていましたね。 この録音では、狭いスタジオの写真からは想像できないような豊かな残響が付いているのには驚きました。それでいて声はニュアンス豊かにしっかりと聴こえてきます。音の肌触りなど、ゾクゾクするほどのすばらしい録音です。 ただ、あまりにリアルな音であるために、全体のハーモニーがサウンドとしてあまり溶け合っていないような気がします。プーランク特有のテンション・コードの味が、あまり感じられないのですね。それと、「アッシジの聖フランチェスコの4つの小さな祈り」のフランス語のディクションがちょっとフランス語には聴こえない、というあたりも少し物足りません。でも、以前のアルバムでのプーランクではなんだか借り物のようなところがありましたが、ここでは見事な流れが感じられるものに変わっています。 次回には、教会のような優れた音響の会場で、5.6MHzDSDの一発録りなどに挑戦されてみてはいかがでしょうか。絶対に買いますよ。 CD Artwork © Brain Music |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |