|
|
|
|
![]()
薔薇、遠く。.... 佐久間學
そんな厳選されたリリースを貫いているRCOレーベルのジャケットデザインが、「地味に」リニューアルしたようです。今までは全体を水平に横切る何本かの帯に演奏情報が記入されていたものが、ここではセンターの正方形の中にまとめられています。これは、このオーケストラの首席指揮者が変わったことを強烈に印象付ける意図が込められたデザイン変更なのではないでしょうか。 これまで11年に渡って首席指揮者を務めてきたマリス・ヤンソンスの後を受けて2016/2017年のシーズンからロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のシェフとなったのは、ダニエレ・ガッティでした。これは、この新しいチームによる最初のSACD、まだ正式に就任する前の2016年3月と4月に渡って行われた3日間の同じプログラムによるコンサートでのライブ録音です。 この、新しい門出を象徴するようなアルバムのリリースでは、SACDだけではなく、DVDとBDという映像ソフト、さらにはLPまでも動員するという力の入れようです。ただ、映像ではコンサートでのすべての演奏曲目が入っていますが、SACDとLPでは「幻想」だけです。LPではそれが2枚組になっていて、かつてのLPには必ずあった。第3楽章の途中で再生を一旦中断してA面からB面に裏返さなければいけないという「欠点」を解消しています。もちろん、外周だけでカッティングを行っていますから、SACDに匹敵する音質も確保されているのでしょう。ついでですが、このアルバムのあたりから、録音フォーマットもそれまでの96kHzからDXD(おそらく384kHz)へとグレードアップしているようですね。 ガッティの演奏は、前任オケであるフランス国立管弦楽団と同時に音楽監督を務めていたロイヤル・フィルとの録音で何種類か聴いたことがあります。最初に聴いたのはマーラーの5番だったのですが、その、聴く者をいつの間にか音楽の中に引きこんでしまう、まるで魔法のような語り口にはとても感心した記憶があります。ただ、その後、一連のチャイコフスキーの交響曲を聴いた時は、曲によってはちょっと疑問を感じるようなところもありました。 今回の「幻想」の演奏も、そんな語り口のうまさが裏目に出てしまっていて、なんとも居心地の悪いもののように感じられます。特に、第1楽章の前半「夢」の部分が、あまりにも作為的過ぎるんですね。気持ちはわかるけど、そこまでやることはないだろう、という感じ、おそらくオーケストラもちょっと嫌気がさしていたのではないか、と思えるほど、全員の気持ちが一つにはなっていないようなアンサンブル上の齟齬を感じる場所が多々ありました。実は、このあたりの演奏について、ブックレットの中のインタビューでガッティはその意図を「詳細に」語ってしまっているのですね。いわば「確信犯」なのですが、結果がこんなものでは興ざめです。 同じインタビューで、第3楽章の冒頭のコールアングレとバンダのオーボエの掛け合いの部分を、ビブラートをかけて演奏していたプレーヤーに指示をしてもっと「ナチュラル」なノン・ビブラートにしてもらった、というようなくだりも、わざわざ他人に話すようなことではないように思えるのですが。というか、最近のオーケストラでは、どこでも同じようなことをやっているのではないでしょうか。 SACD Artwork © Koninklijk Concertgebouworkest |
||||||
今回のアルバムでの「売り」は、「ピリオド楽器による録音」だったのではないでしょうか。これは「世界初」の試みです。最近では例えばストラヴィンスキーなどの20世紀の作品までもその時代の楽器で演奏されることがありますから、いつかはこういうものが出てくるとは思っていました。確かにストラヴィンスキー同様、この「レクイエム」が作られた1940年代のオーケストラでは、現在とはかなり異なる楽器が使われていました。それが、第二次世界大戦を境にしてオーケストラの楽器は大幅に変わってしまっていたのです。弦楽器では、それまではガット弦を使った楽器だったものが、このあたりから徐々にスチール弦の楽器に変わります。そして、特にフランスのオーケストラに関して顕著だったことが、管楽器の変更です。つまり、戦前までは国ごとにオーケストラで使われる管楽器は細かいところで異なっていたものが、次第に全世界共通のものに変わっていったのです。例えば、木管パートの最低音を担う「ファゴット」という楽器は、フランスでは奏法も音色も全く異なる「バッソン」という楽器が使われていました。おそらく、初演当時のフランスのオーケストラでは、間違いなくこの「バッソン」が使われていたことでしょう。ですから、この初演の時の形で今回ピリオド楽器による録音が行われたのであれば、これは非常に画期的な試みということになります。 ところが、ここで使われているのは、1961年になって作曲家が改訂したオルガンと小オーケストラのためのバージョン(第3稿)だったのですよ。この頃になると、世界中のオーケストラの楽器は現在のものとほとんど変わらないものに変わってしまっています。フランスでは「バッソン」がまだ使われていたオーケストラもありましたが、この編成では木管楽器のパートは全てオルガンに置き換わっているのですから、何の意味もありません。つまり、この第3稿を使う限りは、ピリオド楽器を使ったとしてもそこからは「演奏された当時の様子を再現する」という意味は全く存在しなくなっているのです。 クロウベリーとキングズ・カレッジ合唱団は、「レクイエム」を1988年にもEMIに録音していて、その時も同じ第3稿を使っていましたから、彼らにしてはそれがベスト・チョイスなのでしょう。ただ、今回弦楽器にピリオド楽器(ガット弦でモダンピッチ)が使われていることで、このバージョンの欠陥はさらにはっきり表れてきたような気がします。ハイレゾ録音のせいもあるのでしょうが、その弦楽器とオルガンとがあまり溶け合っていないのですね。やはり、せっかくエンライトゥンメント管弦楽団を使ったのですから、ここはオリジナルの第1稿で演奏してほしかったと、切に思います。 ただ、そのガット弦によって得られる独特の音色感は、作曲家が望んだものであるかどうか、という点ではかなり疑問が残るものの、そういう本来の「ピリオド」という意味ではなく、ある種「特殊な音色」を求めたのであれば、それはなかなかの効果を上げていたのではないでしょうか。「Pie Jesu」でのガット弦のチェロのソロは、今まで聴いたことのない独特の雰囲気を醸し出していましたし、トゥッティでのトレモロも、とれもろ(とても)やわらかい響きになっていました。 合唱は、前回の録音同様、成人とトレブルとの間の音色の違いがとても気になります。その成人男声が、かなりレベルが落ちているのも残念です。前回は楽譜通りバリトン・ソロが入っていた部分は、今回はパート・ソロになっていました。 もう一つ、せっかくオーケストラが入ったのですから、「クム・ユビロ」もオリジナルのオーケストラ版で録音してくれればよかったのに。 SACD Artwork © The Choir of King's College, Cambridge |
||||||
ということで、今回のアルバムには、決して口当たりが良いとは言えないような曲が並ぶことになりました。いわゆる「前衛的」と呼ばれる、普通の西洋音楽のイディオムには全くとらわれない作品のオンパレードです。そんなこととは知らずに、まずはペア・ネアゴーという、スウェーデンの本来は「前衛的」なスタイルを持っているはずの作曲家の「Dream Songs」という、いともまったりとした曲で、一旦は和んでしまうはずです。これは、まさに北欧民謡そのもののノスタルジックなチューンを、美しいハーモニーに乗せて歌うという、とてもハッピーな口当たりですが、そこに打楽器が加わって何とも不安定なポリリズムを繰り出した後には、さっきの美しいメロディにはとても気持ち悪い、ほとんど「悪夢」ともいえるようなハーモニーが付けられるという、その後のこのアルバムの進行を予告するような役割を持っていました。 案の定、続くヘルムート・ラッヘンマン(なんだか懐かしい名前)が、世界中がそんな「前衛音楽」の波にもまれていた頃の1968年に作った「Consolation II」は、まさに「そんな」音楽でした。「声」によるあらゆる表現方法を駆使した、当時としては合唱の新しい可能性に向けての先鞭を切っていたという思いで作られたものなのでしょうが、今となってはなんとも空回りしている面しか感じられません。しかし、この素晴らしい合唱団が、とてもしっかりとその「当時の思い」を再現しているのには、感服させられます。 次の、アルフレード・ヤンソンというノルウェーの作曲家は初めてその作品を聴きましたが、ラッヘンマンの曲と同じころに作られた、ニーチェの「ツァラトゥストラ」をテキストにした「Nocturne」では、そのような「前衛的」な手法は、すでにある種の効果を演出する場合のみに有効に活用するという、今の時代にもそのまま通用するような作風が見られます。 次に、フィンランドの作曲家、サーリアホのとても短い「Überzeugung(確信)」という、3人の女声とヴァイオリン、チェロにサンバル・アンティークという薄い編成の、不思議な雰囲気が漂う静かな曲が挟まります。その後には、冒頭のノアゴーが、ここでは本領を発揮して、シューベルトの曲の断片を取り入れたりしつつ、ある意味中途半端な「前衛」を展開しています。 そして、クセナキスの「Nuits(夜)」です。これまで聴いてきた、チマチマとした技法を超越したところにあるのがこの作品、まさか、この曲をこの合唱団で聴けるとは思っていなかったので、感激もひとしおです。彼らは、普段は見られないような「汚れた」歌い方まで駆使して、ひたむきにこの作品に奉仕しているように思えます。これは名演です。 最後に、サーリアホの作品をもう1曲聴くことが出来ます。「Nuits, adieux」という、まるでクセナキスの作品を挑発するかのようなタイトルですが、「前衛的」な手法も結局は美しいハーモニーに集約せざるを得なかったところで、「現代」における「現代音楽」の宿命を感じざるを得ません。「夢」が終わるとともに、「現代音楽」も死に絶えるのでしょう。 SACD Artwork © BIS Records AB |
||||||
今回のガーディナーとロンドン交響楽団のメンデルスゾーン・ツィクルスの3枚目、交響曲第1番と第4番「イタリア」では、それぞれ録音時期が違っていたために、2014年の「4番」は「DSD64fs」、2016年の「1番」は「DSD128fs」によって録音されていました。もちろん、SACDではどちらも64fsになってしまうので違いは分かりませんが、同梱のBD-Aは24/192というフォーマットですから、間違いなくSACDよりもハイスペックのはず、もしかしたらそこにトランスファーされたDSD128fs(5.6MHzDSDとも言う)とDSD64fs(2.8MHzDSD)との違いを実際に体験できるかもしれませんよ。 確かに、DSD64fsの「4番」では、SACDとBD-Aの違いはほとんどありませんでした。しかし、DSD128fs「1番」では聴いてすぐに分かってしまうほどの違いがあったのには、逆に驚いてしまいましたよ。ここでは、おそらくガット弦をノン・ビブラートで演奏しているのでしょうが、その生々しさがSACDとは全然違うんですよ。それと、やはり木管楽器の存在感ですね。最近の体験から、DSDは128fsになって初めて真価が発揮できるのでは、と思うようになっていましたが、やはり64fsと128fsの間には、このぐらいはっきり分かる違いがあったのでした。ですから、やはりSACDのフォーマットも最初から128fsにしておけばよかったんですよね。というより、SACDが出来た時には、CDと同じことでこれが最高のフォーマットだと思われていたのですから、仕方がないのかもしれませんが。 この演奏では、ガーディナーはどちらの交響曲にも普通に使われている楽譜以外のものを使っていると、輸入元のキング・インターナショナルのインフォにははっきり書いてありました。確かに、「1番」の第3楽章については、1829年にイギリスで演奏した時に、1824年に作っていた第3楽章の「メヌエット」の代わりに、1825年に作った「弦楽八重奏曲」からの「スケルツォ」にオーケストレーションを施したものを使ったという史実に則って、二通りの「第3楽章」を演奏しています(実際にライブで並べて演奏したのだそうです)。 しかし、「4番」に関しては、なんの変哲もない「現行版」、つまり「1833年版」で演奏しているのに、それがさっきのインフォではあたかも現行版とは別のものであるかのように書かれているのには絶句です。少なくとも、音を聴いた時点でその間違いに気づくはずですよ。なんと恥ずかしい。これは、ガーディナーが1998年にウィーン・フィルと録音したDG盤で、初出の国内盤に「茂木一衞」という人が書いたデタラメなライナーノーツを、2011年のリイシュー盤でもそのまま使いまわしているユニバーサルと同様の恥ずかしさです。 その、1998年に鳴り物入りで「改訂版」(もちろん、1833年以降に作られたもの)を「世界初録音」したガーディナーですが、それは単なる物珍しさで終わったようで、もはや何の関心もなくなっているのでしょう。 そんな些細なことではなく、少なめの弦楽器(ファースト・ヴァイオリンもセカンド・ヴァイオリンも10人)を対向配置にして、それをノン・ビブラートで弾かせるという、もう少し本質的な点に目を向けるようになったガーディナーの「成長」ぶりこそを、ここでは味わうべきでしょう。キング・インターナショナルのインフォは、それを削ぐことにしかなりません。すぐ、直しましょうね。 SACD & BD-A Artwork © London Symphony Orchestra (11/9追記) どうやら、キングインターナショナルはインフォを訂正したようですね。元の文はこちらのHMVのインフォに残っていますから、比較してみて下さい。 現時点でのインフォは、 キング なお、ガーディナーは、ウィーン・フィルと、1997年に1833年版、そして98年には1834年版の第2楽章から第4楽章をセッション録音しましたが、今回は1833年版を採用しての演奏となっています。 HMV なお、ガーディナーは、ウィーン・フィルと、1997年に現行版、そして98年には1833年版の第2楽章から第4楽章をセッション録音しましたが、今回は1833年版を採用しての演奏となっています。 |
||||||
それと、最近の傾向ではもはやバッハをモダン楽器で演奏するのはやめにしよう、という声がかなり大きくなっているようです。かろうじてピアノあたりではまだまだモダン楽器の存在意義は失われてはいませんが(なんたって、一番売れているCDがグールドのものですから)、フルート・ソナタをピアノ伴奏で演奏するというのは、かなり恥ずかしいことなのではという認識はかなり広がっているのではないでしょうか。今では昔の「フラウト・トラヴェルソ」で演奏しているコンサートや録音の方が、モダン・フルートよりもずっと多くなっているはずです。 というわけで、今回のCDもトラヴェルソとチェンバロによる演奏です。ただ、タイトルにあるように、伴奏は「ハープシコード」だけ、通奏低音と演奏されると指定されている曲でも、低音弦楽器が入ることはありません。ただ、ここでユニークなのは、その「ハープシコード(つまりチェンバロ)」を3台と、さらには「クラヴィコード」を1台用意して、都合4台の楽器がそれぞれの曲を伴奏する、ということです。 BWV1030(ロ短調)、とBWV1031(変ホ長調)、そしてBWV1034(ホ短調)という、おそらくバッハのフルート・ソナタの中では最も演奏頻度のランクが上位になっているはずの3曲では、18世紀のハンブルクのチェンバロ製作者ヒエロニムス・アルブレヒト・ハスの楽器のコピーが使われています。ただ、この録音ではチェンバロにやたら近接しているマイクを使っていて、あまりに生々しい音になっているのに驚かされます。その結果、トラヴェルソとのバランスがとても悪く、最初の2曲のようにチェンバロの右手とトラヴェルソが互いにテーマを歌いかわすという「トリオソナタ」の形の作品では、その構造が全く見えてきません。さらにチェンバロの音色も、まるでモダン・チェンバロのようなパワフルなものになっていますから、違和感は募るばかり、そこに持ってきて、このチェンバリストの演奏がやたらと持って回った歌い方をさせているものですから、ちょっと気分が悪くなってしまうほどです。 BWV1032(イ長調)になると、チェンバロはイタリアの楽器(製作者は不明)のコピーに代ります。これは、それまでの楽器とはがらりと変わった、ヒストリカル・チェンバロらしい繊細な音が聴こえたので一安心です。それが楽器のせいなのか、録音のせいなのかはわかりませんが、これでやっとバッハの音楽を聴いているような気持ちに慣れました。この曲では第1楽章の途中から楽譜がなくなってしまっているのですが、その部分の修復案として、一度頭まで戻って、途中にやはり今まで出てきた経過のパッセージを挟んで最後につなげるという、バッハが実際に作った素材のみでの方法をとっていました。 そして、3台目のチェンバロは、モデルは明示されていませんが、通常の金属弦ではなくガット弦を張った「リュート・チェンバロ」と呼ばれる楽器です。これはもうまさにリュートのような柔らかい響きですから、その違いははっきり分かります。というか、このぐらいの楽器になってやっとトラヴェルソとのバランスが取れるというのですから、このエンジニアはどんな耳をしているのでしょう。この楽器で演奏されているのが、最もJ.S.バッハらしくないと思われているBWV1033のハ長調のソナタです。 最後には、チェンバロではなくクラヴィコードの登場です。この楽器は、ドイツの名工を輩出したシードマイヤー一族のもののコピー、この名前は今でもチェレスタやキーボード・グロッケンシュピールのメーカーとして知られています。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |
||||||
ところが、そんな日はすでに2年前に訪れていたのですよ。前回「Christmas」の新しいLPを入手したのを機にハイレゾ配信サイトを調べてみたら、国内では2タイトルしか出ていなかったものが、ドイツの「HIGHRESAUDIO(ハイレゾオーディオ)」というサイトには、なんと13タイトルものハイレゾ音源が用意されていたではありませんか。「Christmas」と、1974年の「Sentimental Journey」が抜けていますが、それは大した問題ではありません。 おそらく、最近までMPSレーベルを管理していたUniversalは、彼らのアルバムにはそれほど関心がなかったのかもしれません。それが、Edelに移ってリリースに対する環境が変わったのでしょう。これらの音源は、すべてその時期、2014年にリリースされています。長年の夢は、とっくの昔にほとんど叶ってしまっていたのですね。 ただ、いずれは全部入手するにしても、まずはお試しできちんと聴いておかなければいけません。そこで、とりあえず、最も気に入っていた順にこの3枚のアルバムをダウンロードしてみました。 「A CAPELLA I」の音は、まさにCDとは別物の緻密で存在感にあふれるものでした。たぶん、最初に聴いたコロムビア盤のLPがこんな音だったのではないか、という気がしましたね。「A CAPELLA II」では、1曲目の「Clair」のイントロで出てくる口笛の音が、テイチク盤のLPでさえものすごいインパクトがあったのですが、それはCDでは何とも情けない音になっていました。それが、今回のハイレゾではそのLPさえも超えるほどの芯のある音で聴こえてきましたよ。 「A CAPELLA I」を、手元にある何種類かのCDと聴き比べている時に、とんでもないことに気づいてしまいました。リマスターによって、実際の演奏時間が違っているものがあったのです。それはB面の1曲目、CDではトラック6の「The Fool on the Hill」。ハイレゾ音源と単品の2種類のCDでは全て4分31秒なのに、かつてのMPSのプロデューサーで、すべてのアルバムのプロデュースとレコーディングを行ったハンス・ゲオルク・ブリュナー=シュヴェアによって1997年にリマスタリングが行われたボックス・セット「Magic Voices」に収録されているトラックだけ4分12秒だったのですよ。こんなに短くなっているのは、エンディングの「♪spinning round〜」という部分のループが途中でカットされて本来14回あったものが9回に減っているからです。ここは、同じ音型を何度も繰り返しながら他の声部が入ってきてとてつもないクレッシェンドを演出した後にフェイド・アウトする、というカッコいいところなのですが、「Magic Voices」盤ではその盛り上がりがとてもしょぼくなっているのですよね。これだけのことで、このボックス全体に対する信頼感が、もろくも崩れ去ってしまいましたね。どこかの工事現場みたい(それは「とよす」)。 FLAC Artwork © HIGHRESAUDIO UG |
||||||||||||||
手元に届いたLPの現物は、ずっしりとした重さがありました。プレスの状態もとても良好、特に縁の部分が垂直にカットされていて、厚みが感じられるのがいいですね。カッティングのレベルも高く取ってありますから、サーフェス・ノイズもほとんど聴こえません。もちろん、スクラッチ・ノイズも全くありません。 ジャケットの裏面には、オリジナルのライナーノーツがそのまま印刷されている上に小さなシールが貼ってあって、そこにはこういう表記がありました。 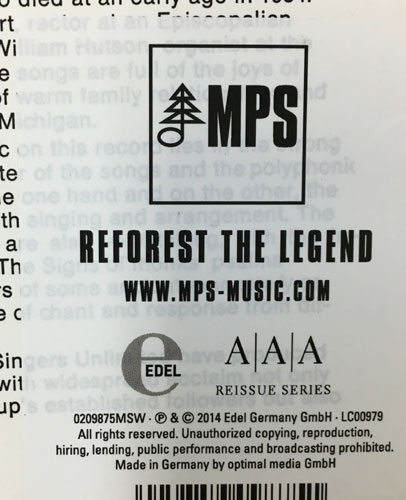 MPS(Musik Produktion Schwarzwald)というのは、1968年にレコーディング・エンジニアのハンス・ゲオルク・ブリュナー=シュヴェアが、それまで属していたSABAレーベルがなくなったために新たに創ったドイツのレーベルでした。オスカー・ピーターソンなど多くのジャズ・ミュージシャンを抱えたレーベルとして、多くの名盤を世に送り出しますが、1983年にブリュナー=シュヴェアはその権利をPHILIPSに売って、別のスタジオを作ります。ですから、シンガーズ・アンリミテッドの音源もPHILIPS、さらにはUNIVERSALへと移ります。1998年にはブリュナー=シュヴェアの手になる先ほどのリマスターCDボックス「MAGIC VOICES」がUNIVERSALからリリースされています。 しかし、2012年になって、Universalはこのレーベルを手放してしまいます。それに対して、2014年にEdelが権利を獲得、新たにリリースを始めます。その際には、CDだけではなく、この「Christmas」のようにLPだったり、さらには「In Tune」と「A Capella」のデビュー・アルバムは88.2/24のハイレゾ音源のような形でリリースされているようです。さらに、なんと38cm/secのオープンリール・テープまで。 今回のLPは、まさに期待通りの音でした。特に外周部分ではCDでは決して味わえないしっとりとしたヴォーカルが再現されています。残念なことに、LPの弱点である内周での歪に対してはないしゅう(なす)すべもなく、CD並みかそれ以下の音でしかありません。このアルバムを含めた残りの13枚のアルバムが、すべてハイレゾで聴くことができるようになれば、本当にうれしいのですが。 このLPで、初めて本来のクレジットを見ることが出来ましたが、アルバムのプロデュースにはブリュナー=シュヴェアはまだ関わっていなかったのですね。つまり、MPSからのリリースは「3番目」ということになっていますが、録音されたのはMPSと契約する前だったことになります。それは先ほどのボックス・セットのブックレットにしっかり書かれてありました。なぜ、ボックスにこれだけが収録されていなかったのか、やっとわかりました。 さらに、アレンジも、ここではジーン・ピュアリング以外の人も行っていたことにも気づきました。キャロルなどは昔からあるグラディス・ピッチャーの編曲、そんな聴きやすさも、このアルバムの人気につながっていたのでしょう。 LP Artwork © Edel Germany GmbH |
||||||
音源に関しては、ユニバーサルと全く同じ手順でマスターが作られているようです。DECCAとPHILIPSは、イギリスのClassic Soundによってオリジナル・アナログ・マスターテープからDSD64に変換されたマスターが使われているそうです。ところが、なぜかDGの場合には、Emil Berliner StudiosからDSDではなく24/192のPCMのマスターが提供されているのだとか。ユニバーサルでのリリースの時にはこちらもDSDだったはずなのに、なぜなのでしょう。それより、この「Classic Sound」というのは、おそらくかつてのDECCAのエンジニアが関係しているスタジオなのでしょうが、ネットで調べるとなぜかその情報が全く見つかりません。不思議ですね。 今回、その中にこのコンドラシンのアルバムがあったので、聴いてみたくなりました。実は、さるオーディオ・ショップの展示会で、試聴用のサンプルとしてこの「シェエラザード」のLPが置いてあったのですよ。それを実際に、最高級のオーディオ機器によって再生するという、なかなか興味深いデモンストレーション、一体どんなすごい音が聴けるのか、と期待したのですが、聴こえてきた音には完全に失望させられました。それは、なんとも薄っぺらで冴えない音だったのです。世の「オーディオ・マニア」は、こんな音で満足しているのでしょうか。お店の人は、おそらく名録音と信じてそのLPを用意したのでしょうが、どうやらその時の何百万円ものシステムからは、それを引き出すことが出来なかったのでしょう。ですから、それがSACDになって目の前にあれば、いったいあのデモはなんだったのか、という検証も含めて聴いてみたくなるじゃないですか。 いやあ、それは、その時に聴いた音とはまるで違っていて、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の美点を余すところなく引き出したというとても素晴らしいものでしたよ。デモの音は全体にのっぺりしていて起伏に乏しいものだったのですが、ここではそれぞれの楽器が輝いています。しかも、それは全体としてはとても繊細な響きとしてのまとまりを見せているのです。弦楽器はあくまで柔らか、コンサートマスターのソロはよく聴くほとんどコンチェルトのソリストのような押し出しの強いものではなく、きっちりオーケストラの中で弾いているという雰囲気が伝わってくるバランスです。もちろん、他の管楽器のソロもでしゃばったところは全くありません。さらに、ホールトーンの美しいこと。 そして、コンドラシンの指揮も、例えばストコフスキーのような脂ぎった演奏になじんだ耳にはちょっと物足りないものの、逆にこのいかにもロシア的な重心の低さからは、この作品の本来の姿がしっかり伝わってくるように思えてきます。とても上品な味わい、おそらく、こういうものは何度聴いても飽きが来るということはないはずです。 カップリングのアルゲリッチとのチャイコフスキーのピアノ協奏曲のジャケットも、ブックレットに忠実に再現されていました。  SACD Artwork c Decca Music Group |
||||||
今回のアルバムは、1964年と1965年にLAの「ハリウッド・ボウル」という、クラシック・ファンにとってもなじみのある野外コンサートホールで行われたビートルズのライブを収録したものなのですが、これは最初からアルバムを作るために録音の準備がされていたものだったのだそうです。とは言っても、当時のことですからそれは単に演奏用のマイクとアンプからの出力を3チャンネルのテープに収めただけのものでした。しかも、そこには演奏以上に大きな音で聴衆の叫び声が録音されていましたから、到底「商品」としては使い物にはならないようなものだったはずです。ですから、録音はされたものの、それはリリースされることはありませんでした。 しかし、それから10年以上経って、もはやビートルズ自体は解散してしまった頃に、ビートルズのプロデューサーだったジョージ・マーティンが、その録音を行ったEMI傘下のアメリカのレーベルCAPITOLから、そのテープを使ってレコードを制作することを依頼されます。マーティンはそれに応えて、エンジニアのジェフ・エメリックとともに様々なエフェクターを使って編集作業を行い、1977年にこの「THE BEATLES AT THE HOLLYWOOD BOWL」を公式ライブアルバムとしてリリースしたのです。  ですから、今回のCDは、それから40年近く経って初めてCD化されたものとなるわけです。しかし、その際には、この前の「1」と同様、ジョージ・マーティンの息子ジャイルズ・マーティンによって、オリジナルの3トラックのテープにまでさかのぼって「リミックス」が行われています。さらに、新たに4曲がボーナス・トラックとして同じ音源から編集されて収録されています。 あいにく1977年盤を聴いたことはないので、このリミックスによってどれだけ音が変わったかを検証することはできませんが、「1」での仕事ぶりを見ていれば、かなりの改善が行われているのではないか、という気はします。実際に、会場の歓声(ほとんど悲鳴)は、全く演奏の邪魔にはなりませんし、演奏もヴォーカルもとても満足のいく音で聴くことが出来ました。逆に、こんなコンディションの悪い録音を、よくぞここまできれいに仕上げたな、という感じですね。 ですから、それぞれのメンバーの声も明瞭に聴き分けることが出来ます。リンゴの1曲はご愛嬌としても、ジョージが2曲もソロを取っているのは意外でした。彼の声はスタジオ録音に見られるような線の細いものではなく、もっと力強く聴こえます。そして、ちょっと意外だったのが、ジョンに比べるとポールのヴォーカルがかなりお粗末だということ。ピッチはおかしいし、かなりいい加減な歌い方だったんですね。その二人ですが「A Hard Day's Night」では、「When I Home~」の部分からはそれまでジョンだったソロがポールに変わっているのですね。この部分は高い音がGまで出てくるので、ジョンには無理だったのでしょうか。スタジオ録音では、最初からダブルトラックなので、ずっと2人で歌っているのだとばかり思っていましたが、このライブでははっきり違いがわかります。 それと、ボーナス・トラックの「I Want to Hold Your Hand」で、歌い出しがきちんとビートに収まっているのにも驚きました。スタジオ録音では、オリジナルでもドイツ語バージョンでも最初のアウフタクトが絶対に半拍多くなっています。反駁できますか? CD Artwork © Calderstone Productions Limited |
||||||
彼は、音楽監督を務めているハンガリー国立フィルと管弦楽曲や協奏曲などの録音を行うだけでなく、室内楽でもピアノ・パートに参加するなどと、ほとんど全ての作品に関与しているというほどの入れ込みようです。ただ、オーケストラ作品で最も有名な「管弦楽のための協奏曲」だけは、同じメンバーでこの企画が始まる前の2002年に録音してしまっているので、まだこのシリーズでの録音はありません。 ただ、ピアノ・ソロのための作品は、新たに録音したのではなく、コチシュがかつて、まだSACDが出来ていなかった頃にPHILIPSに録音していたものを、そのまま使っています。したがって、その分の何枚かだけは普通のCDでのリリースです。 今回は、「合唱作品」の「第1集」というものがリリースされました。それをやはりコチシュが指揮をしている、というのが面白いところです。実は、合唱曲に関しては「2集」の方がすでに2009年にリリースされていました。そちらは児童合唱のための作品を集めたもので、指揮はデーネシュ・サボーでした。 そんな、たった2枚のCDですべてが収まってしまうのが、バルトークの合唱作品です。同じ時代のハンガリーの作曲家コダーイに比べるとそれは何とも物足りない気がします。そもそも、バルトーク自身は合唱の経験はほとんど持っていない人でした。ですから、初期の作品は外部の団体からの依頼によって作られた、というケースがほとんどでした。それは、ハンガリー周辺諸国の民謡を素材にしたものでした。 しかし、「第2集」に入っている児童合唱のための「27の合唱曲」や、このアルバムの男声合唱曲「過ぎ去った時より」などの後期の作品はそのような依頼ではなく、コダーイの勧めに従ってテキストも自分で編集して自発的に作ったものです。 ここでは、2つの合唱団が登場しています。「4つのスロヴァキア民謡」と、「5つのスロヴァキア民謡」はスロヴァキア・フィルハーモニー合唱団、残りの曲はハンガリー国立合唱団が歌っています。混声合唱で歌われる「4つのスロヴァキア民謡」だけにはピアノ伴奏が付きますが、それはクリスティアーン・コチシュという人が弾いています。あいにく、この人は指揮のコチシュとは何の関係もない人のようです。なんでも、同じピアニストの日本人の奥さんと一緒に、仙台市に住んでいるのだとか。 そのピアノの前奏に続いて聴こえてきたスロヴァキアの合唱団は、しばらくぶりに味わう素朴なテイストを持っていました。とても上手、なにしろ、最初のソプラノのチューンは丸ごと終わるまでに完全にカンニング・ブレスで歌いきっていたのですからね。その上で、やはり北欧やイギリスとは全く異なる「泥臭さ」が満載なのですよ。それは、バルトークには絶対に欠かせないファクターでしょう。というか、この「ニュー・シリーズ」全体が、ことさらバルトークの「泥臭さ」を強調しているような演奏で統一されているのでは、と思えて仕方がありません。 他の曲を歌っているハンガリーの合唱団は、もう少し洗練された味がありますが、基本的な「泥臭さ」はやはり健在でした。特に、ハンガリーの音楽に特有な「タ・ター」というリズムは、やはりとても自然に歌われています。 男声合唱のための「4つの古いハンガリー民謡」は、そもそも1910年に作られ、それを1926年に改訂して出版したものですが、ここにはその両方が収録されています。その違いは、なかなか興味深いものがあります。 SACD Artwork © Fotexnet Kft |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |