|
|
|
|
![]()
黒い箪笥。.... 佐久間學
これは、1944年に生まれたデンマークの作曲家、ニルス・ラ・クールのオルガンと合唱のための作品を集めたアルバムです。彼の作品はオーケストラ曲からソロ・ピースまで多岐にわたっていますが、1988年にデンマークアマチュア合唱連盟から「今年の合唱作曲家」という賞を授与されているように、主に合唱曲の作曲家として知られています。 録音が行われたのはコペンハーゲンにあるトリニターティス教会です。ここにはバルコニーに設置されている大オルガンと、小さなクワイア・オルガンの2台を使い分けています。オルガンが合唱の伴奏をする曲ではクワイア・オルガン、オルガン・ソロの作品では、もちろん50以上のストップを持つ大オルガンが使われました。まずは、そのオルガン作品から聴いてみます。 ここでは、それぞれ20分から30分ほどかかる2つの大きな作品が演奏されています。1986年に作られた「オルガンのための3つの間奏曲」は、緩−急−緩という2つの楽章から出来ています。1曲目では、ほとんど無調とも思えるような不思議な音階によるコラールのような穏やかな部分と、まるで鳥の声のようなちょっと動きのある部分とが交互に出てきますが、それはご想像通りまさにメシアンのエピゴーネンです。次の楽章こそはヴィドール風の早いパッセージに支配されていますが、最後の楽章ではもろメシアンの和声が聴こえてくる中で、とても癒される美しいメロディが歌われます。 もう1つの作品は「オルガンのための晩祷」という、全部で9つの曲から成る大曲です。こちらは2003年に作られたもので、もはやメシアンの呪縛からは解き放されて、この作曲家本来のセンスがのびのびと表れているような気がします。それでも、ヴィドール風の部分はかなり残っているので、それは彼自身の個性の反映でもあるのでしょう。最初と最後の曲は、そんなヴィドールのテイストが満載ですが、曲全体の構成はとても巧みで、様々なキャラクターをもった曲が続くので退屈とは無縁です。例えば、6曲目のとてもシンプルなのにしっかり深淵が表現されている曲のすぐ後には、一転して明るさ満載のマーチ風の曲が来る、といった感じです。余談ですが、3曲目では「あ〜る〜晴れた、ひ〜る〜さがり」という「ドナドナ」によく似たメロディが聴こえますし、8曲目の「祈り」という穏やかな曲の中には、ダース・ベイダーのテーマが現れたりします。 合唱は、ほとんどのものが宗教曲で、それこそアマチュアの合唱団で歌うことを想定しているのでしょう、なんとも素直な作り方で、おそらく実際に歌っている時にはとても素敵な気持ちになれるようなものです。「偉大なる指導者来たれり」(2001/2006年)と「良き羊飼いはわが救い主」(2009年)は、それぞれ8小節と4小節のシンプルな伝承曲のようなものを何回も繰り返す(同じハーモニーで)というだけの親しみやすさです。 ただ、女声だけで歌われる「翼」(1978年)だけはこの中では唯一宗教曲ではありません。これはハーモニーもちょっと複雑で、作品としての主張がしっかり込められたものになっています。 オルガンも合唱も、演奏自体はとてもしっかりしたものなのですが、なぜか録音が全然冴えません。オルガンは、特にリード管などが入ってくると音が濁ってきますし、合唱は最初から最後まで混濁がなくなりません。これはコンダクターではなく、エンジニアのプレベン・イワンの責任、この教会の音響に問題があるのか、マイクのセッティングを誤ったのか、彼の今までの録音からは考えられないようなひどい音でした。 CD Artwork © Dacapo Records |
||||||
不幸なことに、おそらく今回の「ゴーストライター」氏は、きちんとした音楽の知識や経験が皆無だったのでしょう。その道のプロの新垣さんの話を正確に理解できないままに原稿に起こしてしまったようなところがかなり見られます。例えば、「ライジング・サン」を作るときに、「依頼主」から「200人のオーケストラで」と言われて面食らった話が出てきます。それは、音楽の現場では当然のリアクションで、せいぜい「100人」もいれば間違いなく「超大オーケストラ」になるのが、この世界の常識です。ですから、その「200人」というのはまさに「アマチュアの発想だ」と新垣さんは言い切っていたはずなのに、いざ実際にスタジオで新垣さんが指揮しているシーンになると、それが突然「200人のオーケストラ」になっているのですよ。これは明らかに現場を知らない「ゴーストライター」氏の勘違い。最悪ですね(それは「ワースト・ライター」)。 そんな体裁はともかく、ここで初めて当事者自身の口から語られた彼の仕事ぶりはやはりとても興味深いものでした。今まで報道されていたイメージでは、依頼主はかなり具体的なイメージを持って新垣さんに「発注」したような感じでしたが、実際にはもっと大雑把な、単に「こんな風にしてくれ」という参考音源を与えることが最大の伝達手段だったようですね。いみじくも、この中で「黒澤明がマーラーの『大地の歌』みたいに作れと武満徹に言った」と語っているのと同じようなパターンなわけです。ですから、依頼者は、実際の「作曲」に対しては何も関与していないということになりますね(コメントなどは逆に邪魔だったと)。 そして、あの、後に「HIROSHIMA」となる「交響曲第1番」を作った時の「本心」には、誰しもが驚いてしまうことでしょう。依頼主からその話があった時には、もしそんなことが実現してしまえば、間違いなく本当のことがバレてしまうと思った新垣さんは、誰も聴こうとは思わないほどのばかでかい作品を作ったのだそうです。ですから、そんな演奏されるはずのないものが実際に広島で演奏されてしまった時には焦ったことでしょうね。もちろん、新垣さんはその初演には立ち会ってはいないのですよ。ですから、以前こちらでその初演の時の指揮者の証言をご紹介しましたが、スコアに指揮者が手を入れた際に激怒したのは、依頼主だということになりますね。そして、新垣さんのスコアは、実は手を入れなければ演奏できないほどのお粗末なものだったということも分かります。 最後に彼がのうのうと「私が行ったことのいちばんの罪は何かと言えば、それは私がワーグナー的に機能する音楽を作ってしまったことでしょう。人々を陶酔させ、感覚を麻痺させるいわば音楽のもつ魔力をうかうかと使ってしまったわけです」と語っていることこそが、彼の最大の「罪」なのだとは思えませんか?彼の作った音楽にそんな力があると思うこと自体が、そもそもの彼の思い上がり。そのような人が、憧れている武満徹ほどの作曲家になれるわけがありません。なれてもせいぜい「HIROSHIMA」をさんざん持ち上げた三枝成彰あたりではないでしょうか。それではあまりに悲しすぎます。 Book Artwork © Shogakukan Inc. |
||||||
いつもの通り、ロトたちのスタンスは演奏された当時の楽器を使用するというもの、もちろん弦楽器ではガット弦が使われています。ブックレットのメンバー表によると、その編成は12.10.8.7.5、これは、現在のオーケストラがこのような作品を演奏するときの編成よりかなり少なめです。 最初の曲は、マスネの「狂詩曲『スペイン』」です。この曲こそは、例えば16型の大編成の弦楽器による「スペクタクル」な録音が巷にあふれていますね。そういうものを聴きなれた耳にはどのように感じられるのでしょう。しかし予想に反して、その音は全く別の意味での「スペクタクル」なものでした。それは、ありがちな圧倒的なパワーで聴く者を興奮させるというものではなく、もっと細かいポイントでの魅力的な音が至る所から伝わってきて、その集積が結果的にとてつもないインパクトを与える、という、とても「賢い」やり方で迫ってくるものだったのです。 まずは、最初の弦楽器のピチカートだけで、すでにその音の虜になってしまいます。それは、まさにガット弦ならではの甘い音色と、温かい発音を持っていました。それがアルコになると、なんとも繊細なテクスチャーで耳元をくすぐります。金管楽器も、最も大切にしているのは音色であることを意識していることが明確に伝わってくる吹き方、こういうのであれば、このサイズの弦楽器でもマスクされてしまうことは決してありません。木管楽器も見事なアンサンブルで的確にアクセントを演出しています。もちろん、今では絶滅した「バソン」の鄙びた音も、ここでは健在です。そして、最も驚かされたのがハープの不思議な存在感です。楽器は初期のエラール、もちろんダブルアクションで、メカニック的には現在のものと変わりがありませんが、そのちょっと舌足らずな優雅さはこの頃の楽器にしか備わっていないものです。 そして、それぞれのパートに生き生きとしたスポットライトをあて、彼らが自発的に音楽を作る手助けをしているのが、指揮者のロトです。その結果、オーケストラ全体はロトの思い通りの方向に向かって動き出すのですから、これほど自然なものも有りません。かくして、スペインのエキゾティシズムとフランスのエスプリが融合した素晴らしい音楽が出来上がりました。 続く、シャブリエの「『ル・シッド』からのバレエ組曲」は、スペインが舞台のオペラから、グランド・オペラならではのバレエのシーンに演奏されるスペインの舞曲だけを集めたものです。名前だけは聞いたことがあってもなかなか聴く機会のない曲ですが、こんな風に情熱的に演奏されればいっぺんで好きになってしまいます。4曲目の「オーバード」冒頭のピッコロの軽やかなイントロは、まるで「スーダラ節」のように聴こえますし、6曲目の「マドレーヌ」のフルートとコール・アングレのソロの掛け合いは、心に染みます。 もう少し先のラヴェルやドビュッシーの時代になると、スペインとの関わり方は微妙に変わってきているようです。そんな中で、「道化師の朝の歌」の最初の喧騒が終わってバソンのソロのあとに広がる不思議なオーケストレーションの世界(弦楽器のハーモニクスの中をさまよう金属打楽器たち)では、またもやロトが作り上げたまるで夢のような極上のサウンドに打ちのめされることになります。ドビュッシーの「イベリア」の最後の曲で現れる鐘の音も、別の世界から聴こえてくるもののよう。 全てがコンサートのライブ録音で、それぞれ会場が異なっています。ただ、どの曲をどこで演奏したかというクレジットがないのは不親切。 CD Artwork © Actes Sud |
||||||
今ではライヒの古典的な「名曲」となったこの作品は、文字通り「18人」の演奏家が楽譜には指定されています。その内訳は2本のクラリネット(バス・クラリネット持ち替え)、4台のピアノ、6人の打楽器(3台のマリンバ、2台のシロフォン、1台のビブラフォン)、ヴァイオリン、チェロ、4人の女声(ソプラノ3人、アルト1人)です。これ以外にも、打楽器奏者はマラカスを演奏します。そんな演奏家たちがステージで並んでいるところをデザインしたのが、このアルバムのジャケットです。確かに18人分の「丸い頭」があって、ピアノが4台、木琴らしいものが6台あります。あとは、クラリネットの人は「棒」をくわえていますし、ヴァイオリンとチェロが持っている弓によって区別されているのも、芸が細かいですね。もちろん、ただ手を広げているだけの人はヴォーカルです。 ところが、今回のCDの「音楽家」の数を数えてみると、「アンサンブル・シグナル」というアメリカの若い演奏家が集まって2008年に設立された団体のメンバーが、楽器を演奏する人だけだと16人なので、エキストラで他の団体から応援が加わっているのですが、それが4人もいるのですよ。合計で「20人」ですね。ちょっと多すぎません? ライヒ自身が加わった最初の録音(ECM/1976年)では、もちろん演奏家は18人しかいません。ところが、メンバー表を見てみるとヴァイオリン、チェロ、クラリネット奏者以外の人たちは、それぞれ別の楽器を演奏したりしているのですね。ライヒ自身もピアノとマリンバを演奏しています。なんと、ヴォーカルの人までピアノに「持ち替え」ていますよ。ということは、このあたりの楽器は、最初から最後まで同じ人が演奏するのではなく、途中で他の人に替わったりするということになりますね。確かに、ピアノなどはほぼ1時間にわたって延々と同じリズムで鍵盤をたたき続けているのでしょうから、そこで緊張を失って演奏が雑になってしまうことを避けるために、適宜「ローテーション」を行うのは必要なことかもしれません。それを、もっと「楽に」するために、もう2人加えたってかまわないじゃないか、という、今回の陣容なのでしょうね。休んでいる間はローションを塗って疲れを取ります。 余談ですが、そのECM盤は、当然初出はLPでしたが、CDの黎明期にいち早くCD化されています。ところが、この頃のCDはろくにマスタリングも行われていなかったものですから、この曲1曲が「トラック1」になっていました。一応連続して演奏されるようにはなっていますが、明らかに14の部分に分かれている音楽ですから、これは困ったものです。たしか、2003年に別の団体が演奏したものがHUNGAROTONからリリースされた時も、同じような途中で切れ目が入っていないマスタリングでしたね。しかし、今ではそのECM盤もリマスタリングが施されて、きちんと14のトラックに分かれています。もちろん、今回のCDもこの形、今までは漠然とビブラフォンのパターンで「セクション」が変わっていたのを認識していたのですが、これでその切れ目がはっきり目で見て分かるようになりました。 そうなってくると、トラック・ナンバーが変わったのを見て、それが新たな「フレーズ」の始まりだと分かり、それがどんどん「成長」していくさまを、つぶさに眺めることが出来るようになります。ここでは、そんな変わり目での演奏家たちの「仕切り直し」の気迫までがまざまざと伝わってくるという、新鮮な体験が味わえます。 CD Artwork © Harmonia Mundi USA |
||||||
しかし、今では2014年に執筆され、2015年の2月にドイツで刊行された彼の著作が、その4か月後には日本語訳で登場するほど、日本のオペラ愛好家、あるいはオペラ製作者にとっては重要な存在となっていたのですね。実際、彼は新国立劇場が作られた時にはブレインとして参加していたり、その新国立劇場のみならず、他のカンパニーでも実際に演出を手掛けるなど、日本のオペラ界とはかなり深いところでつながりを持っていますから、これは当然のことなのでしょう。彼も日本のパンツを愛用しているのだとか(それは「モンペ」)。 この本の原題は「Opernschule für Liebhaber, Macher und Verächter des Musiktheatres」、直訳すれば「音楽劇場の愛好家、製作者、そしてそれを軽蔑している人のためのオペラの学校」となるのでしょうが、これを訳者は「オペラの学校 すべてのオペラ愛好家、オペラの作り手、そして、オペラ嫌いのために」と訳しました。しかし、タイトルの後半はなぜか帯(↓)に印刷されているだけで、それを外してしまうと表紙にはもちろん、本文のどこにもないようになってしまいます。なんか変。 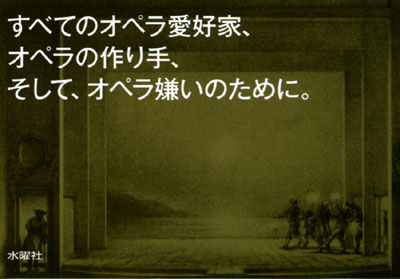 「嫌いなのは機関、すなわちオペラ作品をそれ相応に上演しようとして、400年もの間、例外はあるものの、その作品の価値を低下させている活動です」そんな、ほとんど逆説とも捕えられかねない言い方のような、非常に難解で意味の捕えにくい文章が最後まで続くのですが、どうもそれは著者の責任ではなく、もしかしたら意味も分からないで直訳に走ったのではないかと思えるほどの、極めて劣悪な日本語訳のせいなのかもしれません。例えば、「上拍」という訳語。これは「Auftakt」を訳した言葉で、確かに楽典の教科書などには頻繁に登場する単語ではありますが、その実体を理解できる人はどのぐらいいるのでしょう。そのまま「アウフタクト」と訳せば、その理解度は格段に上がるはずですが、それがやはり特殊な音楽用語であることに変わりはないので、適切な注釈を加えるべきだったのでは。それが使われている章のタイトルが「『トリゾフレニア』による上拍」ですよ。いったい何のことかわかりますか? そのような、まるで読者のことを考慮していないひどい文章を、それなりに理解しようと努めながら読み解くという作業も、時には刺激的な体験です。そんな「苦行」の果てには、間違いなく著者の理想とするオペラ上演の姿が見えてくることでしょう。ここでは、彼のキャリアのスタートは舞台演出家ではなく音楽家(チェリスト)だったということが、重要なポイントです。彼は、スコアを完璧に読む力を備えているのです。したがって、歌手がステージで行わなければいけないことは、全て音楽によってきめられている、と主張しています。これはかなりショッキング。だとしたら、今世界中のオペラハウスで上演されているオペラの演出は、ほとんどが間違ったものだ、ということになるのでしょう。なんと過激なことを。 ドイツのオペラハウスのライブ映像を見ていると、エンドクレジットのスタッフの中によく「ドラマトゥルク」という役職が登場します。これも、ハンペ先生による丁寧な説明を読むことが出来ますから、いったいどんなことをやっている人なのか、詳しく知ることが出来るはずです。これは、かなり有益。 Book Artwork © Suiyosha |
||||||
メシアンの合唱作品を集めたこのアルバム、タイトルは「愛と信仰」です。合唱に限らず、この2つの言葉はまさにメシアンの音楽の核心をなすものです。彼の合唱作品はそんなに多くはありませんが、その中の代表的な「神の降臨のための3つの小典礼」と「おお聖餐よ!」そして「5つのルシャン」が演奏されています。 「小典礼」は、3つの部分から成る大規模な作品です。合唱とは言ってもパートはソプラノだけで、それもほとんどユニゾンで歌われています。そこにピアノとオンド・マルトノ、そして多くの打楽器を含む室内オーケストラが加わります。ここにはもちろんさっきの「愛と信仰」はてんこ盛りですが、第1曲目などではピアノ・ソロがのべつ「鳥の声」を模倣しているというのは、メシアンの常套手段です。それぞれの曲では、プレーン・チャント風のゆったりとした部分とリズミカルな部分とが交互に現れ、わかりやすい表現の変化が楽しめます。そして、合唱パートがシンプルな分、オーケストラが豊穣な和声と色彩的なオーケストレーションで音楽全体をとても立体的なものに仕上げています。 そんな、聴きどころ満載で、それこそ「トゥーランガリラ交響曲」に匹敵するほどのキャッチーな曲なのに、なぜか録音にはそれほど恵まれていません。おそらく、今までに出たもので入手可能なのはバーンスタイン盤(1961年/SONY)、クーロー盤(1964年/ERATO)、エドワーズ盤(1990年/EMI)、ナガノ盤(1994年/ERATO)、チョン盤(2008年/DG)ぐらいなものでしょうか。 このSACDでは、ソプラノが楽譜通りの18人で演奏されています。デンマーク国立ヴォーカル・アンサンブルのメンバーだけでは足りないので、普段はオーケストラの中の大編成の合唱として活躍しているデンマーク・コンサート合唱団のメンバーが加わっています。この合唱が、それぞれの個性を主張して、全体としてかなり骨太のサウンドを聴かせてくれるのはいいのですが、ちょっとピッチに不安のある人が何人かいるために、メシアンならではの精緻なハーモニーに収まりきらない部分が出てきているのが問題です。ですから、ずっとユニゾンだった合唱が曲の最後でパートが分かれると、途端に音が濁ってとても聴きづらくなってしまいます。でも、そんなに頑張らないで歌っている3曲目の静かな部分では、合唱と弦楽器、そしてオンド・マルトノが歌いかわすという場面がとても印象的です。 「ヴォーカル・アンサンブル」だけで演奏している後の2曲は、非の打ちどころのない名演です。「聖餐」のハーモニーはこの世のものとも思えないほどの澄み切った美しさですし、「ルシャン」には逆に荒っぽさまでも魅力と感じられるようなすごさがあります。 それを助けるのが、名エンジニア、プレベン・イヴァンによるDXD(32bit/352.8kHz)のサウンドです。これはまさに理想的なア・カペラの合唱の録音。実は「小典礼」は会場もエンジニアも、そして録音フォーマット(32/88.2)も全く別、合唱が濁っていたのはそのせいだったのかもしれません。 SACD Artwork © Naxos Global Logistics GmbH |
||||||
そのプロジェクトの一環として、ヤスィンスキイさんは2014年10月に、仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団との共演のために来仙しました。本番の1週間前にオーケストラとのリハーサルを行ったほかに、市内の小学校を巡ってミニ・リサイタルを行うなど、精力的に演奏を披露しています。小学校の校歌をヤスィンスキイさんの伴奏で生徒全員が歌う、といったようなサービスもあったそうですね。 仙台ニューフィルと演奏したのは、ラフマニノフの「パガニーニの主題によるラプソディ」でした。この難曲を、彼は軽々と弾ききっていましたね。その模様は、こちらで見ることが出来ます。オーケストラがそのグルーヴにちょっとついていけてなくて足を引っ張っているところがありますが、彼のピアノの素晴らしさは伝わってくることでしょう。 この演奏の後に、アンコールとしてドビュッシーの「エチュード第11番」が演奏され、さらに盛大な拍手で呼び戻されてピアノに座ったヤスィンスキイさんは、お客さんに向かって、「20世紀の偉大なピアニストではあるが、誰もその作品を聴いたことが無いというヨゼフ・ホフマンの『マズルカ』を演奏します」と言って、「マズルカ Op.16-1」を弾きはじめました。実は、彼はこのコンサートの半年前に、ポーランドのスタジオでその「ホフマン」のピアノ曲をアルバム1枚分録音していたのです。それは、世界初録音を含む、とてもレアなアルバムとなりました。仙台で演奏されていた「マズルカ」は、おそらく日本初演だったはずです。 ポーランドのクラクフ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国クラクフ大公国)の近郊に1876年に生まれたヨゼフ・カシミール・ホフマンは、まさに「神童」として、幼少のころからピアニストとして活躍していました。同時に彼は作曲にも天才ぶりを発揮し、なんと4歳の時に最初の作品「マズルカ」を作曲しているのです。そしてその6年後には、このアルバムにも入っているロ短調とニ短調の「マズルカ」を作曲しています。この楽譜は、もう1曲ニ長調の「マズルカ」とともに、当時彼が演奏していた他の作曲家の作品と一緒にまとめられてアメリカで出版されました。その表紙を飾っていたのは、ピーター・パンのような衣装の、かわいらしいホフマン少年のグラビアです。先ほどの作品番号のついた「マズルカ」は、それからさらに5年ほど経ってから作られています。 これらは、いずれも同郷のショパンの影響を色濃く受けた仕上がりになっています。さらに、1893年に出版された4楽章から成る「ソナタ」では、あちこちにシューマンのピアノ協奏曲のモティーフのようなものが顔を出しています。しかし、1903年に出版され、レオポルド・ゴドフスキーに献呈された「4つの性格的スケッチ Op.40」では、ほのかに印象派風の半音階なども見え隠れする、彼独自の個性を感じることが出来ます。 ヤスィンスキイさんは、一音たりともおろそかにしないテクニックと溢れるほどの歌心をもって、これらの作品に命を吹き込んでいます。 CD Artwork © HNH International Ltd. |
||||||
ですから、いつもチェックしているNAXOSのFacebookで、まるできゃりーぱみゅぱみゅのようなふわふわのドレスに身を包んだヴァイオリニストの姿が紹介されているのを見た時には、ついにここまで来たか、という思いに駆られてしまいました。彼女の名前は寺沢希美(のぞみ)さん、こうなると、単に「きれい」なだけではなく、ほとんど「アイドル」ではありませんか。その記事では、CDが出ただけではなく、24/192のハイレゾ・データまでリリースされているのだとか。あのNAXOSが本気になって売り出そうとしていることが、まざまざと伝わっては来ませんか? そのCDはピンクを基調にしたアートワーク、ジャケットでヴァイオリンを抱えて微笑んでいる寺沢さんの姿はまさに「天使」です。あくまで無垢なまなざし、わずかに開いた口元の奥に見える白い歯には、はかない愛しさが宿っています。  せっかくですから、CDの方も聴いてみましょうか。タイトルが「Lovely 恋音」というぐらいですから、「愛」とか「恋」をテーマにした曲を集めたものだと思ってしまいますが、曲目を眺めてみるとあんまり関係ないようなものも並んでいます。それぞれの曲の解説を読んでみると、その中に「愛」という言葉が入っているのは1曲だけ、「恋」に至っては「恋人」という形でかろうじて1曲に使われているだけです。この解説を執筆した篠田さんというライターさんは、逆に「婚約者が元カノと逢引」などと、かなりどぎつい表現を使ったりして、このアルバムのコンセプトにちょっと背を向けているような感じすら抱いてしまいます。それよりも、こういうアルバムにはよく登場する「カッチーニのアヴェ・マリア」を、正しく「ウラディーミル・ヴァヴィロフ作曲『カッチーニのアヴェ・マリア』」とかっちーり決めつけているのが潔いですね。 しかし、そんなちょっと「いじわる」な解説にめげることはなく、彼女の演奏はまさに「アイドル」のスタンスを貫き通したものでした。おそらく彼女が目指したであろうものは、「誰にでも親しめる音楽」だったのではないでしょうか。音色はあくまで澄み切っていますし、メロディ・ラインはあくまで爽やか、そこには「ルバート」や「アゴーギグ」などといったいやらしい「表現」は微塵も見られません。歌手で言えば、ヘイリーとか、年はとっていますがサラ・ブライトマンと共通する「安らぎ」のようなものに満ち溢れた演奏です。 ところで、東京あたりにお住まいの方はご存じないでしょうが、東北地方のテレビでは「三八五引越センター」というところがとってもシュールなCMを流しています。太ったソプラノ歌手が現れて、朗々としたベルカントで「だいじょ〜ぶ〜」と歌いだす、というものなのですが、どこが「だいじょうぶ」なのか、なぜ引越しにソプラノなのかがいまいちわかりません。そのソプラノの陰で、こちらも意味不明のヴァイオリンを演奏しているのが、この寺沢嬢なのですよ。このド田舎感満載のCMと、今回のキャピキャピなCDとのギャップには驚かされます。いや、もっと驚くのは、実年齢から20歳は若く見せている、その特殊メークなのかもしれません。 CD Artwork © Naxos Japan Inc. |
||||||
今回のジョージ・ロックバーグという、1918年に生まれて2005年に亡くなった、まさに「20世紀」をまるまる生きたアメリカの作曲家が果たして「クズ」なのかどうかは、聴いてみるまで分かりません。この世代の作曲家の常として、スタート地点が「無調」や「セリエル」だったというのはお約束、しかし彼の場合は1964年にまだ10代だった息子を亡くしたことにより、そのような技法をきっぱり捨てて、「ネオ・バロック」や「ロマンティック」の方向に転向するというのですから、なんともわかりやすい「変節」ぶりです。 ですから、このアルバムに収められているすべて1970年以降に作られた「フルート作品」では当然そのような作風に染まっていると思ってしまいますが、実はそうではなく、かなり「前衛的」なテイストが強い「ハード」な作風が感じられてしまいました。なかなか一筋縄ではいかないところが、「現代作曲家」のおもしろいところです。 タイトルには「フルート作品全集第1巻」とありますが、この作曲家がフルートのために作った作品は「ほんの一握り」しかないそうなので、あと1枚ぐらいで「全集」が完結してしまうのでしょうか。そもそも、今回のアルバムのメインの「Caprice Variations」(1970年)にしても、オリジナルはヴァイオリン・ソロのために作られたものでした。これは、有名なパガニーニの、やはりヴァイオリン・ソロのための「24のカプリース」と同じテーマを使って作られた51曲からなる変奏曲から、ここでフルートを演奏しているクリスティーナ・ジェニングスが21曲を選んで2013年にフルート・ソロのために編曲したものなのです。彼女がそこまでしてロックバーグの作品を演奏したかったのにはわけがあります。彼女の父親のアンドリュー・ジェニングスは、ロックバードが多くの弦楽四重奏曲を献呈した「コンコード弦楽四重奏団」の第2ヴァイオリン奏者だったのです。彼の演奏によるヴァイオリン版の「Caprice Variations」も全曲Youtubeで見ることができるぐらいですから、まさにロックバーグの音楽は彼女の「少女時代のサウンドトラック」だったのですね。 この作品は、パガニーニのテーマだけではなく、いくつかの曲は有名な作曲家のある作品を下敷きにして作られているという、手の込んだものです。例えば、フルート版では「10番」になっているオリジナルでは「21番」にあたる曲などは、「ベートーヴェンの交響曲第7番の終楽章風パガニーニ」になっています。そのほかにもマーラーやバルトーク、さらにはシェーンベルクと、「元ネタ」を知っていればなかなか笑えます。最後の曲はパガニーニのオリジナルをそのまま、というのが「オチ」ですね。 ジェニングスの編曲は、時折重音、ホイッスルトーン、キータッチ、フラッタータンギングなどの「現代奏法」を織り交ぜて、おそらくヴァイオリンよりも高い難易度が要求されているのではないでしょうか。それを、芯のあるぶっとい音でサラッと吹き上げているところが、素敵です。 そのほかに、「浮世絵」というタイトルの作品が2曲演奏されています。フルートとピアノのための「浮世絵3」(1982年)は、「Between Two Worlds」というサブタイトルが付いていて、ところどころに「日本風」の五音階が出てくることで、その意図が明確になります。ただ、全体的には「無調」のテイストも満載の暗〜い曲、というイメージです。 もう一つの「浮世絵2」は、フルートとハープのための「Slow Fires of Autumn」(1979年)です。こちらはもろ「ジャパニーズ」なテイストで、まるで尺八と筝の合奏のように聴こえます。なんたって、五音階どころか、最後は「五木の子守唄」ですからね。このメロディは、いつ聴いても和みます。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |
||||||
クリュイタンスといえば、なんといってもかつての「暮らしの手帖」で1963年から始まった「レコードの商品テスト」の第1回目で、最高位を獲得したレコードの指揮者、という印象が強く残っています。その時のテーマは「運命/未完成」。今では考えられないようなこんなカップリングのレコードが、世の中で一番人気があった時代です。もちろん、この2曲は録音年代も違いますし、最初にEMIから出たときにはそれぞれ別のアルバムだったものを、日本盤ではこんなカップリングで発売したのですね。ここで、録音担当の菅野沖彦さんは、特に録音が素晴らしいと、高得点を与えていましたね。 その「未完成」の方も、今回のシリーズの中に入っていますが、聴いてみたのはベートーヴェンの9つの交響曲だけの5枚組のボックスです。 ベルリン・フィルが最初に一人の指揮者とスタジオ録音で作ったベートーヴェン全集として有名なこのクリュイタンス盤は、ステレオ録音が実用化されたばかりの1957年12月に始まり、1958年3月、1958年12月、1959年4月-5月、1960年3月という5つの時期のセッションを経て完成されました。その間には、首席フルート奏者が交代していることが注目されます。フルトヴェングラーの時代からそのポストにあったのはオーレル・ニコレですが、彼は1959年に退団して、1960年からはカールハインツ・ツェラーがそれを引き継いだ、と言われています。確かに、この中で1957年と1958年に録音された1、3、5、8、9番は間違いなくニコレの音ですし、1960年の7、8番ではツェラーの音が聴こえてきます。ニコレはあくまで格調高く芯のある音、「9番」では神々しいほどの演奏を聞かせてくれています。それに対してツェラーは同じく強靭な音ですが、そこには多少砕けた味わいも感じられます。問題はまさにニコレが退団したとされる1959年の録音分です。4月に録音された2番はほぼ間違いなくニコレなのですが、5月に録音された4番は、ちょっとニコレではありえないようなユルさがあちこちで見られます。それにしても、フルート奏者一人のせいで、オーケストラ全体の味が変わってしまうのですから、すごいものです。もちろん、この10年後には、もっとチャーミングなフルーティストが入団して、このオーケストラの音色をガラッと変えてしまうのですが。 これらの音源は、マスターテープから24/96でPCMにトランスファーされたデータを、あの杉本一家さんがSACDとCDにマスタリングを行ったものです。当然のことですが、それぞれのレイヤーによって別々のマスタリングが施されています。SACDではそのままDSDに変換すればいいのでしょうが、CDでは多少ハイを上げて、SACDに迫ろうという「小細工」が必要なのでしょう。 SACDで聴いてみると、1957年に録音された「9番」などは、さすがにテープの劣化がかなり進んでいて、ドロップアウトは数知れず、さらに第4楽章の後半では音声データそのものがかなり劣化している状態がありありとわかります(烈火のように)。しかし、1960年のものになると、弦楽器の密度が高まり、細やかな肌触りまでちょっと前のデジタル録音ではとてもかなわなかったような繊細さで音楽を再現してくれています。 SACD Artwork © Warner Music Japan Inc. |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |