■第3展示室 三河線の交換駅はなぜ右側通行か?
(注) 拡大画像はJava Script を使用しています。ポップアップ自動カットを停止してご覧下さい。
●島式ホームが多い路線
 日本では通常電車は左側通行ですが、北新川で撮影した写真を掲載して三河線には右側通行の駅が存在することを改めて認識しました。
日本では通常電車は左側通行ですが、北新川で撮影した写真を掲載して三河線には右側通行の駅が存在することを改めて認識しました。
初めてそれに気づいたのは1979年、豊田市-知立で暫定的に運用を開始した豊田線用の100系に乗りに行ったときです。竹村または若林であったと思われますが、友人と「なぜ右側に入るんだろう?」と話していたら、それを聞いていたおじさん(名鉄の社員の方と思われる。)が、「反対側に入れると運転士から踏切の見通しが悪くなるからだよ。」と教えてくれました。確かに三河線では駅舎からホームへ行くのに踏切を渡らねばならず、その時は納得していたと思いますが、改めて考えてみるとそれだけではないような気がしてきました。
単線が主体の三河線ではかつてタブレット閉塞が行われ、ホームでは駅員さんが運転士さんにタブレットを受け渡す光景が見られました。当線は島式ホーム(線路2本の間にホーム1本)が多いのが特徴ですが、名鉄の電車は一般的な左側運転台であるため、右側の線路に入った方がタブレットの受け渡しが楽になります。ましてやそれが通過電車だったら・・・。
●通過列車のタブレット授受
三河線では1959年に現在の知立駅が完成したことによって入れ換えを行うことなく本線と直通運転ができるようになり、1966年からは三河線内でも特急運転が開始されました。おそらく交換駅も通過する駅があったと思われ、小学生の頃乗った3700系の特急は重原駅を通過したと記憶しています。
停車列車ならば多少不便でも運転席を立って反対側にいる駅員さんにタブレットを渡すこともできたと思われますが、通過電車ではそうはいきません。そこで、通過列車へのタブレット授受を考慮して島式ホームの駅の一部が右側通行になっていた可能性があるのではないでしょうか。
●ご投稿ありがとうございました。
沿線ご在住の皆様を中心に情報をお寄せいただき、当時の三河線の様子が少しずつに見えてきました。既に最初のアップから1年半が経過しいていますので、その後わかったことも踏まえてここでまとめをしておきたいと思います。まとめができるのはご意見、情報をお寄せ下さった皆様のお陰であり、それに敬意を表し、まとめはその下に記載しました。
■お寄せいただいた情報
●No.12
 三河線の通過授受についてお調べのようでしたので、以前私が書いたプログ(閉鎖)が参考なればと思います。(08.7.13)
三河線の通過授受についてお調べのようでしたので、以前私が書いたプログ(閉鎖)が参考なればと思います。(08.7.13)
拝見してあっと声を上げてしまいました。吉浜駅における通過授受の決定的シーンですね。ついに決定的な記録をご紹介することができ、たいへん光栄です。三河線でこのようなシーンを捕らえていた方がいらしたことに驚くと共に、インターネットを通じてそれに出会うことができたことに感謝する次第です。たいへん貴重な写真のご紹介をありがとうございました。
なお、三河湾174号様には本稿で写真を使わせていただける旨ご了解をいただいております。こちらについてもお礼申し上げます。(碧)
●No.11
現在、関西在住の元刈谷市民、もげと申します。1980年頃の小垣江駅の様子の記憶(曖昧です)。
知立方向への電車がホームへ進入しかけで駅長にタブレットを渡して所定位置に停止(駅長室から近いので停止前に受け取り?)。高浜方向への急行がやってきて「停止」し(ドアは開けず)駅長とタブレットを交換してすぐ発車していたような覚えがあります。
それから数年後(1984、5年位?)に、ホーム高浜方向端(駅舎側)にタブレット投げ込み用の釣り竿状の竹の棒(先端が列車がやってくる刈谷方向に曲がっていて細く、色は踏み切り棒と同じ様だった気がします)が設置されました。
刈谷方向からの列車は低速で構内へ進入し、知立方面に向かう通過待ち運転士からタブレットを走行しながら受け取り、受け取ってすぐホーム通過終了時に刈谷市駅までのタブレットを釣竿に投げ入れ、駅を通過。
駅長が先程の刈谷方面への運転士に渡して刈谷方面発車、という段取りに見えました。
当時小学生だったのでタブレットの意味がわからずボーっと見ていただけですが、皮製のリングのやりとりの記憶なので、多分そういう事かと思います。
ちなみに刈谷駅方向への列車は必ずホームで停止していました。(種別に関わらず)
今でも、刈谷駅方向への列車が先着し、高浜方向の列車が到着して発車になっているのは、その名残かも知れません。
ちなみに止まりそうな通過「急行」に意味あるのかと思っていたら、数年で急行が無くなった覚えがあります。(08.7.12)
。
私も三河線のタブレット交換は重原や小垣江で見ているはずなのですが、全く記憶がありません。小学生の頃とのことですが、きっと興味深く見られたのでしょうね。
ご記憶では1980年頃、小垣江駅では通過授受はなかったということですね。知立方面が停車前にタブレットを受け取るのは、きっと歩く距離を減らすためでしょう。長くても4両とはいえ、列車毎であればかなりの距離になったはずです。刈谷方面の列車は急行でも停まったとのことですが、なぜだったのでしょうね。
確かに今は刈谷方面行きの電車が先に着いて待っていますね。小垣江駅は刈谷市側の複線部分が長くなっています。これは河川改修工事の際、嵩上げによってポイントが勾配上に来てしまうため、それを避けてかなり刈谷市寄りにポイントを設置しただめだそうです。碧南行きが複線区間に入れば物理的には発車できるはずですが、律儀にも到着を待っているため、踏切で必ず2列車待たされる地元の人たちはいつもやきもきしているようです。(碧)
●No.10
 西尾線三河線のHPのリンクをたどり、こちらのホームページを拝見させて頂きました。電車が「好き」というわけではないのですが、私が通学に利用していた三河線の情報がいろいろと載っていたので、フムフムと拝見させていただきました。
西尾線三河線のHPのリンクをたどり、こちらのホームページを拝見させて頂きました。電車が「好き」というわけではないのですが、私が通学に利用していた三河線の情報がいろいろと載っていたので、フムフムと拝見させていただきました。
三河線の交換駅はなぜ右側通行か?という設問を読み、次のことを思い出しました。(役に立つものかまったく見当がつきませんが、報告しておきたくなってしまいました。)
1年前のことですが、大学に登校する際、三河線 寺津駅 6時38分発に乗って三河平坂で対向電車待ちをしました。確か進行方向、ホームの「右側」で待っていました。また、対向電車の乗務員さんが革でできた丸いリングを交換していたのを覚えています。なんだろうなーと、当時、見ていました。
「三河線の交換駅はなぜ右側通行か?」のお答えにまったくなっていませんが、何かのお役に立てばと、お節介メールを送信させていただきました。(02.10.16)
ご覧になったのがまさにタブレットですね。碧南-吉良吉田の非電化区間では交換列車のある時間帯のみ三河平坂でタブレット交換が見られ、日中は碧南-吉良吉田が1閉塞区間(途中駅での交換なし)になるようです。
もともと特急、急行列車の通過がない区間も右側通行になっているということは、通過列車のタブレット授受が右側通行の理由ではないということのようですね。(碧)
●No.9
名鉄三河線特急のタブレット授受ですが、新たな資料(?)が見つかりました。「名鉄の廃線を歩く」(JTB キャンブックス)に掲載されている「三鉄ものがたり」です。著者は新實実氏で、かつて名鉄に勤務されていた方です。
それによれば、特急運転が開始されて以来、タブレットの授受には苦労を伴い、落としたり、受け損なったりのトラブルが何度もあったとのことです。
そこから推測すると、通過駅では走行したままタブレットの授受を行っていたことになります。名鉄では国鉄のような窓ガラス保護網が取りつけられま せんでしたので、おそらく電車は最徐行で通過したのでしょうが、やはり時には窓ガラスを割ってしまうこともあったようです。
著者の新實氏は現業機関にいらした方だそうですので、まず間違いないと考えてよさそうです。(02.9.24)
走行中にタブレットの授受をしていたことを証言する資料ですね。伝道師さんがご紹介下さった三河八橋はホームの反対側に授受器があったとのことですのが、手渡しの時代はどうしていたのでしょうか?(碧)
●No.8
幼い頃、吉浜駅のホームから駅舎へのスローブが階段であった頃の話です。当時の急行電車で吉浜か小垣江を通過する際、すぐに止まれそうなスピードでタブレットを授受していたと思いました。それで、HLおなじみのノッチ入れる衝撃が来て加速していったと思います。確か、親に急行でもゆっくりと走って行くんだねと言った覚えがなんとなくありました。(02.9.2)
中学生時代の友人が小垣江駅近くに住んでいて、当時駅で電車を眺めたことがあると思うのですが、全く記憶がありません。Beaverさんは速いはずの急行が最徐行するのがよほど印象的だったのでしょうね。(碧)
●No.7
はじめまして。右側通行の件、大変興味深く読ませていただきました。
ところで、知立〜梅坪間で右側通行なのは若林・竹村と高架化前の梅坪だけです。土橋・豊田市は別格ですし、三河知立はスプリングポイントを使っていませんでした。(豊田市・三河知立は選択使用)そこで、三河八橋ですが、島式ホームの構内踏切を進出側にする原則?からすれば当然左側通行になるレイアウトになっています。
1971年頃(最近豊橋鉄道で引退した7300系が新造された頃で、三河線でも運転されていました。)豊田市&碧南〜弥富系統の本線直通特急が定期で設定されていました。当時はまだ通票閉塞でしたから、通過となる八橋はどうしていたか?
実は駅舎寄りの線路の外側に授受器が設置された(されていた?)のです。確かにこうすれば左側の運転席から直接タブレットの受け渡しができますよね。駅員さんは通過列車のたびに線路を渡ってタブレットの設置・回収をしていました。挙母線の廃止で島式ホーム1本となった上挙母も左側通行になっていますが、通票閉塞の時代に通過列車の設定は無かったと思いますので、三河八橋は例外中の例外だったわけです。
こうしてみると、右側通行の理由はタブレットの授受のしやすさもありますが、構内踏切の保安度の方がさらに優先されていたことになりますね。
蛇足ですが、秩父鉄道も島式ホームの右側通行をやっており、'93年頃まで駅員が手で通過列車の通票を受け取っていました。構内踏切も進出側に設定。独特の背の低い腕木信号機が健在でした。(02.7.24)
ホームがない側にタブレット授受器が設置された駅があったのですね。そうなるとおっしゃるとおりタブレット授受の利便性よりも乗客の安全性が優先されたのでしょうか。
7000系パノラマカーが来ない三河線に「平面顔のパノラマカー」がミュージックホーンを鳴らしっぱなしで走っているのが嬉しくて弟や従弟を誘って近くまで見に行ったことがあります。たぶん1972年のお正月のことです。
(碧)
●No.6
貴サイトの三河線関連記事を興味深く拝見しています。三河線の右側通行や通過列車タブレット授受に関する写真が若干ありますのでご提供させていただきたいと思います。いずれも梅坪駅での撮影です。
疑問点を解明する決定的な情報が含まれていないのが残念ですが、ご参考になれば幸いです。(02.7.21)
貴重な作品をありがとうございます。それにしても梅坪駅をこんなハイアングルから撮影できたとは驚きです。腕を伸ばしている駅員さんがよくわかりますね。対向列車がないのに走行中の列車からタブレットを受け取るのは通過した証でしょうか。
余談ですが、私も小学生の頃、香嵐渓へ紅葉狩りに行ったことがあります。通勤電車並の大混雑だったと記憶しています。(碧)
●No.5
いつもあなたのHPを楽しく拝見させてもらっています。メールしたのは三河線にはなぜ右側通行の駅が?のことなんですが、三河線に右通行が多いという疑問には、僕は答えられないです。でも、最近前川の工事の関係で小垣江駅が仮ホームから、本ホームに変わったときに左側通行に変わりました。なぜ変わったかとか、まったくわからないんですが。ごめんなさい、知識不足で。
あと、電化区間を走るキハのことなんですが、毎日往復とも営業で走っています。走っている時間は行きは、小垣江を10:15に発車する知立行きで、帰りは22:00頃に小垣江を発車する碧南行きです。ここ、5,6年はずっとこの時間で走っています。最近は、30が1両で走っていることが多いです。車内で「なんか珍しいのに乗っちゃった」とか「こんな電車が走っているんだ」という声を結構聞くので単行でもそんなに嫌がられて無いと思います。乗客もそんなに混みあわない程度ですし・・・
僕の知っていることはこの程度なので、もう知っていることだったらすみません。(02.7.20 7.27画像追加)
北新川駅では朝倉さんのご説明どおり知立方面の電車が停まるまで遮断機が下りますが、これから乗るお客さんがあれば一旦上げてまた降ろさなくてはなりません。駆け込み乗車をシャットアウトするにはそのほうがよいかもしれませんが、小垣江駅が左側通行に変わった理由は私にもわかりません。
気動車の件、ご教示ありがとうございます。夜間撮影ながらこれなら小垣江駅が左側通行になったことがよくわかります。バスのような車両が1両で来て驚く人々・・・私も見てみたい気がします。(碧)
●No.4
当三河線では、タブレット閉塞であった時代に無停車でタブレット交換をすることは、定期旅客列車では全然無かったと思っています。確信はありませんが、貨物列車や正月臨・紅葉狩り臨など、主要駅以外を通過する設定の列車があったはずです。その場合でも運転停車をするか、微速通過でタブレット交換をしたのではないかと思います。なぜならば、当線の分岐器は分岐角度が比較的大きく、しかもトングレールがほとんど直線であることから速度制限が大きく、たとえ通過する場合でも極端な減速を余儀なくされたからです。運転台がホームと反対側の場合は、惰行運転のまま運転士が席を立って反対側の車掌扉の窓から手早く交換をしたのでしょう。
国鉄・JRの単線区間でタブレットを使用していたところでは、急行などの通過駅にはタブレットの授受装置があったのはご存知と思います。三河線の場合はタブレット受け器やタブレット保持器を見掛けませんでしたので、原則として全列車 各駅停車だったと思います(CTC化された今でもそう)。(02.7.20)
朝倉様、再度のご投稿ありがとうございます。通過中の電車の運転士が席を立って反対側の窓からタブレットの受け渡しとは今では想像できませんが、30年前にはそんな荒技が行われていたのかも知れません。朝倉さんもご記憶にないというタブレット交換シーンについて引き続き情報をお待ちします。(碧)
●No.3
興味ある貴HPをしばしば拝見しております。小生は三河線を中心とする名鉄とは中学生以来 50年以上の付き合いで、若い頃から(今もかなり)鉄ちゃんしています。
日本の鉄道では道路交通と同様、左側通行が原則ですが、名鉄三河線のすれ違い駅の中に、列車が「右分岐」で入線する駅がいくつかあるのはご指摘の通りです。これはもっぱら乗降客の安全のためと理解して間違いありません。当線もかつては全面的に左分岐でした。タブレットの授受とは関係ないでしょう。
すなわち、ホームが島式になっていて、かつ駅舎(改札口)とホームとを結ぶ通路が(跨線橋や地下道でなく)地平、つまり踏切道であって、到着列車がその踏切を横切るのが危険であるようなところでこれが行われています。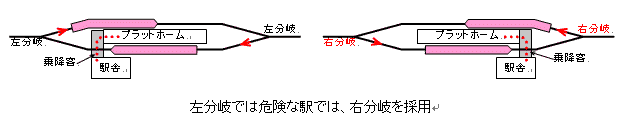
そうやっても反対の出発列車は通路を横切らなければなりませんが、到着列車はその地点ではまだ相当のスピードがあるのにたいし、出発する列車は勢いがついていないし、運転士にとっては目前の状況ですから急停車することもでき、危険が少いというわけです。他方、相対式ホームの場合は必然的にどちらかの到着列車が通路を横切ることになります。従来はそのつど駅員が出て乗降客を警護していました。最近、島式・相対式を問わず、乗降客が線路を横断しなければならないところでは、自動踏切遮断機が整備されました。乗降客の横断通路に設けられた自動遮断機は、その直前で停車する列車が到着するときもご丁寧に閉まります。これは、万一の列車過走事故の予防のためです。列車が発車するときはもちろんです。
分岐器に、転換操作の要らないスプリングポイントが多用されるようになったのは、当線ではかなり前からです。スプリングポイント採用以前は、駅の上り側・下り側のポイントが、ベルクランクと長いロッドで駅舎の外または中にある転換レバーにつながっていて、レバーを駅長が操作して転換していました。これらはまた、ポイントよりも外側にある場内信号器(場内への進入を許可または禁止する信号器)と機械的に連動していて、ポイントが反位のときは列車の進入を認めないように信号が現示されます。CTC化により、この種の転換レバーも見られなくなってしまいましたね。(02.7.18)
とてもわかりやすい解説図を作成いただきありがとうございます。なるほど、踏切を通過してから停車するよりも停止位置の先に踏切があったほうが安全性が高いというわけですね。上の写真は海線区間に残る右側通行の駅、北新川で撮影したものですが、まさに朝倉さんのご説明どおりの構造になっています。説明を加えなくてはならないのはつらいですが、電車はこれから左方向に発車するところです。(碧)
●No.2
三河線の右側通行に関する疑問を拝見して、断片的ではありますが私の記憶をお知らせしたいと思います。
昭和43年(中学2年)から昭和46年(高校1年)まで三河線梅坪駅近くに住んでいました。知立から梅坪までの各駅は全て島式ホームで電車は右側に入ったと記憶しています。スプリングポイントで自然と入るようになっていました。当時の仲間内では「タブレット交換に便利だから。」というのが通説になっていました。秋の行楽シーズンなどの臨時列車が通過する時は最徐行で通過し、駅員の手にタブレットを渡している写真があります。ただ、新しいタブレットをどのように受け取っていたかは記憶がありません。もう一人駅員がいたのかも知れません。
また、手許に梅坪駅で貨物列車が電車に抜かれる写真がありますが、この場合は貨物が右側、電車は左側を通っています。スプリングポイントを手動で切換えていたのでしょうか。(02.7.13)
知立梅坪間はどこも島式右側通行だったのですか。貴重な情報をありがとうございます。通過電車のタブレット授受は興味の持たれるところです。(碧)
●No.1
貴サイトの「甍ヶ淵」拝見しました。新駅開業おめでとうございます。三河線電車の貴重な画像を満喫しました。 さて、三河線の右側通行については、実は私も手元に資料がないのでよくわからないのですが、ご推察の通り通票交換の便を考えての措置ではないでしょうか?通常運転台の7300系や7700系が製造されたのも、三河線や尾西線などでの特急運用を考えてのことだったと思います。 ただ、三河線などでタブレットの走行中の受け渡しがあったかどうかは?です。もし走行中の受け渡しがあれば、7700系や7300系などの乗務員室後ろの窓にガラス破損防止の防護網(国鉄キハ58系などによく見られました)が取りつけられるはずですが、このような防護網をつけた名鉄電車の写真を見たことがありませんので。(02.7.13)
もしタブレット時代に7000系パノラマカーが入線していたら「キリンにえさ」(笑)のようなシーンが見られたかもしれませんね。防護網をつけた名鉄電車はたしかに見たことがありません。(碧)
■それではまとめです。
皆様からお寄せいただいたご意見、情報から一部の駅で右側通行が実施されている目的を考える上でポイントとなる点をピックアップしてみます。
1.三河線では基本的に構内踏切の手前で電車が停止できる側に進入する。(ご投稿3解説図参照)
2.タブレット閉塞の時代、三河八橋(島式ホーム左側通行)にはホームのない側にタブレット授受器があった。
3.特急運転の対象外で、通過列車のない三河平坂も右側通行で、1の構造を満たしている。
4.特急運転区間であってもそれが始まる遥か前から右側通行の駅があった。(吉浜を確認)
5.かつて交換駅を通過する列車があり、停車することなくタブレットの授受を行っていたのは事実。
これらのことから考えれば、タブレットの通過授受は確かに行われていたものの、右側通行の目的はタブレット授受の利便性のためではなく、専ら構内踏切の安全性向上にあったと考えるのが妥当であると思われます。
●締め切りはありません。
2004年2月時点でまとめをさせていただきましたが、情報募集は締め切りません。タブレットの授受方法など、まだ明らかでないことは多々あります。また、たとえ細かいことであってもそれを積み上げてタブレット時代の三河線の姿を記録に留めることは意義深いことであると思います。
こんなことは役に立たないだろうとおっしゃりながらお寄せいただいた情報が立派な判断材料になっています。特定の駅のことなど断片的な情報でもかまいません。また、特急(のち急行)運転当時生まれていなかった若い皆さんはお近くに当時の関係者の方はお見えではないでしょうか。三河線の右側通行やタブレット交換に関する情報がありましたら、ぜひ下記リンク、碧電伝言板に書き込み下さいますようお願いいたします。
時期によって状況に差異がある場合がありますので、いつ頃のことなのかがわかりますとなおありがたく思います。
第4展示室(海線非電化区間廃線間近の頃:ドクターYさん撮影)へ
碧海電子鉄道 © 2002-04 鈴木雄司 (トップページへ)





