|
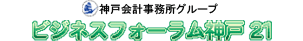
Business Forum Kobe 21 |
|
|
トップページ >税務 >税制改正
| 平成18年度の主な税制改正(企業編) |
1.一人会社の課税強化
|
| 実質的な一人オーナー会社のオーナーへの役員給与について、給与所得控除相当分の損金算入を認めないこととなりました。
実質一人会社とは、同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等、とされています。
ただし、その同族会社の所得等の金額(所得金額+オーナー役員報酬)の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合、および、その平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるそのオーナー役員給与の額の割合が50%以下である場合には、適用されません。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
2.役員賞与の損金算入
|
所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する役員賞与については、損金算入が可能となりました。ただし、事前の届出が必要です。 |
|
非同族会社の一定の要件を満たす業績連動型の役員賞与については、損金算入が可能となりました。
(1)、(2)ともに、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
3.交際費課税
|
法人が支出する交際費の内、1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)について、損金算入を認めることとなりました。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
4.少額減価償却資産の特例
|
30万円未満の減価償却資産の全額損金算入の特例が、上限額300万円とされた上で、平成20年3月31日取得分まで延長されました。 |
5.中小企業投資促進税制
|
取得価額の7%の税額控除または30%の特別償却が認められる中小企業投資促進税制の対象資産に、一定のソフトウェア及びデジタル複合機(取得価額120万円以上のもの(リース総額160万円以上のもの))を加えるとともに、電子計算機以外の器具備品を除外した上で、平成20年3月31日取得分まで延長されました。 |
6.IT投資促進税制の廃止
|
IT投資促進税制は、平成18年3月31日の適用期限をもって廃止されました。 |
7.同族会社の留保金課税
|
同族会社の留保金課税について、不適用要件のうち、「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されました。
同族要件を3株主グループから1株主グループへ改正されました。
控除留保額(留保金課税の対象から控除される金額)が、引き上げられ、留保金課税がかかりにくくなりました。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
8.欠損法人を利用した課税回避行為の規制
|
平成18年4月1日以後に買収された欠損法人が、買収後5年以内に従前の事業を廃止し、その規模を超える事業を開始したこと等、一定の場合には、欠損金の繰越控除の制度を適用せず、3年以内に生じる資産の譲渡等の損失を損金に算入しないこととなりました。 |
9.事業概況説明書
|
法人税の確定申告書の添付書類に「事業概況説明書」が加えられます。 |
|
↑ このページのトップへ
税務のトップページへ
トップページへ
|
| 平成18年度の主な税制改正(個人編) |
1.特別減税の廃止
|
| 定率減税(改正前:所得税20%(上限25万円)、住民税15%(上限4万円))が、平成18年分で半減され、平成19年分では全廃されます。 |
2.所得税・住民税の税率の変更
|
| 所得税(19年度分)
| 現行 |
改正後 |
| 330万円以下 |
10% |
195万円以下 |
5% |
| 900万円以下 |
20% |
330万円以下 |
10% |
| 1,800万円以下 |
30% |
695万円以下 |
20% |
| 1,800万円超 |
37% |
900万円以下 |
23% |
| 1,800万円以下 |
33% |
| 1,800万円超 |
40% |
住民税(平成19年度分(平成18年度所得に基づく)より)
| 現行 |
改正後 |
| 200万円以下 |
5% |
一律 |
10% |
| 700万円以下 |
10% |
| 700万円以下 |
13% |
|
3.耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の創設
|
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、その者の住居の用に供する家屋の耐震改修をした場合には、所得税の特別控除の適用があります。
特別控除額 = 耐震改修工事費用 × 10%(最高20万円) |
4.地震保険料の控除の創設
|
住民用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険料の全額(所得税最高5万円、住民税最高2.5万円)を所得から控除することが出来るようになります。
平成19年分以降の所得税、平成20年分以降の住民税について適用されます。
通常の損害保険は所得控除の対象から外れますが、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の所得控除の適用があります。ただし、地震保険と合わせて、所得税で最高5万円、住民税で最高2.5万円までとされます。 |
5.住宅所得等資金の贈与の特例
|
住宅所得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、適用期限が平成19年12月31日まで2年間延長されます。
なお、550万円までの非課税となる5分5乗方式による特例は、平成17年12月31日の適用期限をもって廃止されました。 |
6.不動産登記の登録免許税
|
不動産登記の登録免許税の税率の1/2軽減措置が、平成18年3月31日の適用期限をもって廃止されますが、土地に関する売買の所有権移転登記および所有権の信託登記については、引き続き1/2軽減されます。 |
7.不動産所得税
|
不動産所得税について、宅地等の課税標準の1/2特例は平成21年3月31日まで延長されます。また、税率4%を3%とする特例は、住宅(土地・家屋)および店舗・事務所などの土地について平成21年3月31日まで延長し、店舗・事務所等の家屋については、特例を廃止するが、2年間(平成20年3月31日まで)は3.5%とされます。 |
8.無申告加算税
|
無申告加算税(現行15%)について、税額50万円を超える部分に対する割合が20%に引き上げられます。
一方、法定申告期限から2週間以内に申告を行い、かつ、納付税額の全額を法定納期限までに納付している等一定の場合には、無申告加算税を課さないこととなります。
いずれの規定も平成19年1月1日以降に法廷期限が到来するものについて適用されます。 |
9.不納付加算税
|
平成19年1月1日以後に法定納期限が到来する源泉所得税について、自主的に法定納期限から1ヶ月以内に納付し、かつ、その納付前1年間、期限後納付がない等一定の場合には、不納付加算税を課さないこととなります。 |
10.更正の請求
|
更正の請求をすることができる後発的事由として、「国税庁長官が法令の解釈を変更して、その解釈が公表されて税額等が異なる取扱を受けることを知ったこと」が加えられました。 |
9.公示制度の廃止
|
平成18年4月1日より、所得税、相続税、贈与税、法人税の公示制度が廃止されました。 |
|
↑ このページのトップへ
税務のトップページへ
トップページへ |
|
|
| Copyright (c) 2006 Business Forum Kobe21 All Rights Reserved. |
|