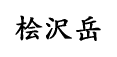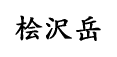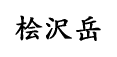
今年は残暑という言葉が聞かれ出すころから晩秋の西上州が恋しく思えていた。ここには小ぶりながら個性的な奇峰が多く、そこここに岩峰やら岩壁があって登れないまでも眺めているだけで楽しい山域だが、それ以上に魅力的なのはほどよく首都圏から離れているせいで落ち着いた山村の佇まいがあちこちの谷筋に見られることだ。
この一帯でもかのバブル期にかなりの林道が造られ、なかには景観が一変した地域もあるらしく、昔の西上州を知る人々からすれば失望めいた声も聞こえてくるのだが、それが地域の活性化につながるのならやむを得ないことかもしれない。だが土建屋を潤して終わっただけの一過性のものならば、単に地元の土地を切り売りして観光自動車の便を図っただけに留まり、持続的な経済の振興にはなんの寄与もしなかったことになる。
効率化を求める競争がどんな辺鄙な場所にも浸透する現在では、小規模の農家や商店は容易に淘汰されていってしまい、挙げ句の果てには大型店舗が建ち並ぶだけのどこにでもある大都市郊外の光景になってしまう。幸か不幸か、西上州は山あいの土地柄のためそういう店舗を建てても採算が合わないはずなので景観上の没個性化を免れている。だがこれはいわば外部からの視点である。ここの眺めは素敵だが、それは自然と人間との共同作業なのであって、人間の側が力尽きれば、たとえ立派な道が通っていようと荒廃するには時間がかかるまい。人間の側を弱体化させているのは、もちろん「過疎」という現象である。そこにいるひとびとからすれば言うのもおこがましいほど切実な問題だろう。経済的にも、おそらくは精神的にも....
桧沢岳(ひさわだけ)へバスと徒歩で行くならば、磐田橋というバス停から山道にはいるまで一時間半ほど車道を歩かなくてはならない。この車道は山越えをして隣村に抜ける道なので、交通量は山の中にしてはそれなりに多い。それでも地元の車なら文句の言いようもないが、まったく別地域のナンバーを付けているのが傍若無人に走っているのに出会うと暗澹たる気分に襲われる。だからできるだけ車の走りにくそうな脇道とかを通るように歩く。そこにはさわがしいエンジン音のかわりに穏やかな家並みがある。だがそういう道筋はすぐ終わってしまって、また幅広の車道に戻されてしまう。
その車道脇に建っている家々では、軒先に大根を干したり、干し柿を吊したりと秋というより初冬の風情である。道ばたに新聞を広げて豆炭を天日干しにしているお年寄りのかたもいた。豆炭なんて見るのはおそろしく久しぶりだ。子供のころ、冬休みに母の田舎へ行くと風呂釜で真っ赤にしたのを火箸で取ってアンカに入れたものだっけ....。その風呂も五右衛門風呂という代物で、足の短い子供には湯の中に浮かんでいる中蓋をひっくり返さないように沈めて湯に入るのにいつもどきどきしたものだった。いまではタイル張りの立派なものになってしまって、風呂場も明るく、かつての面影は微塵もないだろう。長いこと行っていないから、ひょっとしたら今頃はもっと素晴らしいものになっているかもしれない。
桧沢岳への車道歩きはまだ続く。所詮はよそ者の戯言かもしれないが、バス停から長い長い距離を歩きながら店じまいした小売店やひっそりと朽ち果てていく廃屋を目にするにつけ、「山村風景」という名のいわば無形の財産がゆっくりと滅びていくような気がしてならない。
とくに気にも留めず使ってきた茶碗や湯飲みなどが、実はよく見ると味わいの深いものであると再認識され、「民芸」として評価されて今に至っている。同様なことが郷土玩具から古民家にまで言えるが、これらが現在にまで残っているのは、それがある程度の大量生産に適しているか、観光資源として相当の価値を持っているからだ。茅葺き屋根の家並には人が来るかもしれないが、どこにでもあるような集落の眺めは「何もない」として素通りされるだけだ。こうして日本中のどこにでもあった眺めは過疎によって維持者を失い、開発によって改変され、日本中のどこででも見られないものとなるのだろう。つい百年前までは当たり前のようにあった「清流」の川が今やほとんどなくなっているように。だからそうならないよう、もっと「何もない」ことの価値を見直していくべきだろう。「何」も「ない」のではない。「何もない」が「ある」のだ。

長い車道歩きだがここはそれほど苦でもない
大きな集落を抜け、車道はわりと広い谷の中を詰めて山の斜面をジグザグに登っていく。振り返ると鹿岳があの奇妙な姿を彼方に見せている。向かい側の山肌も近くなってきて空が狭くなった。隣村に抜けていくルートが分岐していくところは薄暗い感じだが、車が何台も植林のなかに消えていく一方で、山に向かうこちらは車道とはいえ日があたるなかを歩いていく。進行方向には高台に家も見えて寂しい気はしない。その家の下で道が分岐しており、どちらに行くべきだろうかと地図を見ていると、視界になにか気にとまるものがあり、顔を上げると女性がひとり、家の戸口から合図をしている。普通に話したのでは声の届かない距離なので、身振りで進むべき道を示してくれているのだった。こちらも行くべき道を指さして確認し、感謝のしるしに頭を下げた。
車道行き止まりの集落は、桃源郷のような明るさだった。周囲に広がっているのは桑畑だろうか。耕作されておらず、まったくの更地になった斜面の畑は無人となった最奧のお宅のものだろうか。大屋山の蓼沼の集落といい、南面とはいえ山の上に開墾を試みた先人の境遇にあれこれ想像を働かせながら細い山道を上がっていく。
集落を抜けると荒れた感じすらする道になったが、すぐ植林にはいってヤブはなくなった。尾根道となり、これを詰めていくと右手に絶壁を見る。そこで左手にからみ、コルに出た。右が本峰、左に行けば西峰。眺めのよいという西峰に立ち寄ることとし、一息でてっぺんに上がった。本峰の背後には、隣の小沢岳が恰幅のいい姿で立ち上がっている。左手には鹿岳や四ツ又山に黒滝山、大屋山、その背後に連なる荒船山に続く稜線。本峰と反対側に向けば足元は切れ落ちた岩壁のヘリで、おそるおそる見下ろせば先ほど脇を通ってきた集落の家並みが真下に見える。
午後二時、誰もいないピークで周囲の眺めに浸ったあと、腰を下ろしてお湯を沸かし、お茶をいれて一年ぶりの西上州の山を祝った。
本峰からは荒船から妙義、浅間が西峰よりよく見えた。ここには小ぶりながら気品のある社があり、信仰の山であることがわかる。今はわからないがかつてこの山の麓では「悪罵」という祭りが行われていたそうだ。とにかく遭う人見る人に悪口を浴びせかけ、言われたほうは黙り込んでしまうと農作物の出来が悪くなる、だから負けずに言い返す、というようなものだったらしい。
さて周遊ルートをとろうと、社の裏から山麓に続く道に入る。こちらは北面のため霜がおりたまま乾いてないのかぬかるんでいるところもある。登りの道が陽ならこちらは陰だ。岩壁を右手頭上に見上げるようになると岩窟内に建てられた多少ひしゃげた社の前に出た。この社は残念ながらかつての賑わいをなくしてしまったのだろうか。個人名も含めた落書きがあちこちにされている。そこに書かれた名前の持ち主が後世に至るまで恥を晒し続けるのはいいとして、社そのものは気の毒としか言いようがない。
稜線をたどり、東のコルに出ると穏やかな秋の日差しになる。散り残った葉っぱに西日が透けて柔らかい。斜面をジグザグに下って沢筋に出るころにはその日も向こうの山の端に消えた。沢を渡ると林道で、これに沿って下っていくと登り始めに頭上の人家から行き先を教えてもらった場所が見えてきた。
 |
| 山頂には端正な社がある |
 |
| 晩秋とはいえ彩りの名残もある |
そこからすぐ、カーブしている林道を回っていくと、少し先の道の真ん中を背の低い黒っぽい生き物が短い足でとことこ下っていっているのが目に入った。すれ違うときに一声、わんと吠えてこちらを見上げ、足元に揺り寄ってくる。毛並みのきれいなダックスフンドだった。そのままついてくるようなので、しゃがんで話しかけるとじゃれついてくる。耳の後ろを掻いてやると喜んで頭をもたせかけてくる。気がつくとさきほど道を教えてくれた女性が出てきていた。「ぴーちゃん、そんなところを散歩していたの」。
ぴーちゃんはほんとうに愛想のいい犬で、猫のようにからだを摺り寄せてきてはあちこち撫でられるにまかせている。話しかけながら笑いかけると、いきなりこちらの顔を舐めようと短い足で何度も立ち上がるのだった。「動物は好きなんですか?」と訊かれて、好きなんですけど住宅事情のため飼えないんですと答える。「だからこんなになつかれると、つい構ってしまって」。しかしいつまでもぴーちゃんと遊んでいるわけにはいかない。日もかなり翳ってきた。そろそろこれで、と立ち上がって歩き出すと、一緒についてこようとする。「かわいがってもらったからといって、一緒に行っちゃいけないのよ」と言われて抱きかかえられたぴーちゃんと飼い主に挨拶して再び歩き出した。
帰路に見る家々は歩いている時間が経つにつれ、明かりが灯りだした。ある家の軒先では、炬燵に入ってテレビを見ている老夫婦の姿が垣間見えた。そういえば子供たちはどこにいるのだろう。バスを降りてからずっと、ひとりもみかけていない気がする。今日は土曜日、学校は休みか午前中のみではなかろうか?

夕暮れの家
懐かしさを催させる山村風景に惹かれるのは、昔と今を記憶の範囲内で比較できるほど歳をとったからかもしれない。「もう年寄りになったのか?」と言われそうな気もする。だが、変化は常に善ではない。変化に対応するのに、常にこちらも変化しなければならないという法もない。なにか別な方法があるはずだ....
ぴーちゃんと分かれたときはまだ明るかったが、歩き始めた磐田橋のバス停付近に出る頃には、すっかり真っ暗になっていた。外に出ている人の姿はひとりとして見えない。次々と通り過ぎる車のヘッドライトが、単独行者の目にひどく眩しかった。
2001/11/23
回想の目次に戻る ホームページに戻る
Author:i.inoue
All Rights Reserved
by i.inoue