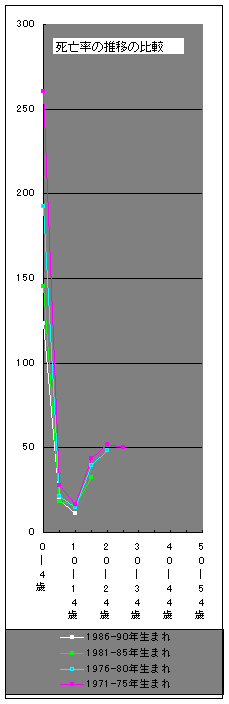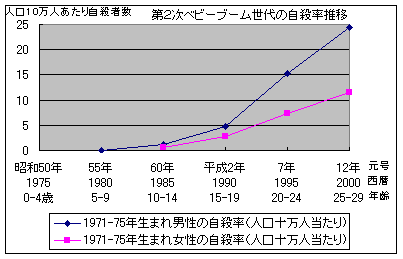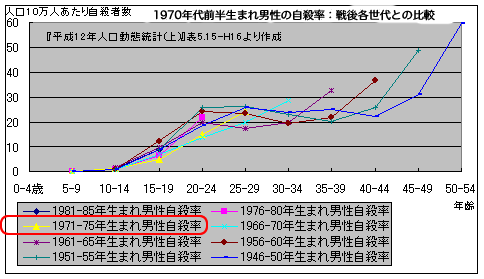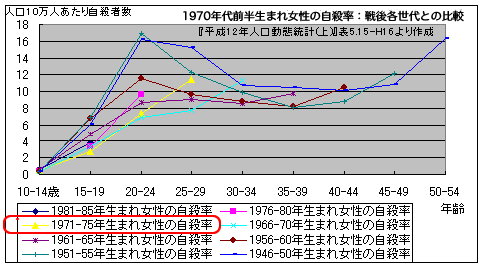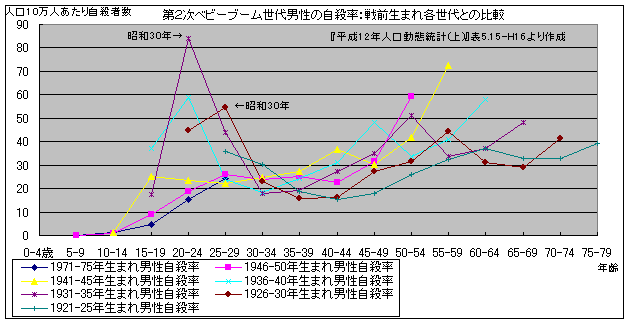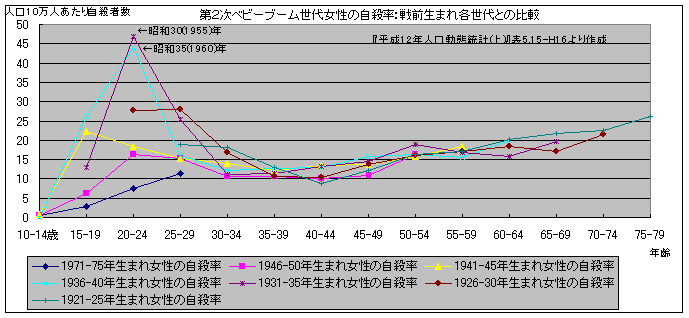乳幼児期は結構死んだが、
物心ついたあと、
ほとんど死なない世代。
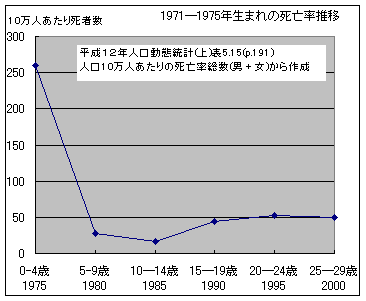
上のグラフは第二次ベビーブーム世代の死亡率(一年間に、10万人あたり何人程度の頻度で死んでいっているか)の推移。
4歳までの乳幼児期には、一年間に10万人当たり250人以上という頻度で死亡。
子供時代は、一年間に10万人当たり25人程度、ティーンエイジ期以降現在までは、一年間に10万人当たり50人程度という頻度(年0.05%)で死亡。
つまり、第二次ベビーブーム世代のほとんどは、物心ついてから現在に至るまで、同世代の死に直面することなく生きてきたのである。
この死亡率の推移を、戦前生まれの各世代、戦後最初の世代である第一次ベビーブーム世代と、比較したのが下のグラフ。
乳幼児期の死亡率は、戦前各世代、第一次ベビーブーム世代ともに、このグラフにおさまらないほど、高かった。これと比べると、第二次ベビーブーム世代の乳幼児期の死亡率は、目を見張るほど低い。
また、成長後の死亡率の推移も、第一次ベビーブーム世代の半分近く、戦前生まれの世代と比べると、1/3,1/4などというレベルに抑えられていることがわかる。
↓
第一次ベビーブーム世代よりも、その直後の 50年代前半生まれの方が死亡率の高い時期もあったものの、それ以外では、世代を下るにつれ、徐々に、死亡率が低下していっているのがわかる。乳幼児期の死亡率低下の激しさには、眼を見張るものがある。
↓
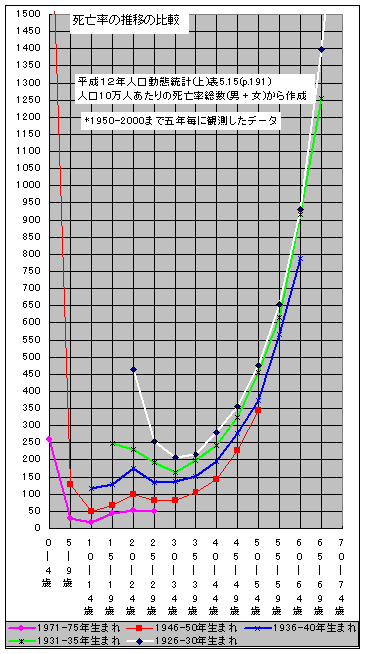
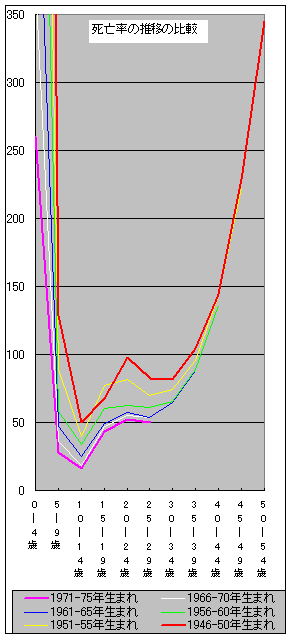
第二次ベビーブーム世代以降の世代の死亡率と比較したのが右のグラフ。第二次ベビーブーム世代以降も、徐々にではあるが、死亡率は低下し続けている。