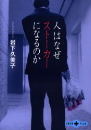★★ ●
★★ ●『負け犬の遠吠え』
酒井順子/2003年10月刊/講談社/1,400円+税(文庫2006年10月刊/講談社文庫/571円+税)
書評ではなく感想文です。読んだらこういう気分になるという例。
まず、戦略的とか問題提起としての意味があったんだろうけど、「勝ち犬/負け犬」転じて「勝ち組/負け組」という言葉を流行らせるきっかけになった責任は大きいと思う。それに「勝ち/負け」の分け方からして、問題あり過ぎだと思う。
「モテ問」みたいな恋愛ショボ系団体に関わっている人間からすると、苦もなく恋愛してきて、キャリアややりがいのある仕事を持ってて、社交性もあって対人恐怖なんて言葉も関係なく社会を飛び回って人生を楽しんで、それでも、結婚してないというだけで「負け犬」です、などというのははっきりいってあきれてしまう。さらに、30代後半になって恋愛にも飽きて(つまりままならなくなってきて)くると、ある意味では「モテない人」の唯一の存在証明の場であった「マニア化」「おたく化」の領域(電車や芝居など)にまで進出しようとしているのは許せない。
自分たちはそれだけ人生を楽しんでいて、結婚した女性は皆、打算か「女を使った」というような書き方をして「勝ち犬」にしているのは、自分を「負け犬」と呼び、被害者側にして、やいたいことばかりやってきた「うしろめたさ」を隠蔽しようとしているように思える。だけど、その「うしろめたさ」こそ、実はこの本の本当のテーマだと思われる、「子どもを産む/産まない」の葛藤なのかもしれないが。
上野千鶴子が、「出産は女にとって最大の快楽です」みたいなことをどこそこで言ってたせいなんじゃないかと思ってしまうのだが、「産んでない女」である著者が産むべきかどうか悩んでいるのは、例えば「次の休暇は海外旅行に行くべきかどうか」と同じ次元であるような気がしてしまう。つまり「楽しいことはやっておかなきゃ損!と思うけれど・・・ちょっとリスクが大きすぎる」というような。
モテ問題を考えるとき、ロマンティックラヴイデオロギー批判が出てくるけど、本当に批判すべきだったのは、恋愛のロマンティックな部分だけ消費して、それにともなう責任や面倒くさいところはいらないというような態度だったんじゃないだろうか。
あと社会の不思議なんだけど、「不倫」ってそんなにポピュラーなものなんですか。
テレビのなかだけの話じゃないんだ?
(2007/06/30 たけだぺてろ) ←一覧に戻る ↑先頭に戻る