 ★★★★★●●●●
★★★★★●●●●
『フェミニズムはみんなのもの─情熱の政治学』
ベル・フックス/堀田碧訳/2003年5月刊/新水社/1,600円+税
現在、フェミニズムvs非フェミニズムの衝突がネット上で多く見られ、大変危惧しています。
ベル・フックスの「フェミニズム」であれば、そのような不毛な衝突は避けられると思っています。
「フェミニズムはみんなのもの(Feminism is for EVERYBODY)」です。
ベル・フックスによる「フェミニズム」の定義は「性差別をなくし、性差別的な搾取や抑圧をなくす運動」です。
「この定義を気に入っているのは、男性を敵だと言っていないことだ。問題は性差別だと、ズバリ核心をついている。」
「思い描くのは、支配というものがない世界に生きること。女と男は同じではないし、いつでもどこでも平等というわけではなくても、交わりの基本はお互いに相手を思いやることだという精神がすみずみまで行き渡った世界に生きることだ。フェミニズム革命だけでそうした世の中ができるわけではない。人種差別や階級的エリート主義や帝国主義も、なくさなくてはならないだろう。でも、愛にみちた共同体を創り、ともに暮らすことのできるような、真に目覚めた女や男になることは可能である。」
ベル・フックスは、「シスターフッド」を新たに結び直すために、フェミニズムの「インフレ」にストップをかけていると僕は捉えています。
「いわゆる〈ライフスタイル・フェミニズム〉は、政治ではなくライフスタイルに焦点を移すことで、女性にもいろいろあるようにフェミニズムの理念もいろいろあってよい、という考えを広めた。あれよあれよという間に、フェミニズムからは次第に政治がなくなった。そして、その女性の政治的信条がどうあれ、保守的であろうと進歩的であろうと、自分のライフスタイルにフェミニズムを合わせることができる、という考え方が幅をきかせだした。(中略)女性が中絶するかどうかを選ぶ権利に反対する〈反チョイス派〉でありながらフェミニストであることはできない。(中略)加えて、「パワー・フェミニズム」などというものもありえない。そこで言うパワーが、他人を搾取したり抑圧したりすることによって得られる権力のことであるなら、そうしたパワーとフェミニズムとは両立しないからだ。
フェミニズムが今、力を失っているのは、フェミニズム運動が明確な定義を持っていないからだ。」
「突然、それまでよりもたくさんの女性が「フェミニスト」を自称したり、自分の経済的地位を上げるために「ジェンダーの不平等」という理論を使ったりするようになった。女性学が学問の制度に組み入れられた結果、大学や出版界で仕事が生まれた。こうしたキャリア上の変化が起きると、政治的にはまったくフェミニズム運動に関わったことのない女性たちが、ただキャリア欲しさに、階級的上昇指向にかられて、フェミニズムの立場やフェミニズムの専門用語を採用するといったご都合主義が生み出された。フェミニズムの支持者になるためには、フェミニズムについて知り、フェミニズムを選びとるという自覚的な選択をしなければならない、という考えは、コンシャスネス・レイジングのグループが解体されたことで、まったくといっていいほど消し去られてしまったのである。」
「フェミニズム運動の初期には非常に重要であった政治的なシスターフッドの呼びかけは意味を失った。それは、ラディカルなフェミニズムが、政治信条は関係ないといううわべだけのフェミニズムに凌駕されてしまったからだ。」
支配や搾取のためのあらゆる暴力(「家父長主義的な暴力」)をなくすこと。
「女性にたいする家父長主義的な暴力を問題にすることは、今後もフェミニズムの最重要課題であろう。しかし、女性にたいする男性の暴力を、それこそがその他の家父長主義的な暴力のどれよりもひどくて問題なのだ、というような形で強調することは、フェミニズム運動の利益にはならない。」
「男性から女性への暴力のみに注意を喚起しようと躍起になっている改良主義的なフェミニストたちは、今でも、つねに女性だけを犠牲者として描くことが多い。子どもへの暴力の多くが女性によってふるわれているという事実が同じく問題としてとりあげられることもなければ、それがもうひとつの家父長主義的な暴力の表現であると見なされることもない。(中略)もし、すべてのフェミニストが、女性による家父長主義的な暴力への怒りを表明し、それを男性から女性への暴力と同じく問題にしていたなら、世間の人々は、家父長主義的な暴力の問題を、反男性運動の一環とみなしてしりぞけるようなことはできなかっただろう。」
僕は、男には「メンズリブ」が必要と思っていますが、一応男についての引用。
「増える失業や報われない仕事、そして女性の階級的権力が増えていることは、裕福でも権力者でもない男性たちが、自分たちの居場所を確かめることを困難にさせている。白人至上主義的で資本主義的な家父長制は、約束したものすべてを与えてはくれない。多くの男性は苦しんでいるが、それは、そうした約束が不正義と支配に根ざしており、たとえ実現されたとしても真の喜びにはつながらないことを見抜けるような、自分を解放してくれる批判精神をもてないからである。解放に背を向け、何よりも自分の魂を殺してしまう白人至上主義的で資本主義的で家父長主義的な考えを再強化している男性たちは、破滅的な行為に突っ走る少年たちと同じく、破壊的である。」
「すべての女性に男性を拒否せよと呼びかけたフェミニストたちが見ようとしなかったものは、女性と男性が共に築いてきた思いやりの絆であったり、あるいはまた、女性を性差別的な男性につなぎとめている経済的または感情的なつながり(よいものであろうと悪いものであろうと)であった。」
「そして、男性であることが否定的に描かれたことに対応するように、女性を敵視するような男性運動が起こった。」
「こうした男性たちは、自分たちこそ性差別の犠牲者であるとして、男性を解放するために活動している。かれらが、男性こそ犠牲者である主たる理由としてあげるのは、固定した性役割である。そしてかれらは、男らしさについての考え方を変えることは望むものの、男性の女性にたいする性差別的な搾取や抑圧については、さしたる関心を払っていないのである。
男性運動は、多くの点で、女性運動のもっとも否定的な要素をなぞってきたのである。」
「昔もそして今も、必要とされているのは、アイデンティティの基となる自分らしさを誇りに思い、愛することができるような、男らしさのヴィジョンなのだ。支配の文化は、自分を誇りに思う気持ちをうち砕き、その代わりに、自分の存在感は他人を支配することからしか得られないという考えを、わたしたちに植えつける。(中略)これを変えるために、男性は、男性によるこの地球の支配を批判しなくてはならないし、男性がより弱い男性や女性や子供を支配することに反対しなくてはならない。だが同時に、男性たちは、フェミニズムの考える男らしさとはどのようなものなのか、はっきりしたヴィジョンを手にする必要がある。イメージできないものに、人はどうやってなれるというのだろう?」
アカデミズムについて。
「フェミニズムが学問として認められたことは、フェミニズム思想の発展にとって決定的なことだったが、それは新たな困難をも生み出した。突如として、思想や実践から直接に導き出されたフェミニズムの思想は顧みられなくなり、専門家にしかわからない難しい用語を駆使したメタ言語学的な理論が注目されるようになった。そうしたフェミニズム理論はただインテリや学者のためにだけ書かれたものだった。それはまるで、フェミニストたちが大挙して、「内輪」だけに通じる難解な理論を書くエリート集団をつくりはじめたかのようだった。
インテリでも学者でもない女性や男性はもはや、フェミニズム思想の重要な受けとり手とは考えられないようになった。フェミニズムの思想や理論はもはや、フェミニズム運動と結びついたものではなくなった。(中略)先進的な内容の学術論文が、かつても、そして現在も書かれていることはたしかである。だが、そうした考えがたくさんの人に届くことはない。こうしたことの結果として、フェミニズムが学問化し専門化すると、フェミニズム運動は非政治化し、弱まってしまう。」
日本では邦訳は現在2冊(2007年6月現在3冊)出版されているのみで、ベル・フックスの名前はあまり知られていないかもしれませんが、欧米ではフェミニズムに関心のある人なら必ず知っている名前だそうです。
(2006/04/08 名木太・別サイトより) ←一覧に戻る ↑先頭に戻る
|
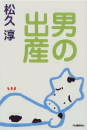
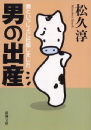 ★★★★★●
★★★★★●
