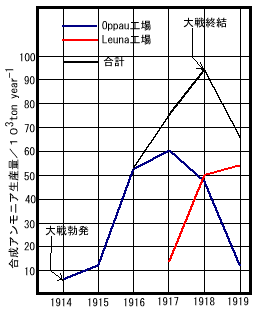|
|
(3webサーバー) |
(midiあり 3webサーバー) |
|
ご感想、ご要望等はこちらへ |
| アンモニア合成法の成功と
第一次世界大戦の勃発 (2/3) (ほぼ原文+注釈)
|
2 .大戦勃発時のドイツ国内の雰囲気(政治的反対理由)
注2・・・・・・・原文では6・2になっていたが明らかにミ スプリと思われるので訂正した。 注3・・・・・・・原文では”硫酸”となっていたが、それ だと本文(アンモニアの酸化の部分)とあ まり関連性がないので”硫酸”はミスプリ と判断し”硝酸”に訂正した。
|
結果的にみて、第一次大戦は第二次大戦と同じく、国の全資材を動員する形態で終わった。しかし前者の開戦時にドイツ軍指導部は、そのようになると予想してはいなかった。彼らは食料と火薬の必須原料であったチリ硝石の輸入が、優勢なイギリスの海軍力により不可能となるにしても、そうなるまでに戦争は勝利に終わると考えていた。したがって「クリスマスには帰りますよ」といって、ドイツの青年は出征していった。こんな状況は多くの歴史書にかかれている。ボッシュを助けて工業化に必要な触媒を発見したA.Mittaschは、「開戦時まで、軍指導部の最高責任者は誰一人として
BASF社の工場を尋ねなかった」と記してそれを裏付けている。永世中立のベルギーへの侵入という国際条約を破る暴挙を行ったのに、九月中旬のマルヌの戦闘に破れた軍部は、以後ようやく短期隊利をあきらめ、化学工場の重要性に気付いたとMittaschはいう。
実際に、化学工業の役割は戦争の進行と共に増大し、アンモニアについていえば、oppau工場の拡張だけでは足りず、第二工場を Leunaに建設し、1917年には運転開始することになる。その結果、図1にみるごとく、アンモニア生産は急激に増加していく。このようにアンモニア合成法はW.ネルンストがいったごとく、”祖国の救助者” となってしまった。 しかし本法は大戦開始直前に、ドイツ国の内外で必らずしも高く評価されず、また成功視されなかった。この点をMittaschは具体例で示しているが、日本側の関連資料を紹介して傍証としょう。それは欧州特にドイツに派遣された森殿五郎氏のB5版562頁の調査報告書である。その発行日は大正3年9月で、ちょうどマルヌ戦の頃であるが、内容は戦争直前のドイツにおける窒素問題の見聞禄といえる。これがいかに重要視されたかは電気化学工業調査を目的とした同氏が、あえて”餘岐ニ渉ルガ如キ” (ヨキニハカルガゴトキかな?)も空中窒素固定法に重点をおき作製したことから推察できる。その結論として注意すべき点は、空中窒素固定法の本命を石灰窒素法におき、ハーバー・ボッシュ法を詳しく紹介しながらも幾多の欠陥をあげ、製造資は発表値の倍となろうとし、試験工場(1912年当時)の将来を楽観していないことである。またBASF社は既にFe/K2O/Al2O3という優れた触媒を発見し、使用していたが、恐らくFeを用いているらしいとの推定に止まっているのも興味がある。したがって、当時の日本の代表的研究所たる東工試が、空中窒素固定法の第一歩として大正6年に採用した研究が、BASF社がすでに中止した空中電弧法であったのも当然である。(しかし翌年臨時窒素研究所が設立され、ハーバー・ボッシュ法の工業化に着手した。)また大戦勃発頃の工業化学雑誌を覗いても同じ感じを受ける。 以上は当時の日本の工業化学の後進性を紹介するためでなく、ドイツの一般化学者のアンモニア合成法に対する評価の反映を示すためである。とすれば、本法の成功を開戦の決意の一因とする通説は甚だ怪しくなる。やはり世界征覇を争った独英の対立が、たまたま6月28日サラエボにおけるオ一ストリア皇太子の暗殺事件を契機として、世界大戦にまで発展したとみるべきであろう。その際に、まず宣戦布告したドイツの決意に、優秀を誇った科学と工業があったであろうが、アンモニア合成法の成功は、その一駒にすぎなかった。この状勢は、第一次大戦後のベストセラーとなった英人H.G.Wellsの著書や第二次大戦後に前者を対象として書かれた歴史書に詳しく述べられている。 以上を要するに、本法を第一次大戦勃発と関連づけるのは、その重要性を強調するための過当な賞め言薬と思われる。さらに上記の結論を、別の観点で、しかも注意されていない理由から支持したい。 |